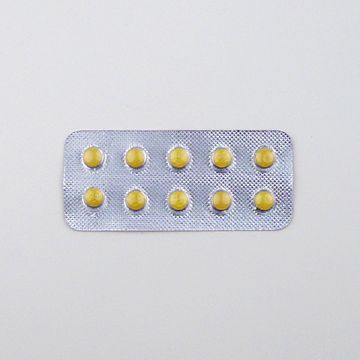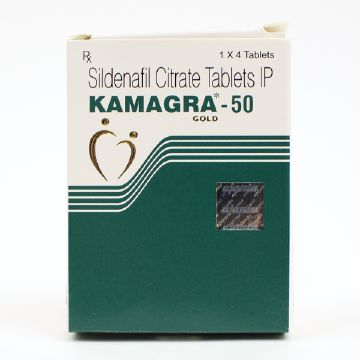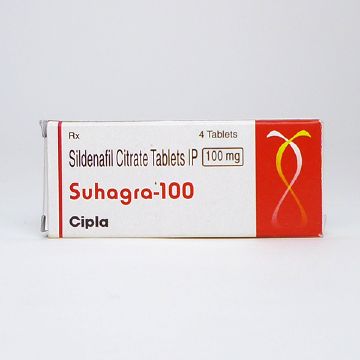ブラパディスペンサリー

-
英語表記Burapha Dispensary Co.,Ltd.
-
設立年月日1980年
-
国タイ
-
所在地99/1 Moo 4, Soi Chalermprakiat Rama 9, Soi 48, Dokmai, Prawet, Bangkok 10250, Thailand
ブラパディスペンサリーの歴史と成長
ブラパディスペンサリーは、タイ国内で高品質な医薬品を提供する製薬会社として、長年にわたり重要な役割を果たしてきました。
会社は、その設立以来、タイの消費者に信頼される医薬品を提供することを使命として掲げています。
ブラパディスペンサリーは、国内の医療基準に厳しく従いながら、製造過程における品質管理を徹底し、医療機関や薬局に向けて信頼性の高い製品を提供してきました。
同社は、GMPという国際的な製造基準に準拠しており、タイの食品薬品管理局からも認証を受けています。
また、WHOからも認証を受けており、その品質基準の高さが証明されています。
これにより、ブラパディスペンサリーの製品は国内外での信頼を勝ち取り、多くの医療現場で使用されています。
設立から現在に至るまで、ブラパディスペンサリーは、タイ国内における医薬品市場での成長を遂げてきました。
特に、ジェネリック医薬品の提供を通じて、コストを抑えながらも高品質な医薬品を提供することに成功しています。
また、OEMサービスにも力を入れており、他のブランドや企業向けに製品を製造することで、幅広いパートナーシップを築いています。
今後も、ブラパディスペンサリーは革新と成長を続け、タイ国内外でのプレゼンスをさらに強化していくことが期待されています。
同社は、品質、信頼性、安全性を維持しながら、次世代の医薬品開発にも積極的に取り組んでいます。
ブラパディスペンサリーの製品ラインナップと技術革新
ブラパディスペンサリーは、タイ国内で多様な医療ニーズに応えるため、幅広い製品ラインナップを提供している企業です。
医薬品、ハーブ製品、ジェネリック薬品、化粧品など、さまざまなカテゴリーの商品を取り揃えており、消費者や医療機関がそれぞれのニーズに合った最適な選択をできるようにしています。
同社の代表的な製品には、以下のようなものがあります。
まず、鎮痛剤および解熱剤として広く使用されるパラセタモール 500mgは、一般的な風邪や頭痛の治療に役立つ製品です。
また、アルサメト 400は、炎症や痛みを軽減するための非ステロイド性抗炎症薬(NSAID)であり、リウマチや関節炎などの症状に対する効果が期待されています。
さらに、ナズィフェド BPOは、気道感染症やアレルギーによる鼻づまりを緩和する治療薬として利用されています。
皮膚の乾燥やかゆみを抑えるための外用薬であるブーラジェル A.M.は、敏感肌の人でも安全に使用できる成分が配合された製品です。
これらの製品は、厳格な品質管理のもとで製造され、タイ国内のみならず、世界中の医療市場にも提供されています。
また、ブラパディスペンサリーは、製造技術の革新にも積極的に取り組んでおり、最新の設備と技術を活用して、より高品質で効果的な医薬品の開発に力を入れています。
さらに、ブラパディスペンサリーはカスタムメイドのOEMサービスも提供しており、顧客のニーズに合わせた製品を製造することで、企業やブランドが自社の製品ラインを拡充し、消費者に新たな選択肢を提供できるように支援しています。
今後も同社は、技術革新と柔軟な対応を続け、顧客ニーズに応える製品を提供していくと考えられます。
引用 : https://www.buraphaosoth.com/about-us
よくあるご質問(FAQ)
-
質問:なぜ薬がないのでしょうか?回答:
薬が不足している理由はいくつかあります。
まず、一部の製薬会社で品質管理の不正が発覚し、多くの企業で業務停止や改善命令が出されたため、薬の製造や供給が止まりました。
さらに、新型コロナウイルス感染症や季節性インフルエンザの流行が進み、薬の需要が急増しています。
この様な状況が重なり、全国の薬局で薬が不足しているのです。 -
質問:なぜ薬が供給不足になるのでしょうか?回答:
薬の供給不足には、製薬業界全体の問題と特定の状況が関係しています。
まず、一部の製薬会社で品質管理の問題が発覚し、その結果、製造や出荷が停止されたことが供給不足の一因です。
また、新型コロナウイルスや季節性インフルエンザの流行により、特定の薬の需要が急増し、供給が追いつかない状況が発生しています。
これらの問題が重なり、薬の供給が不安定になっています。
解決には、製薬会社の品質管理の強化や、需要予測と供給体制の改善が必要です。 -
質問:なぜ処方箋がないと薬はもらえないのか?回答:
薬を受け取るには、通常、医師の診察を受けて処方箋をもらう必要があります。
これは、医療用の薬は専門的な知識を持つ医師や薬剤師によって適切に選ばれ、使用されるべきだからです。
また、一部の薬には副作用のリスクがあるため、安全に使うためにも医師の診察と処方箋が必要です。 -
質問:残薬は社会問題になっていますか?回答:
残薬は大きな社会問題です。
残薬とは、処方された薬の一部が使われずに残ってしまうことを指します。
これにより、治療の効果が十分に得られないだけでなく、「医療費のムダ」が発生します。
この問題は、マスコミでも取り上げられることが増えてきました。
薬剤師が積極的に介入することで、年間で100億円から3,000億円以上の残薬削減が期待されており、日本の医療制度においても、年間約8744億円の薬剤費が無駄になっている可能性があるとされています。
残薬問題を解決するためには、患者の服薬管理の改善や、薬剤師による適切なサポートが必要です。 -
質問:残薬は医師に伝えるべきですか?回答:
残薬がある場合は、医師に正直に伝えることが大切です。
残薬が出る理由には、副作用が強かったり、症状が改善したため服薬を減らしたり、服薬を忘れたり、効果を感じなかったりすることが考えられます。
これらの情報を医師に伝えることで、医師は症状や体調を再評価し、より適切な治療を提案できます。
残薬を隠したり無断で服薬を中止すると、次の処方が適切に行えないため、医師との信頼関係を築くためにも、残薬については遠慮せずに伝えるようにしましょう。 -
質問:薬剤師がなぜ薬について聞いてくるのですか?回答:
薬剤師が薬について質問するのは、患者さんの安全と適切な治療を確保するためです。
患者さんの症状や生活習慣、現在の薬やサプリメント、アレルギー歴などを把握し、最適な薬を選び、正しい服用方法を指導します。
また、薬の相互作用や重複を確認して、安全に薬を使えるようにする役割も果たします。
これにより、患者さんの健康と安全を守るための重要なプロセスなのです。 -
質問:薬局で残った薬はもらえますか?回答:
残薬を薬局で受け取ることはできません。
これは、処方薬は医師が患者さんの病状や体質に合わせて処方したものであり、他の人が使用すると副作用が起こる可能性があるからです。
また、処方薬は医療行為の一部であり、商品の売買とは異なるため、返品や返金の制度もありません。 -
質問:病院でもらった薬は薬局で一包化できますか?回答:
病院で受け取った薬を薬局で一包化することは可能です。
一包化とは、同じ用法の薬を一つの袋にまとめる方法で、飲み忘れや飲み間違いを防ぐのに役立ちます。
ただし、薬剤を処方した医師の許可が必要で、湿気に弱い薬や特別な管理が必要な薬は一包化できないことがあります。
料金や手続きについては、薬局の薬剤師に相談してください。 -
質問:病院で余った薬はどうすればいいですか?回答:
病院で余った薬の対処法は次の通りです。
まず、余った薬は薬剤師に相談してください。
薬剤師が薬の種類や状態を確認し、医師に連絡して次回の処方量を調整してもらうか、次回の受診時に医師に残薬を伝えられるようにお薬手帳などに記録します。
余った薬の処分は、自治体のルールに従って適切に行ってください。
ただし、処方薬を他人に譲ることは法律に違反しており、健康に悪影響を及ぼす可能性があるため絶対に避けてください。 -
質問:薬の説明書は捨ててもいいですか?回答:
薬の説明書は捨てずに保管しておくことが推奨されます。
説明書には、薬の成分や効能、用法・用量、副作用、相互作用など、薬を安全に使うための重要な情報が記載されています。
この情報は、薬を正しく理解し、安全に使用するために必要です。
説明書は、薬を使い切るまで保管しておくと便利です。
次回使用する際にも参考になりますし、万が一副作用が出た場合にも役立ちます。
したがって、薬の説明書は大切に保管し、必要に応じて参照することが重要です。 -
質問:置き薬は使ってなくてもいいの?回答:
置き薬は、急な体調不良時にすぐに使えるように家庭に常備する薬ですが、使わなかった場合でも特に問題はありません。
置き薬は使用した分だけ後で清算され、使わなかった分の薬代は発生しません。
また、定期的に訪問してくれる売薬さんが、使用しなかった薬は無料で交換してくれるので、常に最新の薬を保持できます。
ただし、置き薬は緊急時の対応に適しており、重い症状や長期間続く症状がある場合は、必ず医療機関を受診するべきです。 -
質問:薬は何年くらい持つ?回答:
薬の持続期間は薬の種類や保管状態によります。
未開封の状態であれば、製造から3~5年は効果が保たれることが多いですが、保管条件によっては短くなることがあります。
開封後の保管期間は、薬の種類によって異なります。
粉薬や顆粒は3~6ヵ月、カプセルや錠剤、坐薬、軟膏は6ヵ月から1年、目薬や自己注射製剤は1ヵ月、シロップなどの液剤はすぐに処分するのが推奨されます。
薬は光、熱、湿気を避けて保管することで、効果を長持ちさせることができます。 -
質問:病院でもらった薬は何年もつ?回答:
病院で処方された薬の持続期間は、薬の種類や形態、保管状態によって異なります。
一般的には、製造から数年間は有効ですが、液体薬や錠剤は適切な温度や湿度で保管し、直射日光や高温を避けることで効果が保たれます。
ただし、使用期限が短い薬もありますので、薬のラベルや説明書に記載された使用期限を確認し、期限内に使用することが重要です。
期限切れの薬は効果が低下し、安全性に問題が生じることがあります。 -
質問:薬は冷蔵庫に保管してもいいですか?回答:
薬を冷蔵庫で保管することは、一般的には推奨されていません。
ほとんどの薬は室温で保管するのが適切です。
冷蔵庫に入れると、温度変化や湿気で薬の効果が変わることがあります。
特に、指示がない限り、薬は直射日光を避け、湿気の少ない室温(1~30℃)で保管するのが良いです。 -
質問:薬局以外でオンライン服薬指導はできますか?回答:
薬局以外でもオンラインで薬の服薬指導を受けることが可能です。
2022年9月に厚生労働省が医薬品医療機器等法(薬機法)施行規則を一部改正され、薬局以外の場所でも、調剤にかかわる薬剤師とのオンライン指導が認められました。
ただし、オンライン指導を行うには、薬学の知識だけでなく、情報通信やセキュリティに関する知識も必要です。 -
質問:オンラインで服薬指導は受けられますか?回答:
オンラインで薬についての服薬指導を受けることができます。
これは、法律が改正され、オンライン診療や服薬指導のルールが緩和されたためです。
オンライン服薬指導では、パソコンやスマートフォンを使って、薬剤師が自宅から薬の使い方を説明してくれます。
この方法で、自宅にいながら薬剤師の説明や相談を受けることができ、薬も自宅で受け取ることが可能です。
ただし、オンライン服薬指導を受けるには、いくつかの条件を満たす必要があります。
詳しい条件や手続きについては、薬局の薬剤師に相談してみてください。 -
質問:処方箋なしで買える薬はなんて呼ばれますか?回答:
薬を処方箋なしで購入できるのは、「零売(れいばい)」というシステムを通じてです。
このシステムでは、処方箋がなくても医療用医薬品を買うことができますが、購入できる薬は「処方箋が必要ない医薬品」に限られています。
一部の薬は処方箋が必要です。
零売で薬を購入する際は、薬剤師が薬の効果や副作用などについて説明し、安全性を確認することが重要です。 -
質問:オンライン服薬指導は電話のみでもいいですか?回答:
以前は電話だけで薬のオンライン服薬指導が可能でしたが、新型コロナウイルス感染症の影響で、電話や情報通信機器を用いた時限的な対応が認められていました。
しかし、2023年8月以降の薬機法改正により、オンライン服薬指導には映像と音声が必要となり、電話のみでの指導はできなくなりました。
具体的な手続きや条件については、薬局の薬剤師に相談してください。 -
質問:オンライン服薬指導で薬を受け取る方法は?回答:
ブラパディスペンサリーでの薬についてのオンライン服薬指導の手順は次の通りです。
1.医療機関で診察を受け、処方箋をもらいます。
2.診察後、薬局から通知が届きます。
通知に従って、都合の良い日時と決済方法を選んで予約します。
3.予約した日時に、パソコンやスマートフォンで薬剤師からの説明や相談を受けます。
4.調剤が完了した後、薬剤師の指導を受けた薬が自宅に配送されます。
この手順で、自宅から薬剤師の説明や相談を受けながら、自宅で薬を受け取ることができます。 -
質問:オンライン服薬指導を受けている人の割合は?回答:
薬についてのオンライン服薬指導を受けている人の具体的な割合については、現在公開された情報はありません。
ただし、最近では、オンライン医療や遠隔医療の利用が増えており、新型コロナウイルスの影響で、リモート医療サービスへの需要が高まっています。