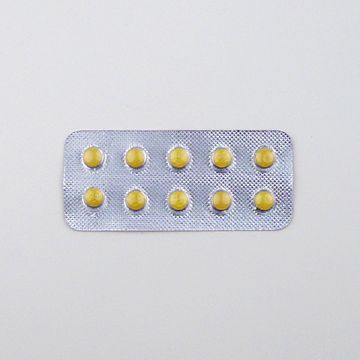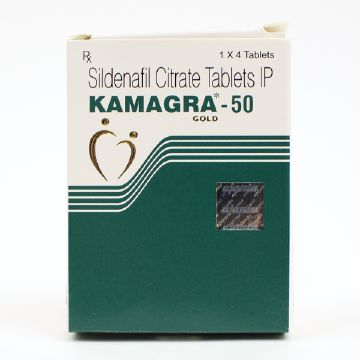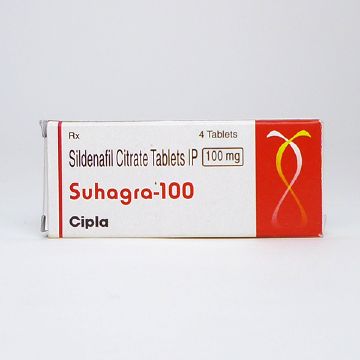第一三共ヘルスケア

-
英語表記Daiichi Sankyo Healthcare Co., Ltd.
-
設立年月日2006年4月3日
-
代表者髙橋 健太郎
-
国日本
-
所在地〒103-8234 東京都中央区日本橋3-14-10 日本橋ビル
生活者のQOL向上を目指す第一三共ヘルスケアの企業理念と事業概要
第一三共ヘルスケアは、第一三共グループの一員として「世界中の人々の健康で豊かな生活に貢献する」というパーパスを掲げています。
特に、生活者のセルフケアパートナーとして、人々のQOL向上に欠かせない製品やサービスの提供に注力しています。
同社のミッションは「生活者満足度の高い製品・サービスを継続的に生み出し、より健康で美しくありたい人々のQOL向上に貢献する」ことです。
このミッションのもと、OTC医薬品、機能性スキンケア・オーラルケア製品、健康食品など、幅広い製品ラインナップを展開しています。
2030年ビジョンとして、第一三共ヘルスケアは「人生100年時代のQOLを支え、独創的な製品と情報で新たな価値を生み出し、サステナブルな社会の発展に貢献する日本発コンシューマーヘルスケア企業」を目指しています。
この目標に向けて、革新的な製品開発や情報提供、社会貢献活動に積極的に取り組んでいます。
事業領域としては、主にOTC医薬品事業、スキンケア事業、オーラルケア事業、健康食品事業を展開しています。
OTC医薬品では、風邪薬や胃腸薬などの一般用医薬品を提供し、セルフメディケーションの推進に貢献しています。
スキンケア事業では、敏感肌向け製品などを展開し、肌トラブルに悩む人々をサポートしています。
オーラルケア事業では、歯周病予防や口腔ケア製品を提供し、口腔の健康維持を支援しています。
健康食品事業では、様々な機能性表示食品を展開し、日々の健康管理をサポートしています。
第一三共ヘルスケアの特徴として、医療用医薬品メーカーである第一三共グループの知見や技術を活かした製品開発が挙げられます。
これにより、高い品質と効果を兼ね備えた製品を提供することができています。
また、消費者ニーズを的確に捉えた製品開発や、わかりやすい情報提供にも力を入れており、生活者に寄り添った企業活動を展開しています。
さらに、第一三共ヘルスケアは、医療機関や薬局との連携も重視しています。
医療用医薬品からスイッチOTC薬への移行や、薬剤師による適切な情報提供のサポートなど、医療と生活者をつなぐ役割も果たしています。
このように、第一三共ヘルスケアは、生活者の健康と美容に関する幅広いニーズに応える製品・サービスを提供し、人々のQOL向上と社会の持続的発展に貢献することを目指しています。
第一三共ヘルスケアの主力製品ラインナップ
第一三共ヘルスケアは、幅広い製品ラインナップを展開し、生活者の多様なニーズに応えています。
同社の主な製品カテゴリーは、OTC医薬品、スキンケア製品、オーラルケア製品、そして健康食品に及び、それぞれの分野で高い品質と効果を誇る製品を提供しています。
OTC医薬品では、風邪薬「ルル」シリーズが長年にわたり信頼されており、総合感冒薬として幅広い層に支持されています。
さらに、「ガスター10」はH2ブロッカーを含む胃腸薬として知られており、胃の不調を抱える人々にとって欠かせない存在となっています。
また、「ロキソニンS」は、NSAIDsの代表的な鎮痛剤であり、頭痛や腰痛などの日常的な痛みに対して迅速に効果を発揮します。
加えて、「トランシーノ」シリーズの目薬は美白効果を謳っており、目の健康と美を両立させたい人に人気です。
スキンケア分野においては、敏感肌向けの「ミノン」シリーズがその中心的存在です。
低刺激性と高い保湿効果を併せ持つ製品は、敏感肌や乾燥肌に悩む人々に幅広く支持されています。
さらに、「トランシーノ」シリーズのスキンケア製品は、美白効果を追求した内服薬と外用薬の両方を展開し、美容意識の高い層に応えています。
これらの製品は、肌トラブルに悩む多くの生活者に信頼されており、美容と健康をサポートするための選択肢を提供しています。
オーラルケア製品では、歯周病予防や口臭ケアに特化した「クリーンデンタル」シリーズが注目されており、歯磨き粉や洗口液がラインナップされています。
これにより、口腔ケアを強化したい生活者に対して効果的な製品を提供し、口内の健康維持をサポートしています。
また、健康食品分野では、「ナチュラルケア」シリーズが機能性表示食品として展開され、生活者の健康ニーズに応えています。
多様な栄養素を含む製品群は、日々の健康維持をサポートし、健康的なライフスタイルの実現に貢献しています。
第一三共ヘルスケアの製品開発においては、親会社である医療用医薬品メーカー第一三共の専門的な知見と技術が活かされています。
これにより、高い品質と効果を追求しつつ、生活者のニーズに合わせた製品改良や新製品の開発にも積極的に取り組んでいます。
例えば、「ルル」シリーズでは、従来の総合感冒薬に加えて、症状に応じた製品ラインナップが展開され、生活者が自身の症状に合った薬を選べるよう工夫されています。
また、「ガスター10」は、もともと医療用医薬品であったものがスイッチOTC薬として開発され、より多くの人が手軽に利用できるようになった代表例です。
さらに、スキンケア製品においては、「ミノン」ブランドを通じて、敏感肌や乾燥肌に悩む人々に寄り添った製品開発を行っており、低刺激性と保湿効果にこだわった製品は多くの支持を集めています。
第一三共ヘルスケアは、これらの主力製品を通じて生活者の日々の健康維持と美容ニーズに応えるだけでなく、セルフメディケーションの推進にも大きく貢献しています。
今後も生活者の声に耳を傾け、革新的な製品開発を続けていくことが期待されており、同社はさらなる成長と発展を目指しています。
第一三共ヘルスケアの研究開発と品質管理
第一三共ヘルスケアは、生活者のQOLの向上に貢献するため、革新的な製品創出を目指して積極的に研究開発を展開しています。
同時に、製品の安全性と品質を確保するため、厳格な品質管理体制を整備し、信頼性の高い製品を提供しています。
これらの取り組みは、親会社である第一三共が持つ医療用医薬品開発の知見と技術を活用することで、OTC医薬品やヘルスケア製品の高品質化を実現しています。
第一三共ヘルスケアの研究開発の特徴の一つとして、医療用医薬品の開発で培った知見を応用し、効果的かつ安全性の高い製品を提供する点が挙げられます。
また、生活者のニーズを重視し、市場調査や消費者のフィードバックを積極的に取り入れて製品開発を行っています。
これにより、実際に求められている製品やサービスを迅速に市場に投入し、生活者の期待に応える製品を提供しています。
さらに、第一三共ヘルスケアは産学連携にも力を入れており、大学や研究機関との共同研究を通じて、最新の科学的知見を製品開発に取り入れています。
これにより、革新的な技術や成分を活用した製品を開発し、生活者の健康と美容に寄与する新たな価値を創造しています。
特に、服用しやすさや効果の持続性を高めるための新しい製剤技術の開発にも積極的に取り組んでおり、従来製品との差別化を図っています。
一方、品質管理の面では、GMPの厳格な遵守が徹底されています。
GMP基準に基づく製造管理と品質管理を行い、高品質な製品の安定供給を実現しています。
原料の調達から製造、出荷に至るまでの全工程において、厳密な品質チェックを実施し、製品の安全性と信頼性を確保しています。
この一貫した品質管理体制により、生活者に安心して使用してもらえる製品の提供を目指しています。
また、製品の安全性に関しては、市販後の使用情報を継続的に収集・評価する仕組みを整えています。
これにより、万が一の問題が発生した場合でも、迅速に対応し、製品の安全性を高めるための改善が行われます。
さらに、トレーサビリティの確保にも注力しており、製品のロット管理を徹底することで、問題発生時には早急に原因を特定し、適切な対応を取ることが可能です。
第一三共ヘルスケアは、これらの研究開発と品質管理の取り組みを通じて、生活者に信頼される製品の提供を目指しています。
特にOTC医薬品の分野では、有効性と安全性のバランスを慎重に検討し、適切な情報提供を行いながら、生活者が安心して使用できる製品を開発・提供しています。
今後も、生活者のニーズに応え、革新的な製品を生み出すことで、セルフメディケーションの推進に貢献し、健康的な生活を支えるパートナーとしての役割を果たしていくことが期待されています。
第一三共ヘルスケアのサステナビリティ活動
第一三共ヘルスケアは、企業のCSRを重視し、持続可能な社会の実現に向けた活動を展開しています。
社会貢献活動として、学校や地域での健康セミナーを通じて健康教育を推進し、正しい医薬品の使用方法や健康管理に関する情報を提供しています。
また、災害時には被災地への医薬品の無償提供や医療支援活動に積極的に参加し、途上国への医薬品提供プログラムや希少疾患患者支援団体との協力も行っています。
次世代育成にも注力し、子供向けの科学教室やインターンシップの提供を通じて、未来の人材を育成しています。
環境への取り組みとしては、CO2排出量の削減や省エネルギー設備の導入、製品包装材の軽量化、リサイクル可能な材料の使用促進、水使用量削減や排水処理技術の向上に取り組んでいます。
さらに、生物多様性を保護するため、工場敷地内での緑化活動や、生態系に配慮した原料調達を推進しています。
加えて、環境負荷を軽減する製剤技術やリフィル製品の開発にも力を入れています。
これらの活動を通じ、第一三共ヘルスケアはSDGsの達成にも貢献しており、「すべての人に健康と福祉を」、「質の高い教育をみんなに」、「気候変動に具体的な対策を」などに焦点を当てています。
また、従業員の多様性やワーク・ライフ・バランスの推進、女性活躍支援にも積極的に取り組んでおり、持続可能な企業成長と社会貢献を両立させています。
引用 : https://www.daiichisankyo-hc.co.jp/
引用 : https://www.daiichisankyo-hc.co.jp/products/
よくあるご質問(FAQ)
-
質問:第一三共ヘルスケアはどんな会社?回答:
第一三共ヘルスケアは、第一三共グループの医薬品メーカーです。
第一三共ヘルスケアは、2005年に第一製薬と三共が合併して誕生した製薬企業です。
主に一般用医薬品、スキンケア、オーラルケアなどを取り扱っています。
本社は東京都中央区にあります。 -
質問:第一三共ヘルスケアは上場していますか?回答:
第一三共ヘルスケアは非上場の企業です。
一方、親会社の第一三共株式会社は、東京証券取引所のプライム市場に上場しています。
第一三共ヘルスケアは、第一三共グループの一員として医薬品を製造している会社です。 -
質問:第一三共の有名な薬は?回答:
第一三共の有名な薬には、グローバルに展開している抗悪性腫瘍剤「エンハーツ」や抗凝固剤「リクシアナ」があります。
国内では、鎮痛剤の「ロキソニン」やしみや肝斑に効果のある「トランシーノ」も広く知られています。
第一三共は、第一製薬と三共が合併して設立された製薬企業で、120年以上の歴史を持ち、長い間サイエンスとテクノロジーの伝統を受け継いできました。 -
質問:第一三共の有名な商品は?回答:
第一三共は循環器領域に強みを持ち、近年ではがん領域にも注力しています。
特にグローバルに有名な製品として、抗悪性腫瘍剤の「エンハーツ」と抗凝固剤の「リクシアナ」があります。
これらの製品は、治療効果が高く、多くの患者に利用されていることから、第一三共の代表的な商品となっています。 -
質問:第一三共の平均年収は?回答:
第一三共の年収は、職種によって異なりますが、全体的に高めの水準です。
年収の範囲は300万円から1,600 万円で、平均年収は約840万円です。
具体的には、営業系の職種で約810万円、事務・管理系で約800万円、医薬・化学などの専門職で約980万円となっています。
これは、日本の平均年収が約460万円であるのに対し、かなり高い水準です。 -
質問:第一三共の何がすごいのですか?回答:
第一三共の強みは、循環器領域での実績と、近年のがん領域への注力です。
特に、がん領域では「がんに強みを持つ先進的グローバル創薬企業」を目標に掲げ、2025年までにその実現を目指しています。
主要な製品には、抗悪性腫瘍剤が含まれており、先進的な医薬品の開発に挑戦し続けています。
これにより、革新的な治療法の提供とグローバルな医療ニーズへの対応を進めています。 -
質問:第一三共ヘルスケアはホワイト企業ですか?回答:
第一三共ヘルスケアはホワイト企業として評価されています。
平均年収は800万円を超え、これは医薬品業界の平均よりも高い水準です。
さらに、日本人の平均年収が約460万円であることを考えると、かなり高い水準となっています。
また、有給消化率も高めで、社員の働きやすさがうかがえます。
このように、良好な労働環境と高い年収水準から、第一三共ヘルスケアは高い満足度を持つ企業と考えられます。 -
質問:第一三共の不祥事ってどんなの?回答:
2022年9月、第一三共で新薬の開発に従事していた男性研究員が、妻に対して毒性のある「メタノール」を飲ませたとして逮捕されるという事件が発生しました。
メタノールは天然ガスから製造されるアルコールの一種で、酢酸やホルマリンの原料として使われる他、エチレンやプロピレンの製造にも使用されます。
人体に多量に摂取すると急性メタノール中毒を引き起こし、視覚障害や吐き気、腹痛、筋肉痛、めまい、衰弱、昏睡などの重篤な症状が現れることがあります。 -
質問:第一三共はランキング何位ですか?回答:
2024年の国内製薬会社売上高ランキングで、第一三共は約1兆6000億円の売上を記録し、第4位にランクインしています。
この成績は、抗がん剤「エンハーツ」や抗凝固剤「リクシアナ」の売上増加によるもので、特にこれらの製品の好調な伸び率が影響しています。 -
質問:第一三共は買収されるのか?回答:
第一三共は2023年に、後発医薬品子会社である第一三共エスファを調剤薬局大手のクオールホールディングスに売却することを発表しました。
この取引で、第一三共は全株式を250億円で譲渡し、国内の後発医薬品事業から撤退することになります。
今後は、抗がん剤などの新薬に経営資源を集中する方針を示しています。 -
質問:日本で1番大きい製薬会社は?回答:
日本で最も大きな製薬会社は武田薬品工業です。
2023年度の売上高は約4.3兆円で、2位の大塚ホールディングスの約2.0兆円を大きく上回り、国内トップの座を確立しています。
また、2022年度には世界の製薬業界においても売上高で第11位にランクインしており、日本を代表する大手製薬会社としてグローバルにリーダーシップを発揮しています。 -
質問:第一三共の特徴は?回答:
第一三共は、循環器領域に強みを持つ一方で、近年はがん領域にも注力しています。
特に、抗悪性腫瘍剤のエンハーツや抗凝固剤のリクシアナといった製品が世界的に高く評価されています。
これらの製品は、同社の先進的な医薬品開発への取り組みを象徴しており、革新的な治療法を提供し続けています。 -
質問:第一三共の採用大学はどこですか?回答:
第一三共は毎年約100名の新卒を採用しており、その採用倍率は100倍を超えることもあります。
採用大学のトップには慶應義塾大学が位置し、次いで大阪大学、東京大学が続いています。
これらの大学から優秀な人材を積極的に採用していることが、同社の高い競争力と専門性を支えています。 -
質問:第一三共のキャッチフレーズは?回答:
第一三共のキャッチフレーズは「イノベーションに情熱を。ひとに思いやりを。」です。
このスローガンは、革新的な医薬品の継続的な創出と、多様な医療ニーズに応える製品提供という企業のミッションを反映しています。
企業の価値観として、イノベーションと人への思いやりを大切にする姿勢が表れています。 -
質問:第一三共グループには何人いますか?回答:
第一三共グループは、様々な企業から構成される大手製薬企業です。
2023年時点で、第一三共単体の従業員数は5,700人を超えています。
また、グループ全体の連結従業員数は1万7,000人以上で、国内外に広がる大規模な人員体制を誇ります。
この規模により、グローバルに展開し、医薬品の研究開発から販売まで幅広く対応しています。 -
質問:第一三共のMRの給料はいくらですか?回答:
第一三共のMR(医薬情報担当者)の年収は、平均で約800万円から900万円とされています。
MRの仕事は主に営業活動が中心で、外回りが多くなります。
そのため、営業日当や営業手当、車代などの手当も支給されることが一般的です。
日本の平均年収が約460万円であるのに対し、第一三共のMRの年収は高い水準にあり、業界内でも競争力のある待遇となっています。 -
質問:日本の5大製薬会社は?回答:
日本の5大製薬会社は、医薬品の開発から生産、販売までを手がける重要な企業です。
これらの企業は、日本の製薬業界の中で特に大きな影響力を持っています。以下の5社がその代表です。
1.武田薬品工業:国内最大手の製薬会社で、広範な製品ラインと国際的な展開を持つ。
2.第一三共:循環器領域やがん領域に強みを持ち、革新的な医薬品の開発に注力している。
3.アステラス製薬:多様な治療領域に対応し、特に泌尿器科やがん治療薬において実績がある。
4.エーザイ:神経領域の薬剤に強みがあり、認知症治療薬などで高い評価を得ている。
5.大塚ホールディングス:幅広い製品ポートフォリオを持ち、国内外での展開を行っている。
これらの企業は、それぞれ独自の専門性や強みを持ち、日本を代表する製薬会社となっています。 -
質問:第一三共の株が下がっている理由は何ですか?回答:
第一三共の株価が伸び悩む理由はいくつかありますが、その一因として契約金の構造が挙げられます。
具体的には、契約金総額約3.3兆円のうち、約2.5兆円が「販売マイルストン」に基づくものであり、その70%以上が「販売後」の受領となっている点が影響しています。
この様な契約構造では、収益化までに長期間かかる可能性があり、短期的な株価の上昇を妨げる要因となっています。
また、製薬業界全般に影響を及ぼす市場環境や規制の変化、競争の激化なども、第一三共の株価に影響を与えている可能性があります。
企業の成長性や収益性を左右する要因は多岐にわたるため、株価の動向はこれらの複合的な要因によって変動することが多いです。 -
質問:第一三共は増配するのでしょうか?回答:
増配とは、前年に比べて株主に支払う配当金の額が増加することを指します。
第一三共は、2024年3月期に年間配当金を前期比で10円増の40円に引き上げることを発表しました。
これは、従来の見通しよりも6円の増配となります。
増配の背景には、主力のがん治療薬「エンハーツ」の販売増や、米メルクとのがん治療薬に関する提携から得る対価による利益の増加があります。
配当金の増配は、会社の業績が好調であることを示しており、株主への還元を強化する姿勢を反映しています。 -
質問:第一三共の今後の株価はどうなるのでしょうか?回答:
第一三共の今後の株価について、2024年のアナリスト予測によると、平均目標株価は6,228円とされています。
これに基づいて、株価は現在の水準から約4.02%の上昇が予想されています。
株価とは、企業が発行する株式1株あたりの市場価格で、企業の資金調達の手段であるとともに、企業の業績や市場の評価を反映するものです。
株価は日々変動するため、将来の動向を予測するのは難しいですが、第一三共の株価が上昇する見込みがあるとされているのは、同社の業績や市場の期待が反映されているからです。