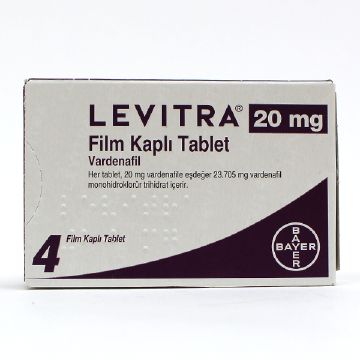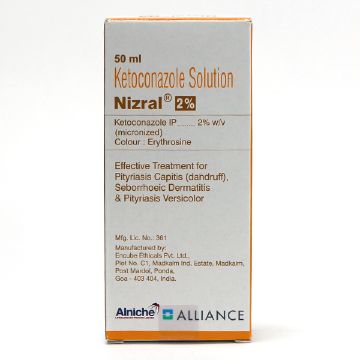大正製薬

-
英語表記Taisho Pharmaceutical Co.,Ltd.
-
設立年月日1928年(昭和3年)5月5日
-
代表者上原 茂
-
国日本
-
所在地東京都豊島区高田3丁目24番1号
100年以上の伝統を持つ大正製薬の歴史と企業理念
大正製薬は、1912年に創業者・上原正吉によって設立された日本を代表する製薬企業です。
創業以来、「健康と美を願う生活者に納得していただける優れた医薬品・健康関連商品、情報及びサービスを、社会から支持される方法で創造・提供することにより、社会へ貢献する」という企業理念のもと、一世紀以上にわたり日本の医療と健康に貢献してきました。
創業当初は、胃腸薬「大正胃腸薬」の製造販売からスタートし、その後、風邪薬や栄養ドリンクなど、日本人の日常生活に密着した医薬品の開発・販売を手がけてきました。
特に1961年に発売された「リポビタンD」は、高度経済成長期の日本社会に大きなインパクトを与え、栄養ドリンク市場を確立する契機となりました。
大正製薬の歴史は、日本の製薬業界の発展と軌を一にしています。
1950年代から60年代にかけては、抗生物質や抗がん剤などの新薬開発に取り組み、医療用医薬品事業にも進出しました。
1980年代以降は、バイオテクノロジーを活用した新薬開発にも注力し、研究開発型製薬企業としての地位を確立しています。
企業理念の実現に向けて、大正製薬は「自主創薬」「セルフメディケーションへの貢献」「国際化」の3つを経営の柱としています。
自主創薬では、独自の技術と知見を活かした新薬開発に取り組み、医療の発展に寄与しています。
セルフメディケーションへの貢献では、OTC医薬品やヘルスケア製品の開発・販売を通じて、人々の健康維持・増進をサポートしています。
国際化では、アジアを中心としたグローバル展開を進め、世界の人々の健康に貢献することを目指しています。
大正製薬の企業文化の特徴として、「挑戦と革新」の精神が挙げられます。
創業以来、時代のニーズに合わせた新製品の開発や、新しい市場の開拓に積極的に取り組んできました。
例えば、1980年代には健康食品市場に参入し、「リビタ」ブランドを立ち上げるなど、常に新しい分野への挑戦を続けています。
また、大正製薬は「品質第一」の姿勢を貫いています。
厳格な品質管理システムを構築し、原料の調達から製造、販売に至るまでの全プロセスで高い品質基準を維持しています。
この姿勢は、消費者からの信頼獲得につながり、ブランド価値の向上に大きく貢献しています。
大正製薬は、これらの理念と伝統を守りつつ、常に時代の変化に対応し、革新を続けています。
大正製薬の主力製品と市場戦略
大正製薬は、OTC医薬品、医療用医薬品、ヘルスケア製品、化粧品など多岐にわたる製品を展開しており、特にOTC医薬品の分野では日本市場でトップクラスのシェアを誇ります。
代表的な製品である「リポビタンD」は、1961年の発売以来、疲労回復や栄養補給に効果的な栄養ドリンクとして広く利用されており、ゼロカロリーの「リポビタンファイン」など、健康志向に応じたラインナップの拡充も進めています。
このように、消費者ニーズに応じた製品展開により、多様な年齢層から支持されています。
風邪薬市場では「パブロン」シリーズが知られており、「パブロンゴールドA」は総合感冒薬として風邪のさまざまな症状に対応する一方、顆粒やスティックタイプなど、携帯しやすい形状の製品も提供しています。
さらに、大正製薬は胃腸薬分野でも強力な存在感を持ち、100年以上の歴史を持つ「大正胃腸薬」は、消化不良や胃の不調を和らげる製品として高い信頼を築いています。
また、便秘薬「コーラック」などもラインナップに含まれ、幅広い消化器系の問題に対応しています。
特に「大正胃腸薬」は、その長い歴史とブランド力から、国内市場での安定した人気を誇っています。
ヘルスケアおよび機能性食品分野では、「リビタ」ブランドを中心に特定保健用食品や機能性表示食品を展開し、科学的根拠に基づいた製品開発を行っています。
たとえば「リビタ コレステロール」や「リビタ ミドルケア」は、コレステロールや血糖値の管理を意識する中高年層をターゲットにした製品で、健康意識の高い消費者層に支持されています。
大正製薬の市場戦略は、長年培われてきた強力なブランド力を活かし、幅広い製品ラインナップの拡充を図ることにあります。
「リポビタン」や「パブロン」といった高い知名度のブランドを基盤に、消費者との信頼関係を深め、新たな製品を投入しています。
また、消費者の年齢層や症状、ライフスタイルに応じたセグメント戦略を展開し、幅広いニーズに対応する製品を提供しています。
販売チャネルにおいても、ドラッグストアやコンビニエンスストアなど、日常的に訪れる店舗での取り扱いを強化し、消費者の購買機会を最大化しています。
今後は、デジタル技術の活用やパーソナライズド・ヘルスケアの進展に対応することが課題とされますが、大正製薬は豊富な経験と技術力を活かし、さらなる成長を目指しています。
大正製薬の未来の医療に向けた取り組み
大正製薬は、「自主創薬」を経営の柱の一つとして掲げ、革新的な医薬品の創出に向けて積極的な研究開発投資を行っています。
同社は、医薬品の開発において重点領域を設定し、中枢神経系疾患、免疫・アレルギー疾患、代謝性疾患を中心に新薬の開発に取り組んでいます。
また、オープンイノベーションを推進し、大学や公的研究機関との共同研究、ベンチャー企業への投資、ライセンス導入など、多様な形で連携しています。
さらに、AIやビッグデータ解析を活用することで、創薬プロセスの効率化を図り、開発期間の短縮とコスト削減を実現しています。
同社の研究開発は、低分子化合物だけでなく、抗体医薬品や核酸医薬品、細胞治療など、多様なモダリティを取り入れた創薬にも注力しています。
具体的な成果として、NS-304(セレキシパグ)という肺動脈性肺高血圧症の治療薬が上市され、現在も多くの患者に使用されています。
さらに、開発中のTS-142は、アルツハイマー型認知症の治療薬として注目されており、TS-091は関節リウマチなどの自己免疫疾患治療薬として期待されています。
また、既存の製品についても、適応症の拡大や剤形改良を行うことで、製品の価値向上を図っています。
大正製薬の研究開発戦略は、短期的な成果だけでなく、中長期的な視点で価値創造を目指しており、アンメットメディカルニーズの高い疾患領域における新薬開発を重視しています。
さらに、予防医学やセルフメディケーションの分野でも、社会的ニーズに応える製品の開発に力を入れています。
今後も、最先端技術とオープンイノベーションを融合させることで、革新的な医薬品の創出を加速させ、社会全体の健康維持に貢献することが期待されています。
大正製薬のグローバル展開と持続可能性への取り組み
大正製薬は、日本国内での強固な事業基盤を背景に、グローバル市場への積極的な展開を進めています。
特にアジア市場を中心に、現地ニーズに合わせた製品開発や販売戦略を構築し、海外事業の拡大を図っています。
このグローバル展開の一環として、海外企業とのパートナーシップを強化し、各市場の特徴に合わせて対応を行っています。
研究開発においても、大正製薬は国際的な視点を持ちながら医薬品開発を進めており、各地域の規制当局との連携や国際共同治験の実施を通じて、世界規模での医薬品提供を目指しています。
また、海外の研究機関や大学との共同研究を行い、グローバルな人材の獲得や育成にも力を入れています。
これにより、最新の科学技術を駆使し、革新的な医薬品の開発を推進しています。
さらに、大正製薬は持続可能性への取り組みにも注力しており、環境保護、社会貢献、ガバナンスの強化を重視しています。
環境面では、省エネルギー対策や廃棄物削減、水資源の保護に努めており、企業全体での環境負荷の低減を図っています。
社会貢献活動としては、途上国への医薬品提供プログラムや健康教育の普及活動などを展開しており、世界中の人々の健康に寄与しています。
大正製薬はまた、持続可能な事業運営を実現するため、サプライチェーン全体での環境や人権への配慮を徹底し、デジタル技術を活用した業務効率化にも取り組んでいます。
これにより、SDGsの達成に貢献し、企業としての責任を果たす姿勢を示しています。
こうした取り組みを通じて、企業価値の向上と社会的責任の両立を目指しています。
今後、大正製薬はデジタルヘルスケアやパーソナライズド医療など、新たな医療ニーズに対応することが求められますが、長年培ってきた技術力とブランド力を活かしながら、柔軟に対応していくことが期待されています。
同社は、これらの取り組みを通じて、グローバルな市場における競争力をさらに強化し、持続的な成長を続けることを目指しています。
引用 : https://www.taisho.co.jp/
引用 : https://www.taisho-holdings.co.jp/
よくあるご質問(FAQ)
-
質問:大正製薬は上場していますか?回答:
大正製薬ホールディングスの株式は、東京証券取引所スタンダード市場から、2024年4月9日に上場廃止となりました。
その理由は、自社株買収(MBO)を通して、高齢化社会に伴う社会保障費・医療費の増大に対する迅速な意思決定ができるように経営体制を見直すためです。
大正製薬は大正元年の1912年に「大正製薬所」として創業しました。
1963年に東京証券取引所市場第2部に上場し、1966年には東京証券取引所市場第1部に指定されていました。 -
質問:大正製薬は世界で何位ですか?回答:
世界の一般医薬品メーカーの中で、2021年度に売上高で第7位になりました。
今後もさらにグローバル市場に進出していく予定です。
一方、国内では2021年の一般医薬品の売り上げは1位でした。
主力商品の「リポビタン」や「パブロン」、「リアップ」などがあります。
そこに加え、近年では女性の美と健康をサポートする「TAISHOBEAUTYONLINE」やエイジングケアブランドの「THEMYTOL」などの新しい領域にも積極的に展開しています。 -
質問:大正製薬の年収は?回答:
転職・就職のための情報プラットフォームであるOpenWorkによると、大正製薬の正社員266人に対するアンケート調査では、平均年収は672万円、年収の幅は380万円から1,100万円でした。
職種別の平均年収は、研究者が687万円、営業職が637万円、MRが608万円、開発者が691万円でした。 -
質問:大正製薬はどんな会社?回答:
大正製薬は大正元年の1912年に「大正製薬所」として設立されました。
以来、健康と美の追求をする人を支える「安心」と「信頼」のブランドとして成長してきました。
現在は、セルフメディケーションと医薬品という2つの事業をグローバルに展開しています。
セルフメディケーション事業では「リポビタン」「パブロン」「リアップ」などが主力商品です。
一方、医薬品事業では、整形外科疾患・代謝疾患・感染症・精神疾患などの領域で薬剤の研究開発から販売までを行っています。
代表的な製品に「クラリス」や「リーマス」などがあります。 -
質問:大正製薬の初任給はいくらですか?回答:
大正製薬の公式ホームページによると、初任給は以下のようになっています。
・学部卒:265,000円
・修士、6年制学部卒:300,000円
・博士卒:350,000円
賞与は年に3回を予定されており、昇給の機会も1年に1回設けられています。 -
質問:大正製薬の就職難易度は?回答:
2023年2月の東洋経済新聞の調査による「入社が難しい有名企業ランキング」で、大正製薬の就職難易度は「60.2」で107位でした。
この難易度は、就職者の人数と出身大学の情報を基に、大学と企業へのアンケート調査と駿台予備学校の模試データを組み合わせて算出されたものです。
最も就職が難しい企業は、難易度「68.9」のマッキンゼー・アンド・カンパニー・インコーポレイテッド・ジャパンでした。 -
質問:大正製薬の出身大学はどこですか?回答:
大正製薬の公式ホームページによると、2021年4月から2023年4月の3年間に採用した大学は、全国の国公立大学や私立大学に分散しています。
北は北海道大学、南は九長崎大学、国公立は東京大学や京都大学、私立大学では早稲田大学や立命館大学の出身者が採用されています。 -
質問:製薬会社に強い大学はどこですか?回答:
ダイアモンドオンラインによる、武田薬品・アステラス製薬・中外製薬の2022年の新卒採用社のランキングに関する調査を参考にすると、東京大学、京都大学、大阪大学、東北大学など旧帝大の国立大学が上位を占めていました。
私立大学では慶應大学や東京理科大学が上位にランクインしました。
全体の傾向として、難易度が高い国立大学と私立大学の人材を採用する傾向が高いと言えます。 -
質問:大正製薬の月収はいくらですか?回答:
求人情報サイトのindeedによると、大正製薬の月収は25万円から38.8万円とされています。
具体的には、創薬研究職が月給25万円、臨床研究関連の職種が月給38.8万円になっています。
大正製薬では、年3回の賞与と1回の昇給の機会があります。
エン・ジャパンのアンケート調査にろよると、25歳から29歳の平均年収は547万円になります。 -
質問:大正製薬の30歳の年収は?回答:
エン・ジャパンによるアンケート調査によると、大正製薬の30歳から34歳の29名の平均年収は573万円で、大正製薬の平均年収703万円よりも低い結果でした。
大正製薬では年齢が上がると年収が上がる傾向にあり、40歳から44歳になると平均年収が777万円となり、全体平均の703万円を上回ることがデータからわかります。 -
質問:大正製薬は住宅手当はありますか?回答:
大正製薬の公式ホームページによると、住宅手当は世帯区分によって額が異なります。
具体的には、自宅の場合には月5,000円、一人で済んでいる場合は月2万円、結婚している場合は月3万円となっています。
ただし、会社の独身寮や、借り上げ社宅に住んでいる人は対象外です。 -
質問:大正製薬のボーナスはいくらですか?回答:
大正製薬のボーナスは、年3回(夏、冬、期末)支給されます。
就職情報サイトのOpenWorkによると、ボーナスの支給額は合計で約5ヵ月分から6ヵ月分のことが多いとされていますが、会社全体の業績、社員の評価によって変動することがあります。
そのため、ボーナスが支給されなかったり、約1ヵ月の支給額になったりすることもあります。 -
質問:大正製薬は土日休みですか?回答:
大正製薬は週休2日制で、土日は休みです。
年次有給休暇は10日から20日まで取得でき、リフレッシュ休暇や特別休暇も設定されています。
祝日や夏季・年末年始休暇も別途設定されており、長期休みの予定は立てやすいとの評判です。 -
質問:大正製薬は宗教と関係がありますか?回答:
大正製薬は特定の宗教とは関係がありません。
社会や消費者からの信頼を得るために、同社はコンプライアンスに積極的に取り組んでいます。
2001年には「全社行動指針」を制定し、2006年には「部署別行動指針」を作成して各部署に具体的な指針を示しました。
さらに、2018年にはグローバル展開を見据えて「グローバルコンプライアンス・ガイドライン」を策定し、実践しています。
このように、大正製薬は法令遵守と倫理的な行動を徹底しています。 -
質問:製薬会社の給料が高いのはなぜですか?回答:
製薬会社の給料が高い理由は主に3つです。
1.高い利益率:医薬品や医療機器は、高い利益率を誇ります。新薬や医療機器の開発には多額の費用がかかりますが、販売が成功すれば高い利益を上げることができます。そのため、利益の一部を従業員の給与として還元することができます。
2.大きな市場規模:医薬品や医療機器の市場は非常に大きいです。世界中の人々が顧客となるため、ヒット商品が出れば数千億円規模の売り上げが期待できます。このため、収益を従業員の給与に反映させることができます。
3.専門知識の需要:製薬会社は化学や生物学の専門知識を持つ人材を求めています。高度な専門知識を持つ職員を確保するためには、高い給与などの魅力的な待遇が必要です。 -
質問:なぜMRは高収入なのでしょうか?回答:
MR(MedicalRepresentative)とは、製薬会社で働く営業職のことです。
MRは、自社製品の正しい使用法を医師や薬剤師に説明し、製品の普及を進める役割を担っています。
MRの給料が比較的高い理由は2つあります。
1.専門知識が求められる:MRは、医薬品に関する幅広い専門知識を持つ必要があります。
自社製品だけでなく、他社製品についても情報を把握する必要があるため、優秀な人材を確保するために高い給与が設定されています。
2.各種手当が充実:MRは、外勤手当、出張手当、住宅手当などの各種手当が支給されます。
これらの手当が給与に追加されるため、収入が増加します。 -
質問:製薬会社に入るには何学部?回答:
製薬会社で働きたい人は、薬学部や理学部などの理系学部に進学することが多いです。
これは、製薬会社には様々な職種があり、それぞれに専門的な知識や経験が必要だからです。
例えば:
・MR(営業職):医薬品に関する専門知識が求められます。
・研究開発職:化学や生物の専門知識と経験が必要です。
・薬剤師:薬学の知識が必要です。
このように、製薬会社で活躍するためには、その職種に必要な専門教育を受けることが重要です。
だから、製薬会社でのキャリアを考えている人は、薬学部や理学部など、将来の仕事に役立つ知識を学べる学部を選ぶ傾向があります。 -
質問:製薬会社で年収が高い職種は?回答:
製薬会社で比較的年収が高い職種はMRです。
転職サービスのマイナビエージェントの調査によると、MRの平均年収は20代で500万円、30代で700万円とされています。
MRは医薬品に対する専門知識に加え、営業のインセンティブや各種手当が支給されるため、年収が高くなる傾向があります。 -
質問:年収900万円を稼ぐのは難しいですか?回答:
国税庁の「令和4年度民間給与実態統計調査」によると、給与が900万円から1,000万円の人は全体の2.2%、つまり112万人です。
また、年収が1,000万円を超える人は全体の7.6%、つまり387万人です。 -
質問:製薬会社業界で1位はどこですか?回答:
2024年の世界の製薬会社売上ランキングで1位はロシュで、売上は673億円でした。
ロシュの新薬、例えば網膜疾患に対する抗体薬バビースモの売上が好調でした。
日本の製薬会社での2024年の売上ランキング1位は武田薬品工業で、売上は4.3兆円でした。
武田薬品工業の抗体薬エンタイビオが特に好調でした。