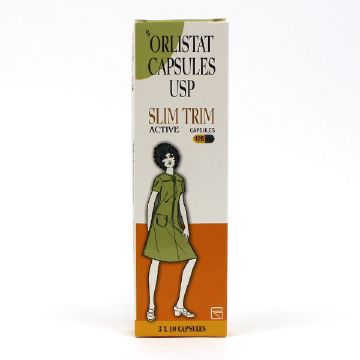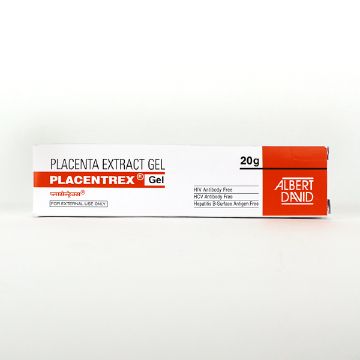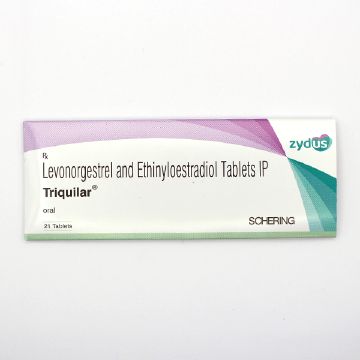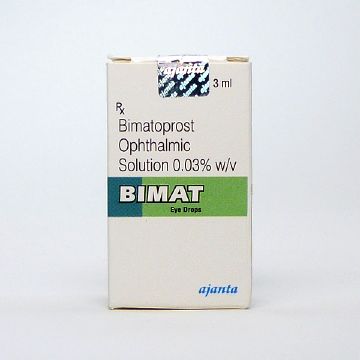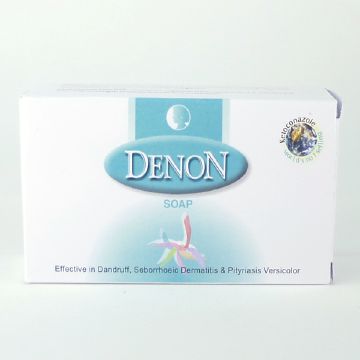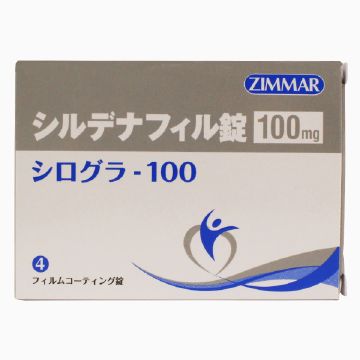ウィンメディケア

-
英語表記Win Medicare
-
設立年月日1981年4月28日
-
代表者Umesh Kumar Modi
-
国インド
-
所在地1311, MODI TOWER, 98 NEHRU PLACE, NEW DELHI, Delhi, India
インドの製薬業界におけるリーディングカンパニー、ウィンメディケア
ウィンメディケアは、1980年代初頭にUmesh K. Modi氏によって設立された、インドの主要な製薬会社の一つです。
Umesh Modi Groupの一部として、ウィンメディケアはインドで最も急成長している製薬企業の一つとして認識されています。
同社の成功は、革新的な製品ラインナップと戦略的な国際提携に基づいています。
ウィンメディケアは、アメリカ、ドイツ、スイスから技術、医薬品、ヘルスケア製品、研究開発を調達し、着実に成長を遂げてきました。
特筆すべきは、1980年代後半のスイスの製薬大手Mundipharma Group of Companiesとの提携です。
この提携により、Win-Medicareは高品質な医薬品の製造と品質保証の面で大きな飛躍を遂げました。
ウィンメディケアの主力製品の一つは、局所殺菌剤Betadine(R)です。
75カ国以上で信頼されているこの製品は、同社の国際的な評価を高めるのに貢献しています。
さらに、ウィンメディケアは他のグローバル企業とも提携関係を築いています。
例えば、シンガポールのMerz Asia Pacific Pvt. Ltd.と提携し、肝臓治療薬HepaMerz(R)や瘢痕管理治療薬Contractubex(R)などの製品を販売しています。
ウィンメディケアの事業は国内市場にとどまらず、南アジアやアフリカ市場にも展開しています。
効率的なマーケティングおよび流通ネットワークを通じて、同社は感染予防、疼痛緩和、不妊治療管理など、様々な専門分野で製品を提供しています。
2005年には、OTCおよびOTX製品を扱う戦略的事業部門としてWin Healthcareを設立し、事業の多角化を図っています。
ウィンメディケアは、倫理的な事業運営にも力を入れており、コンプライアンスホットラインを設置しています。
これにより、透明性の高い企業文化を醸成し、顧客や取引先からの信頼を獲得しています。
v
インドの製薬市場は非常に細分化されていますが、ウィンメディケアはその中で確固たる地位を築いています。
同社の成功は、革新的な製品開発、戦略的な国際提携、効率的な事業運営の結果であり、今後もインドの製薬業界をリードする企業として成長が期待されています。
ウィンメディケアのグローバル展開と製品ポートフォリオの拡大
ウィンメディケアは、1980年代初頭の設立以来、グローバル展開と製品ポートフォリオの拡大を通じて、インドの製薬業界で重要な地位を確立してきました。
同社の成長戦略は、国際的な提携関係の構築と多様な製品ラインナップの開発に基づいています。
ウィンメディケアの国際展開は、1980年代後半のMundipharma Group of Companies(スイス)との提携に始まります。
この提携により、同社は高度な製剤技術と品質管理システムを獲得し、国際水準の製品開発能力を手に入れました。
さらに、ウィンメディケアは世界各国の製薬企業との提携を積極的に推進しています。
例えば、Napp Pharmaceutical Group(イギリス)やPurdue Frederick Co.(アメリカ)との関係を通じて、最新の医薬品技術や研究開発の成果を取り入れています。
製品ポートフォリオの面では、ウィンメディケアは幅広い治療分野をカバーしています。
局所殺菌剤Betadine(R)は同社の代表的な製品で、75カ国以上で使用されており、ウィンメディケアの国際的な評価を高めています。
肝臓治療薬HepaMerz(R)や瘢痕管理治療薬Contractubex(R)など、特定の治療分野に特化した製品も展開しています。
これらの製品は、シンガポールのMerz Asia Pacific Pvt. Ltd.との提携を通じて販売されています。
最近では、Pierre Fabre(フランス)のオーラルケア製品、Sigma Tau(イタリア)のCarnitor(TM)、Norgine(オランダ)のMoviol(R)とMoviprep(R)、LG Life SciencesのCorion(R) C(hCG)など、新たな製品の導入や販売契約の締結を進めています。
ウィンメディケアの事業領域は、感染予防、疼痛緩和、不妊治療管理など多岐にわたります。
この多様な製品ラインナップにより、同社は変化する医療ニーズに柔軟に対応し、市場シェアを拡大しています。
同社の成功の背景は、効率的なマーケティングおよび流通ネットワークも挙げられます。
インド国内市場だけでなく、南アジアやアフリカ市場にも展開し、各地域のニーズに合わせた製品供給を行っています。
さらにウィンメディケアは、研究開発にも積極的に投資しています。
アメリカ、ドイツ、スイスの企業や研究機関と連携し、最新の医薬品技術や治療法の開発に取り組んでいます。
引用 : ttps://www.tofler.in/win-medicare-private-limited/company/U51397DL1981PTC011647
引用 : https://umeshmodigroup.com/win-medicare.html
引用 : https://www.zaubacorp.com/company/WIN-MEDICARE-PRIVATE-LIMITED/U51397DL1981PTC011647
よくあるご質問(FAQ)
-
質問:なぜ薬がないのでしょうか?回答:
薬が足りない理由は様々あります。
「製造段階で問題があり供給が停止」「原材料の不足」「災害などの影響により輸送が遅延」「他の薬が不足している場合に似た薬も不足」様々な背景から薬が十分に行き届かない状況になっています。 -
質問:なぜ薬が供給不足になるのでしょうか?回答:
供給不足の原因も様々ですが、製造工程や含有量が逸脱している場合は供給が停止し、一時的に薬を作ることができない状況となります。
普段納品されている薬であれば安定して納品されることもあります。
しかし、薬局、病院が取引していない薬に関しては納品されないことが多々あります。 -
質問:なぜ処方箋がないと薬はもらえないのか?回答:
「処方箋医薬品」に分類される医療用医薬品は医師の処方がないとお渡しすることができません。
安全性と適切な使用を確保するために、医師と薬剤師によるダブルチェックが行われています。
処方箋医薬品に該当しない医療用医薬品に関しては販売している薬局(零売薬局)も存在します。 -
質問:残薬は社会問題になっていますか?回答:
残薬による社会問題としては1番の問題は「医療費の無駄」になってしまうことです。
患者さんの窓口支払いは1割~3割でそこまで負担にならないことが多いですが、全体金額は膨大になります。
平成27年のデータから1890薬局5447名の患者さんの残薬は合計で8,529,846円であり、1人あたり4,885円でした。 -
質問:残薬は医師に伝えるべきですか?回答:
残薬がある場合は医師に伝えましょう。
「医療費の無駄」になることももちろんですが、その他にも重大な問題があります。
それは「健康リスク」です。
飲んでいないことを伝えない場合、医師は薬をちゃんと服用した現在の患者さんの状態があると判断します。
その場合、薬の増量や追加がなされ、副作用がでてしまう可能性があります。
「飲んでいない、飲み忘れてしまっている場合」は必ず伝えましょう。 -
質問:薬剤師がなぜ薬について聞いてくるのですか?回答:
薬について確認する理由は主に3つです。
1.副作用歴の確認:過去に副作用が出た薬と同じものや似たものを処方されていないかチェックします。
2.飲み合わせの確認:現在の薬と新しく処方された薬が重複していないか、他の薬の副作用と関係がないか確認します。
3.服用状況の確認:薬を継続して飲めるかを確認し、必要に応じて飲みやすい形状や別の薬に変更します。
これらの確認を通じて、薬を安全に正しく使うための対応が行われます。 -
質問:薬局で残った薬はもらえますか?回答:
薬局では、原則として処方箋が無いと医療用医薬品をお渡しすることはできません。
自己管理が難しい患者さんの場合は1度に渡す量を調整し、残りを薬局に保管することがあります。
その場合は服用状況に併せて来局いただき、都度薬をお渡しすることがあります。 -
質問:病院でもらった薬は薬局で一包化できますか?回答:
病院で一包化可能な施設もあるので薬を受け取る前に確認しておきましょう。
また、すでに受け取っている薬や処方箋を提出し、これから受け取る場合に関しては、薬局で一包化することが可能です。
しかし、薬局によっては一包化をする場合、追加料金が発生するところもあるので注意が必要です。
よく行く薬局や最寄りの薬局に事前に相談することをおすすめします。 -
質問:病院で余った薬はどうすればいいですか?回答:
継続して使用している薬であれば捨てずに持っておきましょう。
次回受診する時に医師に伝えるか、処方箋と一緒に残っている薬の数を薬剤師に伝えましょう。
数を調整することで無駄な医療費削減や患者さん負担削減に繋がります。 -
質問:薬の説明書は捨ててもいいですか?回答:
お薬手帳をお持ちでない方は、服用中は説明書を保管しておいていただくことをおすすめします。
薬の作用についてはもちろんですが、副作用などの注意事項の記載もあります。
飲み始めて体調が優れない場合に参考になります。
薬局でもらった薬の説明書(薬情)であれば、電話番号や緊急連絡先などの重要な情報も記載されているので、薬と一緒に保管しておきましょう。 -
質問:置き薬は使ってなくてもいいの?回答:
症状がある時や緊急時に使うための薬は、定期的に使用期限を確認してください。
保管状況によっては、使用期限前に薬の品質や形状が崩れることがあります。
薬は熱過ぎる場所や凍るほど寒い場所を避け、室温で適切に保管しましょう。 -
質問:薬は何年くらい持つ?回答:
製造されたタイミングでは約3年の有効期限が設定されます。
しかし、この有効期限は包装されている状態での期限です。
劣悪な環境だったり、シートに穴が空いていたりする場合はもっと期間が短くなることがあります。
薬を1錠だけ出したままにしたり、サウナの様な高温多湿な環境に放置することはしないようにしましょう。 -
質問:病院でもらった薬は何年もつ?回答:
医薬品の有効期限は、一般的に出荷時に約3年です。
頻繁に処方される薬は1~3年と長めですが、滅多に処方されない薬は数ヵ月から短いもので約1ヵ月です。
頓服以外の薬は、すぐに飲み始めて指定の期間内に使い切ることが前提です。
受け取る際には、薬の有効期限を確認しましょう。 -
質問:薬は冷蔵庫に保管してもいいですか?回答:
薬の保管温度は「室温」もしくは「冷所」であることがほとんどです。
室温は「1~30℃」、冷所は「1~15℃」と定義付けがされています。
冷蔵庫であれば範囲内となるので薬を保管しても問題ない温度になります。
しかし、「結露」と「凍結」には注意が必要です。
湿気に弱い薬も存在するので冷蔵庫ではなく、日陰の涼しい部屋で保管するようにしてください。 -
質問:薬局以外でオンライン服薬指導はできますか?回答:
「薬を受け取る場所=薬局」と考える方が多くいますが、現在はそうでもありません。
オンライン服薬指導のアプリやサイトが登場しています。
もちろん調剤薬局やドラッグストアもオンライン服薬指導に取り組んでいます。
ご自宅はもちろん、旅先でも指導を受けることが可能となっています。 -
質問:オンラインで服薬指導は受けられますか?回答:
2020年からオンラインで服薬指導が受けられるようになりました。
パソコンやスマートフォンを使用し、状態を把握したうえで服用方法や注意点の情報提供を受けられます。
全国どこの医療機関の処方箋でもオンライン指導を受けることが可能です。
ただし、薬局によってはオンライン指導の環境が整っていない箇所もあるので注意が必要です。
また、新な薬剤や対面で指導することが望ましい場合は、対面での指導を提案される可能性があります。 -
質問:処方箋なしで買える薬はなんて呼ばれますか?回答:
医師からの処方が無いとお渡しできないのが医療用医薬品の「処方箋医薬品」です。
「処方箋医薬品以外の医療用医薬品」は処方箋なしで購入できます。
しかし、多くの薬局は処方箋なしでは「処方箋医薬品以外の医療用医薬品」を販売していません。
販売している薬局を「零売薬局」と呼びます。 -
質問:オンライン服薬指導は電話のみでもいいですか?回答:
音声のみ(電話)は不可となっています。
2023年7月末までは音声のみ(電話)でも可能でしたが、同年8月より映像及び音声による対応へと切り変わっています。
テレビ・ビデオ通話による服薬指導を受ける必要があるため、スマートフォンやタブレット、PCを用いてカメラをオンにする必要があります。 -
質問:オンライン服薬指導で薬を受け取る方法は?回答:
受け取り方は「取りに行く」または「配送してもらう」の2通りがあります。
基本的には、自宅や指定の場所に郵送してもらうことが可能です。
また、実店舗を持つ薬局などでオンライン指導を受けた場合は、患者さんの都合の良いタイミングで直接窓口に受け取りに行くことも可能です。 -
質問:オンライン服薬指導を受けている人の割合は?回答:
オンライン服薬指導を受けている方の具体的な数字は不明です。
2023年1月23日~2月20日を期間とした薬局へのアンケート結果から「オンライン服薬指導システム導入あり」は81.0%でしたが、実施薬局は13.1%と多くない結果となっています。
今後のオンライン診療の進歩に併せてオンライン服薬指導も当たり前のものになっていくことが想像されます。