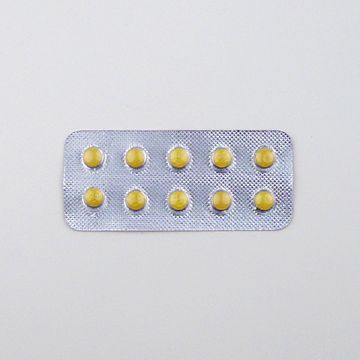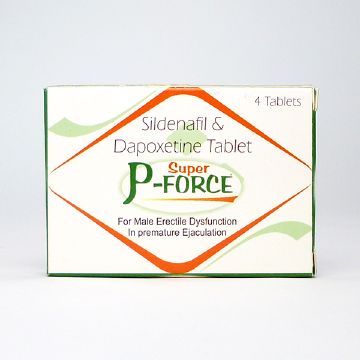MOシキ
-
英語表記Mo-siki
-
設立年月日2003年2月21日
-
代表者Pahilaj Govindram Mohan, Nanak G Mohan, Robin Mohan
-
国インド
-
所在地Gujarat州Vadodara市、Yoginagar Society 52 G F
Mo-siki製品の特長とその意義
Mo-sikiは、インドの急成長中の製薬会社Go-Ish Remediesの一部門として、精神医学領域の薬品を中心に幅広い製品を提供しています。
特に、統合失調症、双極性障害、不安障害、鬱病などの精神的な疾患に対応するための薬剤を製造しており、その製品ラインにはリスペリドン、クロザピン、フルボキサミン、セルトラリンといった有効成分を含むものが含まれています。
これらの薬剤は、錠剤、カプセル、シロップ、注射剤など、患者のニーズに応じたさまざまな形態で提供されており、自分の症状に合わせて治療が可能です。
Mo-sikiの製品は、厳格な品質管理基準のもとで製造されており、原材料には高品質な成分を使用しています。
これにより、医療従事者と患者の双方に信頼される医薬品を提供することを目指しています。
また、これらの製品はインド国内のみならず、国際市場にも対応しており、世界中の患者に優れた治療オプションを提供しています。
精神医学領域においては、特に抗精神病薬や抗不安薬に力を入れており、これらの薬剤は医療機関を通じて患者に供給されます。
例えば、統合失調症治療に使用されるリスペリドンは、患者の症状を管理するために広く使用されており、双極性障害に対するクロザピンも、特定の重度な症例において効果が認められています。
また、不安障害や鬱病に対しては、フルボキサミンやセルトラリンといった選択的セロトニン再取り込み阻害薬(SSRI)が用いられており、精神的な健康改善に貢献しています。
よくあるご質問(FAQ)
-
質問:なぜ薬がないのでしょうか?回答:
新型コロナウイルスの大流行以来、全国の薬局や医療機関では医薬品が不足している状態が続いています。
医薬品不足の原因には、新型コロナウイルスやインフルエンザの流行による需要の増加があり、さらに2020年以降にはジェネリック医薬品メーカーで製造不正が相次いで発覚しました。
これにより、10社以上のジェネリック医薬品メーカーが業務停止処分を受け、製造や出荷が縮小されたため、医薬品の供給不足が深刻化しています。 -
質問:なぜ薬が供給不足になるのでしょうか?回答:
医薬品の供給不足にはいくつかの原因があります。
例えば、製造工場で設備の故障や品質管理の問題が発生すると、製造や出荷が減少することがあります。
また、原材料が手に入らない場合も、製造ができなくなり供給が滞ります。
さらに、薬の需要が急に増えると、生産が間に合わず供給不足が起こります。
最近では、10社以上のジェネリック医薬品メーカーで製造不正が発覚し、業務停止処分が続いています。
そのため、全国的に医薬品の供給不足が深刻化しています。 -
質問:なぜ処方箋がないと薬はもらえないのか?回答:
処方薬を薬局で調剤してもらうためには、医師が診察した上で発行する処方箋が必要であると法律で定められています。
これは、薬を安全に使用してもらい、効果的な治療を行うためです。
医師は診察を通じて患者の症状を確認し、適切な薬を選びます。
その際、他の薬との併用や持病のリスクも考慮して薬を選ばなければなりません。
処方薬は効果がある一方、正しく使用しなければ健康に悪影響を及ぼす可能性もありますので、自己判断で使用することは危険です。
この様な理由から、処方箋薬には医学的な判断と薬学的な判断が求められるため、医師の診察に基づいて発行される処方箋が必要となります。 -
質問:残薬は社会問題になっていますか?回答:
厚生労働省の報告によると、残薬の総額は年間約500億円に達しており、医療財源を圧迫する大きな問題となっています。
もし薬が飲み忘れや飲み残しで余ってしまった場合は、次に処方箋をもらう時に薬局に持参しましょう。
薬の状態や量によっては、残った薬を再利用できることがあります。
この再利用を「残薬調整」と呼びます。
残薬調整を行うことで、自分の薬代を節約でき、医療費の削減にも繋がります。 -
質問:残薬は医師に伝えるべきですか?回答:
残薬が出た場合は、必ず医師に伝えてください。
医師は患者の状態に合わせて治療方針を決めていますが、薬の使用状況がわからないと、治療効果や副作用を正しく判断できません。
また、余った薬を再利用することで、薬代を節約できる場合もあります。
薬が余ったことを正直に医師に伝えることで、自分のためにも役立ちます。 -
質問:薬剤師がなぜ薬について聞いてくるのですか?回答:
現在服用している他の薬がある場合、薬剤師はその薬について詳しく聞きます。
これは、処方された薬と一緒に飲んでも問題がないかを確認するためです。
薬の組み合わせによっては、効果が弱まったり、副作用が出たりすることがあります。
もし薬の組み合わせが良くない場合、薬剤師は処方した医師に確認し、薬の内容を見直してもらいます。
薬を安全に使うために、薬剤師の質問には正直に答えてください。 -
質問:薬局で残った薬はもらえますか?回答:
飲み忘れなどで処方された薬が残った場合、薬局に持っていくと再利用できることがあります。
これを「残薬調整」と呼びます。
まず、薬剤師が薬の状態や数を確認し、再利用が可能か判断します。
その後、医師にその分の処方量を減らせるかを確認し、許可が出た場合、残薬分の処方量を減らすことができるので薬代の節約になります。
ただし、薬の状態によっては再利用できないこともあります。
余った薬の扱い方については医師や薬剤師に相談するようにしましょう。 -
質問:病院でもらった薬は薬局で一包化できますか?回答:
病院で複数の薬を処方された場合、薬局で一包化してもらうことができます。
一包化とは、服用のタイミングが同じ薬を、1回の服用分ずつ1袋にまとめることです。
飲み間違いや飲み忘れを防ぎ、薬の種類が多くて管理が難しい人にとって大変便利な方法です。
ただし、湿気に弱い薬や温度管理が必要な薬、症状に応じて調整する薬など、一包化できない薬もあります。 -
質問:病院で余った薬はどうすればいいですか?回答:
病院でもらった薬が余った場合は、その薬を処方した病院や薬局に持って行って相談してください。
同じ薬で治療を続ける場合、薬剤師が薬の状態や数を確認し、再利用できることがあります。
これを「残薬調整」と言い、残薬分の処方量を減らすことで薬代を節約できます。
余った薬を自己判断で服用するのは危険ですので、必ず医師または薬剤師に相談しましょう。 -
質問:薬の説明書は捨ててもいいですか?回答:
薬の説明書は、使い終わるまで捨てずに保管しておきましょう。
説明書には、薬の正しい使い方や服用のタイミング、飲み方、副作用、他の薬との相互作用など、重要な注意事項が書かれています。
薬を使用する前に、毎回説明書をしっかりと確認してから使用してください。
一度確認しても、次回使用時に忘れることも多いものです。
毎回確認できるよう、説明書は捨てずに手元に置いておいてください。 -
質問:置き薬は使ってなくてもいいの?回答:
置き薬(配置薬)は、使った分だけ料金を支払う仕組みになっています。
使う必要がなければ、薬箱にある薬を使わなくても問題ありません。
使っていない薬の期限が切れた場合は、無料で新しい薬に交換してもらえます。
ただし、自分で処分すると料金を請求されることがあります。
配置薬は、期限切れを心配せずに必要な時だけ薬を使える便利な薬の販売システムになっています。 -
質問:薬は何年くらい持つ?回答:
一般的な市販薬の使用期限は製造から3年で、外箱にその期限が記載されています。
ただし、これは未開封で適切に保管した場合に限ります。
特に液状の薬は、開封後に品質が変わりやすいので注意が必要です。
病院で処方された薬は、指示された通りに飲み切ることが前提で、医師の指示する服用日数が使用期限です。
その薬がいつ製造されたものかを確認したい場合は、調剤した薬局にご相談ください。
頓服薬などの保管期間についても、調剤してもらった薬局に確認するのが確実です。 -
質問:病院でもらった薬は何年もつ?回答:
通常、病院からもらう薬には使用期限が書かれていません。
これは、処方された薬は指示通りに飲み切るのが基本で、医師の指示する服用日数を使用期限と考えるためです。
ただし、症状が出た時にだけ使う頓服薬や長期処方の薬の場合は、保管することもあるかと思います。
一般的に薬は未開封で適切に保管すれば、製造から3~5年は品質が保たれますが、薬が調剤された時点でどれくらいたっているかは薬局で確認する必要があります。
どれくらい保管して使えるかは、調剤した薬局に相談してください。 -
質問:薬は冷蔵庫に保管してもいいですか?回答:
薬を冷蔵庫に入れておけば、食品のように長持ちすると勘違いする方は多いです。
しかし、それは誤りです。
薬の種類によって適切な保管方法は異なりますが、多くの薬は室温で保管することが基本とされています。
室温保存が適している薬を冷蔵庫に入れると、取り出した時に室温との急な温度差で湿気を帯びて劣化する可能性があります。
一方、シロップや坐薬、未開封のインスリンなど、冷蔵庫で保管するよう指示される薬もあります。
その際は、薬を凍らせないよう注意しましょう。
薬の保管方法については、必ず説明書や薬剤師の指示に従いましょう。 -
質問:処方箋なしで買える薬はなんて呼ばれますか?回答:
薬局やドラッグストアで処方箋がなくても購入できる薬は「一般用医薬品」あるいは「市販薬」、「OTC薬(Over-the-Counter薬)」と呼ばれています。
「一般用医薬品」は自分で症状に合わせて薬を選んだり、薬剤師に相談して購入することができます。
対して「医療用医薬品」は、基本的には医師の診察を経て発行された処方箋がないと購入できません。
ただし「医療用医薬品」の中でも、一部は処方箋なしで薬局が販売できる医薬品があり、それらは「処方箋医薬品以外の医療用医薬品」と呼ばれています。
この様な「処方箋医薬品以外の医療用医薬品」を販売することを「零売(れいばい)」と言います。 -
質問:オンライン服薬指導は電話のみでもいいですか?回答:
2023年7月末までは、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う特例措置(通称0410対応)として電話のみでの服薬指導が可能でした。
その後法改正があり、2023年8月以降はオンライン服薬指導を行う際には映像と音声による対応(ビデオ通話)が必須となっています。 -
質問:オンライン服薬指導で薬を受け取る方法は?回答:
まず、医療機関にて対面またはオンラインで診察を受けます。
受診時にオンラインで服薬指導を受けたい旨を医師に伝え、希望の薬局へ処方箋をFAX送信してもいます。
処方箋を受け取った薬局は調剤を行い、調剤完了後、患者さんへ調剤完了の旨とオンライン服薬指導の日時の連絡を送ります。
連絡方法は薬局によって様々で、電話あるいは専用のソフトやアプリを使う場合もあります。
そしてオンライン服薬指導が終わると、薬局から患者さんの自宅や入所している施設に薬剤が配送されます。
ただし、医薬品の内容によっては配送できないものもあり、その場合は薬局まで受け取りに行く必要があります。 -
質問:オンライン服薬指導を受けている人の割合は?回答:
2023年1月~2月に実施された日本保険薬局協会の調査によると、期間中に受け付けた処方箋に対するオンライン服薬指導の実施率はわずか0.045%であったと報告されています。
一方でオンライン服薬指導システムの導入状況は、「導入あり」と回答した薬局が81.0%という高い比率でした。
この結果から、オンライン服薬指導のシステムは導入している薬局は多いものの、実際に利用されている患者さんはとても少ないことがわかります。