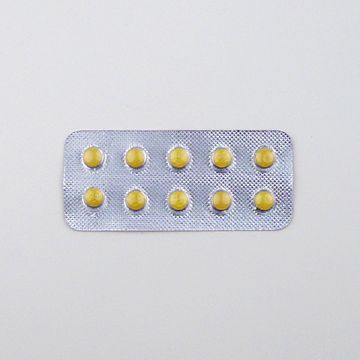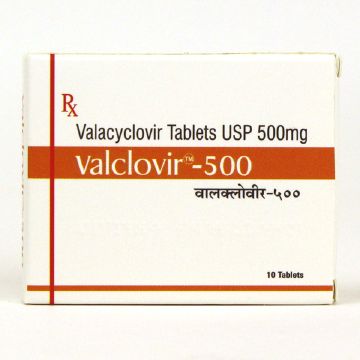ルンドベック

-
英語表記Lundbeck
-
設立年月日1915年8月14日
-
代表者デボラ・ダンサイア
-
国デンマーク
-
所在地Ottiliavej 9, Valby, 2500 コペンハーゲン, デンマーク
精神神経疾患のグローバルリーダー、ルンドベックの歴史と専門性
ルンドベックは、1915年にデンマークで設立された製薬企業で、精神神経疾患に特化したグローバルな企業として知られています。
創業者のハンス・ルンドベックは当初、商事会社としてさまざまな製品を取り扱っていましたが、1920年代半ばから医薬品の取り扱いを開始し、1930年代には自社で医薬品の製造を本格的に進めました。
この時期、特に創傷治療薬「Epicutan」の開発が進み、1939年にはコペンハーゲン市内に本社を移転し、研究所も設立しています。
ルンドベックが精神神経疾患領域に専門特化し始めたのは、1959年に発売された抗精神病薬「Truxal」の成功が大きな契機でした。
この製品は1960年代から1970年代にかけて同社の代表的な製品となり、精神神経領域における地位を確立しました。
1980年代後半には、中枢神経系の疾患に特化する戦略が採用され、これにより、うつ病や統合失調症、アルツハイマー病、パーキンソン病といった領域での研究開発が加速しました。
ルンドベックの強みは、70年以上にわたる精神神経科学の研究蓄積にあります。
脳のメカニズムに関する深い理解を基に、同社は革新的な医薬品の開発に注力してきました。
これにより、うつ病や統合失調症など、患者の生活の質に重大な影響を及ぼす疾患に対する新しい治療法を生み出しています。
未解決の医療ニーズが多いこれらの疾患領域で、同社の製品は患者の症状を軽減し、社会的な負担を軽減する役割を果たしています。
現在、ルンドベックは50カ国以上に拠点を持ち、100カ国以上で製品が販売されています。
毎年、数百万人の精神神経疾患を抱える患者の治療に貢献しており、患者やその家族を支援するための啓発活動にも力を入れています。
特に、精神疾患に対する社会的な偏見をなくし、患者が適切な治療を受けやすい環境づくりを目指しており、これにより精神神経疾患の理解が進んでいます。
ルンドベックの最新の製品としては、抗うつ薬「ブリンテリックス」や統合失調症治療薬「アビリファイ メンテナンス」、またアルツハイマー病の症状を軽減する薬などがあります。
これらの製品は、ルンドベックの精神神経疾患における専門性と、革新的なアプローチの結晶といえます。
革新的な治療薬の開発をするルンドベックの主力製品と研究分野
ルンドベックは、精神神経疾患治療薬の開発において世界的に知られており、うつ病、統合失調症、パーキンソン病、アルツハイマー病など、精神神経疾患領域に特化した研究開発を行っています。
特に未解決の医療ニーズが多いこれらの分野で、同社は画期的な治療薬を開発し、患者の生活の質向上に貢献しています。
ルンドベックの研究開発として特筆すべきは、うつ病治療薬「シタロプラム」の開発です。
1990年代に登場したこの選択的セロトニン再取り込み阻害薬は、うつ病治療の標準薬となり、ルンドベックのグローバル展開を後押ししました。
後継薬として開発された「エスシタロプラム」は、さらに高い効果と副作用の軽減を実現し、世界中で広く使用されています。
加えて、近年開発された「ボルチオキセチン」は、うつ病治療に新しい選択肢を提供し、特に認知機能改善効果が注目されています。
統合失調症分野では、新規抗精神病薬「ブレクスピプラゾール」がルンドベックの主要な治療薬です。
この薬は、ドパミンD2受容体およびセロトニン5-HT1A受容体の部分アゴニスト作用を持ち、症状の緩和と副作用の軽減を両立させた新しい治療アプローチです。
従来の薬剤に比べて、治療の柔軟性が高く、患者に対する負担を減らすことが期待されています。
また、パーキンソン病治療薬「ラサギリン」は、ルンドベックが提供する革新的な製品の一例です。
MAO-B阻害薬であり、疾患の進行を遅らせる可能性が示唆されているため、パーキンソン病患者のQOL向上に寄与しています。
これにより、ルンドベックはパーキンソン病治療の分野でもリーダーシップを発揮しています。
アルツハイマー病に関しては、ルンドベックはタウタンパク質や炎症プロセスをターゲットとする新規治療薬の研究開発を進めています。
この難治性疾患に対する新しい治療法の提供を目指して、ルンドベックは、認知機能改善など、従来の治療では対応しきれなかった症状へのアプローチにも注力しています。
ルンドベックはまた、個別化医療の実現に向けた取り組みも強化しています。
遺伝子解析や脳画像技術を活用し、患者の特性に合わせた最適な治療法の提供を目指す研究が進められています。
これにより、治療の効果を最大化し、副作用を最小限に抑えることが可能になります。
ルンドベックのグローバル展開と日本市場
ルンドベックは、デンマークに本社を置き、精神神経疾患の治療に特化したグローバル製薬企業として成長を遂げています。
1915年にハンス・ルンドベックによって設立され、現在では世界50カ国以上に拠点を持ち、100カ国以上で製品が使用されています。
特に、うつ病、統合失調症、パーキンソン病、アルツハイマー病などの精神神経疾患に焦点を当て、長年にわたる研究と開発を通じて、多くの革新的な治療薬を市場に投入しています。
ルンドベックのグローバル展開は、1950年代から本格化しました。
ニューヨークやパリに拠点を開設し、徐々に国際的なプレゼンスを高めていきました。
1990年代のうつ病治療薬「シタロプラム」の成功により、ルンドベックの国際的な知名度と市場シェアが大きく向上しました。
1998年時点で、ルンドベックは30の子会社を持ち、ヨーロッパ、オーストラリア、ニュージーランド、南アフリカ、カナダに事業を展開していました。
同年、アメリカ市場にも初めて進出し、Forest Laboratoriesとの戦略的提携を通じてシタロプラムを発売しました。
これらの取り組みにより、ルンドベックは主要市場でのプレゼンスを強化し、グローバル企業としての地位を確立していきました。
特に日本市場においては、2001年に「ルンドベック・ジャパン株式会社」を設立し、精神神経疾患治療薬の分野で大きな役割を果たしています。
ルンドベックは日本で、「エスシタロプラム」や「ボルチオキセチン」、統合失調症治療薬「ブレクスピプラゾール」などの革新的な治療薬を展開しています。
特にトリンテリックスは、新しい作用機序を持ち、日本の医療現場で注目されています。
また、ルンドベックは精神神経疾患に関する啓発活動にも力を入れており、患者や医療従事者と連携して正しい知識の普及に努めています。
今後の成長戦略としては、既存市場でのシェア拡大に加え、新興市場でのプレゼンス強化が挙げられます。
特に、中国やインドといったアジア太平洋地域での事業拡大に注力しており、これらの市場での製品展開を加速させています。
また、デジタルヘルスやプレシジョンメディシンといった新技術を活用し、革新的な治療法の開発にも取り組んでいます。
これにより、ルンドベックは精神神経疾患領域におけるグローバルリーダーとしての地位をさらに強化し、世界中の患者に革新的な治療を提供し続けることを目指しています。
ルンドベックの企業理念と持続可能性
ルンドベックは、「脳の健康を回復する」という明確な使命を掲げ、精神神経疾患に苦しむ人々の生活の質を向上させることを目指しています。
この理念は、単に医薬品を提供することにとどまらず、患者さんのウェルビーイングに貢献し、社会全体の偏見解消に向けた取り組みを推進しています。
ルンドベックが特に力を入れているのが、精神神経疾患に対する啓発活動と偏見解消の取り組みです。
世界中で推定7億人以上が精神神経疾患を抱えていますが、その多くが適切な治療を受けられていない状況にあります。
こうした現状を踏まえ、ルンドベックは患者に対する理解促進を目指し、精神神経疾患に関する正しい知識の普及に取り組んでいます。
具体的な活動としては、ルンドベックは毎年10月10日の世界メンタルヘルスデーに合わせ、世界中で啓発イベントやキャンペーンを展開しています。
また、患者団体や医療従事者との協働を通じて、教育プログラムや情報提供にも積極的に関わり、精神疾患に対する偏見を取り除く努力を続けています。
さらに、ルンドベックは持続可能性を重要視しており、事業運営をSDGsに沿った形で推進しています。
環境保護の面では、ルンドベックは2030年までにカーボンニュートラルを達成する目標を掲げています。
このため、製造プロセスの効率化や再生可能エネルギーの利用拡大、廃棄物削減などを通じて、環境負荷の低減に努めています。
ルンドベックはまた、医薬品の環境影響評価にも取り組んでおり、製品のライフサイクル全体を通じた環境負荷の最小化を目指しています。
これにより、企業活動が環境に与える影響を最小限に抑える努力を続けています。
このような持続可能性と啓発活動を通じて、ルンドベックは精神神経疾患に対する偏見をなくし、患者が適切な治療を受けやすい社会を実現するために、医療の発展と社会貢献に努めています。
引用 : https://ja.wikipedia.org/wiki/ルンドベック
引用 : https://www.lundbeck.com/jp/jp/about-us/About-Lundbeck-Japan
よくあるご質問(FAQ)
-
質問:ルンドベックの従業員数は?回答:
ルンドベックは世界中で約5500人の従業員を擁するグローバル製薬企業です。
デンマークに本社を置き、特に精神・神経疾患領域に特化して研究、開発、製造、販売に取り組んでいます。
1915年に設立され、抗精神病薬や抗うつ薬による治療の先駆者となってきた製薬企業です。 -
質問:ルンドベックはどこに上場していますか?回答:
ルンドベックは、1999年にデンマークのナスダック・コペンハーゲン(コペンハーゲン証券取引所)に上場しています。
筆頭株主はルンドベック財団で、全株式の約70%を保有しています。
世界50カ国以上に拠点を持ち、2023年の総売上は約199億デンマーククローネです。 -
質問:ルンドベックジャパンの社長は誰ですか?回答:
2024年1月1日付で、Rune Ejler Andersen(ルネ・アイラ・アンデルセン)氏がルンドベック・ジャパン株式会社の代表取締役社長に就任しました。
ルネ・アイラ・アンデルセン氏はデンマーク出身で、ルンドベックにおいてインドのカントリーマネージャー、中国のビジネスディベロップメントディレクター、本社でのビジネスオペレーションズ部門長といった役職を歴任してきた人物です。 -
質問:ルンドベックの福利厚生は?回答:
ルンドベックは会社の公式ホームページなどで福利厚生に関する情報を公開していません。
正確な福利厚生情報については、ルンドベックの採用担当者に求人情報を問い合わせるのが良いでしょう。
福利厚生の充実度合いを評価するには、休暇制度や健康保険の充実度、フレックスタイムやリモートワークの支援制度を確認してみましょう。 -
質問:なぜ薬がないのでしょうか?回答:
新型コロナウイルスの大流行以降、全国の薬局や医療機関でかつてない医薬品の供給不足が続いています。
薬が足りなくなっている要因は、新型コロナウイルスやインフルエンザの流行で需要が増えたことだけではありません。
2021年以降、ジェネリック医薬品メーカーで製造上の不正が発覚し、業務停止などの行政処分が相次いだことも大きな原因となっています。 -
質問:なぜ薬が供給不足になるのでしょうか?回答:
医薬品の供給不足は、いくつかの理由で起こります。
たとえば、製造工場での機械の故障や品質の問題が原因で薬の生産が止まることがあります。
また、原材料が手に入らなくなることも供給不足の原因です。
さらに、薬の需要が急に増えると、生産が追いつかずに供給不足になることもあります。 -
質問:なぜ処方箋がないと薬はもらえないのか?回答:
処方箋がないと薬がもらえない理由は、患者さんの安全と治療効果を守るためです。
医師は診察により患者さんの病状を確認し、適切な薬を選びます。
また、薬の組み合わせや持病のリスクについても考慮して薬を選ばなければなりません。
そのため、医師が処方箋を出し、薬剤師が薬局にて薬を調剤する必要があります。
処方箋をもらわずに処方薬を自己診断で使用すると健康を害する可能性があります。
処方箋薬は医師の処方のもと、正しく使用しましょう。 -
質問:残薬は社会問題になっていますか?回答:
残薬は薬の使い方や医療費において問題を引き起こしています。
医師は必要な量だけ薬を処方していますが、薬が残ってしまうと、正しく服用されていないことを意味します。
薬を正しく使わないと、治療効果が得られず、症状が悪化する可能性があります。
また、家に残薬が多くあると、誤用や誤飲の危険が高まります。
厚生労働省の報告では、年間で残薬による無駄な医療費が約500億円にも達しています。
処方された薬は最後まで使い切り、もし残ってしまった場合は医師や薬剤師にその旨を伝えるようにしましょう。 -
質問:残薬は医師に伝えるべきですか?回答:
処方された薬を使い切れずに残薬が出た場合は、必ず医師に伝えましょう。
医師に知らせることで、薬の種類や量をより適切に調整することができます。
また、副作用が原因で薬が残る場合は、医師に相談することで他の薬に変更するか、副作用を和らげる方法を教えてもらえます。
治療の効果を最大化し、安全に使用するためには、残薬のことを隠さずに医師に伝えることが大切です。 -
質問:薬剤師がなぜ薬について聞いてくるのですか?回答:
薬剤師が薬について質問するのは、処方された薬を安全に使ってもらうためです。
たとえば、他の薬を一緒に使っている場合、薬同士が影響し合って効果が減ったり、副作用が出たりすることがあります。
もし薬の組み合わせに問題があるかもしれない場合、薬剤師は医師に相談して効果や安全性を確認します。
薬の効果を最大限に引き出し、副作用を少なくするためにも、薬についての質問にはしっかり答えることが大切です。 -
質問:薬局で残った薬はもらえますか?回答:
飲み忘れて余った薬は、薬局に持って行けば再利用できる場合があります。
薬剤師が薬の状態や数量を確認し、再利用可能と判断した場合には、医師にその分の処方量を減らしても良いかを確認します。
医師が許可すれば、薬代を抑えることができます。
ただし、薬の状態によっては再利用できないこともあります。
自己判断で残薬を再利用するのは危険ですので、必ず医師や薬剤師に相談してください。 -
質問:病院でもらった薬は薬局で一包化できますか?回答:
複数の種類の薬を処方されていて、自分や家族での服薬管理が難しい場合は、近くの保険薬局に相談してみましょう。
薬局では、薬を一包化してもらえるサービスがあります。
一包化とは、1回分の服用にまとめてパッケージングすることです。
ただし、湿気に弱い薬や、特別な管理が必要な薬、調整が必要な薬などは一包化できないことがあります。
どの薬が一包化できるかは、薬剤師が判断しますので、まずは薬局で相談してみると良いでしょう。 -
質問:病院で余った薬はどうすればいいですか?回答:
病院で処方された薬が余ってしまった場合は、自己判断で処分せずに、病院や薬局に持って行きましょう。
薬剤師や医師が薬の状態や数量を確認し、再利用できるかどうかを判断します。
また、薬が余った理由を医師や薬剤師が把握することで、飲み忘れを防ぐための適切な管理方法についてアドバイスを受けることができます。
余った薬を自分で処分するのは危険ですし、家族が誤って服用するリスクもあるため、必ず医師や薬剤師に渡すようにしましょう。 -
質問:薬の説明書は捨ててもいいですか?回答:
薬の説明書は、使い切るまで大切に保管しておきましょう。
説明書には、薬の正しい使い方や服用タイミング、副作用、他の薬との相互作用など、重要な情報が書かれています。
これらの指示に従わないと、薬の効果が薄れたり、副作用が強くなることがあります。
説明書はいつでも確認できるようにし、捨てないようにしてください。 -
質問:置き薬は使ってなくてもいいの?回答:
置き薬(配置薬)は、実際に使用した分だけ料金を支払うシステムです。
もし薬箱の中にある薬を使わない場合でも問題ありません。
しかし、使用していない薬の使用期限が切れた場合は、無料で新しい薬と交換してもらえます。
勝手に処分すると、料金が請求されることがありますので、使用しない薬が期限切れになったら、必ず販売員に交換を依頼してください。 -
質問:薬は何年くらい持つ?回答:
市販薬の使用期限は一般的に製造から3年で、外箱に記載されています。
ただし、これは未開封で適切に保管された場合の期限です。
液体の薬(シロップや点眼薬など)は、開封後に品質が変わりやすいので注意が必要です。
病院で処方された薬は、医師の指示に従い、処方された分を使い切ることが重要です。
飲み忘れなどで薬が残った場合、その薬の正確な使用期限はわかりません。
症状が強く出た時だけ使用する頓服薬などは、どれくらい保管しても大丈夫かを確認するために、調剤した薬局に問い合わせると安心です。 -
質問:病院でもらった薬は何年もつ?回答:
薬を冷蔵庫に保管しても良いかどうかは、薬の種類によって異なります。
市販薬の場合は、外箱に保管方法が記載されています。
病院で処方された医療用医薬品の場合は、調剤してくれた薬剤師から保管方法についての説明があります。
もし冷蔵保存が適していない薬を冷蔵庫に入れて保管してしまうと、湿度や温度の変化で効果が減少することがあります。
薬の保管方法については、必ず説明書や薬剤師の指示に従うようにしましょう。 -
質問:薬は冷蔵庫に保管してもいいですか?回答:
薬の保管方法は、薬の種類によって異なります。
市販薬には、外箱に適切な保管方法が記載されています。
病院で処方された薬の場合は、薬剤師から具体的な保管方法について説明があります。
冷蔵庫に保管する必要がある薬もあれば、逆に冷蔵庫で保管してはいけない薬もあります。
冷蔵庫で保存してしまうと、湿度や温度の変化で薬の効果が減少することがあります。
薬を正しく保管するために、説明書や薬剤師の指示を必ず確認して従ってください。 -
質問:薬局以外でオンライン服薬指導はできますか?回答:
2022年9月30日に規則が改正され、オンライン服薬指導が薬局以外の場所でも行えるようになりました。
ただし、オンライン服薬指導を行う場所は、以下の条件を満たす必要があります。
1. 調剤を行う薬剤師と連絡が取れること。
2. 対面での服薬指導と同じ程度に患者さんのプライバシーが守られていること。
3. 音声だけでなく、映像と音声の両方で対応することが求められる。
このように、患者さんのプライバシーを守りつつ、適切な指導を行うための条件が設定されています。 -
質問:オンラインで服薬指導は受けられますか?回答:
スマートフォンやパソコンのビデオ通話を使って、薬剤師からオンラインで処方薬の服薬指導を受けることができます。
さらに、オンライン服薬指導を受けた後は、自宅まで薬を配送してもらえるサービスも利用可能です。
これにより、薬局に行く必要がなくなり、薬が準備されるまでの待ち時間もありません。
自宅でプライバシーを守りながら、体調や症状について安心して相談できるのが大きなメリットです。