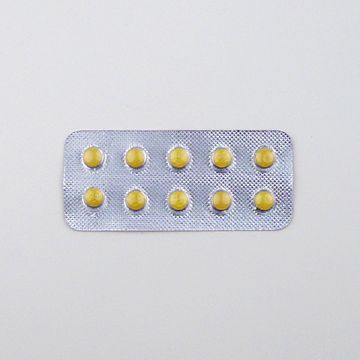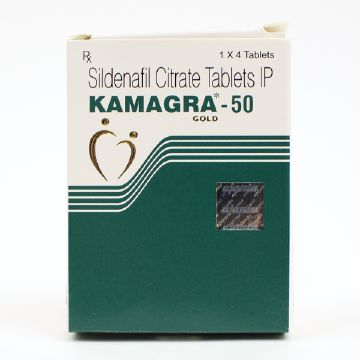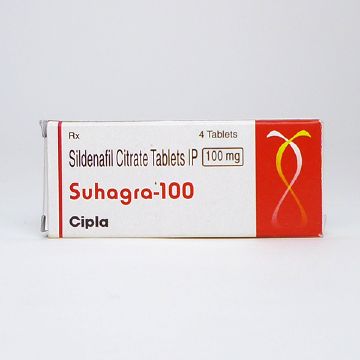インテンディス

-
英語表記Intendis
-
設立年月日2005年
-
国ドイツ
皮膚科領域に特化した製薬会社インテンディス
インテンディスは、2005年に設立されたドイツの製薬会社で、皮膚科領域に特化した医薬品の開発・製造・販売を行っています。
同社は、シェーリング社(現在のバイエル社)の外用剤事業部門が分社化されて誕生しました。
インテンディスの特徴は、皮膚疾患および痔疾患に関する医薬品に焦点を当てていることです。
この専門性により、皮膚科領域における高品質な医薬品の開発と提供を目指しています。
日本においても、インテンディスは2005年1月4日に日本法人「インテンディス株式会社」を設立しました。
日本法人の本社は大阪市淀川区に置かれ、初代代表取締役社長には日本シェーリングの前取締役診断薬事業部長の渡辺修次氏が就任しました。
インテンディスという社名には、企業としての「目的意識性」という意味が込められています。
これは、世界的な皮膚疾患領域市場を支える原動力になりたいという同社の強い意志を表しています。
インテンディスの事業展開は、医薬品の開発から生産、マーケティングまでを一貫して行う体制を持っていることが特徴です。
この垂直統合型のビジネスモデルにより、製品の品質管理や市場ニーズへの迅速な対応が可能となっています。
しかし、2009年にはインテンディスの親会社であるバイエル社が組織再編を行い、インテンディスはバイエル・ヘルスケア社の一部門となりました。
その後、2014年にはバイエル薬品株式会社がインテンディス株式会社と合併し、現在ではバイエルグループの一部として事業を展開しています。
インテンディスの設立と発展は、製薬業界における専門化と効率化の流れを反映しています。
皮膚科領域に特化することで、研究開発の集中と効率化を図り、より高品質な医薬品の提供を目指す同社の戦略は、製薬業界における一つのトレンドを示しているといえるでしょう。
インテンディスの研究開発から患者ケアまでの包括的アプローチ
インテンディスは、2005年の設立以来、皮膚科領域における革新的な医薬品の開発と提供に注力してきました。
同社の特徴は、単に医薬品を開発・販売するだけでなく、皮膚疾患に悩む患者さんのQOL向上を目指す包括的なアプローチにあります。
インテンディスの研究開発部門では、最新の皮膚科学の知見を活用し、より効果的で副作用の少ない外用剤の開発に取り組んでいます。
同社の研究者たちは、皮膚の構造や機能に関する深い理解を基に、新しい有効成分の探索や既存薬剤の改良を行っています。
また、インテンディスは医療現場との密接な連携を重視しています。
皮膚科医や薬剤師からのフィードバックを積極的に収集し、製品開発や改良に活かすことで、実際の臨床ニーズに即した医薬品の提供を目指しています。
インテンディスの製品ラインナップには、アトピー性皮膚炎、乾癬、にきびなどの一般的な皮膚疾患から、より希少な皮膚疾患に対する治療薬まで、幅広い製品が含まれています。
これらの製品は、世界中の多くの国で承認され、使用されています。
さらに、インテンディスは患者教育にも力を入れています。
皮膚疾患の正しい理解と適切なケア方法の普及を通じて、患者さんの自己管理能力の向上を支援しています。
これには、オンラインリソースの提供や、医療従事者向けの教育プログラムの実施なども含まれます。
2009年以降、インテンディスはバイエルグループの一部となりましたが、その専門性と患者中心のアプローチは維持されています。
バイエルの広範なリソースとグローバルネットワークを活用することで、インテンディスの研究開発能力はさらに強化されました。
日本市場においても、インテンディスの製品は重要な位置を占めています。
日本の皮膚科医療の高い水準に対応するため、日本の患者さんのニーズに合わせた製品開発や情報提供を行っています。
引用 : https://rocketreach.co/intendis-profile_b5c6b760f42e0ced
インテンディスの商品
スキノレンクリーム20%とは スキノレンクリーム20%は、アゼライン酸を20%含有するニキビ治療用の外用クリームです。 主にニキビ、赤ら顔、ほてりなどの症状改善に使用されます。 アゼライン酸は、穀類や酵母など天然由来の成分で、飽和ジカルボン酸の一種です。 この製品は、ニキビの原因となるアクネ菌を殺菌し、過剰な皮...
- 有効成分
- アゼライク酸・アゼライン酸
よくあるご質問(FAQ)
-
質問:バイエル薬品はどんな会社?回答:
バイエル薬品株式会社は大阪府にある製薬メーカーです。
医療用医薬品事業を中心に、医療機器、ヘルスケア、動物用薬品などの事業を展開しています。
医療用医薬品部門では、循環器領域、腫瘍・血液領域、ウィメンズヘルスケア領域、眼科領域、画像診断領域に注力しています。
アスピリンやクラリチン、ED治療薬のレビトラ錠などで有名な企業です。 -
質問:ドイツの製薬会社バイエルとは?回答:
バイエルはドイツに本社を置く製薬会社です。
2022年時点、世界83カ国で事業を展開する多国籍企業です。
医薬品、農業用化学製品、消費者向けヘルスケア製品を提供し、アスピリンやED治療薬などで有名です。
農業用化学製品部門では環境保護にも注力し、農業の持続可能な発展に貢献する製品開発に高い評価を得ています。 -
質問:バイエル製薬は合併するのですか?回答:
2024年5月時点で、バイエル製薬は特定の合併計画を公表していません。
ただし、製薬業界の大手企業は、買収や提携を通じて事業拡大や技術強化を行うことを企業戦略の一環としています。
例えば、バイエルは2007年にシエーリング社と統合、2010年に子会社のインテンディスを合併しています。
近年では2018年に米国の農業バイオテクノロジー企業モンサントを買収して農業部門を強化しました。 -
質問:バイエル薬品の英語名は?回答:
バイエル薬品の英語名は「Bayer Yakuhin, Ltd.」です。
大阪に本社を置き、医療用医薬品事業を中心に、医療機器、ヘルスケア、動物用薬品などの事業を展開しています。
親会社はバイエル ホールディング株式会社で、2022年時点、世界83カ国で事業を展開するドイツの企業です。 -
質問:バイエルの正式名称は?回答:
バイエル薬品の英語名は「Bayer Yakuhin, Ltd.」です。
大阪に本社を置き、医療用医薬品事業を中心に、医療機器、ヘルスケア、動物用薬品などの事業を展開しています。
ドイツ・バイエル社の日本法人として、バイエル ホールディング株式会社、バイエル薬品、バイエル クロップサイエンスの各社で構成されています。 -
質問:なぜ薬がないのでしょうか?回答:
薬局に処方箋を持参しても、在庫がないため調剤できないと言われることがあります。
これには様々な理由があります。
薬局内に全ての種類の薬を常時確保しておくことは不可能なので、調剤する機会の少ない薬の場合、薬局内に在庫していないことがあります。
また、製造メーカーで欠品が生じている場合もあります。
2021年ごろから起きている、咳止め薬や解熱鎮痛剤などの医薬品の全国的な供給不足は社会問題となっています。 -
質問:なぜ薬が供給不足になるのでしょうか?回答:
医薬品が供給不足となる要因は様々です。
例えば、製造過程に問題が生じて医薬品の生産がストップした場合や、原材料の入手が困難になることも供給不足を引き起こします。
また、その医薬品の需要が急増した場合も、製造が追いつかず品薄状態になってしまいます。
2021年以降に、全国的な医薬品の供給不足を引き起こしている大きな要因は、ジェネリック医薬品の製造メーカーで製造上の不正が発覚し、業務停止などの行政処分が相次いだことが引き金となっています。 -
質問:なぜ処方箋がないと薬はもらえないのか?回答:
処方箋がないと薬がもらえない理由は、患者の治療効果と安全を守るためです。
医師は診察で患者の病状を確認し、治療に必要な薬を選択します。
また、薬を安全に使用するためには、薬の飲み合わせや持病についても考慮する必要があります。
医師の診察を受けずに自己判断で処方薬を使用すると、健康に悪影響を及ぼす可能性があります。
この様な理由から、処方薬は医師の処方箋がなければ調剤できない薬となっています。 -
質問:残薬は社会問題になっていますか?回答:
厚生労働省の報告によれば、残薬の総額は年間約500億円にも上ると言われています。
それだけの医療費を無駄にしているということから、残薬は大きな社会問題の一つとなっています。
医師は治療に必要な量の薬を処方しているため、決められた用法用量で処方された薬を飲みきるのが一番です。
しかし、飲み忘れてしまうこともあるかと思います。
もし処方された薬が残ってしまった場合、次の診察時に薬局に持参してください。
薬の状態や数によっては、残ったお薬を再利用して薬代を安くできるケースもあります。 -
質問:残薬は医師に伝えるべきですか?回答:
処方された薬を全て使用しきれず、残薬が出た場合は必ず医師に伝えてください。
医師は治療に必要な量の薬を処方しています。
現在の症状が薬を正しく使用した結果なのか、飲み忘れがある結果なのかを正しく把握することで、次の治療方針を決めることができます。
「副作用がつらくて薬を使用したくない」、「種類が多くて飲み忘れてしまう」など、残薬が出てしまう理由に心当たりがあれば、その点もぜひ相談してください。
医師や薬剤師は副作用を軽減する方法や、飲み忘れを防ぐ方法の提案もしてくれます。 -
質問:薬剤師がなぜ薬について聞いてくるのですか?回答:
薬剤師が薬について質問するのは、安全に薬を使っていただくためです。
他の薬を一緒に使っている場合、薬同士が影響し合って、効果が弱まったり副作用が出たりすることがあります。
もし薬の組み合わせが良くない可能性がある場合、薬剤師は処方した医師に確認し、効果と安全性を再確認します。
薬の効果を最大限にし、副作用を減らすために、薬剤師から質問されたらしっかり答えましょう。 -
質問:薬局で残った薬はもらえますか?回答:
飲み忘れて余ってしまった薬は、薬局に持っていくと再利用できることがあります。
薬剤師が薬の状態や数を確認し、再利用が可能と判断した場合、医師にその分の処方量を減らせるか確認してくれます。
医師の許可が出れば、その分の薬代を節約できます。
これを「残薬調整」と呼びます。
ただし、薬の状態によっては再利用できないこともあります。
自己判断で余った薬を使うのは危険ですので、必ず医師または薬剤師に相談してください。 -
質問:病院でもらった薬は薬局で一包化できますか?回答:
病院で複数の種類の薬を処方されると、どれをいつ飲めば良いのか管理が難しいこともあります。
その様な場合、近くの保険薬局で薬を一包化してもらうことができます。
ただし、薬の性質や種類によっては一包化できないこともあります。
例えば、湿気に弱い薬や温度管理が必要な薬、症状に応じて調整する薬などは一包化に適していません。
病院でもらった薬が一包化可能かどうかは、まずは保険薬局に相談してみましょう。 -
質問:病院で余った薬はどうすればいいですか?回答:
病院でもらった薬が余った場合は、その薬を処方してくれた病院や薬局に持っていきましょう。
同じ薬で治療を続ける場合、薬の状態や数を確認して再利用できることがあります。
余った薬をとっておいて、自己判断で飲むのは危険です。
家族が誤って飲んでしまうリスクもあるので、余った薬は自宅でとっておかずに医師または薬剤師に渡すようにしましょう。 -
質問:薬の説明書は捨ててもいいですか?回答:
薬の説明書は、使い終わるまで大切に保管してください。
説明書には、薬の正しい使い方や服用のタイミング、飲み方、副作用、他の薬との相互作用など重要な情報が書かれています。
これに従わないと薬の効果が減ったり、副作用が強くなったりすることがあります。
いつでも確認できるように、説明書は捨てずに手元に置いておいてください。 -
質問:置き薬は使ってなくてもいいの?回答:
置き薬(配置薬)は、使った分だけ料金を支払う仕組みです。
薬箱にある薬を使わなくても問題ありません。
もし使用していない薬の期限(配置期限)が切れた場合は、無料で新しい薬に交換してもらえます。
ただし、自分で勝手に処分すると、薬の料金を請求されることがあります。
置き薬は必要な時だけ使い、期限切れの薬は販売員に交換してもらいましょう。 -
質問:薬は何年くらい持つ?回答:
一般的な市販薬の使用期限は製造から3年で、外箱などに記載されています。
ただし、これは「未開封」かつ「適切な条件下で保管」した場合の期限です。
特にシロップや点眼薬などは、開封後に品質が変わりやすいので注意が必要です。
病院で処方された薬については、指示された用法用量で残さず飲み切ることを前提としていますので、医師から処方された服用日数が「使用期限」であると考えてください。
飲み忘れなどで薬が余った場合、その薬がいつ製造されたものなのかは調剤した薬局に確認しないとわかりません。
症状が強い時にだけ使う頓服薬などは、どれくらい保管して問題ないかを調剤してくれた薬局に確認するのが確実です。 -
質問:病院でもらった薬は何年もつ?回答:
一般的に、病院などで処方された薬の使用期限は、未開封の状態で製造後3~5年とされています。
しかし、薬が調剤された時点で製造からどのくらい経っているかはわかりません。
病院や薬局で処方された薬には「有効期限」の考え方はなく、医師から指示された服用期間が期限と考えてください。
したがって、以前に処方された薬を取っておいたり、飲み残した薬を後で自己判断で使用するのは避けましょう。 -
質問:薬は冷蔵庫に保管してもいいですか?回答:
薬を冷蔵庫に保管して良いかどうかは、薬の種類によります。
市販薬の場合、保管方法は外箱や説明書に記載されています。
病院で処方された薬については、薬剤師が保管方法を説明してくれます。
冷蔵保存が適していない薬を冷蔵庫に入れると、湿度や温度の変化で効果が落ちることがあります。
薬の保管方法については、必ず説明書や薬剤師の指示に従ってください。 -
質問:薬局以外でオンライン服薬指導はできますか?回答:
2022年9月30日の規則改正により、オンライン服薬指導が薬局以外の場所でも実施可能となりました。
ただし、実施場所は調剤を行う薬剤師と連絡が取れ、対面の服薬指導と同様に患者のプライバシーが確保された場所である必要があります。
また、音声のみの指導は認められず、映像と音声の両方による対応が義務付けられています。
インテンディス社の商品に投稿された口コミ・レビュー
-
対象商品:スキノレンクリーム20%投稿日: 2024.12.23いいかも
まだはっきりとは分かりませんが、使っているとニキビがいい感じで減ってくれているのが分かります。3週間ほどの使用ですが、大体、半分くらいの大きさになり、消えていくニキビも増えてきました。今まで使ったニキビ治療薬の中で一番いいかも。
-
対象商品:スキノレンクリーム20%投稿日: 2022.12.30キレイになったよ
病院に行くのが面倒なのでこちらのクリームを使ってみたらものの見事にキレイになったよ。友達からも「キレイになったね。どうやって治したの?」と聞かれたからこのサイトと商品名を教えておいた。届くまでちょっと時間がかかるけど許容範囲内。
-
対象商品:スキノレンクリーム20%投稿日: 2022.06.03ニキビに即効性あります。
レチノAだと皮剥けがひどく、痛みが出て使えなかったのでこちらを試してみました。夜に一度のみの使用です。白ニキビには本当にすぐ効きます。皮脂もかなり防いでくれます。私は30後半になって急に肌が荒れてしまいニキビ跡に使用していますが、穏やかに薄くなってきています。ただ、ニキビ跡に関しては結構時間がかかりそうです。
冷蔵庫にて保管しています。
-
対象商品:スキノレンクリーム20%投稿日: 2020.02.03青春のシンボルが
40代になって青春のシンボルができるとは思ってもみませんでした。すぐに治るだろうと放置していたらひどくなる一方なのでスキノレンクリームを使ってみることに。すると1週間くらいで見事ニキビが消えてなくなってくれました。よく効きますねコレ。
-
対象商品:スキノレンクリーム20%投稿日: 2019.08.20レチンAが合わなかったので
有名なレチンAが刺激が強すぎるようで合わなかったのでこちらにしました。肌の新陳代謝を活発にするピーリング効果は一緒ですが、やはり相性というものがあります。本来はニキビ治療薬なのでそちらへの効果もばっちりで、私の赤いポツポツタイプのニキビも綺麗に治りました。効果が強いぶん使用量に注意ですね。少しで十分効果ありです。

-
対象商品:スキノレンクリーム20%投稿日: 2018.03.12顔だけじゃなく全身に使います
顔だけじゃなくて全身いろんなところのニキビに使っています~背中とか、気づかないうちにブツブツになったりしていませんか?私も気づいたらだいぶ酷くなってたけど、なんとか引き返せて良かったです(笑)もちろん顔にもおすすめ!

-
対象商品:スキノレンクリーム20%投稿日: 2017.11.15これが一番よかった
ニキビの塗り薬も高校生の頃からたーくさん試してきましたが、20代後半にして出会えたこのスキノレンクリームが一番使ってみてよかったです!効果も確かだし、刺激感もないし、使い心地もよかったです。なくなったら絶対リピート買いします!

-
対象商品:スキノレンクリーム20%投稿日: 2017.08.11大満足です!
悩んでた大人ニキビが治りました☆*:.。. o(≧▽≦)o .。.:*☆皮膚科に行くほどではないしな〜となんとなく放置してたけど、やっぱり治ると気持ちが良いものです。通販で手軽に買えるのがすごく良かったです!それでこの効果は大満足です!

-
対象商品:スキノレンクリーム20%投稿日: 2017.06.01よく効くよ!
普通に病院以外で買えるクリームとかよりもずっと効きます。さすが医薬品☆ちょっとしたことでできやすいので、常備していつでも使えるようにしてます。

-
対象商品:スキノレンクリーム20%投稿日: 2017.04.05吹き出物wwにも
若い頃からニキビができやすかったけど、大人になってからできるニキビもまた一味違って…いや、これは吹き出物っていうのかwwいい加減対策しようと思って見つけたのがスキノレンです。結果、もっと早く使いたかったなーってくらい効果がありました!