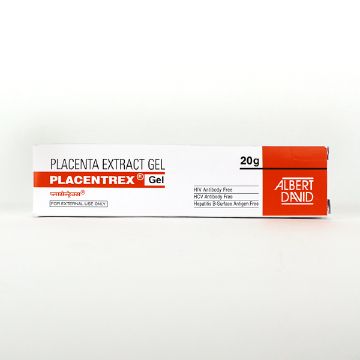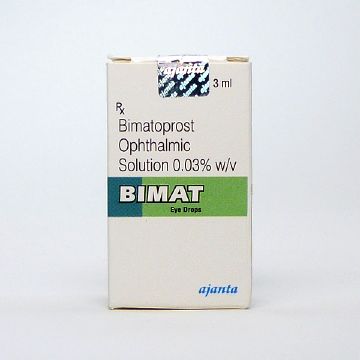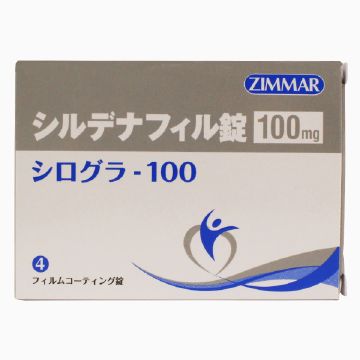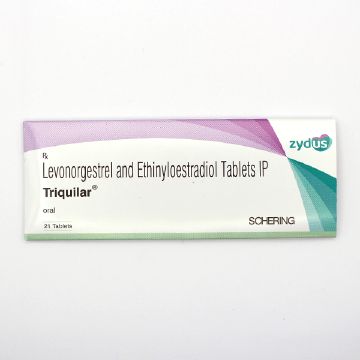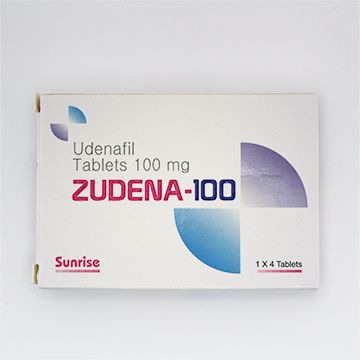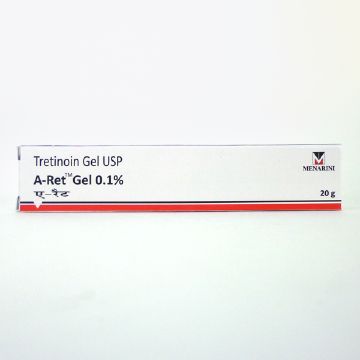エムキュア

-
英語表記Emcure Limited
-
設立年月日1981年
-
代表者Satish Mehta
-
国インド
-
所在地Emcure House, T-184, M.I.D.C., Bhosari, Pune - 411026, India
-
ホームページ
インド発のグローバル製薬企業、エムキュアの成長と展開
エムキュア・ファーマシューティカルズ・リミテッドは、1981年にサティシュ・メータによってインドのプネに設立された多国籍製薬会社です。
設立当初、エムキュアは契約製造を主力事業として運営していましたが、1990年代にはジェネリック医薬品の製造にシフトし、急速な成長を遂げました。
現在、エムキュアはインド国内外で幅広い医薬品を提供しており、70カ国以上で事業を展開しています。
エムキュアの成長の鍵は、積極的な国際展開と戦略的パートナーシップです。
2006年、エムキュアはブリストル・マイヤーズ スクイブおよびギリアド・サイエンシズと提携し、HIV治療薬であるアタザナビルとテノホビルの製造に関するライセンス契約を締結しました。
この契約により、エムキュアはHIV治療薬のグローバルアクセスプログラムに参加し、国際的な存在感を強化しました。
さらに、2012年にはロシュと提携し、抗がん剤であるハーセプチンおよびマブセラのインド国内製造を開始しました。
これにより、これらの重要な治療薬を発展途上国において手頃な価格で提供し、同時に社会的責任を果たすことに成功しました。
この提携は、エムキュアにとってインド市場における市場シェア拡大の大きなステップとなりました。
エムキュアの国際展開は、米国市場への進出によってさらに加速しました。
2021年には米国事業を分離し、新会社であるアベット・ライフサイエンシズを設立しました。
これにより、米国市場での競争力をさらに強化し、グローバル市場における存在感を高めました。
特に、米国市場での拡大に伴い、エムキュアは新しい市場機会を活用することで、さらなる成長を目指しています。
また、エムキュアは2024年にインドの証券取引所に上場し、資本市場からの資金調達を通じて、研究開発や国際展開のさらなる強化を図っています。
この資金調達により、エムキュアは革新的な医薬品の開発を進め、患者への治療オプションを拡充することを目指しています。
エムキュアの成長戦略は、単なる規模の拡大だけでなく、持続可能な成長にも重点を置いています。
同社は環境負荷の低減に積極的に取り組み、持続可能な製造プロセスの採用や社会貢献活動を推進しています。
これにより、エムキュアは企業としての社会的責任を果たしつつ、グローバル市場での競争力を維持しています。
エムキュアの得意分野と多様な製品ポートフォリオ
エムキュア・ファーマシューティカルズ・リミテッドは、幅広い製品ポートフォリオを持ち、特に婦人科、心血管、腫瘍、血液治療薬、HIV抗ウイルス薬、抗感染症薬、ビタミン・ミネラル製剤などの分野で強みを発揮しています。
エムキュアは、これらの治療領域において、患者に質の高い治療を提供するために継続的に革新を行っており、世界70カ国以上で事業を展開しています。
エムキュアの製品ラインアップには、錠剤、カプセル、注射剤など多様な形態があり、国内外の市場で高く評価されています。
特に、HIV治療薬の分野では、インド国内でリーダー的な役割を果たしており、国際的な市場でも重要なプレイヤーとなっています。
代表的な製品としては、HIV治療薬の「アタザナビル」や「テノホビル」が挙げられ、これらはBristol-Myers SquibbおよびGilead Sciencesとの提携により製造されています。
また、抗がん剤の「ハーセプチン」や「マブセラ」は、ロシュとの協力のもとインド国内で製造されており、発展途上国において手頃な価格で提供されています。
エムキュアは、これらの製品を通じて未充足の医療ニーズに応えることを目指し、特にHIV治療薬の分野では、アフリカ、アジア太平洋、CIS諸国への抗レトロウイルス薬の供給を行い、世界中のHIV/AIDS患者の治療に貢献しています。
この取り組みは、エムキュアが国際的に重要な役割を果たす大きな要因となっています。
さらに、エムキュアは研究開発にも積極的に取り組んでおり、約500人の科学者を擁するR&D部門を運営しています。
この部門では、原薬、製剤、バイオテクノロジーの研究に重点を置いており、革新的な治療法の開発を進めています。
エムキュアのR&D活動は、製薬業界における競争力を高め、ジェネリック医薬品にとどまらず、革新的な医薬品の提供を目指しています。
2024年にインドの証券取引所に上場し、資本市場からの資金調達を通じて、さらなる研究開発や国際展開を進めています。
環境への配慮や持続可能な事業運営にも注力しており、社会的責任を果たしながら事業を拡大しています。
今後もエムキュアは、多様な製品ラインアップを通じて、世界中の患者の健康と生活の質の向上に貢献することを目指しています。
エムキュアの戦略的パートナーシップと買収
エムキュア・ファーマシューティカルズの成長は、戦略的なパートナーシップと買収に支えられています。
同社は、国内外の製薬企業との連携を通じて製品ラインアップを拡大し、国際的な市場シェアを拡大してきました。
2006年、エムキュアはBristol-Myers SquibbおよびGilead Sciencesとライセンス契約を結び、HIV治療薬であるアタザナビルとテノホビルの製造を開始しました。
これにより、エムキュアはグローバルアクセスプログラムに参加し、HIV治療薬の普及に貢献しました。
この契約は、同社が国際的なプレゼンスを高めるきっかけとなりました。
また、2012年にはRocheと提携し、抗がん剤HerceptinとMabtheraのインド国内製造を開始しました。
この提携は、発展途上国でこれらのブロックバスター薬を手頃な価格で提供することを可能にし、エムキュアが社会的責任を果たしつつ、市場での影響力を強化する一助となりました。
2014年には、ブラックストーンが保有していたエムキュアの株式13%をベインキャピタルに売却しました。
この取引は、同社がさらなる成長資金を調達し、研究開発および国際展開を加速させる重要なステップとなりました。
エムキュアの成長は単なる規模の拡大にとどまらず、持続可能な成長と環境への配慮にも重点を置いています。
例えば、同社は環境負荷の低減や社会貢献活動に積極的に取り組んでおり、製薬業界全体で持続可能な事業運営のモデルを提供しています。
今後、エムキュアは戦略的パートナーシップや買収を通じてさらなる国際市場での成長を目指すとともに、革新的な医薬品を提供し、世界中の患者の健康向上に貢献していくことを目標としています。
このように、エムキュアは持続可能で革新的な成長を追求し、グローバルな製薬企業としての地位を確固たるものにしつつあります。
エムキュアの社会貢献と企業責任
エムキュア・ファーマシューティカルズは、社会貢献と企業責任を重視した取り組みを行っており、さまざまな分野で活動しています。
特に、HIV/AIDS治療において重要な役割を果たしており、「Let's fight AIDS together」というイニシアチブを通じて、HIV/AIDS患者向けの薬局「Taal」を支援しています。
この活動の一環として、エムキュアはアフリカ、アジア太平洋、CIS諸国に抗レトロウイルス薬を供給し、HIV/AIDS患者の治療に貢献しています。
また、エムキュアは女性の健康に関する啓発活動にも注力しており、特に女性の健康に関するタブーを打破し、健康問題についての意識向上を図っています。
実際の経験を共有するためのプラットフォームを提供し、女性が自身の健康について自由に話し合える環境を整えることで、女性の健康に対する理解を深めています。
さらに、エムキュアは環境保護にも積極的に取り組んでいます。
持続可能な製造プロセスを採用し、再生可能エネルギーの利用を促進しています。
最近では、Sunsure Energyからの太陽光発電を導入することで、クリーンエネルギーの利用を拡大し、環境負荷の低減を目指しています。
これにより、エムキュアは事業活動における環境への影響を最小限に抑える努力を続けています。
一方で、エムキュアは過去に品質管理や価格操作に関する問題で批判を受けたこともあります。
2016年には、米国司法省から価格操作の疑いで告発され、2019年には和解金を支払うことで合意しました。
さらに、2022年にはマハラシュトラ州のFDAからの指示で、製造した注射剤のリコールを実施しました。
これらの問題に対応するため、エムキュアは品質管理の強化とコンプライアンスの徹底に取り組んでおり、製品の安全性と品質を確保するために内部監査を強化し、従業員の教育を充実させています。
エムキュアの社会貢献活動は、企業の持続可能な成長を支える重要な要素であり、単なる慈善活動にとどまらず、企業としての責任を果たす姿勢が明確に示されています。
今後も、エムキュアは革新的な医薬品の提供を通じて、世界中の患者の健康と福祉に貢献することを目指しています。
よくあるご質問(FAQ)
-
質問:エムキュアとは何ですか?回答:
2023年4月15日にマツキヨココカラ&カンパニーから新発売となった、髪の毛と頭皮のうるおいバランスに着目した新発想のヘアケアブランドです。
遺伝子研究、髪質、生活習慣などの要素からパーソナライズされたシャンプー・トリートメントが発売されました。
また「髪の悩み」と「フレグランス」どちらの要素も取り入れたヘアケアで、理想の髪を手に入れることを目的としています。 -
質問:マツキヨのエムキュアの成分は?回答:
頭皮と髪の毛の潤いに着目した、フケやかゆみを防止・育毛促進・頭皮の炎症を抑制の3つの成わから成り立っています。
フケやかゆみを防止する塩酸ジフェンヒドラミン、育毛を促進するセファランチン、頭皮の炎症を抑えるグリチルリチン酸とこの3つの成分で頭皮をケアしています。
さらに保湿力の高いセラミド成分も配合されていて、潤いを保ちます。 -
質問:エムキュアシャンプーの効果は何ですか?回答:
頭皮と髪の毛のうるおいを維持するために特別なペプチドを配合し、水分を保持と髪の毛を守る役割があるため、乾燥によるダメージを防ぎます。
また、この成分は髪の毛一本一本を補修し、健康的な頭皮の維持の役割もあります。
かゆみ・ベタつき・フケ・ニオイといった頭皮のトラブルに対応し、頭皮と髪の毛に潤いを与え、美しい髪を保つ効果があります。 -
質問:なぜ薬がないのでしょうか?回答:
製薬工場では、機械の故障や品質管理の問題、原材料の不足などが原因で計画通りに医薬品を製造できないことがあります。
また、製造中に汚染や不純物が混入した場合、その製品の一部または全部を廃棄しなければならず、供給が一時的に途絶えることもあります。
これらの製造トラブルは、医薬品の生産に大きな影響を与えることがあります。 -
質問:なぜ薬が供給不足になるのでしょうか?回答:
医薬品の供給不足は、2020年12月に発覚したジェネリック(後発医薬品)メーカーの製造の不正が原因の一つと言えます。
製造の工程がきちんと守られていないなど製造の問題が発覚し、業務停止となりました。
製造が停止したことでメーカーからの薬品供給不足となり病院や薬局で薬不足となっています。 -
質問:なぜ処方箋がないと薬はもらえないのか?回答:
日本国内では、処方箋がないと薬を手に入れられないのは、医薬品医療機器等法第49条の規定によります。
この法律では、医師、歯科医師、または獣医師から処方箋を受けた者以外には、特定の医薬品(処方せん医薬品)を販売したり提供したりしてはならないと定められているからです。 -
質問:残薬は社会問題になっていますか?回答:
残薬問題は現代の日本社会において重要な社会問題となっています。
主な原因は「薬の種類や量が多く、複雑な服用スケジュールが理解されずに忘れられること」や「自己判断で病気が治ったと考え服用を中止すること」、「処方された日数と受診間隔の調整が難しいこと」が挙げられます。 -
質問:残薬は医師に伝えるべきですか?回答:
残薬を医師に伝えない患者さんが多いですが、これは非常に危険です。
医師は患者さんの体調に基づいて処方を調整します。
薬の効果が得られていると判断すれば継続や減量を行い、効果が不十分であれば薬の種類や用量を変更します。
しかし、実際に薬を飲んでいないことが原因で効果が得られていない場合、変更や増量は予期せぬ副作用を引き起こす可能性があります。
したがって、正直に服薬状況を医師に伝えましょう。 -
質問:薬剤師がなぜ薬について聞いてくるのですか?回答:
薬剤師は、患者さんの体質や健康状態、アレルギーや副作用のリスクを確認し、同時に同じ様な薬を使っていないか確認するために質問します。
この情報は薬歴簿に記録され、次回の処方時に役立てられます。
薬剤師の質問は、安全かつ効果的な薬の使用を確保するための重要な手段です。 -
質問:薬局で残った薬はもらえますか?回答:
残薬がある場合は、薬局に持っていき薬剤師に相談しましょう。
薬剤師は残薬の量を調整し、次回以降の処方を見直してくれます。
医師に伝えづらい場合でも薬剤師が仲介し、調整を行うので安心です。
また、使用期限や安全性の確認もしてもらえるため、服薬に関する疑問や不安がある時も相談すると良いでしょう。
残薬の処分方法がわからない場合も薬局で適切に処分してもらえます。 -
質問:病院でもらった薬は薬局で一包化できますか?回答:
病院から処方された薬は、保険薬局で一包化が可能です。
錠剤やカプセルが多く処方されると、服用タイミングを間違えやすくなりますが、一包化により、飲み忘れや飲み間違いを防ぐことができます。
薬の管理が簡単になるので、希望する場合は薬剤師に相談しましょう。 -
質問:病院で余った薬はどうすればいいですか?回答:
手持ちの余ったお薬がある場合は、まず医師や薬剤師に相談し次に処方されるお薬の量を調節してもらうようにしましょう。
飲み忘れて余ってしまったお薬は、薬局に持参して薬剤師に相談します。
薬剤師はお薬の状態や数を確認し、医師に連絡して処方日数を調整してもらうことができます。 -
質問:薬の説明書は捨ててもいいですか?回答:
一般用医薬品の場合、外箱や説明書は薬を使い切るまで大切に保管しましょう。
薬と一緒に入っている説明文書はいつでも確認できるように保管しておくことが大切です。
医療用医薬品については、医師や薬剤師の指示に従う必要があります。 -
質問:置き薬は使ってなくてもいいの?回答:
配置薬を使用しなくても、そのまま保管しているだけであれば、消費者は薬代を支払う義務はありません。
ただし、一旦薬を預かると、消費者には薬の保管義務が生じるため、自己判断で処分すると業者から薬代を請求される可能性があります。
不要になった場合は、薬箱に通常封入されている業者の連絡先を確認し、引き取りを依頼するのが良いです。 -
質問:薬は何年くらい持つ?回答:
薬は未開封の状態で正しい保存環境で保存されていれば、製造後約3~5年は効果が変わらず使えるとされています。
一般用医薬品の場合、外箱に記載された使用期限が未開封時の期限を示しています。
開封後は温度や湿度、光の影響を受けやすく、早めに使用することをおすすめします。 -
質問:病院でもらった薬は何年もつ?回答:
病院で処方された医療用医薬品は、未開封の状態で製造から約3~5年は効果が変わらず使用できるとされています。
ただし、医師が患者さんの状態に合わせて処方しており、その指示通りに使用することが重要です。
自己判断で残った薬を後で使用したり他人に勧めたりすると、効果がなかったり症状が悪化したりする可能性があります。
医療用医薬品は医師や薬剤師の指導に従い、必要な量を適切に使用するよう心がけましょう。 -
質問:薬は冷蔵庫に保管してもいいですか?回答:
坐薬や液剤・水薬、または「冷所保管」が指示された場合は、乾燥し光が当たらない冷たい場所が適しているため、冷蔵庫はこれらの薬を保管する最適な場所です。
ただし、シロップ剤は子どもが間違えて飲む可能性があるため、子どもの手の届かない場所に置き、凍結しないように気を付ける必要があります。
一方、錠剤や粉薬は、そのままの包装でなく密閉容器に入れて乾燥剤を使用するのが良いです。
特に目の不自由な方や薬と間違える危険性がある場合は、乾燥剤の使用を避けましょう。 -
質問:薬局以外でオンライン服薬指導はできますか?回答:
2022年9月30日、医薬品医療機器等法(薬機法)施行規則の改正により、オンライン服薬指導が薬局以外の場所でも可能になりました。
この改正により、患者の求めや異議がない場合、薬剤師は薬局外からもオンラインで服薬指導を行うことができます。
今後、オンライン服薬指導がより一般的な方法となるよう、さらなる改正が進められるでしょう。 -
質問:オンラインで服薬指導は受けられますか?回答:
法改正により、薬剤師の判断と責任の下でオンライン服薬指導を受けられるようになりました。
診療形態による制限はなく、医療機関で対面診療を受けた後にオンラインで服薬指導を受けることも可能です。
原則としてすべての薬がオンライン服薬指導の対象ですが、処方内容や患者の体調変化によっては、薬剤師が対面での服薬指導に切り替える場合もあります。 -
質問:処方箋なしで買える薬はなんて呼ばれますか?回答:
処方箋なしで買える薬は「OTC(Over The Counter)医薬品」と呼ばれます。
これらはドラッグストアや薬局で購入でき、医師の処方箋は必要ありません。
一方で、病院で診察を受けて処方される薬は「医療用医薬品」と呼ばれ、購入には通常、医師の処方箋が必要です。
医療用医薬品には「処方箋医薬品」と「処方箋医薬品以外の医療用医薬品」があり、後者は必ずしも処方箋が必要ない薬です。
エムキュア社の商品に投稿された口コミ・レビュー
-
対象商品:パウゼ500mg投稿日: 2024.11.16効果絶大!
飲み始めて、3週間でこんなに効果が出ました! 以前にレーザー治療をしたことがありますが、すぐに戻ってしまったので、こちらの錠剤はすごくオススメです!!

-
対象商品:パウゼ500mg投稿日: 2024.07.03明確な違いは・・・
半年近く飲んでいますが、今一つ明確な違いが解りません
でも日差しが強い時期には飲んでいます。
錠剤が大きいのが難ありですね・・ -
対象商品:パウゼ500mg投稿日: 2023.12.25トラネキサム酸
美白のために購入してみました。副作用などに気をつけながら服用してみます。
いま病院で処方してもらうと日数が少ないので多めに買ってみました。
効果はまだわかりませんが頑張ってみます
-
対象商品:パウゼ500mg投稿日: 2023.02.03夏はマスト
夏になると絶対に必要なお薬です。なぜかというと息子が野球をやっているので観戦に行き日焼けしてしまうから。日焼け跡を放置しておくと痕になってしまいますが、こちらのお薬とスキンケアをしっかり行うことで、痕にならずに元通りになってくれます。なので夏のマストアイテムです。
-
対象商品:パウゼ500mg投稿日: 2022.12.14お高い美容液よりコレです!
肝斑が気になっているアラフォーです。
肝斑には外側のケアより内服薬の方が効果的と聞いて1ヶ月使用しました。私の場合、若干眠気が出てしまったので朝晩半錠ずつです。効果ないかな?と不安でしたが2週間過ぎたあたりから肝斑が薄くなってきました!あとキメが整ったのか、ツヤ感もでてきたように思います。このまま2ヶ月間継続使用してみます。
私のように化粧品では効果を感じられなかった方、体調に問題が無ければ是非試していただきたいです!
-
対象商品:パウゼ500mg投稿日: 2022.10.19抗炎症
トラネキサム酸という抗炎症のお薬が主成分になっています。なので、肝斑や日焼け痕などの炎症性疾患によく効きます。私は日焼け跡の肌の赤みに使っています。服用すると治りが全然違いますね。服用しない場合は2~3か月赤みが残り続けますが、薬を服用すると10日ほどで改善してくれます。
-
対象商品:パウゼ500mg投稿日: 2021.11.18いいかも
メラケアforteクリームと一緒に使ってますがかなりいい感じです。気になっていた頬の色素沈着がかなり薄くなっています。また、日焼け後の赤みなども薄くなっています。以前、カネボウであった副作用的なものもありません。いいと思います。
-
対象商品:パウゼ500mg投稿日: 2020.10.30肝斑が…
30代なのにも関わらず、頬に肝斑が出来て困り果てていました。そんな時に出会ったのがこちらのパウゼ。別段、飲み始めてから変化はないのですが、予防のために飲んでいるという感じです。特に夏は濃くなるのでしっかり服用しようと思います。
-
対象商品:パウゼ500mg投稿日: 2020.01.13肝斑の治療
肝斑の治療薬です。一番よく効くのは日焼けによる頬の赤みですね。何も飲まないと赤みが沈着してシミになりますが、パウゼを飲んでいると赤みが消えやすくなり、その後シミにもなりません。そして肌のキメが細かくなります。これは間違いありません。自分には合ってると思います。
-
対象商品:パウゼ500mg投稿日: 2019.03.19しみの改善
初めて使用してみました。このタイプのものは長期間使用してみないと効果はわからないと思いますが、20日間の使用でそれなりに改善効果が感じられましたので、今度は大容量タイプに挑戦してみようと思います。