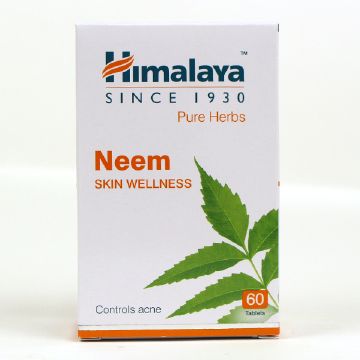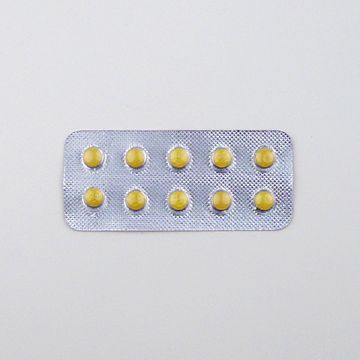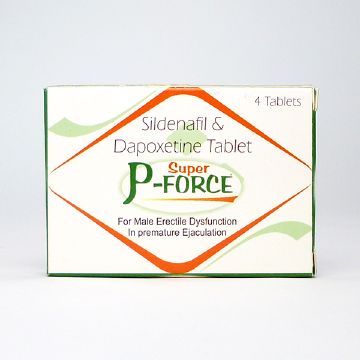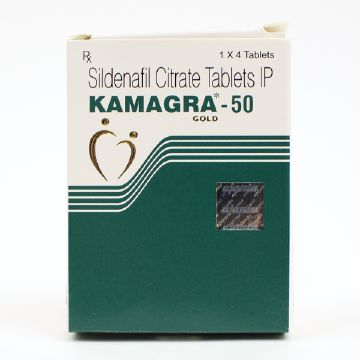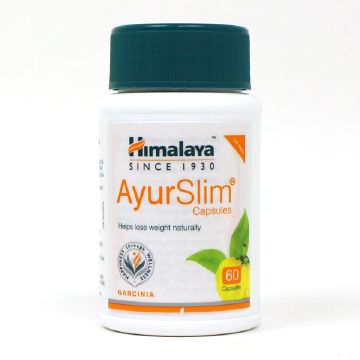シノケムファーマ

-
英語表記Synokem Pharmaceuticals
-
設立年月日1983年8月18日
-
代表者J.M. Arora
-
国インド
-
所在地14/486, Basement & Ground Floor, Outer Ring Road, Paschim Vihar, New Delhi - 110087, India
インドの製薬業界をリードする革新的企業シノケムファーマ
シノケムファーマは、1983年8月に設立されたインドの製薬会社で、契約製造、倫理的マーケティング、輸出、機関向け供給において優れた能力を持つ成長企業です。
同社は、品質の高い製品を社会のあらゆる層に手頃な価格で提供することを目指し、インドだけでなく世界的にも一流の製薬メーカーになることを目標としています。
シノケムファーマの成長は目覚ましく、この成功の背景には、同社の戦略的な事業展開と革新的なアプローチがあります。
同社の強みの一つは、最先端の製造施設です。
ウッタラーカンド州ハリドワールに新設された超近代的な工場は、WHO-GMP認証とISO 9001:2008認証を取得しており、高品質な医薬品の製造を可能にしています。
この施設は、シノケムファーマの製品品質と生産能力の向上に大きく貢献しています。
シノケムファーマの経営陣も、同社の成功に重要な役割を果たしています。
創業者兼会長のJ.M. Arora氏は、50年以上にわたる製薬業界での豊富な経験を持ち、その先見性と卓越した意思決定能力で会社を導いています。
シノケムファーマは、研究開発にも力を入れており、科学的な研究開発チームが革新的な製品の開発に取り組んでいます。
同社は、品質、安全性、有効性に重点を置いた製品開発を行い、患者のニーズに応える医薬品の提供を目指しています。
シノケムファーマの事業戦略
シノケムファーマの事業戦略は、多角的なアプローチによる市場シェアの拡大に焦点を当てています。
同社は、契約製造(CDMO)、倫理的マーケティング、輸出、機関向け供給という4つの主要な事業分野で活動しており、それぞれの分野で独自の強みを発揮しています。
契約製造事業では、シノケムファーマは多くの国内外の製薬会社から信頼を得ています。
同社のWHO-GMP認証を取得した最新の製造施設は、高品質な医薬品の製造を可能にし、顧客のニーズに柔軟に対応することができます。
倫理的マーケティング分野では、シノケムファーマは高品質な医薬品を適切な方法で医療専門家に提供することに注力しています。
同社は、製品の安全性と有効性に関する正確な情報を提供し、適切な使用を促進することで、患者の健康と福祉の向上に貢献しています。
輸出事業においては、シノケムファーマはグローバル市場での存在感を高めています。
同社の製品は品質と信頼性で国際的に評価されており、多くの国々で販売されています。
特に、新興国市場での展開に力を入れており、これらの地域での医療アクセスの向上に貢献しています。
機関向け供給事業では、シノケムファーマは政府機関や非営利組織との協力関係を構築し、大規模な医薬品供給プロジェクトに参加しています。
この分野での実績は、同社の生産能力と品質管理システムの高さを示すものとなっています。
シノケムファーマの革新と持続可能性の追求
シノケムファーマは、革新と持続可能性を追求しながら、将来の成長を見据えています。
同社のビジョンは、商業的に実行可能な主要製薬会社として、社会のすべての層に手頃な価格で質の高い製品を提供することです。
このビジョンの実現に向けて、シノケムファーマは様々な取り組みを行っています。
研究開発分野では、シノケムファーマは継続的なイノベーションを重視しています。
同社の科学研究開発チームは、新しい製剤技術の開発や既存製品の改良に取り組んでおり、患者のニーズに合った革新的な医薬品の創出を目指しています。
特に、ジェネリック医薬品の開発に力を入れており、高品質で手頃な価格の医薬品を提供することで、医療アクセスの向上に貢献しています。
シノケムファーマの将来展望において重要な位置を占めているのが、グローバル展開の加速です。
同社は、既存の輸出事業をさらに拡大するとともに、新たな市場への進出を計画しています。
シノケムファーマの経営陣は、「世界クラスの製薬メーカーになる」という目標を掲げています。
この目標の実現に向けて、同社は継続的な研究開発投資、製造能力の拡充、国際的な人材の育成などに取り組んでいます。
シノケムファーマが、今後どのようにグローバル市場で成長を遂げ、インドの製薬業界をリードする企業としての地位を確立していくか、業界関係者から注目されています。
引用 : https://www.synokempharma.com/
引用 : https://www.tofler.in/synokem-pharmaceuticals-limited/company/U34239DL1983PLC016353
引用 : https://www.cphi-online.com/synokem-pharmaceuticals-ltd-comp245801.html
引用 : https://in.linkedin.com/company/synokem-pharmaceuticals-ltd
よくあるご質問(FAQ)
-
質問:なぜ薬がないのでしょうか?回答:
薬不足の理由としてよく報じられるのは「製造上の不正」ですが、実際には他にも様々な原因があります。
たとえば、「製造段階での問題」や「原材料の不足」、「輸送の遅延」、さらには「他の薬が不足している場合に関連する薬も不足する」といったことが挙げられます。
不正以外にも、意図しない様々な理由で供給が滞ることがあります。 -
質問:なぜ薬が供給不足になるのでしょうか?回答:
薬不足の原因には「製造設備の問題」や「原材料不足」、「品質や現有料の問題」、「供給体制の問題」などがあり、これらの要因が重なると製造が停止し、需要と供給のバランスが崩れることがあります。
この様な状況になると、消費者や医療機関は代替薬を求めて他の類似薬に注文が集中します。
この結果、代替薬の出荷も急増し、供給が追いつかなくなることがあります。
さらに、代替薬の需要が高まることで、他の薬品の供給にも影響を及ぼし、全体的な薬の供給に支障をきたすことが多くあります。
こうして、製造上の問題が一連の供給停止を引き起こし、広範囲にわたる薬不足が発生するのです。 -
質問:なぜ処方箋がないと薬はもらえないのか?回答:
「医薬分業」という言葉があります。
医療分業とは、医師と薬剤師の2つの専門職により、医薬品使用を2重にチェックするシステムです。
同じ様な症状でも患者さんによって薬の種類や量が異なることがあります。
より正しく安全に使用するために処方箋を発行し、第三者である薬剤師のチェックが望まれるようになりました。 -
質問:残薬は社会問題になっていますか?回答:
残薬による社会問題として大きいのは、「医療費が無駄」になってしまうことです。
患者さんの窓口支払いは1割~3割ですが、実際の金額は膨大です。
平成27年のデータですが、1,890薬局の5,447名の患者さんの残薬は、合計8,529,846円であり、1人あたり4,885円でした。
正しく服用することができていれば受診回数が減ったり、服用量が減少したりする可能性もあります。 -
質問:残薬は医師に伝えるべきですか?回答:
残薬がある場合は医師に伝えましょう。
「医療費の無駄」以外にも重要なことがあります。
それは「健康リスク」です。
通常、医師は処方した薬を正しく服用していると思って診察をします。
飲まずに病気が悪化してしまうこともあれば、効果がないと判断され、増量や追加をされて、副作用が出てしまう可能性もあります。 -
質問:薬剤師がなぜ薬について聞いてくるのですか?回答:
薬剤師が薬について質問するのには、以下の様な目的があります。
1つ目は、アレルギーや副作用の履歴、他に服用している薬を確認し、その薬が安全に使えるか判断します。
2つ目は、医師からの説明内容を確認し、薬の使い方に間違いがないかをチェックします。
継続して服用している場合も、使用方法が正しいかを確認します。
3つ目は、薬を続けることで期待される効果が出ているか、また気づかない副作用が出ていないかを確認します。
これらの理由から、薬を渡す際に質問させていただくことがあります。 -
質問:薬局で残った薬はもらえますか?回答:
薬局では、処方箋がないと薬をお渡しすることはありません。
もしご自身で薬を長期間保管するのが難しい場合には、薬局でお薬の一部を預かることがあります。
その後の状況に応じて、残りの薬をお渡しすることがあります。 -
質問:病院でもらった薬は薬局で一包化できますか?回答:
薬局では、一包化が有料になる場合があります。
薬の種類によっては、一包化できないものや一緒に一包化できないものがあるため、その場合は一包化可能な薬のみ対応します。
名前や日付、用法などを印字することも可能です。
一包化には時間がかかることがあるので、時間に余裕を持って薬局に行くか、一旦薬を預けてから外出することも検討してください。 -
質問:病院で余った薬はどうすればいいですか?回答:
飲み続けている薬がある場合は、次回の受診時に残りの錠数を医師に伝えてください。
処方箋の薬は、頓服薬を除き、特別な指示がない限り処方後すぐに飲み始めることが前提とされています。
残薬がいつ貰ったかわからない場合や、1年以上前の薬は使用しないでください。
症状が似ていても、原因が異なる可能性があるため、しっかり診断を受けて必要な薬を再処方してもらいましょう。 -
質問:薬の説明書は捨ててもいいですか?回答:
薬局で貰う説明書は、捨てないようにしましょう。
服用が終了した場合には捨てて問題ありません。
薬の説明書には「薬の名称」「用法用量」「副作用・リスク」について書かれています。
患者さん本人が把握できるのはもちろんですが、緊急事態(災害や緊急搬送など)にも活用できます。
説明書があれば、普段服用している医薬品について正確に情報伝達が可能となります。 -
質問:置き薬は使ってなくてもいいの?回答:
薬には有効期限があるため、年に1、2回は確認するようにしましょう。
有効期限内であれば基本的には問題ありませんが、例外として、薬が割れていたり、湿気で変質している可能性もあります。
定期的に薬の保管状況や外観、期限をチェックして、問題がないか確認することが大切です。 -
質問:薬は何年くらい持つ?回答:
工場の最終包装の段階で約3年の有効期限が設定されています。
患者さんの手に最短で渡れば約3年の有効期限となります。
しかし、ほとんど処方されない様な医薬品に関しては、薬局で保管され続け、患者さんの手に渡った時には、残り数ヵ月ということもあり得ます。
処方されすぐに飲む薬であれば問題ありませんが、症状がある時に飲む頓服薬については、薬剤師に有効期限を確認しましょう。 -
質問:病院でもらった薬は何年もつ?回答:
薬局や病院で受け取る薬の有効期限は、出荷時に約3年です。
しかし、薬の種類によっては、開封後1ヵ月以内に使い切る必要があるものもあります。
また、薬を半分に割ったり、一包化している場合は、有効期限が通常よりも短くなります。
症状がある時だけ服用する薬の場合は、必ず期限を確認してから使用するようにしましょう。 -
質問:薬は冷蔵庫に保管してもいいですか?回答:
薬の保管温度は「室温」「冷所」と表現されています。
室温は「1~30℃」、冷所は「1~15℃」と設定されており、冷蔵庫であればどちらも範囲内となります。
そのため冷蔵庫で薬を保管しても温度においては問題ありません。
一方で、注意点もあります。
それは「結露」「凍結」です。
湿気に弱い薬もあれば、凍ると成分が壊れてしまう可能性などがあります。
冷所と言われていない場合は直射日光を避け、30℃を超えない部屋で保管しましょう。 -
質問:薬局以外でオンライン服薬指導はできますか?回答:
薬局以外でもオンライン服薬指導のアプリやサイトが登場しています。
実店舗を持つ薬局もオンライン服薬指導の環境を整えているところがあります。
よく行く薬局で継続してもらいたい場合は、オンライン服薬指導を実施しているか確認してみましょう。
いずれにおいても、事前予約が必要となる場合があるので注意してください。 -
質問:オンラインで服薬指導は受けられますか?回答:
現在、オンライン服薬指導はどこでも受けられるようになりました。
ただ、パソコンやスマートフォンといったビデオ通話ができるデバイスが必要となります。
患者さんの状態を把握したうえで、薬の服用方法や注意点の情報提供がなされます。
全国どこの処方箋でもオンライン服薬指導を受けることが可能です。
ただし、薬局によってはオンライン指導の環境が整っていない所もあるので注意が必要です。 -
質問:処方箋なしで買える薬はなんて呼ばれますか?回答:
医療用医薬品の「非処方箋医薬品」は処方箋なしで購入できます。
近年、店舗数が増加しているものの、実際に処方箋なしで販売している薬局は多くありません。
不適切な広告で集客につなげるケースもあり規制されつつあるのが現状です。 -
質問:オンライン服薬指導は電話のみでもいいですか?回答:
ビデオ通話による情報提供が必須項目となっています。
以前は可能であった音声のみ(電話)でのオンライン服薬指導は現在は認められません。
スマートフォンのアプリだけで完結するなど、オンライン服薬指導の環境は整ってきています。
スマートフォンやPCの操作に問題がなければ非常に便利です。 -
質問:オンライン服薬指導で薬を受け取る方法は?回答:
オンライン服薬指導での薬の受け取り方は、「薬局で受け取り」と「配送」のいずれかです。
ご自身の都合に合わせて受け取りたいなどの要望があれば、「薬局で受け取り」をおすすめします。
急ぎの薬でない場合は「配送」が良いでしょう。
送料などが別途発生する可能性があるので、事前に確認しておきましょう。
オンライン診療と組み合わせれば、全て自宅で完結することも可能です。 -
質問:オンライン服薬指導を受けている人の割合は?回答:
正式なデータは公表されていませんが、2023年1月23日から2月20日までの期間に実施されたアンケートがあります。
このアンケートには3,838薬局が回答し、回答率は20.9%でした。
その結果、オンライン服薬指導のシステムを「導入している」と回答した薬局は81%と高い割合でしたが、直近3ヵ月に実際にオンライン服薬指導を行った薬局は13.1%で、処方箋の総受付件数に対する割合は0.045%にとどまりました。
今後、オンライン診療や電子処方箋の普及に伴い、オンライン服薬指導も増加することが予想されます。