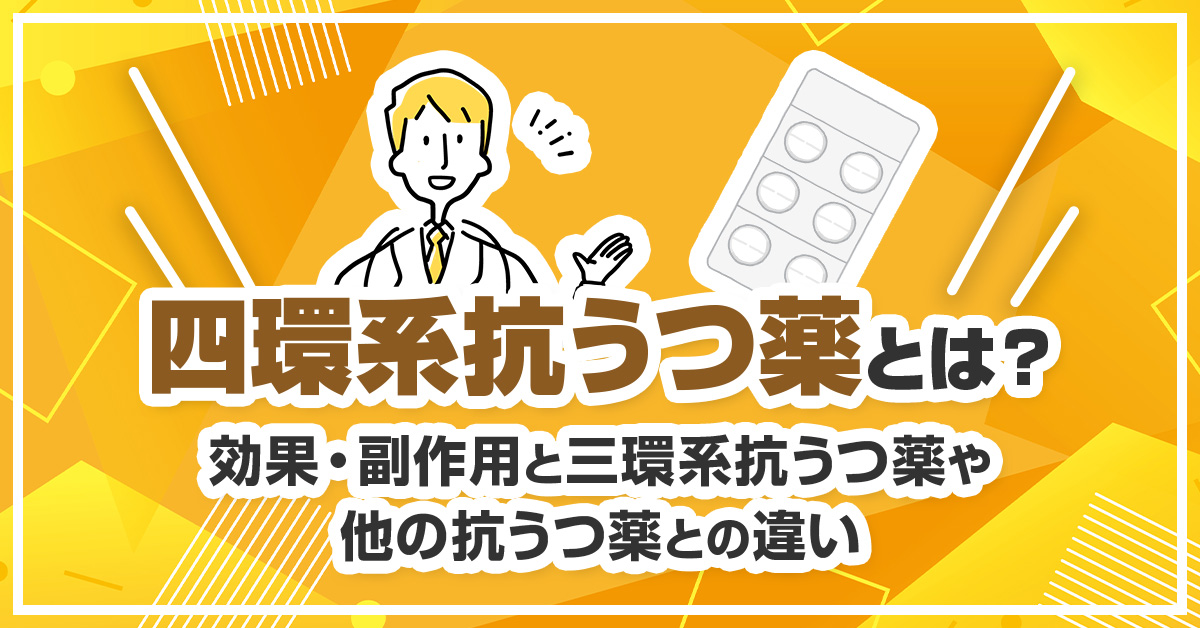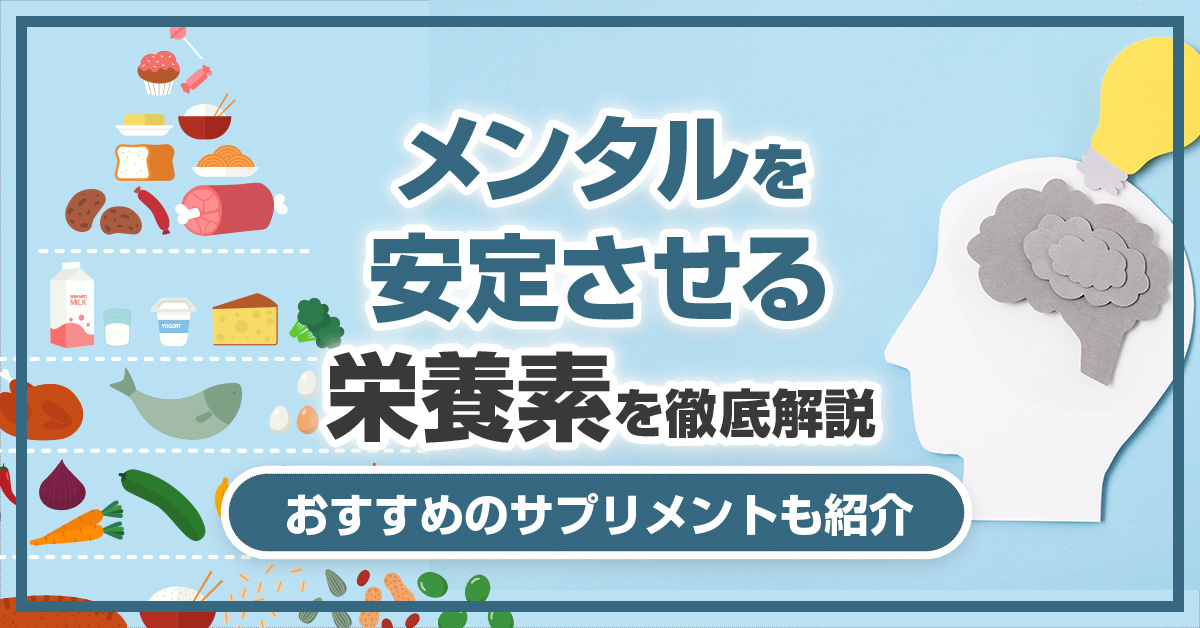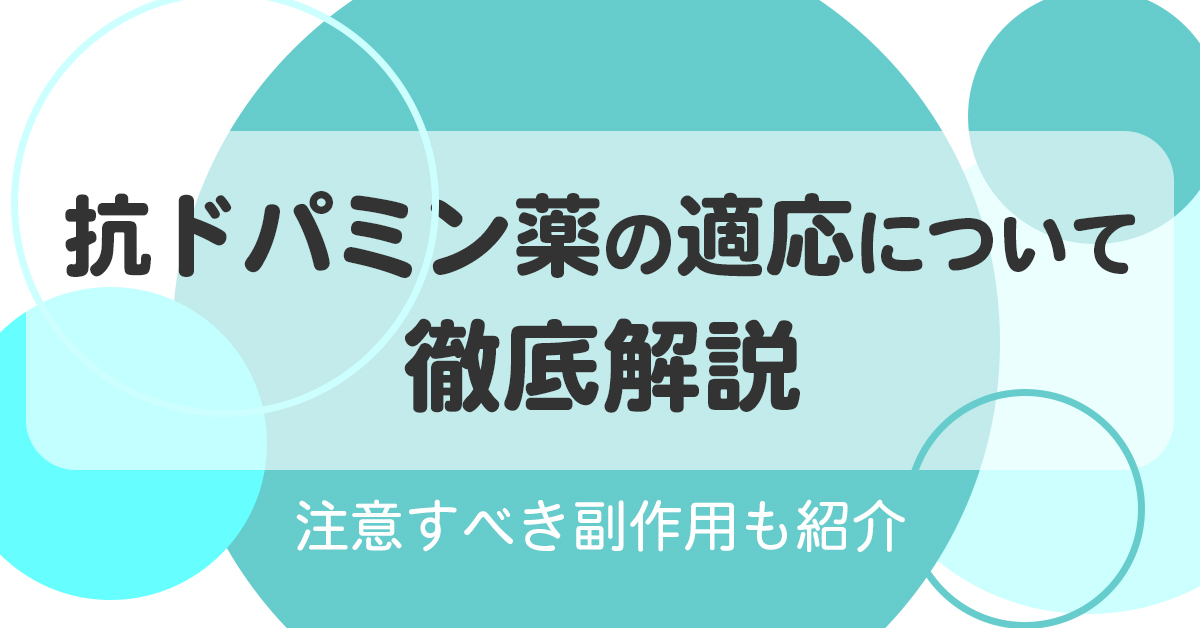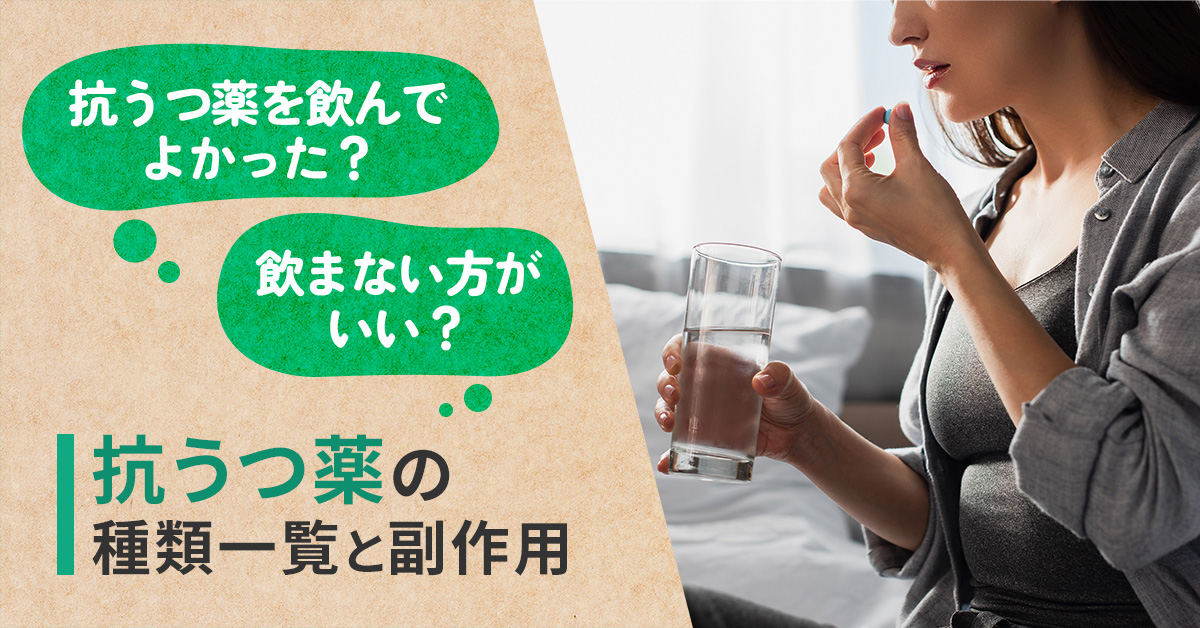抗うつ薬には様々な種類があり、中でも四環系抗うつ薬は即効性が期待できるうつ病の治療薬です。
今回は四環系抗うつ薬の効果や副作用、三環系抗うつ薬の違いについて解説していきます。
他の抗うつ薬についても触れていくので、うつ病の治療薬に不安を感じている方はぜひ参考にしてください。
四環系抗うつ薬とは
四環系抗うつ薬は「よんかんけいこううつやく」と読む、化学構造に4つの環状構造を持つうつ病治療薬です。
四環系抗うつ薬の1つであるマプロチリンが合成されたのは1964年と古く、三環系抗うつ薬よりも副作用のリスクを減らした薬剤として開発された経緯があります。
四環系抗うつ薬の効果
四環系抗うつ薬には脳内の神経伝達物質のバランスを調整して、不安や気分の落ち込み、興味の低下などを改善する効果があります。
うつ病は脳内のノルアドレナリンやセロトニンなどの神経伝達物質がうまく働かなくなり、脳の機能が低下することが原因となってうつ症状が発症する病気です。
四環系抗うつ薬は脳内のノルアドレナリンの再取り込みを阻害して働きを強める作用や、ノルアドレナリンの遊離を促して働きを強める作用によって、脳内の神経伝達物質のバランスを調整する効果があります。
また、四環系抗うつ薬は服用開始から約4日で効果が現れ始める比較的即効性の高い薬剤という特徴もあります。
四環系抗うつ薬の副作用
四環系抗うつ薬は副作用として眠気や頭痛、めまいなどの精神神経症状や、口の渇きや吐き気、便秘などの消化器症状などが現れる可能性があります。
ごく稀に原因不明の高熱や頻脈、発汗、手足の震えなどの症状が出る悪性症候群を引き起こすことがあり、もしこれらの複数の症状が一緒に現れた時にはすぐに医療機関を受診してください。
また、四環系抗うつ薬には依存性はないと言われていますが、薬剤の量を勝手に変えたり、飲み忘れてしまったりした時にめまいや頭痛、吐き気などが起こる離脱症状が現れることがあります。
離脱症状を防ぐためにも「薬が効きにくい」「薬を飲むのをやめたい」と思った時には自己判断で量の増減や中止をせずに、必ず医師に相談するようにしましょう。
四環系抗うつ薬の種類
四環系抗うつ薬には、マプロチリン・ミアンセリン・セチプチリンといった主成分が異なる3種類の薬剤があります。
ここでは四環系抗うつ薬に属するそれぞれの治療薬について解説していきます。
四環系抗うつ薬マプロチリンとは
マプロチリンが主成分の四環系抗うつ薬として、サンファーマのルジオミール錠10mgとルジオミール錠25mg錠が先発薬として販売されており、過去には複数の製薬会社から後発品が販売されていましたが現在は終売となっています。
マプロチリンは第二世代の四環系抗うつ薬に分類される薬剤で作用は穏やかですが、即効性があり、副作用が少ないのが特徴です。
通常成人ではマプロチリン塩酸塩に換算して1日30~75mgを2~3回に分けて服用します。
マプロチリンは服用後、およそ6~12時間で最高血中濃度に達し、45時間ほどで半減します。
マプロチリンの主な副作用には食欲不振や吐き気、起立性低血圧、眠気などがあり、重篤な副作用としててんかん発作や悪性症候群などを引き起こす恐れがあります。
これら副作用の観点からも、過敏症やてんかん、閉塞隅角緑内障、心筋梗塞の回復期にある方、妊婦、新生児などの服用は禁止されているのに加え、他にも複数の病気で注意が必要とされています。
パーキンソン病治療薬のセレギリンやラサギリンなどの薬剤は併用禁止とされ、他の薬剤でも飲み合わせに注意が必要なものが多くあるため、併用する場合には必ず医師に相談するようにしてください。
また、眠気やめまいなどの副作用が出やすくなるので、服用中の飲酒は控えるようにしましょう。
四環系抗うつ薬ミアンセリンとは
ミアンセリンが主成分の四環系抗うつ薬は、先発薬としてオルガノンからテトラミド錠10mgとテトラミド錠30mgが販売されており、後発品はありません。
ミアンセリンは他の多くの抗うつ薬の作用であるセロトニンやノルアドレナリンの再取り込み阻害の働きは持っておらず、ノルアドレナリン放出を抑制するシナプス前α2自己受容体を阻害することでノルアドレナリンの放出を促進させる作用があります。
ミアンセリン塩酸塩に換算して通常成人は1日あたり30mgから服用を始め、最大で1日60mgまで増量できますが、副作用の眠気が強く出るために服用継続が難しいなどの問題も報告されています。
抗うつ効果が現れるまでには2~3週間かかるとされている一方で、せん妄症状に対する効果は約1日で現れるのが特徴です。
ミアンセリンの主な副作用には眠気や口渇、めまいがあり、重篤な副作用として悪性症候群や血圧変動、意識障害などの報告がされていますが、この副作用の眠気を逆手に取って不眠症の改善に使用されることもあります。
ミアンセリンの服用については過敏症の方やMAO阻害剤投与中・投与中止後2週間以内である方、妊婦の使用は禁止とされています。
他にも肝機能障害やてんかん、低カリウム血症などの症状がある方は注意して使用してください。
マプロチリンと同様にパーキンソン病治療薬を始めとする様々な薬剤で飲み合わせ注意とされているので、併用したい薬剤がある時には医師に相談しましょう。
さらにアルコールも副作用のリスクを高める恐れがあるため、薬剤の服用中は控えてください。
四環系抗うつ薬セチプチリンとは
四環系抗うつ薬の1つであるセチプチリンは、先発薬である持田製薬のテシプール錠1mgと、後発品である沢井製薬のセチプチリンマレイン酸塩錠1mg「サワイ」が販売されています。
セチプチリンの用量はセチプチリンマレイン酸塩に換算して通常成人1日あたり3mgから飲み始めて1日最大6mgまで増量することができますが、構造や作用がミアンセリンに似ていることから、やはり眠気などの副作用が出やすいと言われています。
副作用には眠気の他に頭痛、血圧降下などがあり、重篤な副作用には悪性症候群や嚥下困難、頻脈などが報告されているため、MAO阻害剤使用中や使用後2週間以内の方、妊婦は禁忌です。
他の四環系抗うつ薬と同様に飲み合わせに注意が必要な薬剤も多く、飲酒も控えなければなりません。
他の種類の抗うつ薬
四環系抗うつ薬以外にも様々な種類の抗うつ薬がうつ病の治療に使用されています。
ここでは、三環系抗うつ薬・SSRI・SNRI・NaSSAの4種類について解説します。
三環系抗うつ薬
抗うつ薬として最初に開発されたのが三環系抗うつ薬であり、化学構造に3つの環状構造を持つことからこのように呼ばれています。
三環系抗うつ薬は効果が高い反面、副作用も強いという問題があったため、その後、四環系抗うつ薬が開発されました。
三環系抗うつ薬にはアナフラニール、トリプタノール、アモキサン、トフラニール、ノリトレンなどの製品が販売されています。
SSRI
四環系抗うつ薬の降下減退を受けて開発されたのがSSRIです。
SSRIは選択的セロトニン再取り込み阻害薬とも呼ばれる抗うつ薬であり、セロトニンだけを増やすことができる効果を持っています。
副作用は少ないですが、ノルアドレナリンへはほとんど作用しないため、うつ病による意欲向上の作用は弱いという問題点はあります。
SSRIに分類される抗うつ薬としてパキシルやジェイゾロフト、レクサプロ、ルボックスなどの製品が販売されています。
SNRI
SSRIと同じ頃に開発されたのが、セロトニン・ノルアドレナリン再取り込み阻害薬と呼ばれるSNRIです。
SSRIと同様に副作用が少ないうえに、SNRIはセロトニンとノルアドレナリンの両方に作用するため、意欲向上にも効果を示すのが特徴です。
SNRIに分類される抗うつ薬にはサインバルタやイフェクサー、トレドミンなどの製品があり、気分の落ち込みが強い方に使用されるケースが多いです。
NaSSA
NaSSAはノルアドレナリン作動性・特異的セロトニン作動薬と呼ばれる、セロトニンとノルアドレナリンの分泌を促進させる効果がある抗うつ薬です。
SSRIやSNRIのような新しい抗うつ薬の中で最も効果が強い分、強い眠気や食欲増進などの副作用も見られやすい特徴を持ちます。
NaSSAにはレメロンやリフレックスなどの製品があり、不眠症や食欲が低下している方に使用されるケースが多いです。
四環系抗うつ薬は副作用の少ない抗うつ薬
四環系抗うつ薬は化学構造に4つの環状構造を持つうつ病治療薬で、脳内の神経伝達物質のバランスを調整して、不安や気分の落ち込みなどを改善する薬剤です。
服用から4日ほどで効果が現れる即効性や副作用の頻度の少なさが特長の抗うつ薬ですが、一方で他の抗うつ薬と比較すると効果の現れ方は穏やかであると言われています。
四環系抗うつ薬にはマプロチリン・ミアンセリン・セチプチリンの3種類があり、それぞれ作用機序や副作用などに違いがあります。
特にミアンセリンとセチプチリンは副作用の眠気が強いために継続して飲むことが難しいという問題点も報告されています。
三環系抗うつ薬は効果が強い一方で副作用の頻度が高かったため、副作用の少ない四環系抗うつ薬が開発されました。
その後も四環系抗うつ薬の効果の弱さを改善したSSRI・SNRI・NaSSAといった比較的新しい抗うつ薬が開発され、治療薬の選択肢が広がりました。
このように四環系抗うつ薬を始めとするうつ病治療薬には様々な種類があります。
効き目や副作用などを考慮しながら、自分に合った抗うつ薬を見つけていきましょう。