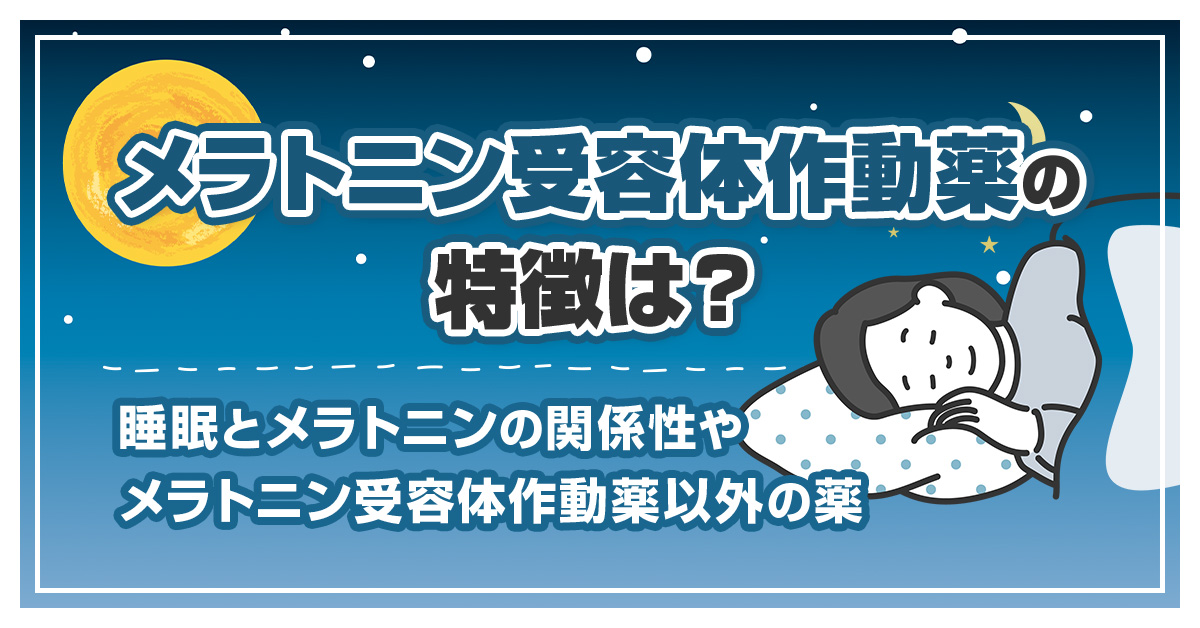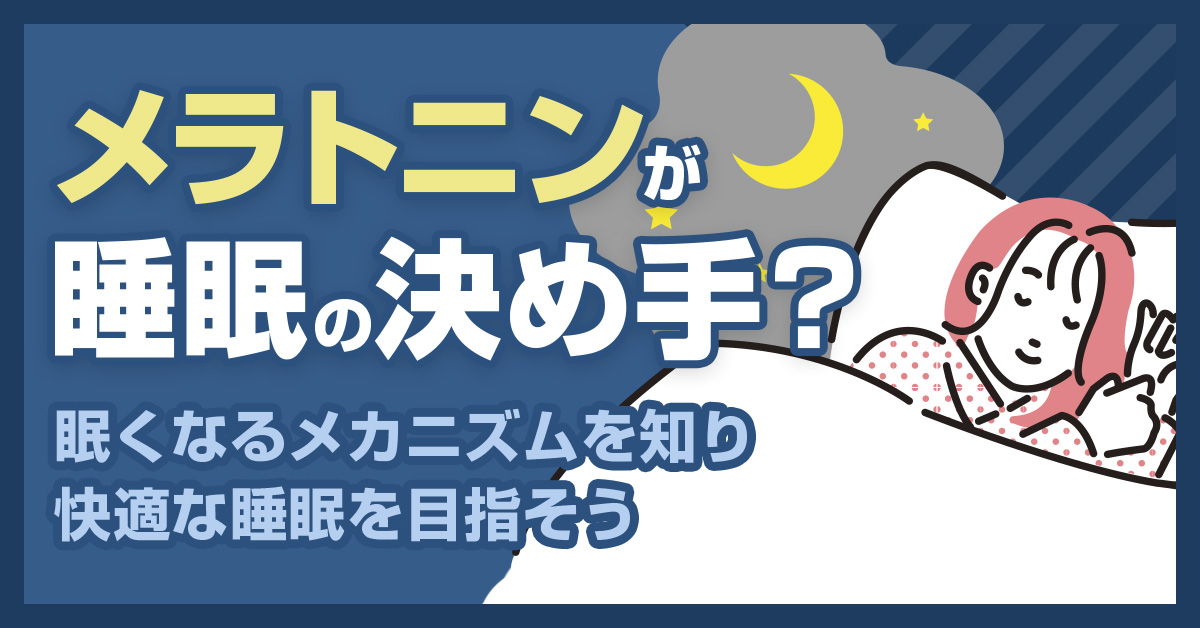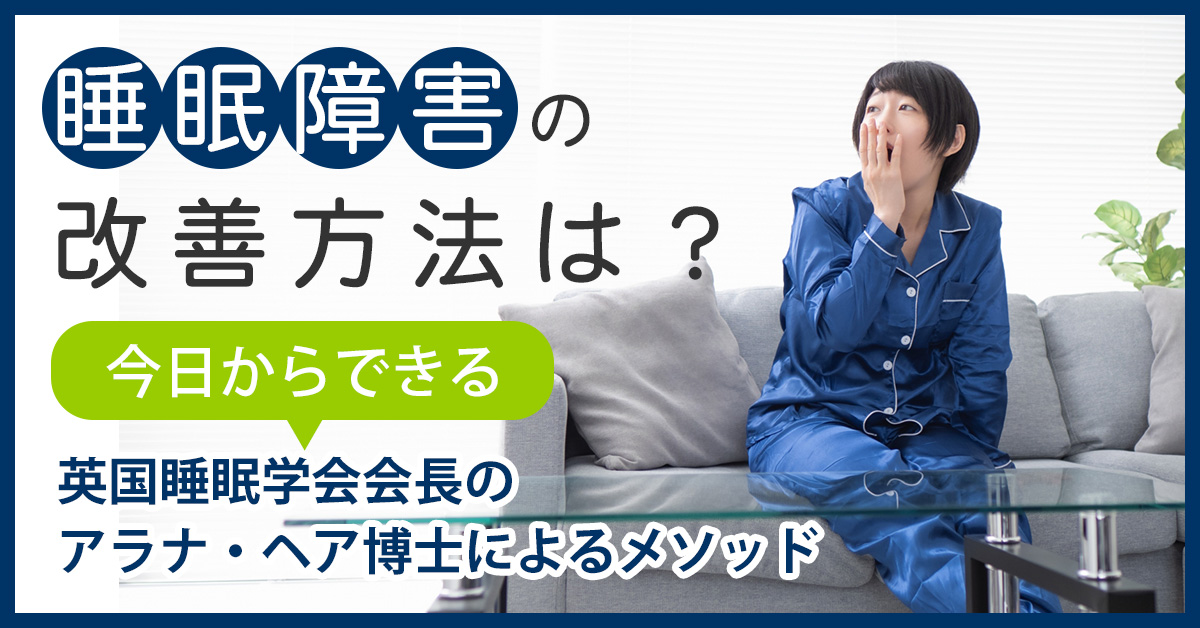なかなか眠れなかったり、夜中に何度も眼が覚めてしまったりするなどの症状を不眠症状と言い、不眠が週3日以上あり、それが3ヵ月以上継続すると治療が必要な不眠症である可能性が考えられます。
今回は不眠症の治療薬であるメラトニン受容体作動薬の作用機序を中心に、不眠症を治療する薬剤の特徴について解説していきます。
睡眠薬がどんなものか分からず不安を感じている方は、本記事を参考にして知識を深めていきましょう。
睡眠とメラトニンの関係性
メラトニン受容体作動薬の特徴を解説する前に、メラトニンによる睡眠のメカニズムについて理解しておきましょう。
メラトニンとは
メラトニンは脳の松果体から分泌される睡眠ホルモンで、体内時計を調整して睡眠と覚醒のリズムを整える作用があります。
起床して日光を浴びることでメラトニンの分泌は抑制されて日中は少ない状態が続きますが、起床後およそ15時間で分泌量が増え、血中濃度が上昇し眠気を誘って睡眠を促します。
また、メラトニンは眠気を誘う作用だけでなく、分泌量を増減することによって交感神経と副交感神経のバランスを取る他、免疫機能を調整する役割もあるとされています。
メラトニンの分泌減少の要因
メラトニンの分泌が減少すると体内時計が乱れ、寝つきが悪くなったり、夜中に何度も目が覚めてしまったりするようになり、慢性化することで不眠症へと繋がっていきます。
メラトニンの分泌量は加齢によって減少し、1~3歳頃をピークに年齢を重ねるにつれて低下していきます。
70歳頃になると、メラトニンの分泌量はピーク時の1/10以下に減少することから、うまく眠れないというような睡眠が不安定になるケースも増えていきます。
また、年齢に関係なく、強い光を浴びることでもメラトニンの分泌量は減少します。
例えば、夜にコンビニエンスストアなどへ出掛けて明るい照明を浴びたり、PCやスマホなどの画面から出るブルーライトを浴びたりすることでも、メラトニンの分泌は低下してしまいます。
不眠症状を引き起こさないためにも夜に強い光を浴びないように心掛け、それでも睡眠が不安定になるようであれば、メラトニン受容体作動薬などの睡眠薬を使用した治療を検討していく必要があると言えます。
メラトニン受容体作動薬の特徴
メラトニン受容体作動薬は「寝つきが悪い」や「夜中に何度も目が覚める」といった睡眠に何らかの問題を抱える不眠症を改善する薬剤です。
ここではメラトニン受容体作動薬について詳しく紹介していきます。
メラトニン受容体作動薬の作用機序
メラトニン受容体作動薬はMT1受容体やMT2受容体といったメラトニン受容体に作用する薬剤で、寝つくまでの時間を短縮することで睡眠時間を確保する効果がある睡眠薬です。
体内に存在する睡眠ホルモンのメラトニンと同じ作用を持っていることから、自然に近い生理的睡眠へと誘導し体内時計を整える働きがあります。
依存性が少なく長期間使用することができる点がメリットですが、薬剤の作用は穏やかで即効性に欠けるため、数週間服用を続けて徐々に睡眠状態を改善させるタイプの睡眠薬です。
メラトニン受容体作動薬の副作用
メラトニン受容体作動薬にはめまいや頭痛などの精神神経系症状や、便秘や吐き気などの消化器症状、乳汁分泌作用を持つプロラクチンが上昇するなどの副作用が現れる可能性があり、人によっては眠気が翌朝まで残ってしまうこともあります。
また、ごく稀にではありますが、蕁麻疹や血管浮腫などのアナフィラキシーを引き起こすケースも報告されています。
これらの副作用の観点から、過敏症や高度肝機能障害の方、フルボキサミンマレイン酸塩投与中の方の使用は禁止であり、精神疾患や統合失調症、うつ病の患者さん、妊婦は相対禁止とされています。
飲み合わせにも注意が必要な薬剤は多く、前述のフルボキサミンマレイン酸塩を始め、キノロン系抗菌薬、マクロライド系抗生物質などの複数の薬剤で影響を与える可能性があることから、他の薬との併用する時には医師や薬剤師に相談するようにしてください。
しかしながら、メラトニン受容体作動薬は自然に近い生理的睡眠へと誘導して体内時計を整える働きをする薬剤であるため依存性が少なく、使用日数の制限がありません。
また、睡眠薬の副作用として現れることがあるせん妄が起こりにくく、認知機能を低下させにくいといった特徴があります。
メラトニン受容体作動薬の商品一覧
メラトニン受容体作動薬はラメルテオンが主成分の治療薬で、先発薬は武田薬品工業のロゼレム錠8mg、後発品として複数の製薬会社からラメルテオンと名前がついた錠剤が販売されています。
先発薬よりも後発品は価格が抑えられているので、長期服用の可能性がある場合には費用の観点も踏まえて薬剤を選択するのも1つの方法です。
メラトニン受容体作動薬以外の睡眠薬の種類
不眠症の治療薬はメラトニン受容体作動薬以外にもいくつか種類があり、作用のメカニズムから大きく2つに分類できます。
脳の機能を抑制する睡眠薬
脳の機能を抑制して入眠させる作用がある睡眠薬で、ベンゾジアゼピン系・非ベンゾジアゼピン系・バルビツール酸系がこれに分類されます。
この3系統の薬剤は、神経細胞の興奮を抑えるGABAの働きを強める働きを持ちますが、バルビツール酸系は中枢神経へも作用してしまう危険性があるために、使用されなくなりました。
現在ではベンゾジアゼピン系と非ベンゾジアゼピン系が使用され、それぞれの薬剤ごとに異なる作用時間や強さを計算して、症状に合ったものを選択していきます。
脳の機能を抑制する睡眠薬は、自然な眠気よりも強い効き目を示す薬剤です。
効果が強い分、副作用のリスクも高くなるので、使い過ぎには注意が必要です。
自然に近い入眠を促す睡眠薬
睡眠薬には自然に近い入眠を促す作用を持つものもあり、これには先ほどまで紹介してきたメラトニン受容体作動薬やオレキシン受容体拮抗薬が該当します。
メラトニン受容体作動薬は体内時計を調整するメラトニンの働きを強めて眠気を誘う作用を持つ薬剤であり、オレキシン受容体拮抗薬は脳を覚醒させるオレキシン受容体を阻害して脳を睡眠状態へ移行させる作用を持つ薬剤です。
どちらも体内の生理的な物質に働きかけるため、依存性が低いメリットがある反面、効果の現れ方には個人差があるというデメリットもあります。
メラトニン製剤と個人輸入
これまでメラトニン受容体作動薬を始めとする様々な睡眠薬を紹介してきましたが、アメリカなどの海外では旅行中の時差ボケ解消やアンチエイジングを目的としたメラトニンが主成分の薬剤やサプリメントが販売・使用されているのはご存知でしょうか。
日本国内では小児の神経発達症による入眠困難の改善にメラトニンが主成分のメラトベルが処方されるだけで、成人の不眠症治療薬にはメラトニンを使用した薬剤がありません。
これは日本国内ではメラトニンの輸入や製造が禁止されているためですが、日本で認可されていない医薬品であっても医師が厚生労働省に薬監証明を取得したり、個人輸入サイトで輸入したりすることは可能です。
お薬ネットでも、メラトニンを主成分とする「メロセット」や「レストファイン」を個人輸入できます。
メロセットの特徴
メラトニンが主成分のメロセットはアリストというバングラデシュの製薬会社の商品で、体内時計を調整して時差ボケや不眠症などを改善する効果がある薬剤です。
経口服用タイプの錠剤で、成人であれば就寝前に1日1回1錠を服用するのが通常です。
副作用には疲労や頭痛、めまいなどの症状が現れる可能性があり、エストロゲン製剤やカフェインと併用すると肝臓でのメラトニン分解を阻害して血中濃度を上昇させます。
副作用のリスクを高めないためにも、他の薬剤と併用する時には医師や薬剤師に相談しましょう。
レストファインの特徴
レストファインはインドの製薬会社ヒーリングファーマが販売している睡眠薬です。
体内に存在するホルモンのメラトニンが主成分であるため、他の種類の睡眠薬よりも自然に近い入眠が期待できるのが特徴です。
1日1回1錠を就寝の3~4時間前に服用しますが、継続して服用する場合は最大13週間までという点には注意してください。
レストファインの副作用には眠気や頭痛、めまいなどの症状が現れる可能性があり、特にアルコールと併用すると作用が強くなりやすいので薬剤の服用中は避けるようにしましょう。
また、眠気やふらつきが起こる恐れがあるため、服用後は乗り物や機械の操作・運転は避けてください。
メラトニン受容体作動薬は自然な眠りを促す特徴がある睡眠薬
睡眠に深く関わるホルモンの1つであるメラトニンの分泌量が増えることで睡眠を促しますが、夜間に強い光を浴びたり、加齢によって分泌量が減少したりすることによって、なかなか寝つけない・夜中に何度も目が覚めてしまうなどの不眠症状を引き起こすことがあります。
メラトニン受容体作動薬はMT1受容体やMT2受容体といったメラトニン受容体に作用して、寝つくまでの時間を短縮する効果を持つ睡眠薬です。
睡眠薬は大きく分けて、脳の機能を抑制する作用を持つ薬剤と自然に近い入眠を促す薬剤の2種類があり、メラトニン受容体作動薬は後者に分類されています。
メラトニン受容体作動薬は効果が穏やかなため、改善までに時間がかかったり、効果の現れ方に個人差があったりしますが、依存性が少なく比較的安全性の高い薬剤と言えるでしょう。
また、海外では睡眠ホルモンであるメラトニンが配合された薬剤が使用されており、これら睡眠薬は個人輸入代行で購入することが可能です。
お薬ネットでも、メラトニンを主成分とする「メロセット」や「レストファイン」を取り扱っておりますので、不眠症でお悩みの方はお気軽にお問い合わせください。