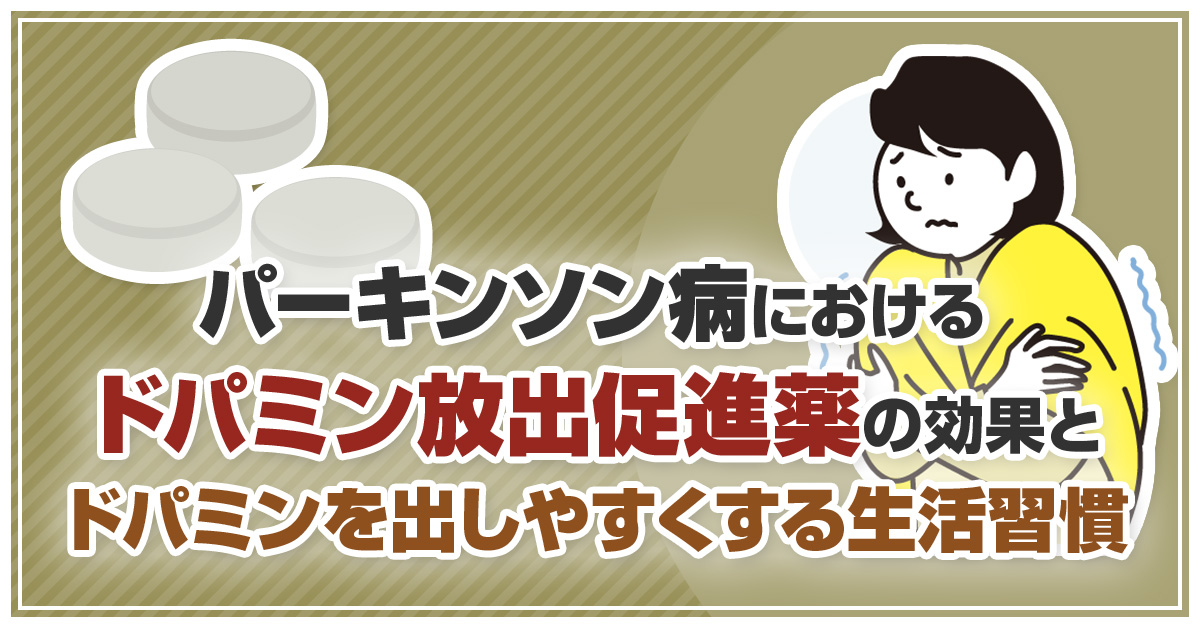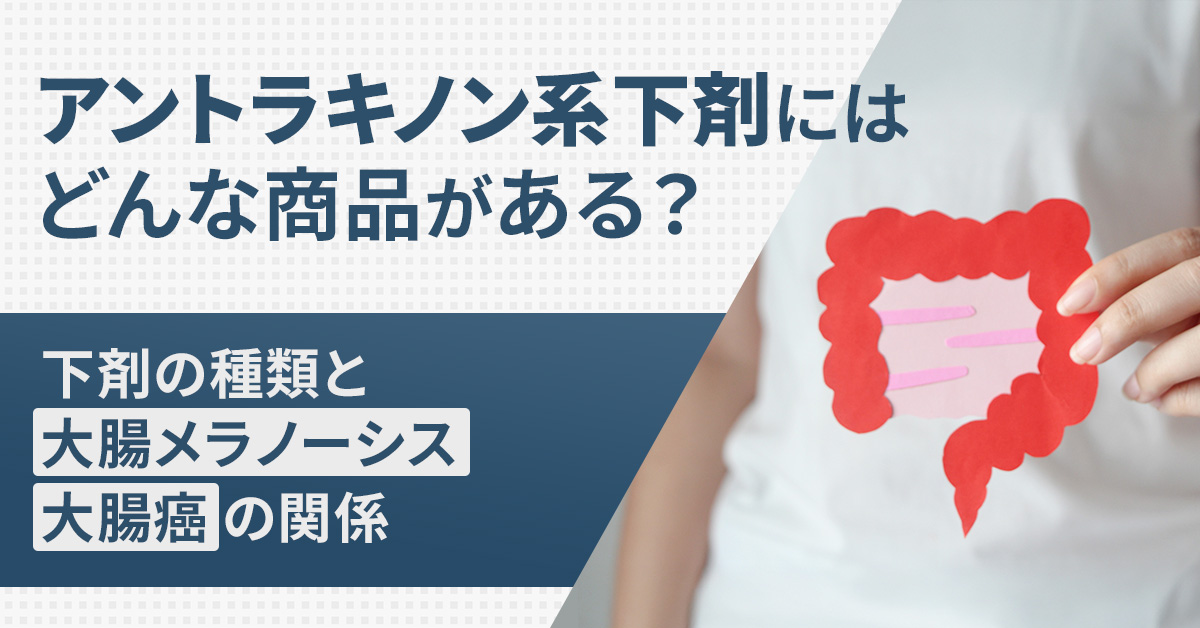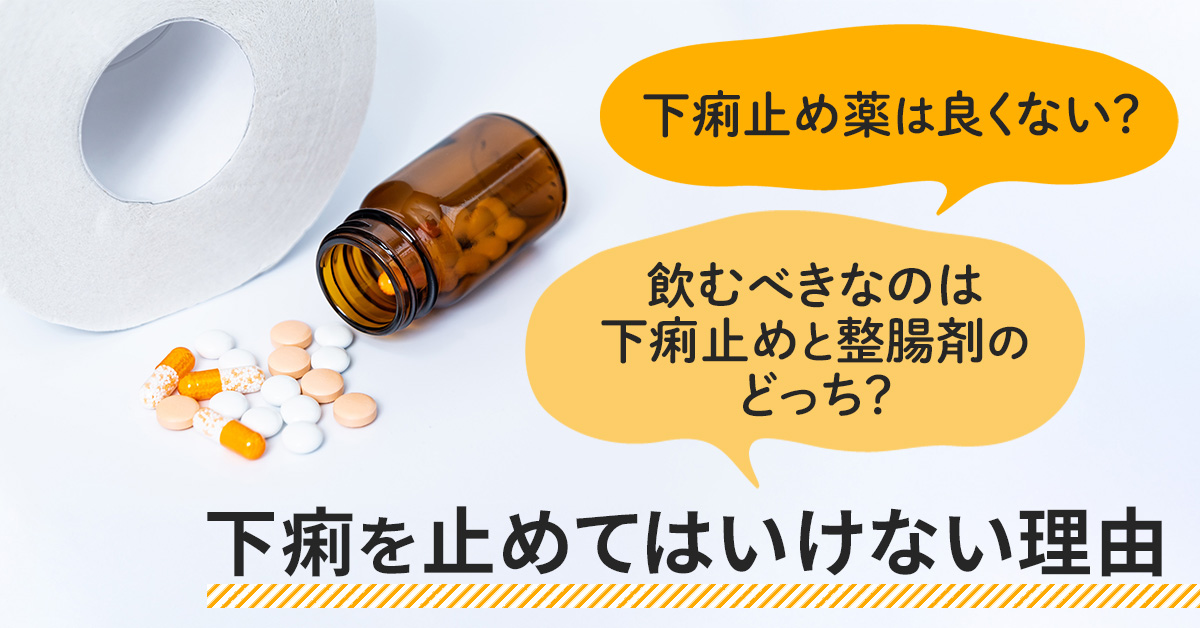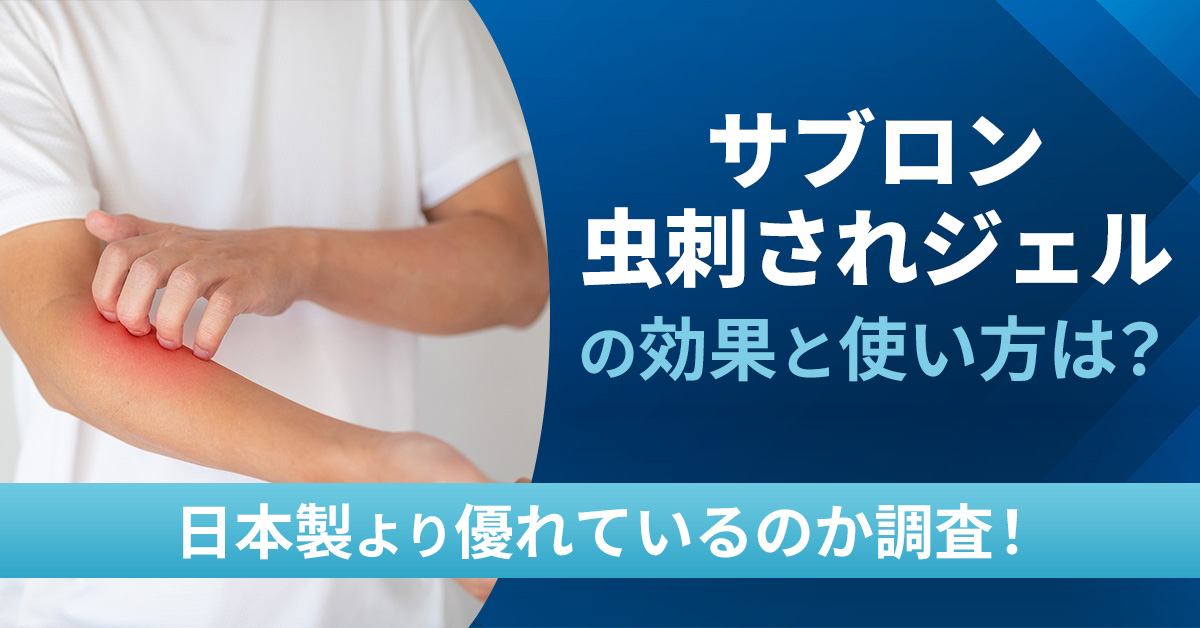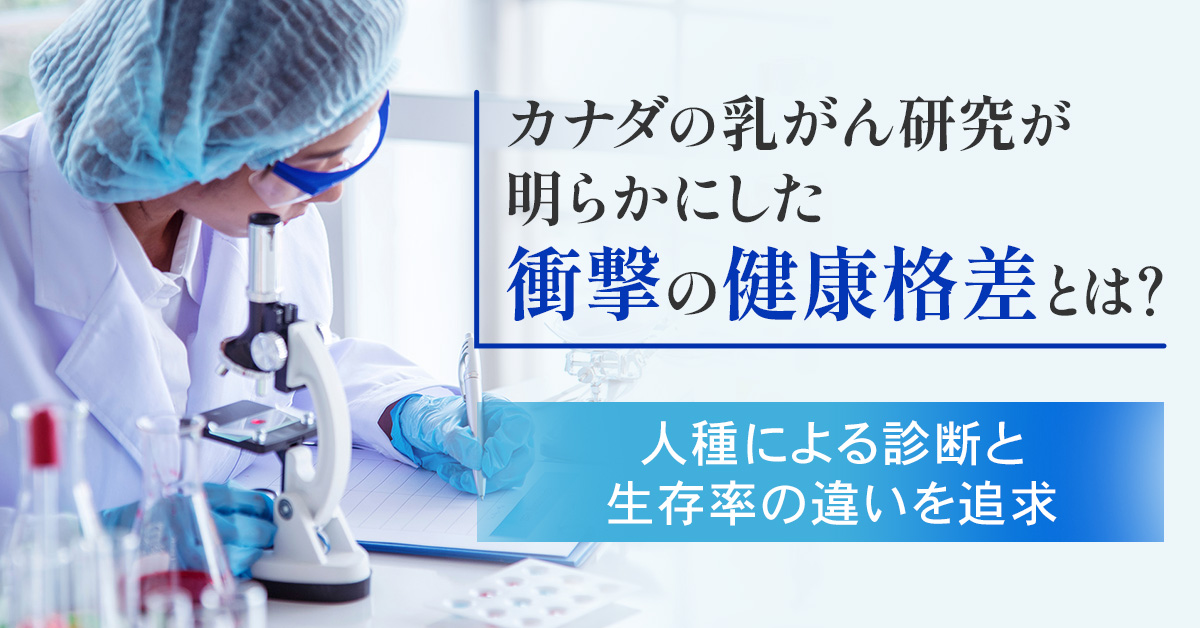パーキンソン病におけるドパミン放出促進薬の効果とドパミンを出しやすくする生活習慣
ドパミン放出促進薬は主にパーキンソン病などの脳内のドパミンに関連する病気の治療に使用される薬剤ですが、その作用機序や効果などを知らない方も多いのかもしれません。
そこで今回はドパミン放出促進薬によるパーキンソン病の治療について解説し、薬剤の種類や副作用を紹介していきます。
また、ドパミン促進薬以外の治療薬や、ドパミンを出しやすくする生活習慣も紹介しますので、不調でお悩みの方はぜひ参考にしてください。
パーキンソン病とドパミン放出促進薬
ドパミン放出促進薬は脳内のドパミンを増やす働きを持つ薬剤で、主にパーキンソン病の治療に使用されます。
ここでは、パーキンソン病やドパミン放出促進薬の効果・副作用について理解していきましょう。
パーキンソン病とは
パーキンソン病は指定難病となっている脳の病気の1つで、脳内のドパミンが減少することで発症します。
パーキンソン病の主な症状は、スムーズに動けなくなったり、体のバランスが取りにくくなったりして歩行が困難になるすくみ足や、身体のふるえなどです。
さらにこれら運動症状だけでなく、低血圧や認知障害、嗅覚障害などの非運動症状が見られることもあります。
パーキンソン病と診断されると薬剤による治療が始まり、治療薬としてドパミン放出促進薬が選択されることがあります。
ドパミン放出促進薬の種類
ドパミン放出促進薬はアマンタジン塩酸塩を主成分とした薬剤で、先発薬はサンファーマのシンメトレルです。
シンメトレルには、錠剤のシンメトレル錠50mgやシンメトレル錠100mg、散剤のシンメトレル顆粒10%があります。
ドパミン放出促進薬の後発品はアマンタジン塩酸塩という名前で複数の製薬会社から商品が販売されています。
一例を挙げると、全星薬品工業のアマンタジン塩酸塩錠50mg「ZE」やアマンタジン塩酸塩錠100mg「ZE」、沢井製薬のアマンタジン塩酸塩錠50mg「サワイ」やアマンタジン塩酸塩錠100mg「サワイ」、アマンタジン塩酸塩顆粒10%「サワイ」などがあります。
ドパミン放出促進薬は薬局やドラッグストアで購入できるような市販薬はなく、医師の診断によって出される処方薬しか取り扱いがありません。
ドパミン放出促進薬の効果
ドパミン放出促進薬は神経細胞に蓄えられているドパミンを脳内に放出して増加させることで、ドパミンの不足が原因で起こるパーキンソン病の症状を改善させる効果があります。
また、ドパミン放出促進薬はノルアドレナリンやセロトニンなどの神経伝達物質にも影響を与えることから、脳梗塞後遺症の意欲低下や自発性低下を改善してやる気を出す効果もあります。
さらにA型インフルエンザウイルスの増殖を阻害する効果も持っているため、ドパミン放出促進薬はインフルエンザの治療にも使用されるケースもあります。
ドパミン放出促進薬の副作用
様々な効果を持つドパミン放出促進薬も、幻覚や妄想、眠気などの精神神経系症状、便秘や食欲不振、下痢などの消化器症状などの副作用が現れる可能性があり、ごく稀に悪性症候群を引き起こす恐れがあります。
万一、高熱が出たり、脈が速くなったりするなどの症状が見られた時には速やかに医療機関を受診してください。
また、重篤な副作用を引き起こさないためにも、透析中の方や妊婦はドパミン放出促進薬の使用禁止、精神障害を抱えていたり、中枢神経系に作用する薬剤を服用していたりする方は相対禁止となっています。
他の薬剤との併用にも注意が必要で、抗パーキンソン薬やレボドパ、抗コリン薬を始めとする複数の薬剤に影響を与えるため、幻覚や睡眠障害などの副作用のリスクが高まります。
加えて、ヒドロクロロチアジドやトリクロルメチアジドなどは錯乱、ヒドロクロロチアジドやカリウム保持性利尿剤は失調を引き起こす可能性があるので、他の薬剤と併用する時には医師や薬剤師に相談するようにしてください。
ドパミン放出促進薬以外のパーキンソン病治療薬
パーキンソン病ではドパミン放出促進薬以外の薬剤で治療することもあります。
パーキンソン病の治療に使われるドパミンを増やす薬剤には次のようなものがあります。
レボドパ
レボドパは脳内に移行してドパミンに変化し、脳内のドパミンを補充してパーキンソン病の症状を改善させる薬剤です。
パーキンソン病の第一選択薬の1つとされており、効果が高く、特に運動症状の改善に有効です。
その一方で、長時間使用すると自分では止めることのできないおかしな動作が現れるジスキネジアを発症する恐れがあります。
繰り返し唇をすぼめたり、勝手に手や足が動いてしまったりする症状が現れた時には、速やかに医療機関を受診して医師の指示を仰ぎましょう。
ドパミンアゴニスト
別名ドパミン受容体作動薬や、ドパミン作動薬とも呼ばれることのあるドパミンアゴニストは、脳内のドパミン受容体を刺激してパーキンソン病を治療する薬剤です。
主にパーキンソン病による手足の震えなどを改善する効果があり、薬剤の種類によってはむずむず脚症候群に使用することもあります。
効果の持続時間が長いことから単体での使用だけではなく、作用時間の短いレボドパと併用することもあります。
作用は緩やかであり、長期服用による弊害も起きにくいため、初期の治療ではドパミンアゴニストの使用が推奨されています。
MAO-B阻害薬
「マオビー阻害薬」と呼ばれるMAO-B阻害薬は、脳内のMAO-Bを阻害してシナプス間でドパミンが減少するのを防ぐ作用と、ドパミンがシナプスへ再吸収されるのを防ぐ作用によって、パーキンソン病の症状を改善させるとされています。
MAO-B阻害薬もレボドパと併用されることがありますが、効果が上がる反面、ジスキネジアのリスクが上がる可能性もあるので注意が必要です。
COMT阻害薬
COMT阻害薬は「コムト阻害薬」と呼ばれ、COMTを阻害してレボドパが分解されるのを防ぎ、効き目を長持ちさせます。
これにより、パーキンソン病の症状である手足の震えや筋肉のこわばりを改善させるとされ、主にレボドパ・カルビドパ配合薬やレボドパ・ベンセラジド配合薬と併用して使用します。
頻度は稀ですが、突発的な眠気をもよおす副作用が見られることがあるため、機械や乗り物の運転・操作は控えるようにしてください。
抗コリン薬
抗コリン薬はドパミンと拮抗し合うアセチルコリンの働きを抑制する作用があり、これによりドパミンの作用を強めて、パーキンソン病の症状を改善させます。
抗コリン薬は特に震えが主な症状として起きている方や、若年性パーキンソン病の方に有効な薬剤とされています。
また、抗精神病薬などによってドパミンが抑制されることで起こるパーキンソニズムというパーキンソン病と似ている症状の改善にも使用されます。
ドパミンを出しやすくする生活習慣
ドパミン放出促進薬を始めとする薬剤を使ってパーキンソン病の治療を行いますが、日常生活でもドパミンを増やすことは可能です。
薬剤の治療の補助的な役割としてドパミンを出しやすくする次のような生活習慣を取り入れてみてはいかがでしょうか。
チロシンとビタミンB6を積極的に取り入れる
ドパミンを生成するには前駆体であるチロシンと、チロシンをドパミンに変換させるビタミンB6が必要です。
この2つの栄養素を意識して摂取することで、体内のドパミン生成を促すことができます。
チロシンが多く含まれる食材には、桜えびやチーズ、しらす、豚肉、鶏肉、大豆製品などがあります。
ビタミンB6が多く含まれる食材は、カツオやマグロなどの赤身の魚やヒレ肉、ささみ、バナナ、パプリカ、サツマイモなどです。
どちらも身近な食材が多いので、食事やおやつなどに取り入れてみてはいかがでしょうか。
運動と睡眠を心掛ける
有酸素運動は多くの酸素を体内に取り込んで心臓や肺の働きを活発にし、血液の循環を促して脳内の血液量を増やすことからドパミンの分泌に良い影響を与えます。
さらに筋トレによって成長ホルモンの分泌が促されることで、ドパミンを出しやすくするとされています。
また、質の良い睡眠では脳内のドパミンが再合成されるとも言われています。
睡眠のリズムを整えるためにも、同じ時間に起床・睡眠をするように心掛けましょう。
日光を浴びる
日光を浴びることで体内時計が調整されて、ドパミンの原料となるセロトニンの分泌が増えます。
つまり、適度な日光を浴びることはドパミンを増やすことに繋がるのです。
春や夏であれば1日約15分、秋や冬であれば1日約30分を目安に日光浴をするとよいでしょう。
ただし、強い紫外線や長時間の日光浴は逆効果になるので避け、日差しが強い時には直射日光ではなく、木陰に約15分いるだけで十分とされています。
ドパミン放出促進薬は主にパーキンソン病の治療に使用される薬
ドパミン放出促進薬はアマンタジン塩酸塩を主成分とした薬剤で、脳内のドパミンが減少することで発症するパーキンソン病の治療に使用されています。
ドパミン放出促進薬を使用することで脳内のドパミン量が増加して、パーキンソン病の症状である震えやすくみ足などの運動症状を改善できるとされています。
ドパミン放出促進薬以外にもドパミン量を増加させる様々なパーキンソン病治療薬があり、特にレボドパは第一選択薬として使用されています。
また、日常生活でもドパミン量を増やすことは可能なので、治療薬の補助的な手段として取り入れてみてはいかがでしょうか。