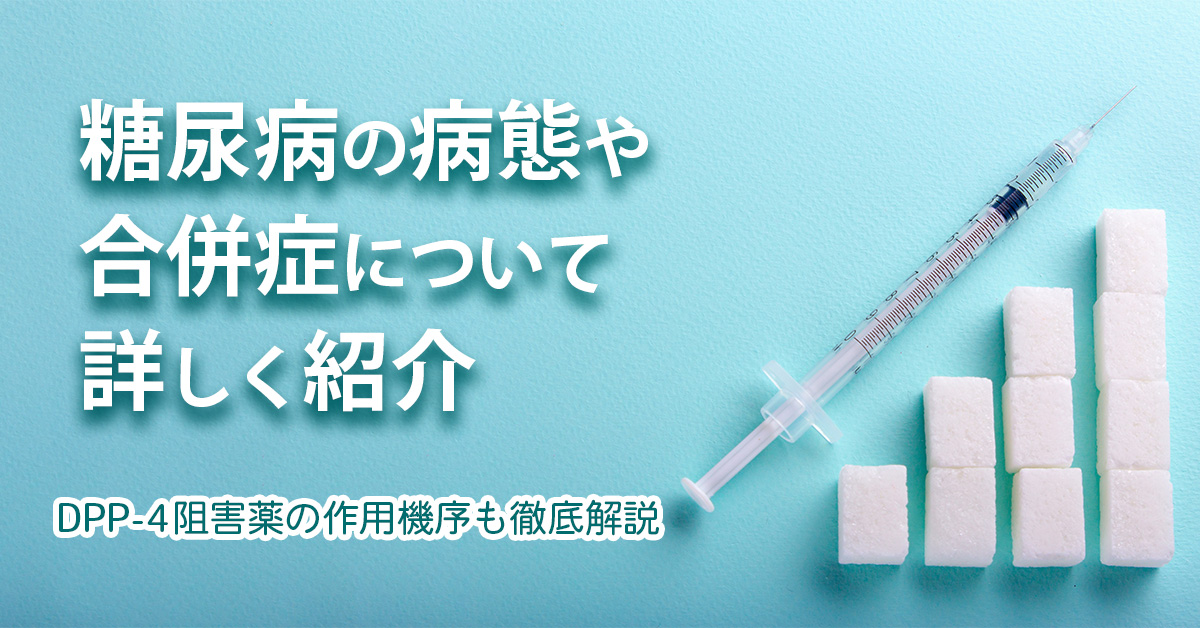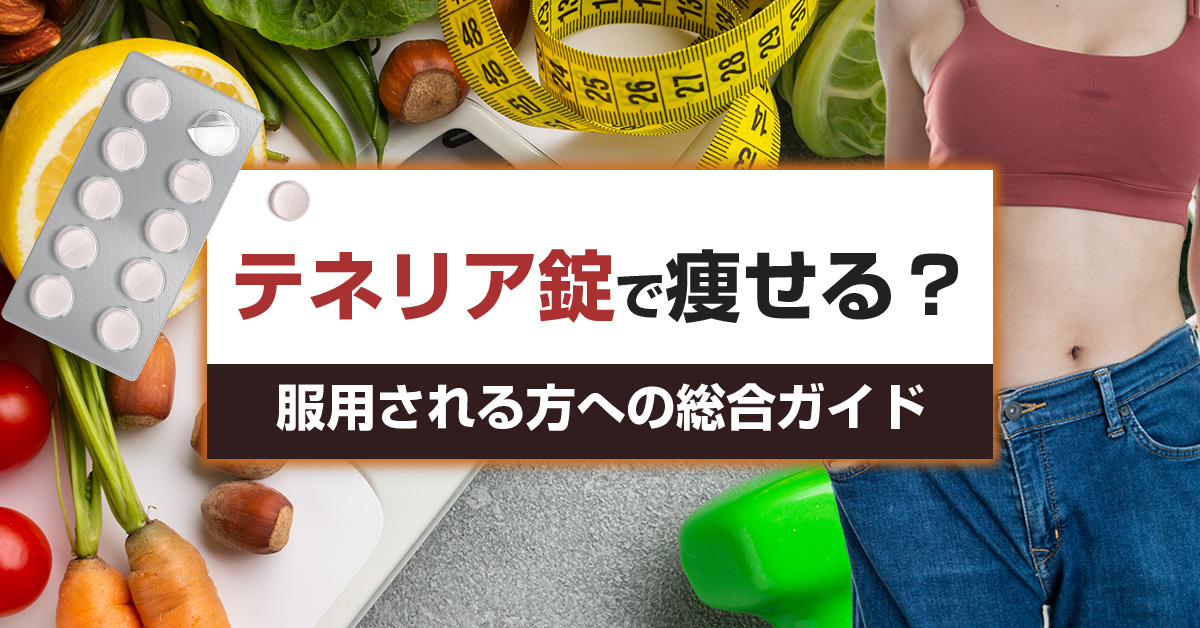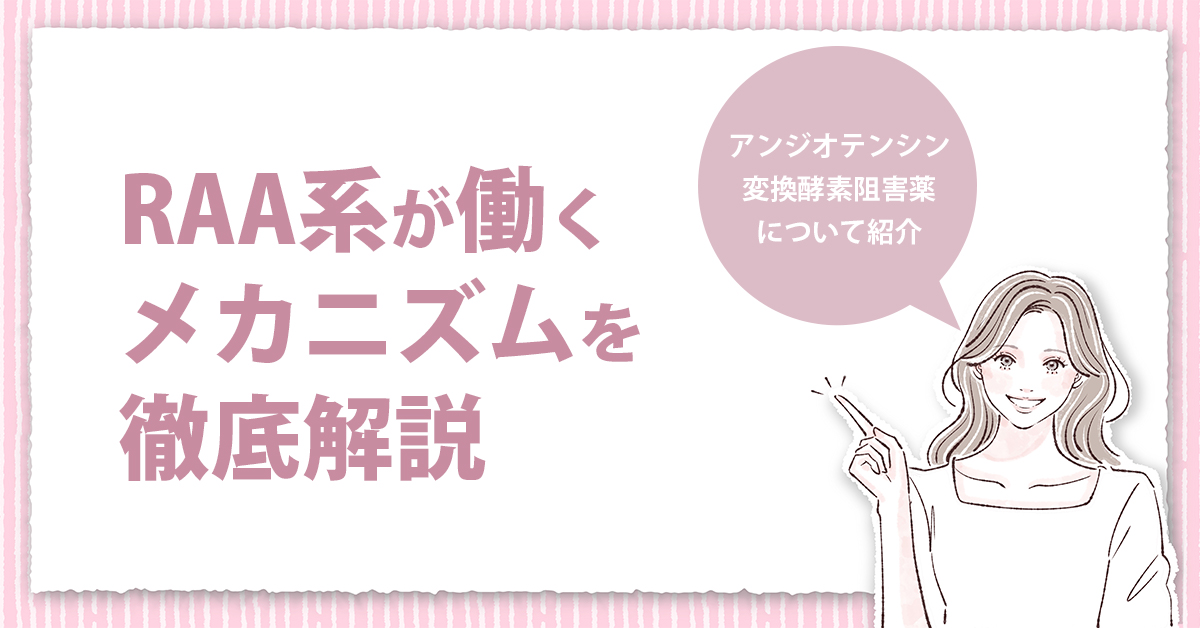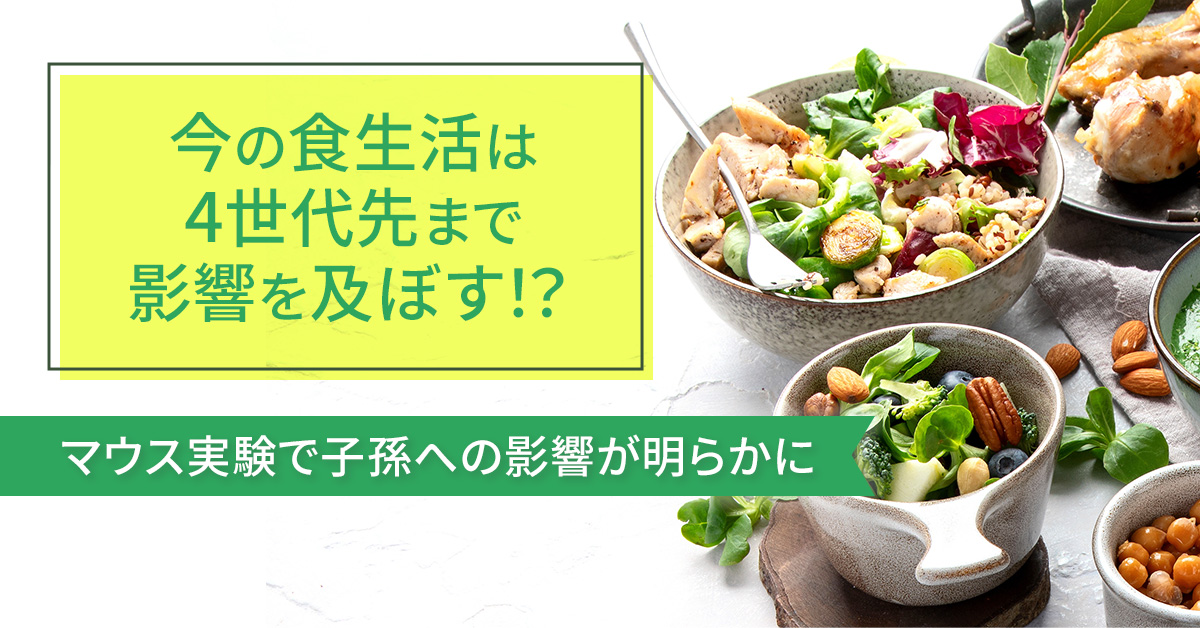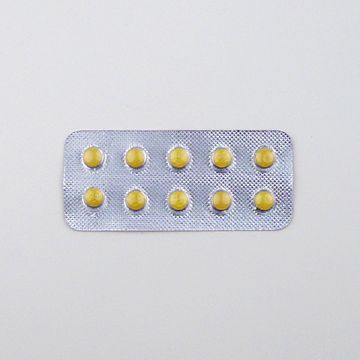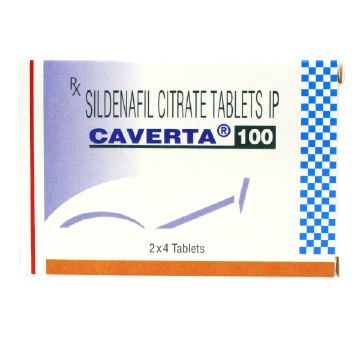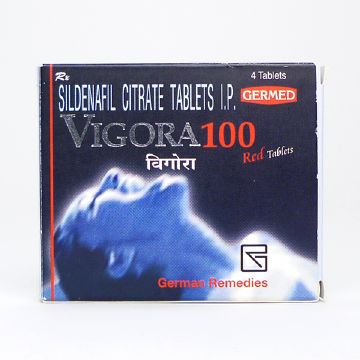「糖尿病ってどんな疾患なの?」
「DPP-4阻害薬の作用機序は?」
このような疑問を持っている人は少なくないのではないでしょうか。
本記事では、糖尿病の病態や合併症、1型糖尿病と2型糖尿病の違いについて詳しく紹介。
糖尿病に対する治療薬である、DPP-4阻害薬の作用機序も徹底解説します。
本記事を読めば、糖尿病やDPP-4阻害薬について理解を深められます。
興味がある人はぜひ最後までご覧ください。
糖代謝の概要
炭水化物などに多く含まれている栄養素であるグルコース(ブドウ糖)は、生体にとって最も重要なエネルギー源です。
全身の細胞がエネルギーを必要とすると、血中から取り込まれます。
過剰な糖が血中に存在する時は、ホルモンの作用によってグリコーゲンや中性脂肪に変換されます。
グリコーゲンは肝臓や筋肉、中性脂肪は脂肪組織に貯蔵され、必要となった時に再びグルコースとして供給されるのです。
血糖調節に関わるホルモン
血糖調節に関わる主なホルモンについて、血糖を上げる or 下げるに分けて見ていきましょう。
①血糖を上げるホルモン
血糖を上げるホルモンとして以下が挙げられます。
| ホルモン名 | 分泌器官 |
|---|---|
| グルカゴン | ランゲルハンス島α細胞(膵臓) |
| カテコールアミン | 交感神経、副腎髄質 |
| コルチゾール | 副腎皮質 |
| 成長ホルモン | 下垂体前葉 |
これらのホルモンは、グリコーゲンの分解や糖新生を促進し、血糖を上げる方向に働きます。
(※糖新生…アミノ酸や乳酸などを原料として、体内でグルコースを合成するプロセス)
②血糖を下げるホルモン
血糖を下げるホルモンは、膵臓のランゲルハンス島β細胞から分泌される、インスリンただ一つのみです。
主に以下の作用を有しています。
- 筋肉/脂肪組織における糖の取り込み促進
- 肝臓/筋肉でのグリコーゲンの合成促進
- 肝臓での糖新生抑制
これらの作用を通じて、血糖を下げる方向に働くのです。
糖尿病とは?
糖尿病は、インスリンが分泌されなくなる(インスリン分泌障害)、もしくはインスリンが効きにくくなる(インスリン抵抗性亢進)ために起こる疾患です。
インスリンの作用不足により、細胞に糖を正常に取り込めなくなり、慢性的な高血糖状態に陥ります。
糖尿病でみられる主な症状は以下の通りです。
- 口渇
- 多飲
- 多尿
- 体重減少
その他、高血糖による血管障害などが原因で様々な合併症が生じます。
厚生労働省が3年ごとに行っている「患者調査」によると、2020年時点で糖尿病の治療を受けている患者総数は、579万1000人(男性338万5000人/女性240万6000人)です。
糖尿病の可能性が高いものの、診断・治療を受けていない人も多くいると考えられるため、糖尿病は非常に身近な疾患の一つであると言えるでしょう。
糖尿病合併症
糖尿病が進行すると、重篤ないくつかの合併症を引き起こします。
代表的なものは以下の通りです。
- 糖尿病神経障害
- 糖尿病足病変
- 糖尿病網膜症
- 糖尿病腎症
- 虚血性心疾患/脳梗塞
- 糖尿病昏睡
それぞれについて見ていきましょう。
①糖尿病神経障害
糖尿病神経障害は三大合併症の一つであり、最も早期に出現する症状です。
慢性的に続く高血糖により、神経細胞の代謝障害や血管障害が起こり、神経障害に繋がると考えられています。
具体的な症状としては、夜間に増悪する痺れや痛みから始まり、進行すると感覚低下がみられるケースが多いです。
自律神経障害により、起立性低血圧や脈拍の異常、排尿障害や下痢/便秘が生じる場合もあります。
②糖尿病足病変
糖尿病足病変は、神経障害と血流障害がある箇所に、外傷や感染症が生じるために発生します。
爪白癬(爪に生じる水虫)や乾燥、変形や潰瘍(皮膚や粘膜に発生する欠損)など多彩な症状をきたし、進行すると足の切断が必要となる恐れもあります。
QOLを著しく損なってしまうため、早期発見・治療が重要です。
③糖尿病網膜症
糖尿病網膜症は三大合併症の一つであり、患者さんの約35%に合併します。
糖尿病の罹患後、数~20年かけて発症しますが、初期には自覚症状がほとんどないケースが多いです。
そのため、以下のような症状が生じた際には、網膜症がかなり進行している可能性があります。
- 飛蚊症
- 視力低下
- 視野障害
- 失明
糖尿病と診断されたら、自覚症状がなくても定期的に眼科を受診する必要があります。
④糖尿病腎症
糖尿病腎症は三大合併症の一つであり、糖尿病の罹患後、5~10年以上経過した人にみられます。
初期には自覚症状がありませんが、進行すると以下のような症状がみられます。
- 蛋白尿
- 浮腫
- 貧血
- 全身倦怠感
最終的には末期腎不全に至り、透析療法が必要となります。
実際、日本における透析導入の原因疾患の第1位が、糖尿病腎症です。
⑤虚血性心疾患/脳梗塞
糖尿病による血管障害は、心臓に酸素などを供給している冠動脈や、脳を流れている血管にも及びます。
健常者と比べて動脈硬化が生じやすくなり、虚血性心疾患や脳梗塞などの発症リスクを高めてしまうのです。
虚血性心疾患には、冠動脈が狭窄する狭心症と、冠動脈が閉塞する心筋梗塞が該当します。
狭心症の主な症状は前胸部の絞扼感、心筋梗塞の主な症状は前胸部の強い痛み・悪心・呼吸困難などです。
脳梗塞では、血管が詰まった場所によって様々な症状がみられます。
具体的には、片側の麻痺や感覚障害、構音障害(喋りにくい)などです。
⑥糖尿病昏睡
ここまでは、慢性的な糖尿病合併症について見てきました。
しかし、急性の糖尿病合併症として、糖尿病昏睡を発症する恐れもあります。
糖尿病昏睡とは、急激に高血糖になることで意識障害や昏睡状態に陥り、時には致命的となる病態です。
原因としては、治療の不適切な中断や感染症、ストレスや高度の脱水などが挙げられます。
1型糖尿病と2型糖尿病の比較
糖尿病は成因により、以下の4タイプに分類されます。
- 1型糖尿病
- 2型糖尿病
- 特定の疾患による糖尿病
- 妊娠糖尿病
ここでは、主要なタイプである1型糖尿病と2型糖尿病を比較していきましょう。
| 1型糖尿病 | 2型糖尿病 | |
|---|---|---|
| 割合 | およそ5~10% | 90%以上 |
| 患者さんの特徴 | ・主に小児~思春期 ・正常~やせ体型 |
・主に中高年 ・正常~肥満体型 |
| 成因 | ・自己免疫 ・遺伝因子など |
・遺伝因子 ・生活習慣 |
| 家族歴 | 少ない | 高頻度 |
| インスリン分泌障害 | 高度 | 軽度~中等度 |
| インスリン抵抗性亢進 | なし | あり(程度は様々) |
| 糖代謝異常の進行 | 改善することなく進行する | 改善することもある |
| 症状の進行 | 急激に症状が出現しやすい | 緩徐に進行しやすい |
| インスリンの必要性 | ・初期は非依存性のこともあるが、最終的に依存性となる | ・非依存性が多いが、重症化すれば依存性となる |
糖尿病の治療
糖尿病の治療は、インスリン依存状態or非依存状態で異なります。
| 定義 | 治療法 | |
|---|---|---|
| インスリン依存状態 | インスリンがほぼ完全に分泌されなくなり、インスリン製剤の投与が不可欠である状態 | ・インスリン注射 ・食事療法 ・運動療法 |
| インスリン非依存状態 | インスリンを多少は分泌可能であり、インスリン製剤の投与が不可欠ではない状態 | ・食事療法 ・運動療法 ・薬物療法(血糖値がコントロール不良な場合) ・インスリン注射(血糖値がコントロール不良な場合) |
糖尿病に対して用いられる薬剤には多くの種類があります。
糖尿病に対して効果を発揮するメカニズムにより、以下のように分類されます。
| 薬剤 | 主なメカニズム |
|---|---|
| ビグアナイド薬 | 肝臓での糖新生の抑制 |
| チアゾリジン薬 | 骨格筋・肝臓でのインスリン抵抗性改善 |
| スルホニル尿素薬 | インスリン分泌の促進 |
| グリニド薬 | 速やかなインスリン分泌の促進による食後高血糖の改善 |
| DPP-4阻害薬 | 血糖依存性のインスリン分泌促進、グルカゴン分泌抑制 |
| α-グルコシダーゼ阻害薬 | 炭水化物の吸収遅延による食後高血糖の改善 |
| SGLT2阻害薬 | 尿中へのブドウ糖排泄促進 |
ここからは、DPP-4阻害薬について解説していきます。
DPP-4阻害薬の作用機序
DPP-4阻害薬の作用機序を理解するためには、「インクレチン」という物質について知る必要があります。
インクレチンとはどんな物質であるのか、そしてDPP-4阻害薬はどのようにして糖尿病に対する治療効果を発揮するのか、見ていきましょう。
①インクレチンとは?
インクレチンとは、食事の摂取に伴って消化管から分泌され、インスリンの分泌を促進するホルモンの総称です。
これまでに、以下の2種類のインクレチンが発見されています。
| インクレチン | GIP | GLP-1 |
|---|---|---|
| 分泌する細胞 | 上部小腸のK細胞 | 下部小腸のL細胞 |
| β細胞に対する作用 | ・グルコース濃度依存性にインスリン分泌を促進 ・β細胞の増殖促進 ・β細胞のアポトーシス(細胞死)抑制 |
|
| α細胞に対する作用 | ・グルカゴン分泌促進 | ・グルカゴン分泌抑制 |
| 膵臓以外への作用 | ・脂肪細胞…脂肪蓄積 ・骨…カルシウム蓄積 |
・脳…食欲抑制 ・胃…胃排泄抑制 ・心臓…心機能改善 ・肝臓…グルコース取り込み増加、グルコース産生抑制 |
グルコース濃度依存性にインスリン分泌を促進するとは、「グルコース濃度が高い時にはインスリン分泌を促進し、低い時には促進しない」という意味です。
また、2型糖尿病の患者さんでは、GIPに対する反応性が低下しています。
そのため、GLP-1の作用の方が重要であると考えられています。
②DPP-4阻害薬とは?
インスリンの分泌を促進するという、非常に重要な役割を果たしているインクレチンですが、残念なことに「DPP-4」という酵素により、数分以内に分解・不活性化されてしまいます。
そのため、実際に生体に作用しているのは、産生されたインクレチンの一部だけなのです。
そこで開発されたのが、DPP-4の作用を阻害する薬剤、すなわちDPP-4阻害薬です。
DPP-4阻害薬を投与すると、分解・不活性化されるインクレチンが減り、インスリンの分泌が十分に促進されます。
その結果、糖尿病に対する治療効果を発揮できるのです。
まとめ:DPP-4阻害薬で糖尿病を治療しよう
糖尿病とは、インスリンの分泌障害や抵抗性亢進を原因として、血糖値が慢性的に高くなる疾患です。
様々な合併症を引き起こし、QOLを著しく低下させたり、時には致命的となったりします。
糖尿病は1型糖尿病と2型糖尿病に分類され、それぞれ病態が大きく異なります。
薬物療法は、基本的に2型糖尿病に対して行われますが、その時一つの選択肢となるのがDPP-4阻害薬です。
作用機序を理解して、DPP-4阻害薬で糖尿病を治療しましょう。