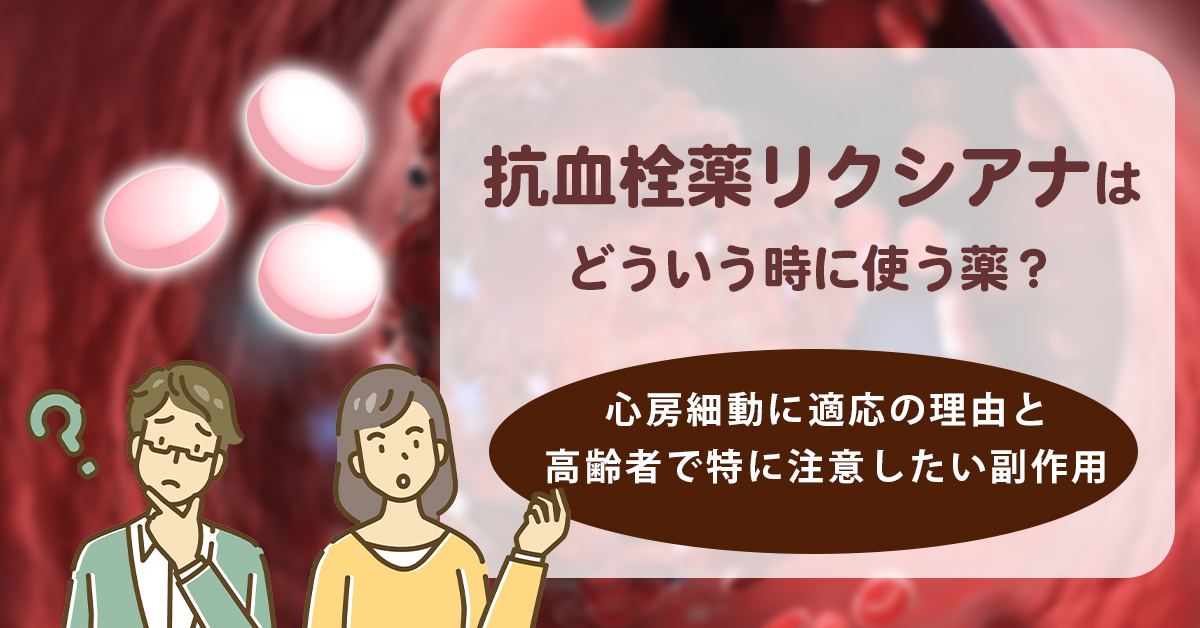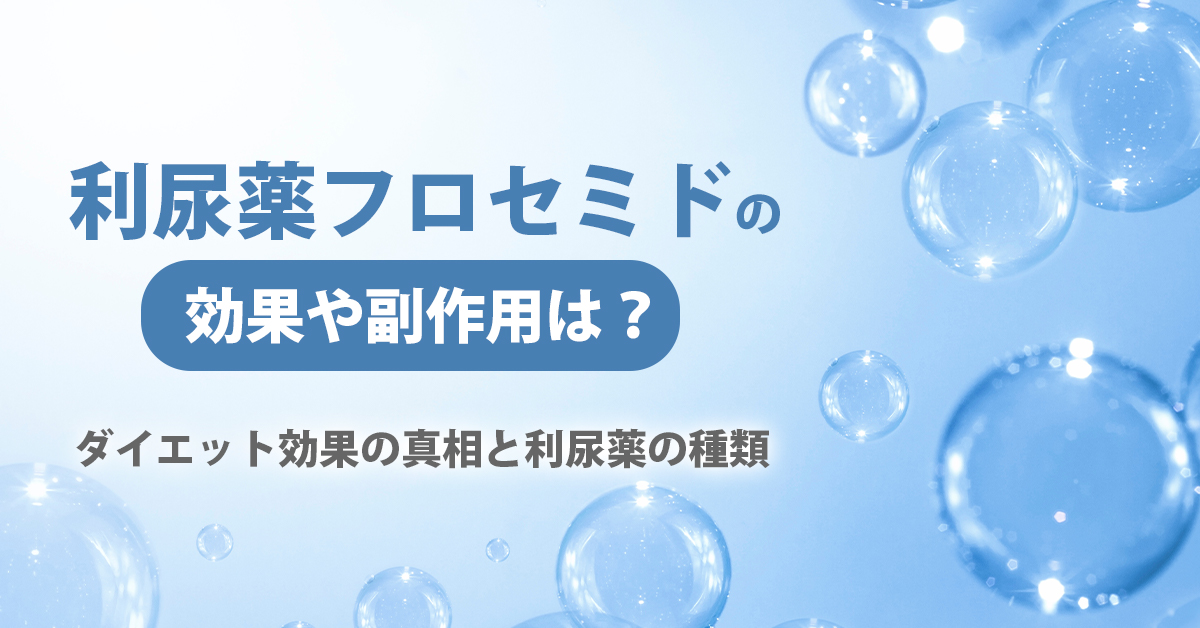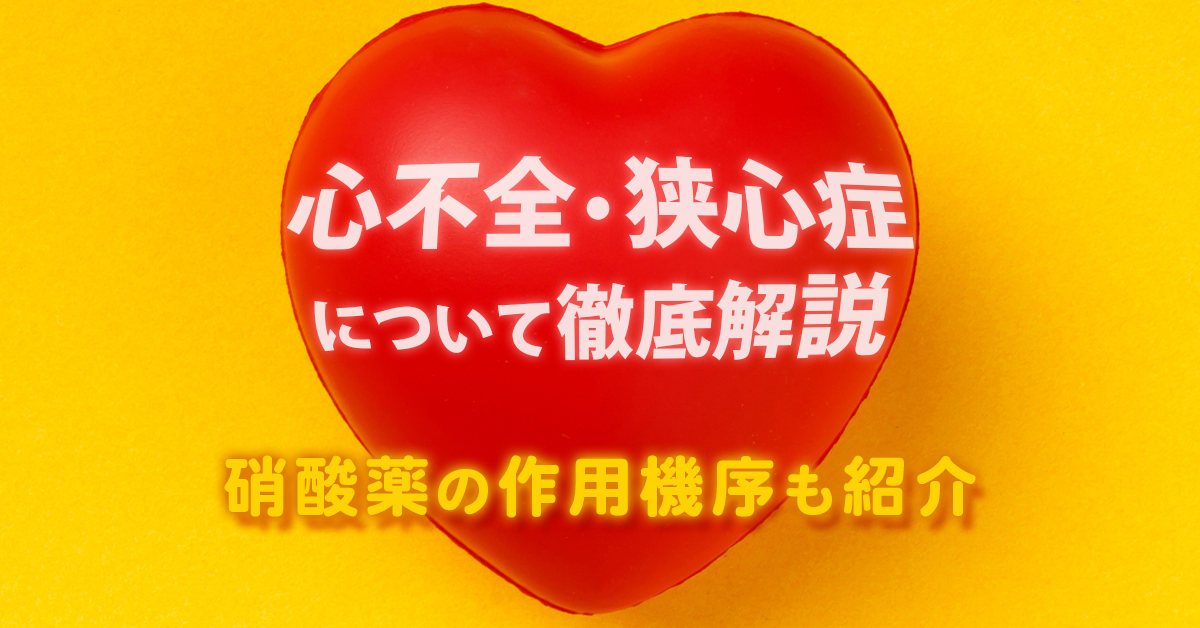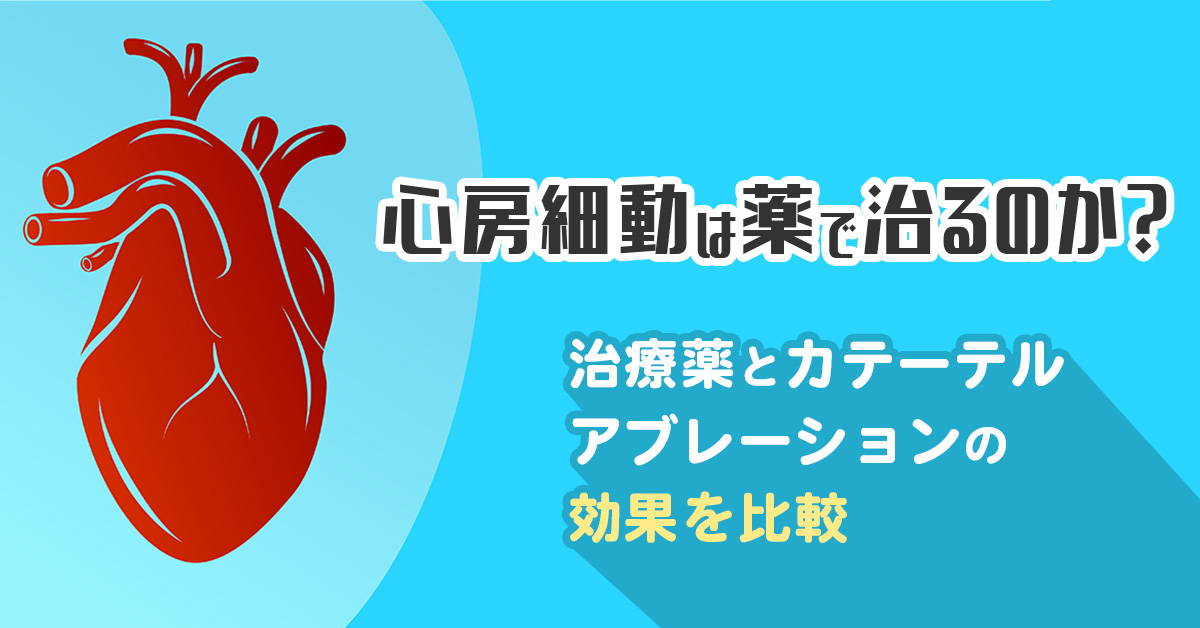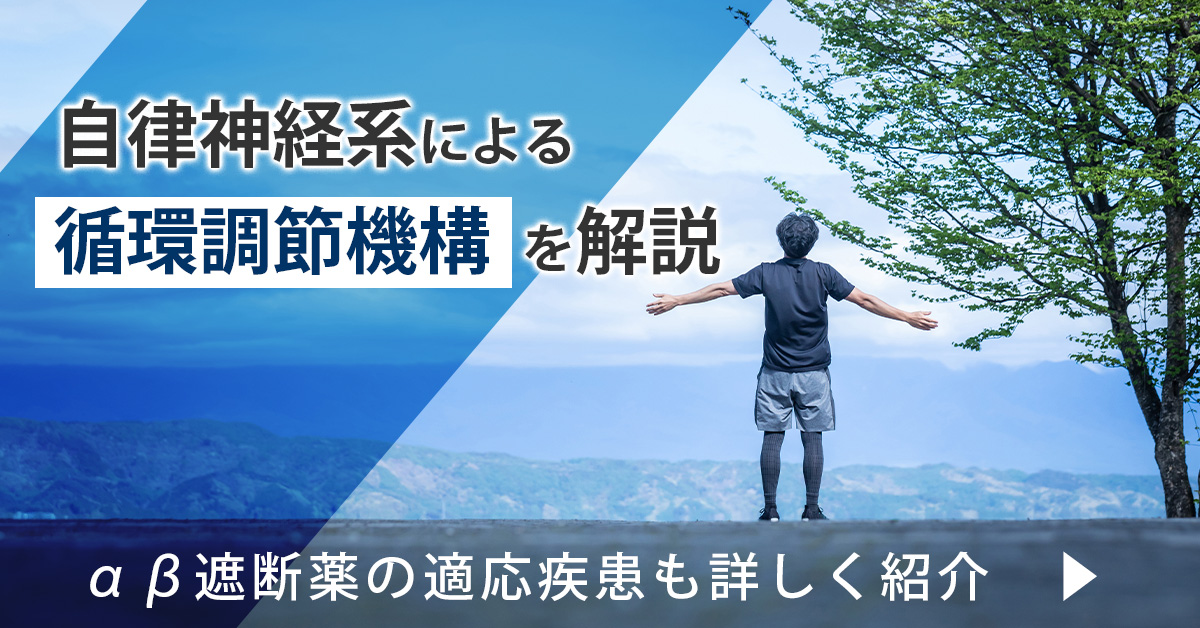「止血機構はどんなメカニズムで働いているの?」
「抗血栓薬にはどんな種類がある?」
このような疑問を持っている人は少なくないのではないでしょうか。
本記事では、止血機構が働くメカニズムについて徹底解説。
血栓傾向により起こり得る疾患や、抗血栓薬の一覧も紹介します。
本記事を読めば、止血機構のメカニズムや抗血栓薬について理解を深められます。
興味がある人はぜひ最後までご覧ください。
止血機構とは?
ヒトの血液は正常時、血管内で流動性を保っており、血管から漏れ出ることなく体内を循環しています。
しかし、何らかの原因で血管が損傷すると出血が起こります。
そこで、出血を止めるために活躍しているのが止血機構というシステムです。
まずは、止血機構の流れや止血機構に関わる物質について見ていきましょう。
①止血機構の流れ
止血機構は、以下の3段階から成り立っています。
- 一次止血
- 二次止血
- 線溶
出血した部位はまず、血の塊である一次血栓・二次血栓によって塞がれます。
その後、損傷した血管が修復されると、不要になった血栓が溶かされます。
この一連の流れが止血機構です。
しかし、出血のない通常時にも血栓ができてしまうと、形成された血栓により様々な疾患が引き起こされてしまいます。
そのため、ヒトの体内では血栓形成作用と抗血栓作用がバランスよく働いています。
②止血機構に関わる物質
止血機構には、血液中を流れる血小板や白血球の他、肝臓などで産生される様々な生理的物質が関わっています。
主な生理的物質は以下の通りです。
| 血栓形成作用 | 抗血栓作用 | |
|---|---|---|
| 一次止血 | ・TXA2 ・ADP ・VWF ・PAF ・セロトニン |
・PGI2 ・NO ・ADPase ・cAMP |
| 二次止血 | ・凝固因子 ・リン脂質 ・コラーゲン ・カリクレイン ・キニノゲン ・ビタミンK代謝産物 |
・ヘパリン様物質 ・トロンボモジュリン ・AT ・プロテインC ・プロテインS ・TFPI |
| 線溶 | ・PAI ・α2-PI ・TAFI ・第Ⅷ因子 |
・PA |
ここからの解説でいくつもの物質が登場するので、わからなくなったら上表に戻ってきてください。
止血機構の第一段階:一次止血
一次止血は止血機構における第一段階であり、血小板を主役とする反応です。
以下の観点から解説していきます。
- 血小板とは
- 一次止血の流れ
- 血小板機能の阻害
それぞれについて見ていきましょう。
①血小板とは
血小板とは、「巨核球」という細胞から産生される、直径2~4μmの円盤状の血球です。
通常10日間ほど血液中を循環した後、主に脾臓で処理されます。
血小板は、表面にいくつかの糖蛋白を有しています。
そのうち、重要となるものが「GPⅠb/Ⅸ/Ⅴ複合体」と「GPⅡb/Ⅲa複合体」です。
②一次止血の流れ
一次止血は、血小板の粘着→放出→凝集という3段階で成り立っています。
具体的なメカニズムは以下の通りです。
| メカニズム | |
|---|---|
| 粘着 | ・GPⅠb/Ⅸ/Ⅴ複合体がVWFに結合し、VWFを介して血小板が血管壁のコラーゲンと結合する |
| 放出 | ・粘着により活性化した血小板が、ADPやTXA2を放出する ・ADPはさらに血小板を活性化する ・TXA2には血小板凝集作用と血管収縮作用があり、止血を促進する |
| 凝集 | ・GPⅡb/Ⅲa複合体が「フィブリノゲン」という物質と結合し、フィブリノゲンを介して血小板同士が凝集する(一次血栓) |
③血小板機能の阻害
出血のない正常な血管では、以下のような物質により血小板機能が阻害されています。
| 生理的物質 | 阻害のメカニズム |
|---|---|
| PGI2 | ・TXA2に拮抗し、血小板凝集と血管収縮を阻害する |
| NO | ・PGI2の産生を増加させる ・血小板の活性化を阻害する ・血管を拡張させる |
| ADPase | ・ADPを分解し、血小板の活性化を阻害する |
止血機構の第二段階:二次止血
二次止血は止血機構における第二段階であり、凝固因子を主役とする反応です。
以下の観点から解説していきます。
- 二次止血の目的
- 凝固因子とは
- 凝固因子の阻害
それぞれについて見ていきましょう。
①二次止血の目的
主に血小板の働きにより一次止血が完了しても、止血機構としては不十分です。
なぜなら、一次血栓は強度が弱く、簡単に?がれてしまうからです。
そこで、より強固な血栓を完成させるために二次止血が行われます。
具体的には、一次血栓の周りを「フィブリン」という物質で覆っていきます。
②凝固因子とは
二次止血の主役となる凝固因子は、全部で14種類存在します。
| 略称 | 凝固因子 |
|---|---|
| Ⅰ | フィブリノゲン |
| Ⅱ | プロトロンビン |
| Ⅲ | 組織因子(TF) |
| Ⅳ | カルシウム |
| Ⅴ | 不安定因子(ACグロブリン) |
| Ⅶ | 安定因子(プロコンバーチン) |
| Ⅷ | 抗血友病因子(AHF) |
| Ⅸ | クリスマス因子 |
| Ⅹ | スチュアート・プロウァ因子 |
| XI | PTA |
| XII | ハーゲマン因子 |
| XIII | フィブリン安定因子 |
| なし | プレカリクレイン |
| なし | 高分子キニノゲン |
以上のうち、第Ⅱ・Ⅶ・Ⅸ・Ⅹ因子は、産生するためにビタミンKが必要です。
そのため、これらの凝固因子は「ビタミンK依存性凝固因子」と呼ばれています。
詳細なメカニズムは省きますが、これらの凝固因子により連鎖的に凝固反応が進行していきます。
そして、最終的にフィブリノゲンからフィブリンが合成され、二次血栓が完成するのです。
③凝固因子の阻害
血小板と同様に、凝固因子もいくつかの生理的物質により阻害されています。
| 生理的物質 | 阻害のメカニズム |
|---|---|
| ヘパリン様物質・AT | ・ATがヘパリン様物質に結合して活性化し、複数の凝固因子に結合して反応を阻害する |
| トロンボモジュリン・プロテインC・プロテインS | ・トロンボモジュリンが、プロトロンビンから産生される物質「トロンビン」と結合して阻害する ・トロンボモジュリンとトロンビンの複合体がプロテインCを活性化し、プロテインSの力も借りて複数の凝固因子を分解する |
止血機構の第三段階:線溶
線溶は止血機構における第三段階であり、「プラスミン」を主役とする反応です。
以下の観点から解説していきます。
- 線溶の流れ
- 線溶の阻害
それぞれについて見ていきましょう。
①線溶の流れ
不要な血栓を取り除く線溶は、PAが「プラスミノゲン」という物質に働きかけるところから始まります。
その結果、プラスミノゲンは活性化してプラスミンへと変化します。
プラスミンの主な作用は、フィブリノゲンやフィブリンの分解です。
その結果、過剰な血栓が溶解されて止血機構の完了となります。
②線溶の阻害
血管の修復前に血栓が溶解されないように、過剰な線溶は阻害されています。
| 生理的物質 | 阻害のメカニズム |
|---|---|
| α2-PI | ・血中のプラスミンと結合し阻害する(血栓内のプラスミンとは結合できない) |
| PAI | ・PAを阻害することで、プラスミノゲンがプラスミンに変化することを抑制する |
止血機構の異常
通常、血栓形成作用と抗血栓作用はバランスが取れており、一方に傾くことはありません。
しかし、何らかの原因によりバランスが崩れると、血管内の不要な場所で血栓を形成しやすくなったり(血栓傾向)、血管に損傷がなくても出血しやすくなったりします(出血傾向)。
血栓傾向時に、血管内に形成される血栓を病的血栓と言います。
形成される部位によって動脈血栓と静脈血栓に分けられ、それぞれ様々な疾患の原因となるのです。
| 動脈血栓 | 静脈血栓 | |
|---|---|---|
| 形成部位 | ・動脈などの血流の速い血管内 | ・静脈などの血流が遅い血管内 |
| 主体となる止血機構 | ・血小板による一次止血 | ・凝固因子による二次止血 |
| 疾患例 | ・虚血性心疾患 ・アテローム血栓性脳梗塞 ・一過性脳虚血発作(TIA) ・末梢動脈疾患 |
・静脈血栓塞栓症(深部静脈血栓症・肺血栓塞栓症) |
代表的な3つの疾患について、簡単に紹介します。
①虚血性心疾患
虚血性心疾患とは、心臓に酸素などを供給している血管である、冠動脈が狭窄・閉塞する疾患です。
主な原因として動脈硬化が挙げられます。
| 疾患 | 狭心症 | 心筋梗塞 |
|---|---|---|
| 冠動脈 | 狭窄 | 閉塞 |
| 症状 | ・前胸部の絞扼感や痛み | ・前胸部の強い痛み ・悪心/嘔吐 ・呼吸困難 |
②アテローム血栓性脳梗塞
アテローム血栓性脳梗塞とは、脳を流れる血管が血栓により詰まってしまう疾患です。
虚血性心疾患と同様に、主な原因として動脈硬化が挙げられます。
安静時に発症することが多く、片側の麻痺や感覚障害、構音障害(喋りにくい)などが生じます。
進行すると症状が悪化していくため、早期の治療が必要です。
③静脈血栓塞栓症
静脈血栓塞栓症とは、「深部静脈血栓症」と「肺血栓塞栓症」という2つの疾患を併せた病態です。
深部静脈血栓症は下肢の静脈に血栓ができる疾患であり、リスク因子として長期臥床や妊娠、手術や経口避妊薬などが挙げられます。
深部静脈血栓症による血栓が静脈に乗って運ばれ、肺に向かう動脈を閉塞すると肺血栓塞栓症を発症します。
肺血栓塞栓症では呼吸困難や胸痛などの症状が生じ、場合によっては致命的となる恐れもあります。
抗血栓療法
抗血栓療法は、血栓の形成予防(再発予防含む)や血栓の増大防止を目的に行われます。
動脈血栓に対しては抗血小板薬が、静脈血栓に対しては抗凝固薬が用いられます。
抗血小板薬と抗凝固薬をまとめて抗血栓薬と呼び、様々な種類があります。
以下で抗血栓薬の一覧を見ていきましょう。
①抗血小板薬の一覧
主な抗血小板薬は以下の通りです。
| COX阻害薬 | ADP受容体遮断薬 | PDE阻害薬 | |
|---|---|---|---|
| 薬剤名 | ・アスピリン | ・チクロピジン ・クロピドグレル ・プラスグレル |
・シロスタゾール |
| 作用メカニズム | ・TXA2を産生するために必要な物質「COX」を阻害する | ・ADPが作用するための受容体に結合するのを阻害する | ・血小板の放出反応を促進する物質「PDE」を阻害する |
| 投与方法 | 経口 | 経口 | 経口 |
| 作用が現れるまでの時間 | 約4時間 | 1~2時間 | 約3時間 |
| 作用の持続時間 | 約1週間 | 約1週間 | 約2日 |
| 適応となる疾患 | ・虚血性心疾患 ・アテローム血栓性脳梗塞 ・川崎病 |
・アテローム血栓性脳梗塞 ・虚血性心疾患 ・末梢動脈疾患 |
・アテローム血栓性脳梗塞 ・末梢動脈疾患 |
| 主な副作用 | ・喘息発作 ・腎障害 ・消化性潰瘍 |
・血栓性血小板減少性紫斑病(TTP) ・無顆粒球症 ・肝機能障害 |
・頭痛、ほてり ・心不全、動悸 |
②抗凝固薬の一覧
主な抗凝固薬は以下の通りです。
| ヘパリン | クマリン系抗凝固薬 | DOAC | |
|---|---|---|---|
| 薬剤名 | ・ヘパリンナトリウム ・ヘパリンカルシウム |
・ワルファリン | ・ダビガトラン ・リバーロキサバン ・アピキサバン ・エドキサバン |
| 作用メカニズム | ・ヘパリン様物質として、ATの作用を促進する | ・ビタミンKと構造が類似しており、ビタミンK依存性凝固因子の産生を阻害する | ・ダビガトランはトロンビンを阻害し、その他は凝固因子を阻害する |
| 投与方法 | 静脈注射、皮下注射 | 経口 | 経口 |
| 作用が現れるまでの時間 | 静脈注射で約15分 | 4~5日 | 数時間以内 |
| 作用の持続時間 | 数時間 | 数日 | 約1日 |
| 適応となる主な疾患 | ・血栓塞栓症 ・播種性血管内凝固(DIC) |
・心房細動 ・静脈血栓塞栓症 |
・心房細動 ・静脈血栓塞栓症 |
| 主な副作用 (出血傾向を除く) | ・ヘパリン起因性血小板減少症(HIT) | ・消化器症状 ・催奇形性(妊婦には投与禁止) |
・肝機能障害 ・消化器症状 |
まとめ:抗血栓薬で血栓傾向による疾患を予防・治療しよう
損傷した血管からの出血を止めるために、体内に備わっているシステムが止血機構です。
通常、血栓形成作用と抗血栓作用のバランスが取れていますが、何らかの原因で崩れる場合があります。
血栓傾向となると、虚血性心疾患やアテローム血栓性脳梗塞をはじめとする、様々な疾患を発症する恐れがあります。
そこで、用いられているのが抗血小板薬・抗凝固薬です。
抗血栓薬を適切に使い分けて、血栓傾向による疾患を予防・治療しましょう。