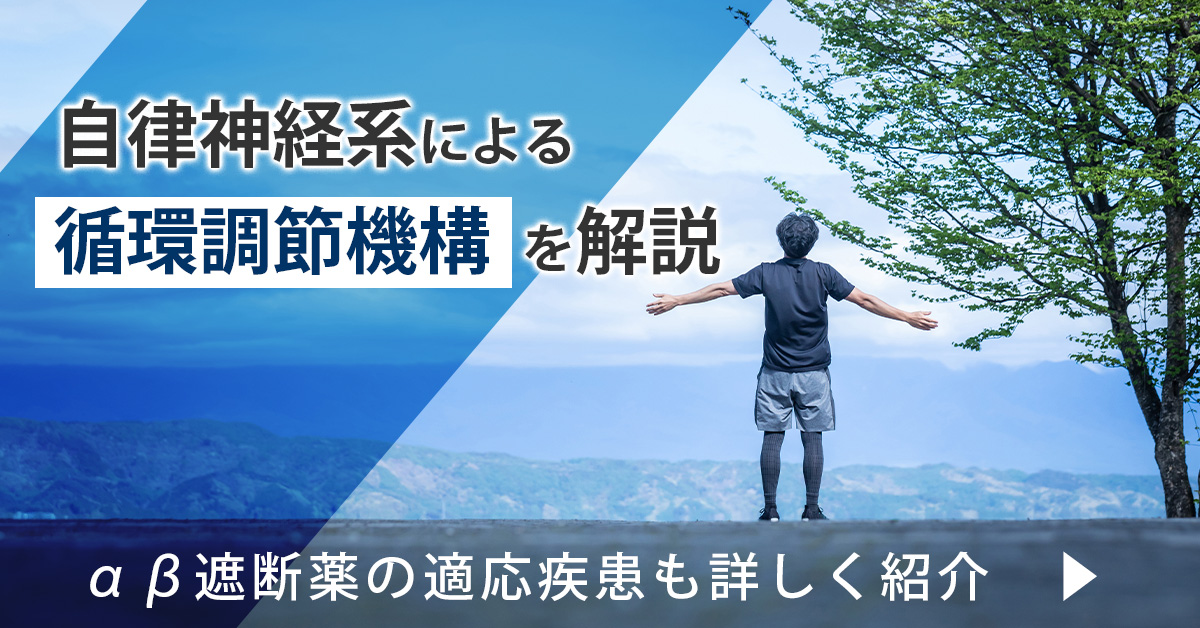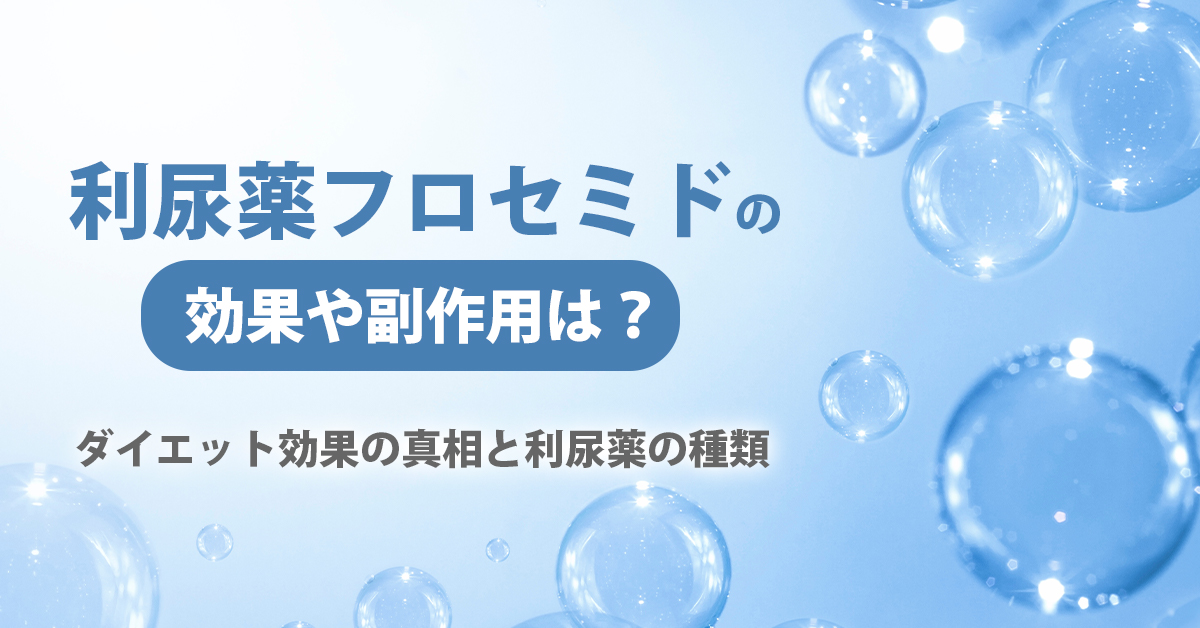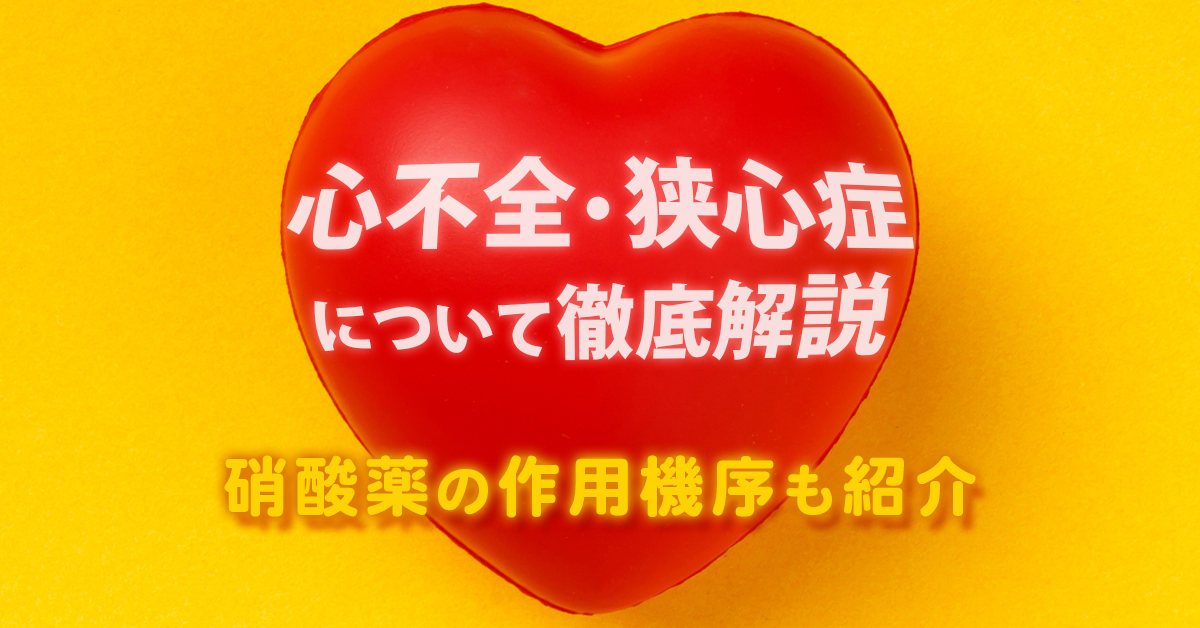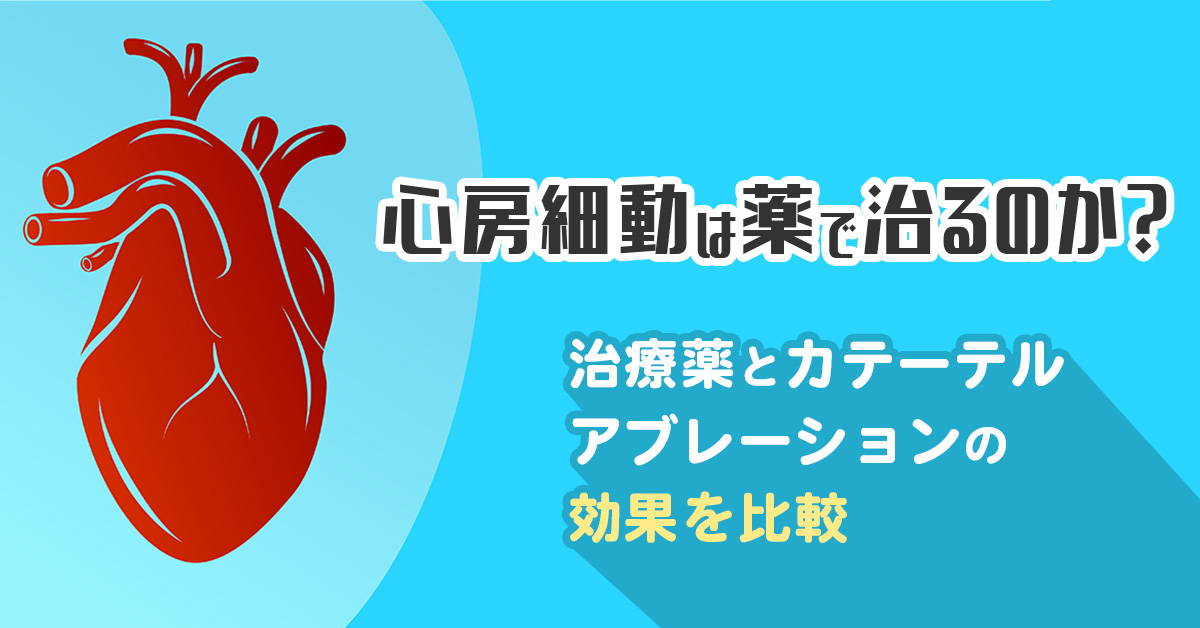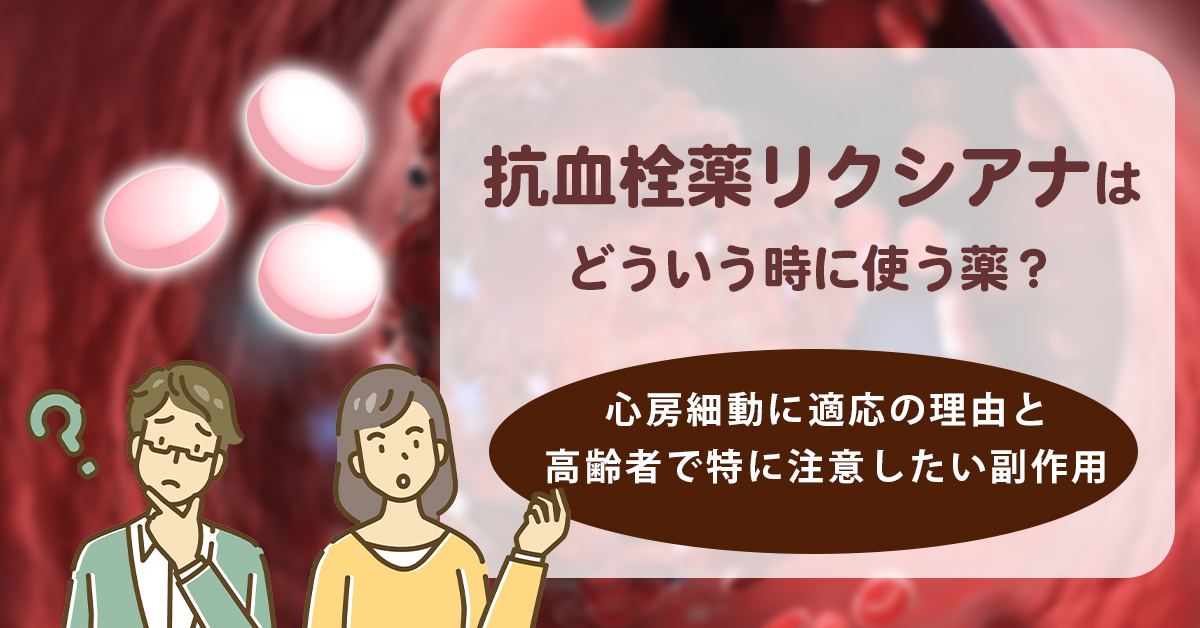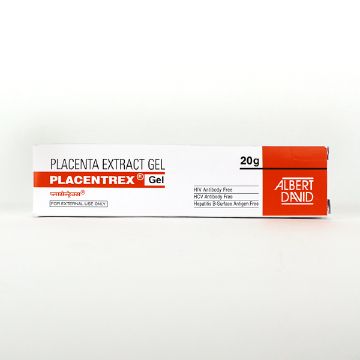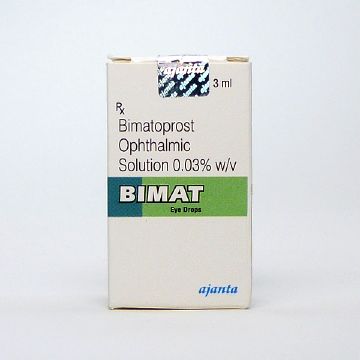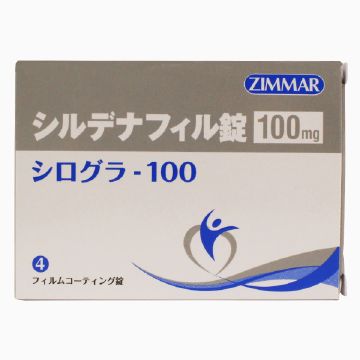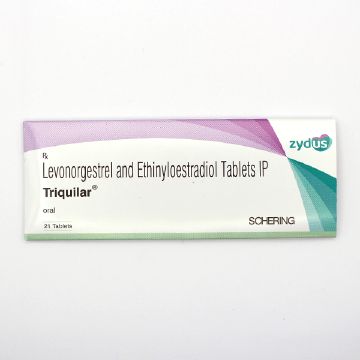「自律神経系は心臓にどんな影響を与えているの?」
「αβ遮断薬はどんな疾患に対して用いられる?」
このような疑問を持っている人は少なくないのではないでしょうか。
本記事では、自律神経系による循環調節機構について徹底解説。
αβ遮断薬が適応となる疾患や、注意すべき副作用についても紹介します。
本記事を読めば、自律神経系による循環調節機構やαβ遮断薬について理解を深められます。
興味がある人はぜひ最後までご覧ください。
循環調節機構とは?
循環調節機構とは、血圧を一定の範囲に保ち全身の血流を維持するために、自律神経系やホルモンによる調節から成り立っているシステムです。
まずは、そもそも血圧とは何であるのか、という点から解説しましょう。
血圧(血液が動脈血管の内壁に与える圧力) = 心拍出量(心臓から全身へ送られる血液の総量) × 末梢血管抵抗(末梢血管での血液の流れにくさ)
心拍出量は、心臓の収縮力や体内を循環している血液量から規定されます。
末梢血管抵抗は、末梢血管の内腔径や内壁の硬さから規定されます。
(内腔径が小さく内壁が硬いほど、末梢血管抵抗が大きくなる)
自律神経系とは?
自律神経系は、緊張・興奮状態で亢進する交感神経系と、リラックス状態で亢進する副交感神経系から構成されています。
全身に対して様々な働きを有しており、心臓・血管に対する働きは以下の通りです。
| 交感神経系 | 副交感神経系 | |
|---|---|---|
| 心拍数 | 亢進 | 抑制 |
| 心収縮力 | 亢進 | 軽度抑制 |
| 血管 | 収縮 | 影響なし |
それぞれ以上の働きを持っているため、交感神経系が活発になると血圧が上昇し、副交感神経系が活発になると血圧が低下するのです。
自律神経系の受容体
自律神経系は「神経伝達物質」を放出し、それが各臓器に存在する「受容体」に結合することで情報を伝達しています。
交感神経系と副交感神経系に分けて、情報伝達のメカニズムを見ていきましょう。
①交感神経系
交感神経系は、受容体に向けて「ノルアドレナリン」という神経伝達物質を放出します。
ノルアドレナリンを受け取る受容体は、「アドレナリン受容体」です。
アドレナリン受容体には、α1・α2・β1・β2・β3という5つのサブタイプがあります。
サブタイプの分布は臓器によって異なり、心臓には主にβ1受容体・β2受容体が、血管には主にα1受容体が分布しています。
②副交感神経系
副交感神経系は、受容体に向けて「アセチルコリン」という神経伝達物質を放出します。
アセチルコリンを受け取る受容体は、「ムスカリン受容体」です。
アドレナリン受容体と同様に、ムスカリン受容体にもM1~M5という5つのサブタイプがあります。
αβ遮断薬が作用を発揮する疾患
αβ遮断薬には、α受容体とβ受容体をノルアドレナリンから遮断する働きがあります。
ノルアドレナリンはアドレナリン受容体に結合できなければ、心拍数や心収縮力を亢進する作用や、血管を収縮させる作用を発揮できません。
その結果として血圧が低下するため、αβ遮断薬は高血圧に対する治療薬として用いられています。
その他、心臓の仕事量も抑制できるため、以下のような心疾患に対しても投与されています。
- 狭心症
- 頻脈性不整脈
- 慢性心不全
ここからは、それぞれの疾患について詳しく見ていきましょう。
αβ遮断薬が適応となる疾患:①高血圧
血圧計さえあれば、自宅でも高血圧かどうかを確認できます。
定義は以下の通りです。
| 分類 | 診察室血圧(mmHg) | 家庭血圧(mmHg) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 収縮期血圧 | 条件 | 拡張期血圧 | 収縮期血圧 | 条件 | 拡張期血圧 | |
| 正常血圧 | <120 | かつ | <80 | <115 | かつ | <75 |
| 正常高値血圧 | 120-129 | かつ | <80 | 115-124 | かつ | <75 |
| 高値血圧 | 130-139 | かつ/または | 80-89 | 125-134 | かつ/または | 75-84 |
| Ⅰ度高血圧 | 140-159 | かつ/または | 90-99 | 135-144 | かつ/または | 85-89 |
| Ⅱ度高血圧 | 160-179 | かつ/または | 100-109 | 145-159 | かつ/または | 90-99 |
| Ⅲ度高血圧 | ≧180 | かつ/または | ≧110 | ≧160 | かつ/または | ≧100 |
| 収縮期高血圧 | ≧140 | かつ | <90 | ≧135 | かつ | <85 |
(診察室血圧:病院で測定する血圧、家庭血圧:自宅などリラックス環境で測定する血圧)
高血圧は様々な疾患の高リスク因子です。
以下のような、命に関わる重大な疾患の発症リスクを高めてしまいます。
| 疾患 | 病態 | 症状 |
|---|---|---|
| 脳出血 | 脳内の血管から出血する | ・感覚障害や麻痺などの運動障害 ・意識障害 |
| 脳梗塞 | 脳内に酸素などを供給する血管が詰まる | ・感覚障害や麻痺などの運動障害 ・呂律が回らなくなる構音障害 |
| 心筋梗塞 | 心臓に酸素などを供給する血管(冠動脈)が詰まる | ・前胸部を締め付けるような強い痛み ・悪心/嘔吐 ・呼吸困難 |
| 大動脈解離 | 大きな血管が脆くなり内側の膜に亀裂が生じる | ・突然の胸背部の激痛(進行に伴い痛みは腰部に移動する) |
αβ遮断薬が適応となる疾患:②狭心症
狭心症とは、心臓に酸素など必要な物質を届けている冠動脈が、何らかの原因により狭窄する疾患です。
狭窄の原因や症状・経過などから、以下の3タイプに分類されます。
- 労作性狭心症
- 冠攣縮性狭心症
- 不安定狭心症
それぞれについて見ていきましょう。
①労作性狭心症
運動時、心臓は全身に多くの血液を送る必要があるため、活発に活動します。
そのため、心臓自体も多くの酸素を必要とし、本来であれば冠動脈が拡張します。
しかし、動脈硬化などにより冠動脈が狭窄しているとうまく拡張できず、心臓の酸素需要を満たせません。
その結果、休息により3~5分ほどで消失する、前胸部を締め付けられるような圧迫感が生じます。
②冠攣縮性狭心症
冠攣縮性狭心症とは、冠動脈が痙攣することで収縮し、心臓に十分な酸素を届けられなくなる疾患です。
その結果、数分~15分ほど続く前胸部を締め付けられるような圧迫感が生じます。
冠動脈の痙攣は、動脈硬化がある場所で発生しやすいと考えられています。
また、運動時に起こりやすい労作性狭心症とは対照的に、安静時や夜間・早朝に起こりやすいです。
③不安定狭心症
不安定狭心症とは、動脈硬化がある場合に血の塊である血栓が発生し、急激に冠動脈が狭窄する疾患です。
数分~15分以上続く強い前胸部の痛みが、安静時/運動時問わず発生します。
なお、同様のメカニズムにより冠動脈が完全に閉塞した病態が、不安定狭心症よりも重篤である心筋梗塞です。
αβ遮断薬が適応となる疾患:③頻脈性不整脈
心臓には「洞結節」という場所があり、そこで興奮が発生します。
そして、発生した興奮が「刺激伝導系」というルートを通って心臓を構成する筋肉に伝わり、心臓が収縮します。
このように、洞結節からの刺激が心臓全体に正しく伝わっている状態が、「洞調律」です。
不整脈とは、正常な洞調律が妨げられた状態です。
不整脈は、心拍数が100回/分を超える頻脈性不整脈と、50回/分未満の徐脈性不整脈に大別されます。
αβ遮断薬が適応となるのは頻脈性不整脈であり、具体的には以下が該当します。
| 不整脈 | 症状など |
|---|---|
| 心房期外収縮 | ・多くは無症状 ・時に動悸 ・胸部違和感 |
| 発作性上室頻拍 | ・突然起こり、突然停止する動悸 ・重症例ではめまいや意識消失 |
| 心房粗動 | ・動悸 ・呼吸困難など |
| 心房細動 | ・動悸 ・血栓が形成され、脳に到達すると脳梗塞の原因に(心原性脳塞栓症) |
| 心室期外収縮 | ・無症状 ・時に動悸 |
| 心室頻拍 | ・動悸 ・息切れ ・時にめまい ・失神 ・意識消失 |
| 心室細動 | ・めまい、その直後に失神 ・治療しなければ数分で致命的となる |
αβ遮断薬が適応となる疾患:④慢性心不全
何らかの原因で心機能が低下すると、心拍出量が減少します。
そのままでは血圧が低下してしまいますが、ヒトにはいくつかの代償機構が備わっており、そう簡単には血圧は低下しません。
なお、本記事で取り上げた交感神経系の亢進も、代償機構の一つです。
しかし、代償機構には心臓の負担を大きくするという、重大なデメリットが存在します。
そのため、慢性的に代償機構が働くと心臓がどんどん弱っていってしまい、代償しきれないほどに心拍出量が低下するのです。
また、全身に送られない血液が心臓に貯留することで、肺や全身にうっ血症状も起こります。
具体的には以下の通りです。
| 原因 | 主な症状 |
|---|---|
| 心拍出量低下 | ・動悸 ・易疲労感 ・尿量減少 ・低血圧 ・四肢冷感 ・冷汗 |
| 肺うっ血 | ・運動時の息切れ ・頻呼吸 ・呼吸困難 |
| 全身うっ血 | ・消化器症状(食欲不振、腹部膨満感、嘔吐、便秘など) ・浮腫 ・体重増加 |
αβ遮断薬の主な副作用
空気の通り道である気管支には主にβ2受容体が分布しており、ノルアドレナリンが結合すると気管支が拡張します。
しかし、αβ遮断薬によりβ2受容体を遮断してしまうと、気管支の拡張が抑制され収縮します。
その結果、呼吸困難や喘鳴(呼吸時のヒューヒュー、ゼーゼーという音)などが生じる恐れがあるのです。
気管支喘息を基礎疾患に持つ患者さんでは、気管支が収縮しやすい状態が続いています。
そのため、αβ遮断薬の中には、気管支喘息の患者さんに対して投与できない薬剤があります。
その他、αβ遮断薬で起こり得る副作用は以下の通りです。
| 精神神経系症状 | めまい、眠気、頭痛など |
|---|---|
| 消化器症状 | 吐き気、食欲不振など |
αβ遮断薬の種類と特徴
αβ遮断薬の主な種類と、それぞれの特徴は以下の通りです。
| 薬剤 | 特徴 |
|---|---|
| アーチスト | ・高血圧、狭心症、頻脈性の心房細動、慢性心不全などに対して用いられる ・気管支喘息患者には原則として投与しない |
| アロチノロール | ・高血圧、狭心症、頻脈性不整脈などに対して用いられる ・気管支喘息患者には原則として投与しない |
| カルバン | ・主に高血圧に対して用いられる ・気管支喘息患者に対しては慎重に投与する |
まとめ:αβ遮断薬で高血圧や心疾患を治療しよう
緊張や興奮状態で活発になる交感神経系は、ノルアドレナリンをα受容体やβ受容体に結合させることで、その役割を果たしています。
αβ遮断薬は、α受容体やβ受容体をノルアドレナリンから遮断し、交感神経系の働きを阻害する薬剤です。
αβ遮断薬の働きにより、血圧や心臓の仕事量を抑えられるため、高血圧や狭心症、頻脈性不整脈や慢性心不全に対して治療効果を発揮します。
副作用には注意しつつ、αβ遮断薬を高血圧や心疾患の治療に役立てましょう。