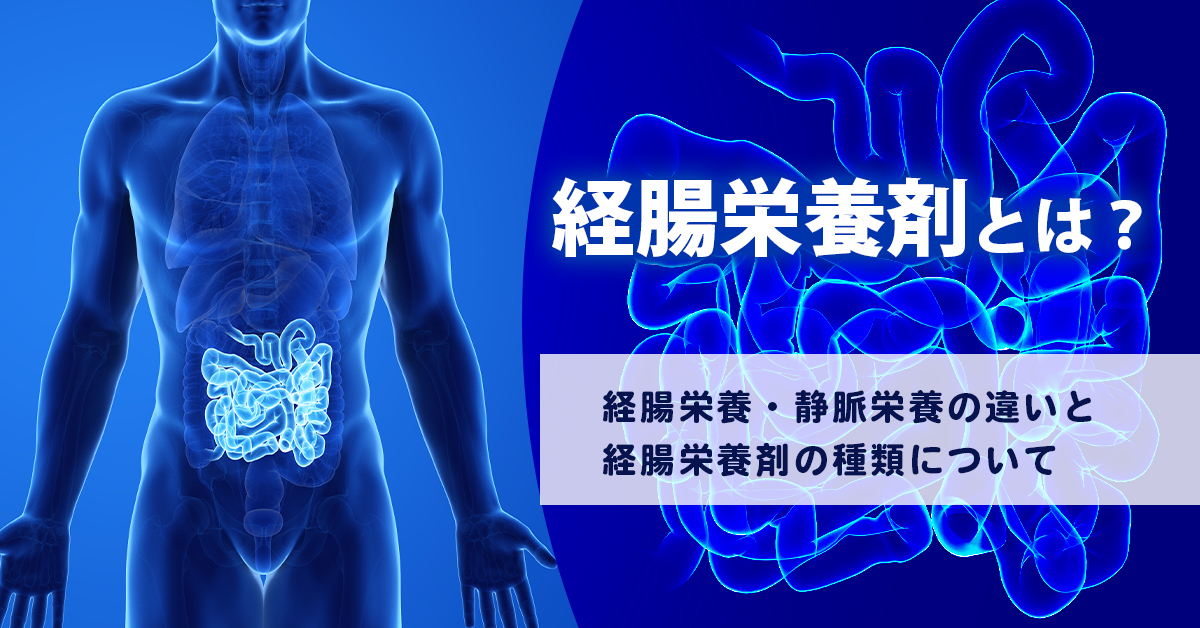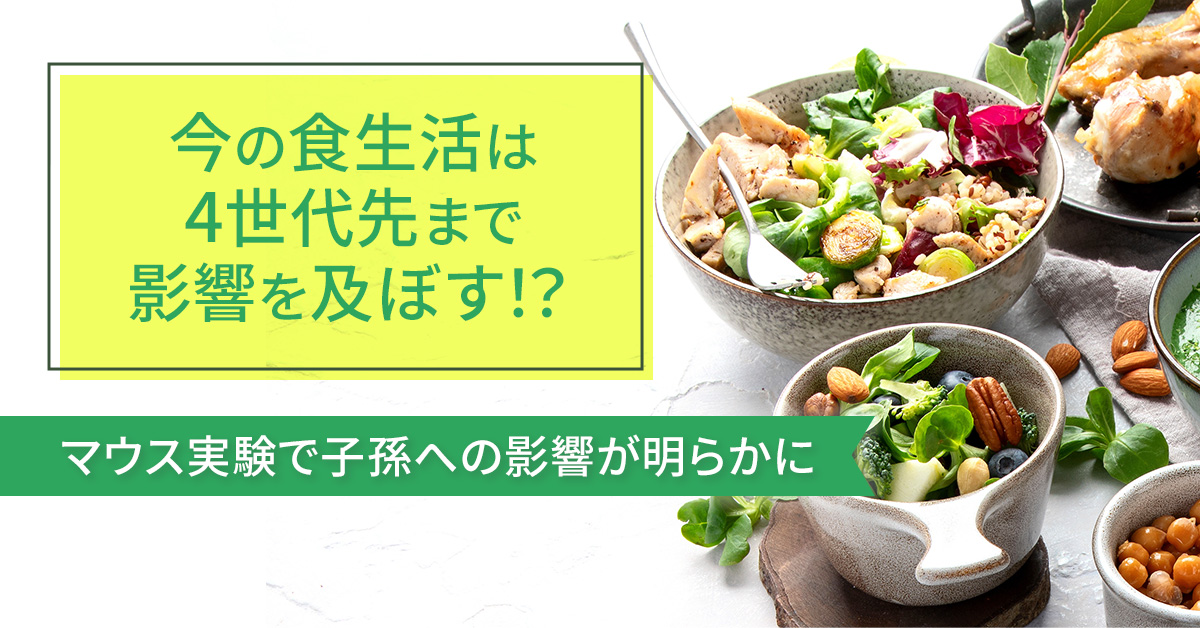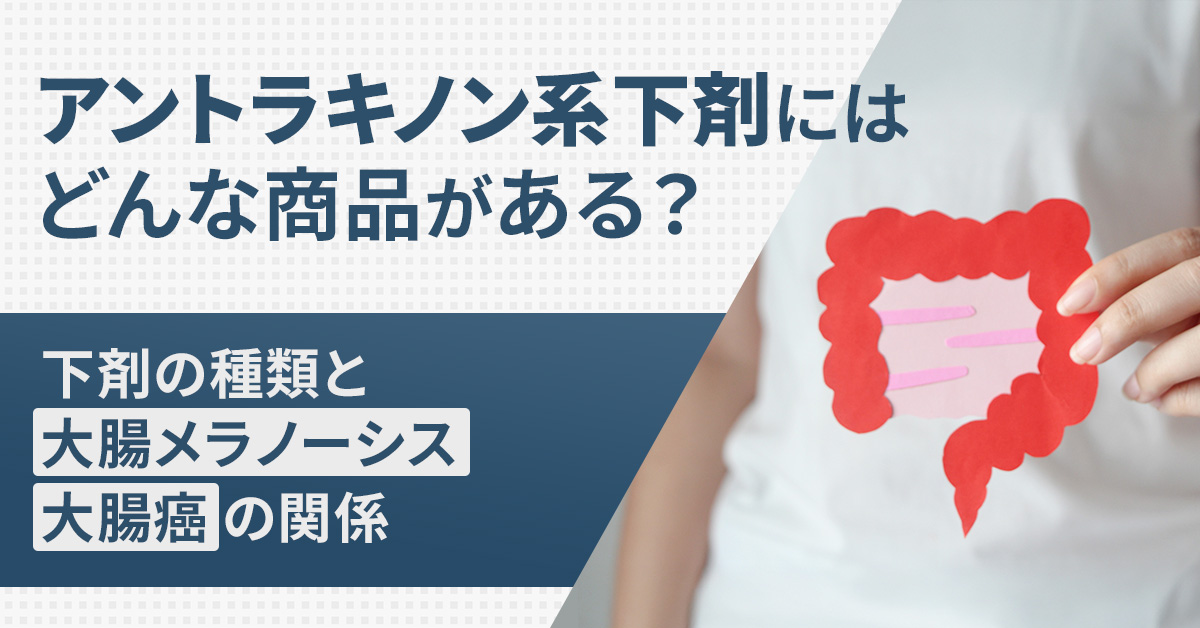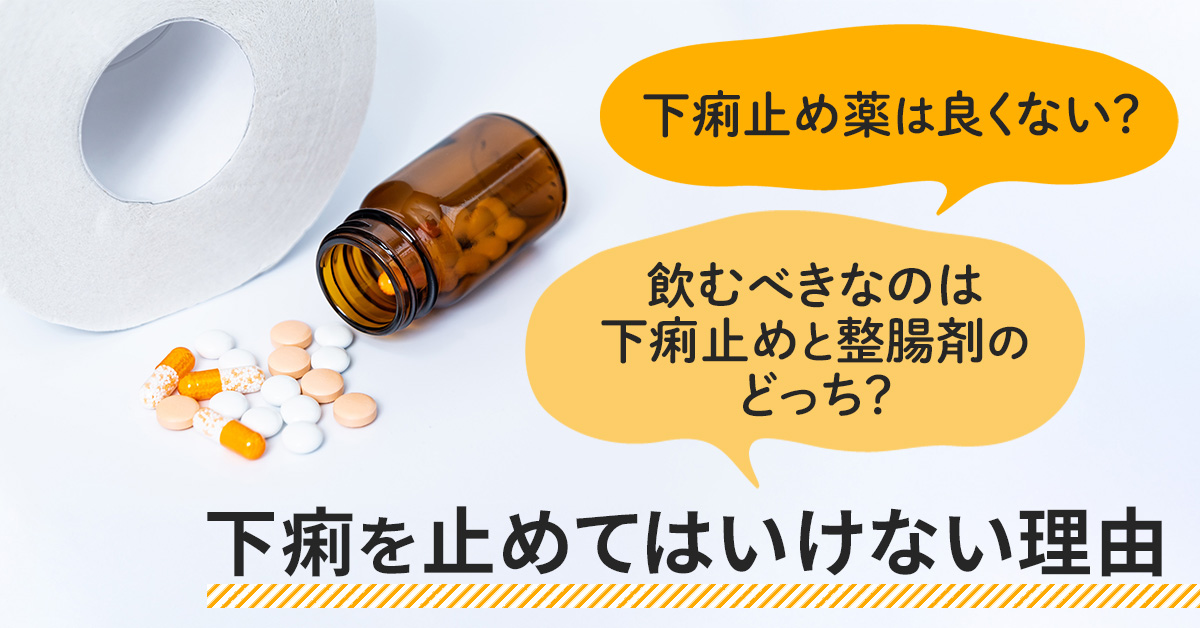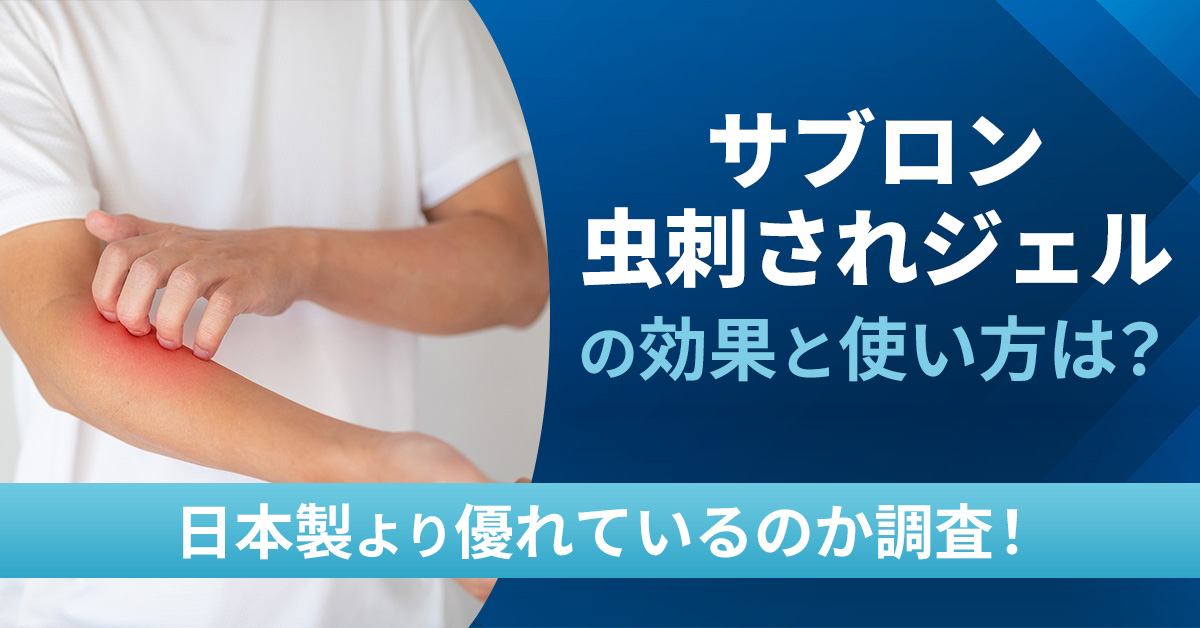食事は健康を維持するうえで、欠かせない要素の1つです。
一日三食様々な食品からバランス良く栄養を摂ることが理想ですが、病気や手術などの影響で難しい方もいらっしゃるでしょう。
今回は食べ物から栄養を摂ることが難しい方の心強い味方となる経腸栄養剤について、その種類や違いなどを解説していきます。
加えて、経腸栄養剤の取り方の工夫についても紹介しますので、なかなか飲めずに困っている方はぜひ参考にしてください。
栄養補給法の違い
健康な時には食べ物を口から食べ、胃や腸を始めとする消化管で消化・吸収をして栄養を摂取しますが、病気や手術によりそれが難しくなるケースもあります。
このような場合には栄養剤などを用いて栄養を補給する形を取るのが一般的です。
ここでは栄養剤を使用した「経腸栄養」と、静脈から栄養を注入する「静脈栄養」について解説していきます。
経腸栄養
経腸栄養には、口から栄養を摂る「経口栄養」と、経鼻チューブや胃ろう・腸ろうから栄養剤を注入する「経管栄養」の2種類があります。
経口栄養は味覚や嗅覚などの感覚的にも満足度が高く、様々な栄養素を補給できるメリットがあるため、まずは経口栄養が可能かどうか検討します。
経口栄養が難しい場合は、次に経管栄養を検討します。
経管栄養は咀嚼や嚥下障害があったり、炎症性腸疾患などの消化管疾患があったりする場合に選択される栄養補給法です。
短期間であれ経鼻チューブによる経管栄養が行われますが、4週間以上になると予想される場合には胃ろう・腸ろうによる経管栄養となります。
静脈栄養
静脈栄養は、消化管が機能していなかったり、重い膵炎を患っていたりして、栄養素の消化・吸収ができない時に選択される栄養補給法です。
グルコースやアミノ酸、脂肪乳剤にビタミン、ミネラルを配合した液体を中心静脈や末端静脈に注入して栄養を補給します。
ただし、栄養静脈には次のようなリスクがあるとされています。
- カテーテル挿入中に血管や神経、臓器などが傷つく
- 皮膚を切開するため感染症にかかりやすい
- 血栓の形成の可能性がある
- 肝機能障害が起きる可能性がある
- 栄養や水分のバランスが崩れやすい
このようなリスクが高まるため、入院中は医師や栄養士、薬剤師、看護師などがチームを組み、患者さんの経過を定期的に計測して確認する必要があります。
病院外で静脈栄養が行われる場合にも、看護師が定期的も訪問し問題ないことを確認します。
経腸栄養と静脈栄養の選択
栄養補給には大きく経腸栄養と静脈栄養の2つの方法がありますが、まずは経腸栄養を優先的に検討します。
経腸栄養を優先的に検討するのは、次のような理由があるからです。
まず、小腸や大腸は消化管に入ってきた食べ物を栄養源として動いているため、食べ物が入って来なくなると粘膜細胞が衰えて正常に働けなくなってしまいます。
特に小腸は食物を消化・吸収するだけに限らず、免疫機能も司っており、その割合は全身の6~7割を担っているとされています。
つまり、小腸が正常に働けなくなると、免疫力が低下して感染症を起こすリスクも跳ね上がってしまうのです。
また、経腸栄養を優先的に検討するのは、静脈栄養の疾患リスクが高いこともあります。
このような理由から特別なケースを除き、経腸栄養を第一選択とし、静脈栄養はガンや消化管の手術後などの消化管が機能していないような時に選択されるのです。
経腸栄養剤の種類
栄養を摂取する時は、腸の機能を維持したり、免疫機能を保ったりするためにできるだけ腸を使用する経腸栄養が選択されることをこれまでお話してきました。
経腸栄養を行う時に最も優先的されるのは口から食べる経口栄養ですが、腸が使えても嚥下障害や消化管の通過障害などがある場合には経管栄養が選択されます。
ここでは、経口栄養や経管栄養で使用する様々な種類の経腸栄養剤について紹介していきます。
天然濃厚流動食
天然濃厚流動食は天然の食品を原料にして製造された経腸栄養剤で、経口栄養と経管栄養のどちらにも対応しています。
最も通常の食事に近い経腸栄養剤とされ、他の種類の栄養剤よりも味や香りがよいという特徴があります。
天然濃厚流動食には、牛乳・人参・米などを使用して作られたホリカフーズの「流動食品A」という商品があり、1200mlで50~69歳日本人男性の1日当たりの食事摂取基準の目安量をおおむね充足できるとされています。
人工濃厚流動食
人工濃厚流動食は、さらに半消化態栄養剤・消化態栄養剤・成分栄養剤の3種類に分類されています。
半消化態栄養剤
半消化態栄養剤は症状が安定している方に使われるケースが多く、経口栄養と経腸栄養の両方に対応している栄養剤です。
糖質はデキストリンや白糖が、窒素源はたんぱく質加水分解物やペプチドが使用されています。
半消化態栄養剤には医薬品の製品に加えて、食品扱いの製品も販売されているのが特徴の1つと言えるでしょう。
医薬品の半消化態栄養剤は、アボットジャパンの「エネーボ配合経腸用液」や「エンシュア・H」「エンシュア・リキッド」、大塚製薬工場の「ラコールNF配合経腸用液」などが販売されています。
例えば、エンシュア・Hにはバニラ味やコーヒー味、バナナ味、ストロベリー味などをはじめとする7種類のフレーバーがあり、食事の醍醐味である味を楽しめる工夫がされています。
他の製品でも色々なフレーバーが用意されているため、好みのものを見つけていきましょう。
食品扱いの半消化態栄養剤には、明治の「メイバランス1.0」や「メイバランスR」、「インスロー」など約200種類の商品が販売されています。
これらは食品扱いではありますが、医師や薬剤師、栄養士の指導に基づいて使用することが推奨されています。
消化態栄養剤
消化態栄養剤は消化吸収機能が低下して半消化態栄養剤が使用できない時に使われる栄養剤で、窒素源にはアミノ酸やジペプチドやトリペプチドが使用されていますが、タンパク質は含みません。
小腸粘膜への負担が少なく素早く吸収されるのが特徴で、医薬品と食品の両方が販売されています。
医薬品扱いの消化態栄養剤には、主に経管栄養に使用する大塚製薬の「ツインラインNF配合経腸用液」が、食品の消化態栄養剤には経口栄養・経管栄養に使用できる大塚製薬の「ハイネックスイーゲル」、ニュートリーの「ペプチーノ」などが販売されています。
成分栄養剤
成分栄養剤の窒素源はアミノ酸、糖質はデキストリンと非常にシンプルな構造になっており、低脂肪のため脂肪乳剤を併用する必要があります。
食物繊維を含まない低残渣で高い浸透圧を持つことから、日本国内ではクローン病や短腸症候群などの時に使用される栄養剤です。
成分栄養剤は医薬品のみで、食品扱いの製品はありません。
医薬品の成分栄養剤は、EAファーマの「エレンタール」「エレンタールP」、エーザイの「ヘパンED」などが販売されています。
例えば、エレンタールはそのまま飲むこともできますが、味が苦手な場合には専用フレーバーで味をつけることも可能です。
専用フレーバーには一般的なコーヒーやオレンジなどの他にフルーツトマトやさっぱり梅など、合計10種類の味が用意されているので、好みのものを見つけてみましょう。
特殊組成経腸栄養剤
特殊組成経腸栄養剤はそれぞれの病気に適した栄養を補うための病態別経腸栄養剤と、免疫力を高める成分を配合した免疫賦活化経腸栄養剤に分類されます。
病態別経腸栄養剤には、クリニコの耐糖能障害用「DIMS」や腎機能障害用「レナジーU」、肝機能障害用の「へパスⅡ」が、肺機能障害用にはアポットジャパンの「ブルモケア-EX」などが販売されており、免疫賦活化経腸栄養剤にはアポットジャパンの「オキシーパ」や大塚製薬工場の「アノム」などがあります。
これらもキャラメルやコーヒーなどのフレーバーが用意されているので、気分に合わせて味を選んでいきましょう。
経腸栄養剤の飲み方の工夫
様々なフレーバーが用意されている経腸栄養剤ですが、それでも味が苦手だったり、飲み飽きてしまったりすることもあるかもしれません。
ここでは経腸栄養剤に変化をつけて少しでも、口に合うように変化させる工夫を3つ紹介していきます。
ただし、粘度などが変化する場合がありますので、嚥下機能に不安がある方は事前に医師に相談してからアレンジするようにしてください。
温度を変える
最も簡単にできるのが、経腸栄養剤を冷やしたり温めたりして温度を変えることです。
経腸栄養剤に氷を入れたり、冷蔵庫で冷やしたりすると、甘味が抑えられてスッキリとした味わいに変化します。
反対に、冷たい経腸栄養剤が苦手であれば温めることも可能です。
ただし、栄養成分を変化させないように温度を高くし過ぎないことがポイントです。
湯煎または温度調整ができる電子レンジで、50℃以上にならないように気を付けながら加熱してください。
形状を変える
経腸栄養剤は凍らせてシャーベット状にして食べることも可能です。
また、ゼラチンや寒天、とろみ剤などを使用して固めると食感が変化して食べやすくなります。
注意点として、エネルギー制限がある場合にはゼラチンなどに含まれるエネルギーを計算すること、食中毒を防ぐために当日中に食べられる分だけ作ることを守りましょう。
他の食品と混ぜる
経腸栄養剤をヨーグルトやココア、コーヒーなどと混ぜると風味が変わります。
特に市販のお湯で溶くタイプのコーンポタージュやかぼちゃスープなどのインスタントスープとの相性がよく、経腸栄養剤の甘味が気にならなくなります。
ただし、固まって成分が変化してしまう可能性があるのでフルーツジュースと混ぜるのは避けましょう。
また、エネルギー制限がある場合には他の食品のエネルギーも考慮するようにしてください。
経腸栄養剤は栄養摂取の強い味方
経腸栄養剤は病気や手術の影響で通常の食事を摂取するのが難しい場合に使用する、消化・吸収に優れた栄養剤です。
経腸栄養剤は口から摂取する経口栄養や、経鼻チューブや胃ろう・腸ろうから栄養剤を注入する経管栄養に使用され、食べやすいように様々なフレーバーが用意されている商品も多くあります。
栄養を摂ることは体力や免疫力の維持・向上や、病気の治癒にも大きく関わってきます。
通常の食事を取るのが難しい場合には、経腸栄養剤でしっかり栄養を充足させていきましょう。