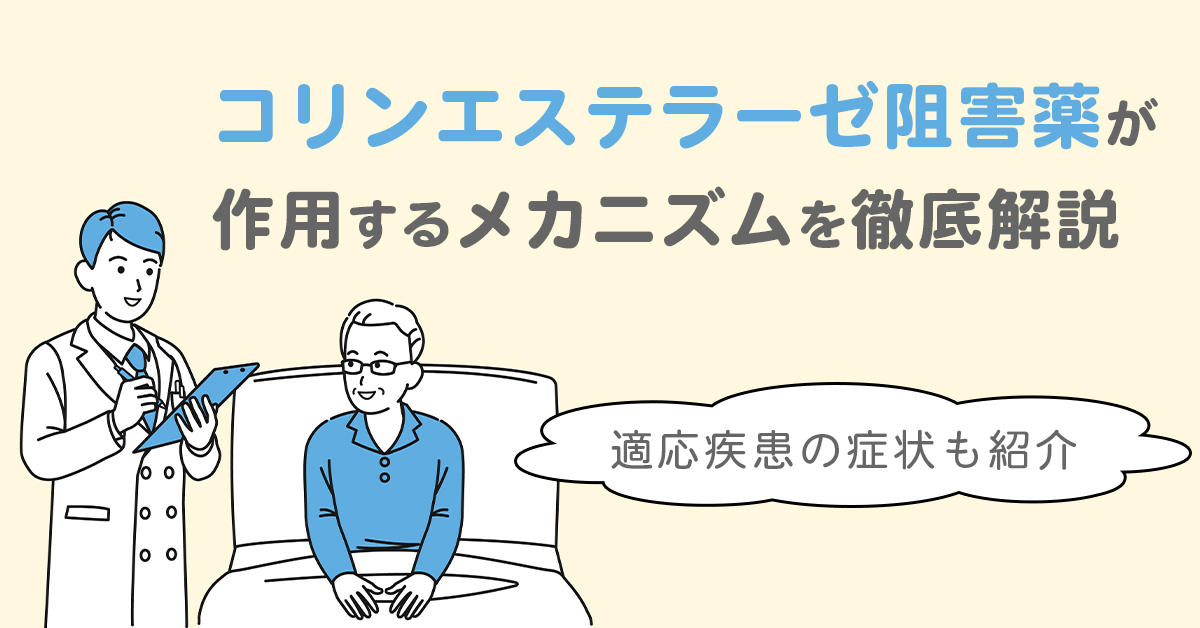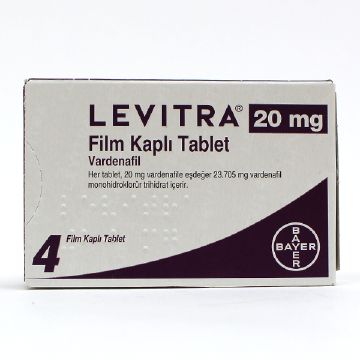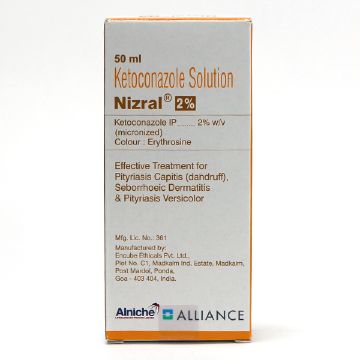「コリンエステラーゼ阻害薬ってどんな薬?」
「神経筋接合部疾患や認知症ではどんな症状が現れるの?」
このような疑問を持っている人は少なくないのではないでしょうか。
本記事では、体内で情報が伝達されるメカニズムや、コリンエステラーゼ阻害薬が効果を発揮するメカニズムについて徹底解説。
コリンエステラーゼ阻害薬が用いられている、神経筋接合部疾患や認知症についても、症状などを詳しく紹介します。
本記事を読めば、コリンエステラーゼ阻害薬や重症筋無力症・認知症について理解を深められます。
興味がある人はぜひ最後までご覧ください。
情報が伝達されるメカニズム
私たちの脳や神経は、「ニューロン」という神経細胞から構成されています。
ニューロンは情報を伝えるために必要な細胞であり、情報伝達元のニューロンと情報伝達先のニューロンの間が「シナプス間隙」です。
伝達すべき様々な情報は、ニューロン内では電気的な刺激として伝わっています。
そして、シナプス間隙においては化学的な信号へと変換され、次のニューロンへと伝達されます。
この時、活躍するのが「神経伝達物質」です。
神経伝達物質は、伝達元のニューロンから放出され、伝達先のニューロンに存在する「受容体」という場所に結合します。
受容体に結合すると情報が無事に伝わり、伝達先のニューロン内を、再び電気的な刺激として伝わっていくのです。
なお、神経伝達物質による情報の伝達が行われているのは、ニューロン同士だけではありません。
ニューロンから効果器への情報伝達も、基本的には同様のメカニズムで行われています。
(※効果器…筋肉など、神経による制御を受ける臓器や器官)
アセチルコリンとコリンエステラーゼ
神経伝達物質には数多くの物質が該当しており、アセチルコリンもそのうちの一つです。
主な作用としては以下が挙げられます。
- 骨格筋への刺激
- 自律神経系の伝達
- 認知機能
このうち、本記事で重要となる作用は「骨格筋への刺激」と「認知機能」です。
一方、コリンエステラーゼとは、アセチルコリンを分解する作用を持つ物質です。
アセチルコリンエステラーゼとも呼ばれています。
コリンエステラーゼが合成されるのは、肝臓を構成している「肝細胞」です。
以下のような疾患により、高値/低値となります。
| コリンエステラーゼ | 疾患 |
|---|---|
| 高値 | 脂肪肝、糖尿病、ネフローゼ症候群、甲状腺機能亢進症 |
| 低値 | 肝硬変、急性肝不全、低栄養(敗血症や悪性腫瘍)、有機リン中毒(農薬中毒) |
コリンエステラーゼ阻害薬が効果を発揮するメカニズム
コリンエステラーゼ阻害薬は、コリンエステラーゼの作用を阻害することで、主に以下の疾患群に対して効果を発揮します。
- 神経筋接合部疾患
- 認知症
それぞれの疾患群について見ていきましょう。
①神経筋接合部疾患
神経筋接合部とは神経と筋肉を繋ぐ場所のことであり、そこで何らかの異常が発生するのが神経筋接合部疾患です。
具体的には、重症筋無力症とランバート・イートン症候群が該当します。
まず、正常な神経筋接合部では何が起こっているのか確認しましょう。
- 筋肉を制御しているニューロン内を電気的な刺激が伝わる
- 電気的な刺激により「電位依存性カルシウムチャネル(VGCC)」という装置が開く
- チャネルを通って「カルシウムイオン」がニューロン内に流入する
- ニューロン内のカルシウムイオン濃度が十分に高くなると、シナプス間隙へアセチルコリンが分泌される
- シナプス間隙に存在するコリンエステラーゼが、分泌されたアセチルコリンの一部を分解する(分解されたアセチルコリンは再びニューロンに取り込まれ、次のアセチルコリンを作るための材料となる)
- コリンエステラーゼにより分解されなかったアセチルコリンが、筋肉に存在するアセチルコリン受容体に結合する
- アセチルコリンからの刺激により、筋肉に微小な電位が発生する
- 電位が一定以上になると筋肉が収縮する
神経筋接合部疾患がある場合、以上のメカニズムが十分に進行しません。
各疾患における異常の主な流れは以下の通りです。
| 疾患 | 異常の主な流れ |
|---|---|
| 重症筋無力症 | 免疫系の異常により「抗アセチルコリン受容体抗体」が分泌される 抗体によりアセチルコリン受容体が阻害される 十分な量のアセチルコリンが受容体に結合できない |
| ランバート・イートン症候群 | 癌細胞がVGCCを発現すると、それに対する「抗VGCC抗体」が分泌される 抗体が癌細胞表面のVGCCではなく、誤って正常なニューロンのVGCCを阻害する ニューロン内にカルシウムイオンが十分に流入できない カルシウムイオン濃度が十分に高くならず、アセチルコリン分泌が抑制される |
以上のように、重症筋無力症とランバート・イートン症候群では、神経筋接合部においてアセチルコリンが十分に作用しません。
そこで、コリンエステラーゼ阻害薬によりアセチルコリンの分解を抑制し、神経筋接合部におけるアセチルコリンの量を増やすことで、作用を増強させようとしているのです。
②認知症
認知症とひとまとめにしても、実際にはいくつかの種類に分類されます。
コリンエステラーゼ阻害薬が主に用いられているのは、アルツハイマー型認知症とレビー小体型認知症です。
アルツハイマー型認知症とレビー小体型認知症では、脳の広範囲にわたってニューロンが変性・脱落しています。
特に変性・脱落が多いのが、「マイネルト基底核」という場所のニューロンです。
マイネルト基底核のニューロンからは、本来多くのアセチルコリンが分泌されています。
分泌されたアセチルコリンの一部はコリンエステラーゼに分解され、残りは他のニューロンに届き記憶形成に深く関与しています。
しかし、認知症患者の脳ではマイネルト基底核のニューロンが変性・脱落しているため、アセチルコリンの分泌が十分ではありません。
そのうえ、正常な状態と同様にコリンエステラーゼにより分解されるため、記憶形成に関与できるアセチルコリンが減少します。
その結果、認知症の様々な症状が生じているのです。
そこで、コリンエステラーゼ阻害薬を投与するとアセチルコリンの分解が抑制され、記憶形成に関与できるアセチルコリンが保たれます。
そのため、認知症症状の一時的改善・進行抑制に繋がるのです。
コリンエステラーゼ阻害薬の適応疾患
ここからは、コリンエステラーゼ阻害薬が適応となる疾患について、症状などを見ていきましょう。
①重症筋無力症
重症筋無力症は、小児・20~40歳代の女性・50~60歳代の男性によくみられる疾患です。
症状の現れ方から、「眼筋型」と「全身型」に分けられます。
眼筋型の主な症状は、眼筋の筋力低下による眼瞼下垂(まぶたが下がってくる)と複視(物が二重に見える)です。
症状は運動により増悪、休息により改善し、朝よりも夕方で強くみられます(日内変動)。
全身型では全身の筋力が低下することで、以下のような症状がみられます。
- 顔面筋麻痺(表情を作れないなど)
- 嚥下障害
- 咀嚼障害
- 構音障害(喋りにくい)
- 易疲労性(疲れやすい)
- 重症例では呼吸筋麻痺(呼吸困難)
眼筋型と同様に、これらの症状にも日内変動がみられます。
②ランバート・イートン症候群
ランバート・イートン症候群は、40歳以上の中高年男性によくみられる疾患です。
症状は重症筋無力症とよく似ており、日内変動のある筋力低下・易疲労性がみられます。
ただし、運動により症状が増悪する重症筋無力症とは対照的に、反復運動により筋力が一時的に回復します。
ランバート・イートン症候群では、基礎疾患として悪性腫瘍を合併しているケースが多いです。
その割合は約70%と報告されており、大半が肺に発生する肺小細胞癌です。
肺小細胞癌は喫煙との関連が強い悪性腫瘍であり、増殖速度が速く、転移しやすい肺癌として知られています。
③アルツハイマー型認知症
アルツハイマー型認知症は、認知症の中で最も高い割合を占めている疾患です。
脳の萎縮の進行とともに、以下のような症状がみられます。
| 進行期 | 主な症状 |
|---|---|
| 初期(1~3年) |
・新しい事を覚えられない ・物の名前を思い出せない ・年月日の感覚が不確か |
| 中期(2~10年) |
・古い記憶も障害され始める ・自分の家を認識できなくなる ・徘徊する ・服を着られなくなる |
| 後期(8~12年) |
・記憶をほとんど失う ・意思疎通が困難になる ・肉親が誰かわからなくなる |
④レビー小体型認知症
レビー小体型認知症は、先述のアルツハイマー型認知症、脳血管障害を背景とする血管性認知症とともに、三大認知症に該当する疾患です。
以下のように多彩な症状がみられます。
| 認知機能障害 | 判断力・注意力が低下して会話がままならない。症状には日内変動があるうえ、数週間~数ヵ月間というスパンでも変動する。 |
|---|---|
| 幻視 | 人・虫・小動物がみられやすい。「知らない子どもが部屋で遊んでいる」など、具体的な幻視が多い。 |
| パーキンソニズム |
・安静時振戦(安静時に手足が震える) ・無動(動作が緩慢になる) ・筋強剛(筋肉がこわばる) ・姿勢保持障害(前かがみになりやすい、転びやすい) |
| REM睡眠行動異常 | 睡眠時に四肢・体幹の運動、大声を上げるなど。悪夢を伴うことが多い。 |
コリンエステラーゼ阻害薬の種類
コリンエステラーゼ阻害薬の主な種類は以下の通りです。
| 適応 | 薬剤 |
|---|---|
| 神経筋接合部疾患 | メスチノン、ウブレチド、マイテラーゼ、ワゴスチグミン |
| 認知症 | アリセプト、アリドネ、レミニール、イクセロン・リバスタッチ |
コリンエステラーゼ阻害薬の副作用
コリンエステラーゼ阻害薬の主な副作用は以下の通りです。
| 適応 | 副作用 |
|---|---|
| 神経筋接合部疾患 | 消化器症状(下痢、腹痛、吐き気)、骨格筋症状(ピクピクとひきつるような筋肉の収縮)など |
| 認知症 | 消化器症状(下痢、吐き気)、精神神経系症状(眠気、めまい)など |
以上のような症状がみられた場合は、悪化を防ぐためにも医療機関を受診しましょう。
まとめ:コリンエステラーゼ阻害薬で神経筋接合部疾患や認知症を治療しよう
アセチルコリンは神経伝達物質の一つであり、骨格筋への刺激や認知機能などに関与しています。
分泌の低下や受容体の阻害などにより作用が減弱すると、神経筋接合部疾患や認知症などが生じてしまいます。
そこで用いられているのが、アセチルコリンの分解を抑制するための薬剤、コリンエステラーゼ阻害薬です。
重症筋無力症やランバート・イートン症候群、アルツハイマー型認知症やレビー小体型認知症に対して使用されています。
副作用などに気を付けつつ、コリンエステラーゼ阻害薬を治療に役立てましょう。