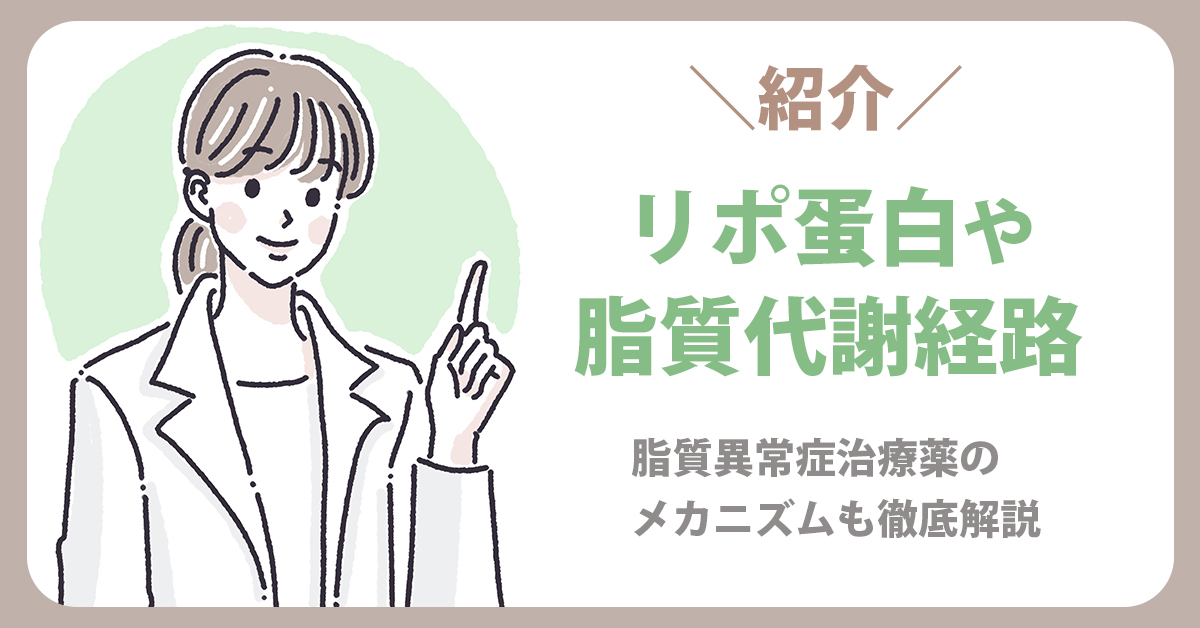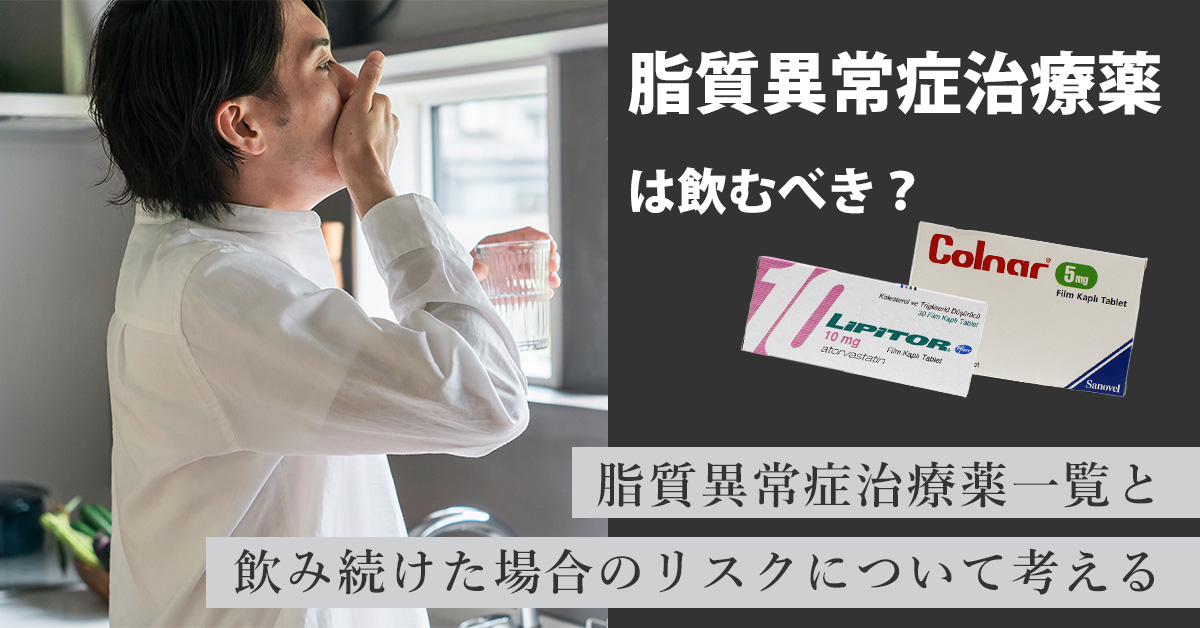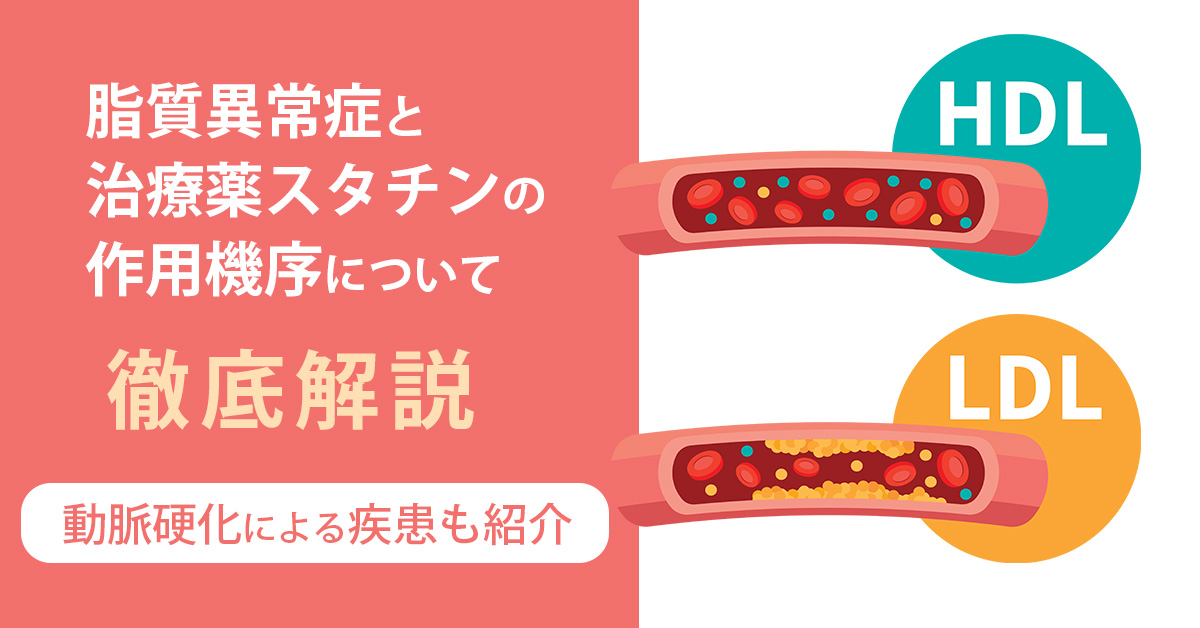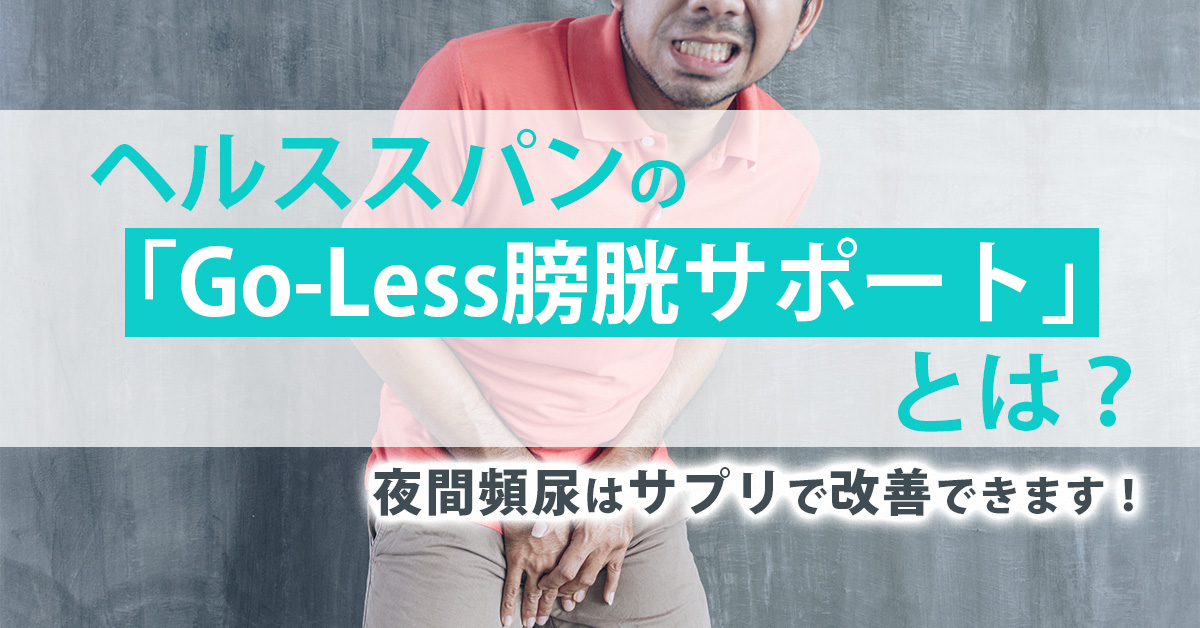「脂質やリポ蛋白って何?」
「脂質異常症の治療薬にはどんなものがあるの?」
このような疑問を持っている人は少なくないのではないでしょうか。
本記事では、リポ蛋白の種類や脂質が代謝される経路を詳しく紹介。
脂質異常症の治療薬が作用するメカニズムも徹底解説します。
本記事を読めば、脂質代謝や脂質異常症治療薬について理解を深められます。
興味がある人はぜひ最後までご覧ください。
脂質とは?
脂質は生体の構造やエネルギー代謝に大きく関わっており、私たちが生命を維持するために欠かせない物質です。
主にエネルギーのもとになる「脂肪酸」と、多くの働きを持つ「コレステロール」を基本として、以下の脂質が作られています。
| 脂質 | 構成 |
|---|---|
| 遊離脂肪酸 | 脂肪酸が遊離したもの |
| トリグリセライド(中性脂肪) | グリセロールに脂肪酸が3つ結合したもの |
| リン脂質 | グリセロールにリン酸と脂肪酸が結合したもの |
| コレステロールエステル | コレステロールに脂肪酸が結合したもの |
| 遊離コレステロール | コレステロールそのもの |
(※グリセロール…アルコールに分類される物質)
このうち、脂質代謝について理解するうえで、重要となる物質がトリグリセライドとコレステロールです。
それぞれの働きを見ていきましょう。
①トリグリセライド
トリグリセライドの役割は、生体内におけるエネルギーの貯蔵です。
主に肝臓や、脂肪細胞などに蓄えられています。
エネルギーが不足すると、「リパーゼ」という物質の働きにより、トリグリセライドがグリセロールと遊離脂肪酸に分解されます。
そして、遊離脂肪酸が「ミトコンドリア」という細胞内器官で「β酸化」という反応を受け、エネルギーとして利用されるのです。
また、グリセロールは肝臓にて、糖の一種である「グルコース」に変換され、こちらもエネルギー源として利用されます。
②コレステロール
コレステロールには主に以下のような働きがあります。
- 細胞を包む膜(細胞膜)の構成成分の一つ
- 胆汁酸(脂肪の吸収に関わる液体)の原料
- ステロイドホルモン(副腎皮質ホルモンや性ホルモンなど)の基本骨格
- 皮膚の保護(化学物質から守る、水分の過剰な蒸発を防ぐなど)
このような働きを有するコレステロールは、主に肝臓で合成される他、食事からも取り込まれています。
リポ蛋白とは?
先ほど代表的な5つの脂質を紹介しましたが、これらは全く水に溶けない「非極性脂質」と、水によく溶ける「極性脂質」に分類されます。
具体的には、遊離脂肪酸が極性脂質であり、トリグリセライドとコレステロールエステルが非極性脂質です。
非極性脂質は水に溶けないため、そのままでは血液中に存在できません。
そこで、「アポ蛋白」や極性脂質に包まれた形で血中に存在します。
この結合体こそがリポ蛋白です。
リポ蛋白=アポ蛋白+脂質
アポ蛋白には様々な種類があり、リポ蛋白の構造を維持するために必要な物質です。
リポ蛋白が細胞に取り込まれる際や、リポ蛋白に含まれる脂質の代謝にも重要な役割を果たしています。
リポ蛋白の種類
リポ蛋白は、含まれているアポ蛋白の種類や脂質の比率の違いから、以下の5種類に分類されます。
| リポ蛋白 | 特徴 |
|---|---|
| CM | トリグリセライドが約8割を占める、最も密度が小さい |
| VLDL | トリグリセライドが半分以上を占める |
| IDL | VLDLとLDLの中間 |
| LDL | コレステロールが約半分を占める |
| HDL | アポ蛋白が約半分を占める、密度が最も大きい |
詳しいメカニズムは次の見出しで解説しますが、LDLには動脈硬化を促進する作用、HDLには抑制する作用があります。
動脈硬化とは、動脈が硬くなって弾力性が失われた状態のことであり、脳梗塞や心筋梗塞などのリスクを高める因子です。
そのため、LDLに含まれるコレステロールは「悪玉コレステロール」、HDLに含まれるコレステロールは「善玉コレステロール」とも呼ばれています。
脂質代謝経路
脂質代謝は以下の3つの経路で行われています。
| 脂質代謝経路 | 主に関与するリポ蛋白 |
|---|---|
| 外因性経路(食事由来) | CM |
| 内因性経路(組織由来) | VLDL、IDL、LDL |
| コレステロール逆転送系 | HDL |
それぞれの経路について見ていきましょう。
①外因性経路(食事由来)
食事により外因性に摂取された脂質は小腸にて吸収され、CMとして血中に入ります。
CMは、身体の各組織に分配されてエネルギー源となったり、不足時にすぐ使えるように貯蔵されたりします。
その後、余ったCMが肝臓に取り込まれ、食事由来の外因性経路は終了です。
②内因性経路(組織由来)
肝臓では、トリグリセライドとコレステロールからVLDLが合成されます。
合成されたVLDLは血中に放出され、「LPL」という物質の作用によりIDLに変化し、その後「HL」という物質の作用によりLDLに変化します。
LDLの主要な作用は、末梢組織への遊離脂肪酸やコレステロールの供給です。
末梢の細胞に存在する「LDL受容体」という部位を介して、これらの物質を細胞内に届けます。
また、肝臓にもLDL受容体が存在し、余ったIDLやLDLの一部が受容体を通して肝臓に戻っています。
しかし、残りのLDLは肝臓に戻らずに動脈の内壁に蓄積し、動脈硬化の原因となるのです。
③コレステロール逆転送系
コレステロール逆転送系は、善玉コレステロールであるHDLが活躍する経路です。
HDLは、末梢組織から余分なコレステロールを回収し、内因性経路のVLDLなどに再分配(逆転送)します。
一部のHDLは、肝臓に存在する受容体の「SR-B1」などを介して、肝臓に取り込まれ代謝されます。
そして、再分配により回収したコレステロールが減少したHDLは、再び余分なコレステロールの回収に向かうのです。
このようなHDLの作用により、末梢組織の余分なコレステロールが無くなると、LDLが余りにくくなり、結果として動脈硬化を抑制します。
脂質異常症とは?
脂質異常症とは、以下の3つの状態を総称する病態です。
| 状態 | 基準値 |
|---|---|
| 高LDLコレステロール血症 | LDLコレステロール:140mg/dL以上 |
| 低HDLコレステロール血症 | HDLコレステロール:40mg/dL未満 |
| 高トリグリセライド血症 | トリグリセライド:150mg/dL以上 |
以前は、血中コレステロールや血中トリグリセライドの異常高値を「高脂血症」と呼んでいました。
そこに、HDLコレステロールの異常低値などを加えて、2007年より脂質異常症と呼ばれています。
脂質異常症の原因
脂質異常症の原因は様々であり、複数の要因が関与し合っているケースが多いです。
代表的な原因としては以下が挙げられます。
| 分類 | 原因 |
|---|---|
| 原発性 | ・遺伝子異常 ・家族性脂質異常症 |
| 続発性(二次性) | ・生活習慣の乱れ(過食、運動不足、喫煙など) ・基礎疾患(糖尿病など)によるもの ・薬物によるもの |
脂質異常症の治療
脂質異常症には自覚症状がほとんどありません。
しかし、放置すると動脈硬化が進行し、脳梗塞や心筋梗塞などの重大な疾患の発症リスクを高めてしまいます。
そのため、動脈硬化の予防・伸展の阻止・退縮を目的として、脂質異常症の治療が行われます。
脂質管理目標値を設定し、始めに取り組むのが生活習慣の改善です。
具体的には以下を行います。
- 禁煙
- 過食せず適正な体重を維持する
- 肉の脂身、動物脂、鶏卵、果糖を含む加工食品を大量摂取しない
- 魚、野菜、海藻、大豆製品、未精製穀類の摂取量を増やす
- 糖質含有量の少ない果物を適度に摂取する
- アルコールを過剰摂取しない
- 有酸素運動(ジョギング、ウォーキング、サイクリングなど)を毎日合計30分以上行う
以上のような生活習慣の改善に3~6ヵ月間取り組んでも、脂質管理目標値に到達しない場合に薬物治療が行われます。
薬物治療中も、生活習慣の改善は並行して行います。
脂質異常症の治療薬:①高コレステロール血症治療薬
脂質異常症の治療薬のうち、高コレステロール血症治療薬として以下が使用されています。
- HMG-CoA還元酵素阻害薬(スタチン)
- 小腸コレステロールトランスポーター阻害薬(エゼチミブ)
- 陰イオン交換樹脂(レジン)
- プロブコール
- PCSK9阻害薬
それぞれが作用するメカニズムを見ていきましょう。
①HMG-CoA還元酵素阻害薬(スタチン)
肝臓では、「アセチルCoA」という物質を原料として、コレステロールが合成されています。
合成する物質の経路は以下の通りです。
アセチルCoA → HMG-CoA → メバロン酸 → コレステロール
以上の経路の中で、HMG-CoA→メバロン酸の反応を進めるためには、「HMG-CoA還元酵素」という酵素が必要です。
スタチンは、このHMG-CoAを阻害し、コレステロールの合成を抑制します。
コレステロールの合成が抑制されると、肝臓内のコレステロール量が減少し、補うために肝臓におけるLDL受容体が増加します。
その結果、肝臓に取り込まれるLDLが増加し、血中のLDLが減少するのです。
②小腸コレステロールトランスポーター阻害薬(エゼチミブ)
食物に含まれるコレステロールは、小腸の壁細胞に存在する「NPC1L1」という部位を介して、体内に取り込まれます。
エゼチミブは、NPC1L1に結合することで小腸でのコレステロール吸収を阻害する薬剤です。
小腸で吸収されるコレステロール量が減ると、肝臓に送られるコレステロールが減少し、補うために肝臓におけるLDL受容体が増加します。
その結果、肝臓に取り込まれるLDLが増加し、血中のLDLが減少するのです。
③陰イオン交換樹脂(レジン)
コレステロールを原料の一部としている胆汁酸は、小腸で再吸収されます。
レジンは、腸管内で胆汁酸と結合することで小腸からの再吸収を抑制する薬剤です。
吸収されなかった胆汁酸は便中へ排泄されるため、原料であるコレステロールも排泄されることとなります。
コレステロールの排泄が進むと、肝臓に運ばれるコレステロールが減少し、なおかつ胆汁酸の原料としてコレステロールの消費が亢進します。
その結果、補うために肝臓におけるLDL受容体が増加し、血中のLDLが減少するのです。
④プロブコール
プロブコールは、胆汁酸の原料としてコレステロール消費を亢進させる作用と、アセチルCoAから始まるコレステロール合成を抑制する作用を主に有しています。
その結果、肝臓に取り込まれるLDLが増加し、血中のLDLが減少するのです。
また、LDLが動脈硬化を引き起こすのは、LDL自身が酸化反応を受け、「マクロファージ」という細胞に貪食されて過剰に蓄積するためと考えられています。
プロブコールには、LDLの酸化を抑制する作用もあり、2つのメカニズムでLDLによる動脈硬化を防いでいます。
⑤PCSK9阻害薬
PCSK9とは、主に肝臓で生成される酵素です。
PCSK9はLDL受容体に結合し、肝臓におけるLDL受容体の分解を促進する作用があります。
PCSK9阻害薬は、そんなPCSK9の作用を阻害する薬剤です。
PCSK9の作用が阻害されると、LDL受容体の分解が抑制されて数が増加します。
その結果、肝臓に取り込まれるLDLが増加し、血中のLDLが減少するのです。
脂質異常症の治療薬:②高トリグリセライド血症治療薬
脂質異常症の治療薬のうち、高トリグリセライド血症治療薬として以下が使用されています。
- フィブラート系薬剤
- オメガ-3系多価不飽和脂肪酸
- ニコチン酸誘導体
それぞれが作用するメカニズムを見ていきましょう。
①フィブラート系薬剤
フィブラート系薬剤は、「PPARα」という受容体を活性化することで、以下のような作用を発揮します。
- 肝臓でのトリグリセライドの合成を抑制する
- 血中のLPLやHLを増加/活性化させ、リポ蛋白内のトリグリセライド分解を促進する
- 小腸や肝臓に働きかけ血中のHDLを増加させる
以上の作用を持つフィブラート系薬剤は、高トリグリセライド血症治療薬の中でも、最も効率的に血中トリグリセライドを低下させます。
②オメガ-3系多価不飽和脂肪酸
オメガ-3系多価不飽和脂肪酸には、具体的に以下の物質が該当します。
- イコサペント酸エチル(EPA-E)
- ドコサヘキサエン酸エチル(DHA-E)
EPAやDHAを多く含む魚をよく食べる民族に、脂質異常症や動脈硬化の発症が少ないことが知られており、そこから薬剤開発のヒントを得たとされています。
オメガ-3系多価不飽和脂肪酸には、肝臓でのVLDL産生を抑制する作用があります。
VLDLはトリグリセライドが半分以上を占めるリポ蛋白であるため、血中のトリグリセライド低下に繋がるのです。
③ニコチン酸誘導体
ニコチン酸誘導体には、遊離脂肪酸の産生を抑制する作用と、LPLの活性化を促進する作用があります。
その結果、血中のトリグリセライドが減少します。
ニコチン酸誘導体を使用するうえで、注意すべき点が副作用です。
血管が拡張することにより、顔面紅潮や頭痛、強い痒みなどが生じる可能性があります。
まとめ:脂質異常症治療薬で動脈硬化の発症・進展を防ごう
脂質は私たちが生きていくうえで欠かせない物質であり、トリグリセライドやコレステロールなどが該当します。
しかし、血中濃度が過剰に高くなると、動脈硬化の原因となり脳梗塞や心筋梗塞などの発症リスクを高めてしまいます。
そこで用いられるのが、高コレステロール血症治療薬や高トリグリセライド血症治療薬です。
作用するメカニズムを押さえつつ、脂質異常症を治療して動脈硬化の発症や伸展を防ぎましょう。