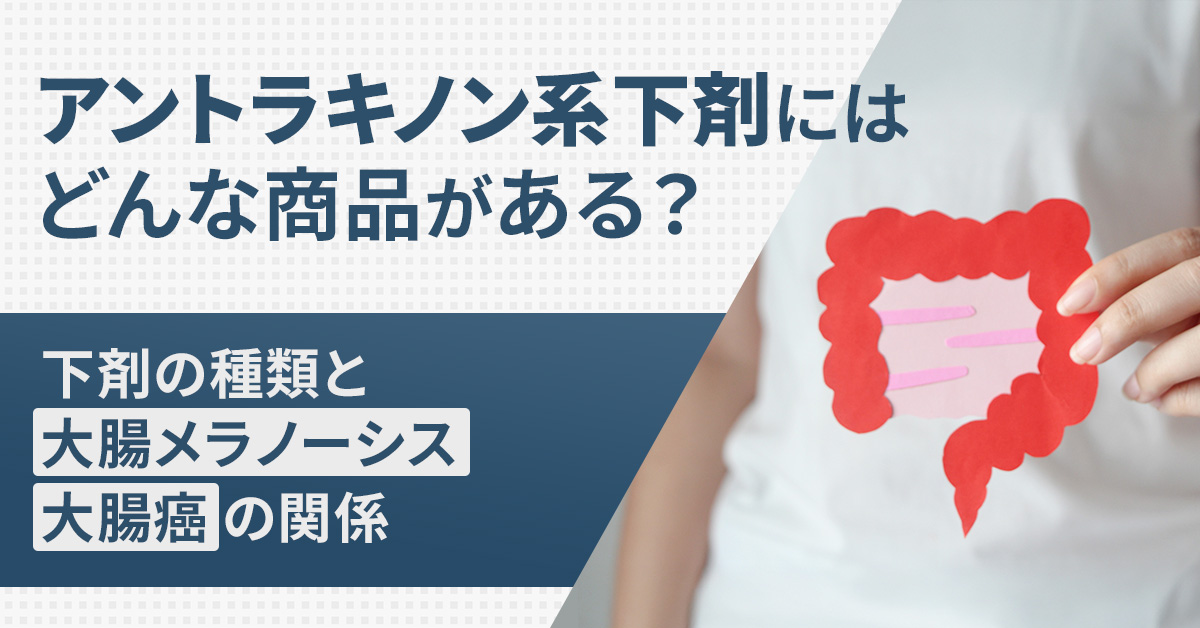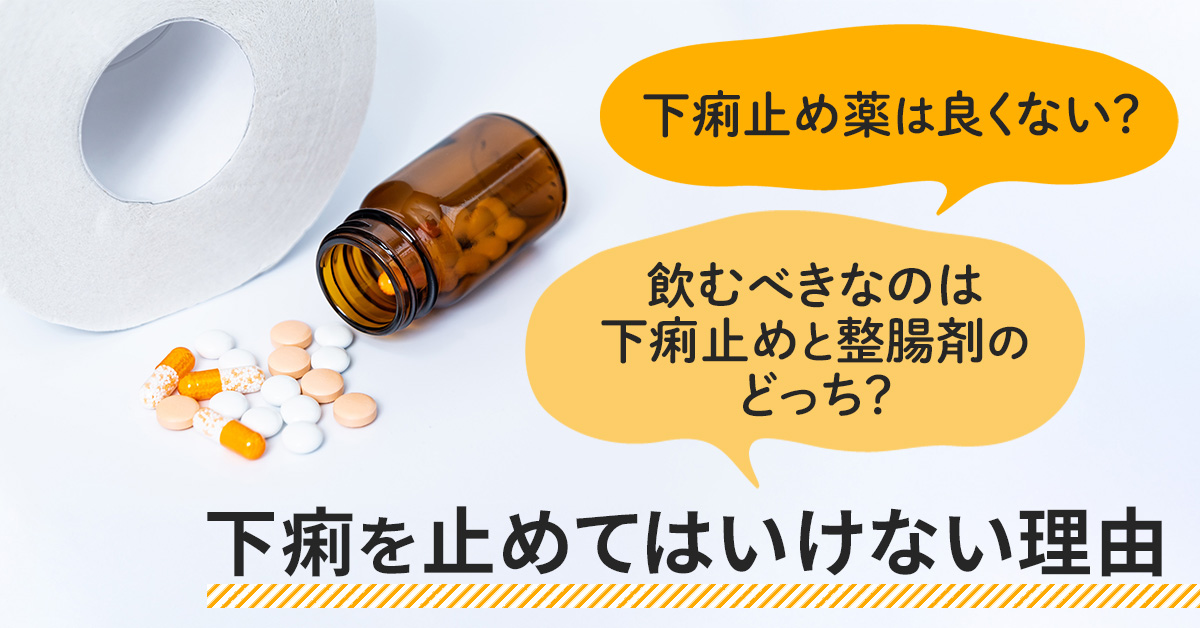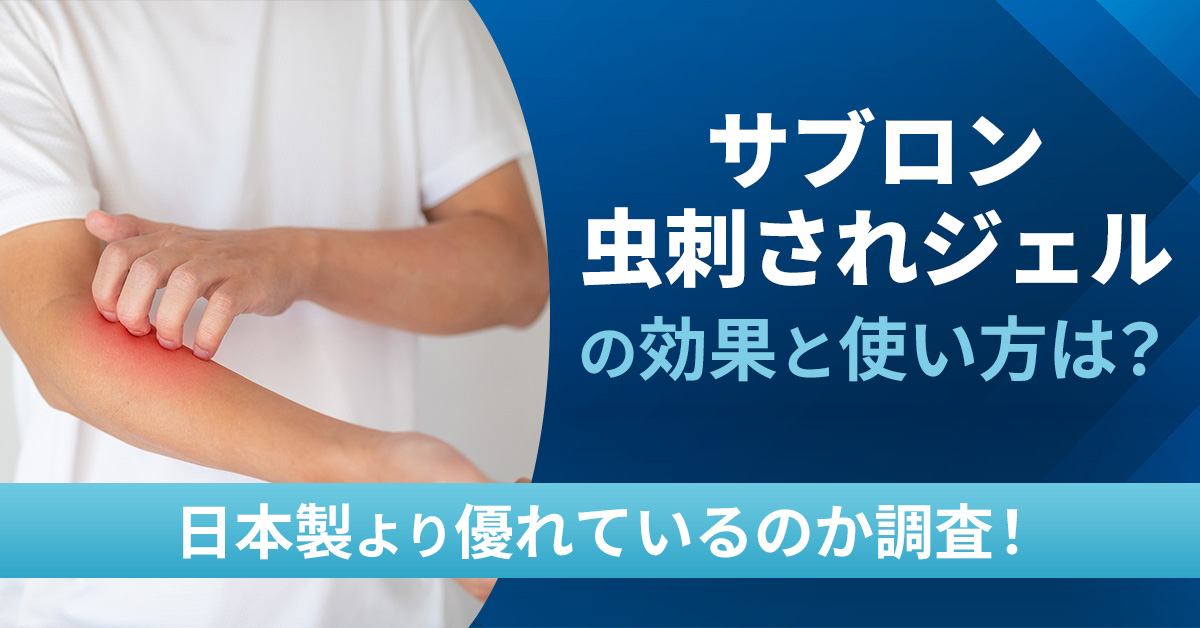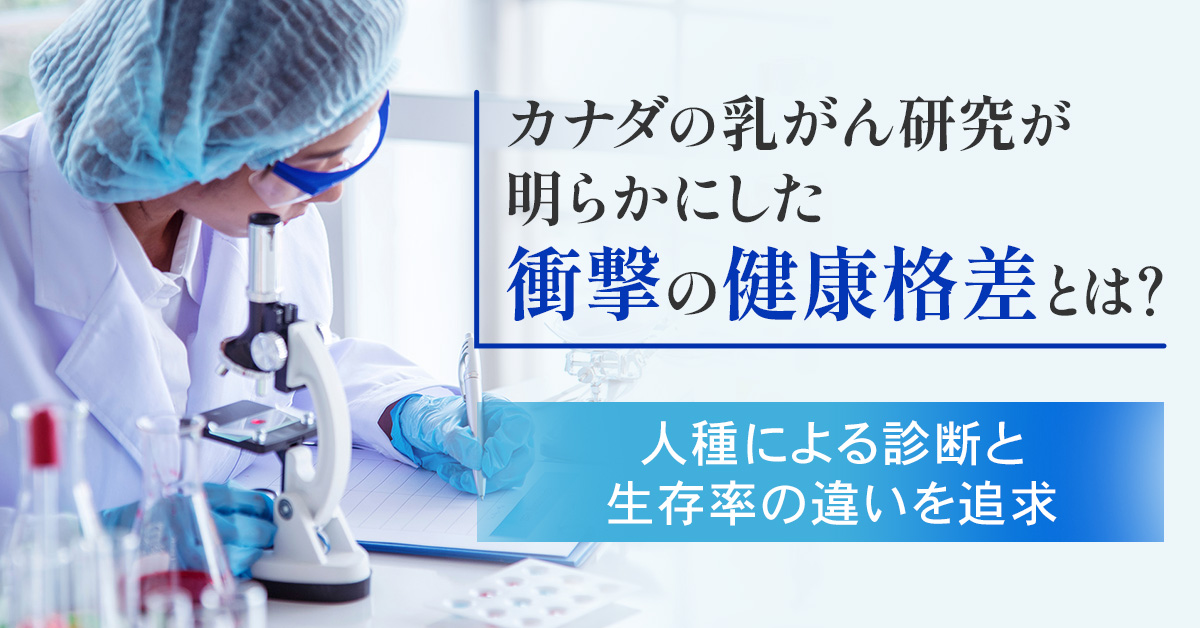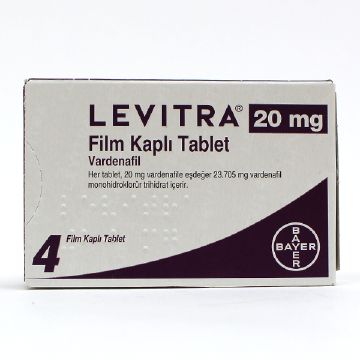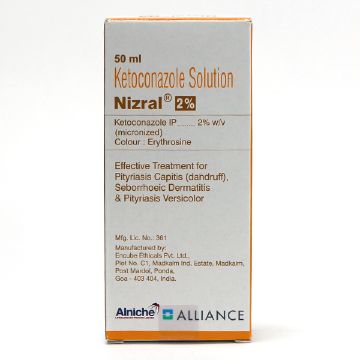「炎症性腸疾患ってどんな病気なの?」
「5-ASAが炎症性腸疾患を治療するメカニズムは?」
このような疑問を持っている人は少なくないのではないでしょうか。
本記事では、炎症性腸疾患である潰瘍性大腸炎とクローン病について詳しく紹介。
5-ASAが炎症性腸疾患に対して作用するメカニズムや、5-ASAとSASPの違いについても徹底解説します。
本記事を読めば、潰瘍性大腸炎/クローン病や5-ASAのメカニズムについてよくわかります。
興味がある人はぜひ最後までご覧ください。
5-ASAは炎症性腸疾患の治療薬
5-ASAは「メサラジン」という薬剤の別名であり、「アミノサリチル酸製剤」に該当する薬剤です。
アミノサリチル酸製剤には、5-ASAの他に「サラゾスルファピリジン(別名SASP)」が該当します。
これらのアミノサリチル酸製剤は、炎症性腸疾患に対する最も基本的な治療薬です。
特に、軽症~中等症のケースに対して用いられています。
まずは、炎症性腸疾患について見ていきましょう。
炎症性腸疾患とは?
私たちが摂取した食物は、消化管と呼ばれる管を通って消化・吸収されています。
具体的な経路は以下の通りです。
口腔 → 食道 → 胃 → 十二指腸 → 空腸 → 回腸 → 盲腸 → 結腸 → 直腸 → 肛門
このうち、十二指腸・空腸・回腸が小腸に、盲腸・結腸・直腸が大腸に該当します。
炎症性腸疾患とは、体内に備わっている免疫システムの異常により、慢性的な炎症が小腸・大腸を中心に発生する疾患です。
具体的には、以下の2疾患が炎症性腸疾患に該当します。
- 潰瘍性大腸炎
- クローン病
どちらも再燃(再び悪化)と寛解(良くなる)を繰り返すなど、共通点が多い両疾患ですが、異なる点も少なくありません。
それぞれの疾患について見ていきましょう。
①潰瘍性大腸炎
潰瘍性大腸炎は、10歳代後半から30歳代前半にかけてよく起こる疾患です。
病変は直腸から始まり、大腸にて連続的に広がっています。
発症要因としては、様々な遺伝子因子やストレスなどの心理学的因子の他、以下のような環境因子が考えられています。
- 高脂質/高糖質の食事
- 細菌/ウイルス感染
- 腸内細菌叢の変化
- 薬物(NSAIDsや経口避妊薬など)
ここで、腸内細菌叢について少し解説を加えましょう。
ヒトの腸管内には500~1000種類、総数100兆個にも及ぶ細菌が存在しており、腸内細菌叢という群を形成しています。
健康的な状態においては、腸内細菌叢と腸管の免疫システムが互いに制御しあっています。
しかし、腸内細菌叢は食生活の乱れや慢性的なストレスなどで変化しやすいです。
その結果、腸内細菌叢と腸管の免疫システムのバランスが崩れ、過剰な免疫応答を引き起こします。
そして、過剰な免疫応答による腸管の炎症により、腸内細菌叢はさらに変化してしまうのです。
このような悪循環により、潰瘍性大腸炎の発症要因となり得ます。
潰瘍性大腸炎の主要な症状は以下の通りです。
- 繰り返す粘血便
- 下痢
- 腹痛
- 発熱
- 体重減少
- しぶり腹(腹痛を伴う便意を繰り返すも、少量の排便があるのみで残便感が生じる状態)
このうち、最初にみられる症状として多いのが粘血便です。
潰瘍性大腸炎において、特に注意すべき合併症は以下の2つです。
- 中毒性巨大結腸症
- 大腸癌
中毒性巨大結腸症とは、潰瘍性大腸炎の重症例で合併するケースのある重篤な病態です。
腸管が著しく拡張し、穿孔する(穴が開く)危険性があります。
そのため、中毒性巨大結腸症を合併した場合は、原則として緊急手術(大腸全摘)が行われます。
大腸癌の発癌リスクは、潰瘍性大腸炎の長期経過例にて高くなります。
その他、若年発症した症例や家族歴のある症例にて発癌しやすいです。
通常の大腸癌と比較すると多発しやすいことがわかっており、症状が安定していても定期的に内視鏡検査などを受けなければなりません。
②クローン病
クローン病は、10歳代後半から20歳代にかけてよく起こる疾患です。
病変は消化管のどの部位にも発生する可能性がありますが、特に回盲部(回腸→盲腸の移行部)に好発します。
病変が連続的に広がっている潰瘍性大腸炎とは対照的に、非連続的に形成されている点も特徴的です。
発症要因としては、様々な遺伝子因子の他、以下のような環境因子が考えられています。
- 高脂質/高糖質の食事
- 喫煙
- 細菌/ウイルス感染
- 腸内細菌叢の変化
- 薬物(NSAIDsや経口避妊薬など)
喫煙は発症だけでなく再燃の危険因子でもあるため、禁煙がとても重要です。
クローン病の主要な症状は以下の通りです。
- 腹痛(特に右下腹部)
- 下痢
- 発熱
- 体重減少
このうち、最初にみられる症状として多いのが腹痛や下痢です。
クローン病において、特に頻度が高い合併症が肛門病変です。
具体的には、以下のような症状がよくみられます。
| 肛門周囲膿瘍 | 肛門に感染が起こり膿瘍(膿が溜まったもの)を形成する |
|---|---|
| 痔瘻 | 肛門周囲膿瘍が破れ周囲の皮膚から膿が漏れ出す |
| 裂孔 | いわゆる切れ痔 |
これらの肛門病変は治りにくく、再発を繰り返しやすいです。
5-ASAが作用するメカニズム
5-ASAが炎症性腸疾患に対して、治療効果を発揮するメカニズムは以下の通りです。
- 活性酸素の除去
- ロイコトリエンの生成抑制
それぞれのメカニズムについて見ていきましょう。
①活性酸素の除去
活性酸素とは、呼吸により生体内に取り込まれた酸素が、通常状態よりも活性化した物質です。
具体的には、以下の物質が活性酸素に該当します。
- 一重項酸素
- スーパーオキシド
- 過酸化水素
- ヒドロキシラジカル
これらの活性酸素は様々な炎症細胞から放出され、炎症の伸展・組織の障害に関わっています。
そのため、5-ASAにて活性酸素の除去を行うことで、炎症性腸疾患を治療できるのです。
②ロイコトリエンの生成抑制
活性酸素と同じく、ロイコトリエンも炎症に大きく関わる物質です。
ロイコトリエンは、「アラキドン酸カスケード」という過程を経て、生体内で合成されています。
アラキドン酸とは、脂質の主要な構成要素である脂肪酸の一種です。
ヒトの細胞を覆う細胞膜の構成要素「リン脂質」から遊離し、「LOX」という物質の働きかけにより、アラキドン酸からロイコトリエンが生成されます。
また、アラキドン酸には「COX」をはじめとする他の物質も働きかけており、様々な物質が生成されています。 この一連の過程がアラキドン酸カスケードです。
5-ASAには、アラキドン酸カスケードを阻害する働きがあります。
そのため、ロイコトリエンの生成を抑制し、炎症性腸疾患を治療できるのです。
5-ASAとSASPの違い
5-ASAとSASPはいずれもアミノサリチル酸製剤に該当する薬剤ですが、構造や作用する場所について違いがあります。
それぞれの薬剤について見ていきましょう。
①5-ASA
5-ASAをそのまま投与すると、腸管に達する前に吸収されてしまい、腸で抗炎症作用を発揮できません。
そのため、5-ASAを腸で溶け出すように工夫した腸溶剤が開発されました。
具体的には以下の3つです。
- ペンタサ
- アサコール
- リアルダ
ペンタサは、「エチルセルロースフィルム」という物質で5-ASAを覆っています。
小腸から大腸にかけて5-ASAが放出されるため、小腸・大腸のいずれの病変に対しても有効です。
アサコールとリアルダは、「高分子ポリマー」という物質で5-ASAを覆っています。
回腸の末端から大腸にかけて5-ASAが放出されるため、主に大腸の病変に対して有効です。
②SASP
SASPとは、病変部位での濃度を高めるために、5-ASAと「スルファピリジン」という物質を結合させた薬剤です。
SASPは大腸に入り、腸内細菌の作用により5-ASAとスルファピリジンに分解されます。
5-ASAは、スルファピリジンと結合した状態では作用せず、分解されるとようやく作用し始めます。
つまり、抗炎症効果を十分に保持したままであるため、大腸で効果を発揮できるのです。
なお、SASPのように体内で活性化される薬剤のことを、「プロドラッグ」と呼びます。
5-ASAの主な副作用
5-ASAの主な副作用は以下の通りです。
- 消化器症状(下痢・腹痛・吐き気など)
- 発熱
- 頭痛
- 関節痛
- 倦怠感
また、稀ではあるものの間質性肺炎をきたす恐れもあります。
間質性肺炎は肺炎の一種であり、呼吸困難や咳、発熱などが生じる疾患です。
5-ASAの使用中にこれらの症状が生じた際は、悪化を防ぐためにも医療機関を受診し、医師に相談しましょう。
まとめ:5-ASAで炎症性腸疾患を治療しよう
炎症性腸疾患とは、体内に備わっている免疫システムの異常により、慢性的な炎症が小腸・大腸を中心に発生する疾患です。
潰瘍性大腸炎やクローン病が該当し、腹痛・下痢・発熱などの症状を引き起こします。
治りにくいケースが多く、再燃と寛解を繰り返す点が特徴です。
炎症性腸疾患の基本的な治療薬が、腸管で抗炎症作用を発揮する5-ASAです。
副作用には注意しつつ、5-ASAで潰瘍性大腸炎やクローン病を治療しましょう。