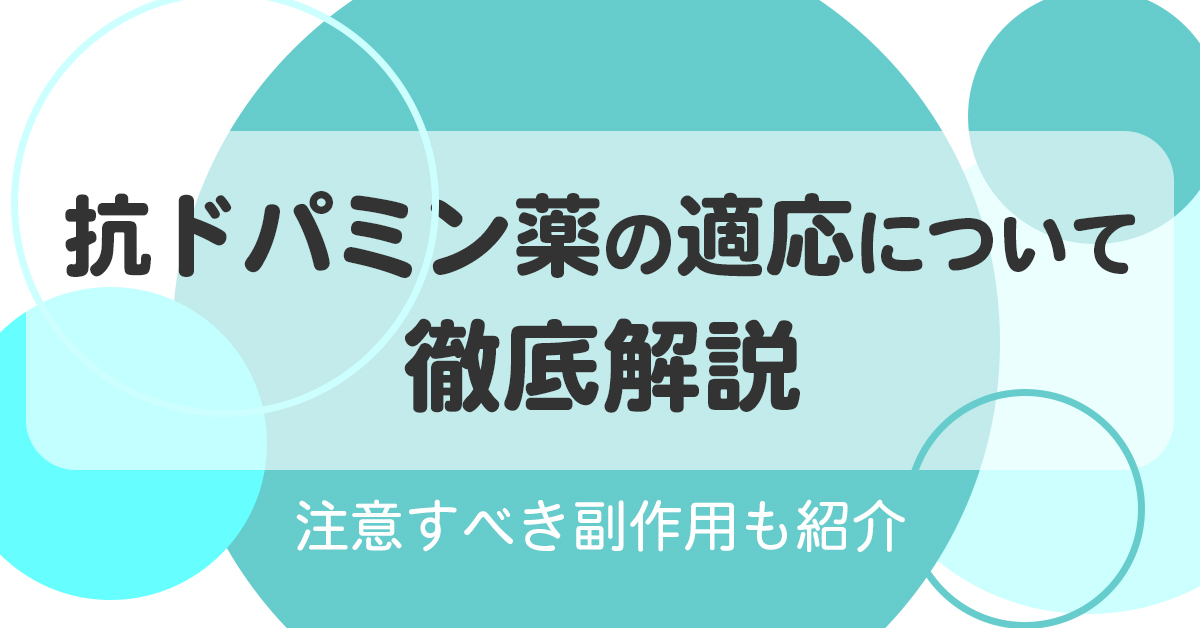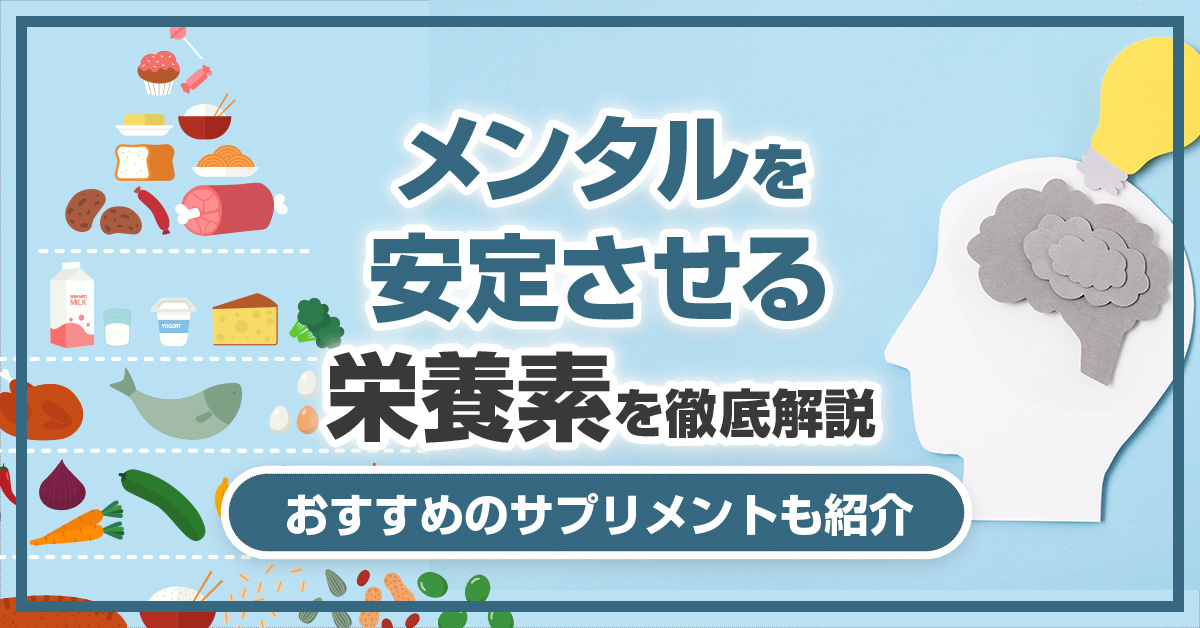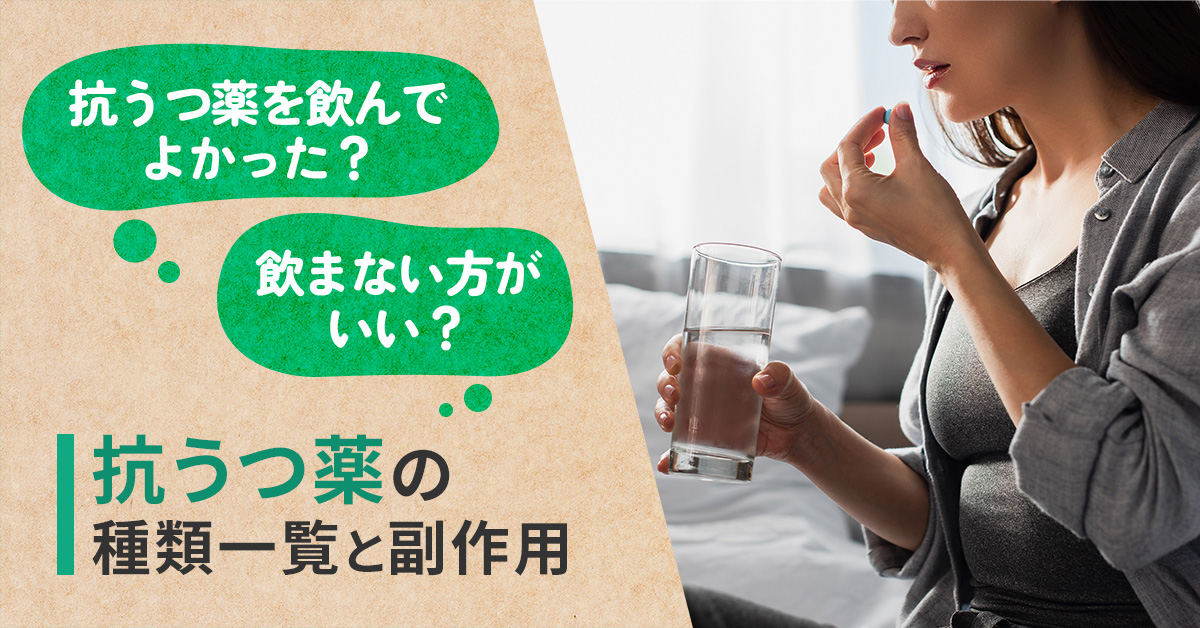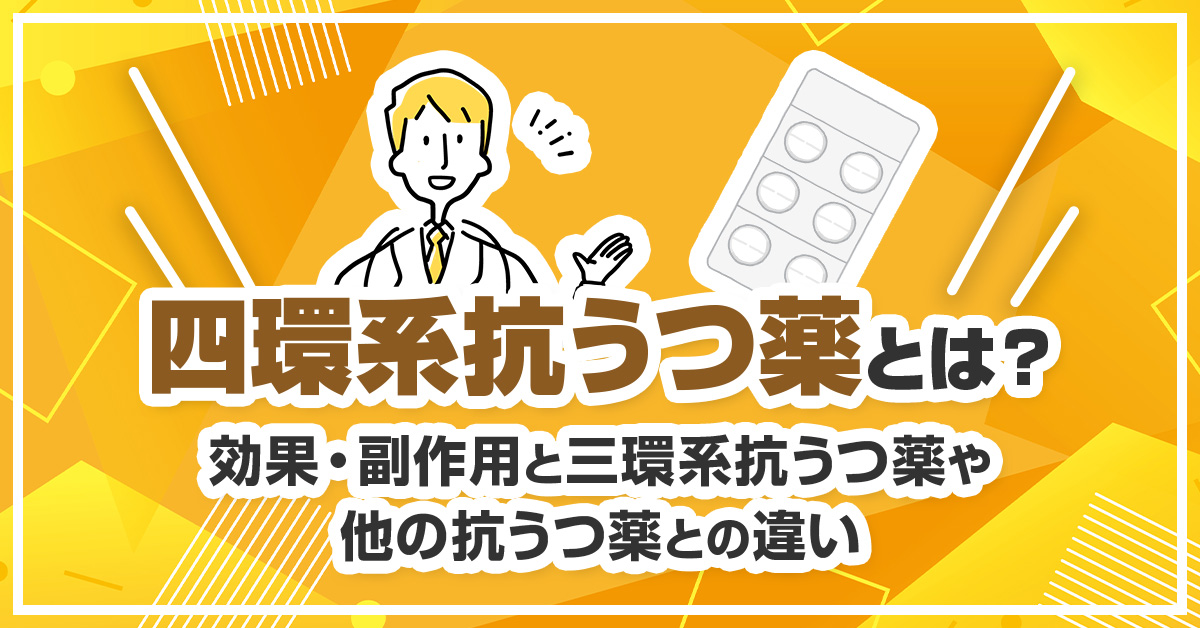「ドパミンってどのような物質?」
「抗ドパミン薬はどんな目的で使用されているの?」
このような疑問を持っている人は少なくないのではないでしょうか。
本記事では、抗ドパミン薬の適応となる統合失調症の治療・消化管運動の改善について徹底解説。
ドパミンそのものの作用や、抗ドパミン薬の副作用についても紹介しています。
本記事を読めば、ドパミンの作用や抗ドパミン薬について理解を深められます。
興味がある人はぜひ最後までご覧ください。
ドパミンとは?
ドパミンとは、神経を構成する細胞が情報を伝達する際に活躍している、神経伝達物質の一種です。
脳内報酬系(私たちが快感を得るシステム)の活性化をはじめ、生体内で様々な作用を有しています。
ドパミンは、「カテコールアミン」と呼ばれるホルモンの一種でもあります。
カテコールアミンとは、「副腎髄質」という臓器でアミノ酸の「チロシン」を原料として合成される、いくつかのホルモンの総称です。
具体的には、以下のルートで合成されています。
チロシン → ドーパ → ドパミン → ノルアドレナリン → アドレナリン
以上のうち、ドパミン・ノルアドレナリン・アドレナリンがカテコールアミンに該当します。
ドパミンの主な作用
ドパミンには様々な作用があり、本記事でその全てを取り上げることはできません。
そこで今回は、抗ドパミン薬が適応となる疾患や副作用に関する、ドパミンの主な作用について取り上げます。
- 神経経路で作用する
- アセチルコリンに拮抗する
- プロラクチンの分泌を抑制する
それぞれ見ていきましょう。
①神経経路で作用する
神経経路とは、脳内で様々な情報を伝えるための経路のことです。
ドパミンは主に、以下の神経経路で作用しています。
| 神経経路 | 主要な役割 |
|---|---|
| 黒質線条体路 | 運動機能の調節 |
| 中脳辺縁系路・中脳皮質路 | 脳内報酬系(アルコールや依存性薬物により活性化される) |
このうち、黒質線条体路はパーキンソン病と、中脳辺縁系路・中脳皮質路は統合失調症と関連しています。
②アセチルコリンに拮抗する
私たちの身体では、交感神経と副交感神経という2つの自律神経が働いています。
このうち、副交感神経が働くうえで欠かせない物質が「アセチルコリン」です。
ドパミンには、アセチルコリンに拮抗し、副交感神経の働きを抑制する作用があります。
③プロラクチンの分泌を抑制する
プロラクチンはホルモンの一種であり、主な働きは以下の通りです。
- 乳腺の発育促進
- 乳汁産生/分泌促進
- 性腺機能抑制
ドパミンは、以上のような働きを持つプロラクチンの分泌を抑制します。
抗ドパミン薬の適応:(1)統合失調症の治療
抗ドパミン薬は、精神疾患である統合失調症の治療に用いられています。
統合失調症について、以下の観点から解説していきます。
- 発症するメカニズム
- 疫学(発症頻度や分布)
- 原因/リスク因子
- 症状
- 経過
それぞれ見ていきましょう。
①発症するメカニズム
統合失調症を発症するメカニズムについて、詳細は未だ解明されていません。
しかし、有力と考えられるいくつかの仮説があり、最も研究されているものがドパミン仮説です。
ドパミン仮説によれば、統合失調症患者の前頭葉(脳内のエリア)ではドパミン機能が低下し、皮質下(同じく脳内のエリア)ではドパミン機能が亢進しています。
そのため、抗ドパミン薬が統合失調症に対して効果を発揮していると考えられています。
②疫学(発症頻度や分布)
統合失調症の生涯有病率(一生のうちに発症する確率)は、全世界的に人口の0.7~1%と報告されています。
100人に1人弱が発症する確率であるため、頻度の高さを意外に思われる方もいらっしゃるのではないでしょうか。
生涯有病率を性別で比較すると、男性の方がわずかながら高いとされています。
発症の平均年齢は女性で20代前半~半ば、男性ではもう少し若年であり、約40%が20歳未満で発症しています。
③原因/リスク因子
統合失調症の正確な原因は未だ不明です。
現時点では、遺伝的な要因と環境的な要因が組み合わさって発症すると考えられています。
統合失調症の発症リスクを高める因子としては以下が挙げられます。
- 都市部での生活
- 移民
- 貧困
- 幼少期の心的外傷
- 虐待/ネグレクト
- 出生前の感染症
- 物質依存(アルコール依存や薬物依存など)
④症状
統合失調症でみられる症状は、以下の4つに大別されます。
- 陽性症状(本来はあるべきではないものが現れる症状)
- 陰性症状(本来はあるべきものが現れない症状)
- 解体症状(陽性症状の一種とも考えられている)
- 認知症状(認知機能の異常)
以上のうち、1カテゴリーの症状のみがみられるケースもあれば、全カテゴリーの症状がみられるケースもあります。
それぞれのカテゴリーでは、具体的に以下のような症状がみられます。
| カテゴリー | 症状 |
|---|---|
| 陽性症状 | ・妄想(自分は尾行されている、他者に自分の思考を読み取られているなど) ・幻覚(幻聴が最も多い) |
| 陰性症状 | ・感情鈍麻(顔の動きが乏しくなる) ・発語の乏しさ(ほとんど話さなくなる) ・快感消失(活動の興味が失われる) ・社交性低下(対人関係への関心が失われる) |
| 解体症状 | ・思考障害(思考にとりとめがなく、発語が支離滅裂かつ理解不能) ・奇異な行動(子どもがするような愚行、不適切な外見など) |
| 認知症状 | 問題解決力、経験から学習する能力、他者の視点を理解する能力などが低下 |
⑤経過
統合失調症の経過については、患者さんの1/3が良好、1/3が一進一退、1/3が進行性に悪化すると言われています。
経過が良好になりやすい、もしくは悪化しやすい因子は以下の通りです。
| 経過 | 因子 |
|---|---|
| 良好 | ・病前機能が良好(優秀な学生/社会人など) ・発症年齢が高い ・突然発症した ・認知障害がほとんどない ・陰性症状がほとんどない ・未治療期間(発症から治療開始までの期間)が短い ・女性 |
| 悪化 | ・病前機能が不良 ・発症年齢が低い ・家族に統合失調症患者がいる/いた ・陰性症状が多い ・未治療期間が長い ・男性 |
統合失調症を治療するうえでは、再発予防が非常に重要です。
再発の大きな原因として、抗ドパミン薬の中止が挙げられます。
そのため、統合失調症に対して抗ドパミン薬を中止するためには、数年間安定した状態を維持する必要があります。
抗ドパミン薬の適応:(2)消化管運動の改善
本記事の序盤でも取り上げましたが、ドパミンにはアセチルコリンに拮抗する作用があります。
そのため、抗ドパミン薬を投与してドパミンの作用を阻害すると、アセチルコリンの作用が亢進し、副交感神経が活発に働くようになるのです。
また、胃や腸といった消化管の運動には、主に副交感神経の働きが関与しています。
そのため、抗ドパミン薬の作用により消化管の運動が改善するのです。
その結果、消化管の運動の低下を原因として生じる、吐き気/嘔吐・胸やけ・食欲不振などの症状が改善されます。
抗ドパミン薬の主な種類
抗ドパミン薬の主な種類は以下の通りです。
| 適応 | 抗ドパミン薬 |
|---|---|
| 統合失調症の治療 | クロルプロマジン、ハロペリドール、スルピリドなど |
| 消化管運動の改善 | プリンペラン、ガナトン、ナウゼリンなど |
抗ドパミン薬の主な副作用
統合失調症の治療目的に使われる抗ドパミン薬には、以下のような副作用があります。
- 精神神経系症状(眠気・めまい・頭痛・不安・不眠など)
- 錐体外路症状
- 内分泌症状(プロラクチンの分泌亢進による女性化乳房(男性の乳房の肥大)など)
以上の中で、特に注目したい副作用が錐体外路症状です。
私たちが様々な動作を行う際には、脳内の「淡蒼球内節」という場所から適度なブレーキを受けています。
そして、淡蒼球内節の働きを程よく抑制しているのが、同じく脳内の「線条体」という場所です。
正常な状態では、線条体の働きはドパミンにより調節されています。
しかし、抗ドパミン薬を投与するとドパミンの作用が弱まり、線条体が淡蒼球内節を抑制できなくなってしまいます。
その結果、淡蒼球内節が持つブレーキ機能が過剰となり、以下のような症状が生じます。
- 安静時振戦(安静時に手足が震える)
- 無動(動作が緩慢になる)
- 筋強剛(筋肉がこわばる)
- 姿勢保持障害(前かがみになりやすい、転びやすい)
これらの症状が、総称して錐体外路症状と呼ばれています。
一方、消化管運動の改善目的に使われる抗ドパミン薬では、下痢や腹痛などの消化器症状が現れる可能性があります。
非常に稀ではあるものの、錐体外路症状や内分泌症状が生じる恐れもあります。
まとめ:抗ドパミン薬を統合失調症の治療や消化管運動の改善に役立てよう
ドパミンは神経伝達物質の一種であり、様々な作用を有しています。
代表的なものが、神経経路での作用やアセチルコリンに拮抗する作用です。
これらの特徴を活かして、抗ドパミン薬は統合失調症を治療したり、消化管運動を改善したりする目的で使用されています。
錐体外路症状をはじめとする副作用に注意しつつ、抗ドパミン薬を治療に役立てましょう。