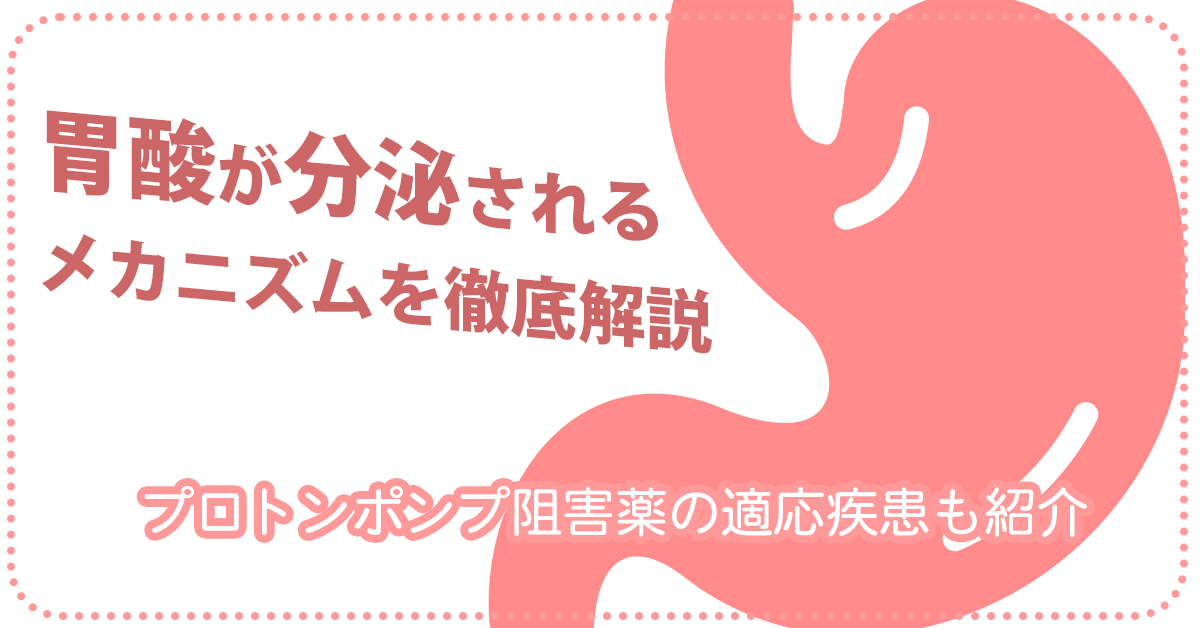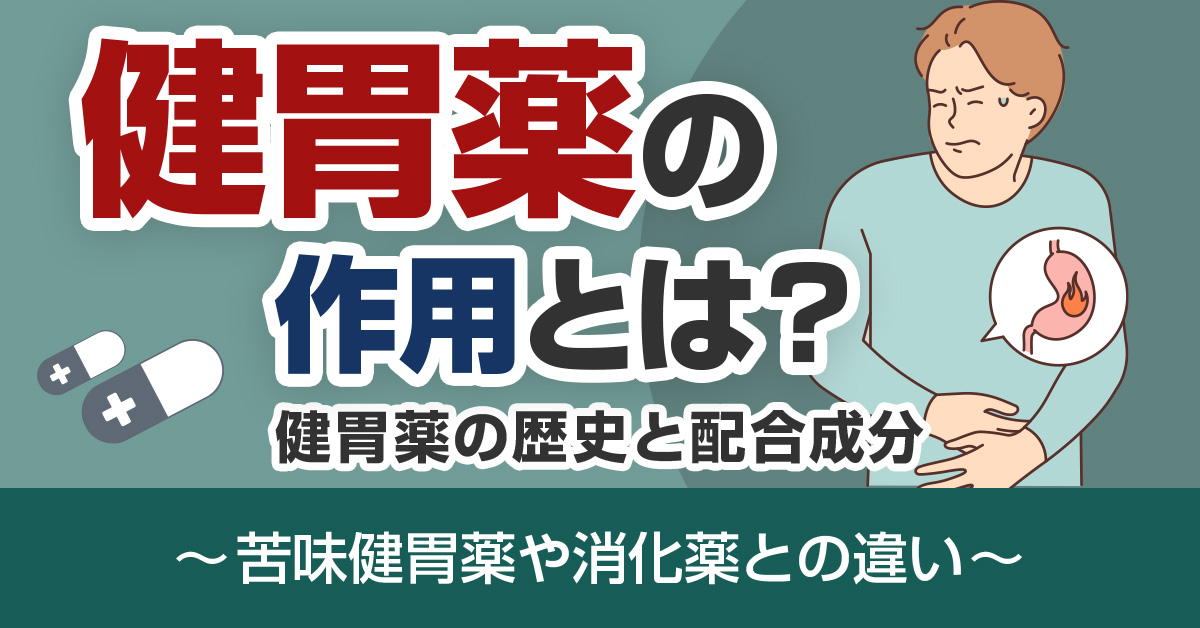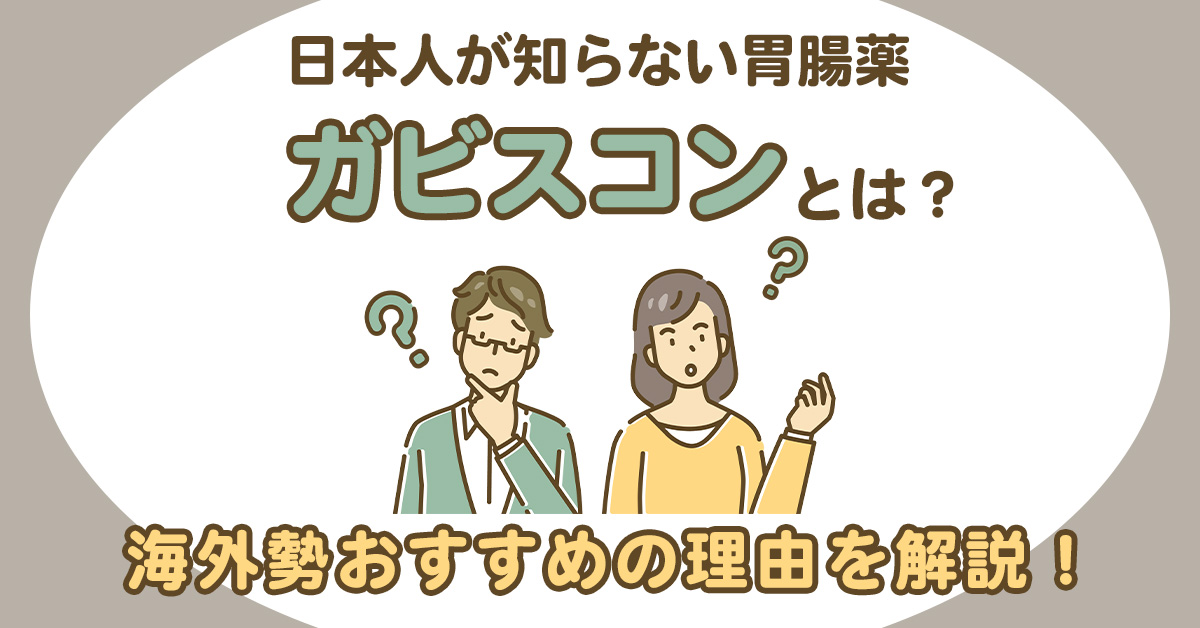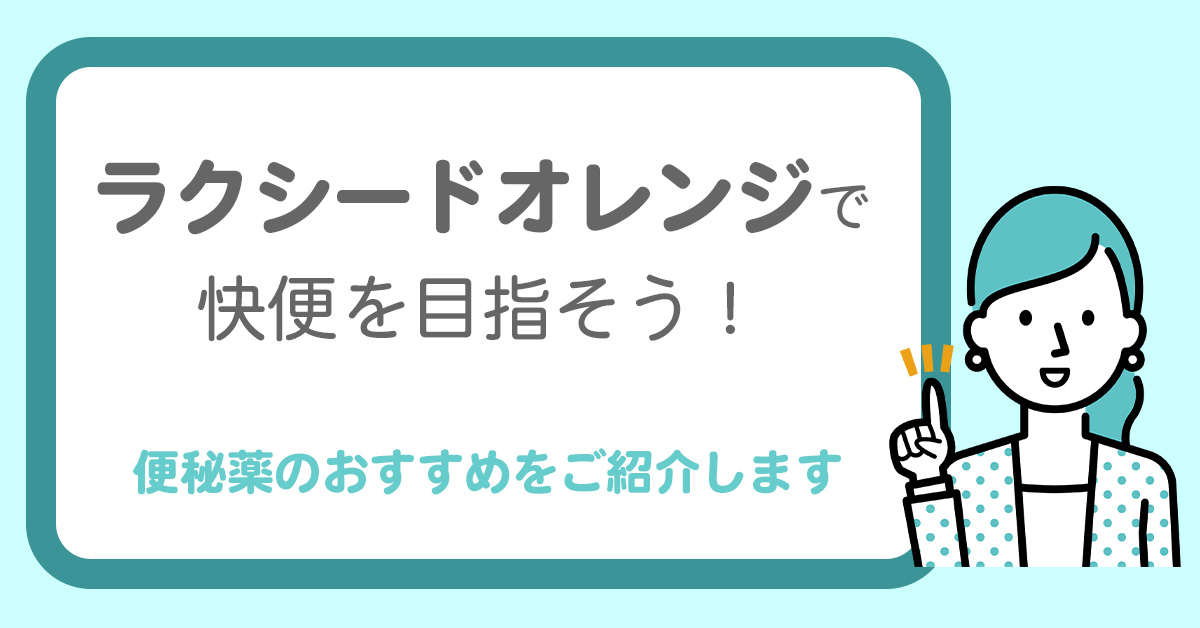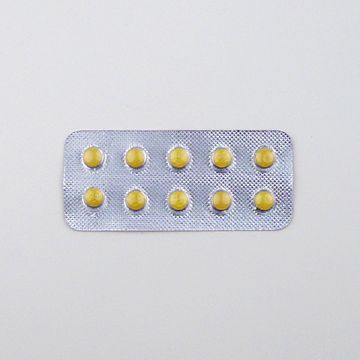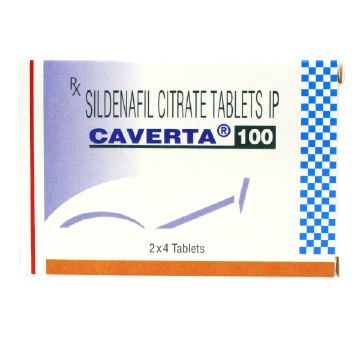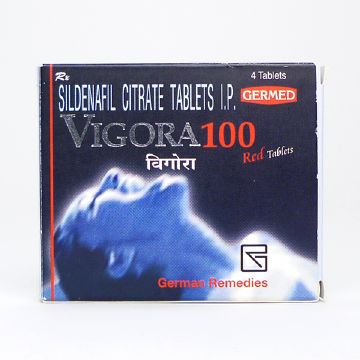「胃酸はどうやって分泌されているの?」
「プロトンポンプ阻害薬が用いられる疾患は?」
このような疑問を持っている人は少なくないのではないでしょうか。
本記事では、胃酸が分泌されるまでのメカニズムを徹底解説。
プロトンポンプ阻害薬が作用するメカニズムや、適応となる疾患についても紹介します。
本記事を読めば、胃酸の分泌やプロトンポンプ阻害薬に関する理解を深められます。
興味がある人はぜひ最後までご覧ください。
プロトンポンプ阻害薬は胃酸分泌を抑制する薬剤
胃酸とは、塩酸から成り立っている、胃の中で分泌される強力な酸のことです。
胃を構成している「壁細胞」から分泌されています。
私たちが食事をすることで胃酸の分泌が促進され、主に以下のような働きを有しています。
- 食べ物を消化しやすくするために分解する
- 消化酵素である「ペプシノーゲン」を「ペプシン」に活性化する
- 体内に侵入してきた細菌やウイルスなどの病原体を排除する
以上の働きからもわかる通り、胃酸は私たちにとって欠かせない存在です。
しかし、胃酸が必要以上に分泌されると、私たちの身体に悪影響を及ぼします。
そこで開発されたのが、胃酸の過剰分泌を抑制する「酸分泌抑制薬」です。
酸分泌抑制薬にはいくつかの薬剤が該当しますが、最も効果が強いとされているのが、本記事で取り上げていくプロトンポンプ阻害薬なのです。
胃酸分泌に関わる消化管ホルモン
胃酸の分泌には、様々な消化管ホルモンが関与しています。
代表的なホルモンは以下の4つです。
| ホルモン | 分泌する細胞 | 分泌される臓器 | 胃酸分泌 |
|---|---|---|---|
| ガストリン | G細胞 | 胃、十二指腸上部 | 強く亢進 |
| セクレチン | S細胞 | 十二指腸 | 抑制 |
| GIP | K細胞 | 十二指腸、空腸 | 抑制 |
| ヒスタミン | ECL細胞 | 胃、小腸、大腸 | 亢進 |
補足ですが、消化管の経路は以下の通りです。
口腔 → 食道 → 胃 → 十二指腸 → 空腸 → 回腸 → 盲腸 → 結腸 → 直腸 → 肛門
胃酸の分泌を調節するメカニズム
先ほどの見出しで紹介した消化管ホルモンなどの働きにより、胃酸の分泌は調節されています。
以下の3つの時相に分けて、どのように調節されているのか詳しく見ていきましょう。
- 脳相
- 胃相
- 腸相
①脳相
食事による刺激が脳に伝わると、脳相がスタートします。
摂食刺激により、まず反応するのが「迷走神経」です。
迷走神経は、壁細胞・ECL細胞・G細胞を刺激し、胃酸の分泌を直接的かつ間接的に促進します。
②胃相
食物が胃の中に流入すると、胃相のスタートです。
食物に含まれる成分の刺激により、G細胞から大量のガストリンが分泌され、胃酸の分泌が亢進します。
さらに、食物の流入により胃腔内のpH(液体の酸性/アルカリ性を表す単位)が上昇し、ガストリンの分泌を後押しします。
③腸相
食物が十二指腸に到達すると、腸相のスタートです。
腸相では、K細胞からGIPが、S細胞からセクレチンが分泌され、胃酸の分泌を抑制します。
また、GIPはインスリン(糖を取り込みエネルギーとするためのホルモン)の分泌を、セクレチンは膵液(食物の消化・吸収に役立つアルカリ性の液)の分泌を促進します。
プロトンポンプとは?
様々なホルモンや神経刺激の働きにより調節され、壁細胞から胃酸が分泌されるメカニズムにおいて、最終段階となるのがプロトンポンプです。
プロトンポンプは、壁細胞を覆っている細胞膜に存在しています。
なお、ここでの「プロトン」とは胃酸とほぼ同義です。
プロトンポンプが稼働するためのエネルギー源は、「アデノシン三リン酸(ATP)」という物質です。
ATPの持つエネルギーを利用して、プロトンポンプは「カリウムイオン」という電解質(ミネラル)を細胞内に取り込み、プロトンを胃腔内に放出しています。
この働きにより、胃の中が強い酸性に保たれているのです。
プロトンポンプ阻害薬が作用するメカニズム
プロトンポンプ阻害薬が作用するメカニズムには、可逆的なものと不可逆的なものがあります。
それぞれ見ていきましょう。
①不可逆的なメカニズム
一般的なプロトンポンプ阻害薬は、胃腔側(壁細胞の外側)からプロトンポンプに不可逆的に結合し、プロトンポンプを不活性化します。
そのため、プロトンポンプが再度生合成されるまで、胃酸分泌の抑制効果が継続するのです。
不可逆的なメカニズムを有するプロトンポンプ阻害薬のデメリットは、投与してから効果が出るまでに数日を必要とする点です。
また、投与を中止してから効果が消失するまでにも、同様に数日かかります。
②可逆的なメカニズム
2015年に認可されたプロトンポンプ阻害薬「ボノプラザン」は、可逆的なメカニズムで胃酸分泌を抑制します。
ターゲットとなる物質は、壁細胞に取り込まれるカリウムイオンです。
ボノプラザンは、カリウムイオンの取り込みを競合的に阻害することで、プロトンポンプの稼働をストップさせます。
このメカニズムから、「カリウムイオン競合的プロトンポンプ阻害薬」と呼ばれています。
ボノプラザンの主なメリットは以下の2点です。
- 効果が出るまでの時間が短い
- 患者さんの体質による効果の差が少ない
導入されてからまだ間もない薬剤ですが、期待が集まっています。
プロトンポンプ阻害薬の一覧
プロトンポンプ阻害薬の主な種類と、それぞれの簡単な特徴は以下の通りです。
| 薬剤 | 特徴 |
|---|---|
| オメプラゾール | 世界初のプロトンポンプ阻害薬 |
| ランソプラゾール | 内服薬だけでなく注射薬もあり |
| ラベプラゾール | 他の薬剤との相互作用が少ない |
| エソメプラゾール | 患者さんの体質による効果の差が少ない、小児にも使える |
| ボノプラザン | カリウムイオン競合的プロトンポンプ阻害薬 |
プロトンポンプ阻害薬が適応となる疾患
プロトンポンプ阻害薬が適応となる疾患は以下の通りです。
- ヘリコバクターピロリ感染症
- 消化性潰瘍
- 胃食道逆流症
それぞれの疾患について見ていきましょう。
①ヘリコバクターピロリ感染症
ヘリコバクターピロリ菌とは、胃粘膜に感染・生息している細菌です。
一般的な細菌は、胃酸により排除されるため胃粘膜には住み着けません。
しかし、ヘリコバクターピロリ菌は胃酸を中和する「ウレアーゼ」という酵素を分泌するため、胃の中でも生存し胃粘膜に定着できるのです。
ヘリコバクターピロリ菌は、後述する消化性潰瘍や、胃癌など様々な消化器疾患の原因となります。
そのため、これらの疾患の発症・再発を予防するために、除菌が推奨されています。
具体的に用いる薬剤は以下の3剤です。
- プロトンポンプ阻害薬
- アモキシシリン(抗菌薬)
- クラリスロマイシン(抗菌薬)
以上の3剤併用により除菌できる確率は、およそ70~90%です。
除菌できなかった場合は、クラリスロマイシンを「メトロニダゾール」という抗菌薬に変更し、二次除菌を試みます。
除菌率はおよそ80~90%であり、二次除菌まででほとんどの人がヘリコバクターピロリ菌の除菌に成功します。
②消化性潰瘍
消化性潰瘍とは、胃酸から胃や十二指腸の粘膜を保護する防御因子の低下などが原因で、胃や十二指腸の粘膜に深い潰瘍(組織の欠損)が生じる疾患です。
主に以下のような症状を繰り返します。
- 心窩部痛(みぞおちの痛み)
- 腹部膨満感
- 悪心/嘔吐
- 胸やけ
- 食欲不振
病態が進行すると吐血や下血をきたし、貧血やショック(血圧が大幅に低下し臓器に血流が行き渡らない状態)に陥る可能性もあります。
消化性潰瘍とひとまとめにしても、胃潰瘍と十二指腸潰瘍ではいくつかの違いがあります。
| 胃潰瘍 | 十二指腸潰瘍 | |
|---|---|---|
| 好発年齢 | 40~60歳代 | 20~40歳代 |
| 男女比 | 1:1 | 3:1 |
| 心窩部痛 | 食後に多い 食事摂取で改善しない | 空腹時・夜間に多い 食事摂取で改善する |
| 粘膜萎縮 | 強い | ない~少し |
| 出血 | 吐血が中心 | 下血(便に血が混じる)が中心 |
| 穿孔(穴が開く) | 少ない | 多い |
③胃食道逆流症
胃食道逆流症とは、主に胃酸が食道や口腔内に逆流してくる疾患です。
主な症状として以下が挙げられます。
- 胸やけ
- 呑酸
- 胸痛
- 咳
- 咽喉頭違和感
呑酸とは、酸っぱい液体が口まで上がってゲップが出る症状のことであり、食後・夜間によくみられます。
胃食道逆流症は、内視鏡検査における所見の違いから、以下の2タイプに分類されます。
| びらん性GERD(逆流性食道炎) | 非びらん性GERD(NERD) | |
|---|---|---|
| 内視鏡検査における食道の粘膜障害 | ある | ない (胃酸に対する食道粘膜の過敏性が亢進している) |
| 自覚症状 | 有無を問わない | 強い |
| 性別 | 男性に多い | 女性に多い |
| 年齢 | 高齢者に多い | 若年者に多い |
| BMI | 高い人に多い | 低い人に多い |
| 胃食道逆流症に占める割合 | 約1/3 | 約2/3 |
プロトンポンプ阻害薬の主な副作用
プロトンポンプ阻害薬の主な副作用は以下の通りです。
- 便秘
- 下痢
- 吐き気
頻度は稀ではあるものの、アレルギー反応による発疹や、肝機能障害による食欲不振・倦怠感・黄疸などが生じる恐れがあります。
プロトンポンプ阻害薬の服用中にこれらの症状が生じた場合は、医療機関を受診し医師に相談しましょう。
まとめ:プロトンポンプ阻害薬で消化器疾患を治療しよう
胃酸は私たちが生きていくうえで欠かせないものですが、時として私たちの身体を攻撃してしまいます。
そこで開発されたのが様々な酸分泌抑制薬であり、中でも最も効果が高い薬剤が、プロトンポンプ阻害薬です。
プロトンポンプ阻害薬は、ヘリコバクターピロリ感染症や消化性潰瘍、胃食道逆流症に対して用いられます。
副作用に注意しつつ、プロトンポンプ阻害薬で消化器疾患を治療しましょう。