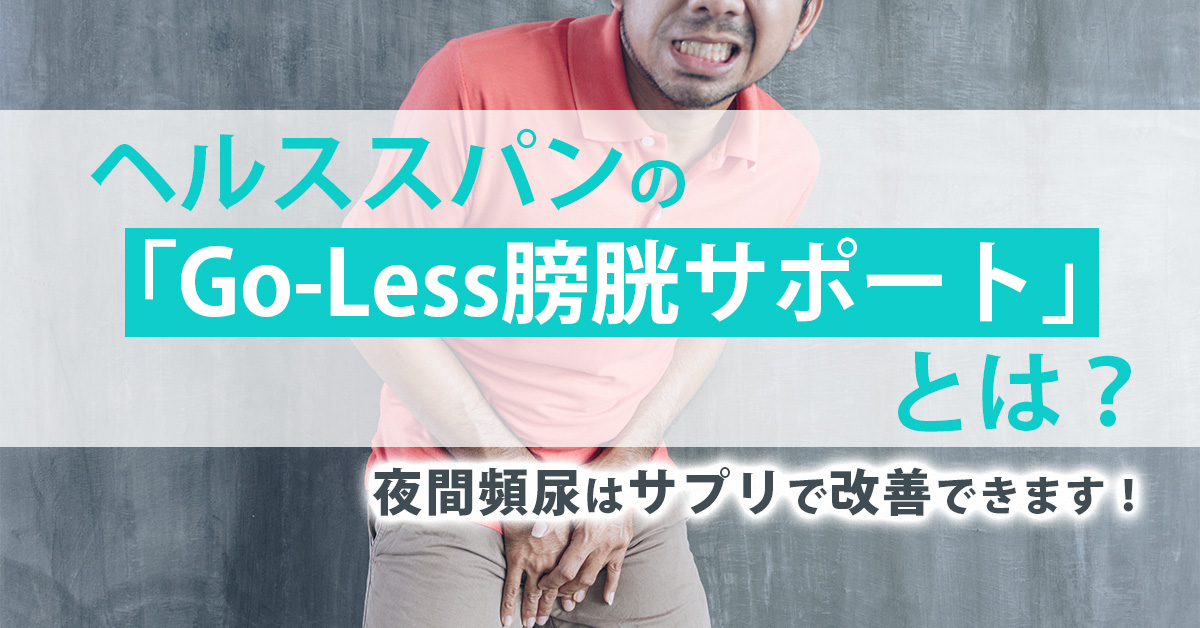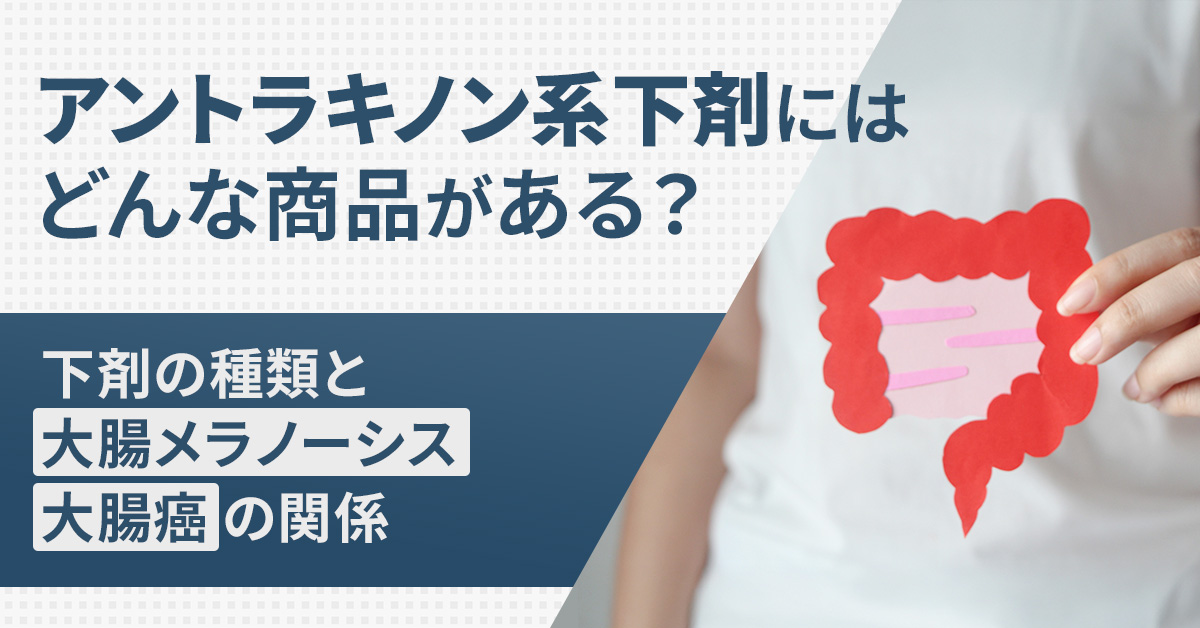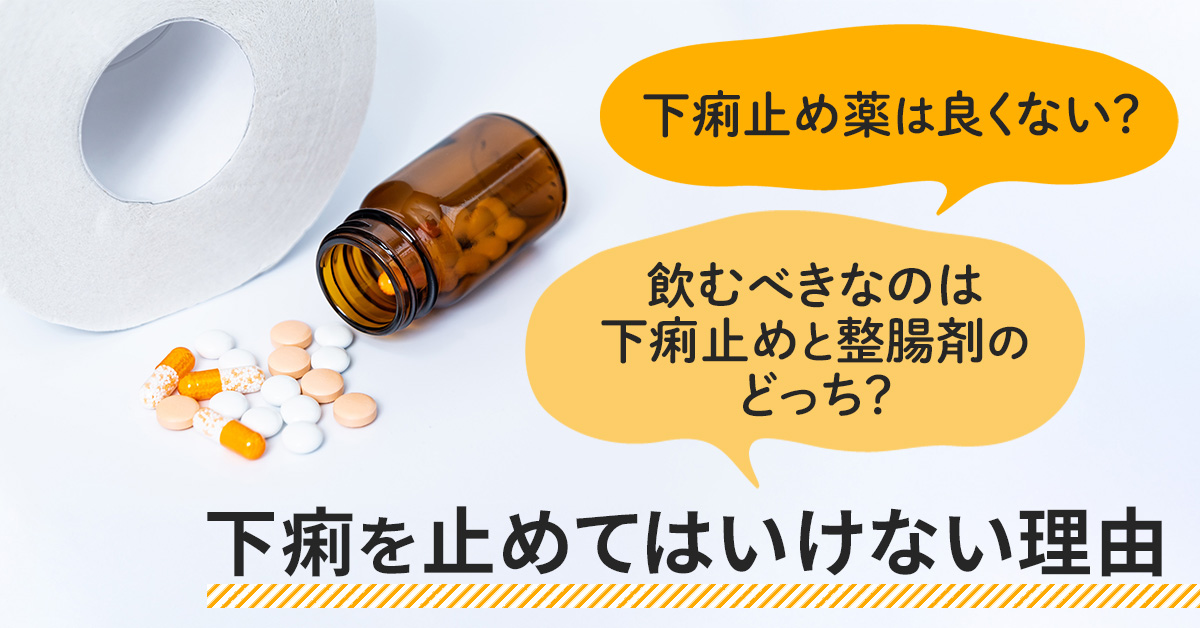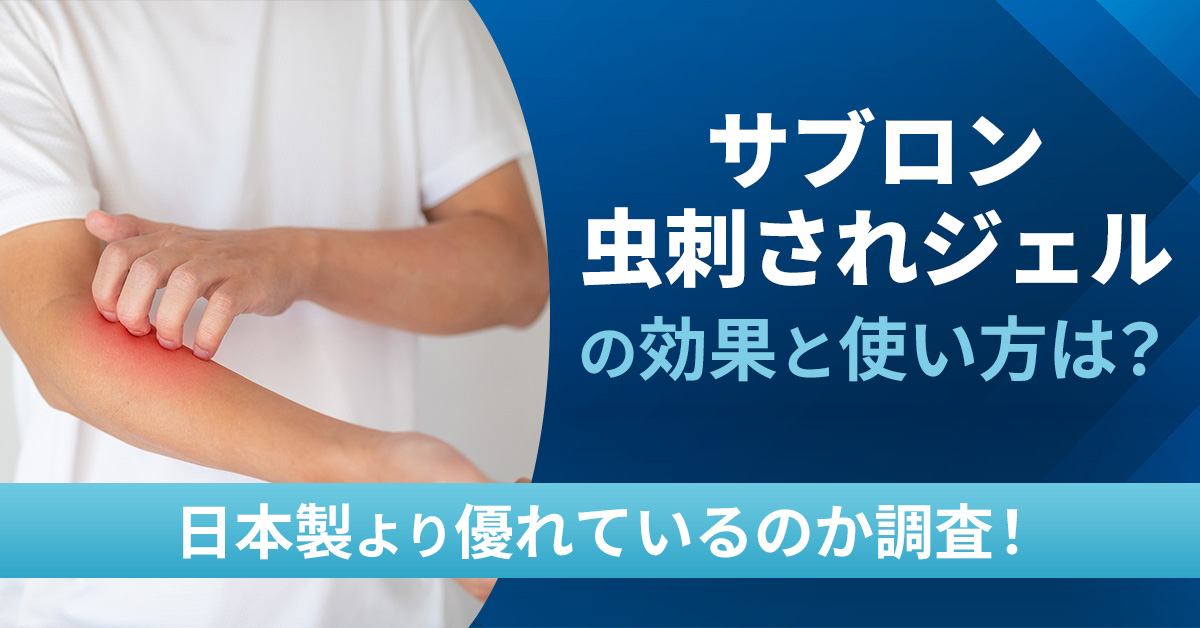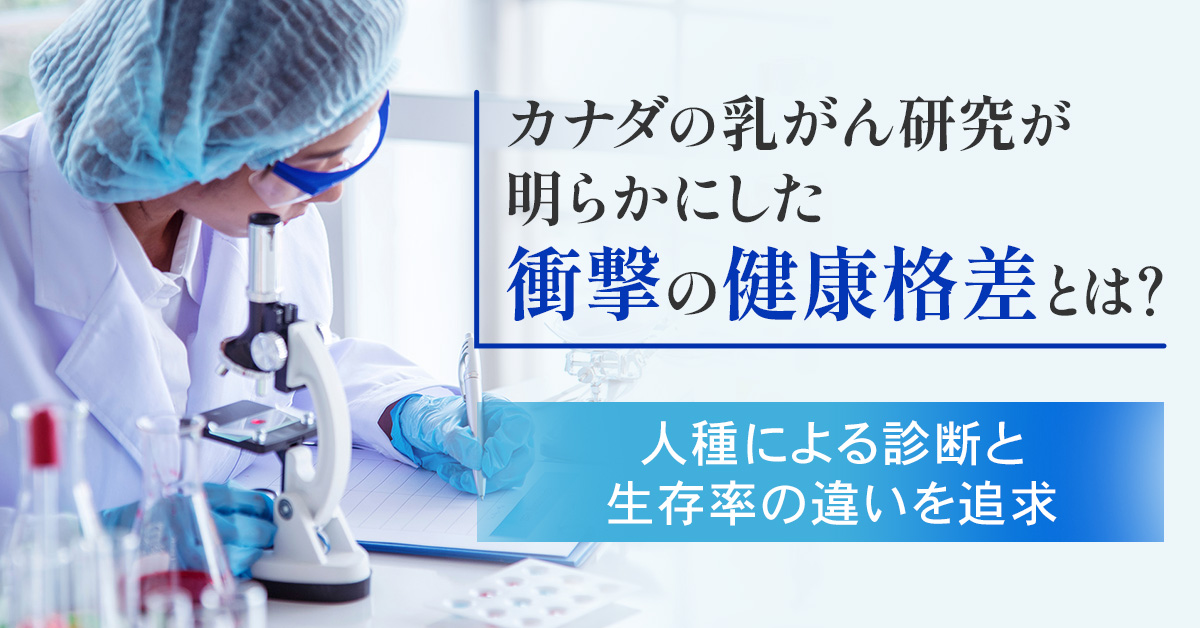人間であれば誰しもが一度は経験したことがある尿の問題を、日常的に抱えている方は少なくありません。
頻尿や尿失禁で悩み、生活に支障をきたしている状態であれば、できるだけ早く医療機関を受診したり、薬剤を購入したりして治療を始めるべきであると言えます。
今回は頻尿の定義と頻尿治療薬の解説に加え、日常生活で取り入れられる頻尿対策も紹介していきます。
「尿の悩みは恥ずかしい」「コントロールできないから仕方ない」そんな一言で片付けないで、一度自分の身体と向き合ってみませんか。
頻尿と原因
尿が近く、排尿でトイレに行く回数が1日に8回以上であったり、就寝中に2回以上トイレに行ったりするような場合を「頻尿」、無意識に尿が漏れてしまうことを「尿漏れ」と呼んでいます。
しかしながら、これはあくまでも一般的な定義であり、1日8回以下であっても排尿回数の多さなどで悩んでいる場合には頻尿であると言えます。
頻尿で悩んでいる方は全国で200万人以上、年に数回以上の尿失禁がある方は600万人以上いるとされ、特に尿失禁は出産経験のある約4割女性が経験していると言われていますが、治療を受けているのは約3~6%です。
頻尿や尿失禁の治療は原因や症状によって治療法が異なることから、まずここではそれぞれの頻尿の定義や原因について解説していきます。
過活動膀胱
膀胱に尿があまり溜まっていないのにも関わらず勝手に収縮して尿意をもよおしてしまう過活動膀胱は、頻尿の原因となることだけでなく、急な尿意が堪えられずに尿失禁する可能性もある病気です。
過活動膀胱の原因はパーキンソン病や認知症、脊髄損傷などの脳や脊髄神経の病気や、前立腺肥大症の影響や加齢によるものだったり、原因が不明だったりと様々です。
過活動膀胱は抗コリン薬やβ3刺激薬などによる薬物療法や、生活指導や膀胱訓練などの行動療法で治療していきます。
もし、これらの治療でも症状が改善しない場合には、手術を行うこともあります。
尿量の増加
膀胱や尿道に疾患がなくても尿の量が多い場合には頻尿となり、1日に3L以上排尿するようになると多尿と診断されます。
尿量が多くなる原因には、水分の摂りすぎや利尿作用のあるカフェインを多く含んだコーヒーや緑茶の影響などが考えられますが、糖尿病や腎臓の機能低下といった病が隠れている可能性もあります。
多尿の対策として喉が乾かない程度に水分摂取を控えたり、カフェインを含んだ飲み物以外を選択したりすると効果があるとされていますが、変化がない場合には医療機関を受診しましょう。
心因性頻尿
心因性頻尿は会議や試験、発表会などの緊張する場面で、トイレに頻?に行きたくなるような状態を言います。
これが一時的なものであれば過度な心配は要りませんが、頻尿が続いて日常生活でもトイレばかりが気になってしまうようであれば、一度医療機関を受診するとよいでしょう。
この心因性頻尿は意識のない就寝中には頻尿が起きないのも特徴です。
夜間頻尿
日中の排尿に問題ないのに、夜になると何度もトイレに行くようになるのが夜間頻尿です。
眠ろうと思って布団に入ってから翌朝起床するまでの排尿の回数を数え、これが2回以上だと夜間頻尿であると定義されています。
70歳以上の2~3割の方が夜間頻尿であるとされ、この夜間頻尿のために生活の質が下がっていると感じる場合は医療機関を受診しましょう。
ただし、夜間頻尿は過活動膀胱や多尿、睡眠障害などの複数の要因が絡み合っているケースも多いため、まずは原因を特定してから治療を行うことが重要です。
残尿
排尿しても出し切れずに膀胱内に尿が残ってしまう症状を残尿と言います。
膀胱内に残尿があることで容量を圧迫し、すぐにトイレに行きたくなってしまうため、頻尿となります。
残尿は前立腺肥大による尿道の圧迫や膀胱の機能障害の他、脳脊髄腫瘍や脳梗塞、パーキンソン病、糖尿病の患者さんなどで起こりやすいとされています。
膀胱に尿が充満してしまうことで腎臓に悪影響を及ぼすこともあるため、残尿感が続く時には医療機関の受診をおすすめします。
頻尿で処方される治療薬の種類
このように頻尿には様々な原因があり、頻尿の治療薬も使い分けられています。
ここでは頻尿の治療で処方される治療薬を種類別に紹介していきます。
抗コリン薬
尿が膀胱内に溜まると膀胱が収縮して尿意をもよおしますが、尿があまり溜まっていないのにも関わらず膀胱の筋肉収縮が起こることで、過度にトイレに行きたくなり、頻尿となります。
膀胱は神経伝達物質のアセチルコリンがムスカリン受容体に作用することで収縮するため、このアセチルコリンの働きを阻害し、膀胱の収縮を抑える抗コリン薬を使用して頻尿を改善していきます。
抗コリン薬は過活動膀胱や心因性頻尿を始めとする頻尿の治療に使用される薬剤で、男性・女性に関係なく使われる第一選択薬です。
貼付剤であるネオキシポラキスやカプセル剤のデトルシトールカプセル、散剤のバップフォー、錠剤のポラキスなどの治療薬があり、貼付剤のネオキシポラキスは口渇などの副作用の軽減が期待できます。
抗コリン薬の主な副作用は口渇や便秘、吐き気などの消化器症状などがあり、稀に麻痺性イレウスや眼圧上昇などを引き起こす可能性もあります。
そのため、お腹が張ったり、ひどい便秘になったりした時には麻痺性イレウスを疑って速やかに医療機関を受診してください。
さらに眼圧上昇の副作用のリスクがあるため、緑内障を患っている方は抗コリン薬を使用できないケースもあります。
また、よくある質問に「バップフォーとポラキスの違い」がありますが、受容体に対する作用の違いや副作用による口渇度合いの違い、残尿量の違いなどがあります。
ポラキスは脂溶性が高く血液脳関門を通過するため認知機能障害を引き起こす可能性があるため、高齢者の使用はできるだけ避ける必要があるとされています。
ポラキスの方が口渇や残尿量についても増加が見られるとされています。
β3刺激薬
交感神経が優位になると膀胱は弛緩して尿道が収縮する機能を持ちます。
そのため、交感神経のβ3受容体を刺激して交感神経を優位にするβ3刺激薬を使用すると、膀胱は広がり、尿道が縮んで尿を蓄えやすくなります。
このような作用をもつβ3刺激薬は、過活動膀胱や頻尿の治療薬として使用されています。
β3刺激薬にはベタニスとベオーバなどの錠剤があり、副作用に便秘や口渇などの消化器症状、動悸や血圧上昇の循環器症状がある他、稀に排尿困難・尿閉などの尿が出にくい・出ないなどの症状が起きることがあります。
排尿困難や尿閉が疑われる場合には速やかに医療機関を受診してください。
また、不整脈などを引き起こすリスクがあるため、ベタニスはフレカイニドやプロパフェノンとは併用を避けましょう。
漢方薬
八味地黄丸や牛車腎気丸といった漢方薬が、頻尿の治療薬として処方されることもあります。
八味地黄丸、牛車腎気丸ともに漢方医学で成長や生殖を司る「腎」の働きを助け、体内の水分バランスを整えて頻尿などの症状を改善する効果があります。
どちらの漢方薬も特に夜間頻尿に効果があるとされています。
抗コリン薬とβ3刺激薬の使い分け
抗コリン薬とβ3刺激薬はどちらも、過活動膀胱の診療ガイドラインの推奨度がA評価で効果が認められている頻尿の治療薬です。
しかし、神経伝達物質のアセチルコリンを遮断する抗コリン薬には認知症の可能性を高める危険性があるという研究結果も報告されていることから、高齢者はこれらのリスクも考慮したうえで頻尿の治療薬を使い分けることが重要です。
また、抗コリン薬で排尿がしにくくなったり残尿量が増えてしまったりする閉経後の女性も、β3刺激薬を選択するとよいとされています。
一方でβ3刺激薬は血圧上昇や動悸を引き起こす可能性あるため、心疾患がある方は医師に相談する必要があります。
さらにβ3刺激薬の生殖機能への影響は未評価であるため、若年層への使用は検討が必要と言えるでしょう。
日常生活に取り入れる頻尿対策
頻尿は治療薬を使用するだけでなく、日常生活で改善を試みていくことも大切です。
まず、水分の過剰摂取と成分に注意しましょう。
当たり前ですが水分をたくさん摂れば摂るほど排尿量は増えるので、喉が渇かない程度を意識しながら摂取量を減らしていきます。
ただし、汗をかく夏や乾燥している冬、喉の渇きを感じにくい高齢者は水分不足を引き起こさないよう気を付けましょう。
また、緑茶やコーヒーなどカフェインが多く含まれているものやビールなどのアルコール類は利尿作用があるため、摂りすぎに注意してください。
そして、少しずつ排尿の間隔を広げて膀胱容量を増やしていく膀胱訓練もぜひ取り入れましょう。
トイレに行く間隔を最初は約15分にすることから始めて、少しずつ排尿の間隔を広げていき、最終的には約2~3時間の排尿間隔を目指して訓練していきます。
さらに尿道を締める力を高める骨盤底筋体操で骨盤底筋を鍛えていくことも、頻尿や尿漏れの改善に期待できます。
仰向けになって軽く膝を立て、お腹には力を入れずに肛門や膣を5秒締めるのを5分繰り返す体操を1日2~3回毎日行います。
仰向け姿勢が基本ですが、イスに座っていても、立っていても行うことができます。
頻尿治療薬は持病や年齢で使い分けよう
頻尿治療薬には抗コリン薬やβ3刺激薬、漢方薬などがあり、効果や副作用などで使い分けられています。
抗コリン薬、β3刺激薬ともに頻尿治療の第一選択薬とされていますが、認知症のリスクが高い高齢者は認知機能低下の副作用がある抗コリン薬、将来的に妊娠・出産の可能性がある若年層は生殖機能が未評価のβ3刺激薬の使用については検討の余地があると言えるかもしれません。
また、口渇などの他の副作用も考慮しながら薬剤を選択していくと良いでしょう。