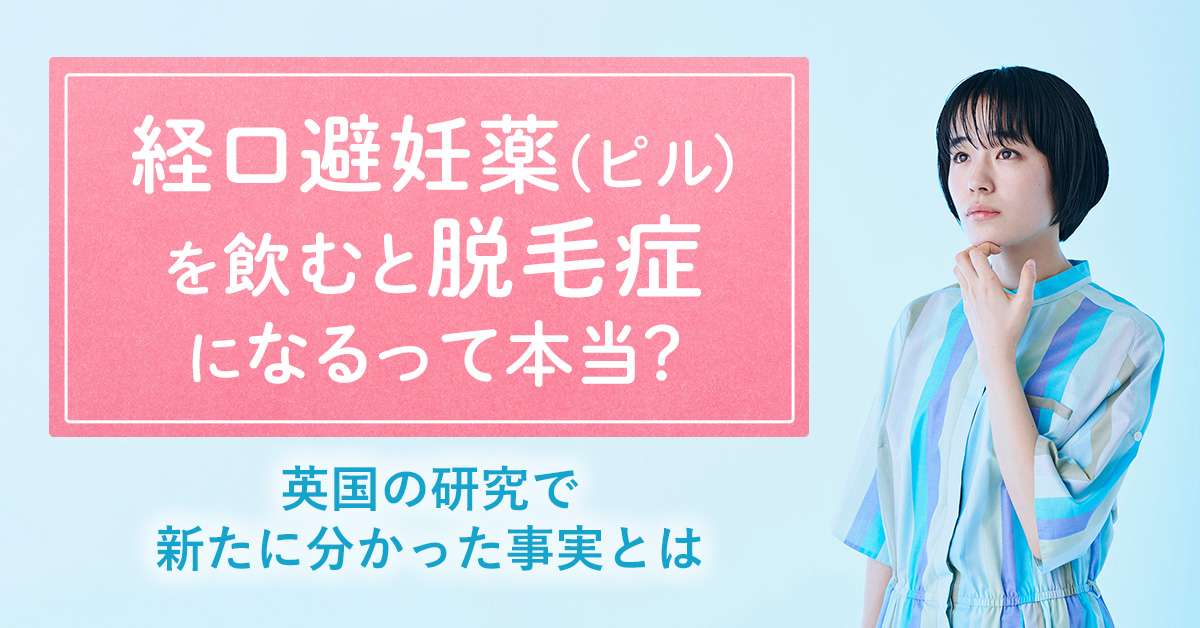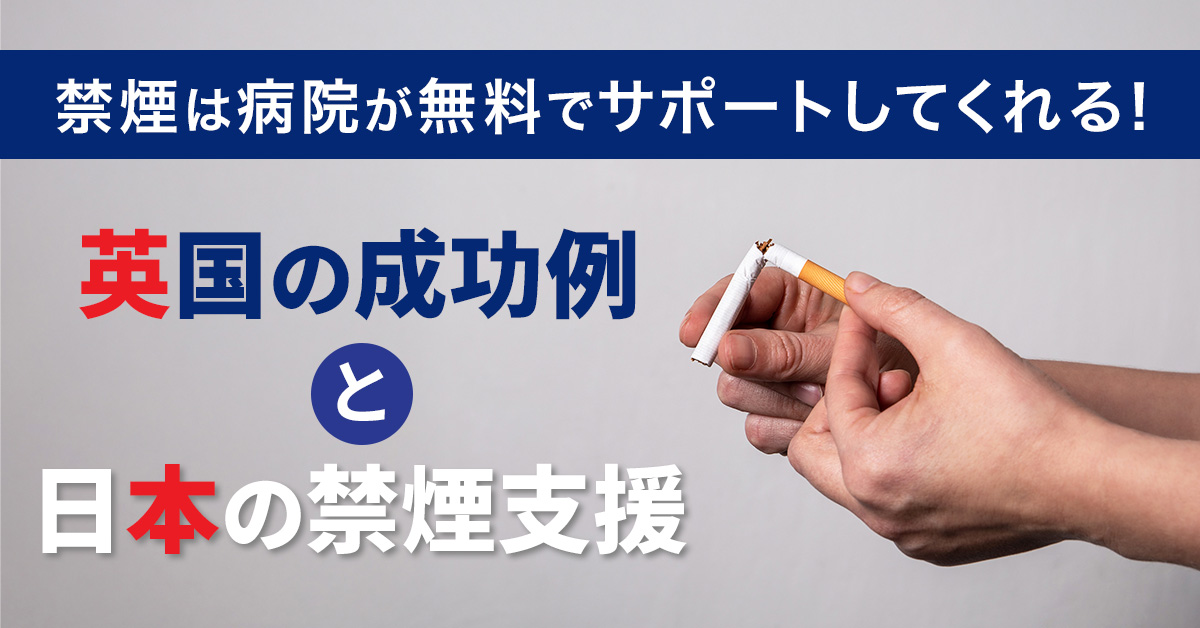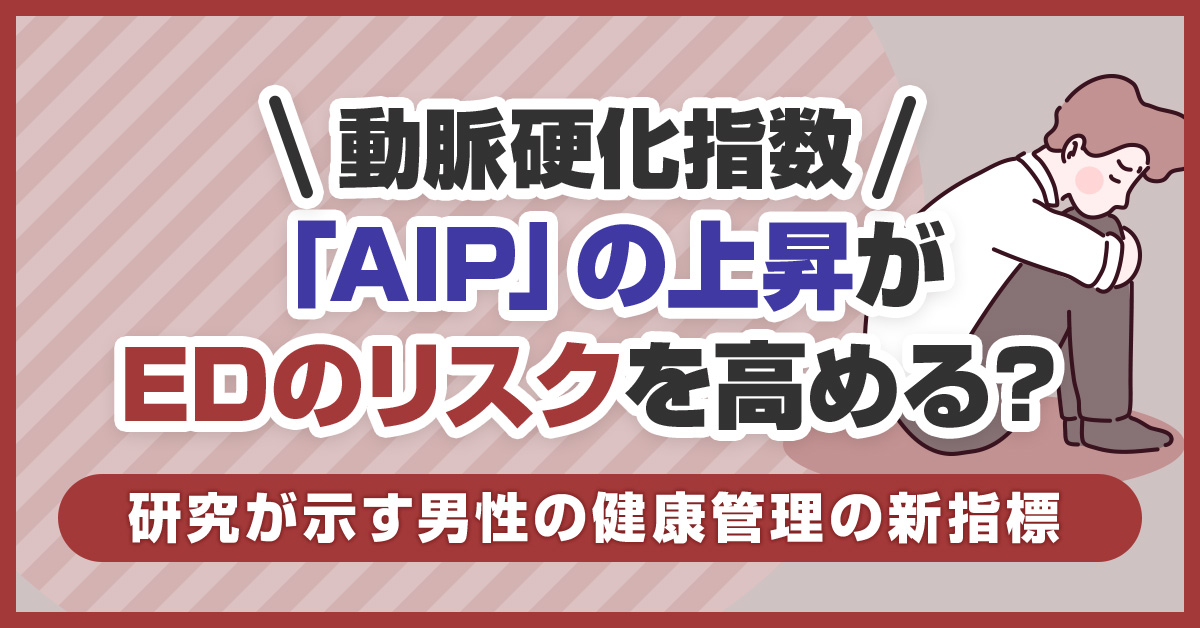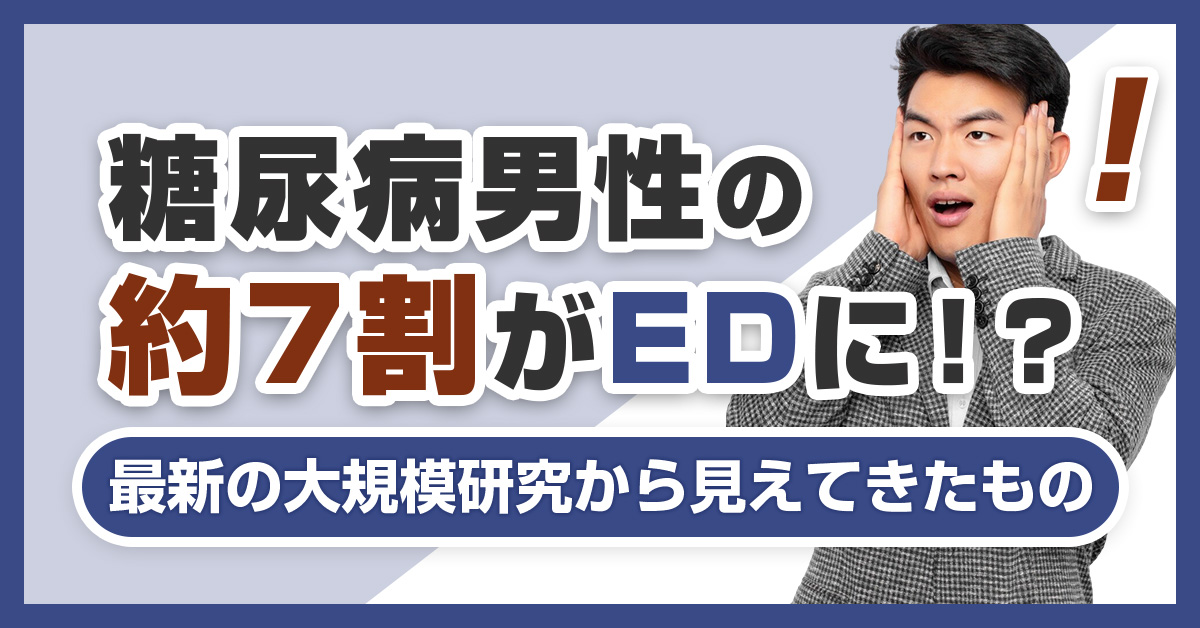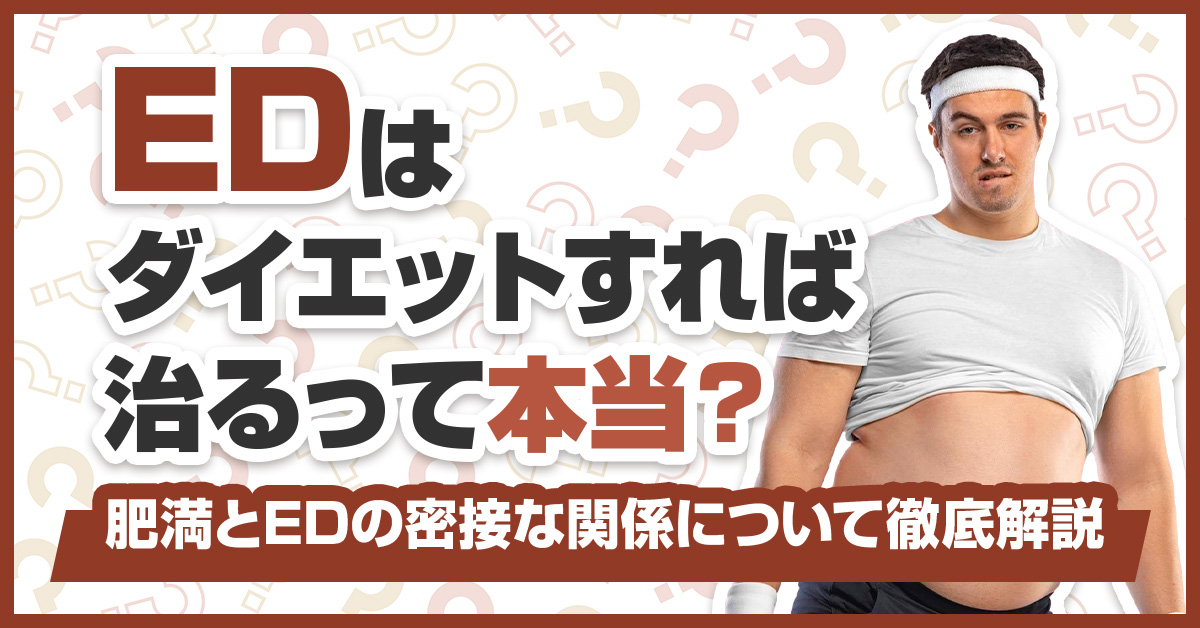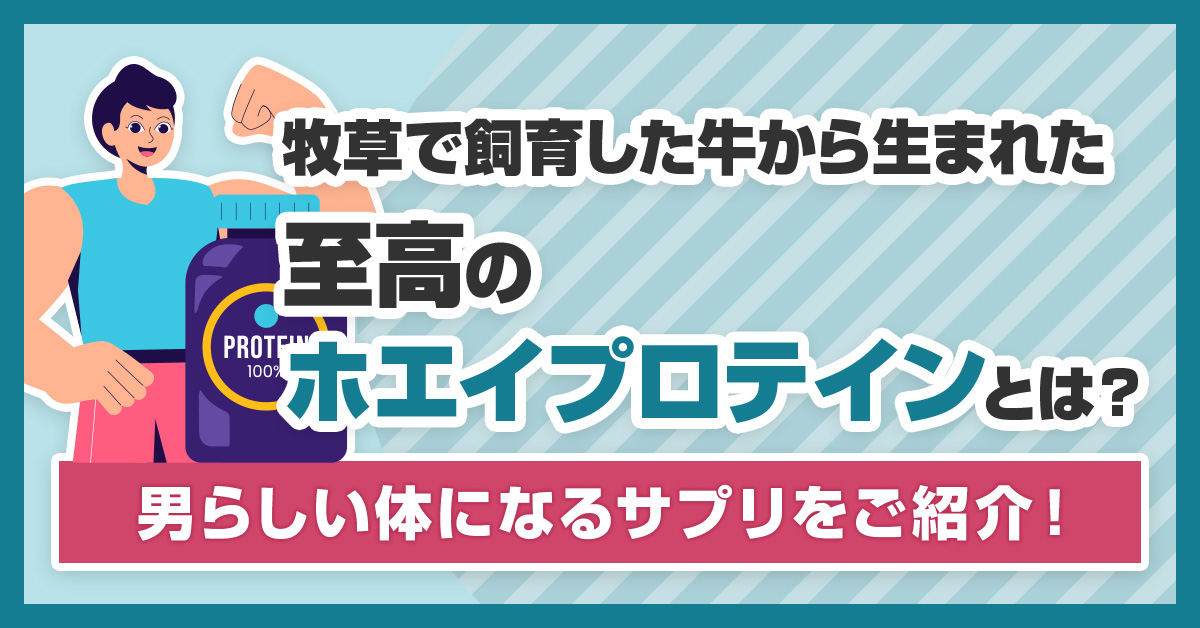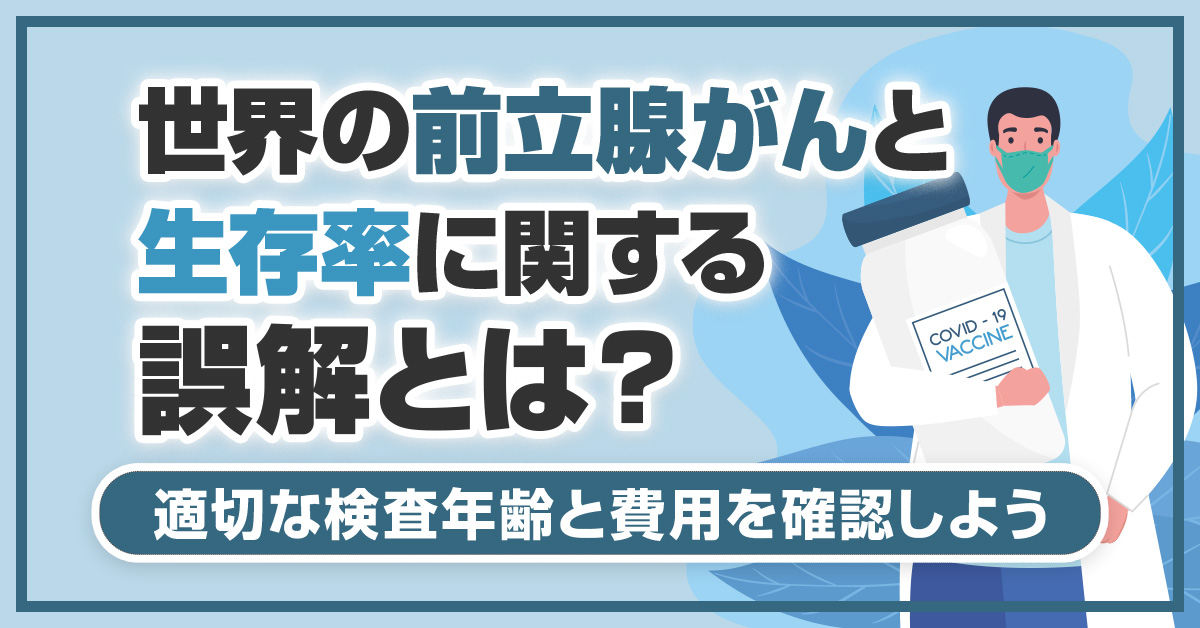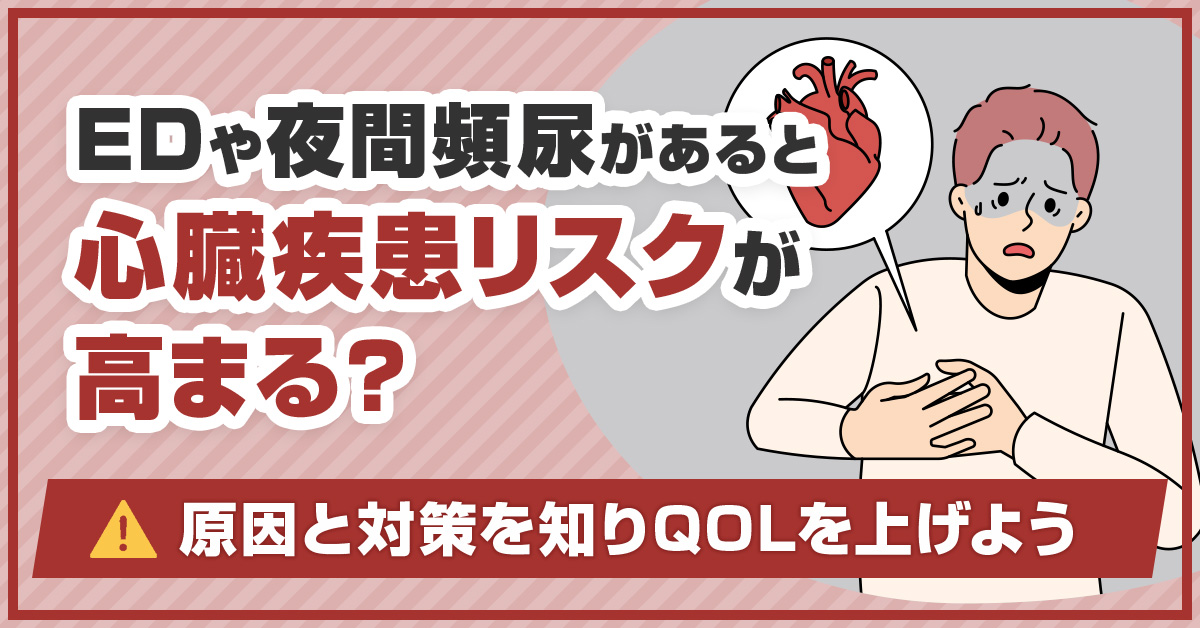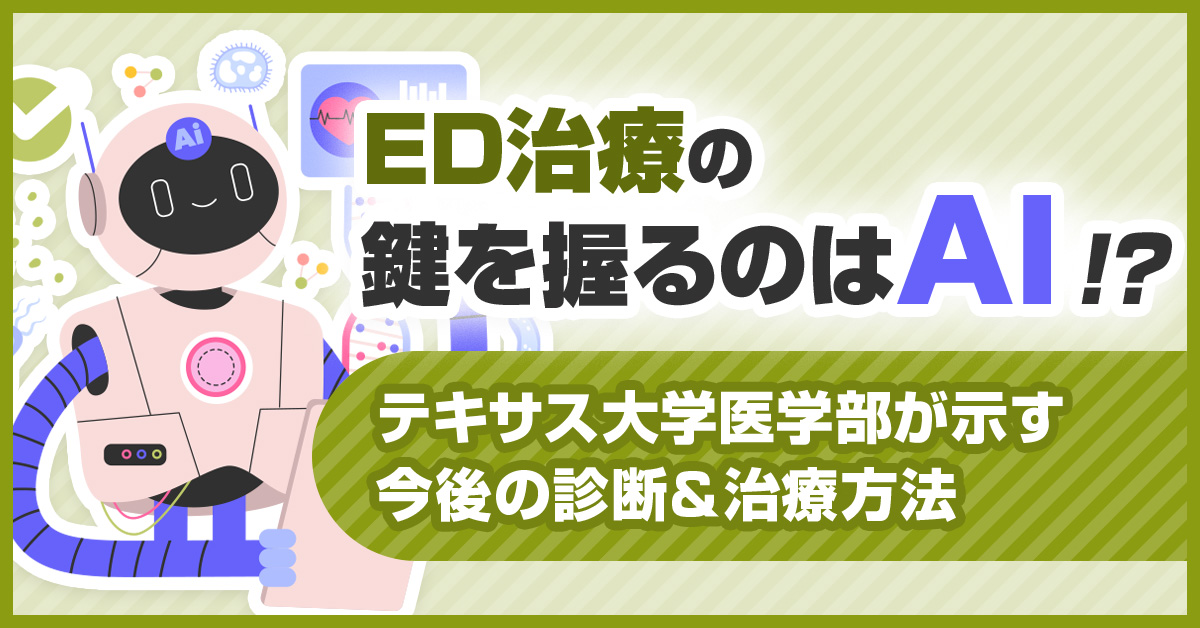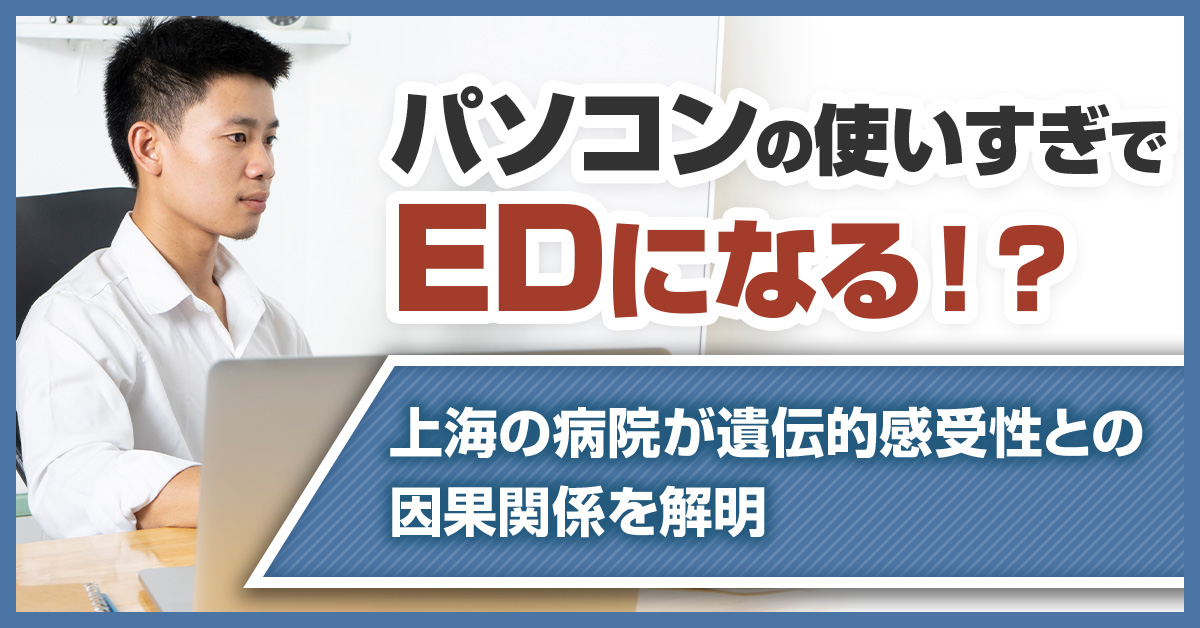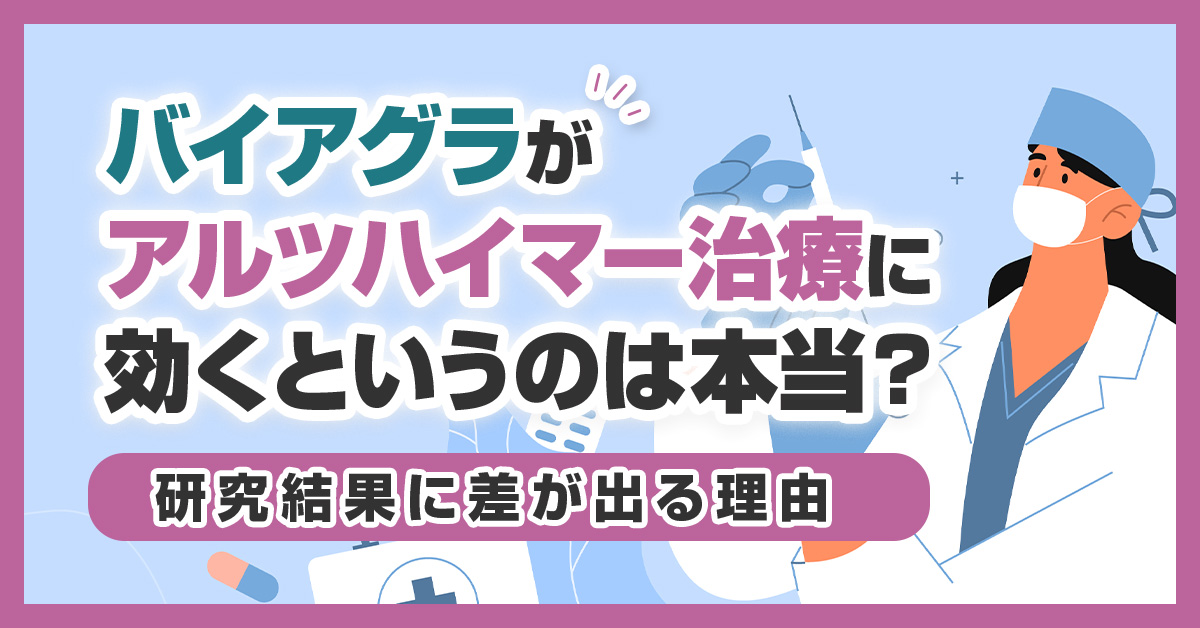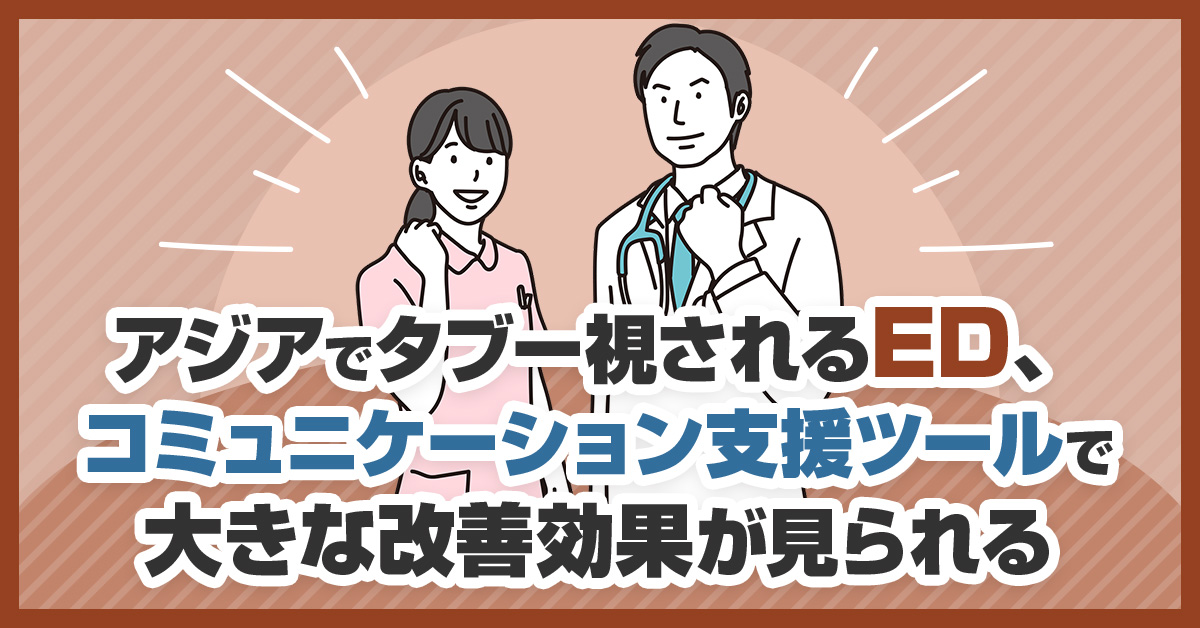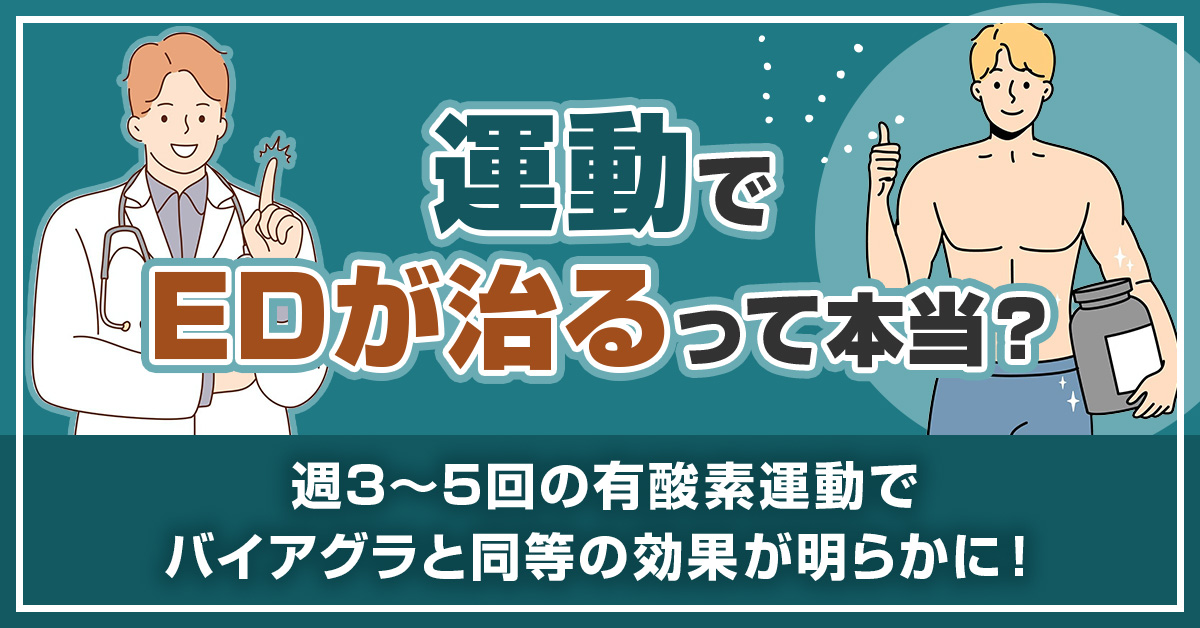2024年5月30日に公開されたJAMA Dermatology誌の記事は、多くの女性が服用する経口避妊薬と、前頭線維性脱毛症(FFA)と呼ばれる疾患との関連性を検証する内容を伝えています。
この研究は、FFAという症状がどのように発症するのか、その背景を明らかにしているのです。
果たして、ピルを飲むと髪の毛が薄くなるというのは本当なのでしょうか。
この記事では、研究結果を掘り下げながら、FFAに関する基本的な情報から、今回の研究の意義、さらにはそこから導き出される新たな考察まで、徹底的に解説します。
前頭線維性脱毛症(FFA)とは?
前頭線維性脱毛症(FFA)は、額の生え際や頭皮全体、場合によっては眉毛にまで広がる瘢痕性脱毛症の一種です。
FFAは、最初は気にならない程度の脱毛として始まることが多いものの、時間の経過とともに進行します。
適切な治療を行わない場合、髪の毛が生える毛包が完全に瘢痕化し、元に戻らない状況に陥ります。
炎症を伴うかゆみや痛みを伴うことがあり、物理的な不快感だけでなく心理的負担も大きい疾患です。
1994年に初めてこの疾患が報告されて以来、FFAの患者数は急増しています。
女性に多く見られることが多いこの症状が増加しているのは、ライフスタイルや環境要因の変化、さらにはホルモン療法の普及と無関係ではないと考えられています。
さらに、近年では若年層の患者さんも増加傾向にあり、疾患の早期発見と予防策が求められています。
FFAと経口避妊薬関連を調べる研究
今回の研究の中核を担ったのは、キングス・カレッジ・ロンドンの研究チームです。
彼らの研究の基礎には、FFAが単なる遺伝的要因だけでなく、環境的要因との相互作用によって発症するという仮説がありました。
この仮説を検証するため、経口避妊薬の影響に焦点を当てた分析が行われたのです。
使用されたデータの詳細
今回の研究データは、2015年7月から2017年9月にかけて英国全土で収集されました。
このデータには、FFAを発症している患者さんと発症していない女性が含まれており、遺伝子情報と生活習慣の記録が比較されました。
CYP1B1遺伝子+経口避妊薬=FFA?
研究では、ホルモン代謝に関与するCYP1B1という遺伝子が、FFAの発症リスクにどのように働くのかが詳しく調査されました。
そして、この遺伝子の変異がある女性が経口避妊薬を服用した場合、FFAを発症するリスクが上昇する可能性が指摘されました。
ホルモン代謝酵素の働きに影響を与えるこの遺伝子が、体内でのホルモンバランスに変化を引き起こし、炎症や瘢痕化を助長している可能性が示されています。
分析結果では、FFA患者の間でCYP1B1遺伝子変異の保有率が、非患者と比較して有意に高いことが示されました。
この発見は、FFAが環境要因だけでなく、特定の遺伝的要因と深く関係していることを強調しています。
避妊薬とFFAの関係をどう捉えるべきか
遺伝子検査の普及が進めば、FFAのリスクを事前に特定し、経口避妊薬を含む生活習慣の見直しを図ることが可能になるかもしれません。
例えば、高リスク群に該当する女性には、ホルモンを含まない避妊法を提案することが選択肢となるでしょう。
また、この研究結果は、避妊薬以外のホルモン療法にも波及効果をもたらす可能性はないでしょうか。
ホルモンの代謝に関連する遺伝子変異がどのように他の疾患に影響を与えるのか、さらなる研究がほしいところです。
経口避妊薬は多くの女性にとって不可欠な薬剤であるため、今回の発見は慎重に対応しなければいけません。
医療従事者や製薬会社は、女性の選択肢を狭めることなく、より安全な方法を提供する責任があります。
現段階では、自分がCYP1B1遺伝子変異の保有率が高いかどうかがわからないと、経口避妊薬を飲むことでFFAになる可能性が高いかどうかもわかりません。
また、CYP1B1遺伝子変異の保有率が高く、経口避妊薬を服用していても、FFAを発症しない人もいます。
逆に、CYP1B1遺伝子変異の保有率が低く、経口避妊薬を服用してもいないのに、髪の毛が薄くなっていく人もいます。
まだまだ確率論であるところが大きいため、安易に「ピル=薄毛になる」という誤解が広まらないよう、情報は正しく理解しなければいけません。
閉経後のホルモン変化とその影響
FFAの原因がホルモンと関連しているかもしれないとのことでしたが、女性は閉経後、どのようなホルモン変化があるのでしょうか。
ホルモンの変化がいつ始まるのか、どのような身体の変化が現れるのか解説していきます。
ホルモンの変化が始まるタイミング
閉経(通常、50歳前後)を境に女性の体内では劇的なホルモン変化が起こります。
この時期を中心に、女性ホルモンであるエストロゲンとプロゲステロンが著しく減少し、月経周期が完全に停止します。
これに伴い、卵胞刺激ホルモン(FSH)と黄体形成ホルモン(LH)が急上昇します。
そして、ホルモン変化の段階は以下のように分けられます。
生殖期後期の変化
卵巣内の卵胞は、女性の身体にとって重要なエストロゲンとプロゲステロンを分泌する源です。
加齢とともにその数が減少し、38歳頃から妊娠が難しくなることが一般的です。
卵胞の減少に伴い、卵胞刺激ホルモン(FSH)を抑制する「インヒビン」が低下します。
その結果、FSHが増加し、月経周期が短くなることがあります。
40歳代前半で月経周期が最短になる場合もあります。
閉経移行期(プレ閉経期)のホルモン動態
閉経の約7年前からFSHが急上昇し始め、エストロゲンの減少が徐々に進行します。
ただし、エストロゲンの減少速度やパターンは個人差が大きく、緩やかに減少する場合もあれば、一度増加した後に急降下する場合もあります。
月経が規則的でない時期が増えますが、稀に排卵が起こることもあります。
このため、妊娠の可能性が完全になくなるわけではありません。
更年期症状の現れ始めの症状
閉経前1~3年になると、FSHの急激な上昇とエストロゲンの急降下が見られます。
このホルモン変化により、以下の症状が現れます。
- のぼせ
- ほてり
- 発汗(いわゆるホットフラッシュ)
- 不安感や気分の落ち込み
閉経後5~8年に起こる症状
閉経後、エストロゲンとプロゲステロンは非常に低い水準に安定し、FSHとLHは高い状態で安定します。
このホルモン変化でエストロゲンが減少するため、骨吸収が進み、骨粗しょう症のリスクが高まります。
しかし、閉経から3年以上経過すると、多くの女性で更年期症状が軽くなります。
エストロゲン不足による以下のような問題が引き続くこともあります。
- 膣乾燥
- 頻尿や尿漏れの増加
閉経後8年以上で起こる症状
エストロゲンが少なくなると、長期的な影響を及ぼします。
この段階では、以下のような問題が目立ちます。
- 膣や子宮の萎縮
- 心血管リスクの上昇
- 皮膚が薄くなり、弾力性が失われる
- 記憶力の低下
閉経後の健康管理を始めよう
閉経は女性のライフステージの一つであり、身体の変化に伴う様々な影響があります。
この時期を健康的に過ごすためには、生活習慣の改善や予防策を取り入れると良いでしょう。
閉経後の生活をより快適にするためのポイントをいくつかご紹介します。
骨密度の低下を防ぐ方法
閉経後はエストロゲンの減少により骨密度が低下し、骨粗しょう症のリスクが高まります。
これを防ぐためには以下の対策が有効です。
-
カルシウムとビタミンDの摂取
牛乳やチーズ、ヨーグルトなどの乳製品、魚、緑黄色野菜からカルシウムを摂りましょう。
また、日光浴をしてビタミンDを体内で合成することも大切です。 -
適度な運動
ウォーキングや軽い筋トレは骨の健康を保つのに役立ちます。
特に重力がかかる運動が骨を強化します。 -
禁煙とアルコール制限
喫煙や過度なアルコール摂取は骨密度を低下させる要因になるため、控えましょう。
心血管疾患を予防する生活習慣
エストロゲンの減少により心血管疾患のリスクが高まるため、心臓と血管を守る生活習慣が必要です。
-
バランスの良い食事
野菜、果物、全粒穀物、脂肪の少ないタンパク質を中心にした食事を心掛けましょう。
塩分や飽和脂肪酸の摂取を控えることも重要です。 -
適度な運動
週に150分以上の有酸素運動(例えばジョギングやダンス)を目指しましょう。
血圧が安定し、血流が良くなります。 -
定期的な健康診断
血圧やコレステロール値を定期的に確認し、異常があれば早期に対処することが重要です。
更年期障害に向けたホルモン補充療法(HRT)
上記のような対策をしても症状がつらいなら、他の対処法を試してみるのも良いかもしれません。
例えば、ホルモン補充療法(HRT)は更年期症状の緩和や骨密度の維持に有効です。
適切に使用すれば、以下のような効果が期待できます。
- 血管運動症状の軽減:ホットフラッシュやのぼせの頻度を減らす。
- 骨折リスクの低減:骨粗しょう症による骨折を予防する。
しかし、HRTには以下のリスクが伴います。
- 乳がんリスクの増加:特に長期間使用する場合には注意が必要です。
- 血栓症のリスク:エストロゲンが血液を凝固しやすくするため、血栓症の可能性がわずかに増加します。
医師に治療のリスクとメリットを聞き、自分にとってより納得できる選択肢を選ぶようにしましょう。
まとめ
この研究は、FFAという疾患が単なる遺伝的要因によるものではなく、経口避妊薬の服用を含む環境要因との複雑な相互作用によるものであることを明らかにしました。
まだまだ確定要素が足りませんが、髪の毛が薄くなることに強い抵抗を感じる女性の場合は、ピルの服用について再検討すると改善するかもしれません。
しかし、ピルそのものが薄毛を誘発するわけではありませんし、ピルのメリットは計り知れないため、安易に服用を止めるのはむしろリスクとなりえる点にも注意が必要です。