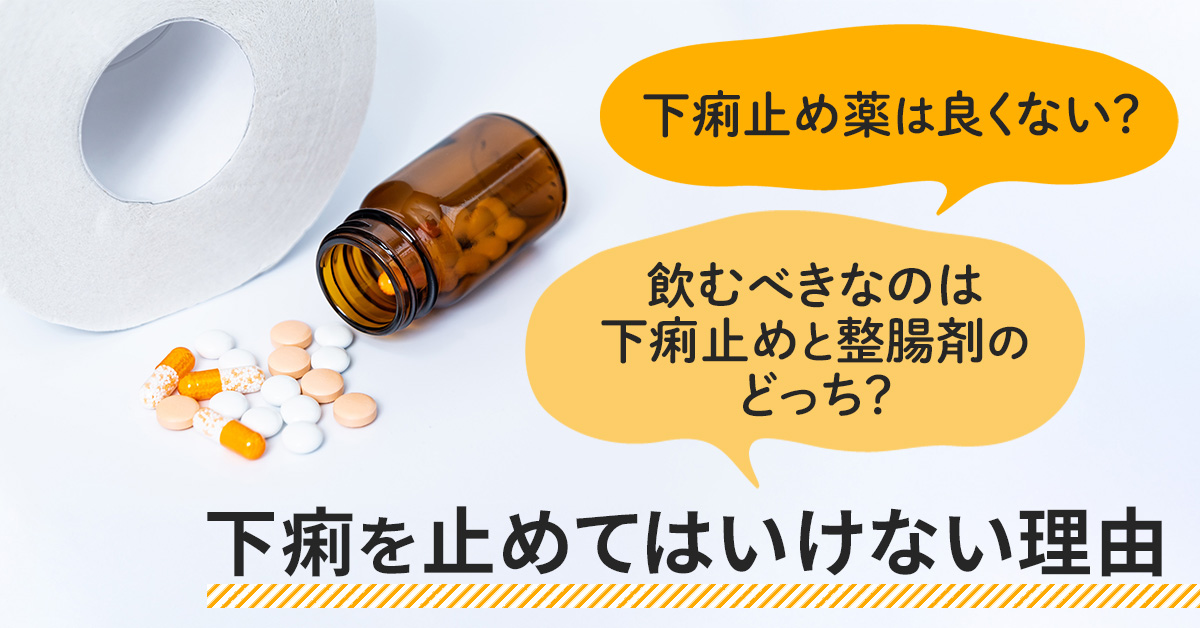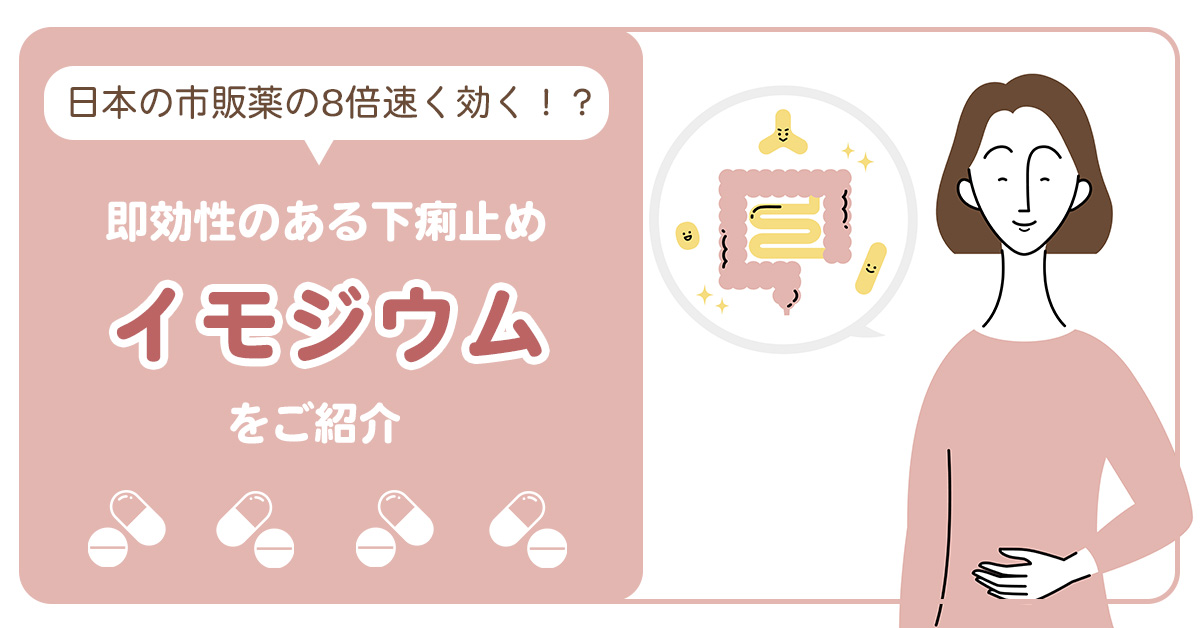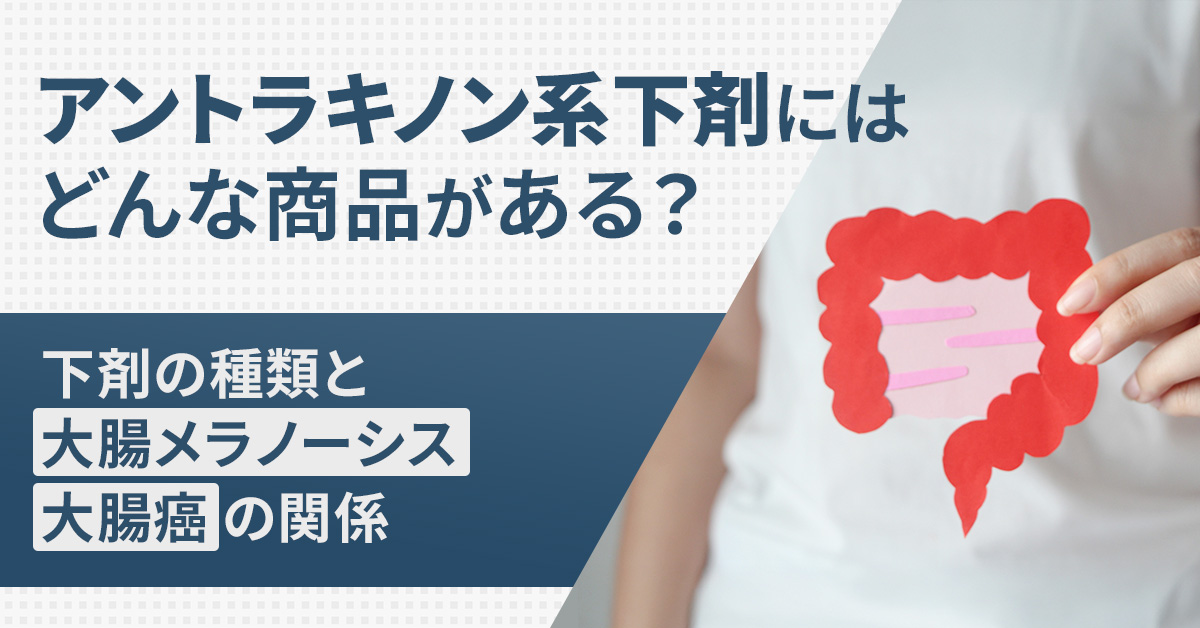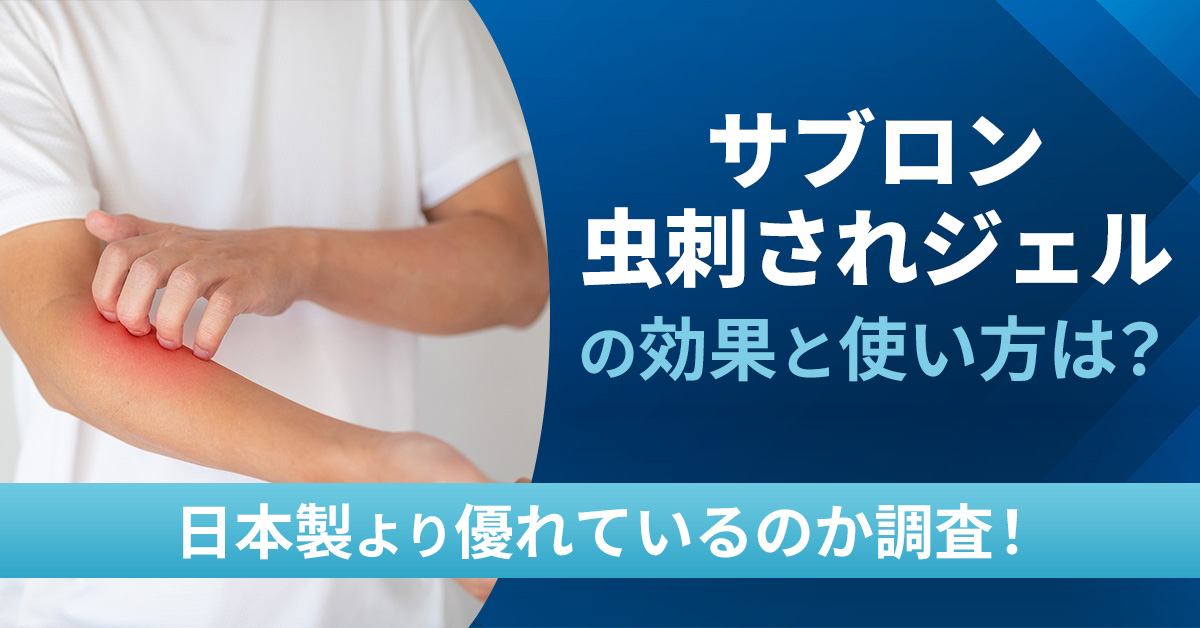タイミングもお構いなしに襲ってくる下痢の症状に悩んでいる方は少なくないかもしれません。
簡単にはトイレに行けない不安と、なかなか落ち着かない辛い症状に冷や汗をかいた経験は誰にでもあるのではないでしょうか。
今回はそんな辛い下痢の症状を抑える効果を持つ下痢止め薬を中心に「下痢止め薬は良くない」「飲まない方がいい」という噂の真相に迫っていきます。
下痢止め薬のことが気になっている方はぜひ参考にしてください。
下痢とは
水分量が増えて液状や液状に近い状態となった便を「下痢便」といい、液状ほどではない通常よりもやわらかい状態の便を「軟便」と呼びます。
通常の便の水分量は約70~80%ですが、80%を越えるようになると軟便や下痢に分類されます。
下痢が起きる原因
腸は水分を吸収しながら蠕動運動によって食べ物のカスを肛門に送りますが、何らかの原因によって水分調節機能や蠕動運動に異常が起きると軟便や下痢となります。
軟便や下痢の原因については、以下のようなことが考えられています。
- 食あたり
- 水あたり
- 感染症
- 消化不良
- ストレス
食あたりは賞味期限切れや調理から時間が経った食べ物、火の通りが甘かった食材を食べてしまうことで起きます。
食あたりや水あたりは食品や水が細菌やウイルスに汚染されていることが原因となるケースがあります。
また、細菌やウイルスによる感染症は食べ物が原因となるケース以外にも、感染者の飛沫や嘔吐物が原因となることもあります。
他にも刺激の強い香辛料やカフェイン、脂肪分・糖分の多い食べ物を食べ過ぎることで消化不良が起きたり、緊張や不安などのストレスによって自律神経が乱れたりして下痢を引き起こすこともあります。
下痢を止めてはいけない理由
冷えや食べ過ぎなどが原因の下痢であれば下痢止めを使用することもありますが、細菌やウイルスが原因となる下痢では基本的には下痢止めは使用しません。
感染症が原因の下痢は細菌や有毒物質を体外に排出する働きがあるため、下痢止めを使って下痢を止めてしまうと細菌や有毒物質が身体の中に留まってしまいます。
病原体をできるだけ速やかに身体から出すためにも、感染症が原因の下痢の時には下痢止めを使用するのは避けましょう。
下痢止め薬の効果と副作用
ここでは下痢止め薬の効果や作用機序、副作用などを具体的に紹介していきます。
効果
下痢止め薬は腸の過剰な蠕動運動や消化管の炎症を抑制したり、下痢を引き起こす原因物質を吸着したりして下痢を止める作用があります。
これら作用は薬剤の成分によって異なり、例えばロペラミド塩酸塩を主成分とするロペミンカプセルでは蠕動運動や水分や電解質の異常を抑制する作用、次硝酸ビスマスであれば腸内のガスによる刺激を和らげて下痢を止める作用などがあります。
副作用と注意点
下痢止め薬の副作用には、腹部膨満感や吐き気、便秘などの消化器症状や薬剤によっては不安や注意力低下などの精神神経症状があります。
また、下痢止め薬で最も注意が必要となるのが、赤痢菌などの重篤な感染症による下痢には使用してはいけないという点です。
病原菌や毒素の排出を抑えてしまうと症状が悪化したり、治療期間が長くなってしまったりする可能性があるため、感染症が原因となる下痢には使用しないようにしましょう。
加えて、下痢止め薬と飲み合わせに注意が必要な薬剤や食べ物もあります。
タンニン酸アルブミンが配合された薬剤は乳性カゼインを含んでいることから牛乳に対してアレルギーがある方への使用は禁止されています。
さらに天然ケイ酸アルミニウムが主成分のアドソルビンはやニューキノロン系抗菌薬やテトラサイクリン系抗菌薬は抗菌作用が弱くなる可能性があるため、併用する場合には間隔を空ける必要があるとされています。
また、下痢止め薬を約4~5日飲み続けても下痢が改善されない時には、大腸がんや潰瘍性大腸炎などが原因の可能性もあるため、放置せずにできるだけ早く医療機関を受診してください。
下痢の時の薬剤の選び方
ここまで下痢止め薬の効果や注意点を紹介してきましたが、下痢が辛い時にどんな薬剤を飲めばよいのか分からなくなってしまった方もいらっしゃるかもしれません。
下痢や軟便の時には、整腸剤を使用するのも1つの手段です。
整腸剤とは
整腸剤は腸内の善玉菌を増やして腸内環境を整える薬剤で、下痢や便秘などの消化器症状を改善する効果が期待できます。
整腸剤には乳酸菌やビフィズス菌、酪酸菌などが配合されており、有害なガスを発生させる悪玉菌の増殖を抑えて、腸の働きを正常化していきます。
即効性はありませんが、少しずつ腸内環境を整えて、下痢や便秘などの消化器症状を起きにくくする効果が期待できます。
下痢止め薬と整腸剤どっちを使う?
これまでもお話しているように下痢止め薬は下痢を止めると同時に、病原菌や毒素の排出も阻害してしまう可能性があるため、使いどころが難しい薬剤です。
一方で整腸剤は下痢止め薬と違って病原菌や毒素の排出を止める効果はないため、症状やタイミングを選ばすに使用できるのがメリットです。
これらの理由からも安易に下痢止め薬は使用せず、整腸剤を使用して下痢を少しずつ改善していく方がトラブルになりにくいと言えるでしょう。
ただし、感染症が原因であっても脱水症状が酷い時には、水分の流出を抑えるために医師から下痢止め薬が処方されることがあります。
このような時には指示に従って、下痢止め薬を飲んでください。
また、食べ過ぎや冷えなどが原因で明らかに感染症ではないとわかる時には下痢止め薬を使用するのも1つの手段です。
下痢止め薬は整腸剤と併用しても問題ないので、両方の薬剤を服用することも可能です。
市販の下痢止め薬
下痢止め薬は、薬局やドラッグストアでも販売されています。
製品によって少しずつ作用が異なりますので、購入の際は説明書をよく読んで自分に合った薬剤を選ぶようにしましょう。
食べ過ぎや冷えによる下痢
食べ過ぎや冷えなどが原因の下痢には、活発化した腸の動きを抑えて水分量を調整する作用のあるロペラミド塩酸塩を配合した大正製薬の「ピタリット」や、興和の「トメダインコーワフィルム」などがおすすめです。
トメダインコーワフィルムは口の中で溶けるシートタイプの下痢止め薬で、水なしで服用できるため、急な腹痛でも場所を選ばず服用できます。
ただし、これらの下痢止め薬は眠気が現れる可能性があるため、服用後は乗り物や機械の運転操作は避けましょう。
過敏性腸症候群による下痢
過敏性腸症候群は、不安や緊張などのストレスによって自律神経のバランスが崩れ、腸の蠕動運動が活発になりすぎて下痢を引き起こします。
蠕動運動を抑えて腸がしっかり水分を吸収できるようにして症状を落ち着かせ、下痢を改善していきます。
過敏性腸症候群におすすめの市販薬はライオンの「ストッパ下痢止めEX」です。
個人差はありますが効果がスピーディーに現れるのが特徴とされ、早い人であれば約10分で効き始めると言われています。
予防としての使用はできませんが、水なしで飲めるので、お腹に違和感が出始めた時にすぐ服用できます。
下痢の症状を和らげる3つのポイント
最後に下痢を和らげる生活のポイントを3つ紹介します。
下痢は腸が弱っている証拠とも言えるので、できるだけ腸に負担をかけない生活を心掛けていきましょう。
消化のよい食事にする
下痢の原因は様々ありますが、腸に直接影響を与える食事を優しいものに変えていくことは非常に大切なポイントです。
胃に負担をかけにくいおかゆやスープなど消化によい食事を、よく噛んで食べるようにしてください。
また、食べる量が増えると胃の負担が大きくなるため、少し量は控えめにするとよいでしょう。
反対に下痢の時に避けたい食べ物には、冷たい食べ物や飲み物、油っこい食べ物、刺激の強い香辛料、カフェイン、アルコールなどがあります。
さらに普段は身体によいとされている豆やかぼちゃ、根菜類はガスを発生させやすいので、症状が落ち着くまでは避けましょう。
身体を温める
お腹が冷えると交感神経が優位になり、腸の動きが悪くなって下痢を引き起こすため、身体を冷やさないようにしましょう。
上着羽織る、腹巻をするなどの身体の外から温める方法に加え、温かい食べ物を食べるなどの身体の内側から温める方法も取り入れていくと効率的です。
夏でも汗やクーラーによって、思ったよりもお腹は冷えています。
冷たいものを飲みたくなる季節でもありますが、腸への負担を和らげるためにも一気に飲むのではなく、少しずつ口に含んで飲み込むようにしていきましょう。
心身を整える
自律神経に影響を与えるストレスは、自律神経によって動いている腸にとっても厄介な存在です。
自律神経のバランスが崩れると、腸が過敏になって下痢などの症状を引き起こすため、できるだけ原因となるストレスを溜めないことが大切です。
自律神経を安定させるためには、質の良い十分な睡眠に加え、バランスの良い食生活を送ること、適度な運動をすることなどが大切です。
身体と心の両面から整えて、心地良い生活が送れるよう心掛けていきましょう。
下痢止め薬は感染症の下痢にはよくない
下痢止め薬は辛い下痢を止める効果がある薬剤ですが、病原体や毒素の排出を妨げてしまうため、感染症が原因の下痢に使用するのはよくないとされています。
このような感染症が原因となる下痢には整腸剤を使用して、腸内環境を整えていく治療を行うケースが多いです。
一方で、冷えや食べ過ぎなどが原因の下痢の場合は、下痢止めを使用することができます。
市販の下痢止め薬も即効性が期待できる商品が販売されているので、下痢でお悩みの方は検討してはいかがでしょうか。