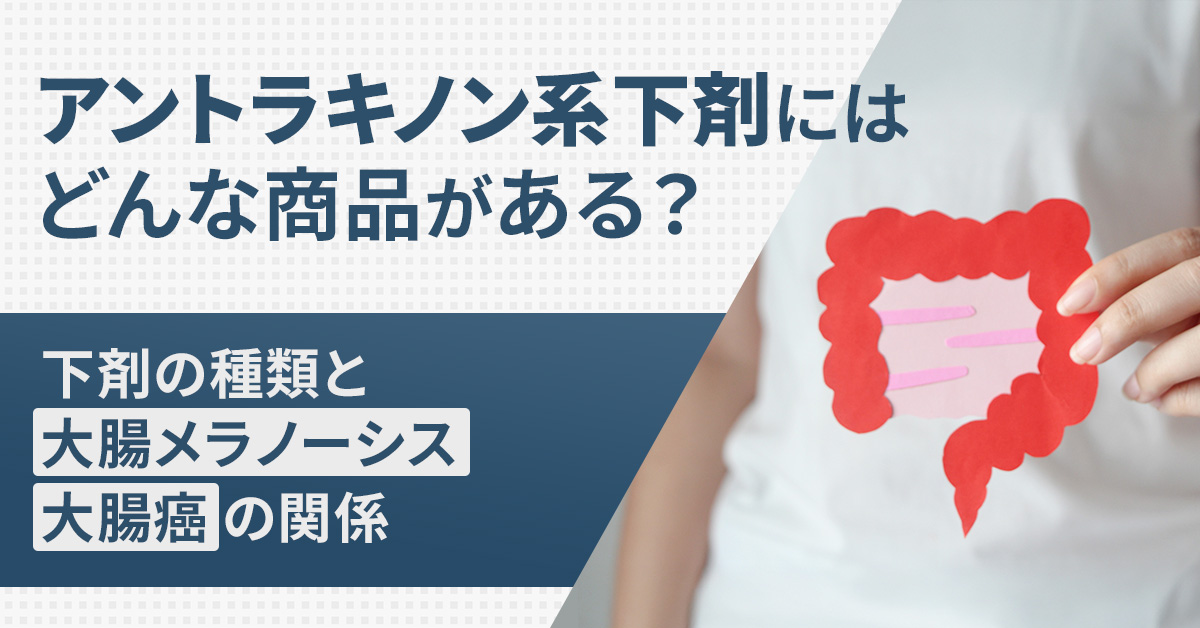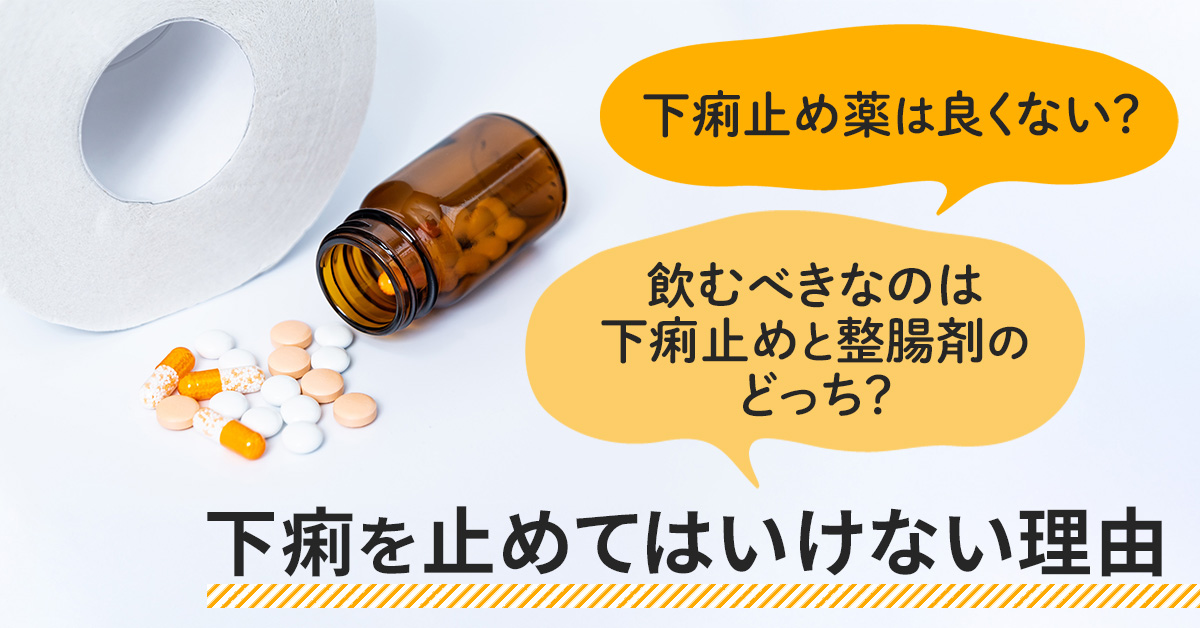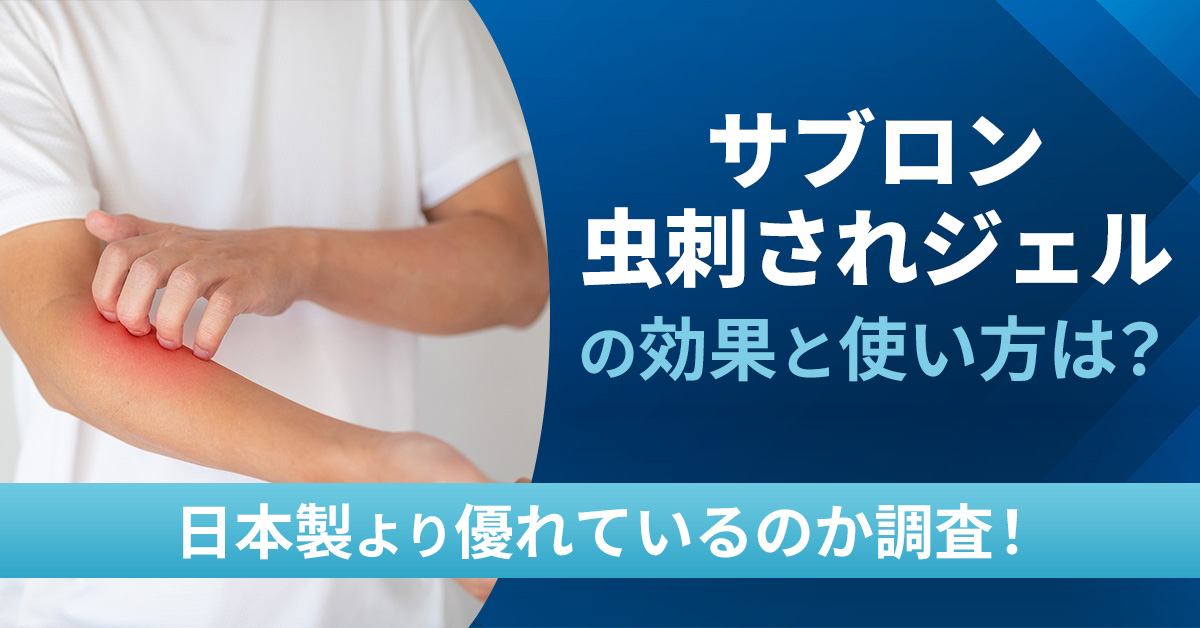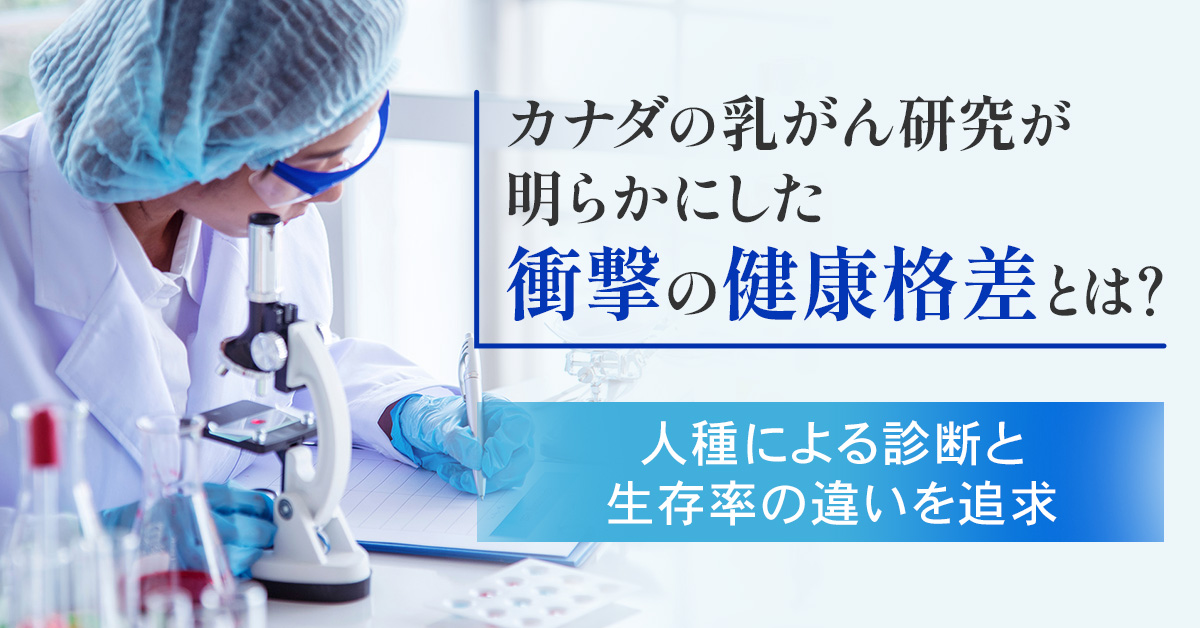体内に長時間便が残ってしまう便秘は腹痛や腹部膨満感による食欲不振を招くだけではなく、腸閉塞や切れ痔に加え、心筋梗塞や脳卒中などを引き起こす恐れがあります。
このような辛い症状を改善するために下剤を使用することがありますが、下剤には様々な種類があり成分や作用が異なるのをご存知でしょうか。
今回は下剤の中でもアントラキノン系と呼ばれる種類にフォーカスし、成分や作用などを紹介していきます。
また、アントラキノン系でしばしば問題になる大腸メラノーシスについても解説しますので、下剤選びの参考にしてください。
アントラキノン系下剤とは
アントラキノン系下剤は大腸を刺激して排便を促す作用を持つ薬剤で、大腸刺激性下剤に分類されます。
大腸刺激性下剤もさらに「アントラキノン系下剤」「ジフェノール系下剤」「ジフェルニルメタン系下剤」に分かれ、作用の強さや副作用などに違いがあります。
ここではアントラキノン系下剤を中心に解説していきます。
アントラキノン系下剤の成分と市販薬
アントラキノン系下剤の主成分にはセンナ、ダイオウ、アロエなどがあり、下剤だけでなく、漢方薬や便秘改善・ダイエット効果をうたっている健康茶などに使用されています。
センナ
センナはアフリカ原産の生薬で、ヨーロッパでは古くから下剤として使用されていました。
実や葉にアントラキノンの一種であるセンノシドを含むセンナは、大腸の粘膜を刺激して蠕動運動を活発化させる作用があるため、特に弛緩性便秘に効果があるとされています。
センナを含む商品としては、センノシドやプルゼニド、アローゼン、スルーラックなどが製造されています。
ダイオウ
ダイオウは主に中国や日本に生息する背丈が2~3mにもなる大型の多年草で、乾燥させた根や根茎を使用します。
腸を動かして排便を促す作用があり、便秘や便秘に伴う吹き出物などを改善します。
ダイオウを含む商品には、大黄甘草湯や防風通聖散、セチロ、大柴胡湯などがあります。
アロエ
アロエは肉厚な葉の中にゼリー状の組織を蓄えた多肉植物で、食用とされるアロエベラや薬用として使用されるキダチアロエなどの種類があります。
鑑賞用としても楽しまれるアロエは「医者いらず」という異名が付くほど様々な作用があるとされ、古くから火傷や切り傷の治療、胃痛や便秘などを和らげるために使用されてきました。
アロエを含む商品には、アロエ便秘薬やアロエ錠などが販売されています。
アントラキノン系下剤の特徴
アントラキノン系下剤は腸を直接刺激して排便を促す作用があるため、効果が得られやすい点がメリットです。
ただし、薬剤に頼るようになって何度も使用していくうちに大腸を動かす平滑筋が働きにくくなって効果が鈍くなる弛緩性便秘を引き起こすデメリットがあります。
また、アントラキノン系下剤は、大腸が黒くなる大腸メラノーシスを発症することでも知られています。
アントラキノン系下剤の成分は自然由来のものが多く安心してしまいがちですが、その効果は強力で癖になりやすい特徴を持ちます。
これらのことからも、アントラキノン系下剤は、長期的使用を避け、用法用量を守って正しく使うことが大切と言えるでしょう。
大腸メラノーシスと大腸癌の関係
アントラキノン系下剤の問題点となっている大腸メラノーシスとは一体どんな症状なのでしょうか。
また、大腸メラノーシスと大腸癌との関連性についても解説していきます。
大腸メラノーシスとは
大腸メラノーシスは、リポフスチンという物質によって大腸の粘膜が褐色や黒色に染まってしまう症状のことです。
「メラノーシス」と呼ばれているもののメラニンによって色が付いているわけではないため、厳密には「偽メラノーシス」と言います。
この黒色は、刺激性下剤の影響を受けた腸管の細胞が死滅してそれをマクロファージが食べることで生成されると言われています。
大腸メラノーシスになるとどうなる?
大腸メラノーシスそのものは病気ではなく、癌のリスクを直接高めたりもしません。
ただ、粘膜が黒くなることで大腸の異変を見つけにくかったり、蠕動運動に関連する神経がダメージを受けて大腸の動きが悪くなり弛緩性便秘を引き起こしたりする恐れがあります。
弛緩性便秘になると刺激性下剤が効きにくくなり、排便の効果が弱まってしまうという負の連鎖が起きてしまうことがあります。
大腸メラノーシスは治る?
大腸メラノーシスは病気ではないため、基本的に治療をする必要はありません。
ただし、弛緩性便秘を引き起こすなどのデメリットもあるので、改善していくことが望ましいと言えます。
アントラキノン系下剤を始めとする刺激性下剤が原因となる大腸メラノーシスの場合は、刺激性下剤の使用を中止することで改善されていきます。
しかしながら、正常な粘膜の色に戻るまでは1年くらいの時間を要するため、アントラキノン系下剤は長期的に服用するのは避けて、大腸メラノーシスにならないように予防することが大切です。
大腸メラノーシスを引き起こす下剤
大腸メラノーシスを引き起こす下剤は、腸を刺激して排便を促す作用を持つ刺激性下剤のうちのアントラキノン系下剤に属するものです。
刺激性下剤は他に「ジフェノール系下剤」「ジフェルニルメタン系下剤」がありますが、この2つは大腸メラノーシスにはならないとされています。
アントラキノン系下剤には、センナやアロエ、ダイオウなど自然由来の生薬などを成分としたものが多く、一見身体に害がなさそうに思い込んでしまいますが、その作用は強く癖になりやすい特徴があります。
また、アントラキノン系下剤に使われている成分は便秘薬だけでなく、医師の処方の必要がない健康食品などにも配合されています。
「自然由来」や「健康茶」などの耳あたりの良い言葉に踊らされないよう、しっかり成分を確認してから使用するようにしましょう。
下剤の種類と作用
これまでアントラキノン系下剤を中心に解説してきましたが、大腸メラノーシスを引き起こしたり、癖になりやすかったりするデメリットがあるため、一体どんな便秘薬を選んだら良いのか困ってしまった方も多いかもしれません。
そこで、ここではアントラキノン系下剤以外の下剤についても紹介していきます。
主な下剤については下記一覧表にまとめた通りです。
| 分類 | 種類 | 一般名 |
|---|---|---|
| 刺激性下剤 | アントラキノン系 | センナ、アロエ、ダイオウなど |
| ジフェニール系 | ピコスルファートナトリウムなど | |
| ジフェルニルメタン系 | ビサコジルなど | |
| 膨張性下剤 | カルボキシメチルセルロース | |
| 浸透圧性下剤 | 塩類下剤 | 酸化マグネシウム、水酸化マグネシウムなど |
| 浸潤性下剤 | ジオクチルスジウムスルホサクシネートなど | |
| 高分子化合物 | ポリエチレングリコール | |
| 上皮機能変容薬 | クロライドチャネルアクチベーター | ルビプロストン |
| グアニル酸シクラーゼC受容体アゴニスト | リナクロチド | |
| 胆汁酸トランスポーター阻害薬 | エロビキシバッド |
ここからは下剤の分類ごとに、1つずつ簡単に解説していきます。
刺激性下剤
刺激性下剤は大腸を刺激して排便を促す作用を持つ下剤で、これまで解説してきたアントラキノン系やジフェニール系、ジフェルニルメタン系などがあります。
大腸が黒く変色する大腸メラノーシスが起きるのはアントラキノン系下剤だけですが、ジフェニール系下剤とジフェルニルメタン系下剤も弛緩性便秘を引き起こす可能性があります。
長期間使用を続けると癖になり、さらにひどい便秘になってしまう恐れがあることから、注意が必要な下剤と言えます。
膨張性下剤
膨張性下剤は、薬剤が水分を吸収し便を大きくして排便を促す作用を持つ下剤です。
非刺激性下剤なので効果が出るのが少し遅いですが、耐性はつきにくく比較的癖になりにくいという特徴があります。
ただし、大腸にポリープや癌があったりすると、大きくなった便によって腸閉塞を引き起こす可能性があるため注意が必要です。
浸透圧性下剤
浸透圧性下剤は腸管内の浸透圧を高めて水分を腸管内に集め、便を柔らかくして排便を促す作用のある下剤です。
耐性がつきにくいため癖になりにくく、血液中にもごくわずかしか吸収されないため、安全性が高い下剤と言えます。
注意点としては、腎障害がある人は高マグネシウム血症を生じる可能性があるため、医師に相談してから使うようにしてください。
上皮機能変容薬
上皮機能変容薬は腸内にある粘膜に作用して水分を集め、便を柔らかくして排便を促す作用を持つ薬剤です。
上皮機能変容薬も非刺激性下剤に分類され、癖になりにくいのが特徴です。
また、浸透圧性下剤は高マグネシウム血症を引き起こす可能性がありますが、上皮機能変容薬では認められていません。
ただし、副作用として下痢や吐き気などが報告されており、特に食事時間が近いと影響を受けやすいと言われています。
このような理由からも、食後の服用は避けて食前30分前に飲むとよいでしょう。
胆汁酸トランスポーター阻害薬
胆汁酸トランスポーター阻害薬は胆汁酸トランスポーターという物質を阻害して、腸内に流入する胆汁酸の量を増やす作用があります。
これにより、腸管内の水分分泌が増加し、消化運動を促して便秘を改善していきます。
また、胆汁酸トランスポーター阻害薬にはコレステロールの吸収を助ける作用もあるため、コレステロールの低下も期待できると言われています。
下痢や吐き気、腹痛などの消化器症状の他、稀に頭痛やめまいなどの精神神経系症状や肝機能の異常などの副作用を引き起こす可能性があるため、注意が必要です。
アントラキノン系下剤は大腸メラノーシスに注意
アントラキノン系下剤はセンナやアロエ、ダイオウなどの自然由来の生薬が主成分となっていますが、長期的に使用すると腸内粘膜が黒く変色する大腸メラノーシスや、大腸を動かす平滑筋が働きにくくなる弛緩性便秘を引き起こす可能性がある下剤です。
癖になりやすいので、使いすぎには気をつけるようにしてください。
下剤には大腸メラノーシスや弛緩性便秘になりにくい非刺激性下剤も多数あるので、癖になりにくく、自分に合った薬剤を見つけていきましょう。