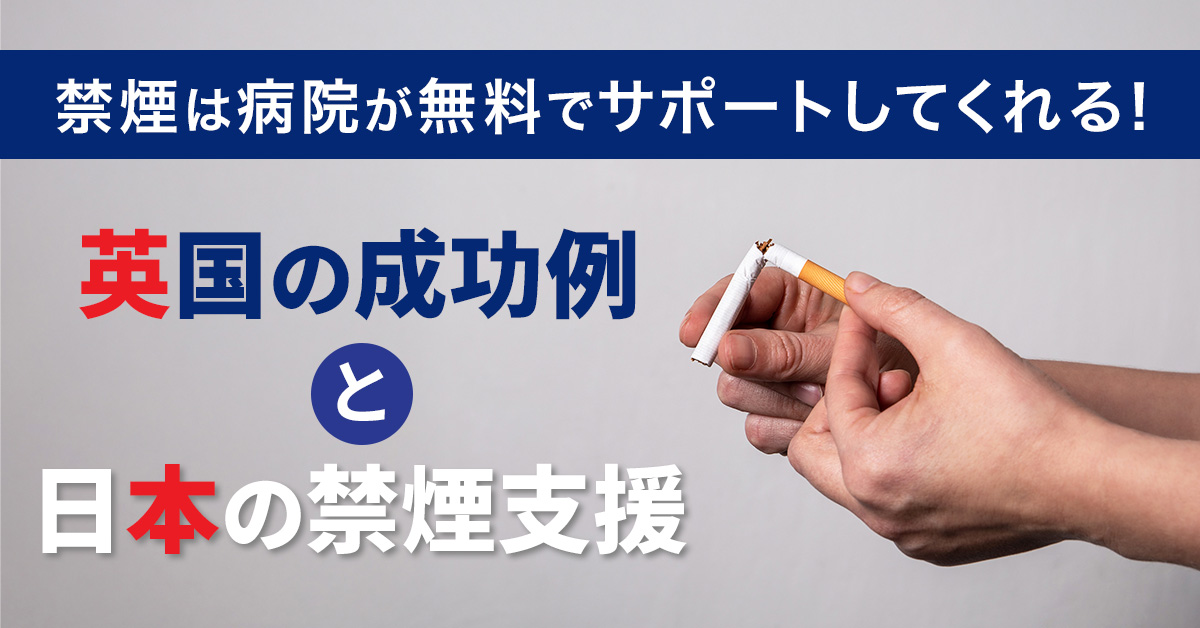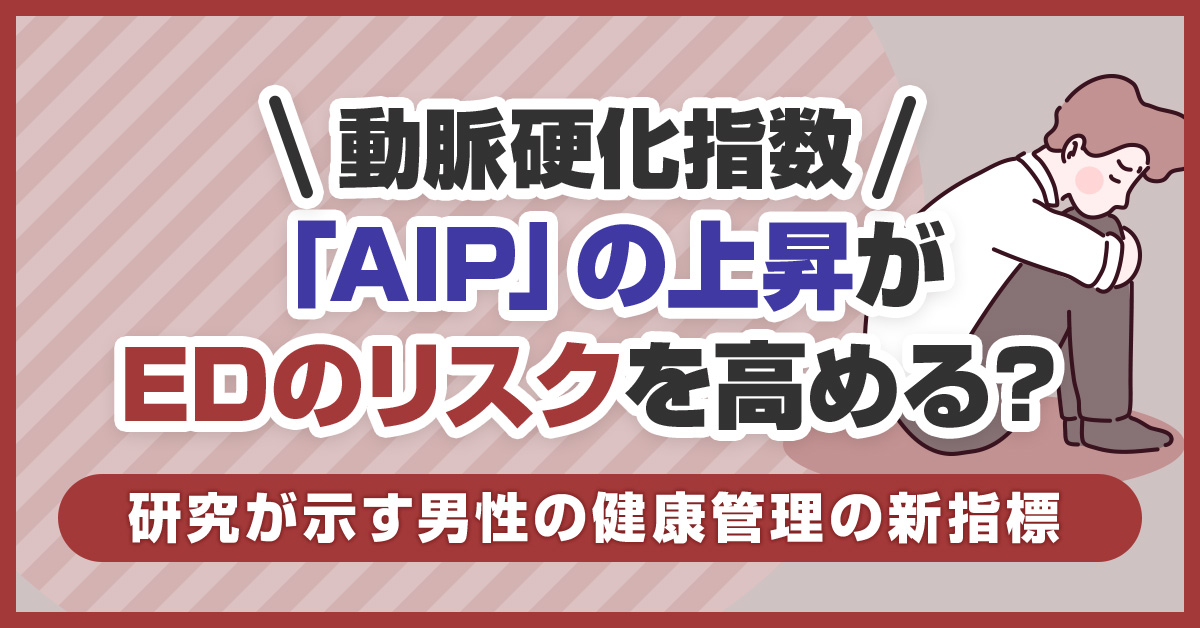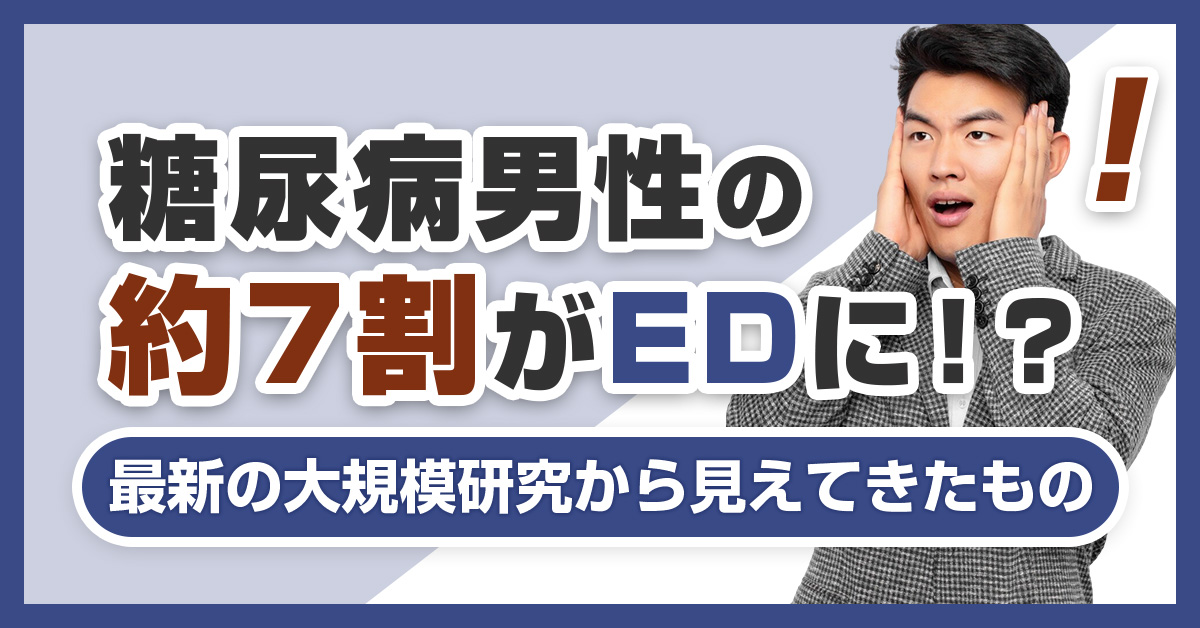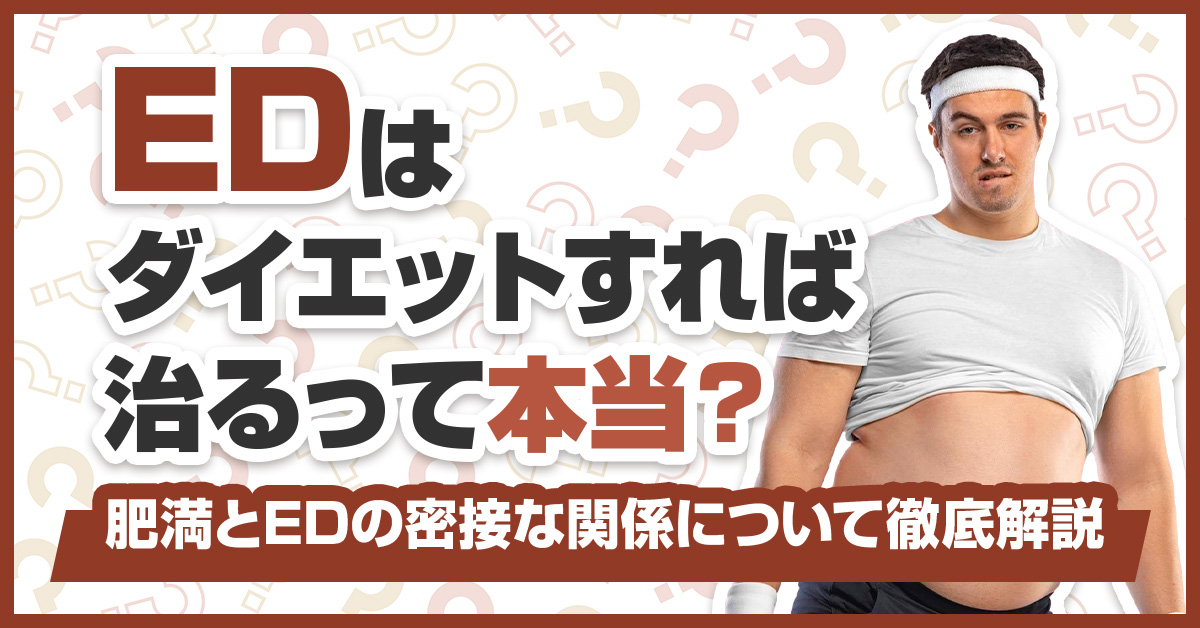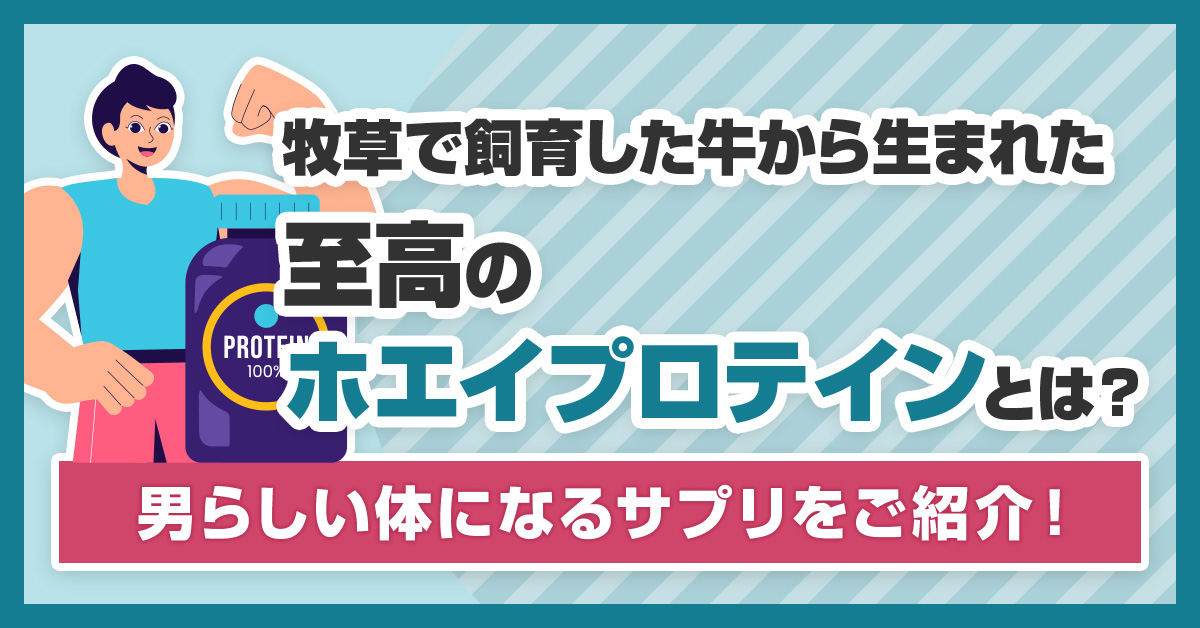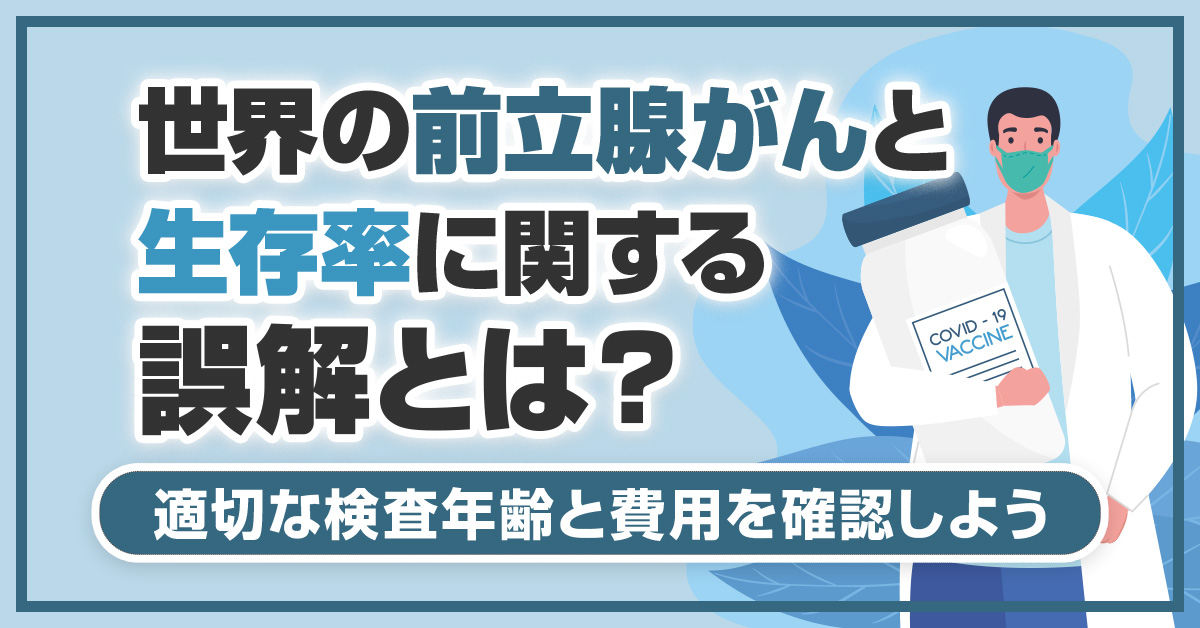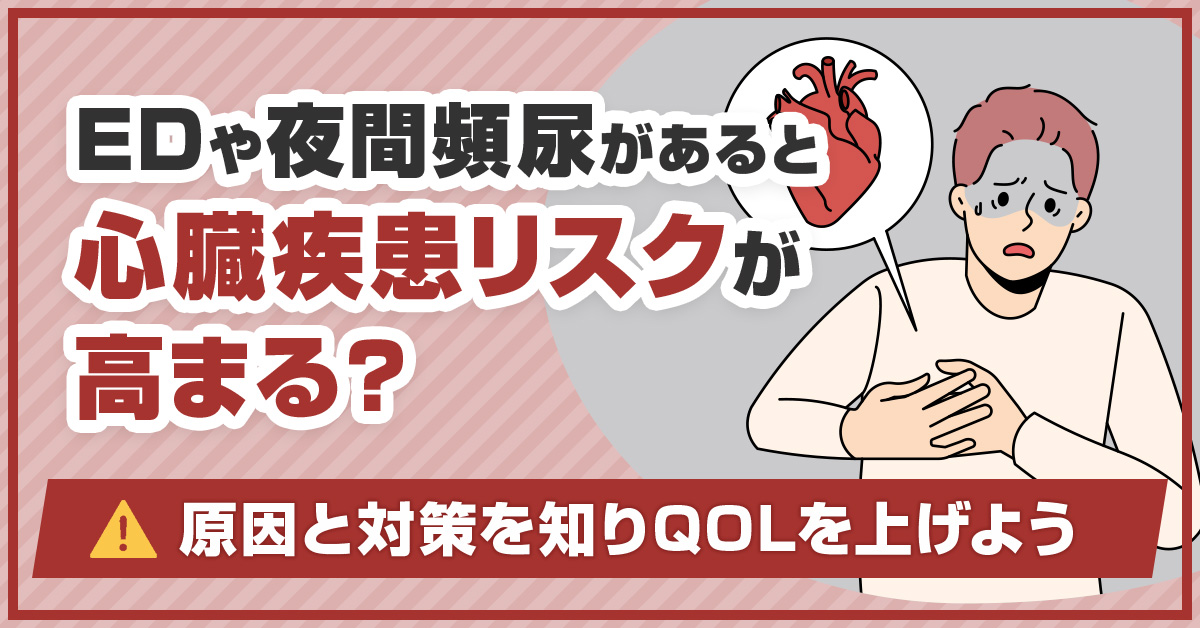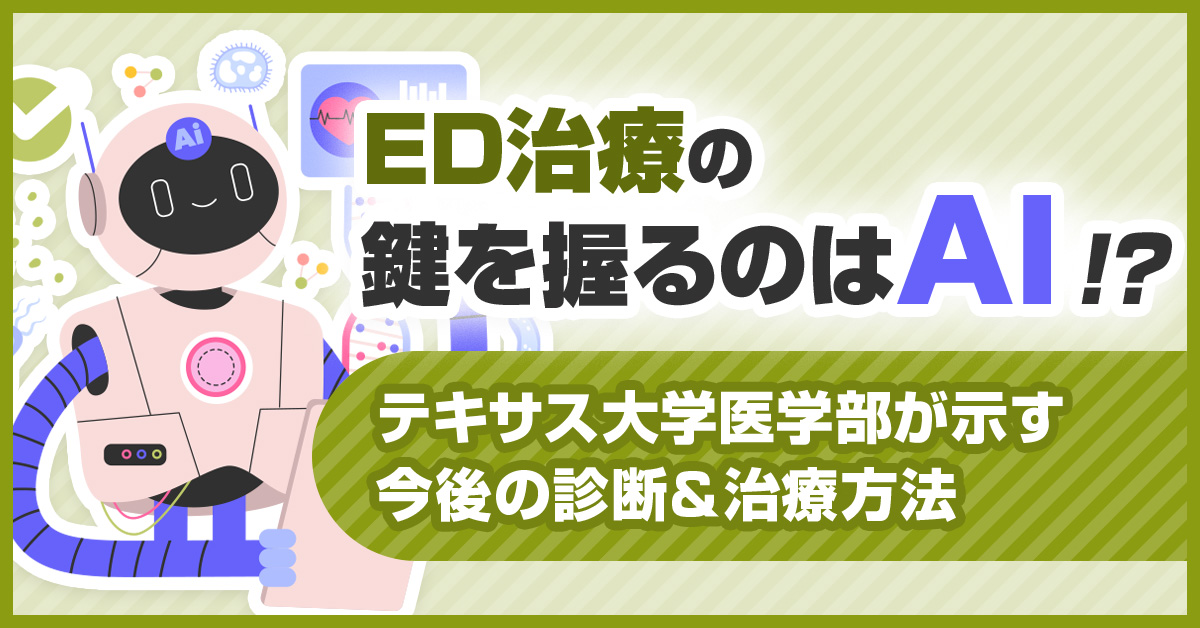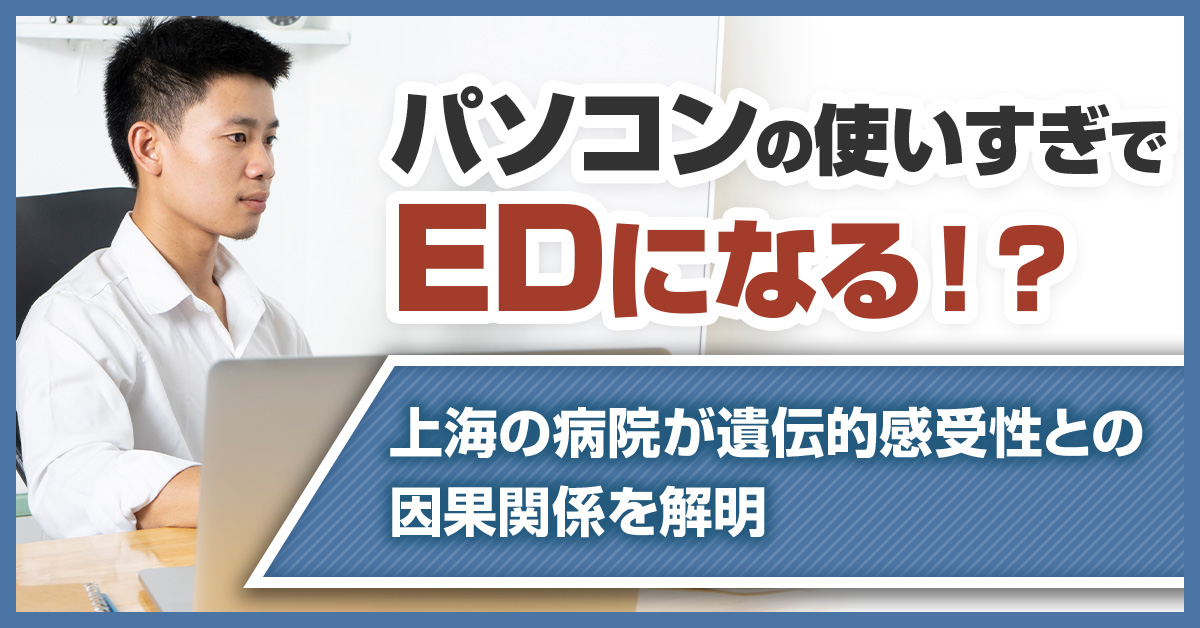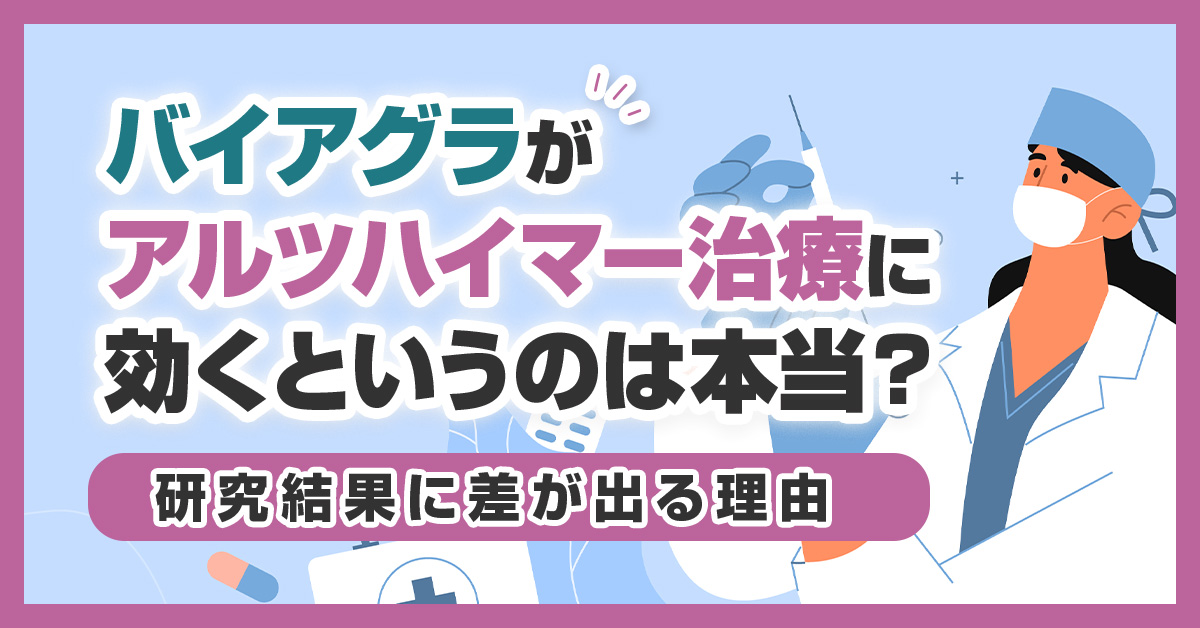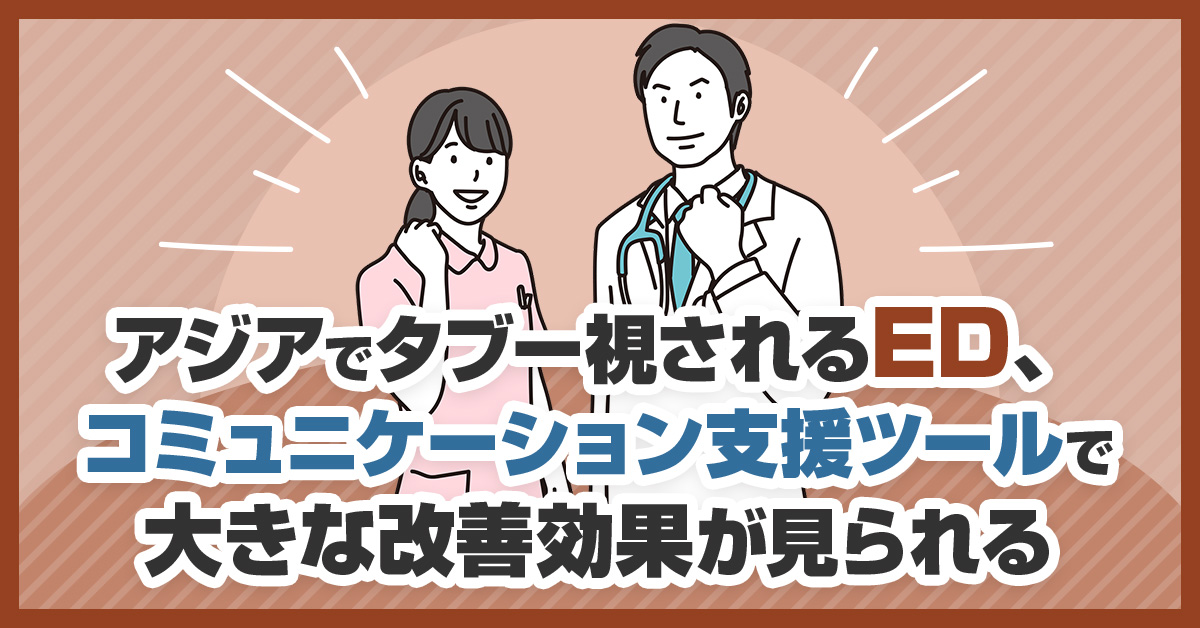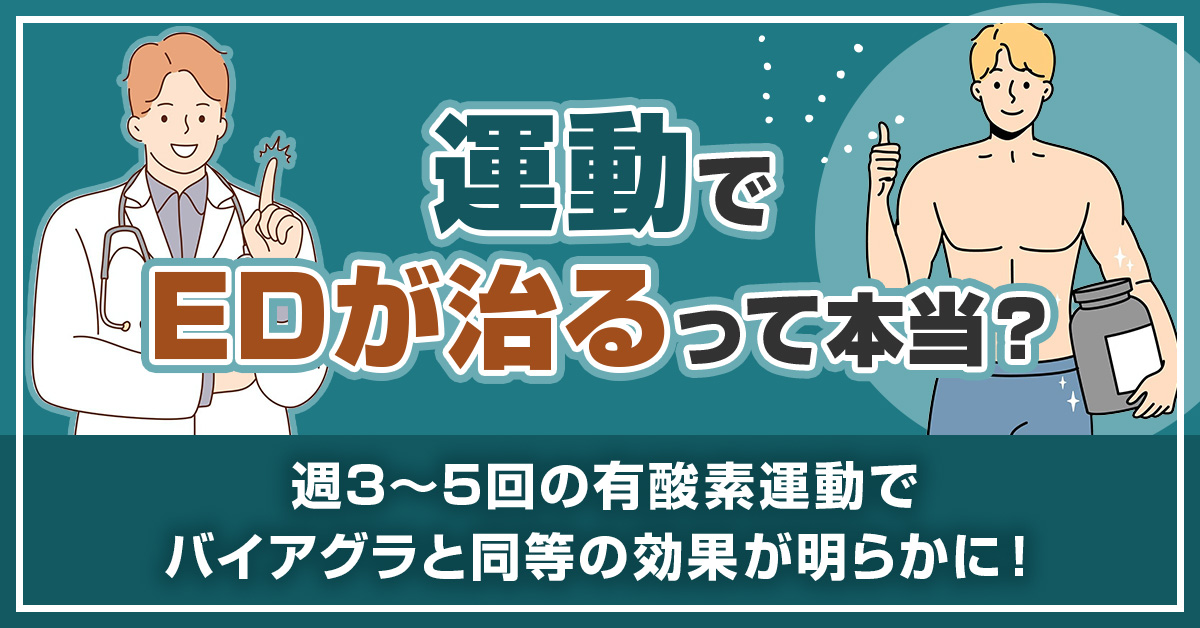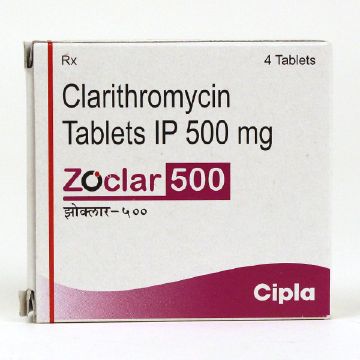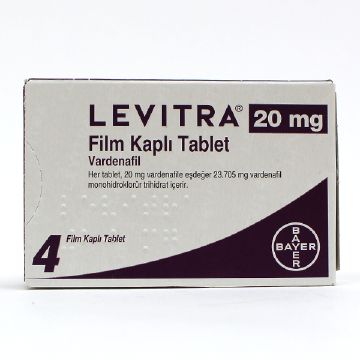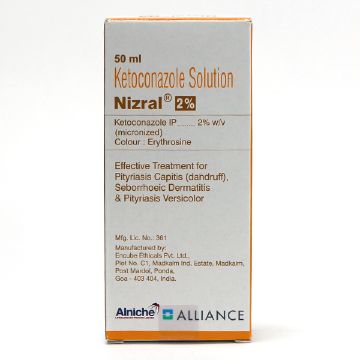エヴィリーナ ロンドン小児病院では、建築家やデザイナー、エンジニアといった医師以外の専門家が集結し、今後の小児がん治療をサポートするための新しい取り組みを進めています。
このプロジェクトは、医療施設の環境が患者さんの治療に与える影響を大いに考慮したものであり、患者さんとその家族に寄り添った空間作りを目指しています。
病院のイメージを、建築とデザインの方面から変える試みは興味深いものです。
この記事では、その概要と取り組みのポイントをご紹介していきます。
エヴィリーナ ロンドン小児病院の進化とは?
エヴィリーナ ロンドン小児病院では、患者さんがより安心して治療を受けられる空間を作るために、環境に配慮した設計にしようという計画が持ち上がりました。
この病院はNHS(国民健康サービス)による地域の小児がん治療センターとしての指定を受け、建築家やデザイナーがその環境整備に力を尽くしています。
患者さんの心理的サポートが目的
建築家やデザイナーは、建物のデザインを通して子どもたちと家族の心理的なサポートを図ります。
治療の負担を軽減するのが目的です。
患者さんや病院のスタッフが意思決定に積極的に参加し、ニーズを反映させるとのこと。
デザインは単なる建築物ではなく、実際の治療の一部として機能するように設計されています。
患者参加型であるところがとても良いですよね。
未来の医療施設づくりにおいて重要なモデルとなるかもしれません。
専門家の協力体制
今回のプロジェクトには、建築を担う「ADPアーキテクチャー(ADP Architecture)」と、エンジニアリングを担当する「ランボル(Ramboll)」がリーダーとして参加しています。
ADPアーキテクチャーは、これまでにも受賞歴のある子ども向け施設を手掛けた経験があり、ランボルlは多分野にわたる技術を持つエンジニアリングの専門家です。
この2社が協力し、設計と技術の面で様々な視点を取り入れることで、施設の耐久性や機能性、そして温かみのあるデザインの両立が期待されています。
さらに、都市計画や道案内サポートを専門とするコンサルタントも加わっており、子どもやその家族が使いやすい空間づくりが進められています。
例えば、道案内のアートや視覚的なサポートを得意とする専門家が参加することで、施設内を迷うことなく移動できる工夫がなされる見通しです。
患者さんと家族の声を尊重した設計
今回の設計プロセスの特徴の一つは、患者さんの代表や病院スタッフの意見が設計に反映されている点です。
患者さんの声が大切にされ、特に小児がんを患う子どもたちが安心して過ごせる環境づくりが優先されています。
小児がん主任治療センターの運営ディレクター、ジェームズ・オブライエン氏は、専門家の知識と患者さんの意見を融合させることで、治療を受ける子どもたちにとって最高の環境を提供したいと述べています。
患者さんや家族が参加することで、施設の内装や導線、プライバシーの確保など、通常の設計にはない細部まで配慮されるのは嬉しいことですね。
病院内の各スペースには、家族がリラックスできる空間や、治療中のストレスを少しでも和らげる工夫が盛り込まれる予定です。
例えば、明るく温かみのある色彩を使ったり、自然光を取り入れたりする設計が計画されており、病院のイメージを「怖い場所」から「安心できる場所」へと変えることが目標だそうです。
医師以外の視点がもたらす新しい医療サービスの形
医療施設の設計において、建築家やデザイナー、エンジニアなど、医師以外の専門家が関与する意義は大きいでしょう。
彼らの視点を取り入れることで、医療行為を行う場としてだけでなく、子どもたちやその家族にとって快適でリラックスできる環境ができあがります。
医療の技術が進化する一方で、治療を受ける人々の心理的・感情的なケアも重要視されており、このような取り組みがさらに広がればいいなと思います。
完成形の「チルドレンズ デイ トリートメント センター」とは?
実は、エヴィリーナ ロンドン小児病院に先駆けて、建築家やデザイナーが作り上げた病院があります。
それが、「チルドレンズ デイ トリートメント センター(Children's Day Treatment Centre)」です。
この病院は、入院が必要ない手術を受ける子どもや若年層のために建てられた最新鋭の日帰り手術センターです。
この施設は、子どもやその家族の負担を減らすため、建築家やデザイナーが工夫を凝らして設計しました。
2023年に完成したこのセンターは小児病院の建物のすぐ隣に位置し、患者さんが院内を移動する手間を省いた利便性が魅力となっています。
手術室の改良で日帰りが可能に
チルドレンズ デイ トリートメント センターの設立により、年間2,300人の子どもたちが日帰り手術を受けられるようになりました。
新しいセンターのおかげで、通常の病院の手術室もより効率よく使え、入院が必要なケースにも専念できるようになっています。
センター内には、日帰り手術専用の2つの手術室が完備され、手術に必要な検査や、手術、回復、退院の準備がすべて1つの空間で行えるように設計されています。
このような設計により、家族の待ち時間が短縮され、1日の中で手術から退院までを完了できるようになったそうです。
子どもたちは日帰りで治療を受けられるので、家族も安心してサポートできますね。
デザインがもたらす快適さと安心感
施設内の快適な待合室も、家族を中心に考慮してデザインされています。
待合室には十分なスペースがあり、親子がリラックスして過ごせるよう配慮された設計です。
温かみのある内装や快適な家具の選定など細部まで工夫を凝らして、病院特有の緊張感を和らげ、子どもたちにとって親しみやすい空間になりました。
日本の病院デザインは良い?悪い?
日本の病院建築は、医療の質の高さと共に患者さんが心地よく待てる空間を重視してきましたが、海外に比べると違いがあるそうです。
東洋大学理工学部建築学科の岡本和彦教授は、日本は海外とは異なる文化的・社会的な背景が影響を与えていると言います。
待合室は過ごしやすい設計
日本国内では診療の完全予約制が一般的でなく、多くの病院で待合室が必要不可欠なものとなっています。
これは、例えばイタリアの病院と比べても明確な違いで、日本の待合室が患者さんの長い待ち時間に配慮して設計されている点が際立っているそうです。
今後、待合室が「待つための場所」から「過ごすための空間」へと変わり、さらに多様化が進むかもしれません。
欧米のような個室は増える?
日本の病室は昔から4人部屋が標準であり、欧米の個室が主流の病室とは対照的です。
この背景には、建築構造や文化的な要因が影響しているそうです。
欧米の病院は細長い部屋が多いため、少人数部屋が一般的となっている一方、日本の病室は4人部屋の形を保ちながらもプライバシーに配慮した設計がなされています。
例えば「個室的多床室」と呼ばれる新しい設計では、4人部屋でありながら各ベッドが自然光を受けられるよう窓が設けられ、患者さんがリラックスできる空間作りがされています。
このような日本特有の病室デザインは、患者さんの精神的な快適さを追求した結果生まれたものだと言います。
しかし、岡本教授は日本でも今後は個室化が進むと予測しています。
特に、団塊世代以降の患者さんがコミュニケーションよりも自分のプライベート空間を重視する傾向が強まっているためです。
さらに、コロナ禍での感染防止対策としての個室の評価が高まったことも、病室の個室化を促進する要因となるでしょう。
エヴィリーナ・ロンドン小児病院のように、患者さん一人一人に合わせたケアとプライバシーの確保を実現することが、今後の病院設計の課題となると考えられます。
医療機器と場所の制約
日本の病院建築においてもう一つの課題は、医療機器の導入と空間の持続可能性です。
日本の病院にはCTやMRIなどの医療機器が数多く配置されていますが、これらの機器が増えるたびに増築が必要となり、空間に制約が生まれています。
コロナ禍ではCTの多さが迅速な対応に役立ちましたが、サステナビリティの観点からは効率的な設計が求められています。
岡本教授は、丈夫な建物躯体を作り、内部のリノベーションを繰り返しながら長期的に利用する考え方が必要であると述べています。
病院が地域交流の場となっている国もある
岡本教授はさらに、今後の病院の役割が医療提供だけにとどまらず、地域社会の交流の場としての機能も果たすべきであるとしています。
これは、台湾や韓国の病院が地下鉄駅と直結し、多目的スペースとしての利用が進んでいる事例に学ぶところが大きいでしょう。
日本でも、地域住民が気軽に立ち寄れるようなオープンな空間となるのでしょうか。
ただ、気分が悪い方もいる中で雑談だけをしに来る人たちがいるとしたら、それは本当に患者さんに向けての精神的なサポートとなるのかは疑問です。
まとめ
医療は、医師や看護師だけでなく、建築家やデザイナーの力で成り立っているのですね。
今後、エヴィリーナ・ロンドン小児病院はどのように変わるのでしょうか。
患者さんだけでなく、医療従事者にとっても過ごしやすい病院になればいいなと思います。
また、日本の病院建築の進化にも着目したいところです。
海外の例を取り入れるのか、はたまた日本独自の路線を切り開くのか、医療の発達と共にデザインの変化にも焦点が当てられるかもしれませんね。