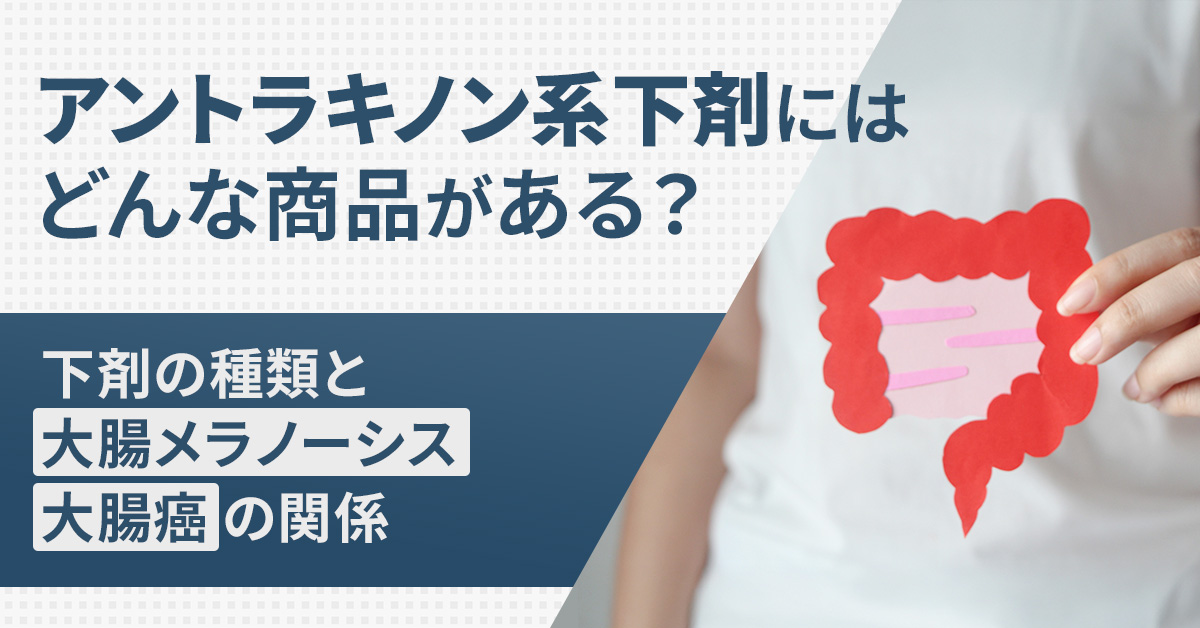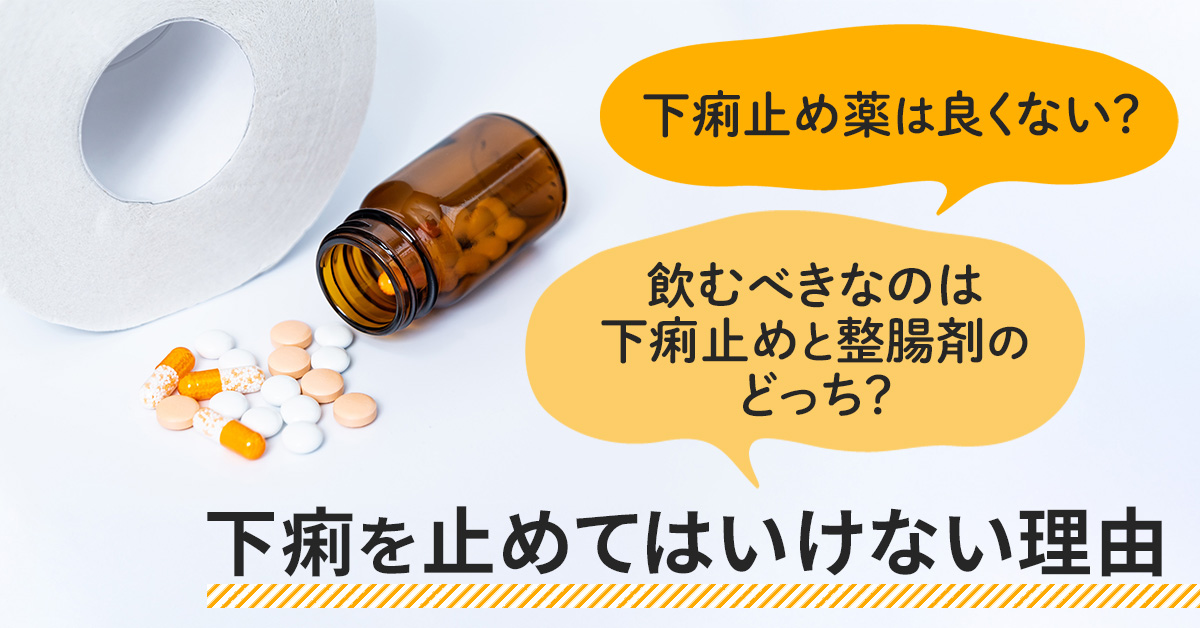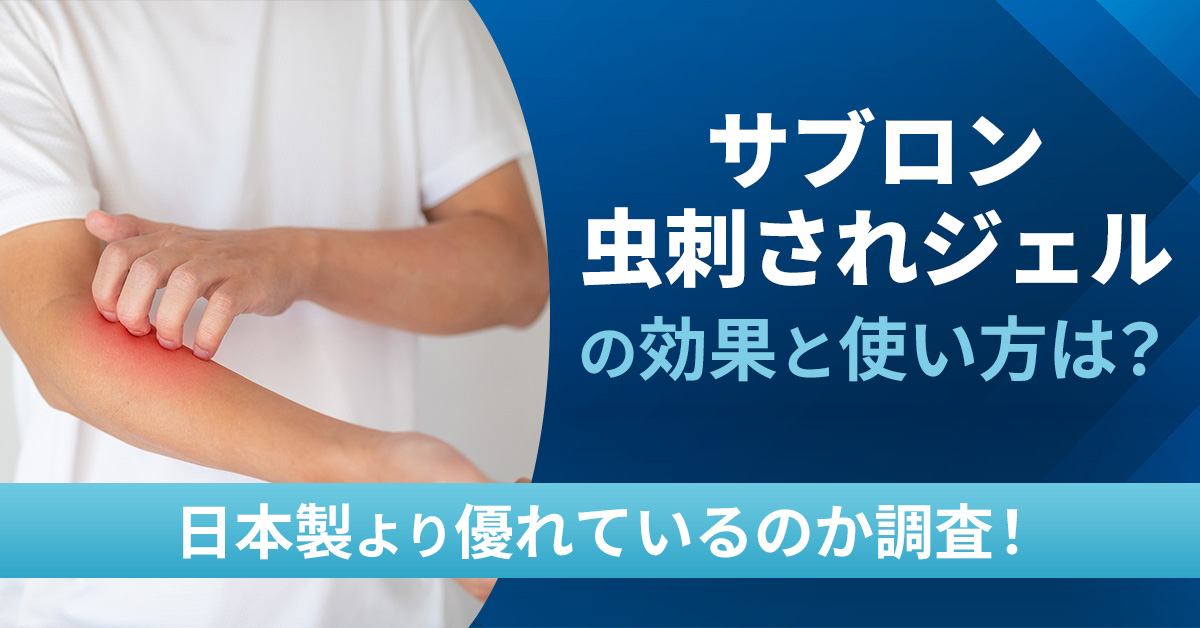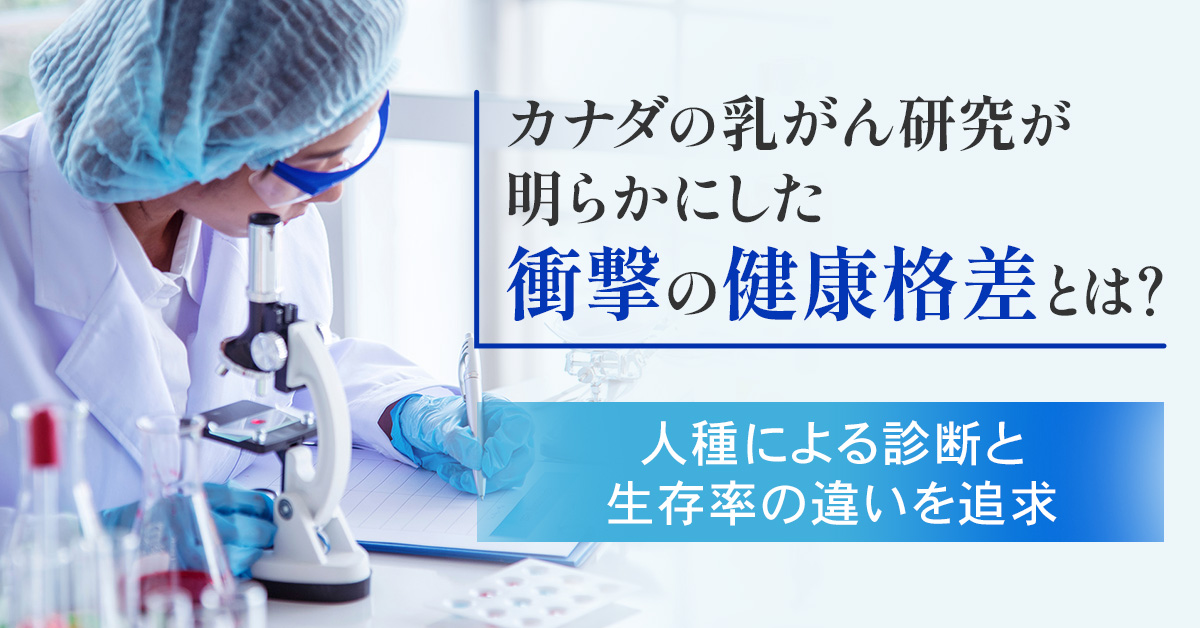皆さんは、食べ物に何かアレルギーはありますか?
食べられないものがあると不便ですし、食事を楽しめなくなることもあります。
そんな私たちの周りで増え続ける食物アレルギーは、特に子どもたちの間での発症増加が社会的な課題となっています。
そんな中、エヴェリーナ・ロンドン小児病院とキングス・カレッジ・ロンドンの研究チームが、臨床試験を開始したというニュースが届きました。
アレルギーで悩まなくても良い未来が、そこまで来ているかもしれません。
湿疹とアレルギーを止める臨床試験
「湿疹が食物アレルギー発症の最も強いリスク要因だということは、実は何年も前からわかっていたんです」と語るのは、今回の臨床試験の共同リーダーを務めるヘレン・ブラフ教授です。
この知見に基づき立ち上げられたのが、"SEAL(湿疹とアレルギーを止める)臨床試験"。
生後12週までの乳児を対象に、早期の湿疹治療介入によって食物アレルギーの発症を予防できるかを検証します。
これまでの研究で明らかになっているのは、生後3ヵ月未満で湿疹を発症し、ステロイド治療が必要となった赤ちゃんは、ピーナッツやゴマ、卵などへのアレルギー発症リスクが50%も高まるという事実です。
この数字は決して小さくありません。
2つにグループ分けして検証
SEAL試験では、参加者は2つの治療グループのいずれかに振り分けられます。
第一のグループでは、従来通り症状が出てから対処する方法を取ります。
赤ちゃんのヘルスケアチームが湿疹の症状に応じて治療を行い、再発時に対応する形です。
一方、第二のグループでは予防的なアプローチを採用します。
毎日の保湿剤の使用に加え、湿疹の再発を防ぐために予防的にステロイド薬を使用します。
どちらのグループも、研究チームとオンラインで定期的なチェックを行い、きめ細かなサポートを受けられる体制が整えられているとのことです。
2年間にわたる追跡調査
この試験期間は2年間に渡ります。
参加者は専門のアレルギー研究センターで3回の詳しい検査を受けることになります。
さらに、2歳になるまでの期間、年1回の食物アレルギー検査が実施され、最終的には実際に食物を摂取する負荷試験も予定されているそうです。
アメリカの国立衛生研究所が資金を提供するこの研究で、英国での唯一の試験実施機関となるのがエヴェリーナ・ロンドン小児病院です。
期待を込めて参加を決意した親子
現在、この臨床試験への参加を希望して検査を受けているのが、生後8週間のユスラちゃんとお母さんのファルハナ・ラーマンさん。
ファルハナさんは一般開業医としての顔も持っています。
「私自身が湿疹とアレルギーに悩まされてきた経験があるので、娘にも同じリスクがあるかもしれないという不安がありました」とファルハナさん。
「でも、この研究に参加することで、娘だけでなく、将来の子どもたちのためにも何か貢献できるかもしれない。それを思うとわくわくします」
確かに、自分が食物アレルギーを持っている場合、子どもにその影響がどれほどあるのか、また、生まれた時にどんなアレルギーを持っているのかは気になるところでしょう。
医師としての視点も持つファルハナさんは、食物アレルギーの管理の難しさを誰よりも理解しています。
「最終的には一人の母親として、子どもにとって最善の選択をしたいだけなんです。世界トップクラスの専門家たちが私たちをサポートしてくれる。そう思うと本当に心強いですね」
新たな希望をもたらす研究
この臨床試験の中核となるのが、皮膚バリア機能の回復と炎症のコントロール。
これにより、食物アレルゲンが皮膚から侵入するのを防ぎ、アレルギー反応の連鎖を断ち切ることができるのではないかと期待されています。
ブラフ教授は「SEAL研究を通じて、湿疹のある子どもたちの皮膚に早く対処することで、食物アレルギーを予防できる可能性を探ります。
この臨床試験が次世代の子どもたちの人生を変えるきっかけになることを心から願っています」と、研究への期待を語っています。
食物アレルギーは、患者さん本人の生活の質を低下させるだけでなく、家族全体に大きな影響を及ぼします。
毎日の食事の準備から外食時の対応まで、常に細心の注意が必要となるからです。
この研究が成功すれば、多くの子どもたちがアレルギーの心配なく、自由に食事を楽しめる未来が開けるかもしれません。
医療関係者や研究者たちの真摯な取り組みが、確実に新しい希望を生み出そうとしています。
今後、この臨床試験がどのような結果をもたらすのでしょうか。
食物アレルギーに悩む家族は世界中にいるので、世界中から注目されていると言っても良いでしょう。
日本の現状と最新の予防研究
英国で始まった臨床試験のニュースは、日本の医療関係者からも大きな注目を集めているといいます。
ここからは、日本の食物アレルギーの実態と、最新の研究動向について考察してみましょう。
日本の食物アレルギー事情
日本国内では実に乳幼児の5~10%が食物アレルギーを抱えているとされています。
注目すべきは、その原因となる食物の分布です。
日本人の食生活に欠かせない鶏卵、牛乳、小麦が全体の70%を占め、特に鶏卵は40%という高い割合を示しています。
これは日本の食文化と密接に関係していると考えられます。
和食には出汁巻き玉子や茶碗蒸しなど、卵を使用する料理が数多くあります。
また、パンや麺類など、小麦を使用した食品も私たちの食生活に深く根付いています。
最近は健康のためにグルテンフリー食品が好まれることもありますが、一般的なスーパーでは小麦を避けた商品探しが難しいです。
また、グルテンフリー食品は値段が高い傾向にあるので、家計を圧迫することもあります。
年齢による変化と新たな課題
食物アレルギーは年齢とともに変化していきます。
学童期に入ると、甲殻類や果物、木の実類へのアレルギーの割合が増加する傾向にあるそうです。
これは、子どもの成長とともに免疫システムが変化していくからだと言われています。
上記でご紹介した英国の SEAL 試験が注目する「皮膚バリア機能」という観点は、日本の研究者たちの間でも重視されています。
特に、アトピー性皮膚炎と食物アレルギーの関連性については、日本でも活発な研究が進められているといいます。
診断と治療の最前線
日本の医療現場では、食物アレルギーの診断に際して慎重なアプローチが取られています。
症状の観察だけでなく、血液検査による特異的IgE抗体の測定、皮膚プリックテスト、そして最も信頼性の高い食物経口負荷試験など、複数の検査を組み合わせて総合的な判断が行われます。
特筆すべきは、日本で進められている「食物経口免疫療法」の取り組みです。
これは、極めて少量の原因食物から始めて、徐々に摂取量を増やしていく治療法です。
ただし、この治療法にはアナフィラキシーのリスクも伴うため、必ず専門医の管理下で実施します。
社会的サポート体制の充実
日本の特徴的な取り組みとして、教育現場での対応の充実が挙げられます。
文部科学省や厚生労働省が発出したガイドラインに基づき、「生活管理指導表」を活用した学校と医療機関の連携が義務付けられています。
これは、英国の SEAL 試験が目指す早期介入・予防の考え方と通じるものがあるように思います。
社会全体で食物アレルギーの子どもたちをサポートする体制づくりは、今や世界的な潮流となっているのかもしれませんね。
予防医療への期待
英国で始まった SEAL 試験の結果は、日本の食物アレルギー対策にも大きな影響を与える可能性があります。
特に、生後12週という早期からの介入が、アレルギー発症予防にどのくらい効果的なのか、日本の医療関係者も強い関心を寄せているとのことです。
日本でも、アレルギー予防に関する研究は着実に進んでいます。
妊娠中の母親の食生活がアレルギー発症に与える影響や、腸内細菌叢とアレルギーの関係など、新たな視点からの研究も活発化しているそうです。
家族の負担を考える
食物アレルギーは、医学的な問題であると同時に、大きな社会的課題でもあります。
アレルギーを持つ子どもの家族は、毎日の食事準備から学校行事への参加まで、常に細心の注意を払う必要があります。
特に日本国内では、行事での食事や給食など、集団での食事の機会が多いことが特徴です。
それに対して欧米では、サンドイッチと果物をランチパックとして持っていくなど、親がお弁当を作る機会が多いところもあります。
そのため、日本国内ではより周囲の理解と適切なサポート体制の構築が不可欠となっていると言えるでしょう。
まとめ
英国のSEAL試験の開始は、食物アレルギーの予防に向けた大きな一歩と言えるでしょう。
日本でも、この研究成果を踏まえながら、独自の文化や食生活に即した予防・治療法の開発が進められていくのではないでしょうか。
医療がさらに進歩し、社会的支援が充実すれば、食物アレルギーに悩む子どもたちとその家族の負担が軽減するでしょう。
そして何より、アレルギーを持つ子どもたちが、安心して食事を楽しめる日が来ることを心から期待したいと思います。