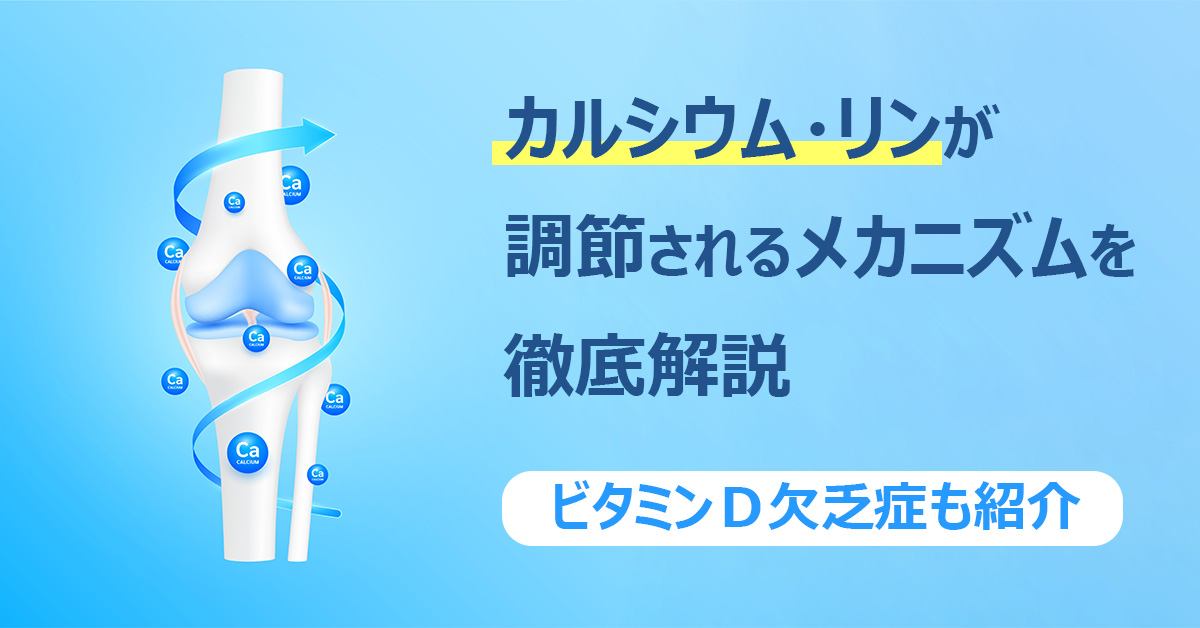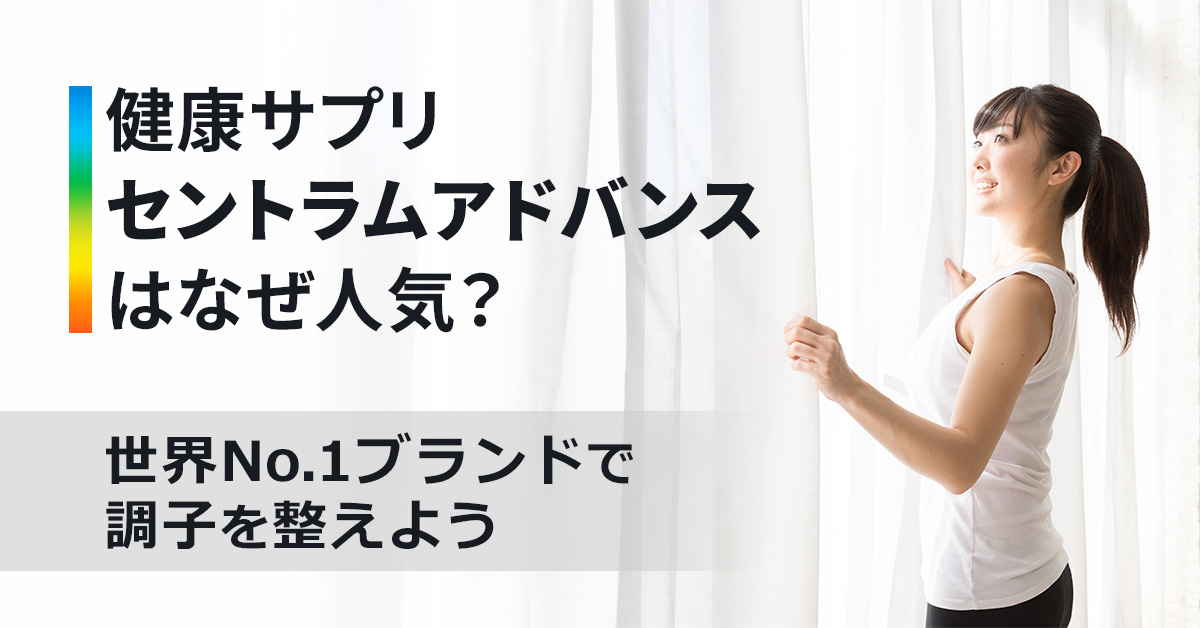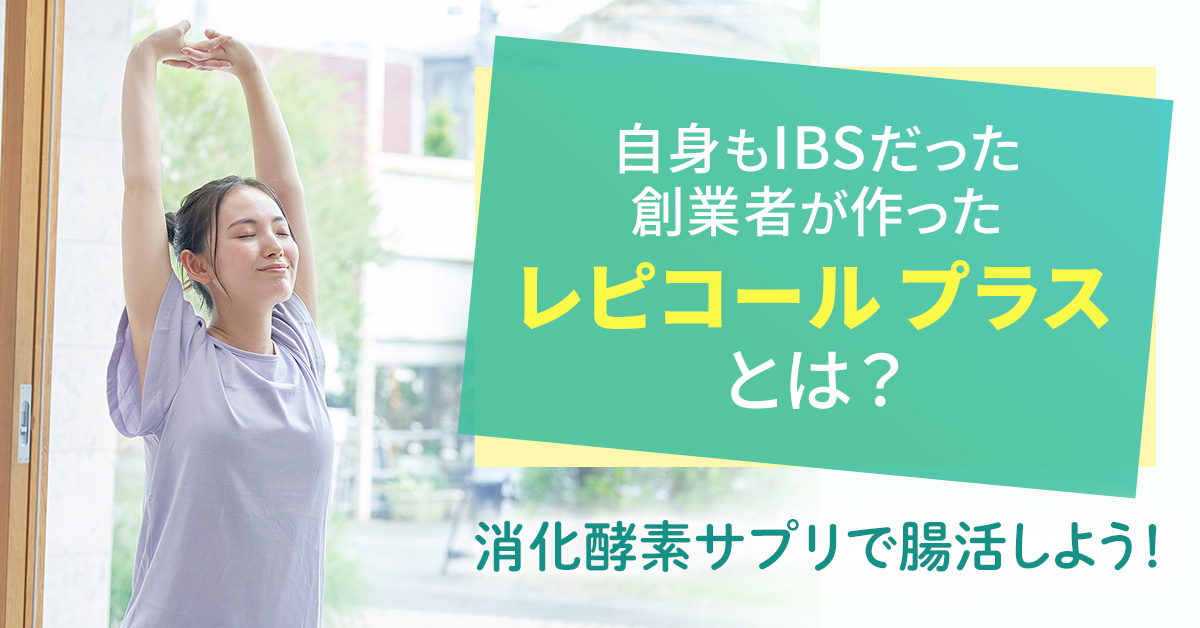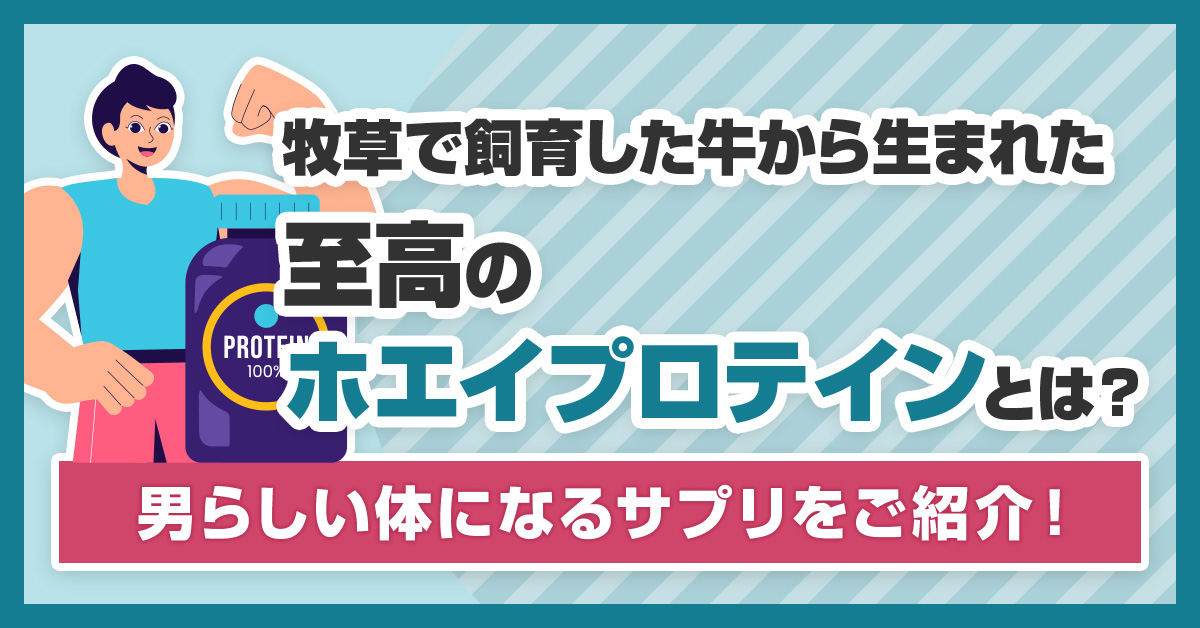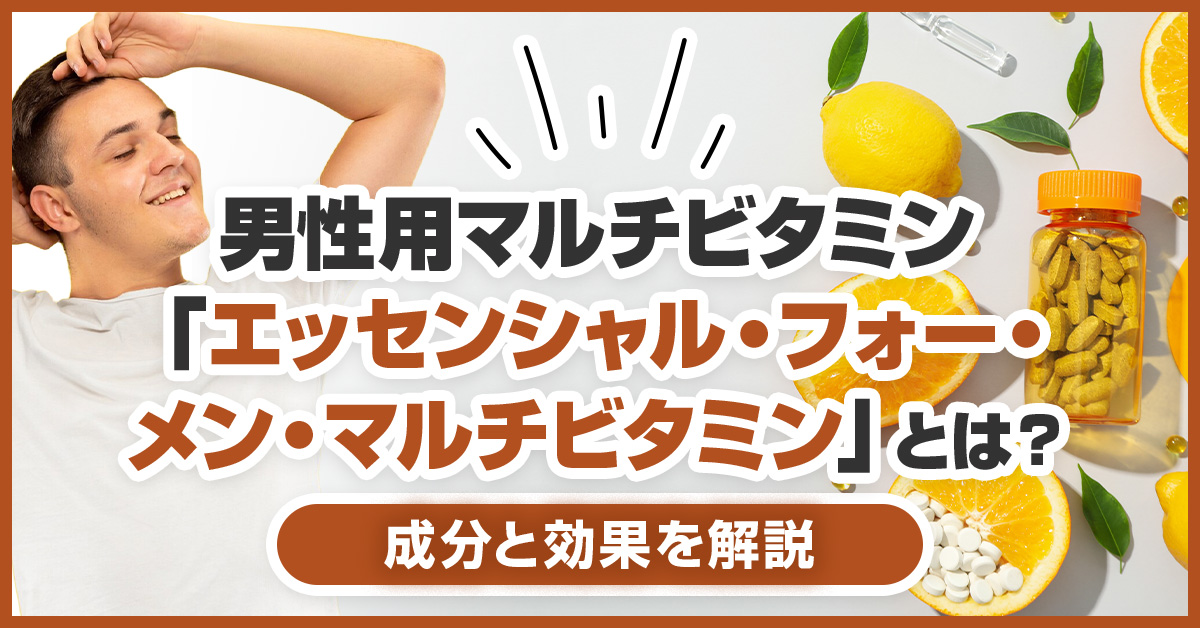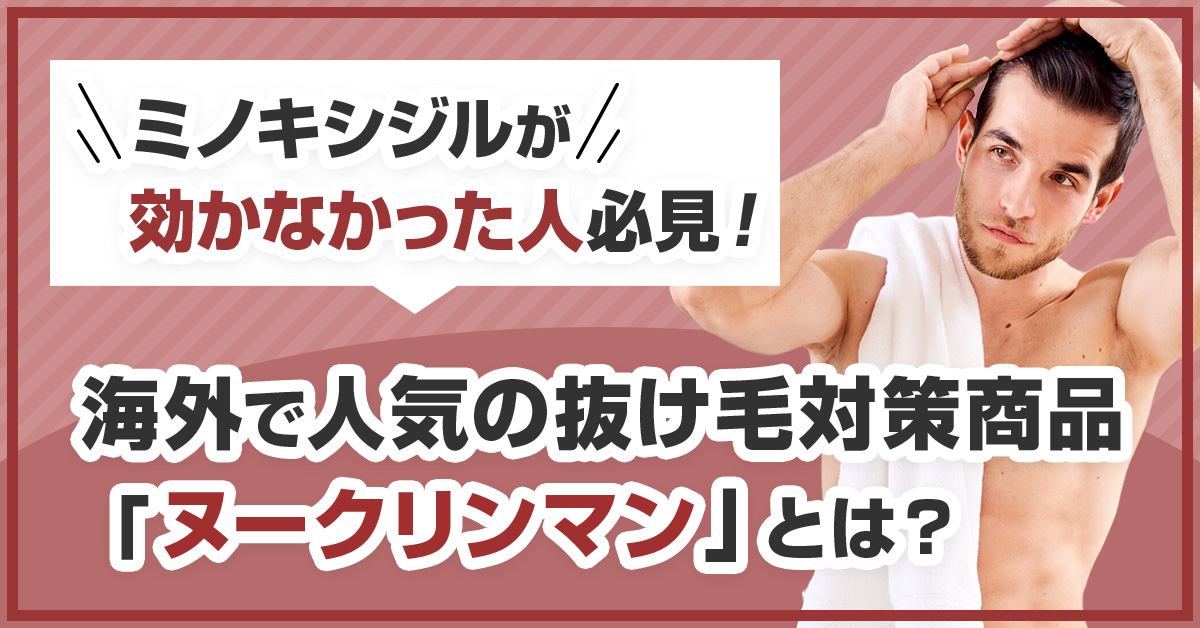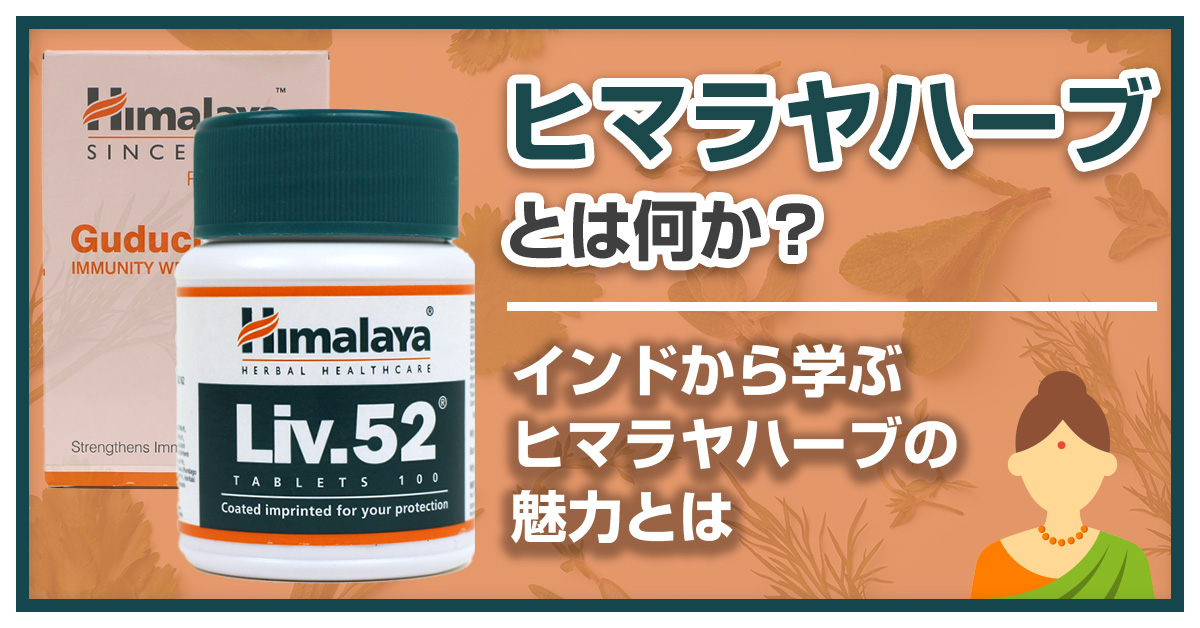「ビタミンDの主な働きは?」
「ビタミンDが不足するとどんな病気になるの?」
このような疑問を持っている人は少なくないのではないでしょうか。
本記事では、ビタミンDとPTHによるカルシウム・リンの調節メカニズムを徹底解説。
ビタミンD欠乏症や、欠乏症を予防するための方法についても紹介します。
本記事を読めば、ビタミンDの働きや欠乏症について理解を深められます。
興味がある人はぜひ最後までご覧ください。
ビタミンDと関係が深い3つの物質
ビタミンDは食品から摂取される他、日光を浴びることで体内でも合成されるビタミンの一種です。
合成されたビタミンDは、肝臓や腎臓で活性化され「活性型ビタミンD3」となります。
ビタミンDの主要な働きは、カルシウムとリンの調節です。
これらのミネラルは、私たちが生きていくうえで非常に重要な働きを担っています。
また、ビタミンDやカルシウム・リンについて理解するうえで、欠かせない物質が「PTH」というホルモンです。
まずは、カルシウム・リンとPTHについて見ていきましょう。
カルシウム・リン
カルシウムとリンは生体内で、以下のような働きを有しています。
| ミネラル | 働き |
|---|---|
| カルシウム | 筋肉の収縮、血液の凝固、細胞内における情報伝達 |
| リン | エネルギー源となるATPの構成要素となる、蛋白質をリン酸化して作用を調節する |
カルシウムとリンはいずれも、多くが骨に蓄積されています。
体内の総量における骨の蓄積割合は、カルシウムで約99%、リンで約85%です。
PTH
PTHとは、副甲状腺という臓器から分泌されるホルモンです。
働きの詳細は後述しますが、基本的には血液中のカルシウム濃度の上昇を目的として作用します。
PTHは、ビタミンDとも深い関わりを持っています。
PTHがビタミンDの活性化を促進する一方、ビタミンDは副甲状腺に働きかけて、PTHの分泌を抑制するのです。
カルシウム・リンの調節メカニズム
カルシウム・リンの調節は、血液中のカルシウム濃度が低下し、副甲状腺が感知してPTHを分泌したところから始まります。
分泌されたPTHは骨と腎臓に向かい、それぞれの臓器に働きかけて血液中のカルシウム濃度を上昇させます。
各臓器でのメカニズムについて見ていきましょう。
骨におけるカルシウム・リンの調節
私たちの骨は、「骨芽細胞」「骨細胞」「破骨細胞」という3つの細胞成分と、それ以外を占めている骨基質から形成されています。
このうち、今回カギを握っているのが破骨細胞です。
破骨細胞はその名の通り、古い骨基質を分解して吸収します(骨吸収)。
そして、PTHには破骨細胞を活性化し、骨吸収を促進する働きがあります。
骨基質にはカルシウム・リンが多く含まれているため、PTHの作用により、血液中のカルシウム濃度・リン濃度が上昇するのです。
また、ビタミンDは骨吸収と、骨芽細胞による骨基質の産生(骨形成)をともに促進します。
この作用により、古い骨基質がどんどん更新されていくのです(リモデリング)。
腎臓におけるカルシウム・リンの調節
腎臓におけるカルシウム・リンの調節は、骨におけるそれよりも複雑です。
前提として、「PTHとビタミンDの働きにより、血液中のカルシウム濃度が上昇する」ことを押さえておきましょう。
私たちの腎臓の主な働きは、体内で不要になった物質の排泄です。
具体的には、生体に必要だが既に十分存在しているもの、老廃物などが挙げられます。
これらの不要となった物質は腎臓の「尿細管」という管を通り、尿として体外へ排泄されるのです。
ただし、尿細管を通る物質が全て排泄されるわけではなく、一部の物質は体内へ戻っていきます(再吸収)。
ここで、腎臓におけるPTHの働きは、カルシウムの再吸収促進とリンの再吸収抑制です。
その結果、血液中のカルシウム濃度は上昇し、リン濃度は低下します。
また、PTHは腎臓におけるビタミンDの活性化を促進します。
活性化したビタミンDは、カルシウムの再吸収を促進するとともに、小腸でのカルシウム・リンの吸収を促進します。
その結果、血液中のカルシウム濃度とリン濃度がいずれも上昇します。
カルシウム濃度を下げるメカニズム
ここまで見てきたように、ビタミンDとPTHはいずれも、血液中のカルシウム濃度を上昇させる作用を持っています。
一方、カルシウム濃度を下げるメカニズムも生体には用意されています。
代表的なシステムが、カルシウム自身による「ネガティブフィードバック」です。
血液中のカルシウム濃度が上昇すると、副甲状腺に働きかけてPTHの分泌が抑制されます。
血液中のカルシウム濃度を低下させるもう一つのメカニズムが、甲状腺という臓器から分泌される「カルシトニン」というホルモンです。
カルシトニンは破骨細胞の働きを阻害し、骨吸収を抑制する作用を持っています。
この作用から、カルシトニンはいくつかの疾患の治療薬としても用いられています。
ビタミンD欠乏症
ビタミンDが欠乏する原因として、代表的なものは以下の4つです。
- 日光不足(合成量の低下)
- 食事性(摂取量の低下)
- 吸収障害
- 肝臓/腎臓での活性化障害
日本においては、腎不全に伴う活性化障害が欠乏する原因として多いです。
生体内でビタミンDが欠乏すると、ここまで見てきたカルシウム・リンの正常な調節がうまくできず、血液中のカルシウム濃度が低下します。
その結果、以下のような欠乏症が生じる可能性があります。
- くる病/骨軟化症
- 骨粗鬆症
- 低カルシウム血症
それぞれの欠乏症について見ていきましょう。
①くる病/骨軟化症
くる病/骨軟化症とは、骨形成において異常が生じる疾患です。
くる病/骨軟化症について理解するためには、骨形成のメカニズムを押さえておかなければなりません。
骨芽細胞による骨基質の産生では、まず「類骨」という初期段階の骨が形成されます。
その後、骨芽細胞から放出された「基質小胞」という袋状の物質の中で、「ハイドロキシアパタイト」という結晶が生成されます。
そして、ハイドロキシアパタイトの結晶が生成されるためには、カルシウムとリンが欠かせません。
基質小胞の内部が結晶で満たされると、小胞は破裂して結晶が飛び出します。
その後、飛び出したハイドロキシアパタイトの結晶が類骨に沈着します。
その結果、類骨が石灰化されて骨基質が完成するのです。
ビタミンDの欠乏によりカルシウム濃度が低下すると、ハイドロキシアパタイトの結晶が正常に生成できません。
そのため、骨の量自体は問題ないものの類骨の割合が増加します。
その結果、小児期で様々な身体所見が生じるのがくる病です。
具体的には以下が挙げられます。
- 低身長
- 関節の腫大
- 鳩胸/漏斗胸(胸骨の異常)
- 下肢の変形(O脚やX脚)
- 筋緊張低下(筋肉の収縮が弱い)
- 痙攣
一方、成人期に類骨の割合が増加して起こる疾患が骨軟化症です。
具体的な症状として以下が挙げられます。
- 骨の痛み
- 筋力低下
- 骨折
ビタミンDの欠乏が原因でくる病/骨軟化症が起こっている場合、ビタミンDの投与が行われます。
リンの欠乏によりくる病/骨軟化症が起こっている場合でも、ビタミンDはリンの調節に関わっているため、リンとビタミンDの投与が行われます。
②骨粗鬆症
骨粗鬆症とは、骨吸収が骨形成を上回るペースで進むことで、骨が脆くなり骨折しやすくなる疾患です。
ビタミンDの欠乏によりカルシウム濃度が低下すると、カルシウム濃度を上げるために骨吸収が進行するため、骨粗鬆症が起こりやすくなります。
骨粗鬆症の好発(生じやすい人)は、閉経後の女性と高齢者です。
女性ホルモンである「エストロゲン」には、破骨細胞の働きを阻害して骨吸収を抑制する働きがあります。
しかし、閉経するとエストロゲンが急激に減少するため、破骨細胞の働きが活発になり骨吸収が急速に進行するのです。
また、高齢者では骨形成が低下するため、男女とも骨粗鬆症が起こりやすくなります。
骨粗鬆症により特に骨折しやすい部位は、大腿骨近位部(腰に近い辺り)や椎体(脊椎を形成する骨)です。
その他、橈骨遠位端(前腕を形成する骨の手首に近い辺り)や上腕骨近位部(肩に近い辺り)も骨折しやすくなります。
骨粗鬆症に対する予防法や治療法は、食事療法・運動療法・薬物療法の三本柱です。
食事療法では、カルシウムやビタミンDなどを積極的に摂取します。
骨量の維持には力学的な負荷も欠かせないため、運動による刺激も重要です。
薬物療法では、小腸からのカルシウム吸収や骨のリモデリングの促進を期待して、ビタミンDが用いられます。
破骨細胞を阻害して骨吸収を抑制するカルシトニンも、主に痛みを緩和する目的で使用されています。
その他、骨粗鬆症に対してよく使われている薬剤が、「ビスホスホネート」と「選択的エストロゲン受容体調整薬」です。
ビスホスホネートには、骨に取り込まれて骨吸収を抑制する強い作用があり、第一選択薬(疾患に対して最初に投与する薬)となっています。
また、選択的エストロゲン受容体調整薬は、骨に対してのみエストロゲン作用(骨吸収抑制)を発揮します。
一方、乳房や子宮には作用しないため、乳癌や子宮体癌などの副作用発生リスクを回避できるのです。
③低カルシウム血症
血液中のカルシウム濃度が低下することにより、全身に様々な症状を引き起こすのが低カルシウム血症です。
起こり得る具体的な症状として以下が挙げられます。
- 手指/口唇の痺れ
- 筋攣縮(筋肉の痙攣)
- 呼吸器症状(喘息・呼吸困難など)
- 消化器症状(腹痛・悪心・嘔吐など)
- 中枢神経症状(知能低下・イライラ・鬱など)
- 心電図異常
- 白内障
- 皮膚乾燥
以上の中でも、特に手指/口唇の痺れや筋攣縮がみられやすいです。
治療としては、カルシウムやビタミンDの投与が行われます。
ビタミンDの欠乏を予防するには?
ここまで見てきたように、ビタミンDの欠乏は様々な疾患の原因となります。
予防するためには、ビタミンDを多く含む食品の摂取が有効です。
具体的には、以下のような食品が挙げられます。
- 鮭
- サンマ
- イワシ
- キクラゲ
- 干し椎茸
乳幼児のビタミンD欠乏を予防するためには、適度な日光浴が大切です。
ビタミンDは母乳に含まれていないため、合成量を増やす必要があります。
ビタミンD過剰症
ビタミンDが関連する疾患は欠乏症が中心ですが、反対に過剰症が生じるケースもあります。
原因として、ビタミンD欠乏症に対するビタミンDの過剰な投与が挙げられます。
ビタミンD過剰症として、重要な疾患が高カルシウム血症です。
具体的な症状として、意識低下や筋力低下、悪心・嘔吐などがみられます。
カルシウム濃度がさらに高くなると、急性腎障害や昏睡状態に陥る恐れもあります。
高カルシウム血症に対する治療としては、まず点滴や利尿薬の投与が行われます。
それでも改善しない重篤なケースでは、骨吸収を抑制するためにカルシトニンやビスホスホネートが使用されます。
まとめ:ビタミンDを積極的に摂取して欠乏症を予防しよう
ビタミンDは、カルシウムやリンの調節に関わる非常に重要な栄養素です。
不足するとカルシウム濃度が低下し、骨粗鬆症をはじめとする様々な疾患を引き起こします。
ビタミンDを不足させないためには、食品からの積極的な摂取や日光浴が大切です。
普段の生活から心掛け、ビタミンD欠乏症を予防しましょう。