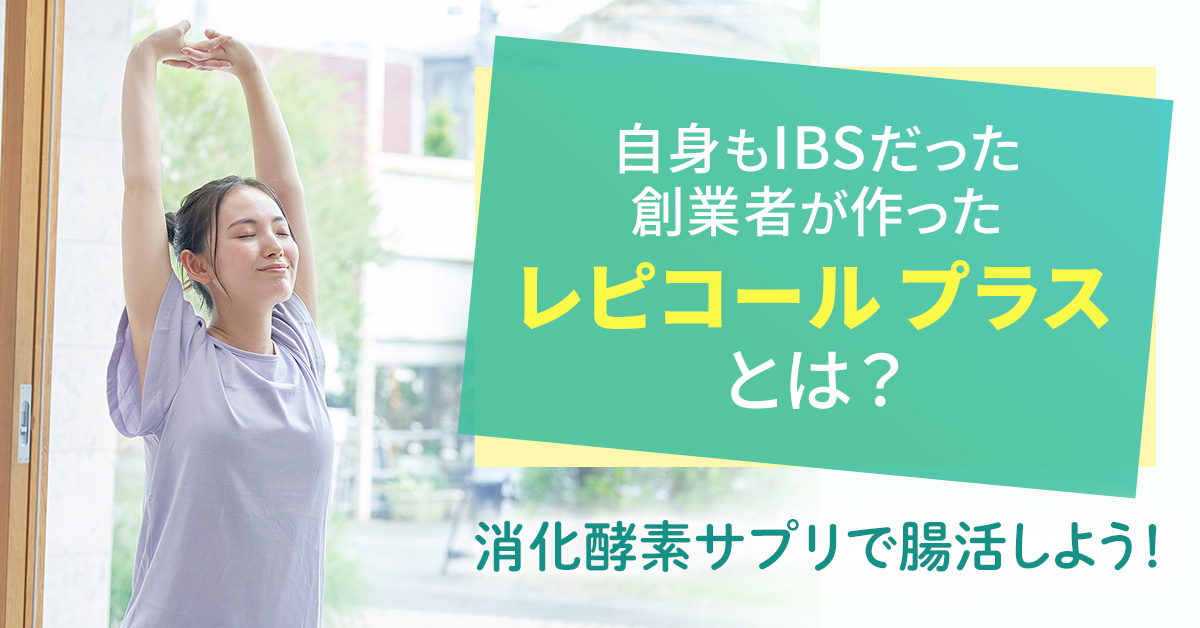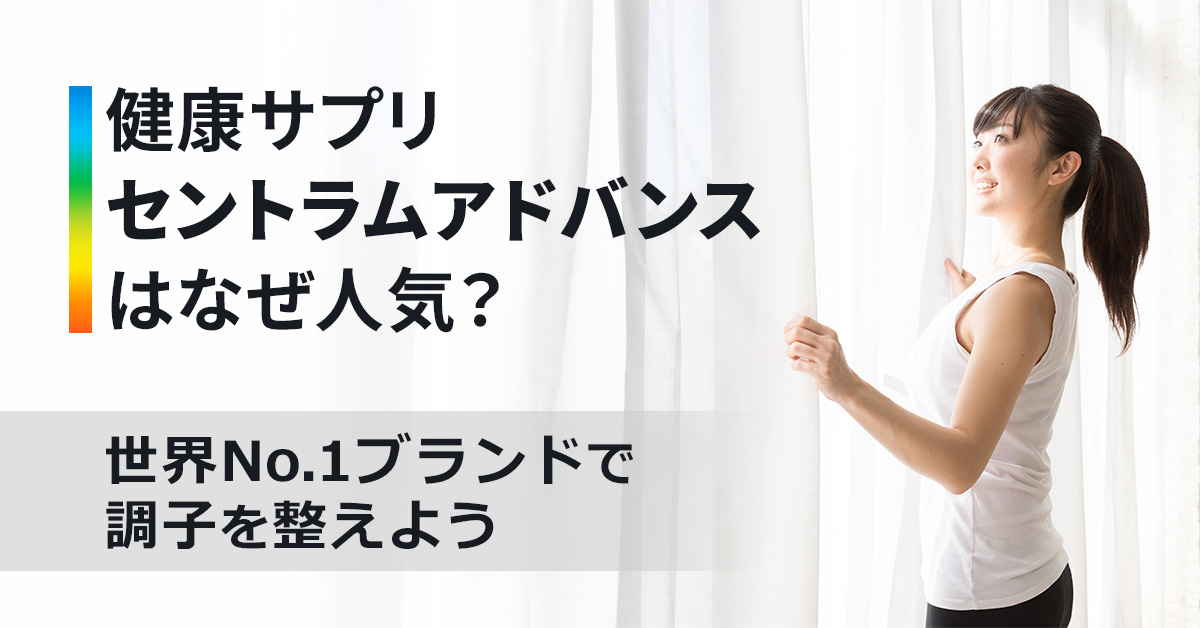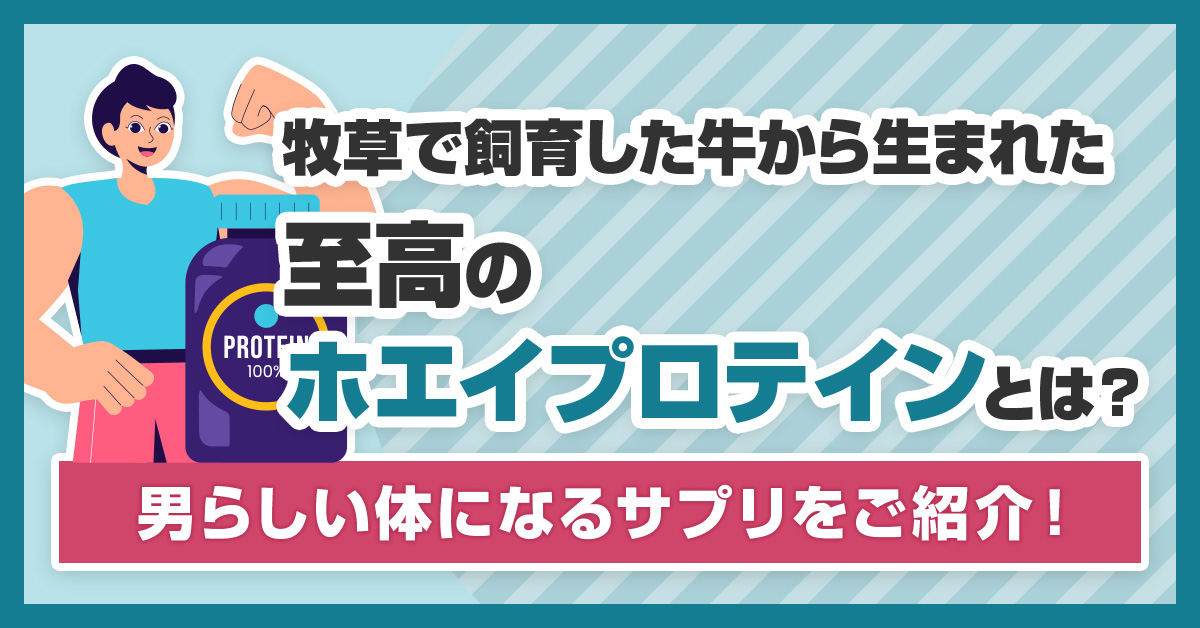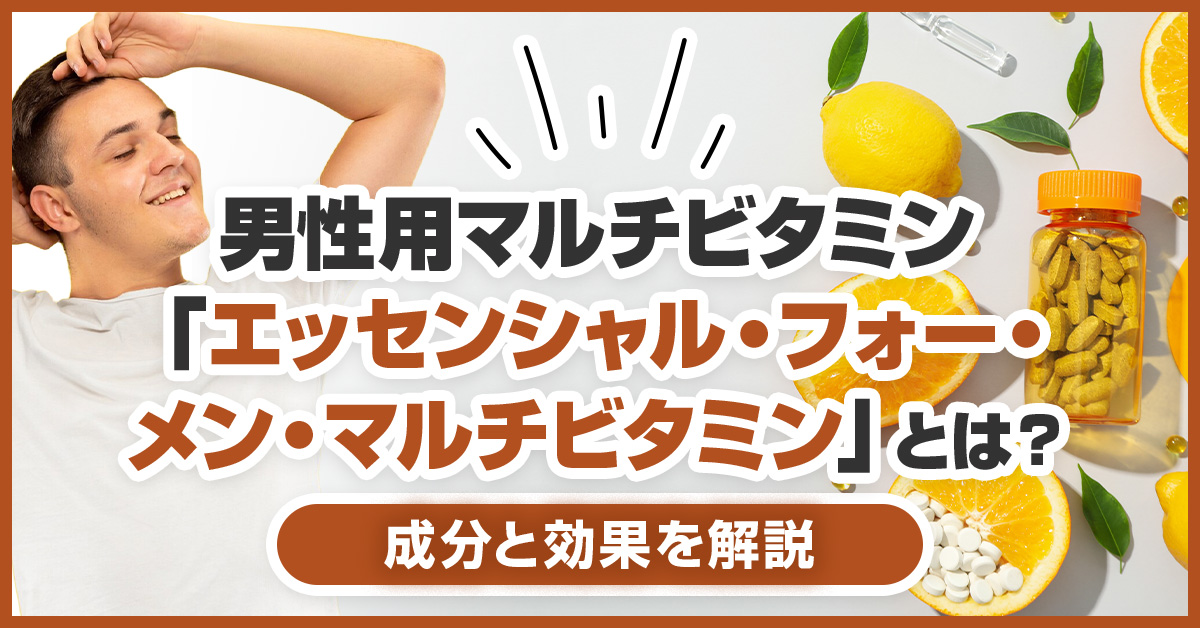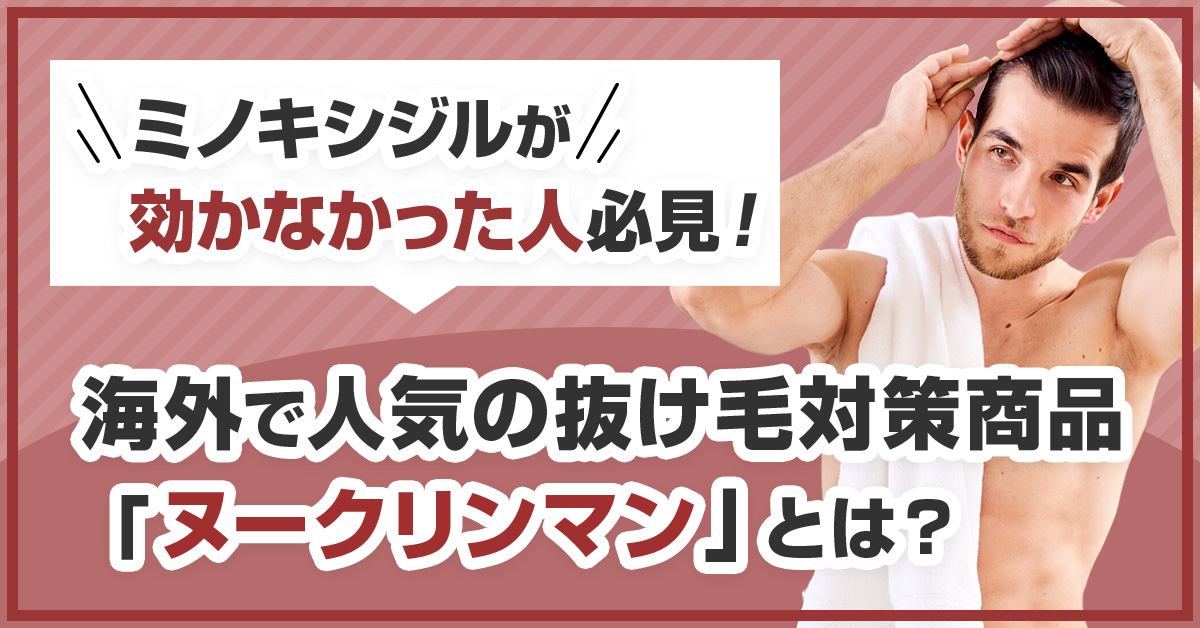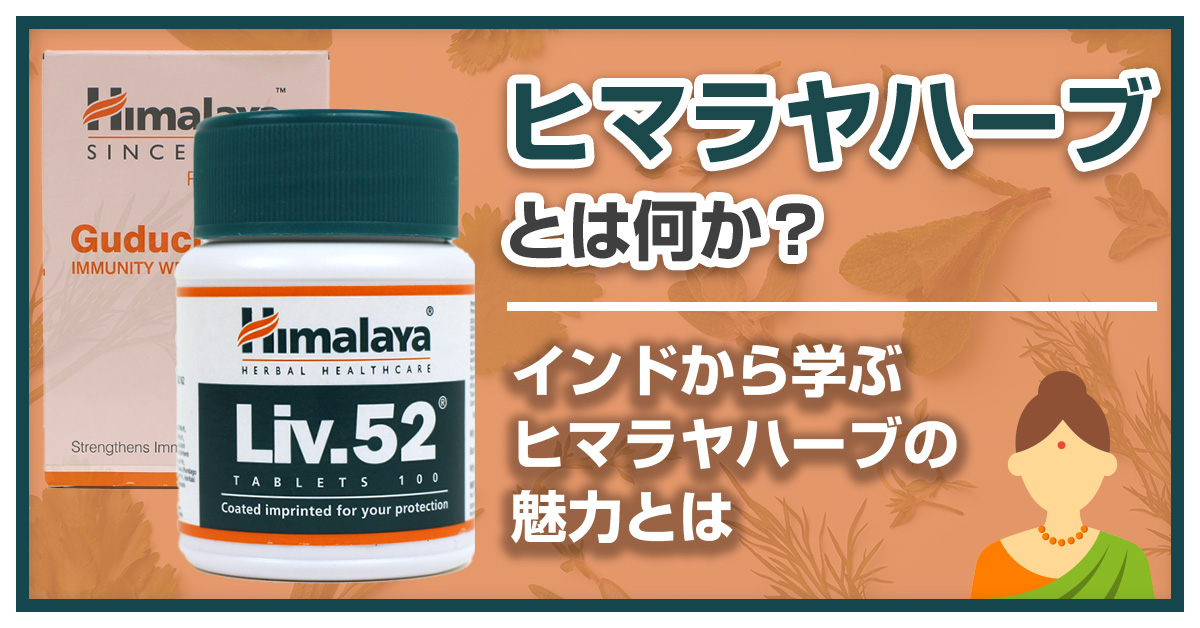「ビタミンB1ってどんな栄養素?」
「ビタミンB1が不足すると病気になる?」
このような疑問を持っている人は少なくないのではないでしょうか。
本記事では、ビタミンB1の働きや欠乏するとどうなるのかについて徹底解説。
ビタミンB1が欠乏する主な原因や実際に起こり得る欠乏症についても詳しく紹介します。
本記事を読めば、ビタミンB1の働きや欠乏症について理解を深められます。
興味がある人はぜひ最後までご覧ください。
そもそもビタミンとは?
「ビタミン」という栄養素の名前を聞いたことはあるけれど、具体的にどのような栄養素なのか、明確にはわからない人は多いかもしれません。
ビタミンの一般的な定義は以下の通りです。
微量で生理作用を発揮するが、体内で必要量を合成できない有機化合物。
すなわち、私たちが生きていくために必要であるけれど、体内で作れないため食物から摂取しなければならない物質、というわけです。
ビタミンは、油脂に溶けやすい脂溶性ビタミンと、水に溶けやすい水溶性ビタミンに大別されます。
具体的なビタミンの分類は以下の通りです。
| 分類 | ビタミン |
|---|---|
| 脂溶性ビタミン | ビタミンA、ビタミンD、ビタミンE、ビタミンK |
| 水溶性ビタミン | ビタミンB群(ビタミンB1、ビタミンB2、ナイアシン、ビタミンB6、ビタミンB12、パントテン酸、葉酸、ビオチン)、ビタミンC |
これらのビタミンは、それぞれ異なる働きを持っています。
本記事では、ビタミンB1について見ていきましょう。
ビタミンB1の働き
ビタミンB1の働きは主に以下の2つです。
- 糖の代謝に関わる
- 体内で情報を伝える神経細胞の膜を構成する
ビタミンB1が欠乏状態に陥るとこれらの働きが障害され、欠乏症と呼ばれるいくつかの症状が生じます。
ビタミンB1の欠乏症を理解するうえで、特に重要となるのが糖の代謝に関わっている点です。
まずは、ビタミンB1が糖代謝においてどんな作用を持っているのか見ていきましょう。
ビタミンB1と糖代謝
私たちの身体を構成している全ての細胞は、活動するためにエネルギーを必要とします。
体内でエネルギーを保存し、必要な時にエネルギーを放出している物質が「ATP」です。
ATPはさまざまな栄養素から産生されますが、代表的なものが炭水化物です。
ここからは、正常状態とビタミンB1の欠乏状態に分けて、糖代謝の流れを見ていきましょう。
正常状態の糖代謝
炭水化物に含まれる糖は、「グルコース」という物質として細胞内に入り込みます。
グルコースを細胞内で待ち受けているのが、「解糖系」と呼ばれる化学反応の経路です。
解糖系を経て、グルコースは「ピルビン酸」という物質に変化します。
この過程でATPが2分子産生されます。
グルコースから変化したピルビン酸が向かう先は、細胞内の器官「ミトコンドリア」です。
ピルビン酸は「ピルビン酸デヒドロゲナーゼ」という酵素の作用により、「アセチルCoA」という物質に変化します。
この時、ピルビン酸デヒドロゲナーゼの作用を補助している物質(補酵素)が、ビタミンB1なのです。
その後、アセチルCoAは「クエン酸回路」と呼ばれる化学反応の経路に入り、「NADH」と「FADH2」という物質を生み出します。
そして、NADHとFADH2は「電子伝達系」と呼ばれる化学反応の経路に入り、大量のATPが産生されます。
最終的に産生されるATPの数は32分子です。
ビタミンB1欠乏状態の糖代謝
ビタミンB1の欠乏状態では、「ピルビン酸→アセチルCoA」の反応があまり進みません。
このような状態では、ピルビン酸は「乳酸」という物質に変換されやすくなります。
なお、「ピルビン酸→乳酸」の反応は、組織が低酸素状態に陥った場合にも亢進します(嫌気性解糖)。
アセチルCoAの量が減ると、産生されるATPの減少は必然です。
その結果、体内がエネルギー不足となり、神経系・心臓・消化管などに機能障害をきたすことがわかっています。
ビタミンB1が欠乏する原因
ビタミンB1が欠乏する原因として挙げられるものは以下の通りです。
- 低栄養状態
- ビタミンB1需要量の増大
- アルコール依存症
ビタミンB1需要量の増大として考えられるのは、ビタミンB1を含まない高カロリー輸液です。
高カロリー輸液とは、医療現場にて糖を補うために投与する液体です。
高カロリー輸液を投与すると、糖を代謝するためにビタミンB1が急激に消費されるため、ビタミンB1欠乏状態に陥ります。
その他、重労働などにより大量のATPが必要となる状態も、ビタミンB1需要量を増大させるでしょう。
重度のアルコール依存症も、ビタミンB1欠乏の大きな原因です。
過度の飲酒は、消化管からビタミンB1を吸収したり、肝臓でビタミンB1を貯蔵したりするのを阻害するからです。
また、アルコール依存症患者は低栄養状態になりがちであるため、ビタミンB1の摂取量が足りていない場合も少なくありません。
ビタミンB1の欠乏症
ビタミンB1の欠乏症として主なものは以下の3つです。
- 脚気
- ウェルニッケ脳症
- 乳酸アシドーシス
それぞれについて見ていきましょう。
①脚気
脚気は、さまざまなビタミン欠乏症の中でも発症頻度が高い疾患です。
末梢部の神経障害が主に現れる「乾性脚気」と、心臓の機能が低下した状態である心不全に陥る「湿性脚気」に分類されます。
ただし、症例の多くは両者の混合型です。
乾性脚気では、末梢部に生じる神経障害により感覚障害や運動障害がみられます。
具体的な症状としては、手足に痛みや痺れが生じたり、歩きにくくなったりするなどです。
湿性脚気に伴う心不全では、以下のような症状が現れます。
- 心臓の肥大
- 頻脈
- 拡張期血圧(下の血圧)の低下
- 下肢のむくみ
重症度の高い脚気として、血液循環の悪化が急速に進むものを衝心脚気と呼びます。
衝心脚気で起こり得る症状は以下の通りです。
- 動悸
- 呼吸困難
- 口が渇く
- 悪心/嘔吐
- 尿が出ない
- チアノーゼ(血液中の酸素が不足して皮膚が青紫色になる)
特に重症度が高いケースでは、1~3日で命にかかわる場合があります。
そのため、今よりも低栄養状態に陥りやすかった江戸時代には、衝心脚気を「3日坊主」と呼んで恐れていたようです。
②ウェルニッケ脳症
ビタミンB1の欠乏により神経系に異常をきたした結果、発生する疾患がウェルニッケ脳症です。
脳内にある「脳室」という場所の周囲に炎症や壊死が起こります。
その結果、以下のような症状がみられます。
- 記憶障害
- 意識障害
- 眼球運動障害
- 運動失調
眼球運動障害の中では、眼球が痙攣するように動いたり細かく揺れたりする、眼振が最もよくみられます。
また、運動失調によって歩きにくくなるケースが多いです。
ウェルニッケ脳症に対しては、速やかにビタミンB1を大量投与することで回復が見込めます。
しかし、治療が遅れると後遺症を残したり、致命的となったりする場合があります。
ウェルニッケ脳症の後遺症として、代表的なものが「コルサコフ症候群」です。
コルサコフ症候群では、以下のような症状がみられます。
- 記銘力障害(記憶障害の一種で、新しく物事を覚えられない)
- 見当識障害(時間・場所・人物を認識する能力が低下する)
- 作話(?の体験をつくりあげる)
コルサコフ症候群はさまざまな疾患に関連してみられますが、ウェルニッケ脳症の後遺症として生じたものはウェルニッケ-コルサコフ症候群と呼ばれています。
③乳酸アシドーシス
中学校や高校の理科の授業で、「pH」という言葉を聞いたことがある人は多いでしょう。
私たちの身体におけるpHとは、動脈血中の「水素イオン」という物質の濃度を表しており、水素イオンが増加するとpHは小さくなります。
正常値は7.35≦pH≦7.45であり、7.35未満の状態が「アシドーシス」、7.45を超える状態が「アルカローシス」です。
極端なアシドーシスやアルカローシスに陥ると、さまざまな身体機能に異常が生じます。
ここで、ビタミンB1の欠乏状態では、ピルビン酸が乳酸に変換されやすいことを思い出してください。
そして、乳酸には水素イオンを放出する作用があるため、乳酸が多く存在する状態ではアシドーシスとなりやすいのです。
その結果、以下のような症状がみられます。
- 悪心/嘔吐
- 腹痛
- 全身倦怠感
- 意識障害
意識障害を起こす可能性があることからもわかるように、乳酸アシドーシスは緊急性の高い疾患です。
ビタミンB1が多く含まれる食材
ビタミンB1の欠乏症を起こさないためには、十分なビタミンB1を摂取しなければなりません。
ビタミンB1が多く含まれる食材として、代表的なものは以下の通りです。
- 豚肉
- 赤身肉
- 全粒穀物
- ナッツ
- 大豆
- カリフラワー
- ほうれん草
ビタミンB1は食材だけでなく、サプリメントからも摂取可能です。
ただし、過剰に摂取し過ぎると頭痛や不眠をきたす可能性があるため、摂り過ぎには注意してください。
なお、通常の食事による過剰症はほとんど起こらないと考えられています。
まとめ:ビタミンB1を摂取して欠乏症を予防しよう
ビタミンB1は水溶性ビタミンの一種であり、糖の代謝に関わる重要な栄養素です。
低栄養状態やアルコール依存症などが原因で、欠乏状態に陥ります。
ビタミンB1の欠乏により、脚気・ウェルニッケ脳症・乳酸アシドーシスが引き起こされる可能性があります。
多く含まれる食材を積極的に食べるなどして、欠乏症を予防しましょう。