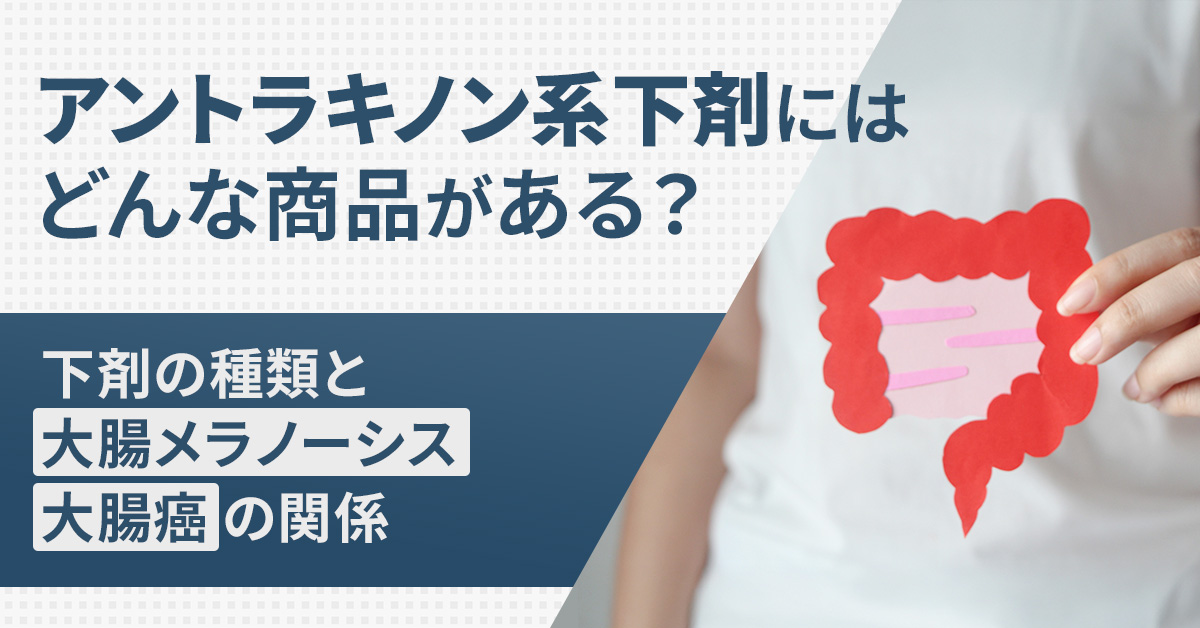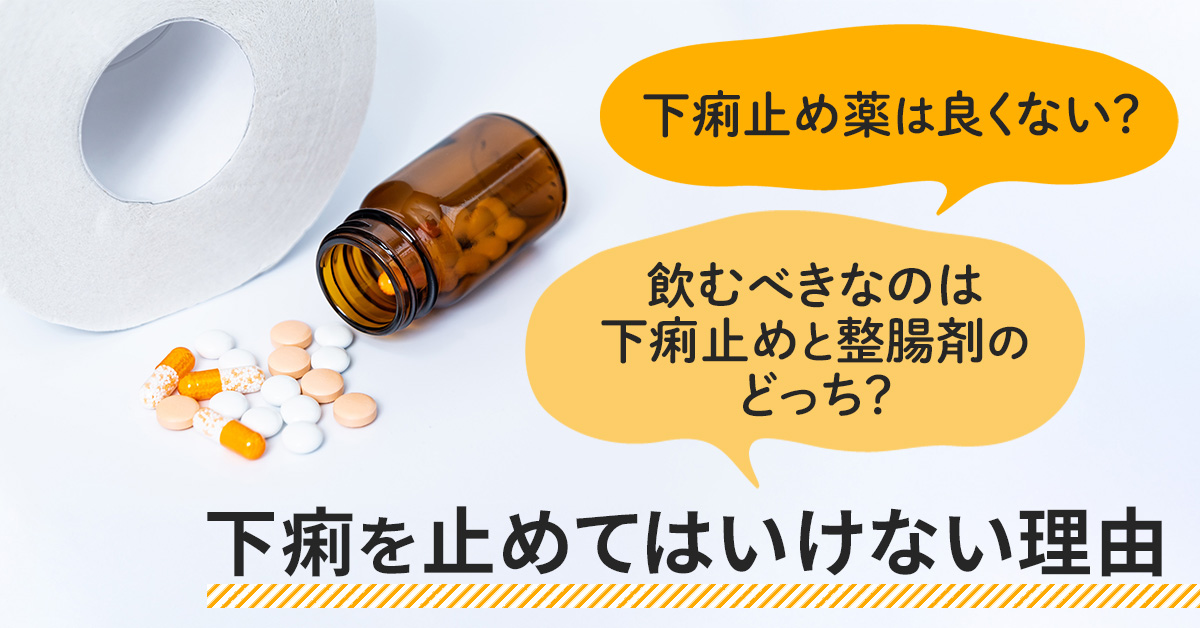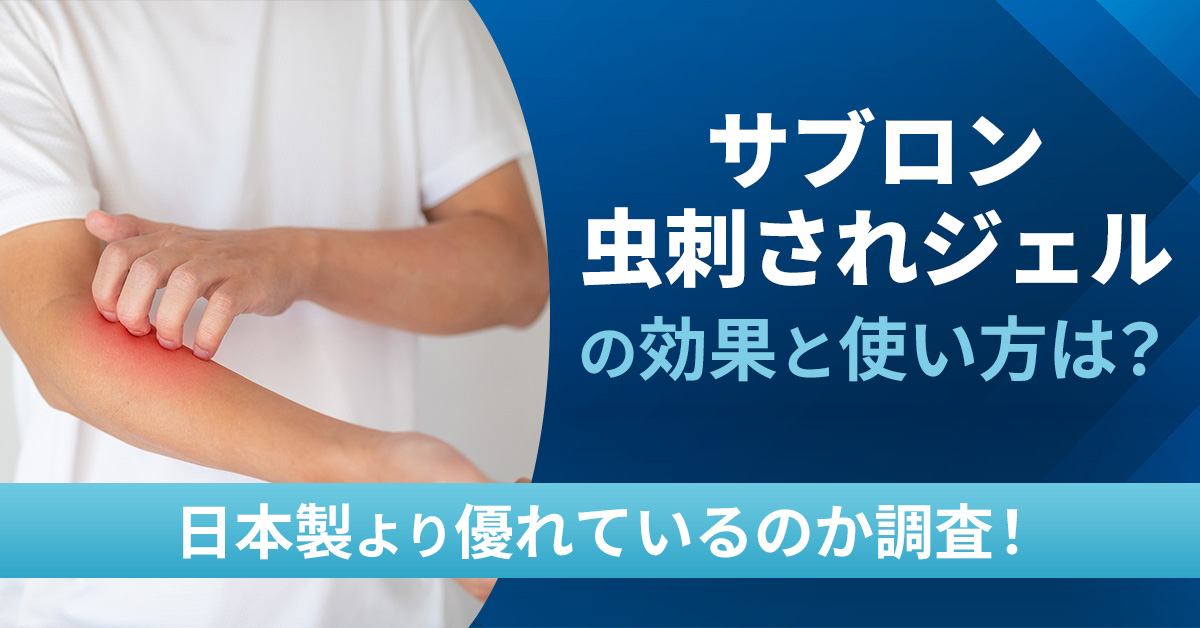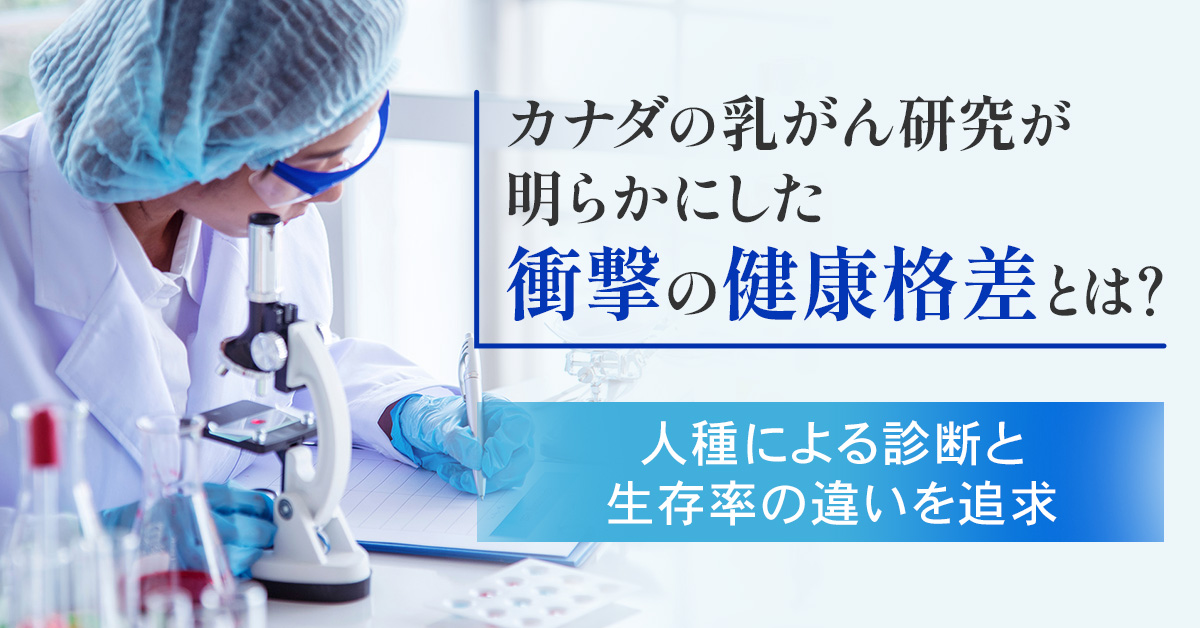「抗がん剤を使うとなぜ悪心・嘔吐が起こるの?」
「制吐薬はどうやって使い分けられているの?」
このような疑問を持っている人は少なくないのではないでしょうか。
本記事では、抗がん剤で悪心・嘔吐が起こるメカニズムについて徹底解説。
制吐薬の種類や、実際に使い分けについても詳しく紹介します。
本記事を読めば、抗がん剤による悪心・嘔吐や制吐薬について理解を深められます。
興味がある人はぜひ最後までご覧ください。
制吐薬は抗がん剤の副作用に対して使われている
2020年のデータに基づくと、男性の62.1%/女性の48.9%が一生のうちに癌と診断されています。
また、2022年のデータに基づくと、男性の25.1%/女性の17.5%が癌で死亡しています。
統計からもわかるように、癌は決して他人事ではないのです。
癌の治療において、薬物治療が行われるケースは少なくありません。
そして、抗がん剤には複数の副作用がみられることが報告されています。
代表的な副作用が悪心(嘔吐しそうな不快感)と嘔吐です。
制吐薬は、このような悪心・嘔吐に対して主に用いられています。
乗り物酔いや胃炎・胃潰瘍に伴う嘔吐に対して用いられる場合もありますが、今回は抗がん剤の副作用緩和に注目して解説していきます。
抗がん剤で悪心・嘔吐が起こるメカニズム
私たちの脳には「第4脳室」という、髄液(脳を保護している液体)が貯留している場所があります。
そして、第4脳室の底に位置する「CTZ」という箇所にあるのが、「NK1受容体」・「5-HT3受容体」・「ドパミンD2受容体」という部位です。
抗がん剤を使用すると、これらの受容体が刺激を受けます。
具体的には以下の通りです。
| 刺激する物質 | 受容体 |
|---|---|
| サブスタンスP | NK1受容体 |
| セロトニン | 5-HT3受容体 |
| ドパミン | ドパミンD2受容体 |
また、消化管の一部である小腸でも同様に、抗がん剤を理由とする受容体の刺激が起こっています。
特に、セロトニンによる5-HT3受容体への刺激がよくみられます。
刺激を受けた受容体が影響を与える先は、脳内の「延髄」という場所にある「嘔吐中枢」という箇所です。
嘔吐中枢という名前からもわかるように、ここへ興奮が伝わると私たちは悪心を感じます。
また、「迷走神経」・「横隔膜神経」・「脊髄神経」という複数の神経を刺激して、嘔吐を引き起こしているのです。
抗がん剤による悪心・嘔吐リスク
一口に抗がん剤と言っても、非常に多くの薬剤が治療のために使われています。
それぞれ悪心・嘔吐を引き起こすリスクが異なるため、抗がん剤はリスク別に以下の4つに分類されています。
| リスク分類 | 悪心・嘔吐がみられる患者さんの割合 |
|---|---|
| 高度リスク | 90%を超える |
| 中等度リスク | 30~90% |
| 軽度リスク | 10~30% |
| 最小度リスク | 10%未満 |
なお、リスク分類における悪心・嘔吐がみられる患者さんの割合とは、制吐薬を予防的に投与しなかった場合にみられる割合を指しています。
制吐薬の種類
制吐薬の種類について紹介します。
なお、2024年9月時点でのがん診療ガイドラインに基づき、国内で悪心・嘔吐に対して承認されていない薬剤には()を付けています。
| 分類 | 薬剤名 |
|---|---|
| 副腎皮質ステロイド | デキサメタゾン、(メチルプレドニゾロン) |
| 5-HT3受容体拮抗薬(第一世代) | アザセトロン、インジセトロン、オンダンセトロン、グラニセトロン、ラモセトロン |
| 5-HT3受容体拮抗薬(第二世代) | パロノセトロン |
| NK1受容体拮抗薬 | アプレピタント、ホスアプレピタント |
| ドパミンD2受容体拮抗薬 | ドンペリドン、メトクロプラミド |
| ベンゾジアゼピン系抗不安薬 | (アルプラゾラム)、(ロラゼパム) |
| フェノチアジン系抗精神病薬(ドパミンD2受容体拮抗作用) | (プロクロルペラジン)、(クロルプロマジン) |
| ブチロフェノン系抗精神病薬(ドパミンD2受容体拮抗作用) | (ハロペリドール) |
| ベンズイソオキサゾール系抗精神病薬(ドパミンD2受容体拮抗作用) | (リスペリドン) |
| 多受容体作用抗精神病薬(ドパミンD2・ヒスタミンH1・5-HT3受容体拮抗作用) | オランザピン |
| プロピルアミン系抗ヒスタミン薬 | (クロルフェニラミン) |
以上のうち、NK1受容体拮抗薬・5-HT3受容体拮抗薬・デキサメタゾンの3剤が主に使用されています。
NK1受容体拮抗薬と5-HT3受容体拮抗薬については、先ほど解説した抗がん剤で悪心・嘔吐が起こるメカニズムをブロックすることで、作用を発揮しています。
一方、副腎皮質ステロイドであるデキサメタゾンが悪心・嘔吐に作用するメカニズムについては、はっきりとは解明されていません。
制吐薬の使い分け
紹介した通り制吐薬には多くの種類があり、状況に応じて使い分けられています。
ここからは、がん診療ガイドラインに則って使い分けについて解説します。
具体的な内容は以下の通りです。
・抗がん剤による急性の悪心・嘔吐の予防
・抗がん剤による遅発性の悪心・嘔吐の予防
・5-HT3受容体拮抗薬の第一世代or第二世代
・突出性悪心・嘔吐の治療
・軽度または最小度リスクの抗がん剤による悪心・嘔吐の治療
・予期性悪心・嘔吐の予防と治療
・放射線治療による悪心・嘔吐の治療
・小児がんに対する抗がん剤による悪心・嘔吐の対処
・オピオイド鎮痛薬による悪心・嘔吐の治療
それぞれ見ていきましょう。
①抗がん剤による急性の悪心・嘔吐の予防
抗がん剤の投与後、24時間以内に出現するものが急性の悪心・嘔吐と定義されています。
急性の悪心・嘔吐は、患者さんの薬物療法への積極性を大きく左右するため、予防的な制吐薬の投与が必要です。
抗がん剤のリスク別に、以下の制吐薬が推奨されます。
| リスクレベル | 推奨される制吐薬 |
|---|---|
| 高度リスク | アプレピタントまたはホスアプレピタント・5-HT3受容体拮抗薬・デキサメタゾンの3剤併用 |
| 中等度リスク | 5-HT3受容体拮抗薬・デキサメタゾンの2剤併用 一部の抗がん剤でアプレピタントの追加 |
②抗がん剤による遅発性の悪心・嘔吐の予防
抗がん剤の投与後、24時間以降に出現するものが遅発性の悪心・嘔吐と定義されています。
遅発性の悪心・嘔吐は、患者さんのQOLや精神的安定を損なうものであり、急性と同様に予防的な制吐薬の投与が必要です。
抗がん剤のリスク別に、以下の制吐薬が推奨されます。
| リスクレベル | 推奨される制吐薬 |
|---|---|
| 高度リスク | アプレピタント・デキサメタゾンの2剤併用 |
| 中等度リスク |
デキサメタゾンの単独投与 症例に応じてアプレピタント・デキサメタゾンの2剤併用や、5-HT3受容体拮抗薬またはアプレピタントの単独投与 |
③5-HT3受容体拮抗薬の第一世代or第二世代
5-HT3受容体拮抗薬には第一世代と第二世代があります。
それぞれが推奨される状況は、抗がん剤のリスク別に以下の通りです。
| リスクレベル | 推奨される治療薬 |
|---|---|
| 高度リスク | NK1受容体拮抗薬・5-HT3受容体拮抗薬・デキサメタゾンの3剤併用時で第二世代が好まれる |
| 中等度リスク |
NK1受容体拮抗薬を併用する場合は第一世代が好まれる NK1受容体拮抗薬を併用しない場合は第二世代が好まれる |
④突出性悪心・嘔吐の治療
抗がん剤に対する予防的な制吐薬の投与を行っても、悪心・嘔吐が生じてしまうケースが突出性悪心・嘔吐と定義されています。
突出性悪心・嘔吐の治療は困難である場合が多いため、可能な限り起こさないことが前提として重要です。
しかし、十分に予防的投与を行ったとしても、突出性悪心・嘔吐が起こる可能性は0にはなりません。
もし発生した場合は、作用するメカニズムが異なる制吐薬の複数かつ規則的な投与が推奨されます。
また、制吐薬を投与しても突出性悪心・嘔吐が持続するケースでは、本当に悪心・嘔吐が抗がん剤により引き起こされているのか確認しなければなりません。
具体的には、以下のような状態で悪心・嘔吐が生じている可能性があります。
・消化管の部分的狭窄や完全閉塞
・頭蓋内圧亢進
・電解質(カルシウム・ナトリウム・カリウムなど)異常
・心因性
⑤軽度または最小度リスクの抗がん剤による悪心・嘔吐の予防
軽度または最小度リスクの抗がん剤に対する、予防的な制吐薬の投与は推奨されていません。
ただし、悪心・嘔吐が出現する患者さんがいないわけではないため、軽度リスクの抗がん剤に対してデキサメタゾンが単独投与されるケースもあります。
⑥予期性悪心・嘔吐の予防と治療
薬物療法や放射線治療により悪心・嘔吐が生じた経験のある患者さんは、次回以降に同様の治療を受ける前から悪心・嘔吐をきたすケースがあります。
このようにして起こる悪心・嘔吐を予期性悪心・嘔吐と呼び、治療について考えたり病院に来たりするだけで催すケースも少なくありません。
もちろん、急性や遅発性の悪心・嘔吐を完全にコントロールして、患者さんに悪心・嘔吐を経験させないのが最善の予防法です。
しかし、完全に0にすることはできないため、予期性悪心・嘔吐に対してベンゾジアゼピン系抗不安薬が用いられています。
制吐薬の投与だけでなく、以下に挙げる心理学的な治療法も有効と考えられています。
・系統的脱感作(不安の対象に徐々に慣れていくことで克服する行動療法)
・リラクセーション
・催眠療法
⑦放射線治療による悪心・嘔吐の治療
癌に対する治療では、薬物療法だけでなく放射線治療もよく行われています。
そして、抗がん剤同様に、放射線治療により悪心・嘔吐が引き起こされるケースも少なくありません。
その結果、治療継続が難しくなったり、患者さんのQOLが低下したりする場合が多いです。
放射線治療に関しても、抗がん剤と同じようにリスク分類がなされています。
ただし、悪心・嘔吐の発生頻度が抗がん剤のリスク分類におけるそれとは異なります。
具体的なリスク分類と、それぞれで推奨される制吐薬は以下の通りです。
| リスク分類 | 頻度 | 放射線照射部位 | 制吐薬 |
|---|---|---|---|
| 高度 | 90%を超える | 全身、全リンパ節 | 5-HT3受容体拮抗薬・デキサメタゾンの2剤併用(予防的投与) |
| 中等度 | 60~90% | 上腹部、半身 | 5-HT3受容体拮抗薬の単独投与または5-HT3受容体拮抗薬・デキサメタゾンの2剤併用(予防的投与) |
| 軽度 | 30~59% | 頭蓋、頭蓋脊髄、頭頸部、胸部下部、骨盤 | 5-HT3受容体拮抗薬の単独投与(予防的または症状発現後) |
| 最小度 | 30%未満 | 四肢、乳房 | ドパミンD2受容体拮抗薬または5-HT3受容体拮抗薬の単独投与(症状発現後) |
⑧小児がんに対する抗がん剤による悪心・嘔吐の対処
小児がんに対しては、薬物療法が効果を発揮するケースが多くみられます。
そのため、制吐薬による悪心・嘔吐の予防が非常に重要です。
小児に対しても、基本的には成人と同様に、5-HT3受容体拮抗薬・デキサメタゾン・NK1受容体拮抗薬の3剤併用が可能です。
ただし、小児適応(小児に対して使っても大丈夫か)や用量の確認を怠ってはいけません
⑨オピオイド鎮痛薬による悪心・嘔吐の治療
癌に関与して引き起こされる痛み(癌性疼痛)に対しては、「オピオイド鎮痛薬」という薬剤が用いられています。
オピオイド鎮痛薬は、癌患者の痛みを緩和するうえで有効な薬剤ですが、副作用として悪心・嘔吐をきたすケースが少なくありません。
オピオイド鎮痛薬による悪心・嘔吐は、主にドパミンや「ヒスタミン」という物質の遊離により引き起こされています。
そのため、ドパミンD2受容体拮抗薬による予防が推奨されます。
まとめ:制吐薬で抗がん剤による悪心・嘔吐に対処しよう
制吐薬とは、抗がん剤により引き起こされる悪心・嘔吐に対して用いられる治療薬です。
悪心・嘔吐が生じるメカニズムをもとに、様々な薬剤が開発されています。
制吐薬は、癌の治療状況に応じて使い分けられています。
抗がん剤のリスク分類なども踏まえて、制吐薬で悪心・嘔吐に対処しましょう。