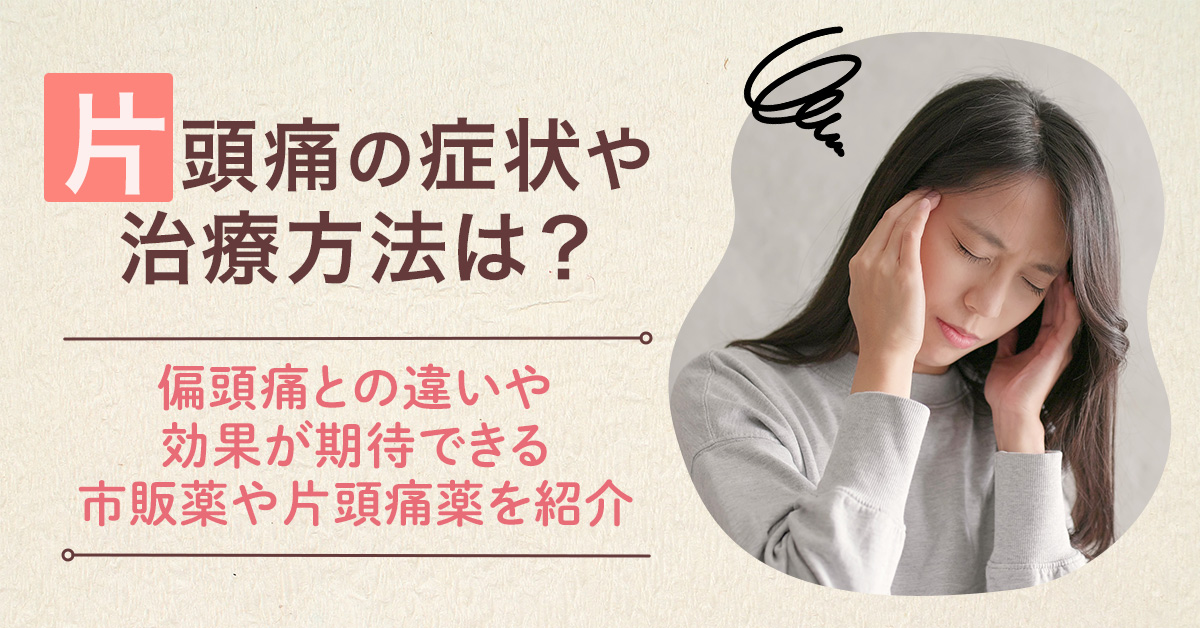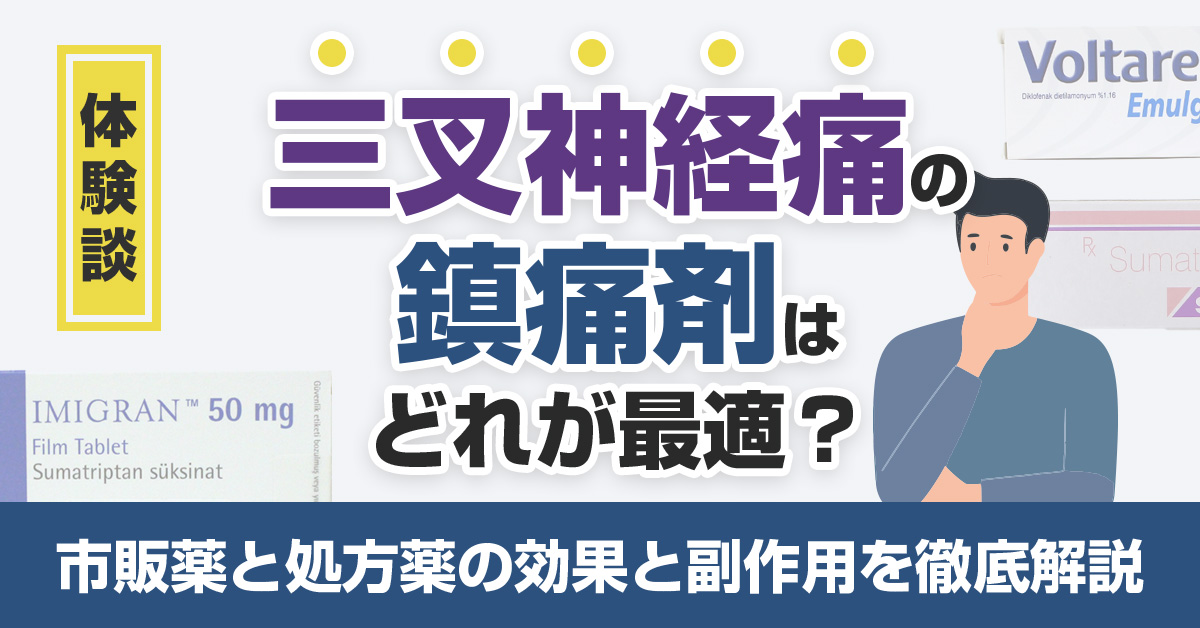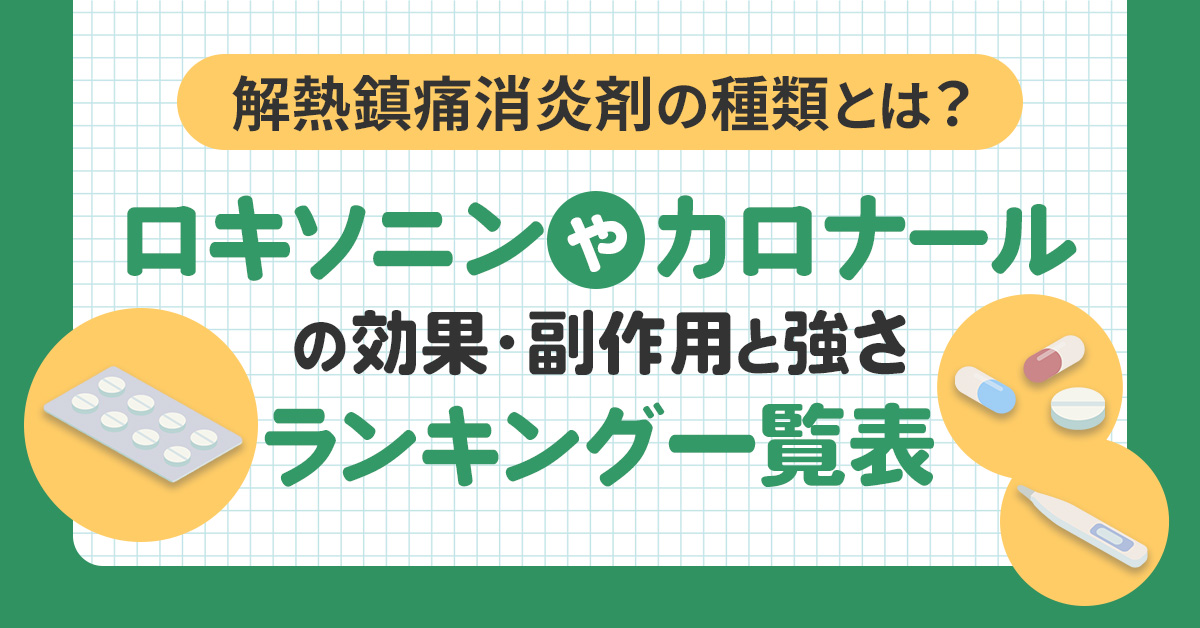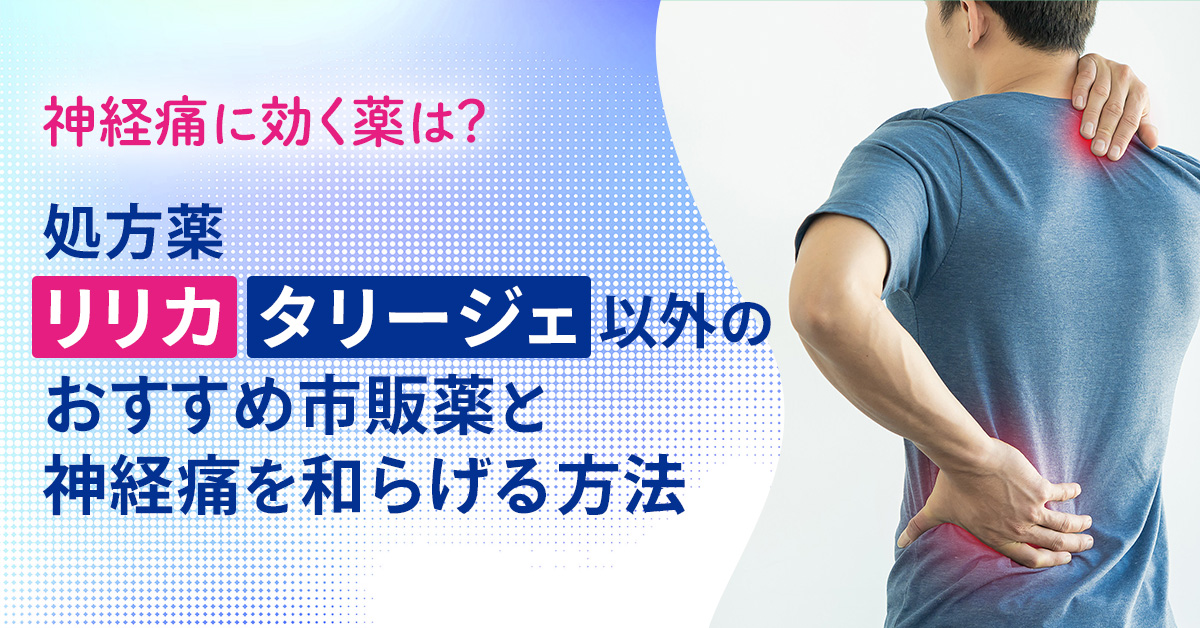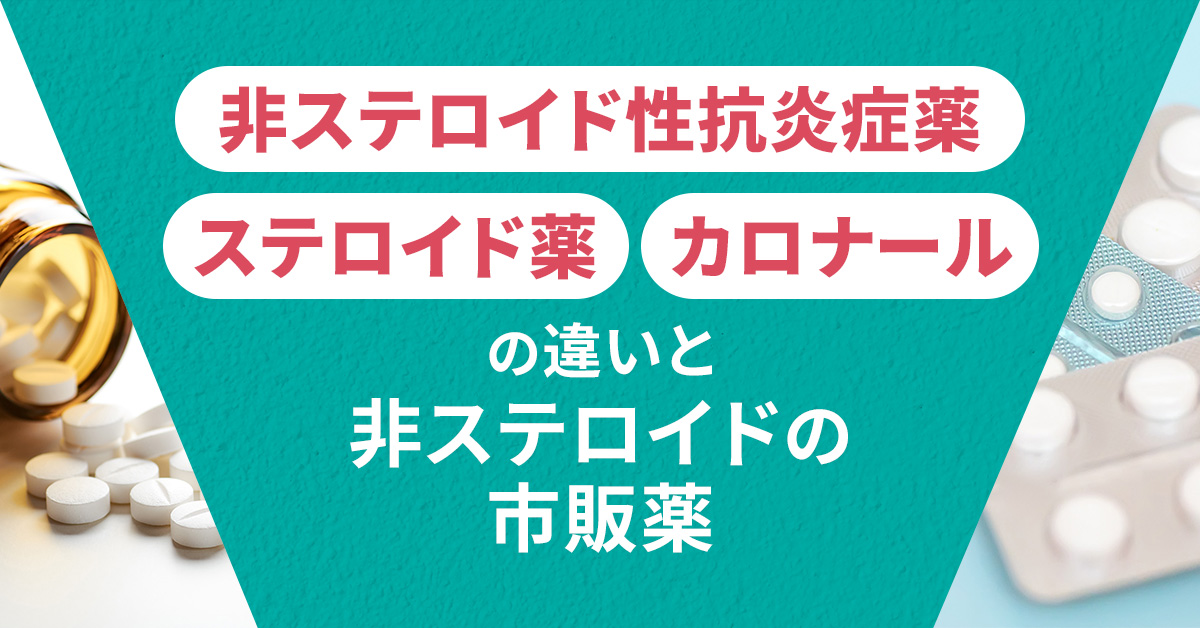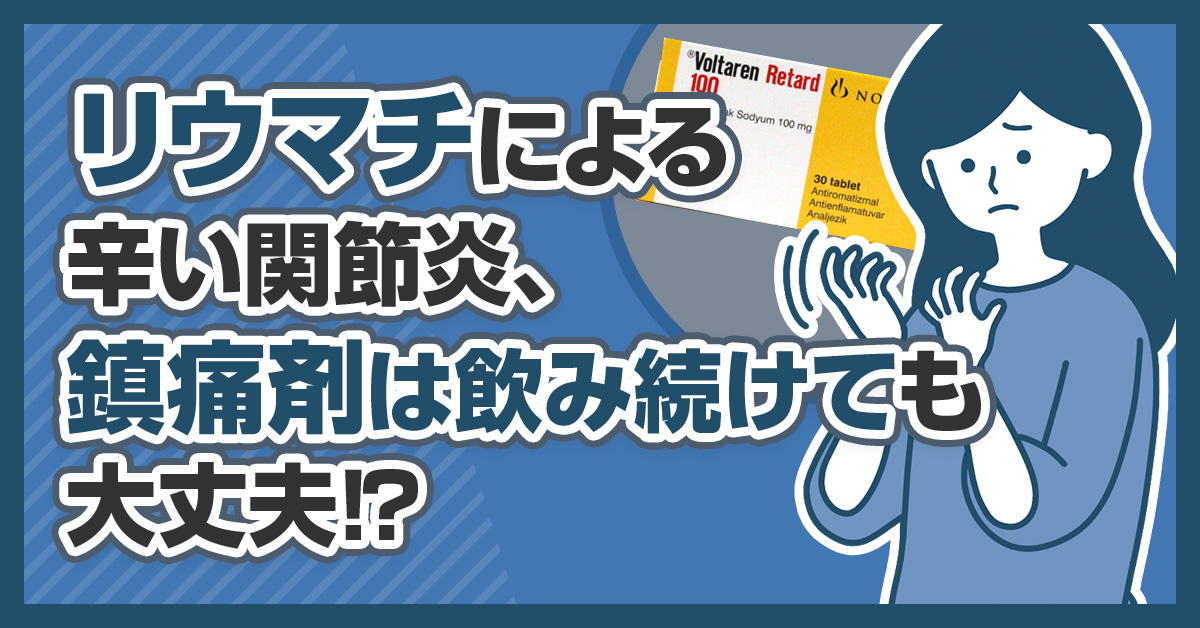「炎症ってなんで起きるの?」
「NSAIDsが炎症を治療するメカニズムは?」
このような疑問を持っている人は少なくないのではないでしょうか。
本記事では、炎症の症状が生じるメカニズムから、NSAIDsが抗炎症作用を発揮するメカニズムまで徹底解説。
NSAIDsの種類や副作用も紹介します。
本記事を読めば、炎症やNSAIDsについて理解を深められます。
興味がある人はぜひ最後までご覧ください。
NSAIDsは炎症に対する代表的な治療薬
NSAIDsとは、炎症に対して用いられる代表的な治療薬です。
解熱作用や鎮痛作用を持っており、様々な症状に対して広く使われています。
そもそも炎症とは、感染症や外傷によって組織が障害を受けた際に、有害な因子を排除して組織を修復するための過程です。
その過程の中で、以下のような症状が現れます。
- 発赤
- 腫脹
- 熱感
- 疼痛
以上の4症状は、「炎症の4徴候」と呼ばれており重要な所見です。
まずは、これらの症状がどのようなメカニズムで生じるのか見ていきましょう。
炎症の症状が生じるメカニズム
感染症や外傷による組織障害を受けた際、まず動き出すのが免疫に関わる細胞である「マスト細胞」や「マクロファージ」です。
これらの細胞は「ケミカルメディエーター」や「サイトカイン」と呼ばれる様々な物質を放出し、炎症の過程を進めます。
マスト細胞の働き
マスト細胞が放出するのは主に以下の物質です。
- ヒスタミン
- プロスタグランジン
- ロイコトリエン
- 血小板活性化因子
これらの物質には、血管透過性(血管と血管の周囲組織との間で物質が移動する性質)を亢進させる作用があります。
その結果、血液中の様々な成分が漏出し、周囲組織に腫脹が生じるのです。
周囲組織の圧力の上昇や、漏出した成分である「ブラジキニン」の作用により疼痛も生じます。
また、プロスタグランジンやブラジキニンには血管を拡張する作用があります。
その結果、局所的に血流の増加が起こり、発赤や熱感が生じるのです。
マクロファージの働き
マクロファージが放出するのは主に以下の物質です。
- TNF-α
- IL-1
- IL-6
これらの物質は、免疫に関わる細胞を組織に呼び寄せるとともに、血流に乗って脳に到達するとプロスタグランジンの産生を促進します。
このようにして産生されたプロスタグランジンは、脳内にある「視床下部」という場所の「体温調節中枢」という箇所に働きかけ、全身の体温を上昇させるのです。
炎症の目的
ここまで見てきたように、マスト細胞やマクロファージの働きにより炎症の症状が生じ、私たちに苦痛がもたらされるのです。
それではなぜ、このようなメカニズムが必要なのでしょうか?
それはひとえに、障害を受けた組織の修復をスムーズに進めるためです。
マスト細胞による血管透過性の亢進により、免疫や修復に関わる物質が障害を受けた組織に移動しやすくなります。
血管拡張による血流の増加は、組織の代謝を亢進して修復を促します。
マクロファージが働く目的も同様です。
免疫に関わる細胞を組織に呼び寄せることで、有害な因子を除去します。
全身の発熱に関しては研究が進められていますが、免疫に関わる細胞の能力を増強している可能性が考えられています。
プロスタグランジンを生成するアラキドン酸カスケード
炎症の症状が生じるメカニズムで解説したように、プロスタグランジンは炎症の過程を進める代表的な物質です。
そんなプロスタグランジンを生成しているのが、「アラキドン酸カスケード」と呼ばれる反応です。
「アラキドン酸」は脂肪酸(脂質の主要な構成要素)の一種であり、細胞を覆う「細胞膜」を構成している「リン脂質」という物質から遊離します。
遊離したアラキドン酸は、「シクロオキシゲナーゼ(COX)」という物質の働きにより、プロスタグランジンに変化します。
ここでポイントとなるのが、COXには「COX1」と「COX2」の2種類があるという点です。
COX1はほとんど全ての組織で恒常的に発現しており、ここで生成されたプロスタグランジンは以下のような働きを持ちます。
- 胃粘膜を保護する
- 腎臓に流れ込む血流を調節する
- 血小板の機能を調節する
以上の働きからわかるように、COX1には様々な生理機能を調節する作用があるのです。
一方、COX2は多くの組織であまり発現していませんが、炎症の際には免疫に関わる細胞などで発現が誘導されます。
ここで生成されたプロスタグランジンには、前述のように炎症の過程を進める働きがあります。
つまり、COX2には炎症反応を促進する作用があるのです。
また、アラキドン酸に対してはCOXだけでなく「LOX」という物質も働きかけており、LOXの働きによりロイコトリエンが生成されます。
ロイコトリエンはプロスタグランジンと同様に炎症に関わる物質であり、空気の通り道である気管支を収縮させる作用も持っています。
NSAIDsが抗炎症作用を発揮するメカニズム
アラキドン酸カスケードの解説で述べた通り、炎症の症状を引き起こすプロスタグランジンの生成にはCOXが必要です。
そこで、NSAIDsはCOXの働きを阻害することにより、抗炎症作用を発揮しています。
一般的なNSAIDsでは、COX1とCOX2の両方が阻害の対象です。
このようなNSAIDsでは、COX2の阻害により抗炎症作用を得られる一方で、COX1の阻害により生理機能を調節する作用も障害してしまいます。
そのため、様々な副作用を生じる恐れがあります。
副作用を抑えるために近年登場したのが、COX2のみを抑制するNSAIDs(COX2選択的阻害薬)です。
COX2選択的阻害薬はCOX1を阻害しないため、生理機能を調節する作用が障害されません。
NSAIDsの種類
NSAIDsに該当する代表的な薬剤は以下の通りです。
- アスピリン
- インドメタシン
- ジクロフェナク
- ロキソプロフェン
- イブプロフェン
- セレコキシブ(COX2選択的阻害薬)
それぞれのNSAIDsについて、適応となる疾患や用法用量を見ていきましょう。
また、特によく使われているアスピリンについては詳しく解説します。
①アスピリン
アスピリンの特徴として、COXの働きを不可逆的に失わせる点が挙げられます。
他のNSAIDsが持っているCOXを阻害する作用は可逆的であるため、薬剤がなくなるとCOXの働きが復活します。
しかし、アスピリンであればCOXの働きは永久的に復活しません。
そのような特徴を持つアスピリンの、適応となる疾患と用法用量は以下の通りです。
| 適応となる疾患 | 用法用量 |
|---|---|
| 関節リウマチ、リウマチ熱、変形性関節症、強直性脊椎炎、関節周囲炎、結合織炎、術後疼痛、歯痛、症候性神経痛、関節痛、腰痛症、筋肉痛、捻挫痛、打撲痛、痛風による痛み、頭痛、月経痛 | 1回0.5~1.5g、1日1.0~4.5gを経口投与 |
| 急性上気道炎 | 1回0.5~1.5gを症状に応じて服用、原則1日最大4.5gかつ1日2回まで |
| 川崎病 | 急性期:体重1kgあたり1日30~50mgを3回に分け経口投与 回復期~慢性期:体重1kgあたり1日3~5mgを1回経口投与 |
また、アスピリンは炎症に対する治療薬としてだけでなく、抗血栓療法としても用いられています。
血栓とは、血小板をはじめとする血液中の物質が集まってできた塊であり、心筋梗塞や脳血管障害の原因となります。
アスピリンが抗血栓作用を持つのは、COX1の阻害により血小板の凝集を抑制できるからです。
なお、抗血栓療法として用いられるアスピリンは「バイアスピリン」として扱われており、NSAIDsとして用いられるアスピリンとは区別されます。
②インドメタシン
インドメタシンの内服薬は、2018年に製造中止となっています。
そのため、同様の働きを持つ「インドメタシンファルネシル(インフリー)」について紹介します。
適応となる疾患と用法用量は以下の通りです。
| 適応となる疾患 | 用法用量 |
|---|---|
| 関節リウマチ、変形性関節症、腰痛症、肩関節周囲炎、頸肩腕症候群 | 1回200mgを朝夕1日2回食後経口投与 |
③ジクロフェナク
ジクロフェナクが適応となる疾患と用法用量は以下の通りです。
| 適応となる疾患 | 用法用量 |
|---|---|
| 関節リウマチ、変形性関節症、変形性脊椎症、腰痛症、腱鞘炎、頸肩腕症候群、神経痛、後陣痛、骨盤内炎症、月経困難症、膀胱炎、前眼部炎症、歯痛、手術ならびに抜歯後の鎮痛・消炎 | 1日75~100mgを原則3回に分け経口投与 |
| 急性上気道炎 | 1回25~50mgを症状に応じて服用、原則1日最大100mgかつ1日2回まで |
④ロキソプロフェン
ロキソプロフェンが適応となる疾患と用法用量は以下の通りです。
| 適応となる疾患 | 用法用量 |
|---|---|
| 関節リウマチ、変形性関節症、腰痛症、肩関節周囲炎、頸肩腕症候群、歯痛、手術後、外傷後並びに抜歯後の鎮痛・消炎 | 1回60mgを1日3回経口投与 症状に応じて服用する場合は1回60~120mgを経口投与 |
| 急性上気道炎 | 1回60mgを症状に応じて服用、原則1日最大180mgかつ1日2回まで |
⑤イブプロフェン
イブプロフェンが適応となる疾患と用法用量は以下の通りです。
| 適応となる疾患 | 用法用量 |
|---|---|
| 関節リウマチ、関節痛及び関節炎、神経痛及び神経炎、背腰痛、頸腕症候群、子宮付属器炎、月経困難症、紅斑(結節性紅斑、多形滲出性紅斑、遠心性環状紅斑)、手術並びに外傷後の消炎・鎮痛 | 以下の1日量を3回に分け経口投与 5~7歳:200~300mg 8~10歳:300~400mg 11~15歳:400~600mg 成人:600 mg |
| 急性上気道炎 | 1回200mgを症状に応じて服用、原則1日最大600mgかつ1日2回まで |
⑥セレコキシブ
ここまでに紹介したNSAIDsはいずれも、COX2だけでなくCOX1の働きも阻害します。
一方、セレコキシブはCOX2のみを阻害するCOX2選択的阻害薬です。
セレコキシブが適応となる疾患と用法用量は以下の通りです。
| 適応となる疾患 | 用法用量 |
|---|---|
| 関節リウマチ | 1回100~200mgを朝夕1日2回食後経口投与 |
| 変形性関節症、腰痛症、肩関節周囲炎、頸肩腕症候群、腱・腱鞘炎 | 1回100mgを朝夕1日2回食後経口投与 |
| 手術後、外傷後並びに抜歯後の消炎・鎮痛 | 初回のみ400mg、2回目以降は1回200mgを6時間以上の間隔空け1日2回経口投与 |
NSAIDsの副作用
NSAIDsの副作用として、代表的なものは以下の通りです。
- 消化性潰瘍(胃潰瘍や十二指腸)
- 腎障害
- アスピリン喘息
- 心筋梗塞や脳卒中のリスク増大の恐れ(COX2選択的阻害薬)
それぞれの副作用について見ていきましょう。
①消化性潰瘍
COX1により生成されたプロスタグランジンには、強力な胃酸から胃粘膜を守る作用があります。
そのため、NSAIDsによりプロスタグランジンの生成が抑制されると、胃粘膜がダメージを受け胃潰瘍や十二指腸潰瘍が生じやすいのです。
COX2選択的阻害薬はCOX1の働きを阻害しないため、一般的なNSAIDsよりも消化性潰瘍は生じにくいです。
しかし、COX2に対する完全な選択性があるわけではないため、消化性潰瘍が生じる可能性があります。
②腎障害
プロスタグランジンには、腎臓に流れ込む血流を調節して腎臓を保護する作用もあります。
そのため、NSAIDsを使用すると腎保護作用が失われてしまうのです。
そのため、NSAIDsの服用により腎障害をきたす可能性があります。
ただし、健康な人の場合はあまり起こり得ません。
③アスピリン喘息
NSAIDsによりCOXの働きが阻害されると、プロスタグランジンの原料であるアラキドン酸が余ります。
その結果、LOXの働きが活発になりロイコトリエンが増加するのです。
ロイコトリエンの主な作用には気管支の収縮があるため、喘息の原因となります。
このようなメカニズムで生じる喘息は、NSAIDsの代表的な薬剤であるアスピリンの名前をとって、アスピリン喘息と呼ばれます。
なお、COX2選択的阻害薬であるセレコキシブは、アスピリン喘息を起こしにくいです。
そのため、安定期のアスピリン喘息患者にも使用可能です。
④心筋梗塞や脳卒中のリスク増大の恐れ
消化性潰瘍やアスピリン喘息が生じにくいCOX2選択的阻害薬ですが、心筋梗塞や脳卒中のリスクを増大する恐れがあると報告されています。
あくまでも臨床試験での結果であり、詳細に関する議論が続いています。
まとめ:NSAIDsで炎症の症状に対処しよう
炎症とは感染症や外傷から身を守るための過程であり、炎症の4徴候と呼ばれる発赤・腫脹・熱感・疼痛が生じます。
これらの症状を引き起こしている物質の中で、主要なものがプロスタグランジンです。
NSAIDsはCOXの阻害を通してプロスタグランジンの生成を抑制し、抗炎症作用を発揮します。
用法用量や副作用に気を付けつつ、NSAIDsで炎症の症状に対処しましょう。