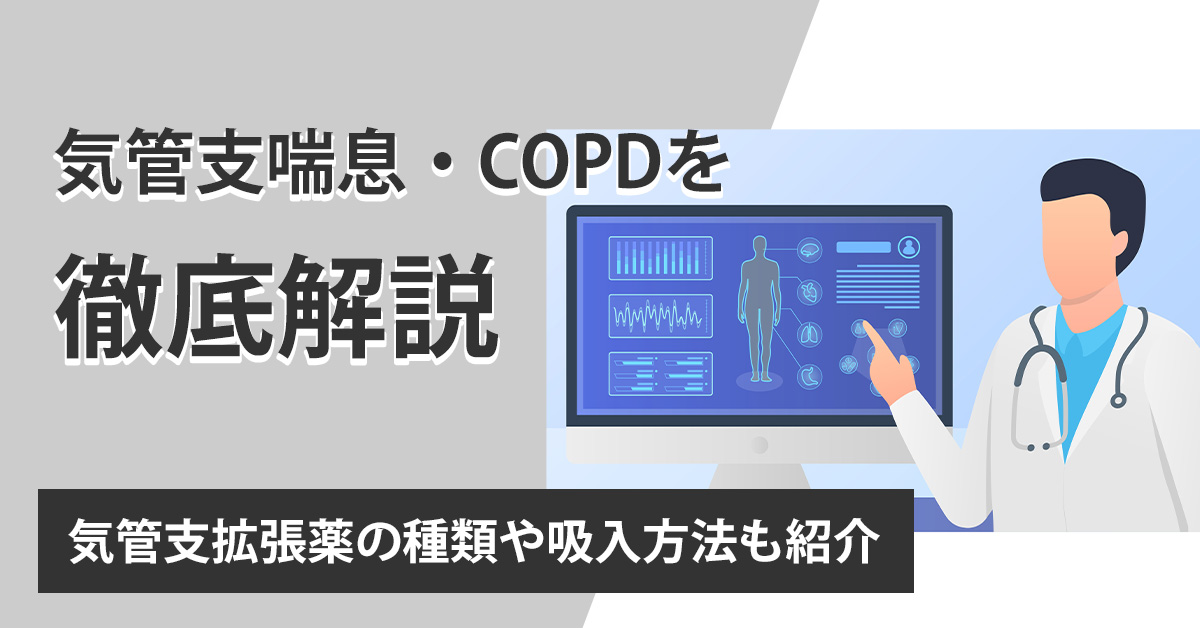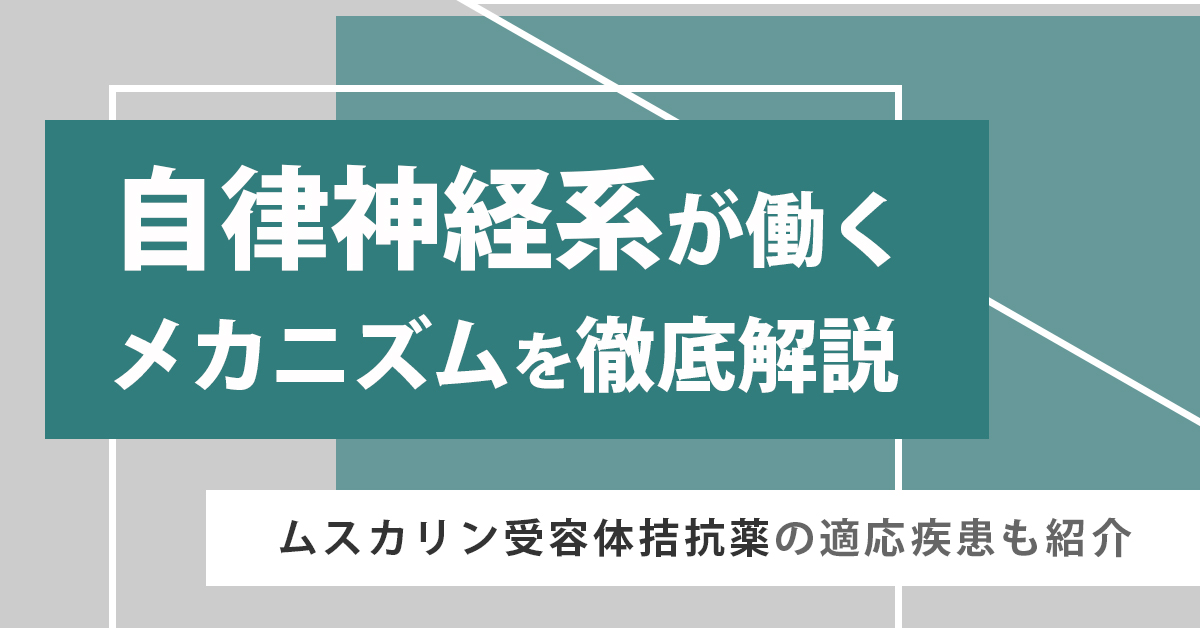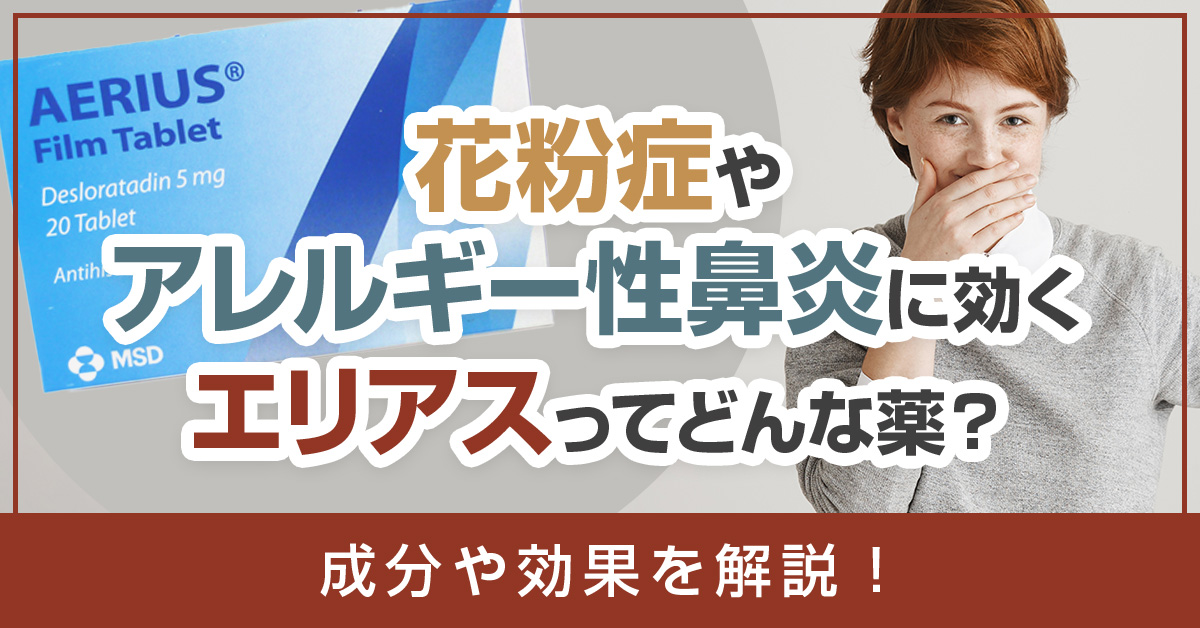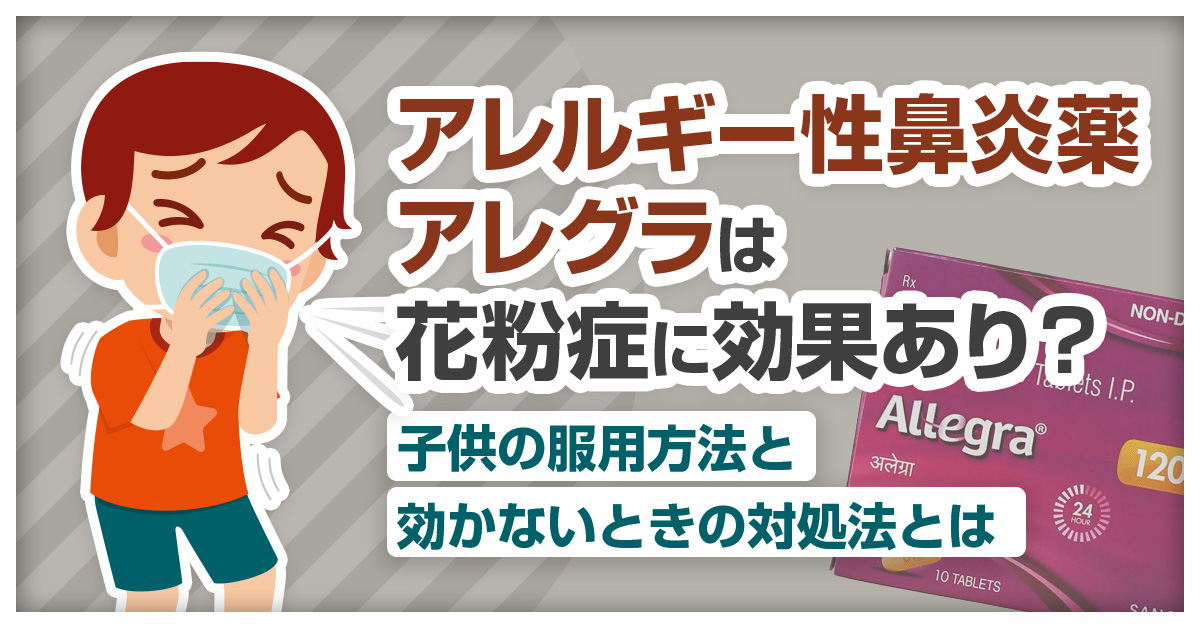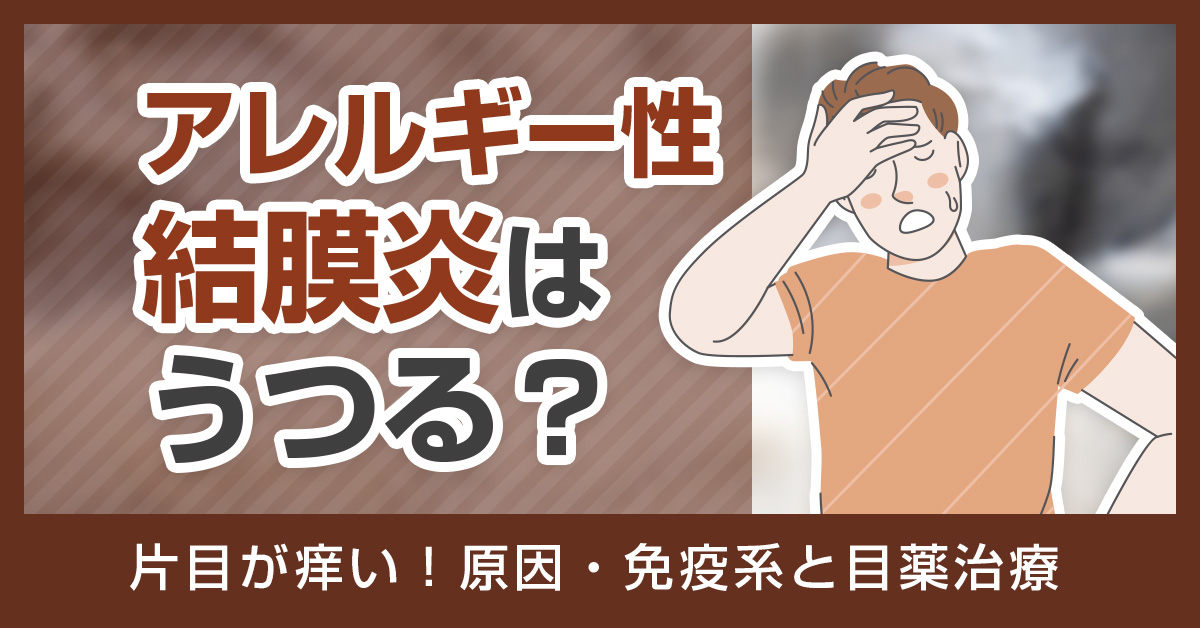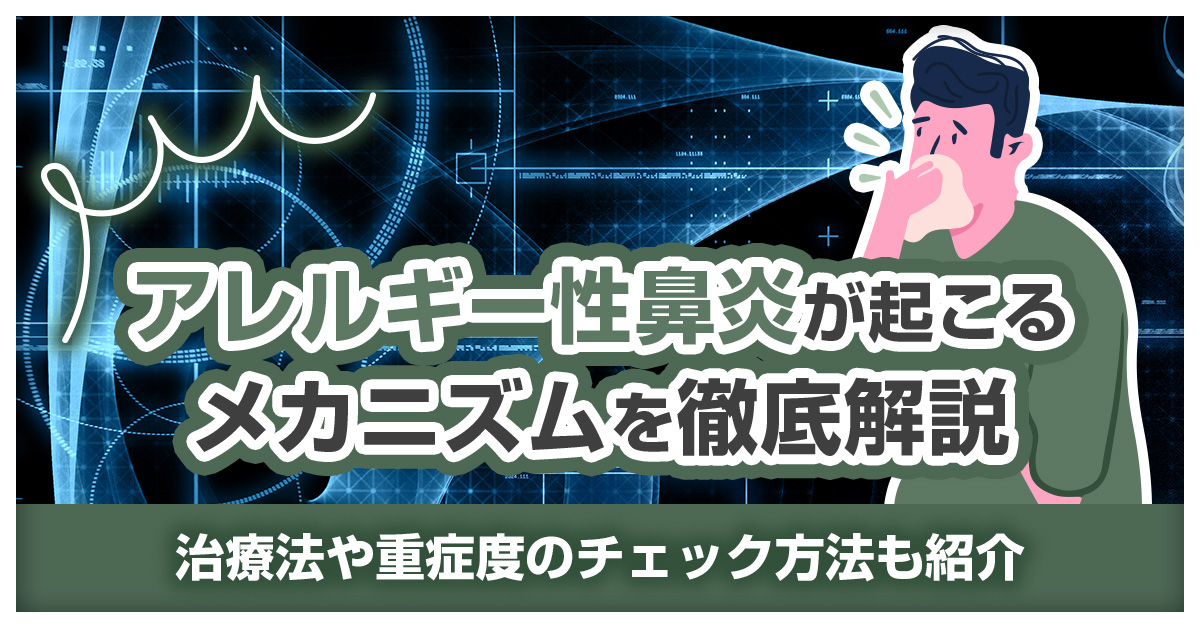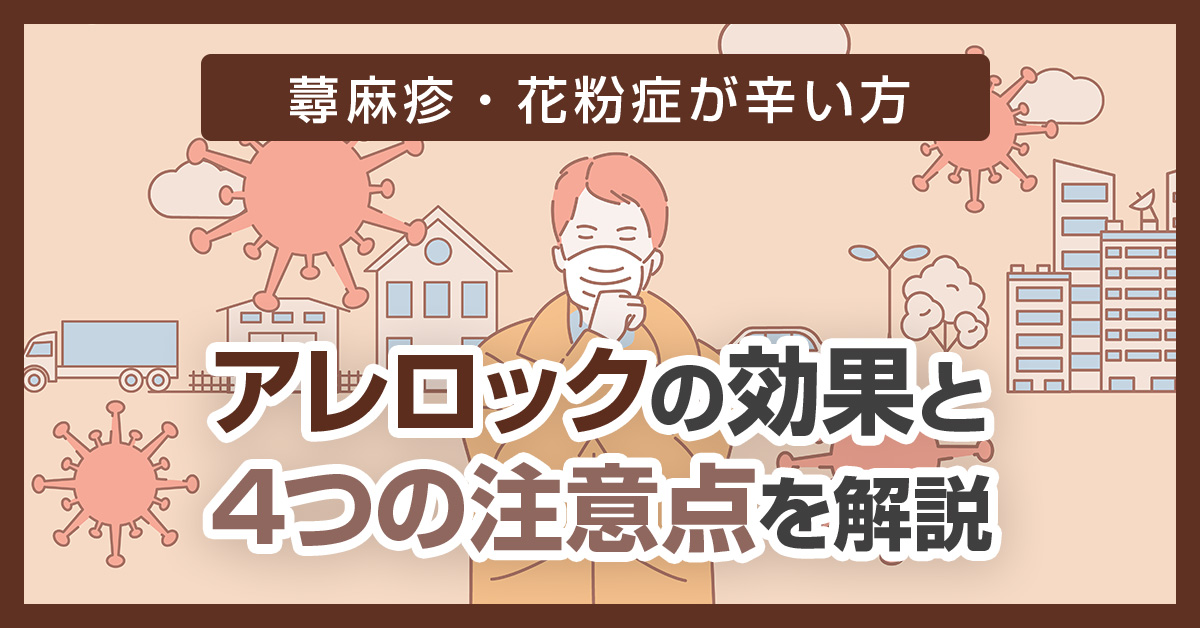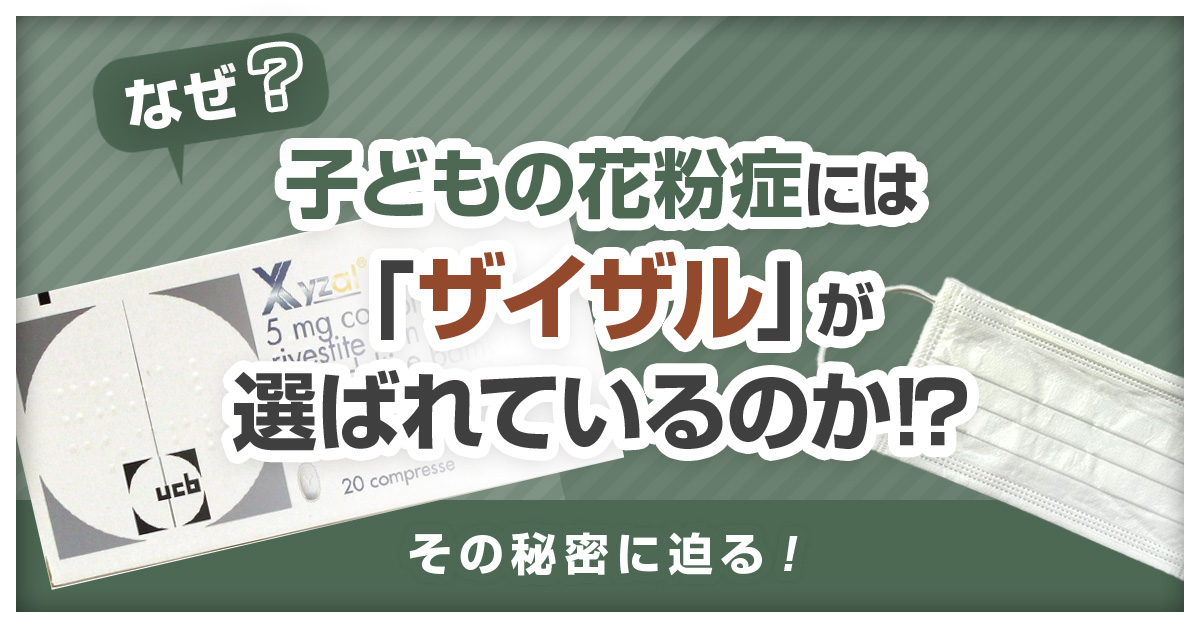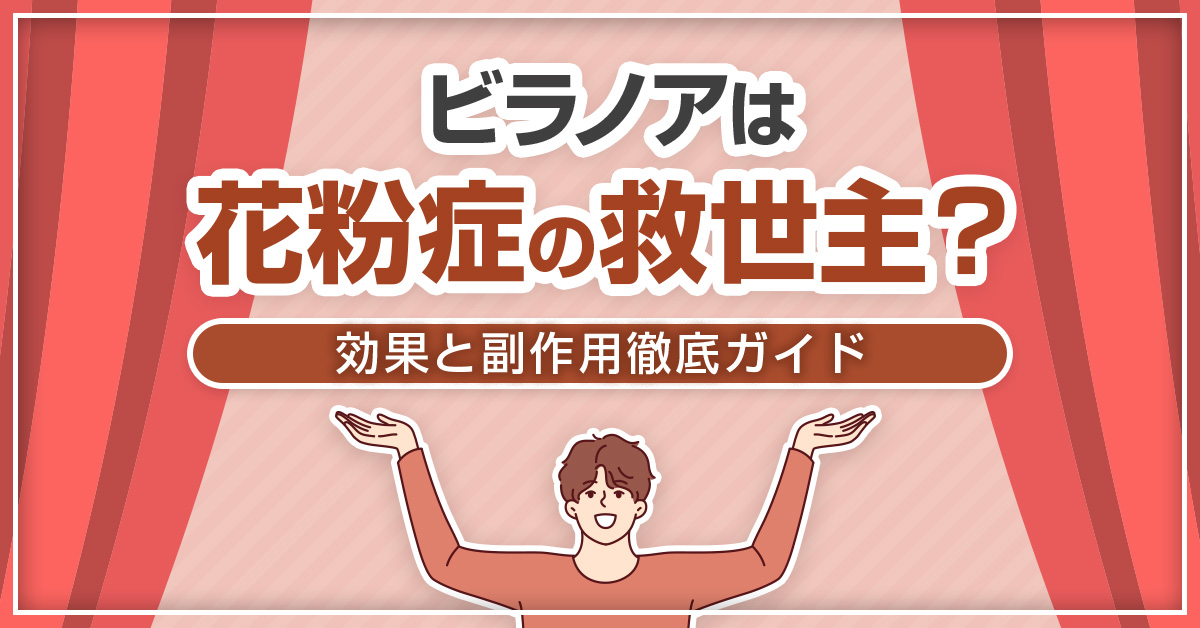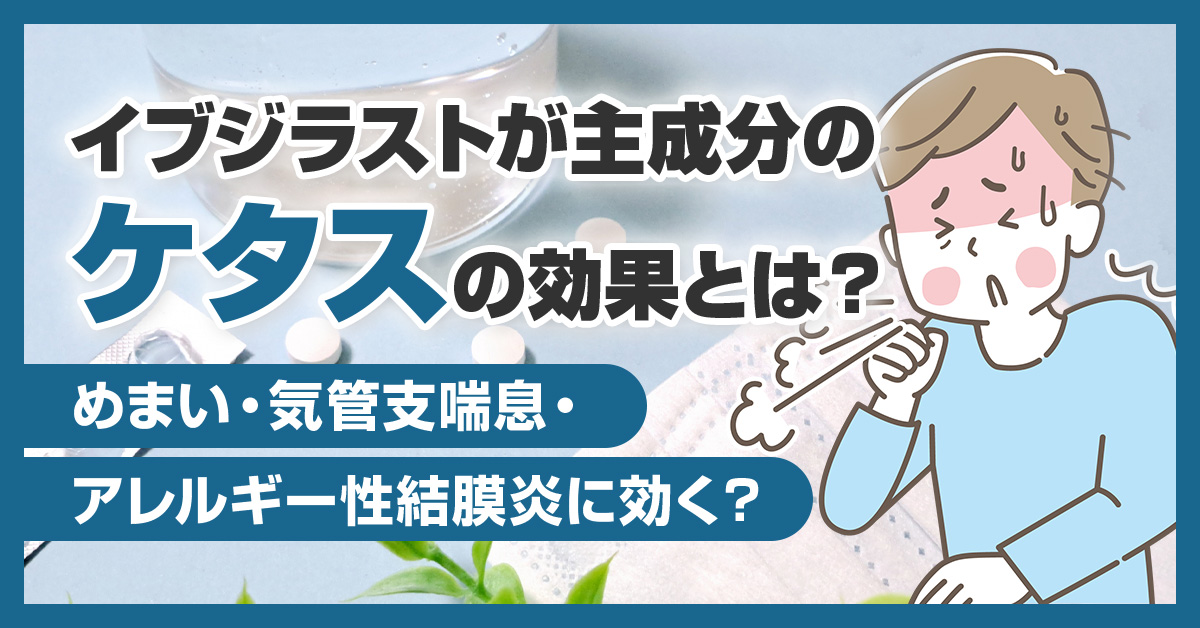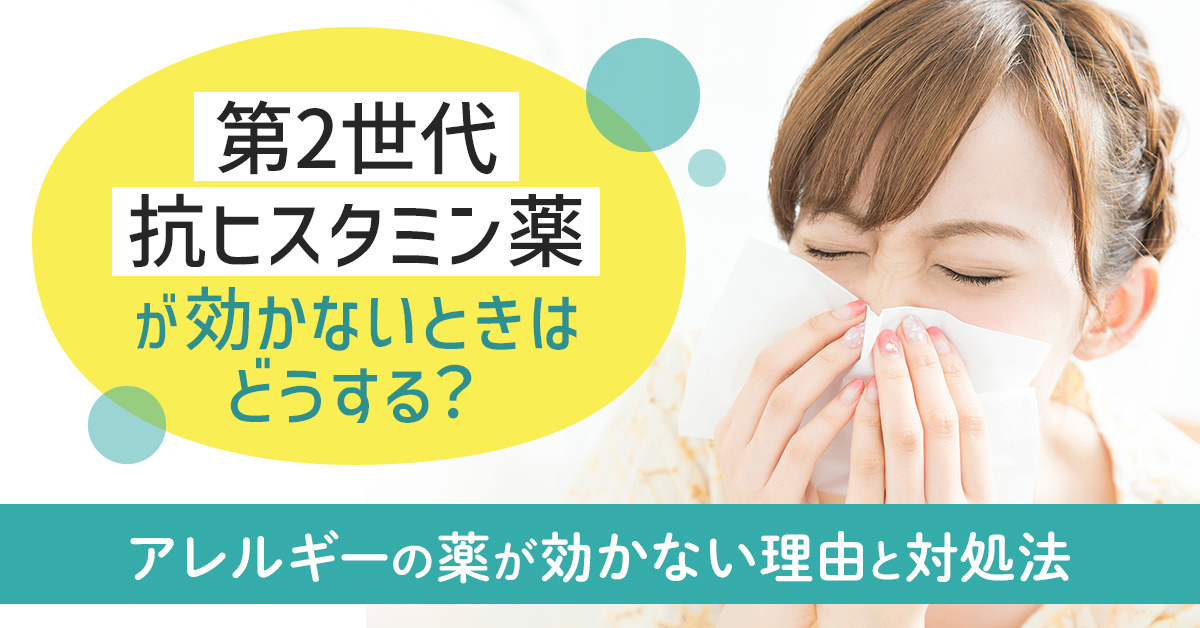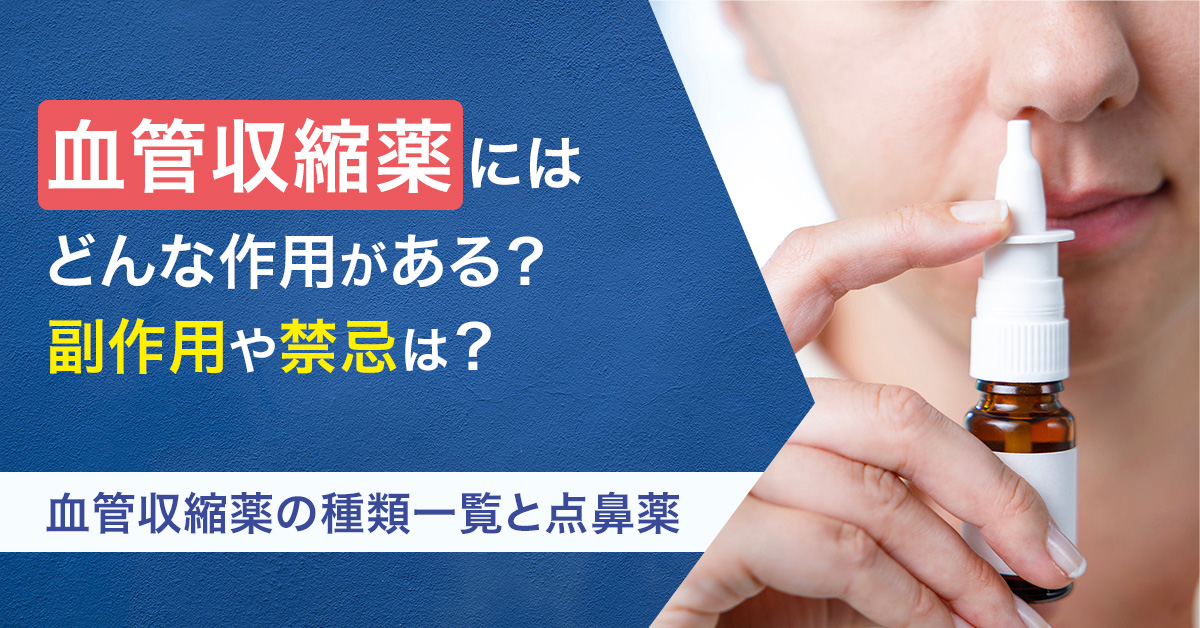「気管支喘息やCOPDってどんな病気?」
「気管支拡張薬にはどんな種類があるの?」
このような疑問を持っている人は少なくないのではないでしょうか。
本記事では、気管支拡張薬が効果を発揮する気管支喘息やCOPDについて徹底解説。
気管支拡張薬の3つの種類や、適切な吸入方法も紹介します。
本記事を読めば、気管支喘息・COPDや気管支拡張薬についてよくわかります。
興味がある人は、ぜひ最後までご覧ください。
気管支拡張薬は気管支喘息・COPDに対する治療薬
気管支拡張薬とは、気管支喘息やCOPD(慢性閉塞性肺疾患)に対して用いられている治療薬です。
一部は内服や注射により投与されますが、基本的には吸入により使用します。
気管支拡張薬を詳しく知るためには、治療対象となる疾患の気管支喘息やCOPDについて理解する必要があります。
それぞれについて見ていきましょう。
気管支喘息とは?
気管支喘息について以下の流れで解説していきます。
- 危険因子
- メカニズム
- 症状
それぞれ見ていきましょう。
気管支喘息の危険因子
気管支喘息の危険因子として以下が挙げられます。
| 個体因子 | 環境因子 |
|---|---|
|
・遺伝的要因 ・性別(小児は男児に多く、成人は女性に多い) ・肥満 ・出生時低体重 |
・アレルゲン(アレルギーの原因となる物質、ダニやカビなど) ・喫煙 ・呼吸器感染症 ・大気汚染 |
気管支喘息のメカニズム
気管支喘息の危険因子を起点として、気道の慢性的な炎症が発生します。
炎症を起こしているのは、免疫機能に関わる細胞の「好酸球」・「マスト細胞」・「T細胞」や、気道を構成している細胞の「上皮細胞」・「線維芽細胞」・「平滑筋細胞」などです。
これらの細胞は、「メディエーター」や「サイトカイン」と呼ばれる様々な物質を分泌します。
分泌された物質の作用により、気道は以下のように変化します。
- 気道を構成する筋肉の「気管支平滑筋」が収縮する
- 気道を覆う粘膜に浮腫が生じる
- 気道に分泌される粘液量が増える
- 気道の内腔を構成する細胞の「気道上皮細胞」が破壊・?離される
以上のうち、①~③の変化により可逆的な急性の気道狭窄が起こります。
また、④の変化により気道過敏性が亢進し、後述する発作のトリガーに反応しやすくなるのです。
メディエーターやサイトカインの分泌が慢性的に続くと、気道の変化はさらに進行し、以下のようになります。
- 気道上皮細胞の下で線維が増殖する
- 平滑筋が肥大する
以上の変化により気道の狭窄が進行します。
なお、①~③による急性の気道狭窄とは異なり、今回の気道狭窄は不可逆性です。
この不可逆的な気道狭窄は「リモデリング」と呼ばれています。
ここまでが、気管支喘息の慢性的な病態です。
ここに、以下のような発作のトリガーが加わることで、喘息発作が生じます。
- 呼吸器感染症
- アレルゲン
- 運動
- 過呼吸
- 気温や気圧の変化
- アルコール
- 薬物(NSAIDsやβ遮断薬)
- 喫煙
- 疲労やストレス
- 時間帯(夜間や明け方)
- 月経
以上が引き金となり、メディエーターやサイトカインの分泌が亢進し、急性の強い気道狭窄が発生するのです。
その結果、様々な症状が現れます。
気管支喘息の症状
喘息発作が起こった時の症状は、主に以下の通りです。
- 咳
- 喘鳴(息を吐く時に「ゼェー」「ヒュー」という音が聞こえる)
- 呼吸困難
これらの症状は、喘息発作が起こっていない時にはほとんどみられません。
ただし、症状がない時にも気道の慢性的な炎症は持続しています。
COPDとは?
COPDについても以下の流れで解説していきます。
- 危険因子
- メカニズム
- 症状
それぞれ見ていきましょう。
COPDの危険因子
COPDの危険因子として最も重要であるのがタバコの煙です。
COPD患者の約90%に喫煙歴があると報告されています。
その他、代表的な危険因子は以下の通りです。
- 大気汚染
- 受動喫煙
- 職業による粉塵や化学物質への継続的な暴露
COPDのメカニズム
タバコの煙をはじめとする有害物質が気道や肺に入ると、「好中球」・「マクロファージ」・「CD8陽性T細胞」などの免疫機能を司る細胞が集まります。
これらの細胞は、炎症を引き起こすサイトカインを分泌するとともに、「プロテアーゼ」や「オキシダント」という物質も産生します。
プロテアーゼやオキシダントの作用は、サイトカインによる炎症の増強と、直接的な組織障害です。
反復される炎症や組織障害により気道や肺が障害され、不可逆的な状態まで進行した状態がCOPDです。
以上のようにして気道の末梢部と、肺を構成する組織である「肺胞」が障害されます。
末梢気道の変化に関しては、気管支喘息における変化と類似しています。
そのため、ここからは肺胞の変化について見ていきましょう。
そもそも肺胞とは、肺に取り込んだ酸素と体内の二酸化炭素を交換するための組織です。
直径約0.3mmの小さな袋状の構造をしており、薄い膜からできています。
これらの肺胞が集まる(左右合わせて約7~8億個)ことで、私たちの呼吸が可能になっているのです。
そんな肺胞ですが、COPDにより障害を受けると肺胞の壁が破壊されてしまいます。
その結果、肺胞同士の融合が起こったり、肺胞が潰れてしまったりします。
肺胞壁の破壊がさらに進行すると、肺の過膨張や酸素と二酸化炭素の交換障害など、肺機能の低下が生じてしまうのです。
COPDの症状
COPDの症状として、代表的なものは以下の通りです。
- 労作時(運動時)呼吸困難
- 咳
- 痰
特に、労作時呼吸困難は最もよくみられる症状として知られています。
また、COPDが重症になると以下のような症状がみられるケースもあります。
- 口すぼめ呼吸(呼吸困難を緩和するため、無意識に口をすぼめて呼吸している)
- 体重減少
- チアノーゼ(血液中の酸素不足により皮膚が青っぽくなる)
気管支拡張薬には3種類ある
ここまで見てきたように、気管支喘息とCOPDでは気道に狭窄が生じます。
そこで、気道を広げるために用いられているのが、以下の3種類の気管支拡張薬です。
- β2刺激薬
- 抗コリン薬
- テオフィリン薬
これらの薬は、それぞれ作用するメカニズムや副作用が異なります。
それぞれについて見ていきましょう。
①β2刺激薬
一口にβ2刺激薬と言っても、有効成分や効果が異なるいくつかの種類があります。
これらのβ2刺激薬はほとんどが吸入薬であり、以下のいずれかに分類されます。
| 効果の持続時間 | 使用目的 | |
|---|---|---|
| 長時間作用性β2刺激薬 | 12時間以上 | 長期管理 |
| 短時間作用性β2刺激薬 | 5~15分間 | 発作時の治療 |
続いて、β2刺激薬が作用するメカニズムについてです。
β2刺激薬は、気道に分布している「β2アドレナリン受容体」という部位を刺激します。
刺激を受けたβ2アドレナリン受容体は、気管支平滑筋内の「cAMP」という物質の濃度を上昇させます。
そして、cAMPには気管支平滑筋を弛緩させる働きがあります。
このようなメカニズムで、β2刺激薬は気管支を拡張しているのです。
また、β2刺激薬の副作用としては以下が挙げられます。
- 動悸
- ふるえ
- 頭痛
- 高血糖
以上の副作用を踏まえ、高血圧や心疾患、甲状腺機能亢進症や糖尿病を抱えている場合は注意しなければなりません。
②抗コリン薬
β2刺激薬と同様に、抗コリン薬にも様々な種類があり、それらは長時間作用性抗コリン薬と短時間作用性抗コリン薬に分類されます。
使い分けもβ2刺激薬と同様であり、吸入薬として使用されています。
続いて、抗コリン薬が作用するメカニズムについてです。
抗コリン薬には、「アセチルコリン作動性ムスカリン受容体(M3)」という部位を阻害する働きがあります。
この阻害の働きにより、「アセチルコリン」という物質の作用が抑えられます。
そして、アセチルコリンの働きの一つに気管支の収縮があります。
この働きが抑制されるため、抗コリン薬には気管支を拡張する効果があるのです。
また、抗コリン薬の副作用としては以下が挙げられます。
- 口渇
- 眼圧上昇
- 排尿困難
- 動悸
- 頭痛
- 悪心
- 便秘
以上の副作用を踏まえ、症状のある前立腺肥大症や閉塞隅角緑内障という疾患を持っている人には使えません。
③テオフィリン薬
主に吸入薬として使われているβ2刺激薬や抗コリン薬と異なり、テオフィリン薬は静注薬(注射)や内服薬として使われています。
具体的な使用法は以下の通りです。
| 薬剤名 | 投与方法 | 用途 |
|---|---|---|
| アミノフィリン | 静注薬 | 発作時の治療 |
| テオフィリン | 内服薬 | 長期管理 |
続いて、テオフィリン薬が作用するメカニズムについてです。
テオフィリン薬には、「PDE(ホスホジエステラーゼ)」という物質を阻害する働きがあります。
PDEの主な働きは、β2刺激薬のメカニズムを説明する際にも登場した、cAMPの分解です。
つまり、PDEを阻害するとcAMPの濃度が上昇するため、気管支平滑筋が弛緩します。
このようなメカニズムで、テオフィリン薬は気管支を拡張しているのです。
また、テオフィリン薬の副作用としては以下が挙げられます。
- 不整脈/心停止
- 悪心/嘔吐
- 心窩部痛(みぞおちの痛み)
- 興奮
- けいれん
致命的な副作用である心停止を可能な限り防ぐために、血中濃度を測定しながら使用します。
気管支拡張薬の吸入方法
気管支拡張作用を持つ吸入薬は、気管支喘息やCOPDに対して高い効果を発揮しますが、使い方が難しい薬剤でもあります。
上手く吸入できていないと、十分な治療効果を得られません。
気管支拡張薬の適切な吸入方法は以下の通りです。
- 「カチッ」という音がするまで、吸入器のカバーをしっかり開ける
- カウンターの数字が1減ったことを確認する
- 一度息を吐き出す(吸入口には吹きかけないように)
- 吸入口全体をしっかりとくわえて深く吸い込む
- 吸入口から口を離し、少なくとも3秒以上息を止める(その後は通常通り呼吸)
- 吸入器のカバーを忘れずに閉じる
- うがいをして喉や口の中に残った薬剤を洗い流す
使用時のポイントは、吸入した後にしっかりと息を止める点です。
息止めにより、薬剤を気管支全体に届けることができます。
最後のうがいも忘れてはいけません。
気管支拡張薬の吸入薬では、炎症を抑制する効果を持つ吸入ステロイド薬も併用しているケースがほとんどです。
もし薬剤が喉や口の中に残っていると、吸入ステロイド薬の副作用により、口内炎ができたり声がかすれたりする可能性があります。
まとめ:気管支拡張薬で気管支喘息・COPDを治療しよう
気管支喘息やCOPDでは、慢性的な炎症により気道が狭窄します。
その結果、咳や喘鳴、痰や呼吸困難といった症状が起こります。
気管支喘息やCOPDに対して、高い効果を発揮するのが気管支拡張薬です。
気管支拡張薬には、β2刺激薬・抗コリン薬・テオフィリン薬があり、その多くが吸入薬として用いられています。
気管支拡張薬の適切な吸入方法を覚えて、気管支喘息やCOPDを治療しましょう。