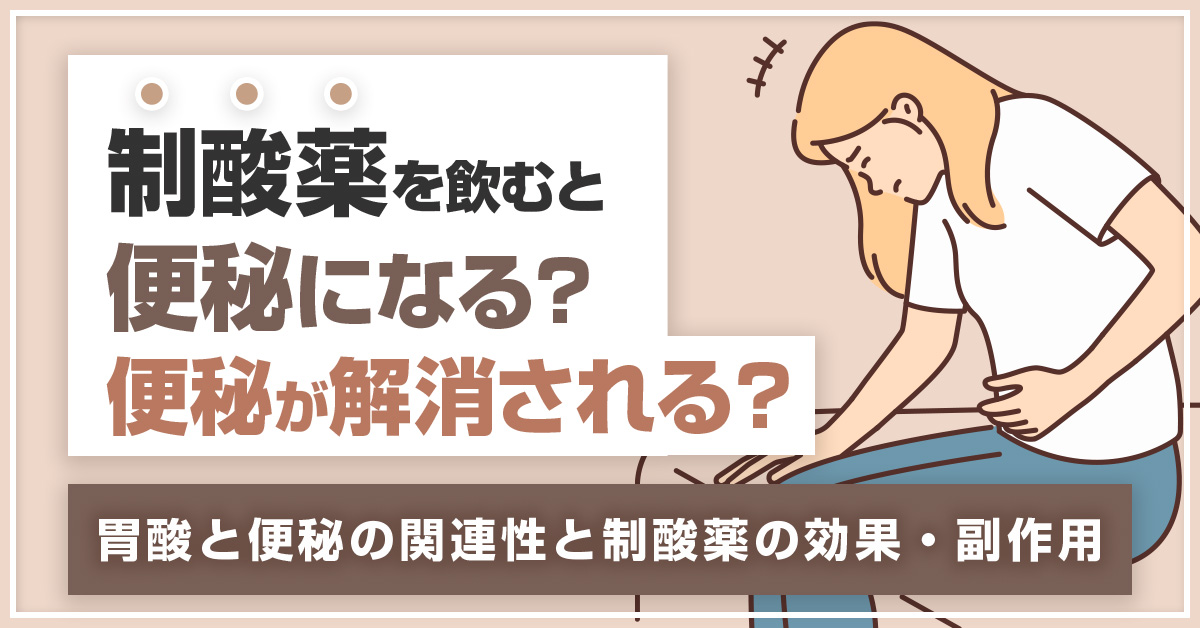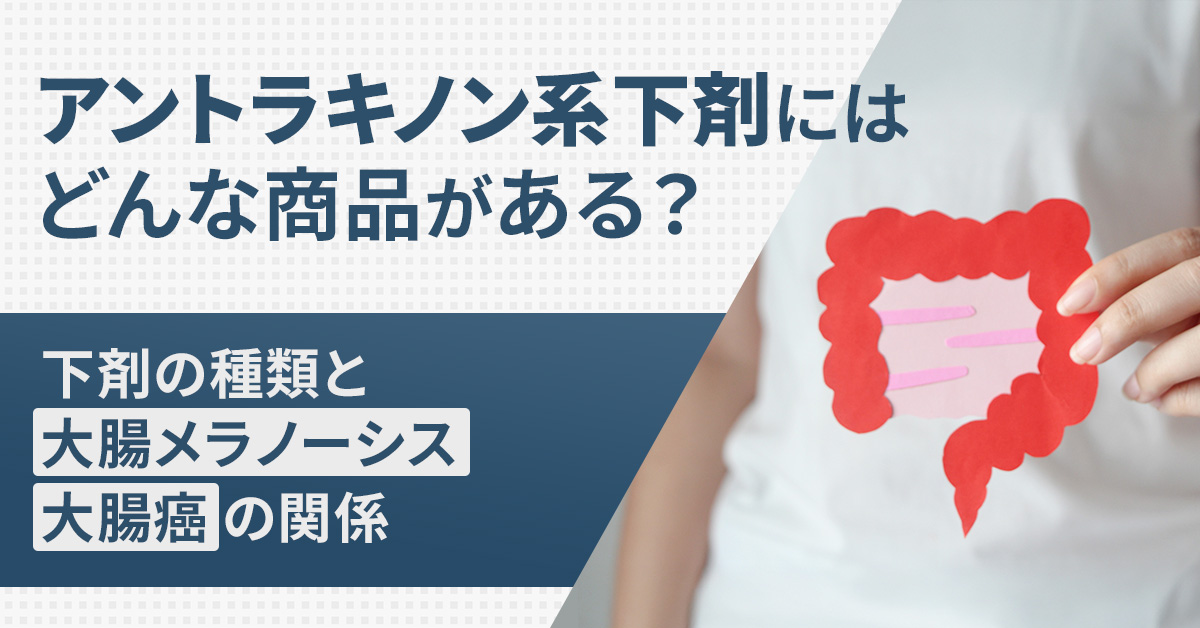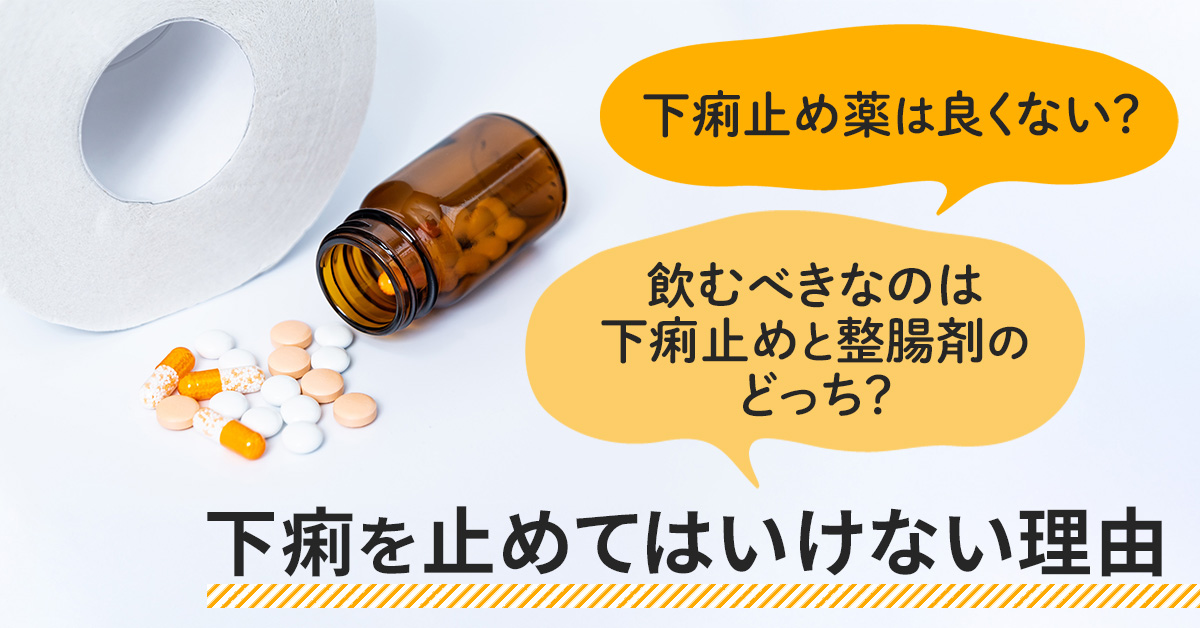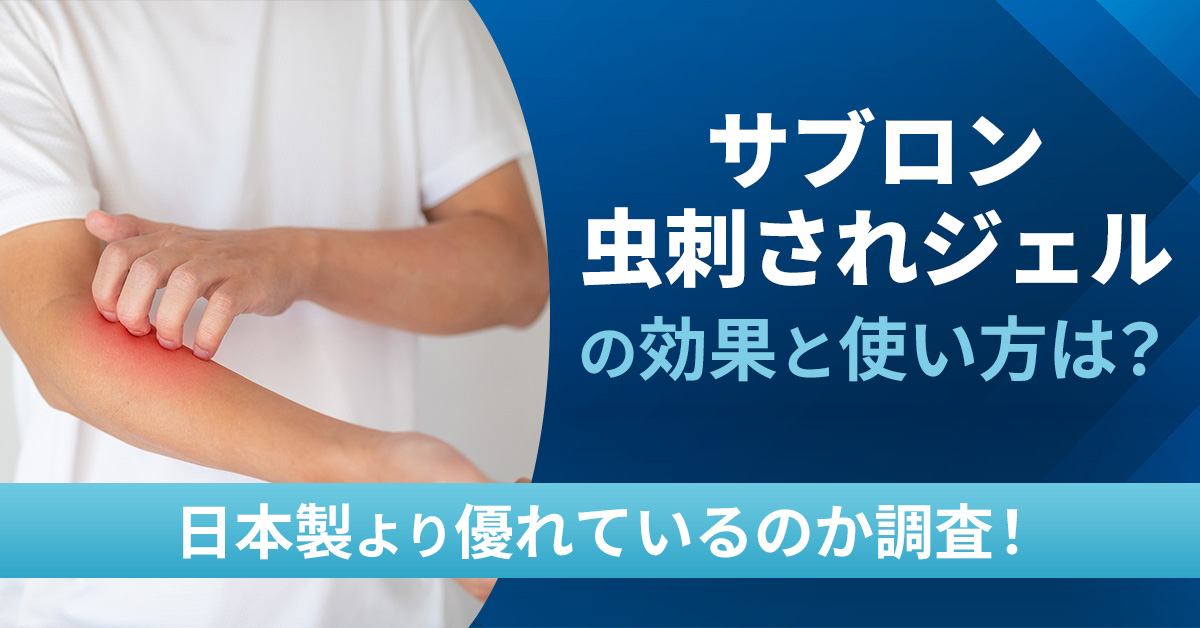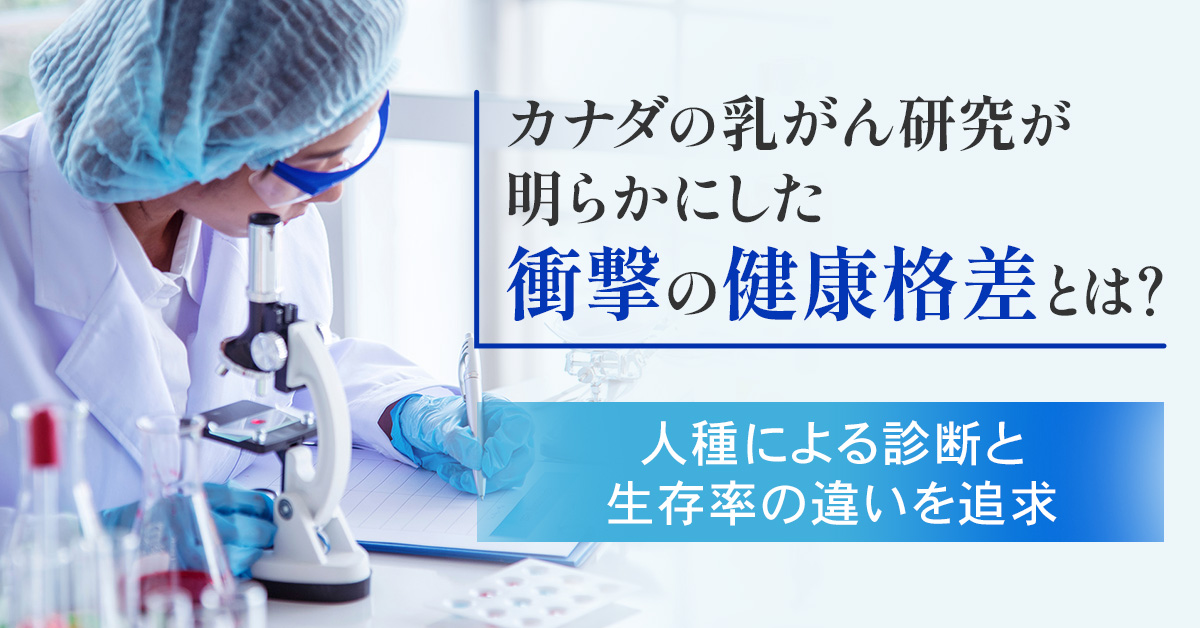食べ過ぎ飲み過ぎなどの不摂生やストレス、加齢などが原因となり、胸焼けや胃炎を発症した時に使われる薬剤の1つに制酸薬があります。
制酸薬には排便を促す作用があるものがある一方で、副作用に便秘の報告がある薬剤もあり、どれを飲むべきか悩まれている方も多いのかもしれません。
今回は制酸薬と便秘の関連性にフォーカスしながら、様々な制酸薬の種類と効果について解説していきます。
胃の不調と便秘でお困りの方はぜひ参考にしてください。
制酸薬とは
胃の内側は胃粘膜で覆われており、胃酸などから保護するために表面は胃粘液をまとっています。
しかしながら、食べ過ぎやストレスなどで胃酸が過剰分泌されると胃粘液だけでは胃を守ることが難しくなり、胃酸が胃粘膜の組織を傷つけてしまいます。
このような時に胃を守る役割で使用されるのが制酸薬です。
制酸薬の効果
制酸薬は胃液を中和して胃粘膜を守る作用があり、消化性潰瘍や胃炎などの治療に使われる薬です。
制酸薬には水酸化アルミニウムや酸化マグネシウム、炭酸カルシウムが主成分として配合されており、その成分に含まれるアルミニウムやマグネシウム、カルシウムなどが酸性の胃酸を中和して胃を保護します。
制酸薬の副作用と飲み合わせ
制酸薬の副作用として便秘や下痢などの胃腸症状が報告されており、長期間服用を続けると成分が臓器に溜まってしまう可能性も示唆されています。
さらに制酸薬を長期間服用し、胃液の分泌を抑制すると消化に必要な胃液が足りなくなり、消化不良や吸収障害などを引き起こすことがあります。
特にビタミンB12、カルシウム、マグネシウムの欠乏に注意してください。
また、キノロン系抗菌薬やテトラサイクリン系抗菌薬との併用は、抗菌薬の効果が弱まってしまう恐れがあるため、併用の必要がある場合には服用時間の間隔を空けるなど調整する必要があります。
制酸薬と便秘の関連性
制酸薬には便秘を引き起こす副作用があるとお話しましたが、実は反対に便秘解消を促す効果を持つ薬もあります。
ここでは制酸薬と便秘の関連性について解説していきます。
便秘とは
口から食べた食事は胃で消化された後に小腸で水分と栄養の90%が吸収され、残った食べ物のカスは大腸へと送られます。
大腸でも水分をさらに吸収しながら、蠕動運動で肛門へと食べ物カスを運び、最後に大便となって排出します。
この時、何らかの原因で大便が腸の中で留まり、排出されなくなってしまっている状態を便秘と言います。
便秘には、腸で炎症が起きたり、ポリープなどができたりする病気で腸管内が狭くなることで起きる器質性便秘と、腸の動きが鈍くなったり機能が衰えたりすることで起きる機能性便秘の2種類があります。
制酸薬と便秘
制酸薬には胃酸を抑える作用がある他、マグミットなどの制酸薬に配合された酸化マグネシウムには腸内の水分を集める作用があり、便を柔らかくして便秘を改善して排便を促す効果があります。
酸化マグネシウムによる作用は腸管を刺激する下剤と比較しても、癖になりにくく、腹痛も起きにくいという点はメリットです。
ただし、副作用として便秘を引き起こす制酸薬もある上に、長期連用をすると身体に悪影響を与えてしまう可能性もあるので注意が必要です。
制酸薬の種類と効果・副作用一覧
制酸薬には便秘を改善する効果があるものや、反対に副作用として便秘を引き起こす恐れのあるものがあります。
ここでは主な制酸薬の種類と、その効果・副作用について紹介していきます。
乾燥水酸化アルミニウムゲル
乾燥水酸化アルミニウムゲルが主成分の制酸薬は過剰分泌された胃酸を中和して胃粘膜への刺激を抑え、胸焼けや胃のむかつきを改善する効果があり、胃炎や胃潰瘍の治療に使用されています。
乾燥水酸化アルミニウムゲルが配合された制酸薬は、処方薬以外にも薬局やドラッグストアで購入することができる市販薬として「マリジンAグリーン」が販売されています。
乾燥水酸化アルミニウムゲルの制酸薬の主な副作用は便秘や吐き気などの胃腸症状に加え、アルミニウムが体内に蓄積することで起きるアルミニウム脳症やアルミニウム骨症などを引き起こす恐れがあるので、長期服用や過剰摂取は避けるようにしましょう。
また、透析を受けている方は使用禁止、妊娠中の方も相対禁止となっており、腎障害がある方やリン酸塩欠乏症の方、授乳中の方、高齢者は注意して服用する必要があります。
クエン酸製剤やニューキノロン系抗菌薬を始めとする様々な薬剤で相互作用を引き起こす恐れもあるため、服用中の薬剤がある場合には医師または薬剤師に相談しましょう。
水酸化マグネシウム
水酸化マグネシウムが主成分の制酸薬には胃酸を中和して胃粘膜を保護する作用の他に、腸内の水分を集めて便を柔らかくして排便を促す作用があるのが特徴です。
そのため、胃炎や胃潰瘍の治療に加えて、便秘を改善する薬剤としても使用され、さらに尿路蓚酸カルシウム結石の発生を予防するために用いられることもあります。
水酸化マグネシウムが主成分の処方薬にはマグミット330などがあり、用法・用量が目的によって変わる点には注意してください。
例えば、制酸薬として使用する場合には、酸化マグネシウムの1日の投与量が0.5~1.0gになるように1日数回に分けて飲みます。
緩下剤として使用する場合には、酸化マグネシウムの1日の投与量が2gになるように食後3回に分けて飲むか、寝る前に1回だけ飲むようにします。
水酸化マグネシウムが配合された制酸薬には市販薬も多く、「パンシロンアクティブ55」や「ストマクールA細粒」などがあり、便通を促す整腸剤としては「太田胃散整腸薬デ・ルモア錠」「錠剤ミルマグLX」「コーラックファイバーplus」などが販売されています。
水酸化マグネシウムの主な副作用には下痢が報告されており、重大な副作用として高マグネシウム血症や意識障害、心停止などを引き起こす可能性があるため、妊娠中の方、授乳中の方、高齢者は慎重に服用してください。
また、テトラサイクリン系やニューキノロン系の抗菌薬の他、セレコキシブ、フェキソフェナジンなど多種多様な薬剤で飲み合わせに注意が必要とされています。
カルシウムを多く含む牛乳や乳製品、干しエビに加え、鉄分を多く含むひじきやあさりなどの食品も相互作用が起こりやすいため、服用中は避けるようにしましょう。
沈降炭酸カルシウム
沈降沈降炭酸カルシウムは胃酸を中和する制酸薬の役割と、体内にカルシウムを補うカルシウム製剤の役割を持つ薬剤です。
そのため、胃潰瘍や胃炎に加え、骨粗鬆症や高リン血症などを改善する効果があります。
沈降炭酸カルシウムは処方薬の他に市販薬も販売されており、水酸化マグネシウムも一緒に配合されている「パンシロンアクティブ55」や、加齢に伴う骨の衰えを防ぐ「コンドロアミノCa錠」などの商品を購入できます。
大きく2つの役割を持つ沈降炭酸カルシウムですが、代謝異常や高カルシウム血症、腎結石、尿路結石などの副作用が報告されているため、甲状腺機能低下症の方や副甲状腺機能亢進症の方の使用は禁止されています。
また、便秘を引き起こす可能性もあるため、注意が必要です。
便秘を解消する3つの方法
制酸薬には胃酸を抑えて胃腸の機能を整えたり、排便を促して便秘を改善したりする作用を持つ薬剤もありますが、成分が体内に蓄積して思いがけない副作用を引き起こす可能性があるため、薬剤の長期連用は避けなければなりません。
そのため、薬剤以外の方法も併用しながら、便秘解消を目指すことが大切になります。
ここでは制酸薬以外の便秘解消に役立つ3つの方法を紹介していきます。
どれも日常生活に取り入れやすいものばかりですので、ぜひ試してみてください。
腸に良い食品を摂る
消化・吸収・排泄する役割を持つ腸は、食べ物の影響を直接受ける臓器です。
便秘解消を助ける効果が期待できる食物繊維や乳酸菌、オリゴ糖などはできるだけ積極的に摂取するようにしましょう。
海藻類や根菜類、きのこ類などに多く含まれる食物繊維は水を含むとゲル状になるため便を柔らかくしたり、便のかさを増して腸の動きを良くしたりする働きがあります。
ヨーグルトや漬物、味噌などに含まれる乳酸菌は腸内を良好な環境に整える効果や、オリゴ糖は善玉菌のエサとなってさらに善玉菌を増やす効果があるとされています。
マッサージやストレッチをする
マッサージやストレッチは腸に刺激を与えて蠕動運動を促すため、便秘解消に効果が期待できると言われています。
腸内の便の動きに合わせ時計回りに「の」の字を書きながらお腹をさする「のの字マッサージ」や、わき腹を伸ばす「わかめストレッチ」などを生活に取り入れてみましょう。
また、合谷や神門という手のツボには便意を起こさせる作用があるとされているので、試してみてください。
十分な水分を摂る
便は硬くなることで排泄されにくくなって便秘を引き起こしてしまうため、身体に十分な水分を補給して潤しておくことが大切です。
1日で摂取する水分量の目安は2リットルとされていますが、一気に飲むのではなく、こまめに摂る方が良いと言われています。
起床後に白湯を飲んだり、食事に汁物を加えたりして、工夫しながら水分を摂取していきましょう。
制酸薬は成分によって便秘に対する作用が異なる
制酸薬は胃酸を中和して胃粘膜を保護する役割がある薬剤です。
制酸薬の主成分の1つである水酸化マグネシウムには胃酸を中和する作用に加えて、便を柔らかくして排便を促すため、便秘解消に効果があるとされています。
その一方で、成分によっては副作用で便秘を引き起こす恐れがある制酸薬もあるため、便秘で悩んでいる方は薬剤を注意して選びましょう。