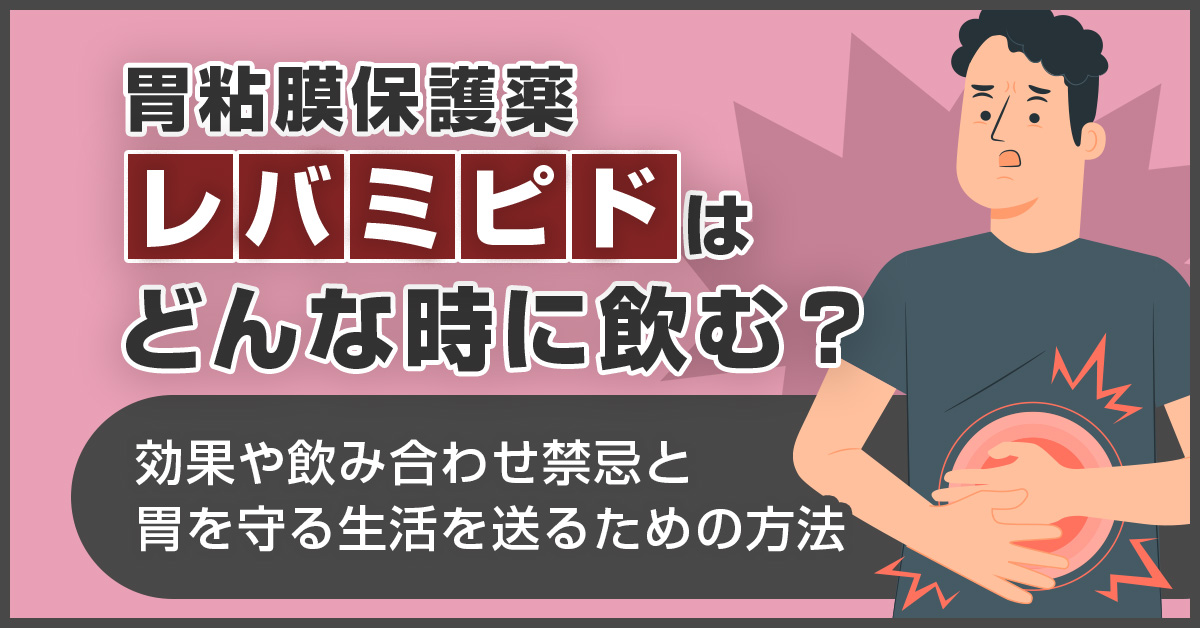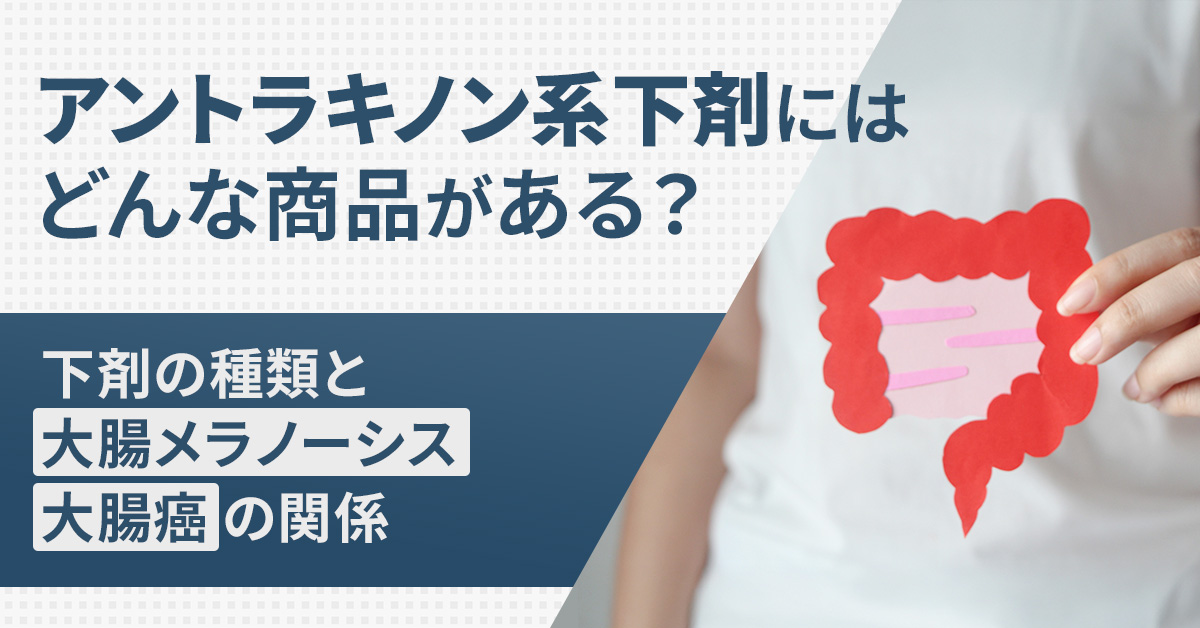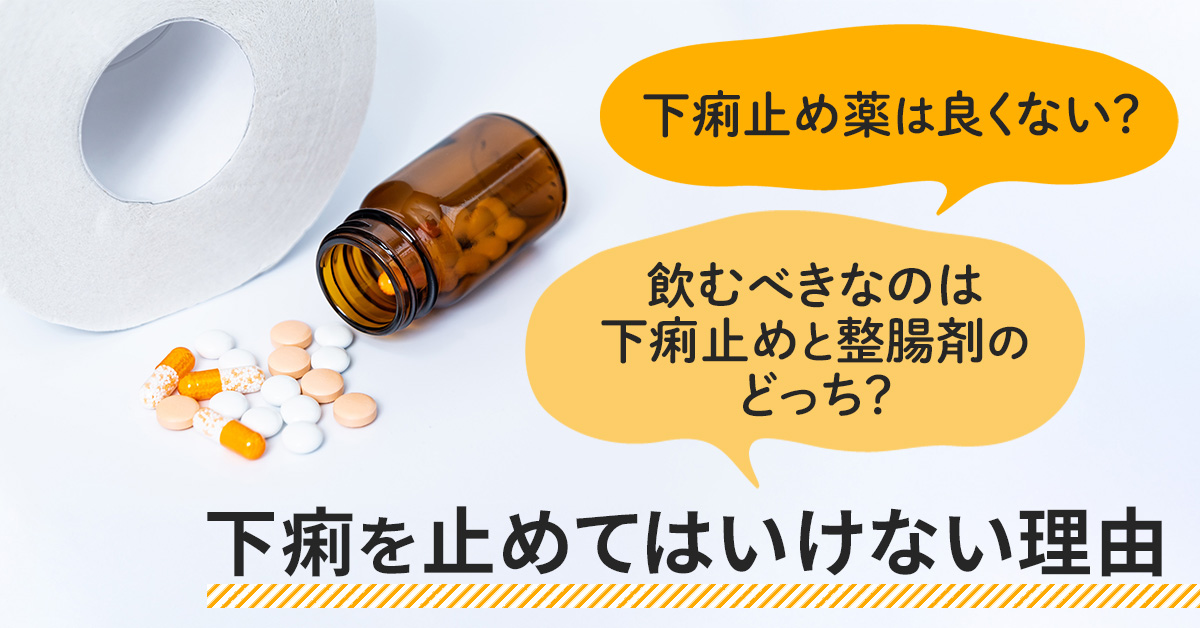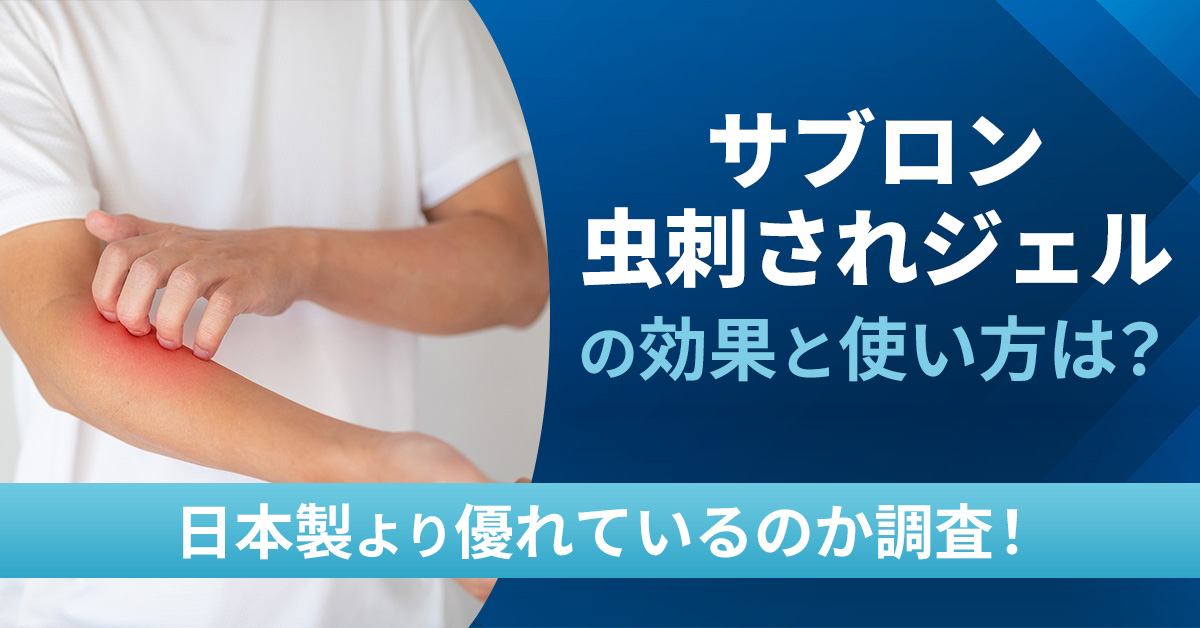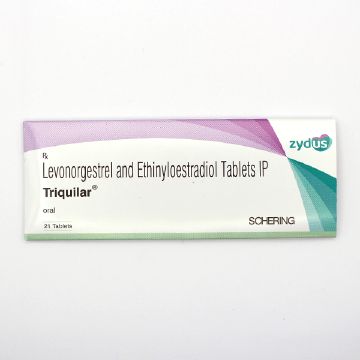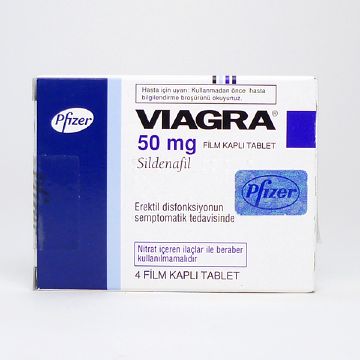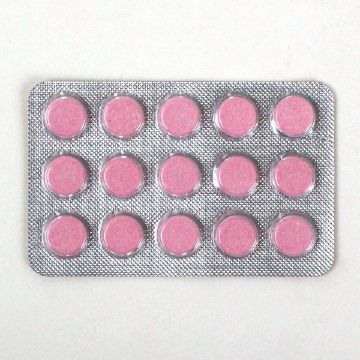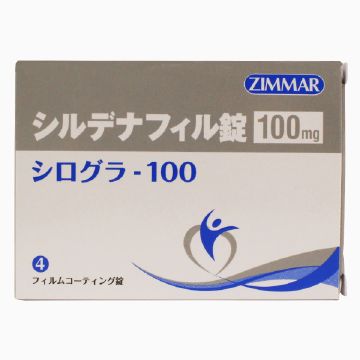食事の多様化が進んで飽食の時代となったことやストレス過多、病気の治療薬の影響により、胃に不快感を抱えている方は少なくないのかもしれません。
今回は胃腸薬の1つである胃粘膜保護薬の中のレバミピドに注目し、その効果や副作用、飲み合わせ禁忌について解説します。
さらにレバミピドを使用した処方薬や他の胃粘膜保護作用のある市販薬にも触れつつ、胃に優しい生活を送るためのポイントを紹介していきます。
胃粘膜保護薬レバミピドとは
胃の内側を覆っている粘膜層のことを胃粘膜といい、粘膜・粘膜上皮・粘膜筋板から構成され、食べ物を消化する胃液を分泌する働きや胃酸などから胃を守る胃粘液を分泌する働きがあります。
ゼリー状の胃粘液は通常0.5~2.5㎜の厚みがありますが、加齢とともに分泌量は少なく厚さは薄くなり、胃酸の影響を受けやすくなって胃粘膜が荒れてしまいます。
このような胃粘膜の荒れを修復したり、保護したりするための薬剤が胃粘膜保護薬レバミピドです。
ここではレバミピドの効果に加え、副作用や併用禁忌についてお話していきます。
レバミピドの効果
レバミピドはキノリン誘導体に分類される薬剤で、胃粘液の分泌を促す働きがある胃粘液膜内のプロスタグランジンEαを増やす作用があります。
胃粘液が増えることで胃酸からの影響を受けにくくなり、胃潰瘍や急性胃炎、慢性胃炎などで荒れてしまった胃粘膜を保護・修復する効果があります。
胃潰瘍は胃酸によって胃粘膜が消化されて胃壁が炎症を起こしてしまう病気で、強いストレスやピロリ菌への感染、胃に負担のかかる薬剤の長期服用が原因となって、胃粘液が薄くなったり胃酸が過剰になったりすることで発症します。
急性胃炎や慢性胃炎は、胃潰瘍ほど深い組織に炎症が起きてはいないものの、胃の粘膜に赤みやびらん、出血などが見られる状態を言います。
急性胃炎は細菌や食中毒などが原因となり急に痛みが現れるのに対して、慢性胃炎は長期間にわたって慢性的に胃のむかつきやもたれを感じるような状態のことです。
胃潰瘍、胃炎のどちらも胃粘膜に問題が起きているため、胃粘液の分泌を増加させて保護するレバミピドを使用して傷ついた組織を修復していきます。
ただし、胸焼けなどの原因が胃粘膜ではなく、逆流性食道炎などの別の病気が原因となっている場合はレバミピドでは症状はおさまりません。
「胸焼けや胃痛にレバミピドが効かない」と感じた時は別の原因があるかもしれないので、速やかに医療機関を受診しましょう。
レバミピドの副作用と禁忌
レバミピドは比較的安全性が高く副作用はほとんどないとされていますが、ごく稀にアナフィラキシーショックや血液障害、肝障害が起こる可能性があります。
息苦しさや発熱、黄疸などの症状が現れた時には、すぐに医療機関を受診してください。
また、レバミピドは胎児への移行や乳汁への移行が確認されているため、妊娠中や授乳中の方の使用については有用性が上回らない限りは避けることが望ましいです。
15歳未満の小児や高齢者も副作用が現れやすいため、使用の際には注意する必要があります。
他の薬剤との併用禁忌はなく、ロキソニンを始めとする鎮痛剤など胃を荒らす副作用がある薬剤と一緒に処方されるケースが多いです。
ただし、レバミピドと同じ胃粘膜保護作用がある薬剤は過剰投与となり、副作用のリスクが高まるので医師や薬剤師に相談してから使用しましょう。
レバミピドと飲み合わせに問題がある食品も特にないため、食事制限の必要はありません。
レバミピドの使用方法
レバミピドは通常、1日3回服用しますが、飲むタイミングが病気によって異なります。
胃潰瘍の場合は朝・夕・就寝前に、急性胃炎や慢性胃炎の場合は毎食後に服用し、ロキソニンなどの鎮痛剤やステロイド薬による胃への副作用を抑える目的で使用する時には併用する薬剤と同じタイミングで服用していきます。
レバミピドと他の胃粘膜保護薬
胃粘膜保護薬にはレバミピドが主成分となった薬剤の他にも、様々な種類のものが存在します。
ここではレバミピドとそれ以外の成分が配合された胃粘膜保護薬を解説します。
レバミピド
これまで解説してきたレバミピドが主成分となっている処方薬には、ムコスタ錠という胃粘膜保護薬があります。
以前はレバミピド錠やレバミピドOD錠という商品がありましたが販売を中止となりました。
副作用や他の薬剤との飲み合わせにも問題が少なく、使用しやすい薬剤の1つと言えますが、レバミピドが配合された市販薬の販売はなく、処方でしか手に入れることはできません。
そのため、胃粘膜保護薬を市販で購入したい時には他の成分の薬剤を選ぶ必要があります。
スクラルファート
スクラルファートも胃の粘膜を保護して胃潰瘍や胃炎を治療していく胃粘膜保護薬です。
胃液のペプシンを抑える作用もあるスクラルファートは、臨床試験の実績があり海外の評価も高くなっています。
スクラルファートも胃を保護する目的で解熱鎮痛剤と併用されますが、ニューキノロン系抗菌薬やテトラサイクリン系抗生物質、テオフィリンを始めとする様々な薬剤の効果を弱めてしまうため、注意が必要です。
また、腎臓障害があるとアルミニウム中毒を引き起こす可能性があるため、重い腎臓病の人や透析を受けている人の使用は避けた方がよいとされています。
クエン酸を含む食べ物も血中のアルミニウム濃度を上げやすいので、服用中はレモンやお酢、梅干しなどを控えてください。
スクラルファートが配合された処方薬にはアルサルミン顆粒やスクラルファート内用液などがあり、市販薬にはライオンが販売している「スクラ-ト胃腸薬」や佐藤製薬の「イノセアプラス錠」などがあります。
テプレノン
テプレノンもレバミピドやスクラルファートと同じ胃粘液の分泌を促す胃粘膜保護薬ですが、レバミピドが食事の影響を受けない一方、テプレノンは空腹時に服用すると効果が低くなることがあるため、食後に服用するという特徴を持ちます。
テプレノンも胃を荒らす副作用がある解熱鎮痛剤などと一緒に処方されることが多く、安全性が高いと言われている薬剤ですが、ごく稀に肝機能障害や血小板減少などの副作用を引き起こす恐れがあるため、だるくなったり黄疸が見られたりした時にはすぐに医療機関を受診してください。
また、妊娠中の方の服用は禁止とされ、授乳中の方や15歳未満の子ども、高齢者は注意して服用していく必要があります。
テプレノンが配合された処方薬にはテプレノン顆粒やテプレノンカプセル、セルベックス顆粒、セルベックスカプセルなどがあり、市販薬としてはエーザイの「セルベール」などが薬局やドラッグストアで販売されています。
メチルメチオニンスルホニウムクロリド
メチルメチオニンスルホニウムクロリドも胃粘膜保護薬の1つで、胃潰瘍や胃炎の治療、解熱鎮痛剤から胃を保護する目的で処方される薬剤です。
代表的な製品には興和の「キャベジンコーワ」の市販薬があり、薬局やドラッグストアで購入することも可能です。
副作用には便秘や下痢などの胃腸症状や過敏症、発疹などがありますが、安全性が高いため過度な心配は要らないと言えるでしょう。
ただし、妊婦は相対禁止とされ、授乳婦や15歳未満の子どもや高齢者の使用には注意が必要とされています。
胃を守る生活を送るためのポイント
ここまで、レバミピドを始めとする胃粘膜保護薬について解説してきましたが、胃を健康に保つ方法は生活の中にも多くのヒントが隠されています。
ここからは、できるだけ胃に負担をかけないためのポイントを4つ紹介していきます。
ストレスを避ける
胃とストレスの関係は密接と言われており、心配事があったりストレスを受けたりすると胃痛が起きることがあります。
これは内臓の運動を司る自律神経の交感神経と副交感神経のバランスが崩れることが原因と考えられています。
通常、ストレスがかかると交感神経が優位になって胃酸や胃液の分泌が減少する一方で、副交感神経が働くと胃酸と胃液の分泌が増加します。
ストレスを受けることによって、この調節機能がバランスを崩し、胃粘膜を傷つけて胃痛などを起こしてしまうのです。
このような理由からも、できるだけストレス状態を避け、心身ともに健やかな状態を保つことが胃を守ることに繋がると言えます。
大量のアルコールや刺激物は控える
アルコールはリラックス効果があり副交感神経を優位にさせるため、胃酸の分泌を促します。
さらにアルコール分子はとても小さいため、胃粘液をすり抜けて直接胃粘膜に影響を及ぼしてしまいます。
適量のアルコールであれば、それほど問題にはなりませんが、アルコールを大量に摂取し続けることは胃を刺激し続けることに繋がるため、注意する必要があります。
また、香辛料が多く含まれる食事やカフェインなども胃へ悪影響を及ぼすので、ほどほどに楽しむ程度を心掛けましょう。
禁煙する
喫煙をすると血行不良を起こして胃の機能や抵抗力を低下させ、さらに胃粘膜を修復する物質を減少させてしまいます。
喫煙者は非喫煙者よりも胃潰瘍や十二指腸潰瘍にかかりやすいという調査報告もあり、タバコは百害あって一利なしです。
禁煙することは胃を守る生活を送るための第一歩と言えるでしょう。
胃粘膜保護薬のレバミピドで胃を守っていこう
胃の内側には粘液をまとった胃粘膜があり、胃酸から胃を守っています。
この胃粘液は加齢やストレスなどが原因で、分泌量が減ったり厚みが薄くなったりして、胃酸の影響を受けやすくなり、胃が荒れて胃潰瘍や胃腸炎などを引き起こします。
胃潰瘍や胃腸炎などには、胃粘液の保護や修復を促す作用のあるレバミピドなどの胃粘膜保護薬を使用して治療していきます。
レバミピドは処方薬でしか手に入りませんが、他の成分が配合された胃粘膜保護薬であれば、市販でも購入することが可能です。
また、ストレスやアルコール、タバコなどの刺激物で胃は荒れてしまうため、できるだけこれらの要因も避けて胃に優しい生活を心掛けていきましょう。