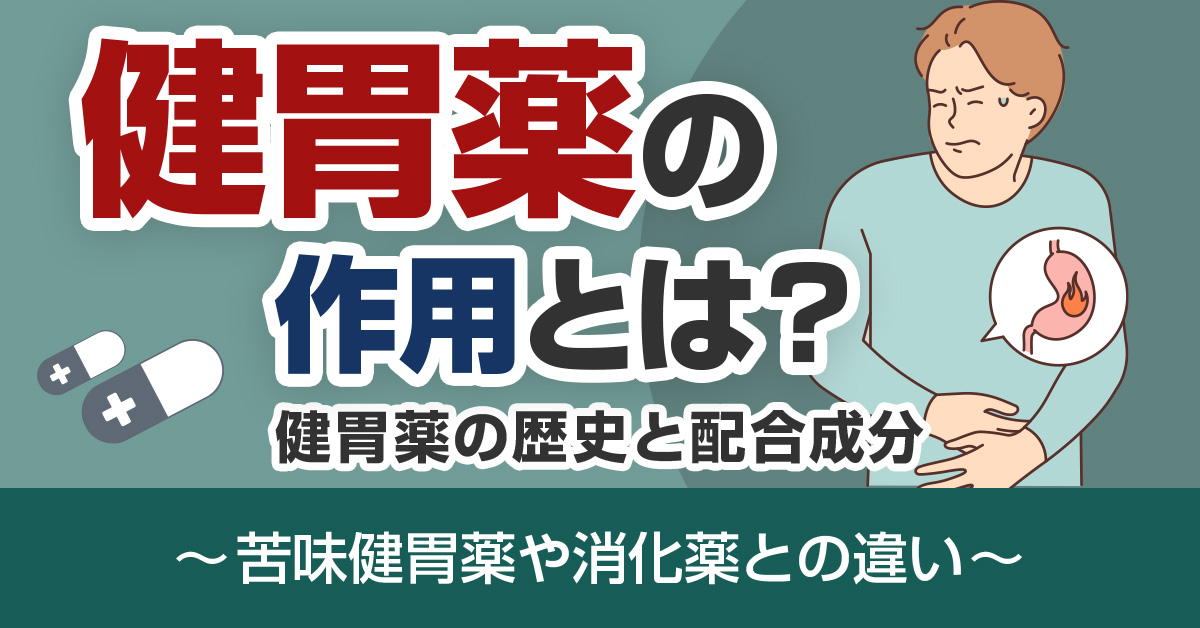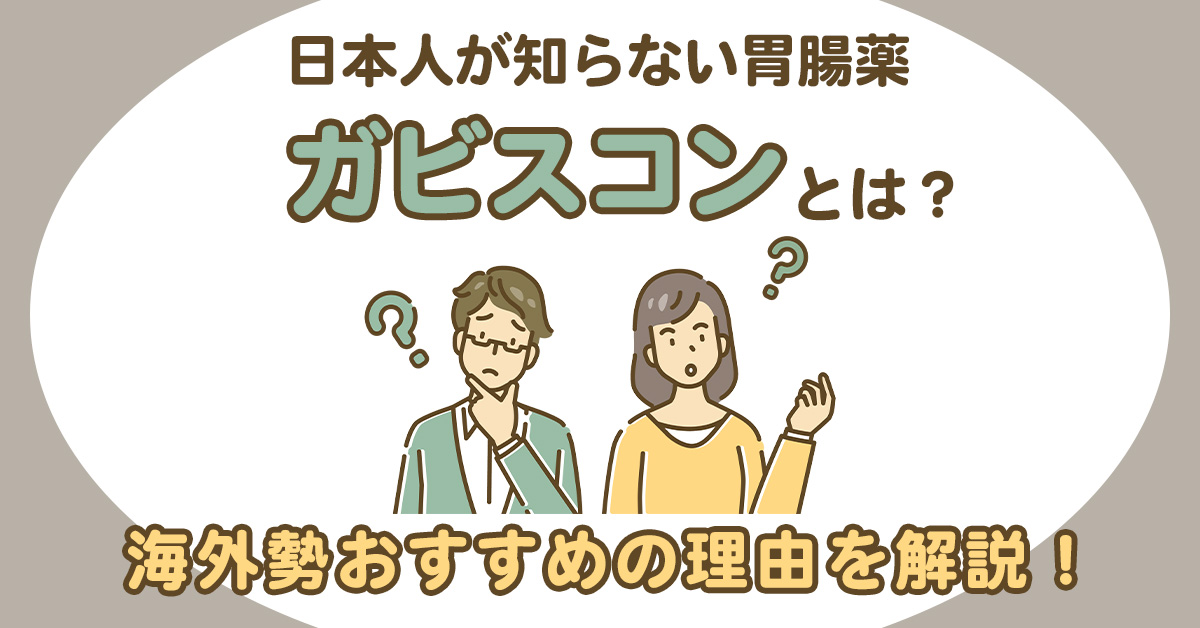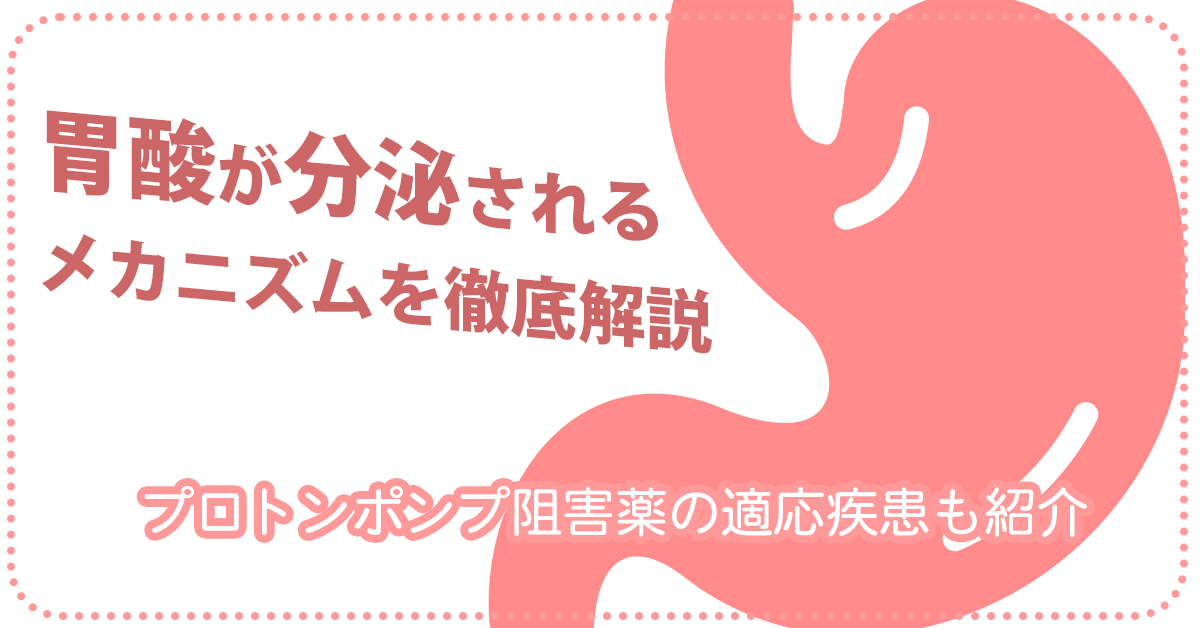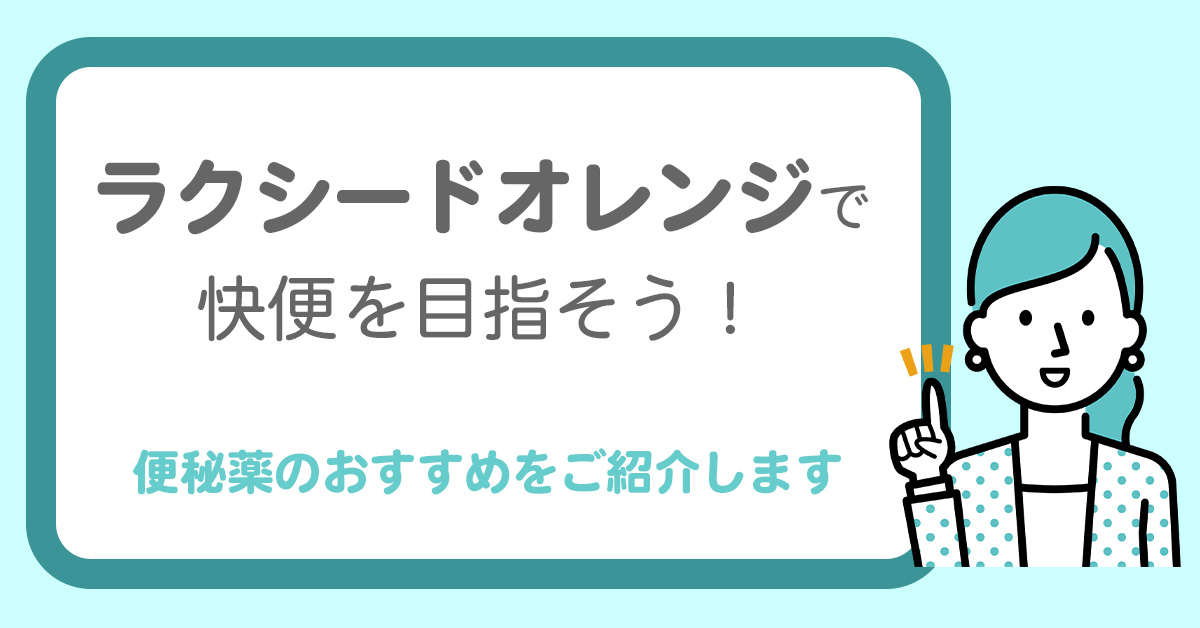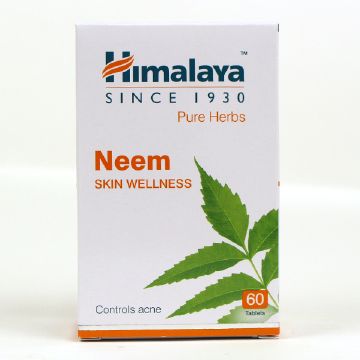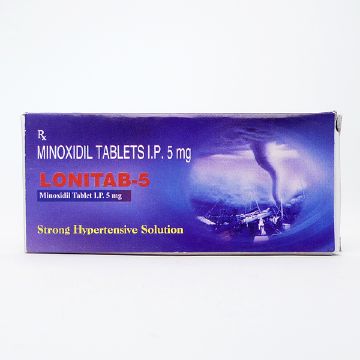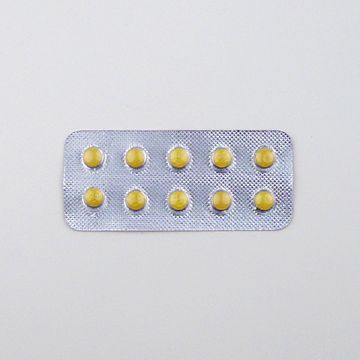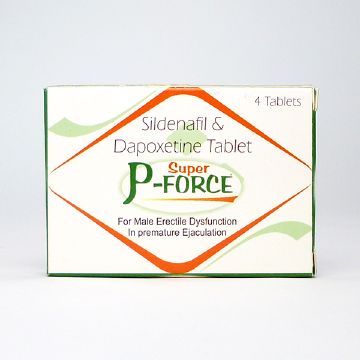常備薬として家庭に置いてあることの多い胃腸薬ですが、種類によって作用が異なることはご存知でしょうか。
同じ胃腸薬に分類されている薬剤であっても作用が真逆となるものもあるため、症状に合った薬を正しく選択することが大切になります。
今回は胃腸薬の中でも「健胃薬」に分類される薬剤にフォーカスし、その作用や歴史を紐解いていきます。
また、同じような名前の苦味健胃薬や消化薬などとの違いについても解説していきます。
健胃薬(けんいやく)とは
胃の働きが悪くなると胃酸の逆流や胃の保護作用の低下が起こり、胸焼けや消化不良、胃もたれなどの症状が現れます。
このような症状に対して、健胃薬は胃の運動・分泌・消化などの機能を促進し、胃もたれや二日酔いなどの不快な症状を緩和してくれます。
健胃薬は胃腸機能成分以外にも生薬や酵母など多種多様な成分が使用されており、その歴史は古くまでさかのぼります。
健胃薬の歴史
健胃薬の元祖は諸説ありますが、赤玉の愛称で知られる赤玉神教丸は350年前の江戸時代の頃に販売された薬剤であると言われています。
腹痛、食傷、下痢止めの妙薬として有名だった赤玉神教丸は胡椒・胡黄蓮・苦参・楊梅皮に寒晒米の溶汁や木胡桃油を調合して製造した薬剤とされ、食欲不振や胃部・腹部膨満感、消化不良などを緩和する効果が期待できるとされています。
その後、明治維新を経て欧米文化が導入されるようになると医学の研究が進み、様々な薬剤が開発されていきます。
そんな中、胃痛によく効く薬剤として販売が始まったのが、現在でも多くの人が耳にしたことがあるであろう太田胃散という名の健胃薬です。
太田胃散はオランダ人の名医であるボードウィン博士が緒方拙斉医師へ伝えたイギリスの処方薬で、肉食を主体とするヨーロッパ人が日常的に使用するスパイスが薬剤に含まれているのが特徴的でした。
時は流れ、太平洋戦争が終結して高度経済成長期からバブル期へ向かう頃、日本人の食生活は大きく変化していきます。
家庭の食卓に肉を中心とする洋食が並び、社会人の間では頻繁に飲み会が行われるようになったことで、胃腸症状を訴える人々が増え、製薬会社はそれぞれの症状に合った薬剤を開発・販売するようになりました。
そして現在、健胃薬はまだまだ人々に必要とされ続け、様々な新商品が販売されているのです。
健胃薬の効能や副作用
健胃薬に配合されている成分ごとに作用機序は異なりますが、基本的には働きが弱まった胃に起きる胸焼けや不快感、胃もたれなどの症状に対し、胃粘膜を保護したり、胃の働きを促進させたりする効果が期待されています。
似ている薬剤として挙げられる消化薬は胃の消化を助ける酵素を補って消化不良を改善する薬剤として健胃薬とは違う薬剤に分類されていますが、健胃薬にこの消化薬が配合された総合健胃薬も販売されています。
健胃薬の副作用は便秘などの消化器症状や、長期投与により腎結石や尿路結石が現れる可能性もあります。
また、キノロン系抗菌薬やテトラサイクリン系抗菌薬と併用すると、抗菌薬の作用が弱くなる恐れがあるので注意してください。
健胃薬の成分
健胃薬には、生薬、酵母、胃腸機能調整成分などを使用した様々な製品が販売されており、さらに生薬が使われている健胃薬は苦味健胃薬(くみけんいやく)と芳香性健胃薬の大きく2つに分類されています。
ここでは健胃薬に配合されている成分について紹介していきます。
苦味健胃薬
苦味健胃薬は苦味によって胃の機能促進作用がある生薬で、独自の香りで胃の機能を促進させる芳香性健胃薬と分類されています。
オウレン、センブリ、オウバクが苦味健胃薬に分類され、どれも強い苦味があるのが特徴です。
オウレン
オウレンはキンポウゲ科オウレンの根茎を用いた生薬で、健胃・消炎作用、精神安定などの作用があるとされています。
苦味が非常に強く、舐めると舌に黄色がついてしまうという特徴があります。
センブリ
リンドウ科センブリは秋の開花期に草を採取して素早く乾燥させた生薬で、食欲不振や胃のむかつきなどの胃腸症状を改善する効果が期待できます。
センブリは千回振り出してもまだ苦いと言われるほど苦味が強く、その苦味が強ければ強いほど品質が良いとされています。
オウバク
オウバクはミカン科のキハダという落葉樹の樹皮の内側部分を使用した生薬です。
健胃や消炎などの作用があると言われ、健胃薬の他に打撲などの外用薬に配合されることもあります。
オウバクも苦味が強く、舐めるとオウレンと同様に舌が黄色くなってしまいます。
芳香性健胃薬
芳香性健胃薬は生薬独自の香りで胃の機能を促進させる作用がある生薬です。
芳香性健胃薬の生薬にはスパイスやハーブとして日常的に使われているものも多く、ハッカやサンショウ、ウコンなどがあります。
苦味健胃薬も芳香性健胃薬もその苦味や香りの刺激が効果に直結しているため、オブラートや服薬ゼリーなどで包んでしまうと効果が弱まってしまう可能性があるため注意しましょう。
ハッカ
ハッカはシソ科の植物でスーッとした清涼感のある香りが特徴的な生薬です。
駆風・発散・清涼・興奮などの作用があり、健胃薬の他には感冒・皮膚疾患を改善する漢方薬に配合されています。
ハッカは3500年前の古代ギリシャの時代から利用されてきた歴史があり、日本でも古くから人々に役立てられてきました。
新潟県や北海道などが産地となっていることからも、私たち日本人にとって身近な生薬の1つであると言えるでしょう。
サンショウ
ミカン科サンショウの木の成熟した果皮が生薬に使用されるサンショウです。
サンショウは独自の香りがあり、口に入れると舌が痺れるような辛さがあります。
冷えによる腹痛や膨満感を改善する作用があるとされ、健胃薬や苦味チンキなどに配合されています。
ウコン
ウコンはショウガ科の植物の根茎で、中でも秋ウコンと呼ばれる種類が生薬として利用されています。
ウコンには健胃作用の他に、血行促進や痛み止めの作用があることから、月経痛や打撲などに使用されることもあります。
別名ターメリックとも呼ばれるウコンは、カレーに欠かせないスパイスの1つでもあります。
酵母
胃腸の働きに重要となる栄養素を含んでいる酵母も健胃薬の成分に使用されています。
例えば、ビール酵母には40種類の栄養素が含まれ、胃もたれや消化不良などの症状を緩和する効果が期待できます。
また、酵母は人間の小腸に住みついて消化吸収に加え、内分泌系や自律神経系、免疫の機能を良い状態に保つ働きもあります。
これら善玉菌と呼ばれる身体に良い働きをする菌が増えることは、腸内環境を正常に保つことに繋がると言えます。
胃腸機能調整成分
健胃薬には、他の医薬品のように生薬や酵母以外の胃腸機能成分も使用されています。
健胃薬に使用されることの多い胃腸機能調整成分には塩化カルニチンやトリメブチンマレイン酸塩などがあります。
塩化カルニチンは胃の働きに関与している副交感神経を刺激して、胃の働きを促進させる効果が、トリメブチンマレイン酸塩は自律神経を整えて胃が正常に働けるように調節する作用があります。
健胃薬以外の胃腸薬の種類
これまで健胃薬の効能や成分について触れてきましたが、健胃薬以外にも様々種類の胃腸薬があります。
胃腸薬と一口に言っても、胃の運動を活発にする働きがある薬剤と胃の運動を抑制する薬剤があるため、使い方を間違えるとかえって症状が悪化する恐れもあるので注意が必要です。
ここでは代表的な胃腸薬の種類について簡単に紹介していきます。
| 種類 | 効能 |
|---|---|
| 健胃薬 | 食欲不振や胸焼けの時に胃液の分泌を増やして胃の運動を促進させる |
| 消化薬 | 消化不良の時に消化を助ける |
| H2ブロッカー | 胃酸の出過ぎが原因となる胸焼けや胃痛の時に余分な胃酸の分泌を抑える |
| 制酸剤 | 胃酸の出過ぎによる胸焼けや胃痛の時に胃酸を中和して症状を緩和する |
| 整腸剤 | 腸内フローラのバランスを整えて腸の水分量や運動性を正しく保つ |
| 便秘薬 | 腸内の水分量を増やしたり腸を刺激したりして便の排泄を促し、便秘を改善する |
このように胃腸薬には様々な種類があり、市販の胃腸薬はこれら薬剤を複数配合した総合胃腸薬として販売されているものも多くあります。
医療機関に行く時間が取れない時には市販の胃腸薬を利用するのも1つの手段と言えるでしょう。
また、お薬ネットでは市販薬よりも高い効果が期待できる海外の薬剤を通販で購入することが可能です。
お薬ネットの通販では、逆流性食道炎や胃潰瘍、十二指腸潰瘍を治療するアストラゼネカ社から販売されているネキシウムを購入できます。
お忙しい方や外出が難しい方はぜひご利用ください。
胃もたれや消化不良には健胃薬を
胃腸の働きが悪くなって起こる胃もたれや消化不良には、胃腸の働きを促進する健胃薬を使います。
日本国内では江戸時代頃から健胃薬が使われるようになり、高度経済成長期からバブル期頃の食文化の欧米化や飲み会の増加などによって、様々な製品が開発されてきました。
健胃薬には胃腸機能成分の他、酵母や生薬など多種多様な成分が配合されているのが特徴です。
また、生薬には苦味や香りの成分で症状を緩和する苦味健胃薬や芳香性健胃薬などがあり、これら生薬の中にはハーブやスパイスとして使われている身近なものもあります。
健胃薬以外にも消化薬やH2ブロッカーなど様々な胃腸薬が存在し、胃腸の働きを促進させるものもあれば、逆に抑制するものもあります。
このことからも胃腸薬を一括りに考えず、効能をよく確認して症状に合ったものを選ぶことが大切と言えるでしょう。