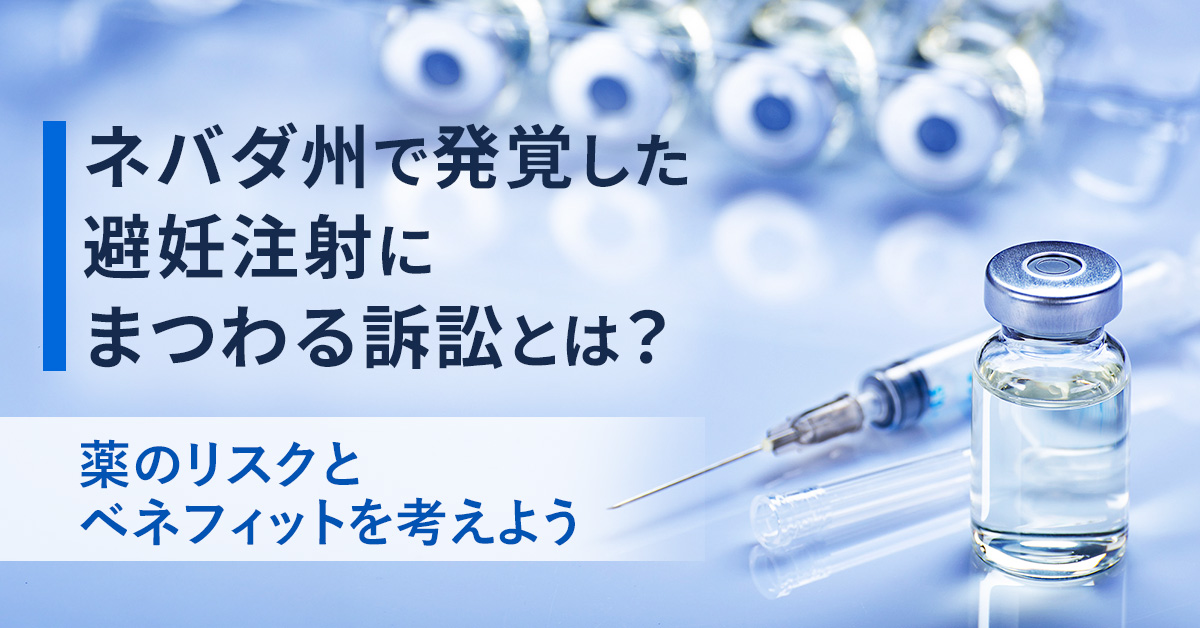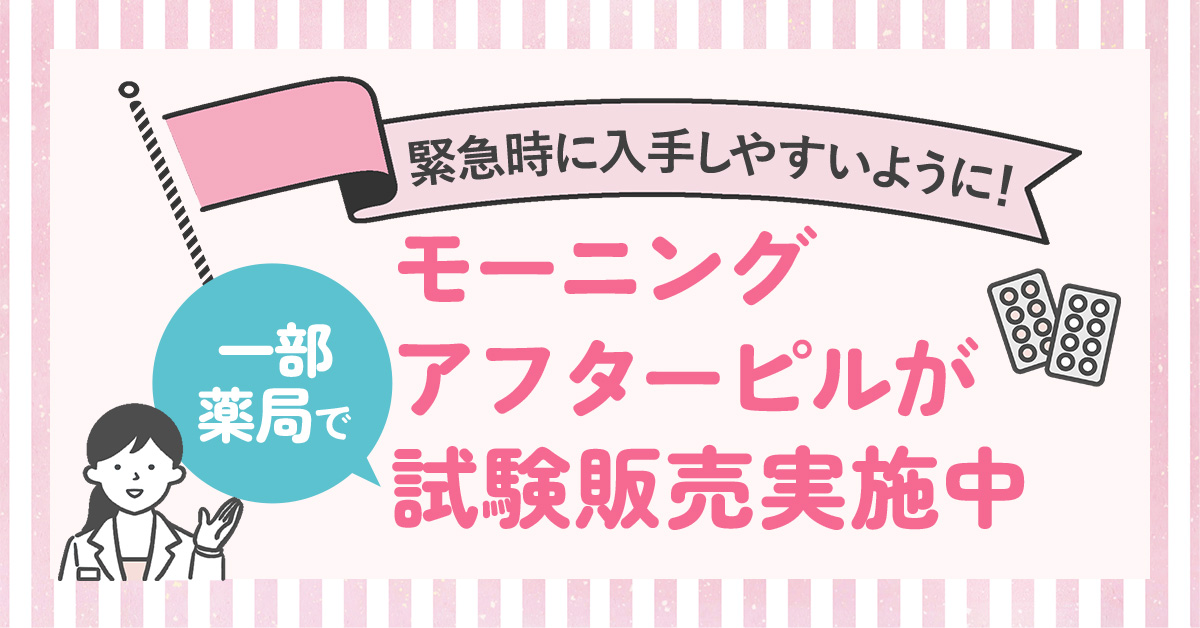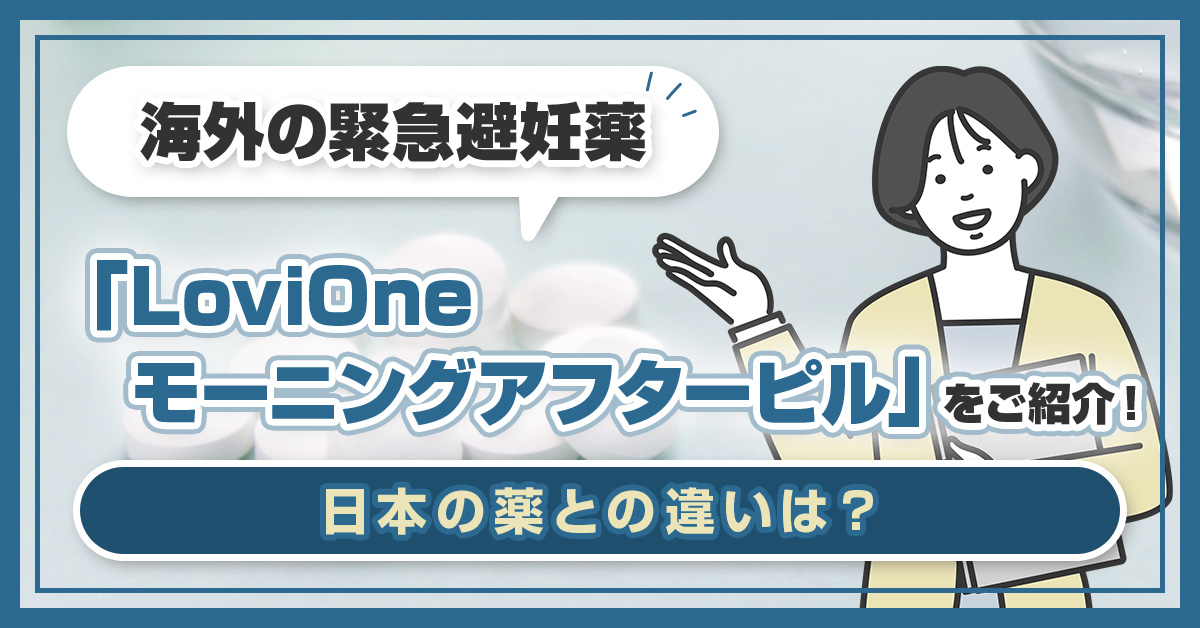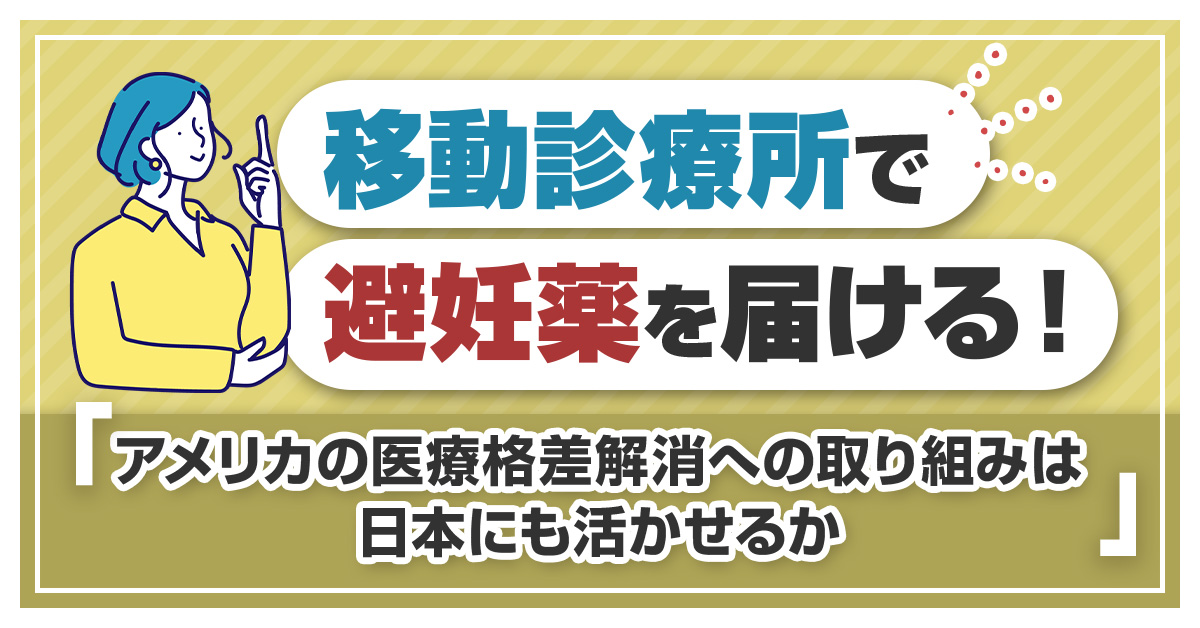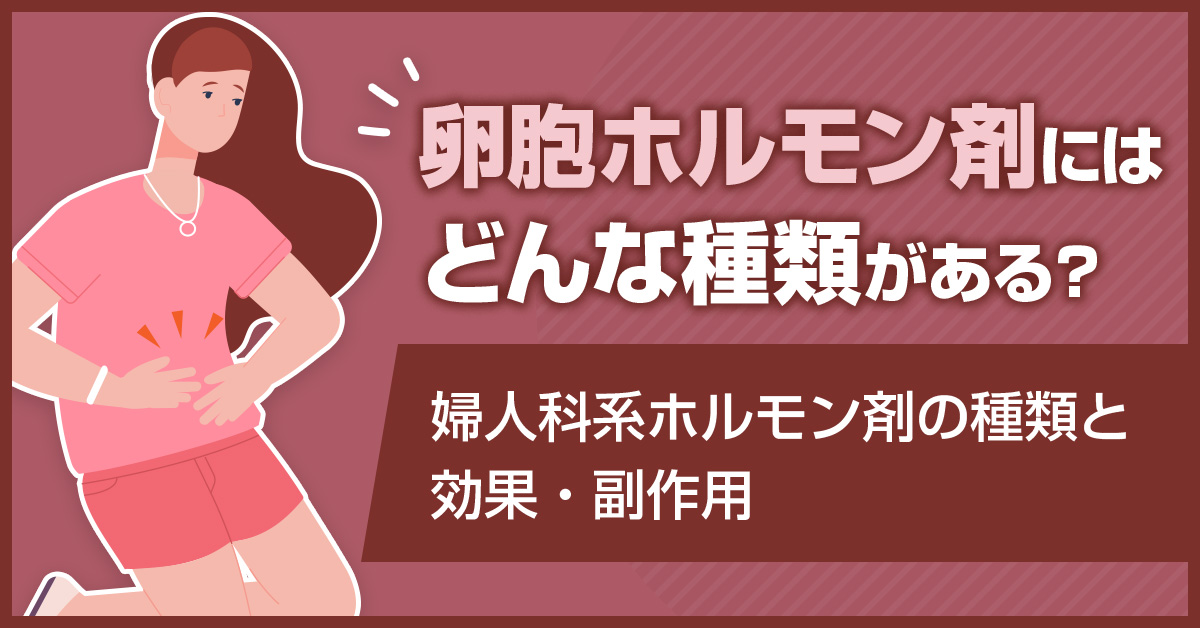黄体ホルモン薬を飲むとどうなる?効果・副作用や低用量ピルとの違いを知ろう
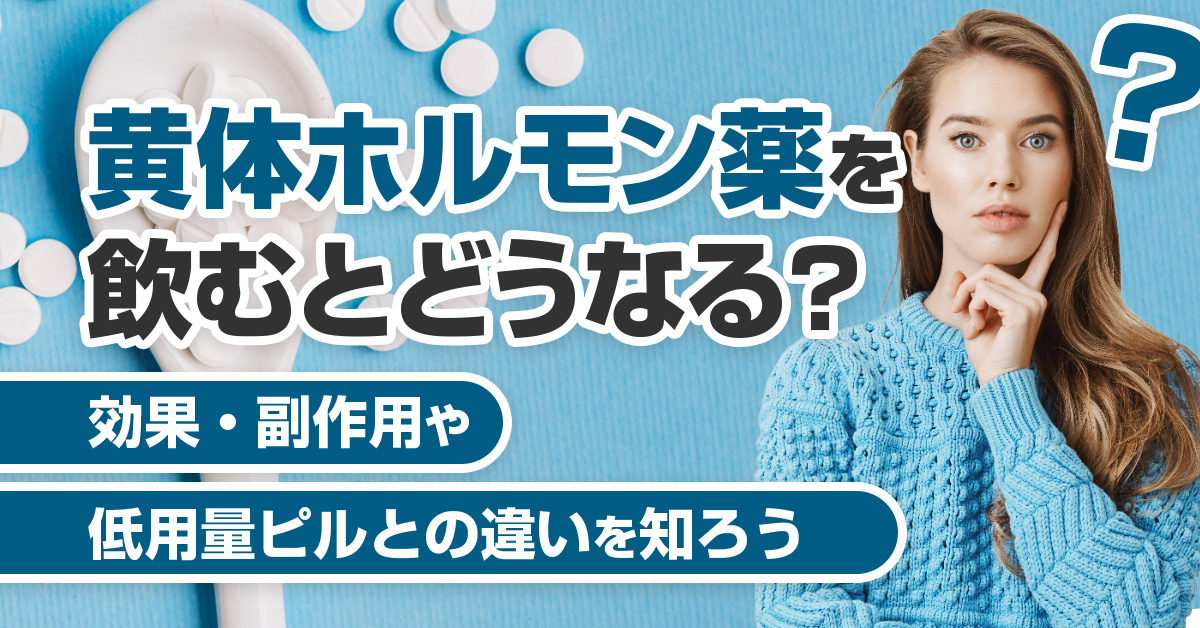
身体の機能を調整する役割を持つホルモンの中でも、生理や妊娠に大きく関わるのが女性ホルモンの一種である黄体ホルモンです。
今回はこの黄体ホルモンが不足した時に補充する目的を持つ黄体ホルモン薬について解説していきます。
黄体ホルモン薬の効果や副作用をチェックし、何のために飲む薬なのか理解を深めていきましょう。
黄体ホルモンとは
人間の身体の機能を調整する働きを持つホルモンは100種類以上あり、成長やエネルギー代謝、血圧、食欲などに影響しています。
ホルモンは栄養のように身体の外から摂取するのではなく体内で作られ、どのホルモンであってもごく少量で効果を発揮するのが特徴です。
ホルモンはバランスが非常に大切で、多すぎても少なすぎても身体に様々な悪影響を及ぼします。
黄体ホルモンの働き
ホルモンのなかでも卵巣で作られる女性ホルモンは妊娠や出産に影響を与える性質を持ち、生理も女性ホルモンによってコントロールされています。
この女性ホルモンには、エストロゲンと呼ばれる卵胞ホルモンと、プロゲステロンと呼ばれる黄体ホルモンの2種類が存在しています。
今回話題となる黄体ホルモンは、子宮内膜を柔らかくして受精卵が着床しやすくさせる作用がある妊娠準備のためのホルモンで、排卵直後から分泌量が増えるのが特徴です。
妊娠しなかった場合には排卵後約1週間で黄体ホルモンは減少し始め、それから約1週間後に生理が起きます。
黄体ホルモンが減少すると
黄体ホルモンが減少して黄体機能不全となると、妊娠しやすい形に子宮内膜が形成できなくなったり、黄体ホルモンが抑えていた子宮収縮が起こりやすくなったりするなど不妊の原因になります。
また、黄体ホルモン不足すると月経周期異常や無月経などを引き起こす恐れもあります。
このように黄体ホルモンは女性の身体に深く関わっており、バランスが崩れることで様々な悪影響を及ぼします。
そのため、黄体ホルモンに異常が見られる時には黄体ホルモン薬を使用してバランスを整える治療がなされるのです。
黄体ホルモン薬を飲むとどうなる?
黄体ホルモン薬を使用して、身体に不足している黄体ホルモンを補充することにより、女性特有の様々な不調が改善されます。
ここでは黄体ホルモン薬を飲むとどうなるのかについて解説していきます。
不妊治療
不妊は様々な原因が考えられますが、その中の1つに黄体機能不全があります。
黄体機能不全になると、受精卵が子宮内膜に着床しなかったり、着床しても妊娠状態が維持できずに初期流産を起こしたりします。
この状態を改善するために黄体ホルモン剤で黄体ホルモンを補充し、妊娠しやすい身体を目指します。
月経困難症の緩和
黄体ホルモン薬の中には排卵を抑制して、子宮内膜を薄くさせる作用があります。
子宮内膜が薄くなることで、生理による出血量が減り、月経困難症の症状を和らげる効果があるとされています。
月経困難症の定義は幅広く、お腹が痛くなる生理痛や頭痛、吐き気、イライラなどの生理が原因で起こる身体・精神的症状が当てはまります。
これら月経困難症に対しては低用量ピルを使用するケースが多いのですが、低用量ピルの副作用に不安がある方に対して、リスクの低い黄体ホルモン薬を処方するケースがあります。
月経不順・無月経の改善
黄体ホルモンの分泌が起こらないことが原因となる月経不順や無月経などの卵巣機能不全にも、黄体ホルモン製剤を使用する治療を行います。
子宮内膜を厚くするエストロゲンが分泌されている状態で黄体ホルモン薬を使用することで子宮内膜が?がれて、服用終了後3~7日で月経が始まります。
これを周期的に繰り返すことで、月経を正常に戻していきます。
生理を移動させる
生理を遅らせたり移動させたりする効果がある薬として低用量ピルが有名ですが、血栓症のリスクが高まる40歳を過ぎると、処方が難しくなるデメリットがあります。
この時に代わりに処方されるのが黄体ホルモン薬です。
黄体ホルモン薬は低用量ピルと比較して生理を移動させる確実性は劣るものの、血栓症のリスクが低いため、比較的安全に使用できるメリットがあります。
黄体ホルモン薬の副作用
不妊治療や辛い生理の症状を和らげる効果がある黄体ホルモン薬にも副作用のリスクがあります。
黄体ホルモン薬の1つである「デュファストン錠」で起きる可能性がある副作用は次の通りです。
- 吐き気・嘔吐・食欲不振・腹痛・胃の膨満感・下痢
- 発疹 ・蕁麻疹
- 頭痛・めまい・眠気
- むくみ・倦怠感・体重増加
- 胸の張り・乳房痛・不正出血
- 肝機能障害
飲み始めに起こりやすい吐き気や胸の張り、頭痛などは、飲み続けるうちに落ち着いてくるケースが多いです。
ただし、副作用が続いたり重かったりする場合には、医師や薬剤師に相談するようにしましょう。
また、黄体ホルモン薬デュファストン錠は、重篤な肝障害・肝疾患がある方への使用は禁止されています。
さらに、心疾患や腎疾患、ポルフィリン症、重篤ではないケースの肝障害の方の使用は注意が必要とされています。
黄体ホルモン薬と低用量ピルとの違い
これまで黄体ホルモン薬の効果や副作用について解説してきましたが、その特徴が低用量ピルと似ているように感じた方もいらっしゃるかもしれません。
ここでは黄体ホルモン薬と低用量ピルの違いについて解説していきます。
成分と作用の違い
黄体ホルモン薬に配合されているホルモン成分が黄体ホルモンのみなのに対して、低用量ピルは黄体ホルモンに加えて、卵胞ホルモンであるエストロゲンも配合されています。
どちらも排卵を止めて子宮内膜が厚くなるのを防ぐ作用がありますが、排卵を止める作用は低用量ピルの方が高く、子宮内膜が厚くなるのを防ぐ作用は黄体ホルモン薬の方が強いという特徴があります。
そのため、黄体ホルモン薬が生理痛の緩和や子宮内膜症の治療に使用されるのに対し、低用量ピルは生理痛・排卵痛・月経前症候群の緩和や避妊に効果があるとされています。
黄体ホルモン薬にも避妊効果はあるものの低用量ピルに比べて効果が劣るため、別の避妊方法を併用するようにしましょう。
副作用の違い
避妊効果が高い低用量ピルは妊娠を望まない時に使用されることの多い薬ですが、血栓症のリスクが通常の2~3倍ほど高くなるため、使用できるのは若い健康な方に限られます。
つまり、肥満の方や喫煙習慣のある方、40歳以上の方、高血圧や糖尿病、肝臓障害の患者は低用量ピルが使用できないのです。
このような低用量ピルが使用できない方に対して、同じような作用を持ち、且つ血栓症のリスクがない黄体ホルモン薬を使用するケースが多いです。
ただし、黄体ホルモン薬も薬の種類によって重度な肝臓疾患がある方や重度の貧血症状がある方、強いうつ症状が見られる方の使用は禁止されている場合があります。
黄体ホルモン薬の一覧
黄体ホルモン薬にはいくつかの商品があり、同じような薬理作用があると言っても、その特徴は少しずつ異なります。
ここでは「デュファストン」「ヒスロン」「プロベラ」の3種類の薬を紹介していきます。
デュファストン
デュファストンはジドロゲステロンを主成分とする薬で、合成黄体ホルモンの中でも天然型黄体ホルモンに構造が近く、副作用が少ないメリットがあります。
デュファストンには子宮内膜が厚くなるのを防ぐ作用があるため、生理の問題や不妊症などの治療に使用される他、切迫流早産や習慣性流早産に使用するケースもあります。
ヒスロン・プロベラ
ヒスロンとプロベラはどちらもメドロキシプロゲステロン酢酸エステルを主成分とする薬で、ヒスロンが1錠に主成分を5mg含有しているのに対し、プロベラは2.5mgを含有している違いがあります。
ヒスロンとプロベラには子宮内膜が厚くなるのを防ぐ作用に加えて、子宮内膜を萎縮させる作用があることから、デュファストンで抑えることのできない子宮内膜の増殖を抑えるために使用されるケースもあります。
さらにヒスロンには、ヒスロンH錠200mgという高用量の商品があり、子宮体癌や子宮内膜癌、乳癌の治療に使われています。
黄体ホルモンの避妊リング「ミレーナ」
ここまで黄体ホルモンの内服薬について解説してきましたが、最後に黄体ホルモンによる避妊リング「ミレーナ」について触れておきます。
ミレーナは手の平に乗る程度の大きさのT字型の小さなリングで、これを子宮内に留置させ、合成黄体ホルモンであるレボノルゲストレルを子宮内に直接届けて避妊する薬です。
このミレーナは長い間避妊目的で使用されてきましたが、最近では月経困難症の症状緩和に効果があることが分かり注目されています。
生理や妊娠の悩みには黄体ホルモン薬
女性ホルモンの1つである黄体ホルモンは生理や妊娠などに関係し、その量によって身体に様々な影響を及ぼします。
黄体ホルモン薬は身体に黄体ホルモンを補充する役割を持ち、子宮内膜が厚くなるのを防ぐ作用がある薬です。
そのため、月経異常や月経困難症などの改善や不妊治療に効果を発揮し、特に血栓症のリスクが高い低用量ピルの服用が難しい場合に使用されるケースが多くなっています。
ただし、黄体ホルモン薬よりも低用量ピルの方が生理痛・排卵痛・月経前症候群への効果が高く、避妊の効果にも差が見られます。
黄体ホルモン薬と低用量ピルのどちらでも選べるのであれば、目的に合わせて薬を選択していくことが悩みの早期解決に繋がることと言えるでしょう。