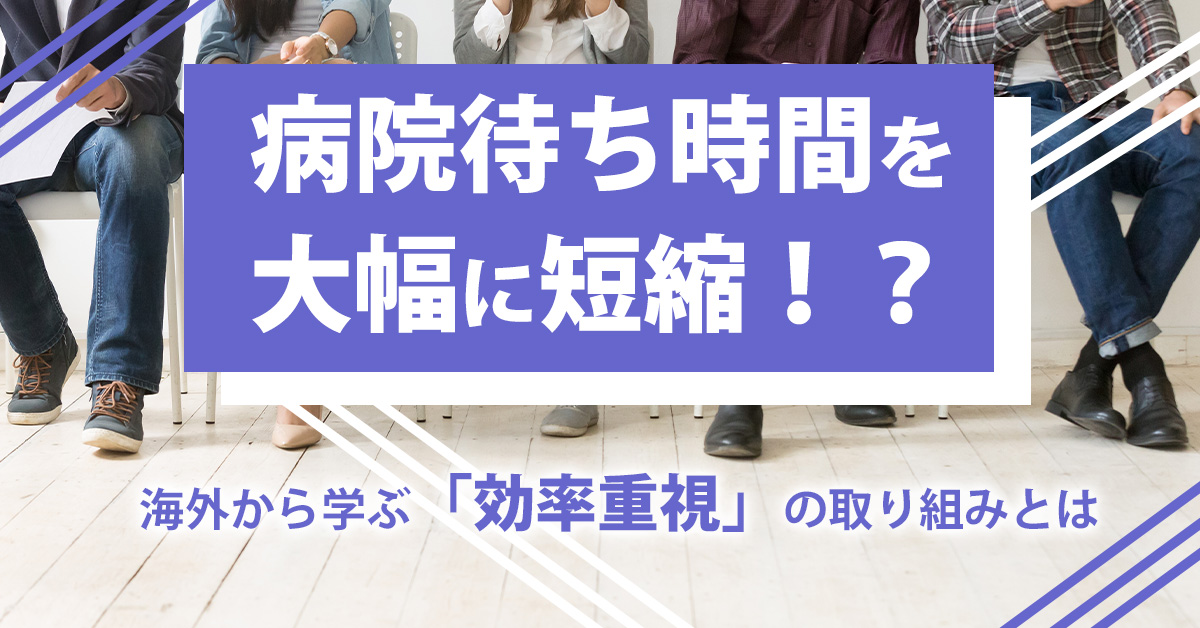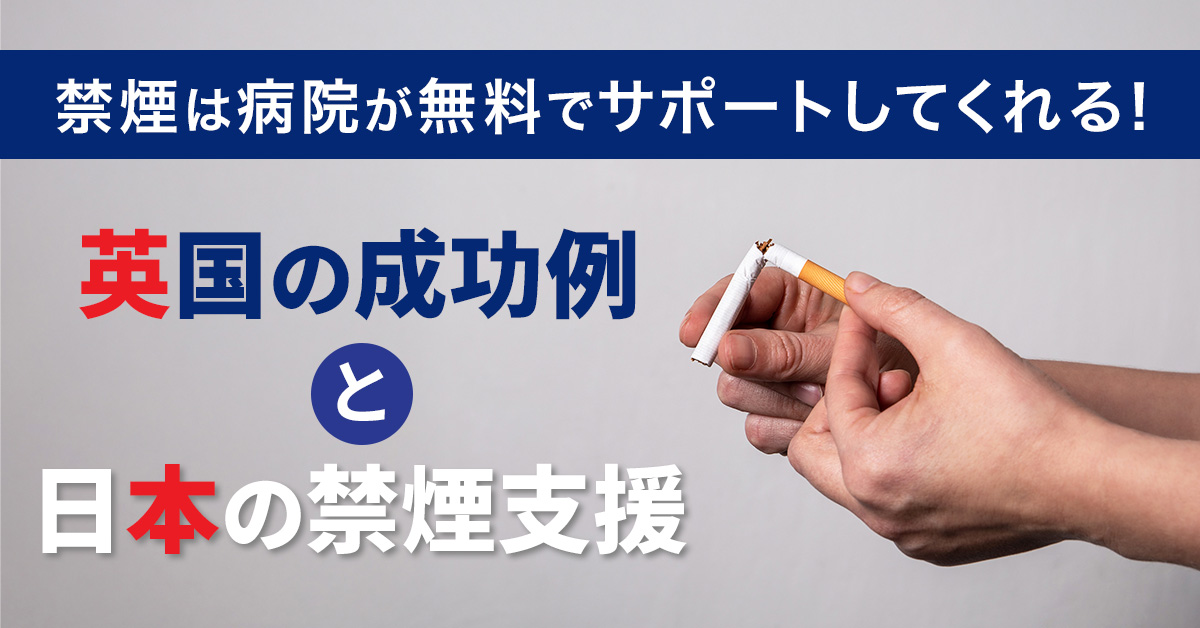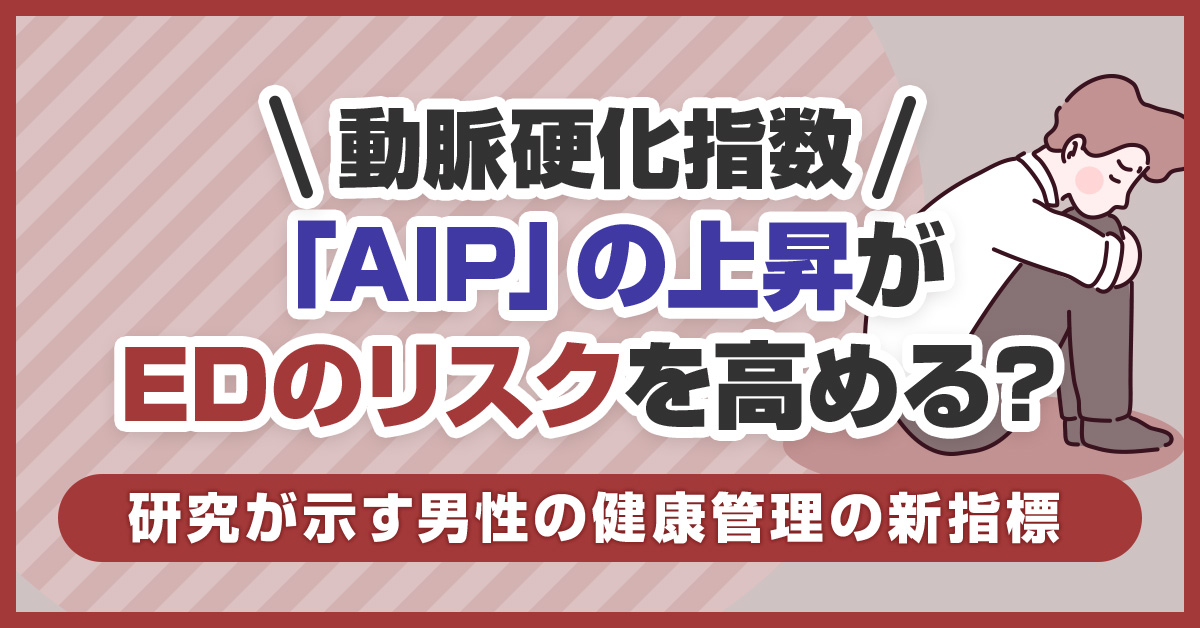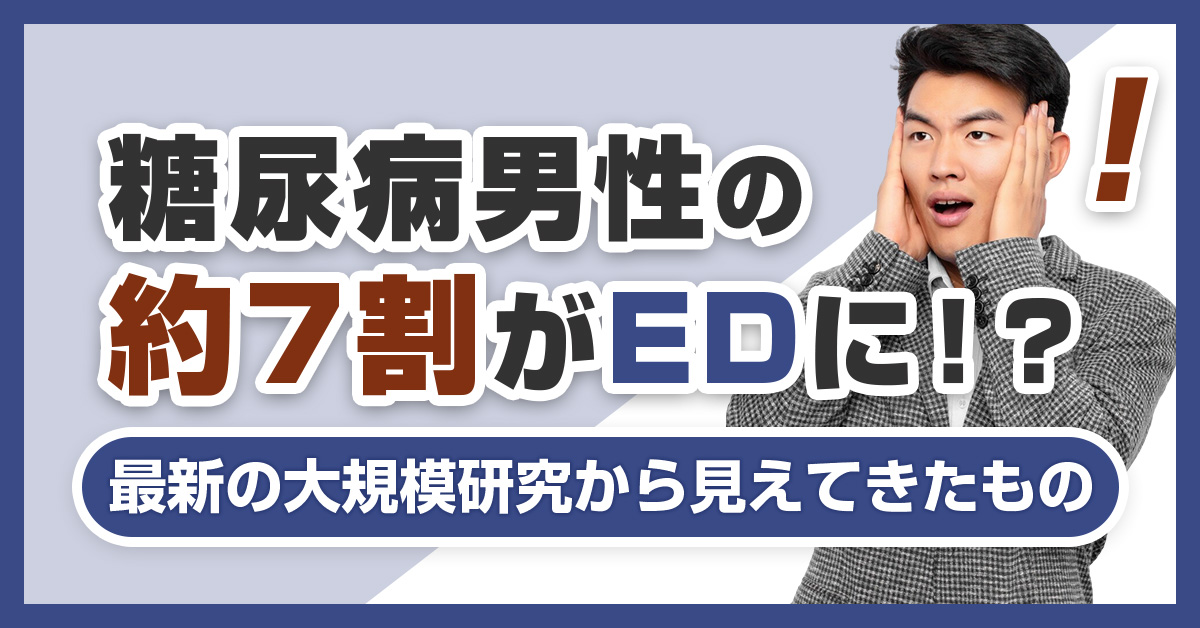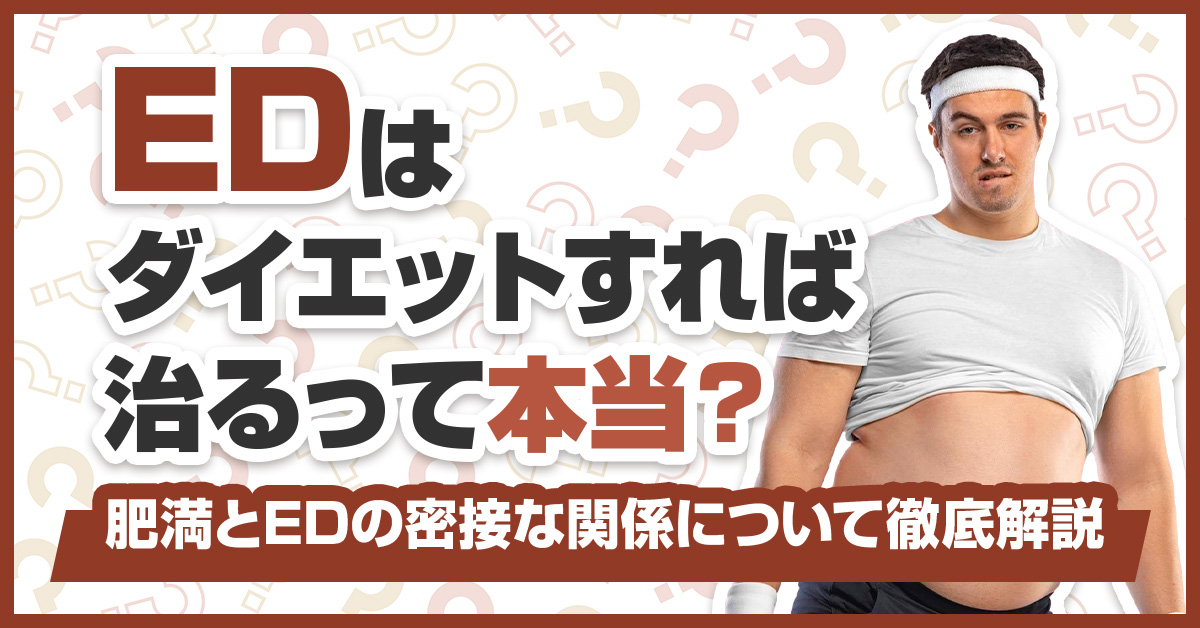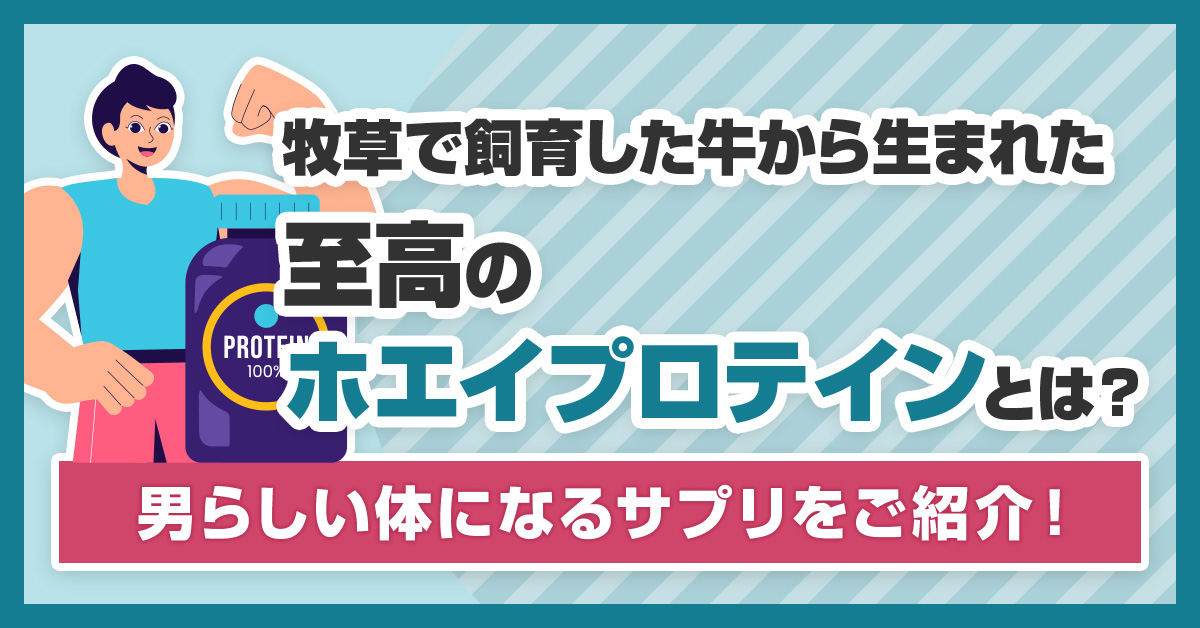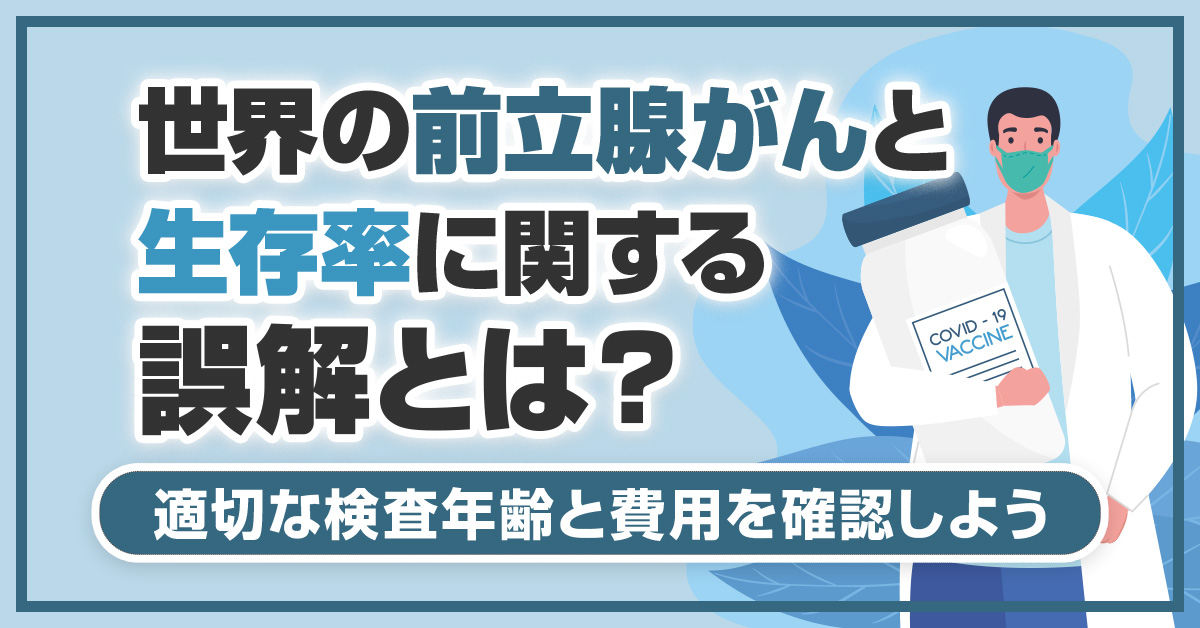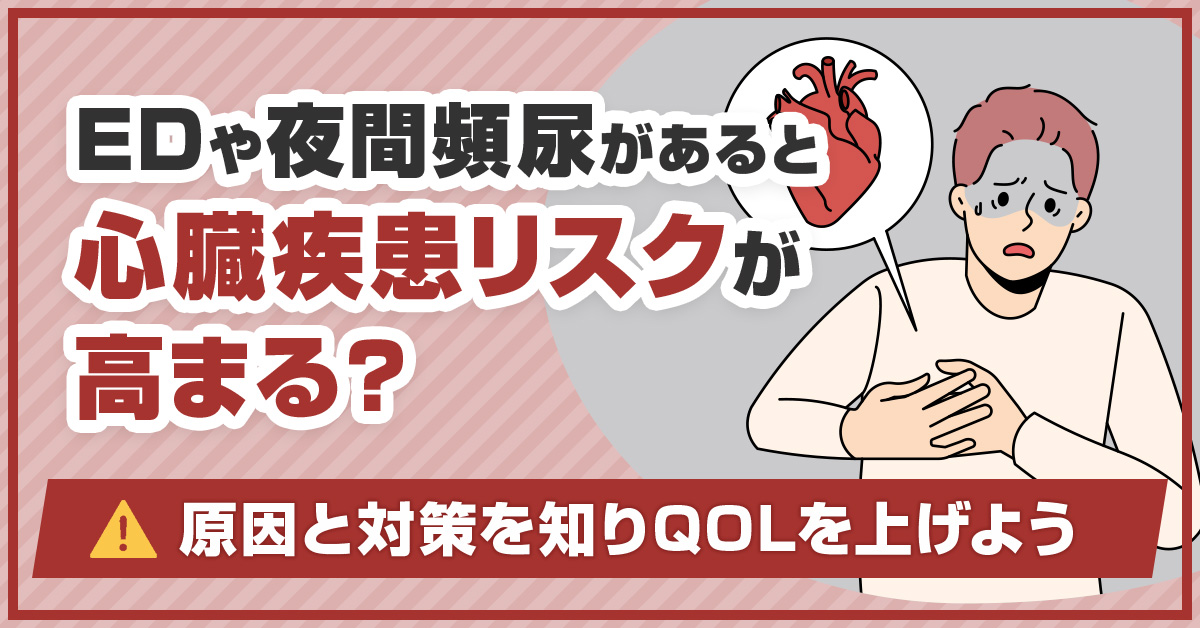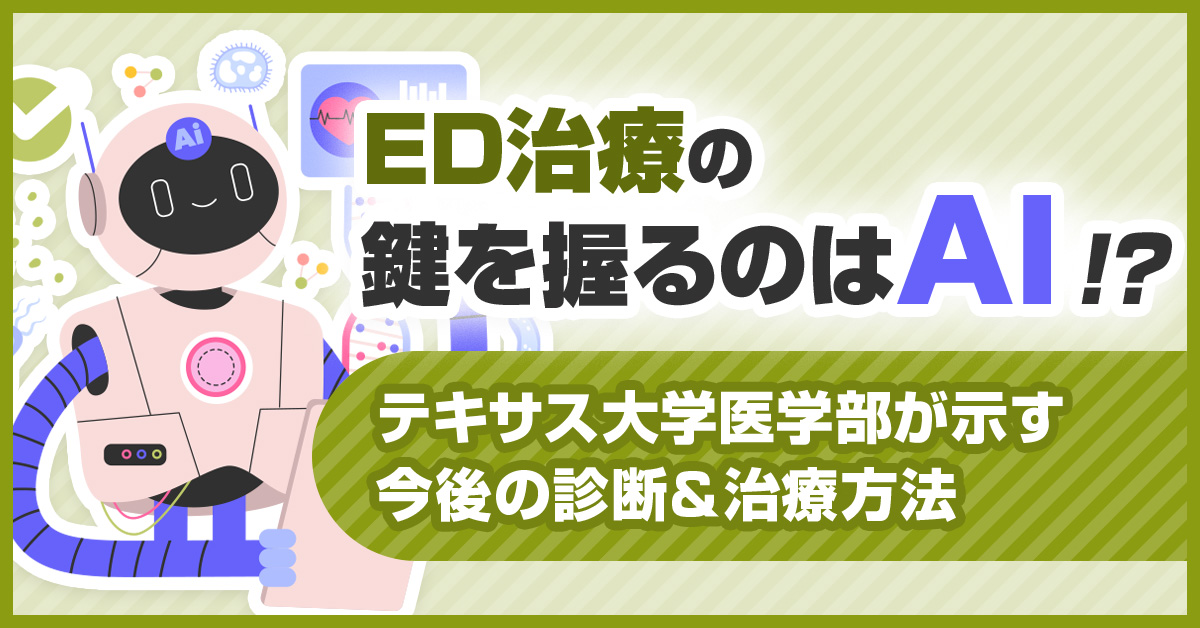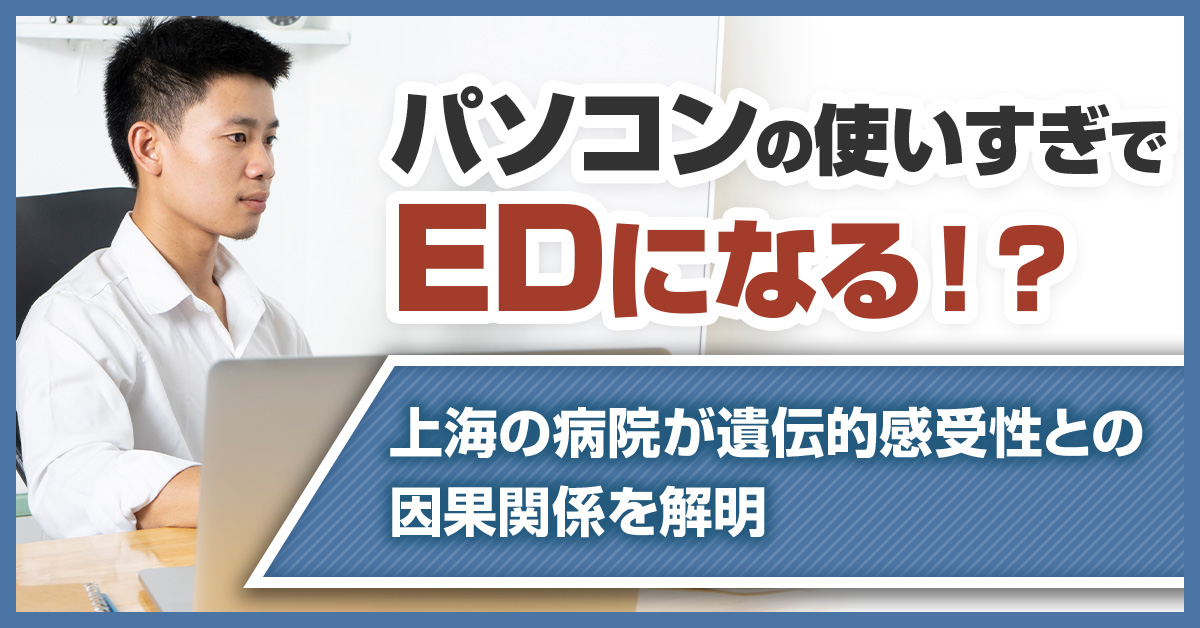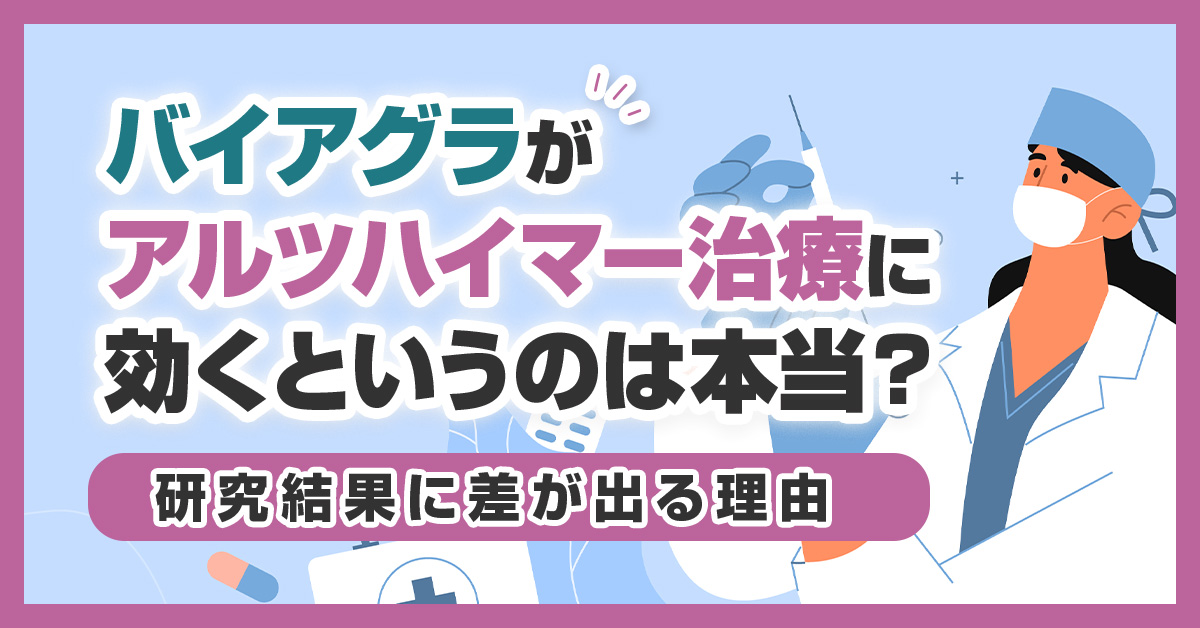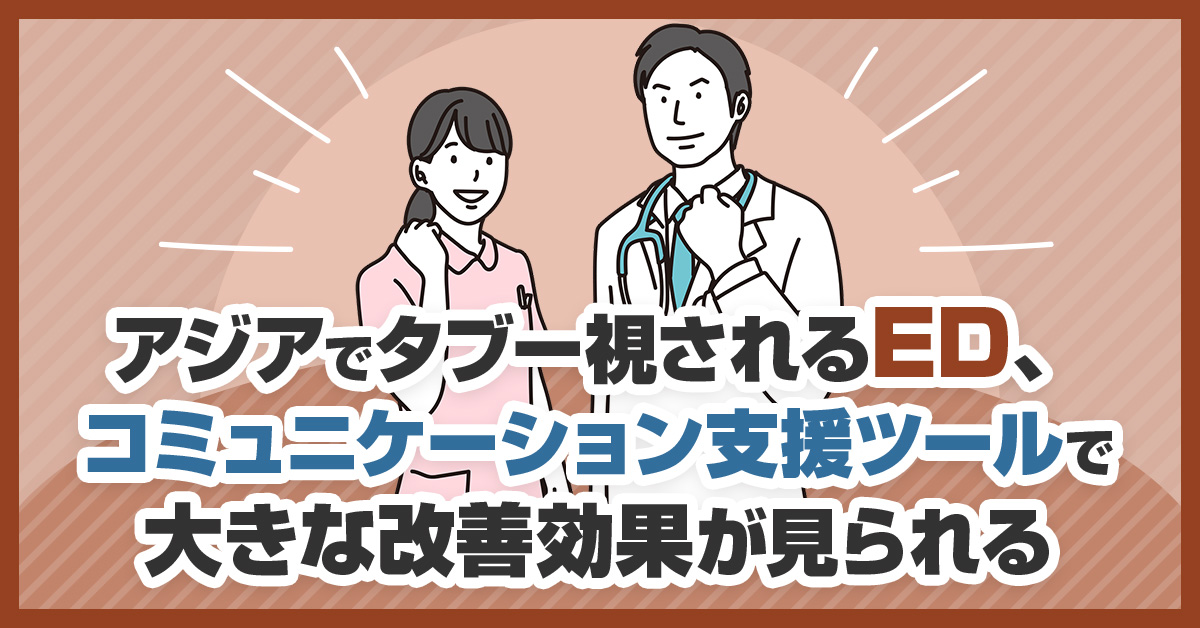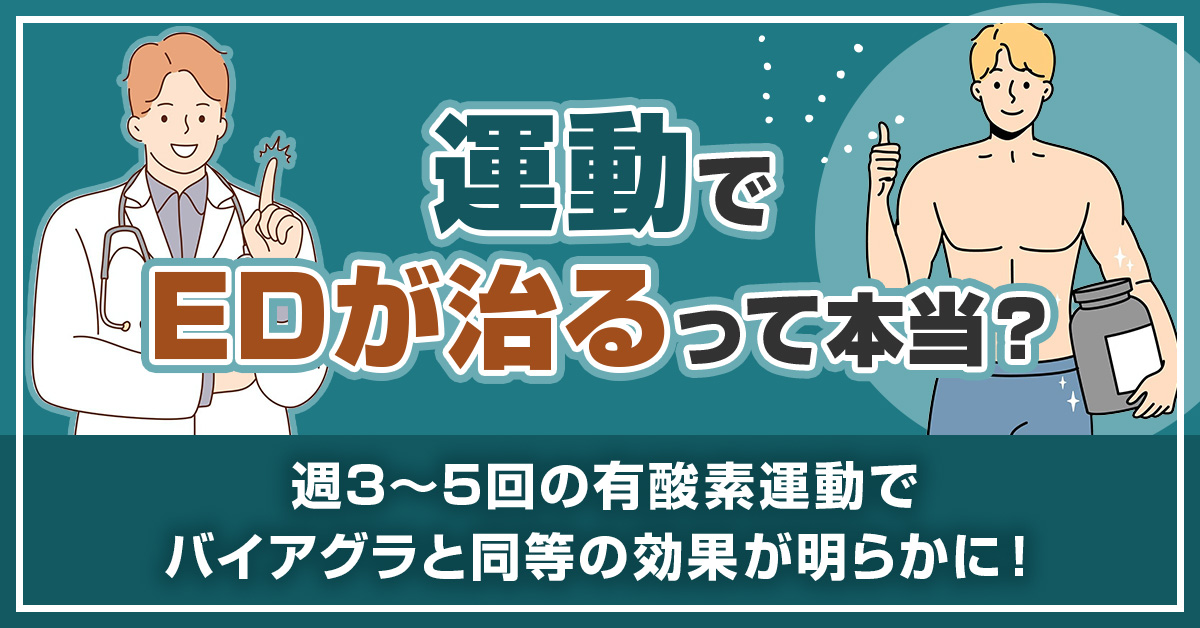病院の長い待ち時間は、どうしたら短縮できるのでしょうか。
今回は、イギリスの医療サイトで公表された、セント・トーマス病院などの新しい取り組みを2つご紹介します。
この取り組みの結果、救急科の待ち時間が劇的に短縮された他、スタッフの移動時間が短縮されるなどしたそうです!
どうやって待ち時間を減らしたのか、以下で見ていきましょう。
日本の病院の待ち時間は何分?
皆さんは、病院の待ち時間にイライラしたことはありませんか?
診察待ちや薬待ち、全体にかかる時間を考えると、忙しくてなかなか行けないという方もいるのではないでしょうか。
オンライン診療などのサービスも普及していきてはいますが、それでも実際に医師の診察が必要な場合は、多少なりとも待ち時間は発生してしまいます。
このような病院の待ち時間は、世界一の少子高齢社会である日本の大きな課題とも言えるでしょう。
まずは、日本の現状についてご紹介します。
診察までの待ち時間は「15分以上30分未満」が最多
厚生労働省が公表したデータによると、診察までの待ち時間について、「15分以上30分未満」の待ち時間が最も多く、全体の23.3%を占めています。
思ったより短いと感じた方もいるのではないでしょうか。
これには、都心と地方などの地域差や、高齢人口が多い地域かどうか、人気のクリニックかどうかなどの要因も大きく関係してくるように思います。
また、予約の有無別に見た場合、診察までの待ち時間が「30分未満」で済んだ割合は、予約をしていた患者さんで52.8%、予約をしていなかった患者さんで45.2%という結果でした。
このことから、予約をした方が待ち時間が短くなる傾向があることが示されています。
病院の種類別に待ち時間の違いを確認すると、大病院や特定機能病院では予約の有無による待ち時間に大きな差が見られました。
特にこれらの大規模病院では、予約をすることで待ち時間が大幅に短縮される傾向があるようです。
一方、小規模な病院や療養病床を持つ病院では、意外にも予約の有無に関わらず待ち時間にあまり大きな差は見られませんでした。
初診・再来による診察までの待ち時間の違い
初診と再来で診察までの待ち時間を見た場合、全体的に再来患者の方が短い待ち時間で診察を受けられる傾向が見られます。
具体的には、30分未満で診察を受けた割合は「初診」が44.9%であるのに対し、「再来」は47.1%とやや高い数値を示しています。
データで見てみると、あまり差が出ないのも意外ではないでしょうか。
また、病院の種類別に見ると、病床規模が大きくなるほど、初診よりも再来患者が30分未満で診察を受ける割合が増える傾向が顕著になっています。
特に大規模な病院では、再来患者に対して診察が迅速に行われていることがわかります。
診察時間は「3分以上10分未満」が半数以上!
外来患者が実際に医師に診察を受けた時間に関するデータでは、「3分以上10分未満」の診察時間が全体の50.6%を占めており、この時間幅が最も多いことが示されています。
また、全体の67.0%が「10分未満」での診察が行われており、短時間での診察が一般的です。
長い間待ったのに診察は数分だったという経験は、多くの方がしているのではないでしょうか。
病院の種類別に見ても、「3分以上10分未満」が最も多い結果となっています。
さらに、診察時間が「3分未満」である割合を比較すると、特定機能病院では10.0%と最低値を示しているのに対し、小規模病院では18.7%と最も高い結果となりました。
特定機能病院では、比較的じっくりとした診察が行われやすい一方で、小規模病院では短時間での診察が多いことがわかります。
セント・トーマス病院の新システム「queue trial」
では、イギリスでは病院の待ち時間にどのように対処しているのでしょうか。
救急科の待ち時間を減らすことに力を入れた病院が実験的に導入した新システム「queue trial」をご紹介しましょう。
鍵となるのはトリアージを行う看護師の存在
「queue」は、イギリス英語で「列」や「列に並ぶこと」を意味し、「 trial」は「試験」などの意味です。
この新しいシステムでは、看護師が受付から救急科の玄関口へと移動し、「トリアージフローナビゲーター」として、到着した患者さんの状態をその場で評価する役割を担います。
トリアージとは、災害や事故などの緊急時に、傷病者の緊急度や重症度に応じて治療や搬送の優先順位を決めることです。
ナビゲーターは、病院を訪れた患者さん一人ひとりに対して初期評価を行い、症状や状態に基づき必要な処置を素早く決めます。
この試みは、NHSイングランドの指針に基づき、患者さんが到着後15分以内に評価を受けることを目標としています。
評価結果は、5段階の重症度スコアに従って記録され、最も重症と判断された患者さんは即座に蘇生処置を受けます。
それ以外の患者さんは、眼科救急や小児科など、適切な専門部門へ速やかに移されます。
他部門への適切な誘導で効率アップ
「queue trial」は、救急科に来る患者さんの中でも、他の診療科へ誘導すべき患者さんをいち早く特定する役割も果たしています。
データによれば、待機列にいる10~12%の患者さんは、本来別の診療科へ行くべき患者さんであることがわかり、患者さんが移動することで待機時間が短縮されています。
救急科の看護婦長であるジョン・オニール氏は、以前勤務していたメドウェイ病院での経験を活かし、「queue trial」をセント・トーマス病院でも導入しました。
同氏は、「15分以内に患者さんの状態を評価することで、患者さんの安全を確保し、早期に必要なケアを受けさせるための重要なステップです」と述べています。
試験的導入から本格採用へ!
この「トリアージフローナビゲーター」の役割は、2023年11月に2週間の試験期間を経て年末まで延長されました。
試験の結果、待ち時間の短縮や患者さんの満足度の向上といった明確な成果が認められ、管理チームは、午前8時から午後8時30分まで週7日体制でこの役割を正式に導入することを決定しました。
オニール氏はさらに、「この新しい役割のおかげで、患者さんは最初から高い知識や技術を持った医師から治療方針を決めてもらえるため、迅速な評価を受けることで安心感が得られるようになりました。
また、これにより救急科の待ち時間が減り、他の部門で適切なケアを受けるべき患者さんもスムーズに誘導されています」と語っています。
「電動カーゴバイク」でスタッフの移動効率が向上!
「queue trial」の他にも、スタッフの移動効率を上げる取り組みがあります。
ガイ病院とセント・トーマス病院では、電動カーゴバイク(E-cargo bikes)の使用によってスタッフがロンドンの交通渋滞を避け、より早く患者さんの元へ到着できるかどうか、また移動中の二酸化炭素排出量を削減できるかを検証する試験を行いました。
電動カーゴバイクの試験内容
電動カーゴバイクのバイクの後ろにはトラックの荷台のようなものが付いており、運転手の前には透明なシールドが付いています。
この試験的プロジェクトでは、ウェストノーウッドにあるエルムコート健康センターの@homeサービスのメンバー9名が、車や公共交通機関、自転車の代わりに電動カーゴバイクを使用して、患者さんの自宅を訪問しました。
電動カーゴバイクを提供したのはEAVという企業で、スタッフが安全に自転車を使用できるよう、インストラクターによる路上トレーニングも実施したそうです。
入院患者を減らすことにも繋がる!
@homeサービスは、看護師、セラピスト、医師、薬剤師、ソーシャルワーカーなど、多岐にわたる医療従事者で構成されています。
彼らの主な役割は、患者さんが早く自宅へ戻れるようサポートし、入院をしないで済むようにすることです。
これにより、ガイズ・アンド・セント・トーマス病院とキングス・カレッジ病院の病床を解放できるため、医療提供の効率も向上するというわけです。
この試験に参加したハリエット・スレイド氏(@homeサービスの副責任者)は、スタッフが電動カーゴバイクを利用することで、患者さんの自宅に早く到着し、必要な治療を迅速に提供できるだけでなく、持続可能な移動手段としても注目していると述べました。
環境への配慮と患者ケアの迅速化が両立できる点で、大きな期待が寄せられています。
電動カーゴバイクの利便性と期待
電動カーゴバイクには、交通規制が行われているエリアを自由に移動できるという強みがあります。
車の通行が制限される住宅街や公園などもスムーズに走行でき、駐車許可証や制限を気にする必要がないため、スタッフの移動効率を大幅に向上させられるのです。
また、最大150kgまでの荷物を運べるため、患者宅で必要となる医療機器やかさばる物品を運搬する際にも十分な積載能力を持っていると言えます。
ガイズ・アンド・セント・トーマス病院の担当官、ティム・ル・ルージュテル氏は、「カーゴバイクは、交通の便が悪い場所でも効率よく移動でき、患者宅への訪問がこれまで以上にスムーズになる」と述べ、試験の成果に期待を寄せています。
さらに、この取り組みが病院の二酸化炭素の排出削減にも大いに貢献するのではないかと言われています。
まとめ
イギリスでは医療サービスの取り組みが積極的に行われていて、結果を出していることもわかりましたね!
特に救急科ではその名の通り急を要するので、1分1秒と時間とのせめぎ合いです。
また、入院患者を増やさない取り組みは、入院をしたくない患者さんの意志に沿う形でもあり、病院と患者さん双方にメリットがある場合も多いのではないかと感じました。
世界的に人間の寿命が伸びている今、病院の待ち時間への対策は急務と言えるのではないでしょうか。