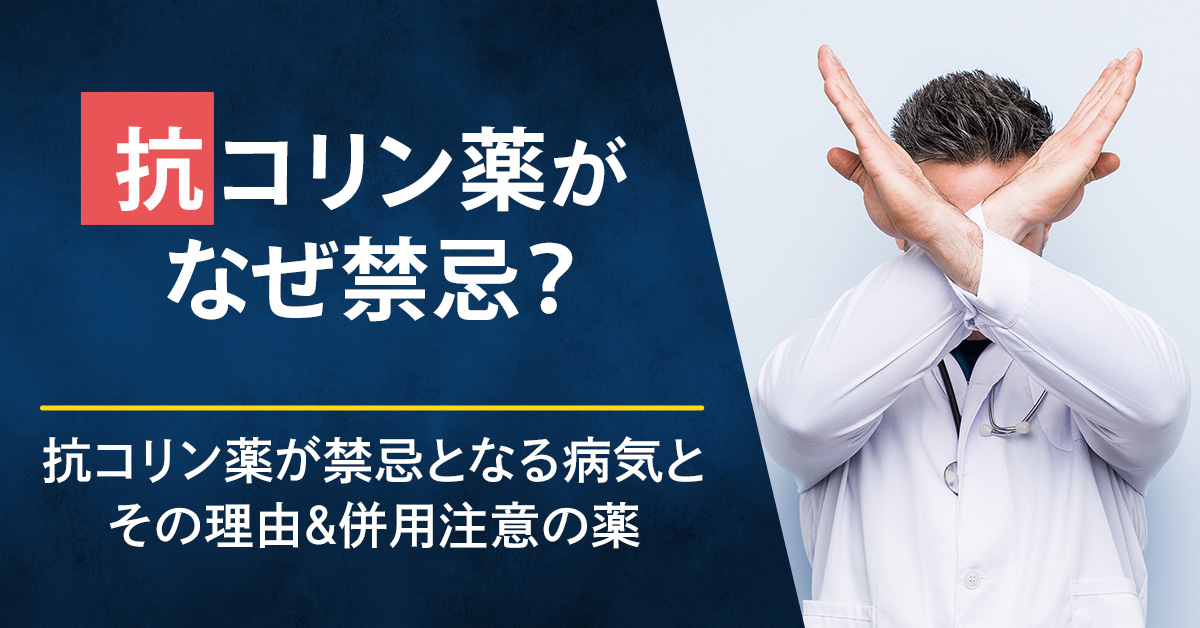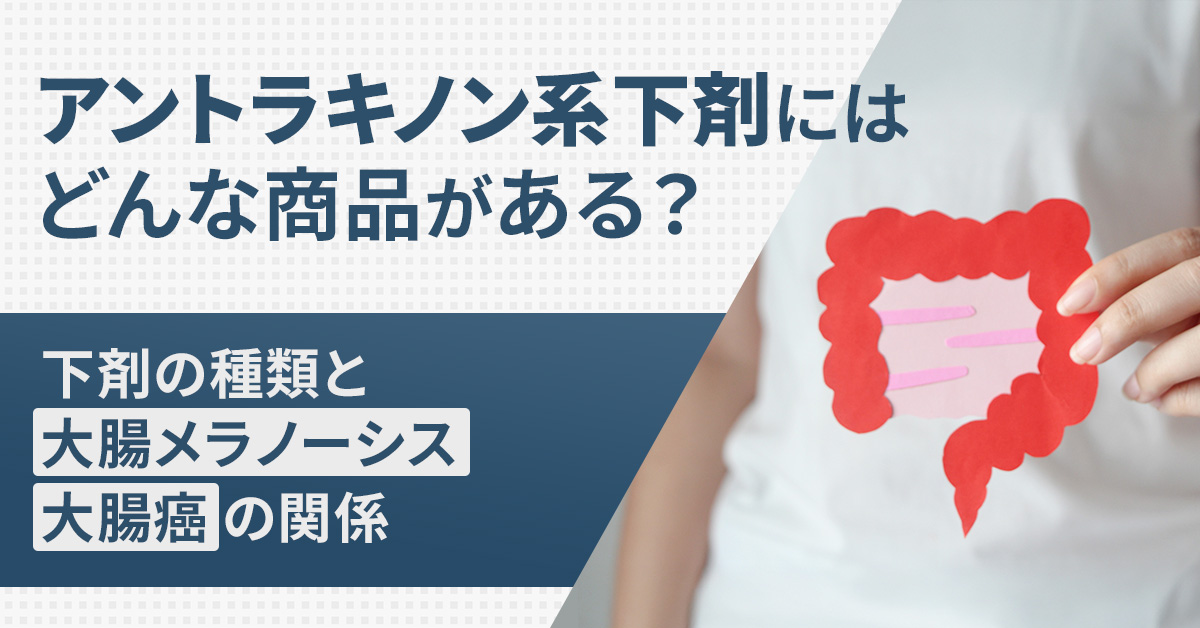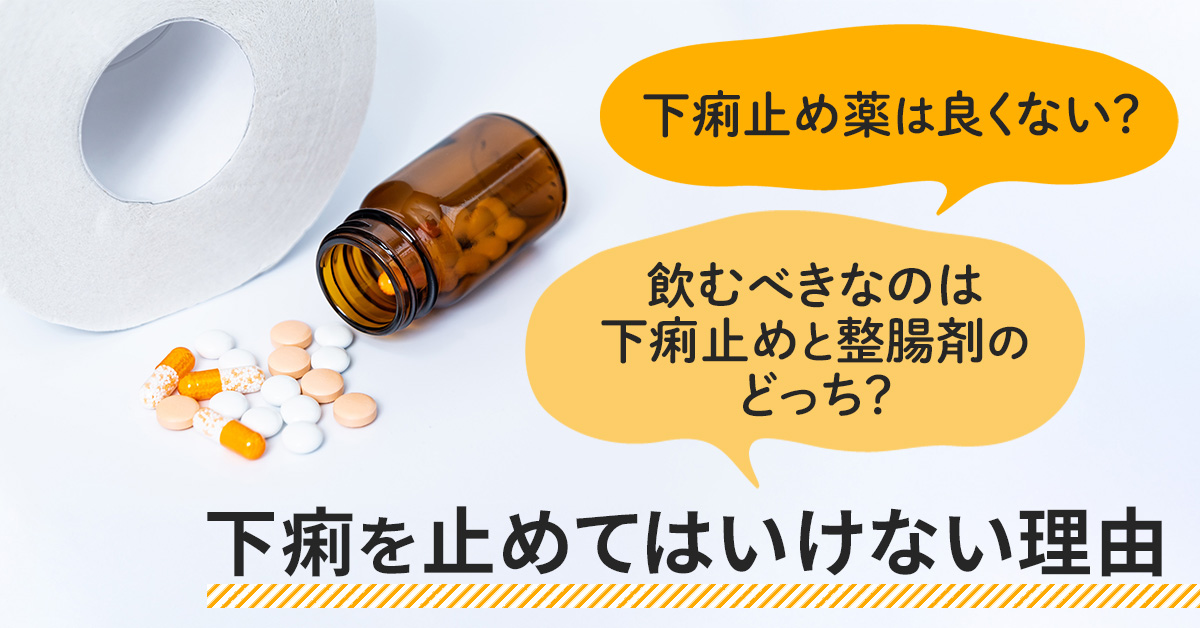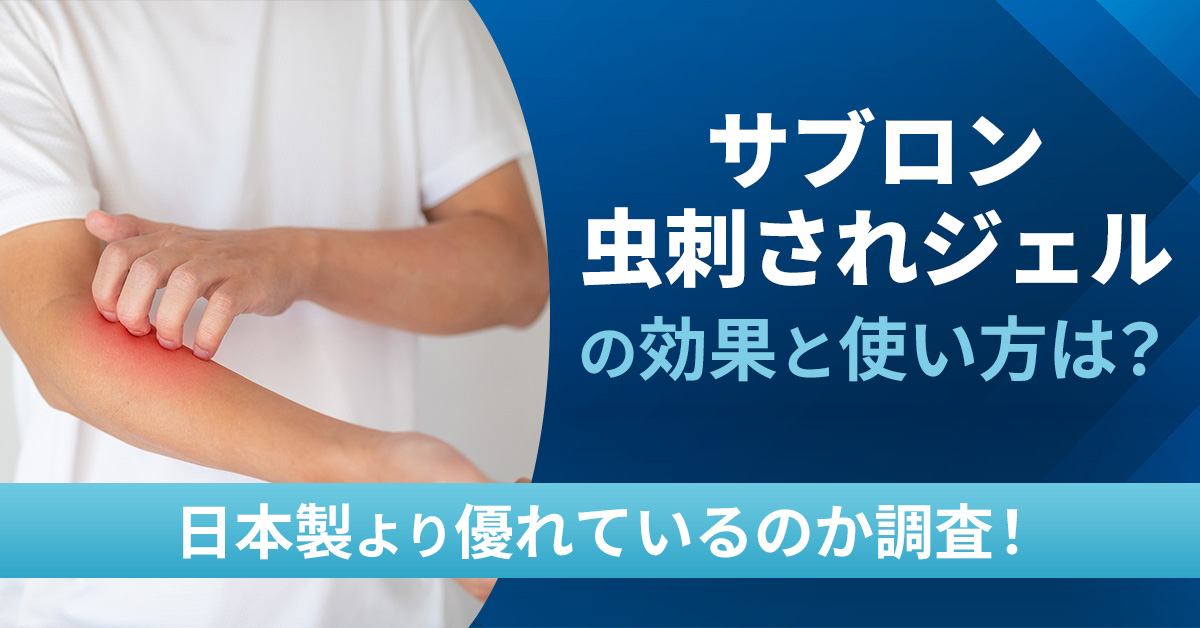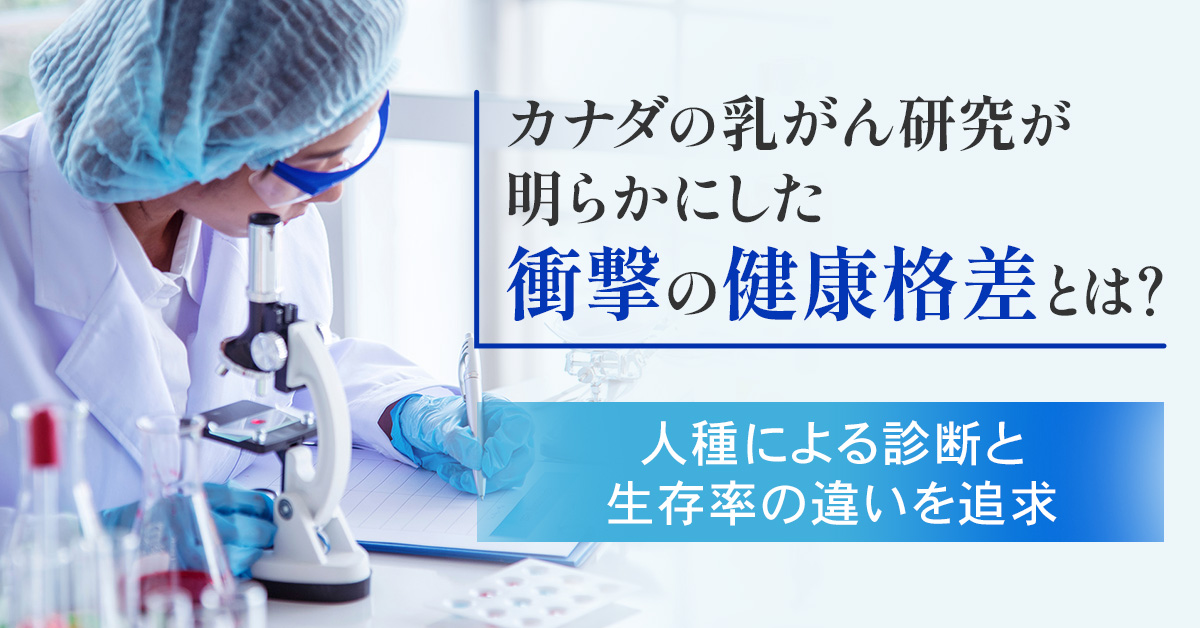副交感神経を抑制する作用がある抗コリン薬は、様々な病気の治療に使用されている薬剤です。
しかしながら、抗コリン薬が禁忌とされていたり注意が必要とされていたりする病気や、併用注意とされている薬剤は数多くあり、なぜなのか疑問に思う方もいらっしゃるのではないでしょうか。
今回は抗コリン薬の禁忌や服用に注意が必要な病気、併用注意の薬剤にフォーカスして解説していきます。
抗コリン薬を正しく安全に使用するためにも、内容をしっかりとチェックしておきましょう。
抗コリン薬とは
抗コリン薬は作用や化学構造などによって、ムスカリン拮抗薬、3級アミン類、4級アンモニウム類などの複数の種類に分類されますが、今回は各抗コリン薬に共通する内容を中心にお話していきます。
まずは様々な病気の治療に使用される抗コリン薬の効果と副作用について、基本的な情報をおさえておきましょう。
効果
抗コリン薬は体内の神経情報を伝達する物質であるアセチルコリンの働きを抑制する薬剤です。
胃腸の痛みの抑制や頻尿症状の改善、気管支喘息の治療、流産の予防など、様々な場面で使用されています。
胃腸の痛みの抑制
胃や腸などの消化器の運動に関わる副交感神経伝達物質であるアセチルコリンが活発になると消化器の働きが高まりますが、この働きが強くなりすぎると胃腸のけいれんや炎症の発症・悪化などにより痛みが現れます。
この過剰なアセチルコリンの働きを抑制して痛みを抑えるために抗コリン薬は使用されます。
頻尿の改善
頻尿は膀胱の活動が過剰となり、膀胱内に尿が溜まっていないのに尿意をもよおしてしまう病気です。
これはアセチルコリンがムスカリン受容体に作用することで起きる膀胱の収縮が原因であるため、アセチルコリンの働きを阻害する抗コリン薬が頻尿の改善に活用されています。
気管支喘息の治療
気管支喘息は気管に炎症が起きて狭くなる病気で、気管の炎症を抑えて気道を広げて治療していきます。
気管は交感神経が働くことで拡張し、反対に副交感神経が働くことで収縮するため、副交感神経を調整しているアセチルコリンの働きを抗コリン薬で抑制することで、症状が緩和できます。
流産の予防
アセチルコリンは消化器だけでなく子宮の運動にも作用しており、抗コリン薬を服用することで子宮の収縮を抑え、妊娠中のお腹の張りや腹痛、出血などの前兆症状を和らげて切迫早産や早産を予防します。
副作用
抗コリン薬には様々な種類がありますが、抗コリン作用を有する薬剤に共通する副作用として以下の症状が現れる場合があります。
- 消化器症状:口の渇き、唾液や消化液分泌抑制、便秘など
- 泌尿器症状:排尿障害、尿閉など
- 中枢性症状:記憶障害、幻覚、せん妄など
- 循環器症状:動悸、不整脈、頻脈、めまいなど
- 眼科症状 :眼圧上昇、ドライアイ
抗コリン薬を使用するとこれら副作用が現れる可能性があるため、副作用が起きやすい部分に病気を抱えている場合は、より慎重に服用する必要があります。
抗コリン薬の禁忌
抗コリン薬は消化器や気管支喘息を始めとする様々な病気の治療に使用されている薬剤ですが、抗コリン薬の使用によって病状を悪化させたり、深刻な副作用が現れたりする可能性が高いために禁忌とされている病気が複数あります。
ここでは抗コリン薬がなぜ禁忌となっているのか、理由を添えて解説していきます。
前立腺肥大
精液の一部を作る男性特有の臓器である前立腺が加齢とともに肥大化する病気が前立腺肥大です。
前立腺肥大になると頻尿や残尿感、排尿遅延などのおしっこに関連する異常が現れます。
抗コリン薬は副交感神経を抑制して膀胱平滑筋を弛緩させる作用があり、膀胱の排出力を弱めたり、尿道を収縮させたりして尿閉や排尿困難を引き起こす恐れがあることから、前立腺肥大には禁忌とされています。
重症筋無力症
厚生労働省の特定疾患である難病に指定されている重症筋無力症は、末梢神経と筋肉の接合部分で筋肉の受容体が自己抗体によって破壊されてしまい全身の筋力が低下する病気です。
重症筋無力症についてはまだ研究段階であるものの、免疫機能がアセチルコリン受容体に反応して起きている可能性があることから、アセチルコリンに作用する抗コリン薬が禁忌とされています。
閉塞隅角緑内障
閉塞隅角緑内障は虹彩が隅角へ押し上げられることにより、房水排出が妨げられて眼圧が上昇する病気です。
眼圧が上昇すると視神経の障害が発生しやすくなるデメリットがあります。
抗コリン薬は副交感神経を抑制する作用があるため、毛様体筋を弛緩させて隅角を狭くし、眼圧を上昇させる副作用があります。
閉塞隅角緑内障は眼圧を下げて視神経の障害を緩和したり改善したりするため、眼圧を上昇させる副作用がある抗コリン薬は禁忌とされているのです。
イレウス
イレウスは腸炎や腹膜炎、手術、自律神経の機能異常による腸管の麻痺が原因となり、腸の内容物が肛門へと流れなくなる病気です。
抗コリン薬の腸管の収縮運動を抑制する効果により余計に腸が動きにくくなり、症状を悪化させてしまうことからイレウスの患者さんには禁忌とされています。
抗コリン薬の使用に注意が必要な患者さん
抗コリン薬が禁忌とはされていなくとも、使用に注意が必要となる患者さんもいます。
ここでは抗コリン薬の使用に慎重になるべき患者さんを紹介していきます。
ただし、抗コリン薬の主成分の種類によっては禁忌とされているケースもあるので、使用前には必ず医師や薬剤師に確認してください。
心疾患の患者さん
抗コリン薬は副交感神経を抑制して交感神経を優位にするため、血圧が上昇して心臓の収縮を強め、心拍数を上げます。
この作用により、心臓に重い負担がかかり、症状を悪化させる危険性があるため、心疾患がある患者さんの抗コリン薬使用には注意が必要とされています。
潰瘍性大腸炎の患者さん
潰瘍性大腸炎は小腸や大腸の粘膜に慢性の炎症・潰瘍を引き起こす原因不明の病気です。
この病気の患者さんが抗コリン薬を使用すると、炎症が激しくなって大量出血したり、腸に穴が空いたりする中毒性巨大結腸症が現れる可能性があることから、慎重に使用することとされています。
認知症患者や高齢者
アルツハイマー型認知症はアセチルコリンを作る細胞が減ってアセチルコリンの分泌が減少することで症状が現れるため、アセチルコリンの減少を補う薬剤を服用して治療を進めていきます。
一方、抗コリン薬は神経情報を伝達する物質であるアセチルコリンの働きを抑制させる作用があることから、認知症の悪化に繋がる恐れがあるため、使用には慎重になる必要があります。
また、認知症の症状がない高齢者も記憶障害や、他の副作用である口の渇きや緑内障、排尿困難などの副作用が現れやすいため、抗コリン薬を使用する時は注意しなければなりません。
妊娠中・授乳中の方
胎児や新生児に頻脈を起こす可能性があるため、妊娠中や授乳中の方には抗コリン薬を投与しないことが望ましいとされています。
また、抗コリン薬が乳汁の分泌を抑制する恐れもあります。
抗コリン薬と併用注意の薬
抗コリン薬との併用に注意が必要となる薬剤もあります。
ここでは主な併用注意の薬剤を紹介します。
抗コリン作用がある薬
抗コリン薬と同じ抗コリン作用のある薬剤を併用すると、副作用が強くなる危険性があるため注意してください。
併用する場合には、医師による定期検査を受診し、問題ないことを確認しながら使用していきましょう。
抗コリン作用がある薬剤には、抗ヒスタミン剤、三環系抗うつ剤、フェノチアジン系薬剤、イソニアジドがあります。
特に抗ヒスタミン剤は花粉症などのアレルギー薬や総合風邪薬として市販されている使用頻度の高い薬剤のため、抗コリン薬との併用には注意が必要です。
MAO阻害剤
ドパミンの分解を阻害して脳内のドパミン量を増やし、パーキンソン病の手足の震えや筋肉のこわばりを改善するMAO阻害剤も、抗コリン薬の作用が強くなる恐れがあるため併用には注意してください。
ジギタリス製剤
ジギタリス製剤は心筋細胞内のカルシウムイオン濃度を上げて収縮力を増加させる効果がある心不全などの治療に使われる薬剤です。
抗コリン薬と併用するとジギタリス製剤の血中濃度が上昇し、嘔吐やめまい、不整脈などが現れるジギタリス中毒を引き起こす恐れがあります。
抗コリン薬と併用する場合には心電図検査や血中濃度の測定などを定期的に行い、注意しながら使用していきましょう。
抗コリン薬は禁忌・飲み合わせに注意しながら使用しよう
抗コリン薬は神経情報伝達物質であるアセチルコリンの働きを抑制する効果があり、胃腸の痛みの緩和、頻尿症状の改善、気管支喘息の治療、流産の予防などに使用されている薬剤です。
このように様々な病気に役立つ抗コリン薬ですが、前立腺肥大や重症筋無力症、閉塞隅角緑内障、イレウスなどを患っている方は禁忌とされており、他にも使用注意とする病気が多数ある点には注意が必要です。
また、飲み合わせに注意が必要な薬剤も複数あります。
特に抗コリン薬と同じ抗コリン作用がある抗ヒスタミン剤は風邪やアレルギーの薬剤として市販されていることから、気づかずに併用してしまわないように気を付けてください。
市販薬を購入する際には、注意書きをよく読み、不明点があれば薬剤師に相談するとよいでしょう。