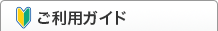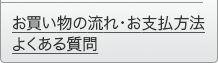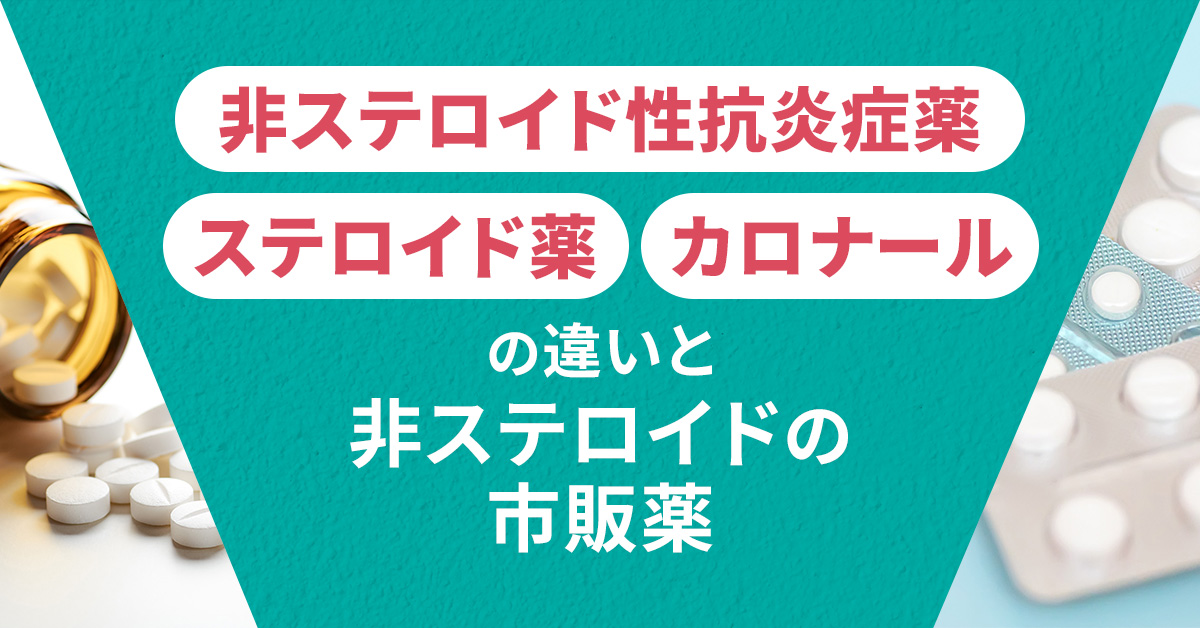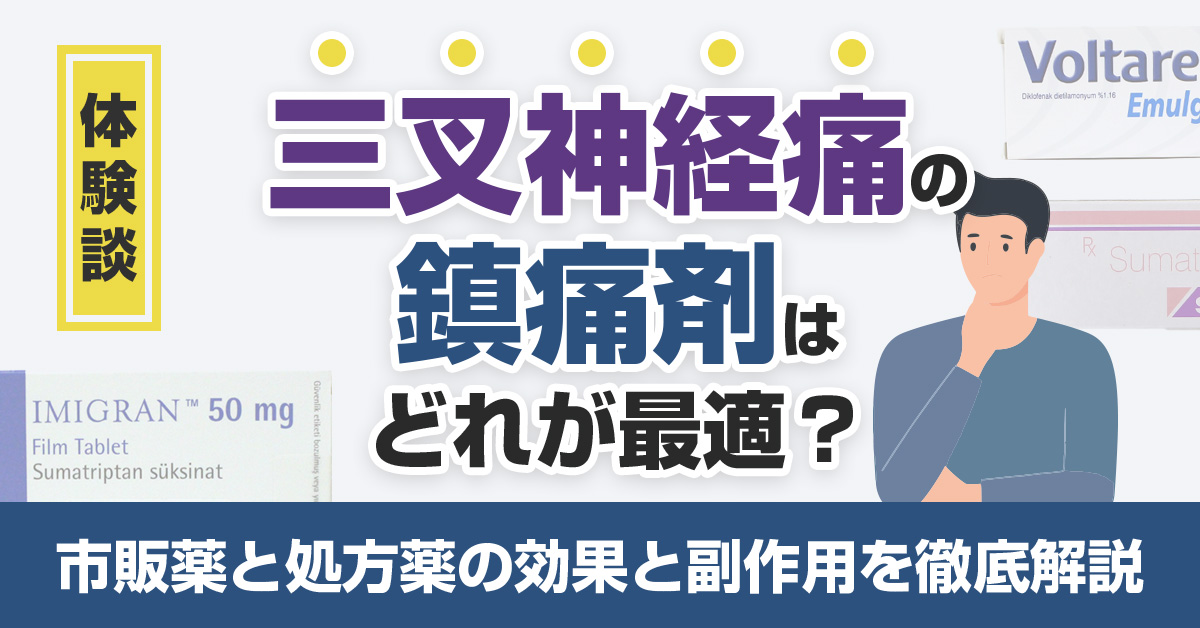高熱の時や痛みを止めたい時に使用する非ステロイド性抗炎症薬ですが、同じような名前のステロイド薬とはどのような違いがあるのかご存知でしょうか。
今回は、非ステロイド性抗炎症薬とステロイド薬の違いについてわかりやすく解説するとともに、同じような効能のカロナールとの違いについてもフォーカスしていきます。
また、非ステロイド性抗炎症薬の市販の飲み薬も併せて紹介していきますので、ご自身の症状に合った薬剤を見つけられるように理解を深めていきましょう。
ステロイド薬と非ステロイド性抗炎症薬の違い
ステロイド薬を処方されると「使って大丈夫なのかな?」と思う方もいらっしゃるようですが、ほとんどの場合はステロイドについて正しい知識を持っていないために起こる不安と言えるのかもしれません。
まずはステロイド薬と非ステロイド性抗炎症薬についての知識を身につけ、それぞれの違いを確認していきます。
薬剤の効果や副作用を理解し、薬剤を正しく扱えるように知識をアップデートしていきましょう。
ステロイド薬とは
ステロイドは人間の体内にある副腎という臓器で作られるホルモンの一種で、このホルモンを応用して作った薬剤がステロイド薬です。
ステロイド薬には炎症を抑制する抗炎症作用や身体の免疫力を抑える免疫抑制作用などがあり、アレルギー疾患などを始めとする様々な病気に使用されています。
ステロイドはとても効果の高い薬剤ですが、その反面、免疫力が低下することで感染症にかかりやすくなったり、骨がもろくなったりするなどの副作用に加え、ステロイド性の糖尿病や胃腸の潰瘍を引き起こす可能性もあります。
さらにステロイドを途中で急に使用するのを中断したり、勝手に使用量を減らしたりすると体内のステロイドホルモンが不足して、倦怠感や頭痛、吐き気などが現れるステロイド離脱症候群を引き起こすので注意が必要です。
また、ステロイドの剤型は内服薬・注射薬・外用薬に分類され、特に外用薬は皮膚疾患用の塗り薬、アレルギー性鼻炎を抑える点鼻薬、かゆみを抑える目薬などがあります。
内服薬や注射薬などの全身に投与する薬剤に比べて、外用薬のように身体の一部にしか使用しない薬剤の方が、副作用が起きにくいとされています。
つまり、花粉症などで処方される点鼻薬などは用法用量を守って正しく使用すれば、副作用も起こりにくいです。
副作用や使用上の注意点の多さから「ステロイドは怖い」「使ってはダメ」などのイメージが先行し、避けたいと考える方がいるのも事実です。
しかしながら、ステロイド薬は非常に効果が高い薬剤であるため、過度に恐れるのではなく症状が強い時には上手に力を借りていく姿勢が大切であると考えられます。
非ステロイド性抗炎症薬とは
非ステロイド性抗炎症薬は体内にある痛みを増殖させる作用のあるプロスタグランジンやロイコトリエンを作る過程で働きを抑制して、痛みを緩和させたり炎症を鎮めたり熱を下げたりする薬剤でNSAIDsと呼ぶこともあります。
リウマチ性疾患や歯の治療時の痛み止め、感染症などによる高熱を解熱するために使用されるなど適応範囲が広いため、使用したことがある方も多いのではないでしょうか。
ただし、非ステロイド性抗炎症薬は痛みなどを抑える対症療法であるため、病気の原因そのものを治療する薬剤ではありません。
非ステロイド性抗炎症薬は内服薬として利用されることが多いですが、塗り薬や湿布、座薬などの剤型も存在します。
非ステロイド性抗炎症薬の副作用として腹痛や吐き気などの胃腸症状や、ごく稀に喘息発作や腎機能障害を引き起こす可能性があります。
また、非ステロイド性抗炎症薬は有効成分の種類が多く、特徴も異なるのも特徴で、例えば、アスピリン系・ボルタレン系の薬剤はインフルエンザ脳症になる危険性があるため、インフルエンザの解熱には使用しないなどの注意があります。
ステロイド薬と非ステロイド薬は何が違う?
非ステロイド性抗炎症薬は炎症を起こすロイコトリエンやプロスタグランジンを作る働きを抑制する一方、ステロイド薬はより炎症原因の根本に近いアラキドン酸の働きを抑える効果があります。
そのため、ステロイド薬の方が非ステロイド性抗炎症薬よりも強い効果があるとされています。
また、ステロイド薬の副作用ばかり取り沙汰されることが多いですが、非ステロイド抗炎症薬も長期使用により副作用を引き起こす可能性が高くなるため注意が必要です。
このように炎症を抑える効果についてはステロイド薬の方が高いとされていますが、ステロイド薬と非ステロイド性抗炎症薬は適応症状や剤型が異なるなどの違いもあるため、優劣はつけられません。
カロナールは非ステロイド性抗炎症薬ではない
カロナールはアセトアミノフェンを主成分とした非ピリン系解熱鎮痛剤で、解熱剤として使用される他、頭痛や歯痛、生理痛、腰痛、神経痛などで使用される薬剤です。
アセトアミノフェンは非ステロイド性抗炎症薬と効能は似ていますが、作用機序が異なるため、違う種類の薬剤です。
さらにその効果は非ステロイド性抗炎症薬よりも穏やかであるとされています。
しかしながら、非ステロイド性抗炎症薬は15歳以上が対象であることや、インフルエンザ脳症の関連性が疑われているためインフルエンザの時には使用できないなどの規制がある一方、カロナールであれば小さな子どもが服用できる商品があったり、インフルエンザの解熱剤としても使用できたりするメリットがあります。
例えば、1歳から服用できる顆粒タイプの解熱剤「ムヒのこども解熱鎮痛顆粒」が池田模範堂から販売されており、幅広い年齢層と症状に対応できるのが特徴です。
その他にも日本臓器製薬の「ラックル」は腰痛・神経痛に効く薬剤として、ライオンの「バファリンルナ」は生理痛に効く薬剤として市販されています。
非ステロイド性抗炎症薬の市販の飲み薬
非ステロイド性抗炎症薬は様々な剤型で、薬局やドラッグストア、ネット通販などで市販されています。
ここでは非ステロイド性抗炎症薬の市販の飲み薬を成分別に紹介していきます。
非ステロイド性抗炎症薬の飲み薬には解熱・鎮痛・消炎効果があり、高熱で辛い時や身体の痛みを和らげる目的で使用され、主成分によってアスピリン、イブプロフェン、ロキソニンロキソプロフェンナトリウム、セレコキシブに分類されます。
アスピリン
アスピリンが主成分の市販薬には、ライオンの「バファリンA」や「エキセドリンA錠」、佐藤製薬の「バイエルアスピリン」があり、薬局やドラッグストアで購入できます。
アスピリンは痛み止めや解熱剤として様々な場面で使用されてきた薬剤ですが、インフルエンザ脳症との関連性が示唆されているため、インフルエンザの時には使用しないように気を付ける必要があります。
イブプロフェン
イブプロフェンが主成分の市販薬には、佐藤製薬の「リングルアイビー」やアリナミン製薬の「フェリア」などがあり、頭痛や生理痛などに高い効果が期待できるとされています。
イブプロフェンは単体で使用されるよりも、カロナールの主成分アセトアミノフェンと一緒に配合されているケースが多いのが特徴です。
イブプロフェンが熱や痛みの原因となるプロスタグランジンを抑制し、アセトアミノフェンが脳の中枢に作用するダブルの効果で、薬剤の効果を高めています。
市販薬で言えば、アラクスの「ノーシンアイ頭痛薬」やライオンの「バファリンプレミアム」「バファリンルナi」などが販売されています。
ロキソプロフェンナトリウム
ロキソプロフェンナトリウムは血中への移行が早いため痛みに対して即効性があることと、イブプロフェンやアスピリンよりも鎮痛効果が強い特徴があります。
また、胃の中では薬剤として作用しないプロドラッグであるため、消化器障害などの副作用も軽減できるとされています。
ロキソプロフェンナトリウムが主成分の市販薬には、第一三共ヘルスケアの「ロキソニンS」があります。
また、他の成分も配合された「ロキソニンクイック」はより早い効果を、「ロキソニンSプレミアム」は頭痛に高い効果を示す市販薬として販売されています。
セレコキシブ
セレコキシブはロキソプロフェンナトリウムなどよりも消化器障害の副作用が抑えられているため、服用時の胃腸症状で悩んでいた方でも使用しやすい薬剤です。
また、作用時間が長いことから、1日2回の服用で効果が持続する特徴もあります。
セレコキシブが主成分の薬剤には腰痛や関節痛に高い効果を示す「セレコックス」がありますが、病院で処方される医療用医薬品であるため、薬局やドラッグストアなどの市販薬はありません。
そのため、セレコキシブの薬剤が欲しい時には医療機関の診察を受診するのが基本ですが、それが難しい場合には個人輸入代行のお薬ネットでセレコキシブを主成分とした「コビックス」を購入することも可能です。
コビックスはセレコックスのジェネリック医薬品で、セレコックスと同様に炎症を鎮めて腫れや痛みを抑える効果があります。
世界100ヵ国以上で使用されているメジャーな薬剤であるコビックスは、海外において十分な実績をあげています。
非ステロイド性抗炎症薬とステロイド薬は働く場所が違う
非ステロイド性抗炎症薬は、解熱・鎮痛・消炎効果がある薬で、高熱時や身体の痛み止めとして使用されることの多い薬剤です。
非ステロイド性抗炎症薬がプロスタグランジンやロイコトリエンを作る過程で働きを抑制して作用しますが、ステロイド薬はそれよりも炎症原因の根本に近いアラキドン酸の働きを抑える効果がある点が大きな違いです。
また、非ステロイド性抗炎症薬と同じような効果があるアセトアミノフェンのカロナールは、非ピリン系解熱鎮痛剤で作用機序が異なるため、非ステロイド性抗炎症薬とは違う種類に分類されます。
このように似た名前、似た効能であったとしても分類や適応・副作用などが異なるうえに、同じ系統に属する薬剤であっても少しずつ作用が違い、得意とする症状に差異が出てきます。
このことからも、自分の症状にはどの薬剤が合っているのかを考え、ベストな薬剤を選択していくことが大切と言えるでしょう。