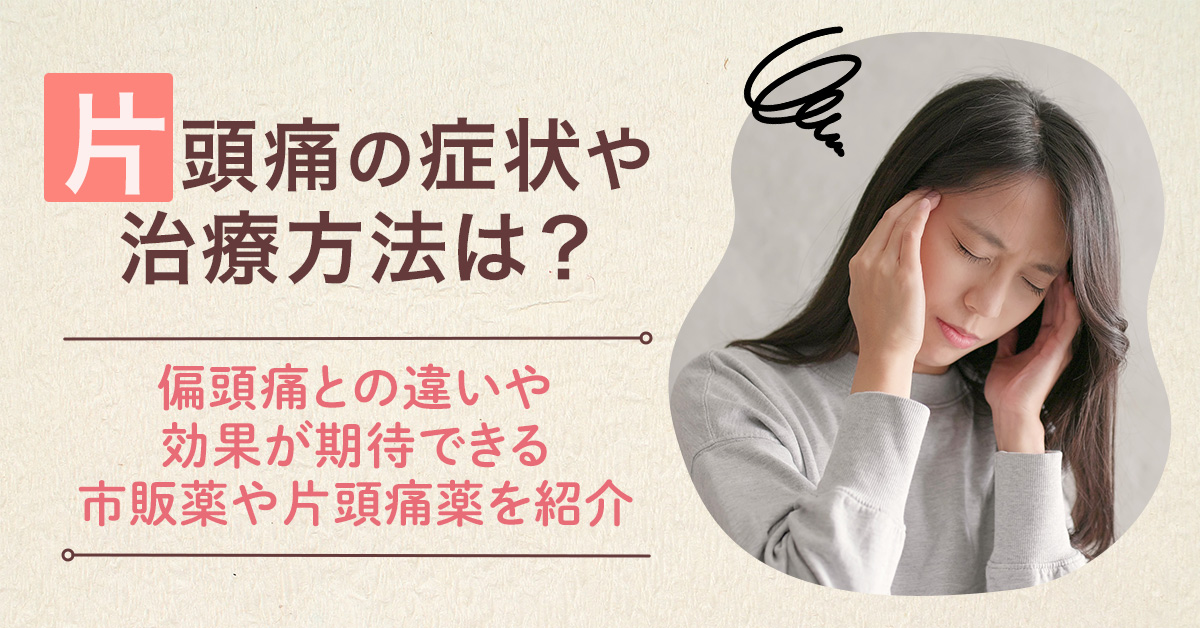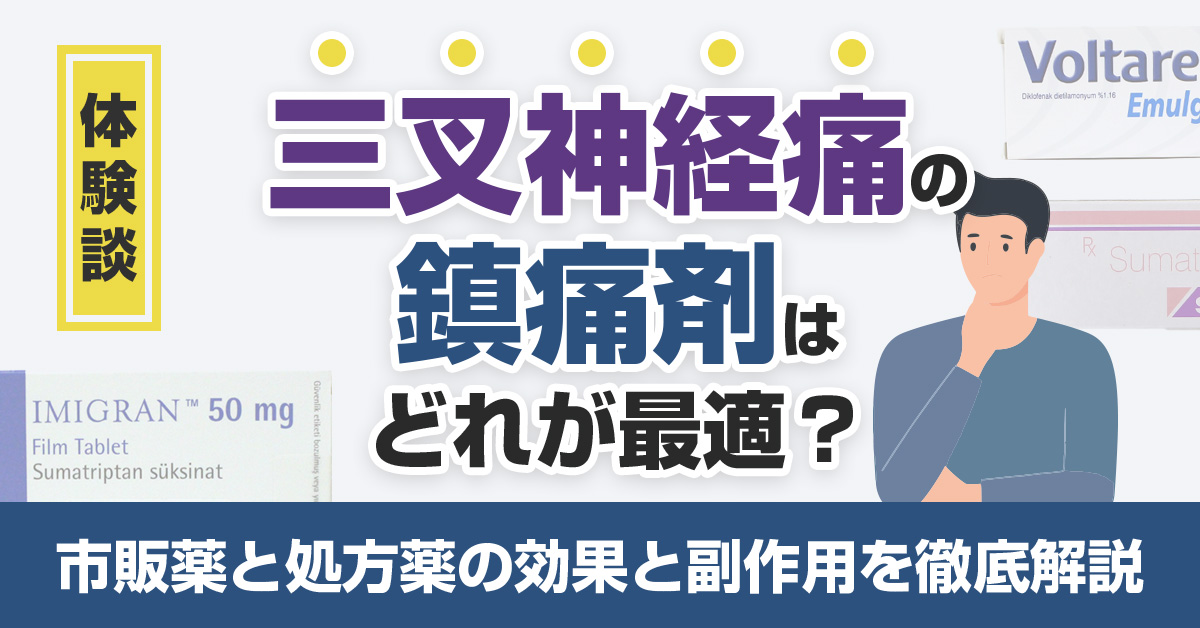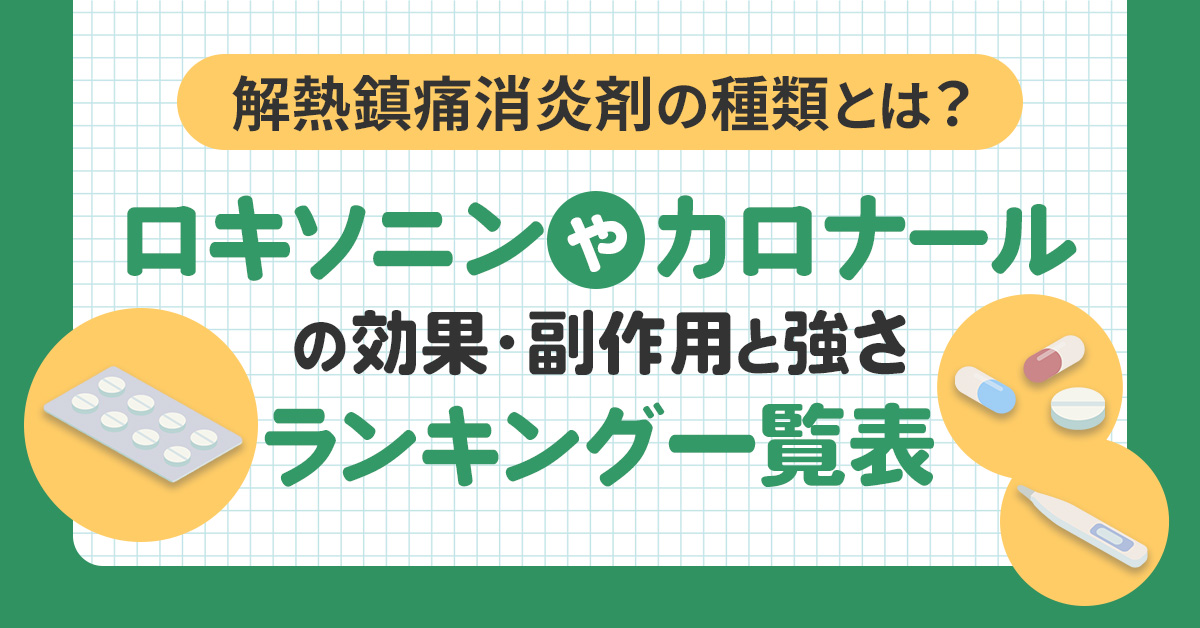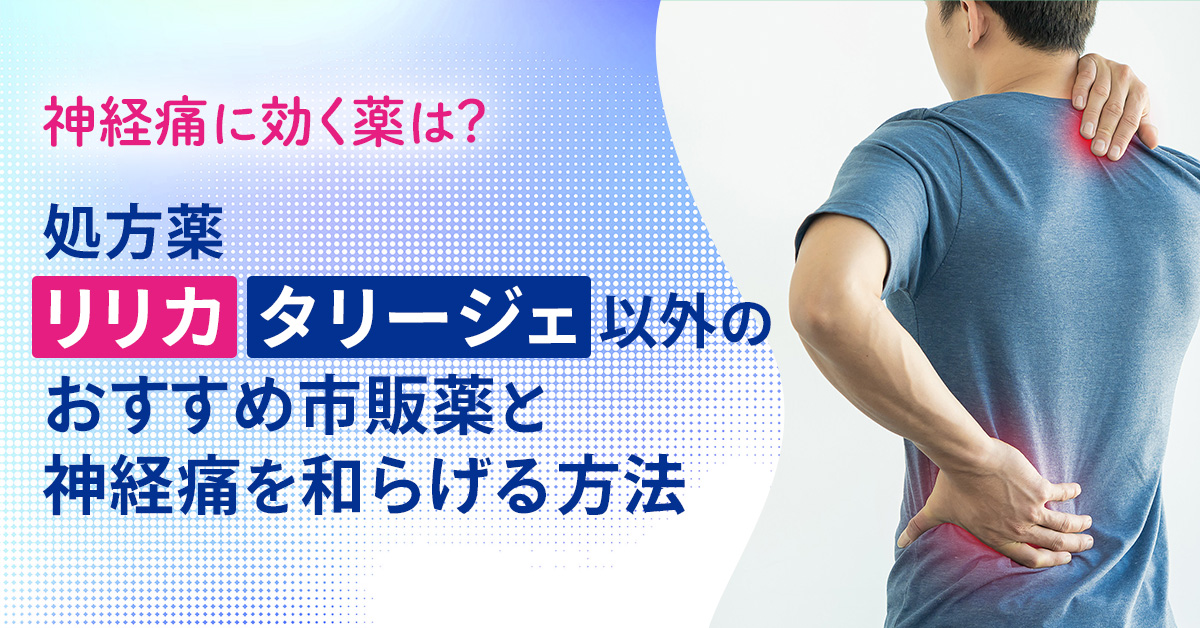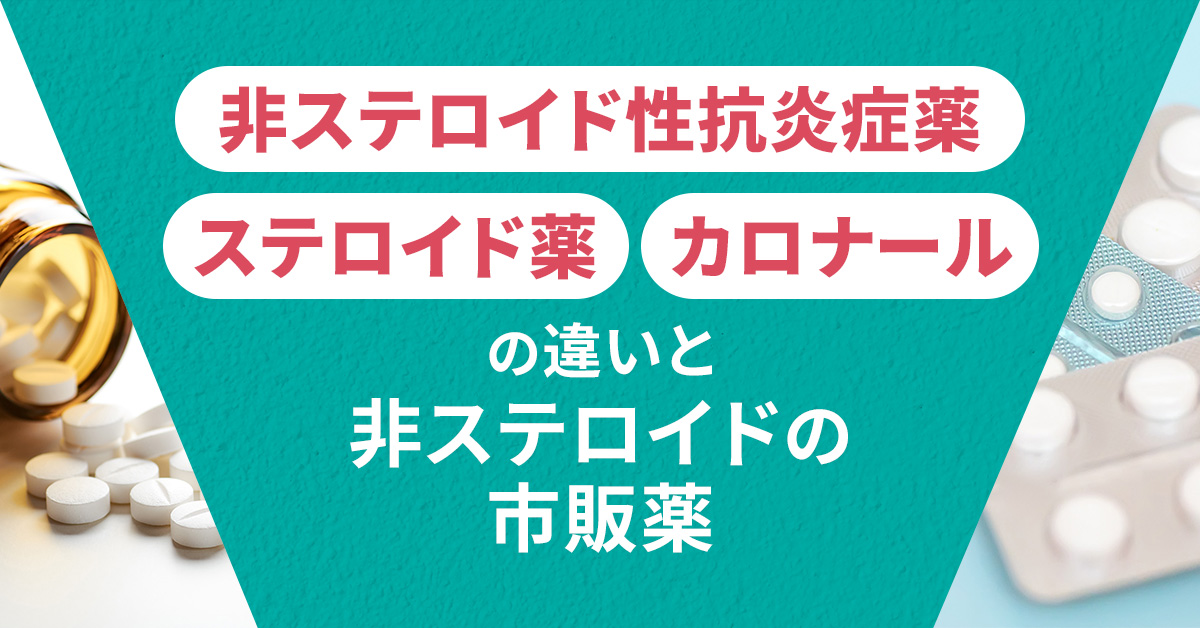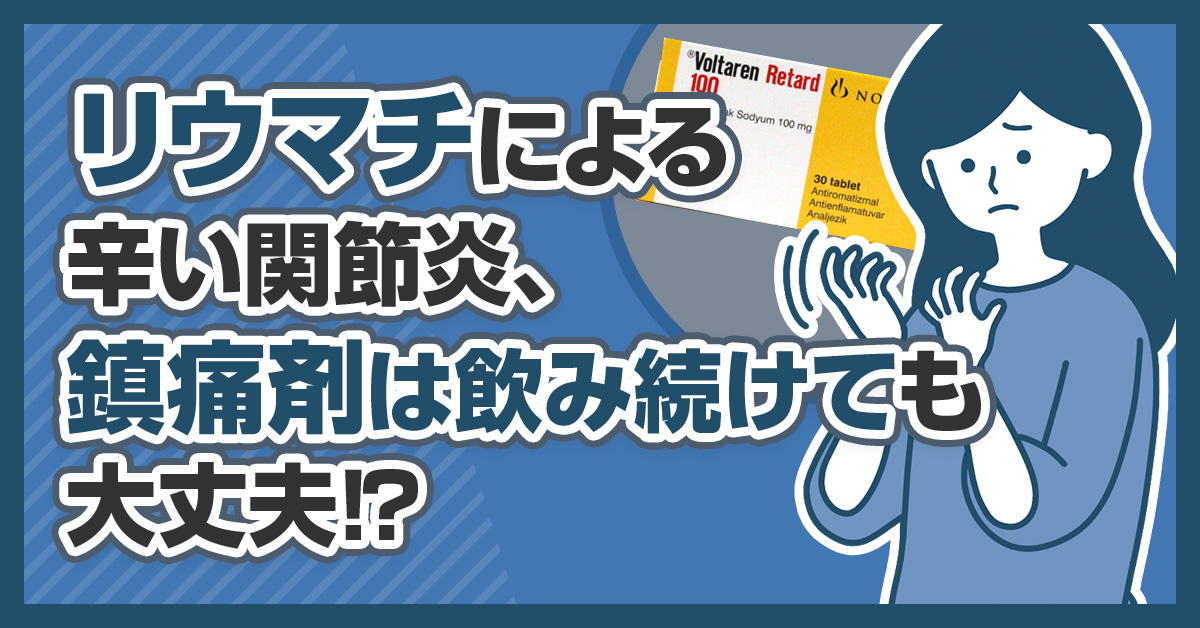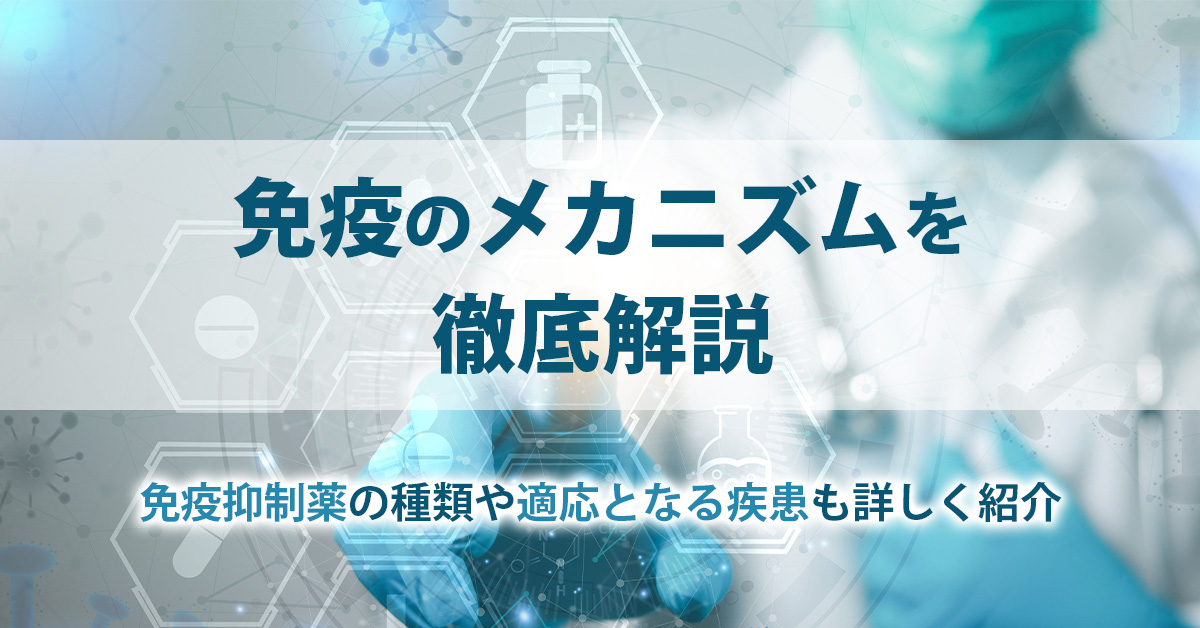打ち身やねんざなどで身体を痛めた時に使用する湿布薬は様々な種類があり、使い分けに悩む方も多いのではないでしょうか。
炎症を抑える成分が布地に塗ってあるという点ではどの湿布薬も同じですが、選ぶべき種類は症状によって異なります。
今回は湿布薬の種類を成分や材質などで分類し、どのように使い分けるべきなのかを解説し、加えて湿布薬の悩みで多いかぶれ対策についてもご紹介していきます。
湿布薬の種類「パップ型」と「テープ型」とは
一口に湿布薬と言っても、様々な製品があり特徴も多種多様です。
適切な湿布薬を使用するためにも大まかな種類を理解し、症状によって使い分けられるようにしておくことが大切です。
湿布薬の剤形は「パップ型」と「テープ型」の大きく2つに分類されます。
パップ型とテープ型は特徴や適応する症状が違うので、自分の症状をよく確認してから使用するようにしましょう。
パップ型とは
パップ型と呼ばれる湿布薬は不織布に水分を多く含んだ軟膏が塗布されている白い湿布薬で、多くの水分を含んでいて肌に優しい反面、はがれやすいのが特徴です。
炎症を抑える作用にプラスして患部を冷やためにメントールやカンフルなどの精油成分が加えられた「冷感タイプ」と、唐辛子の成分を含んだ皮膚の温感に作用する「温感タイプ」があります。
冷感タイプのパップは、打撲やねんざ、肉離れなどの急激な炎症で起こる熱を持った痛みや腫れがある症状に使用します。
これらの症状が起きた時から7日目くらいまでは、冷感パップで対処していくのが一般的です。
温感タイプのパップは、慢性的な肩こりや腰痛などの症状に対して使用します。
これらの症状は患部が硬く凝り固まっていて冷たいことが多いため、温感タイプのパップで血流を促進し温めてほぐしていきます。
ただし、温感タイプのパップは刺激が強く、皮膚がかぶれやすいので使用には注意が必要です。
このように急性の痛みは冷感タイプ、慢性の痛みには温感タイプが適していますが、どちらの症状なのか分からないような場合にはご自身の感覚に頼るしかありません。
氷などで冷やすと気持ち良い時には冷感タイプ、お風呂で温まると気持ち良い時には温感タイプを使用するとよいでしょう。
また、パップは冷たさや温かさが消えてしまうと効いていないように感じるかもしれませんが、炎症を抑える薬効は有効です。
すぐにはがしてしまわず、説明書に記載してある時間までは使用することをおすすめします。
テープ型とは
テープ型の湿布薬は粘着性が高くはがれにくい特徴があるため、関節部分などの動きがある部分で使用するケースが多くなっています。
また、薄茶色の湿布薬で目立ちにくいことから、洋服で隠れにくい部分での使用も好まれます。
テープ型はパップ型と異なり水分がないため、冷感や温感などの温度による違いはありません。
つまりテープ型は、急性の痛み、慢性の痛みのどちらでも使用できるのです。
ただし、粘着力が強いテープ型はパップ型よりも肌への刺激が強く、かぶれやすいというデメリットがあることは覚えておきましょう。
湿布薬の成分種類一覧
湿布薬は剤型による分類だけでなく、主成分も製品によって異なります。
こちらは湿布薬の代表的な主成分と適応症状の一覧表です。
| 主成分 | 適応 |
|---|---|
| ロキソプロフェン | 変形性関節症、筋肉痛、外傷後の腫脹・疼痛の消炎・鎮痛など |
| ケトプロフェン | 腰痛症、変形性関節症、肩関節周囲炎、外傷後の腫れや痛み、関節リウマチの鎮痛など |
| フェルビナク | 変形性関節症、肩関節周囲炎、腱・腱鞘炎、腱周囲炎、上腕骨上顆炎など |
| フルルビプロフェン | 変形性関節症、肩関節周囲炎、腱・腱鞘炎、腱周囲炎、上腕骨上顆炎など |
湿布薬の主成分にはこのような種類があり、適応症状も異なります。
ここからはそれぞれの主成分ごとの効能や副作用、製品名などを具体的に解説していきます。
ロキソプロフェン
ロキソプロフェンは鎮痛解熱剤として知られているロキソニンに配合されている成分で、非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDs)の一種です。
効き目が強いうえに副作用が比較的少ないため、内服薬から外用薬まで幅広く使われています。
ロキソプロフェンが主成分となった第一三共ヘルスケアの市販薬「ロキソニンSテープ」は、皮膚から成分が浸透して炎症を引き起こすプロスタグランジンの合成を阻害し、腰痛や肩こり、関節痛、筋肉痛、腱鞘炎などの腫れや痛みを緩和します。
ロキソニンSテープはテープ型の湿布薬ではがれにくく、1日1回の使用となっています。
汎用性の高い成分ではありますが、15歳未満の子どもには使用できない点には注意してください。
また、副作用には発疹・かゆみ・かぶれなどの皮膚症状や胃部不快感などの消化器症状に加え、稀にアナフィラキシーショックやアスピリン喘息などの重篤な副作用が起きる可能性があります。
使用中に違和感が現れた時には、医師や薬剤師に相談しましょう。
ケトプロフェン
ケトプロフェンはモーラステープの主成分で、ロキソプロフェンと同じく非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDs)の一種です。
痛みや炎症を引き起こすプロスタグランジンを阻害して痛みを緩和するという効能の面もロキソプロフェンと同じです。
ケトプロフェンが主成分となった久光製薬の「モーラステープ」は、腰痛や肩こりなどの湿布薬が使用される一般的な症状に加え、関節リウマチの痛み止めとしても使用されるのが特徴です。
また、モーラステープの効果時間は24時間なので、1日1回の貼付でよいのも利便性が高いと言えるでしょう。
ただし、モーラステープは市販されていないため、手に入れるためには病院を受診し処方してもらうようになります。
副作用にはかぶれなどの皮膚症状の他に、光線過敏症やアスピリン喘息が起こる可能性があります。
特に光線過敏症はモーラステープの特徴的な副作用であり、モーラステープを貼っていた部分に日光が当たると赤みやかゆみなどの炎症を起こしてしまう可能性があります。
モーラステープをはがした後であっても成分が皮膚に残留していれば炎症を起こす恐れがあるため、貼付した場所には日光が当たらないように洋服やサポーターなどで隠してください。
フェルビナク
フェルビナクもロキソプロフェンやケトプロフェンと同じく非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDs)の1つで、炎症を引き起こすプロスタグランジンの合成を阻害する作用があります。
効果の強いロキソプロフェンやケトプロフェンよりもやや穏やかな分、コスパに優れているメリットがあります。
フェルビナクを主成分とした久光製薬の「フェイタスシップ」は伸縮自在な冷感タイプのパップで、かぶれが気になる方にも使用しやすいのが特徴です。
副作用には発疹・かゆみなどの皮膚症状と重篤な副作用としてアナフィラキシーショックがあります。
また、15歳未満の子どもや妊娠している可能性がある方には使用できない点にも注意が必要です。
フルルビプロフェン
フルルビプロフェンも他の成分と同様にプロスタグランジンの合成を抑える非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDs)の1つです。
薬剤の強さはロキソプロフェンとほぼ同じと考えられていますが、成分がより吸収されやすい性質で飲み薬に近い性質を持っているのが特徴です。
そのため、フルルビプロフェンを貼付した際は、薬剤の飲み合わせにも注意しなければならないことは覚えておきましょう。
フルルビプロフェンが主成分の湿布薬には大正製薬の「ロコアテープ」がありますが、市販されていないため、病院で処方してもらう必要があります。
貼付は1日1回で、患部が複数あったとしても最大で2枚を超えないようにしてください。
副作用にはかゆみ・発疹などの皮膚症状に加え、重篤な副作用としてアナフィラキシーショック、アスピリン喘息などを引き起こす恐れがあります。
また、成分が体内に吸収されやすい性質があるため、他の消炎鎮痛剤との併用は避けてください。
湿布薬のかぶれの対策法
患部に貼付するだけで痛みなどの症状を緩和してくれる湿布薬ですが、よくある悩みとして挙がるのが「かぶれ」です。
ここでは湿布薬を使用する時に、できるだけかぶれにくくする方法と、万が一かぶれてしまった時に早く治す方法を紹介します。
湿布薬でかぶれない方法
湿布薬でかぶれてしまうのは主に副作用によるものですが、工夫によってかぶれにくくすることも可能です。
かぶれは以下のようなものが原因となることが多いと考えられています。
- 汗や蒸れ
- 長時間の使用
- 成分によるもの
汗や蒸れなどで皮膚に刺激が起きてバリア機能が落ちた時には、湿布薬の刺激に対しても反応が起きやすいです。
汗をかいたらはがして、再度貼る時には汗が引いて水分をしっかりふき取って貼り直すようにしましょう。
この時湿布の1日の貼付枚数の上限を超えないように気をつけてください。
長時間の使用もかぶれの原因となります。
長時間貼っている方が効きそうに感じますが、1日1回貼付の湿布薬であれば、約8~10時間ではがしても皮膚に浸透した効果が持続すると言われています。
さらに1日2回の湿布薬であれば、約4~6時間でよいとされています。
かぶれやすい方は長時間貼り続けることは避けて、適度に間隔を空けながら使用するようにしましょう。
また、成分によっても体質に合う・合わないがあります。
かぶれに悩んでいた方でも、別の湿布薬に変えた途端、かゆみが治まるようなケースもあります。
テープ型でかぶれる時にはハップ型に変えてみるなど、工夫をするとよいでしょう。
モーラステープの主成分であるケトプロフェンは貼っていた場所に日光が当たるとかぶれる副作用があります。
モーラステープを使用した後は、洋服などで患部が日光に当たらないような工夫をしてください。
湿布薬かぶれを早く治す方法
湿布薬でかぶれてしまった時にはまず原因となっている湿布薬をはがし、かゆみがあれば保冷剤などで患部を冷やして落ち着かせます。
もし、かぶれやかゆみが酷い場合には、医療機関を受診し、炎症を抑えるステロイド薬や抗ヒスタミン薬などを処方してもらうことで比較的早く治すことが可能です。
湿布薬の種類を知って上手に使い分けよう
湿布薬には水分を多く含んだ白いパップ型と、粘着力が強い茶色いテープ型の2種類の剤型があります。
さらにパップ型には急性の痛みに適した冷感タイプと、慢性の痛みに適した温感タイプの2つに分類されます。
製品ごとに主成分も異なり、多くのものは筋肉痛や変形性関節症などに適応していますが、モーラステープの主成分であるケトプロフェンに関しては関節リウマチの鎮痛にも適応しているのが特徴です。
しかしながら、湿布薬のかぶれは多くの人が悩む副作用となっており、長時間貼り続けないなど工夫しながら使用していく必要があります。
身近な薬である湿布薬を上手に使い分けて、生活の質を上げていきましょう。