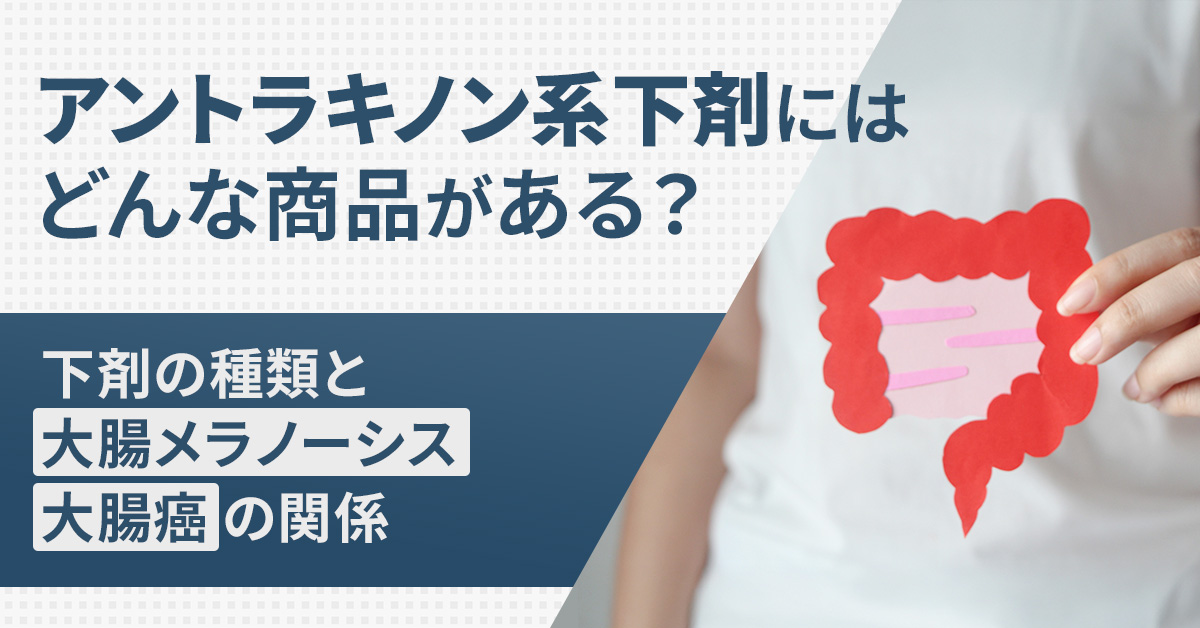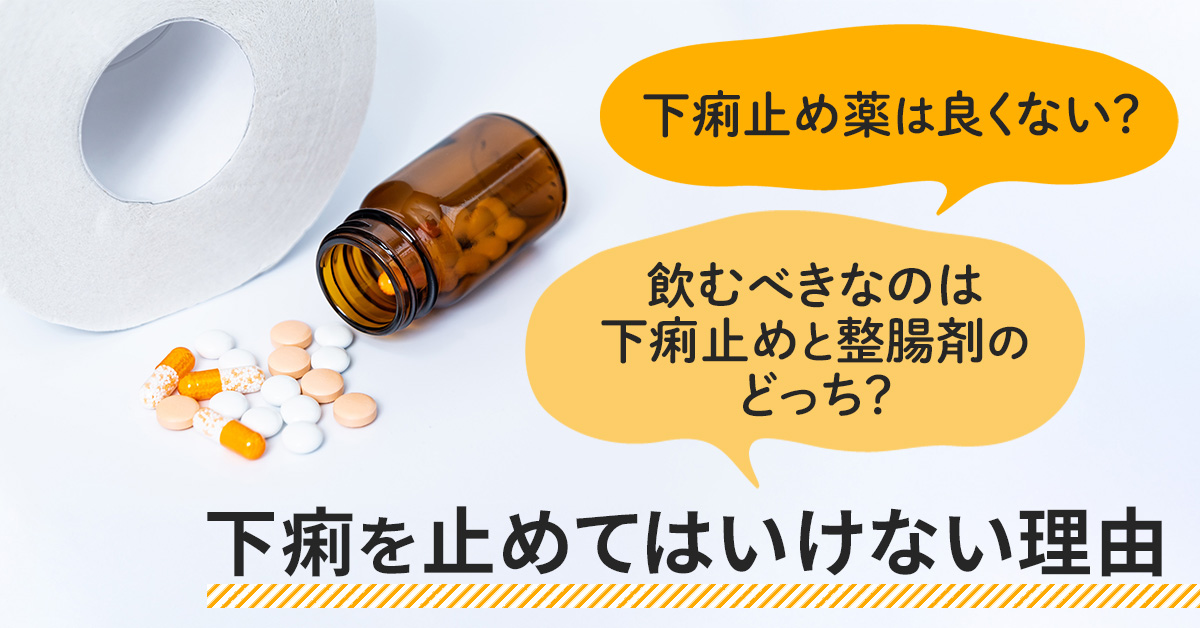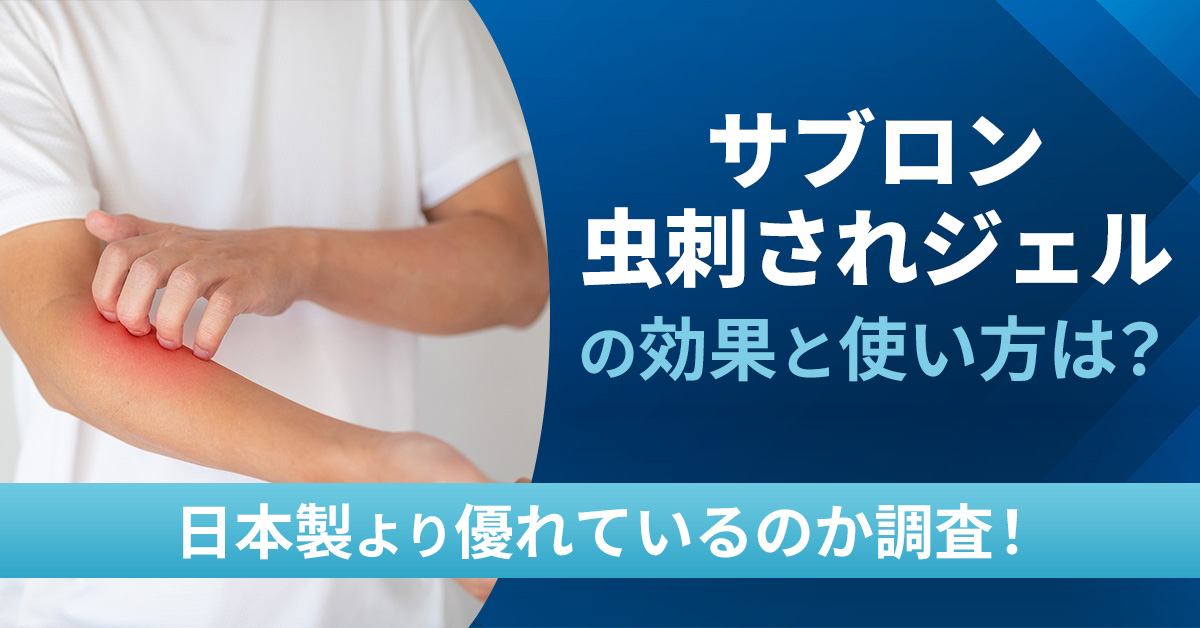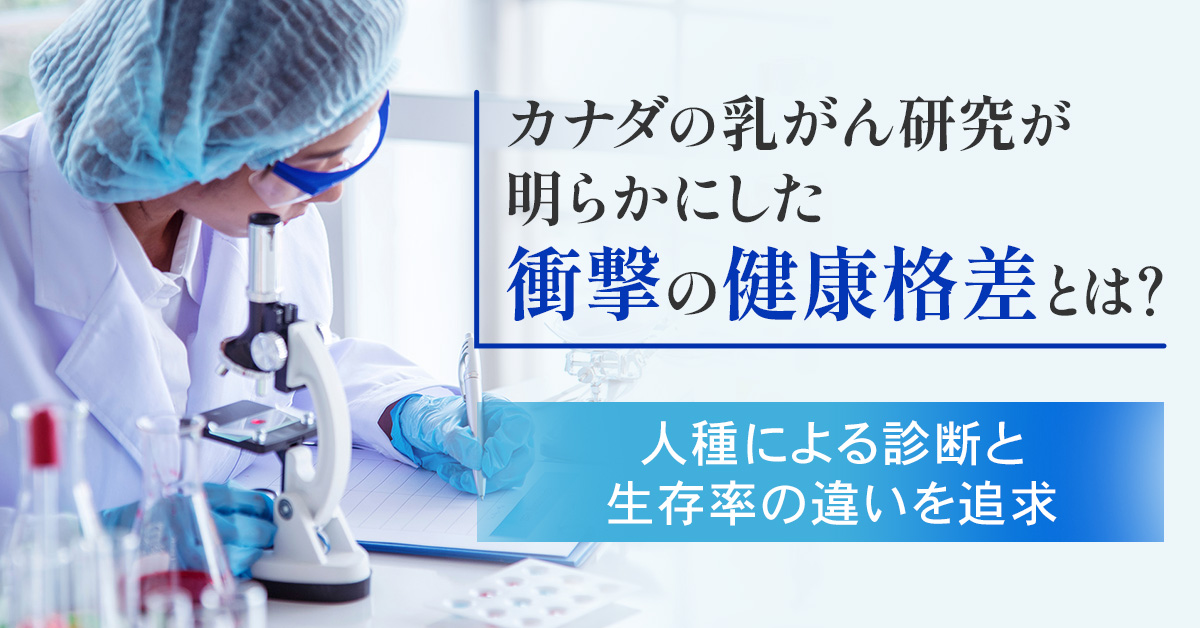喉の痛みの緩和や感染症予防の一環として使用されるうがい薬には複数の種類があり、効能や適応する症状に違いがあることはご存知でしょうか。
今回はよく耳にするイソジンうがい薬とアズノールうがい液の違いや症状別のおすすめうがい薬について解説していきます。
日々何となく使用しているうがい薬の知識をアップデートしていきましょう。
うがい薬の種類と効能・副作用
うがい薬は、イソジンなどのポビドンヨードを主成分とする茶色のうがい薬と、アズノールなどのアズレンスルホン酸ナトリウム水和物を主成分とする青色のうがい薬の大きく2つに分類されます。
ここでは、分かりやすいようにポビドンヨードのうがい薬をイソジン、アズレンスルホン酸ナトリウム水和物のうがい薬をアズノールとして解説していきます。
イソジン(ポビドンヨード)
イソジンに含まれるポビドンヨードは、昆布やワカメなどの含有物であるヨードというミネラルを、ポリビニルピロリドンを加えて毒性を下げ水に溶けるように調合した成分です。
ヨードと聞くとうがい薬のイメージが強いかもしれませんが、手術の際の手洗いや傷の殺菌にも使われる殺菌消毒剤の有効成分の一つとされています。
幅広い細菌やウイルスに効果があるイソジンは、インフルエンザやおたふく風邪、風疹などの感染症予防にも有効なうえに、ノロウイルスやサルモネラ菌などの食中毒の原因菌に対しても効果を発揮します。
このように優れた殺菌効果と即効性があるイソジンは、口腔内の消毒や感染症予防で使用するのに向いているうがい薬です。
イソジンの副作用はほとんどありませんが、万が一かゆみを感じるような時は医療機関に相談しましょう。
また、ごく稀にアナフィラキシーショックを起こす可能性があるため、ヨードアレルギーがある方は使用を控えてください。
妊娠中の方も、新生児の甲状腺機能低下症が起きる恐れがあるため、使用しないようにしましょう。
アズノール(アズレンスルホン酸ナトリウム水和物)
アズノールに含まれるアズレンスルホン酸ナトリウム水和物は、アレルギー反応の原因となるヒスタミンを抑制する効果があり、口腔内や喉の粘膜に直接作用して炎症をしずめます。
アズレンスルホン酸ナトリウム水和物を含むうがい薬はアズノールの他に、アズレンやアズレイ、アーズミンなどの名称の製品があり、製品によって粉末・錠剤・液体の剤型があります。
ただし、どの形であっても効能は変わらず、水に溶かしてうがいをする点も同じです。
また、イソジンが消毒や感染症予防に向いているのに対し、アズノールは患部の炎症を和らげて治癒を促進させる効果が高いという違いがあります。
そのため、風邪などで喉が腫れているような症状の改善に使用されることが多いです。
穏やかな抗炎症薬であるため、副作用の心配はほとんどないと言えるでしょう。
アズノールに関しては妊娠中の使用も問題ないとされています。
「うがい薬はよくない」と言われる理由
インターネット上には「うがい薬はよくない」というコメントが見受けられることがありますが、それは一体どうしてなのでしょうか。
これにはいくつか理由があるようです。
まず、イソジンに含まれているヨードを過剰に摂取することが甲状腺機能の低下を招く恐れがあるためです。
ヨード(ヨウ素)は人間の身体に必要な栄養素ですが、1日の推奨量0.13mgに対して、イソジンで1日3回うがいをすると平均4mgのヨードが吸収されていることが分かりました。
この条件で毎日習慣的にイソジンを使用してうがいをするとヨードの1日の推奨量を大きく超えるため、甲状腺機能の低下を引き起こす可能性が示唆されているのです。
2つ目が、ポビドンヨードは人間に害を及ぼすウイルスだけでなく、もともと口の中にいる常在菌も殺菌してしまうため、かえって防御力が低下してしまう可能性があるという理由からです。
過去に行った研究によれば、イソジンでうがいをした人よりも水道水でうがいをした人の方が風邪にかかりにくかったというデータもあります。
また、長期間使用を続けて口腔内の常在菌のバランスが崩れると、従来存在しなかった菌が住み着いてしまう可能性があります。
その結果、喉にカビが生えてしまうようなケースもあることが分かってきたようです。
これらの理由からも、特に問題がない場合に習慣的に、そして長期的にうがい薬を使用するのは避けた方が無難であると考えられます。
しかしながら、うがい薬は殺菌・治癒力が高い薬であることは変わりないので、喉が痛い時や感染症の心配がある時などに上手に使用していくのが賢い使い方であると言えるのではないでしょうか。
症状別おすすめのうがい薬
ここからは症状別おすすめのうがい薬を紹介していきます。
市販薬の一例も挙げるので、購入時の参考にしてください。
感染症を予防したい時
感染症を予防したい時には、殺菌効果の高いポビドンヨードが配合されたうがい薬が向いています。
塩野義製薬の「イソジンうがい薬C」や明治の「明治うがい薬」がポビドンヨード入りのうがい薬です。
ただし、先ほどもお伝えしたように日常的にポビドンヨードうがい薬を使用し続けることについては様々な意見があるのも事実です。
そのため、感染症予防という観点から常用的に使用するというより、家族が感染症を発症した時や、人混みに出掛けて不安がある時などに使用するくらいが良いのかもしれません。
また、ポビドンヨードに不安がある方やヨードアレルギーの方は、塩化セチルピリジニウムが主成分となった興和の「新コルゲンうがいワンプッシュ」がおすすめです。
塩化セチルピリジニウムは優れた殺菌効果があり、うがい薬の他にトローチなどに採用されている成分で、喉の細菌の増殖を抑制して炎症を和らげるとされています。
喉が痛い時
喉が痛い時には炎症を抑える効果があるアズレンスルホン酸ナトリウム水和物が主成分のうがい薬を選ぶと良いでしょう。
浅田飴の「浅田飴AZうがい薬」や白金製薬の「パープルショットうがい薬F」はアズレンスルホン酸ナトリウム水和物が配合されたうがい薬です。
ただし、喉の痛みが続く時や高熱などの他の症状がある場合には、医療機関を受診するようにしましょう。
扁桃炎の時
扁桃炎の時は医療機関を受診して適切な処置を受けることがベストですが、それが難しい場合には市販のうがい薬で炎症を抑え、殺菌していきましょう。
これまで紹介したポビドンヨードのイソジンも、アズレンスルホン酸ナトリウム水和物のアズノールも扁桃炎に適応するうがい薬です。
そのため、塩野義製薬の「イソジンうがい薬C」などのポビドンヨード系、浅田飴の「浅田飴AZうがい薬」などのアズレンスルホン酸ナトリウム水和物系のどちらを選んでも問題ありません。
うがい薬を使った正しいうがいの方法
「うがい薬を使用したのにあまり効かない」と感じたことはありませんか?
それはもしかしたら、うがい薬の使用方法が間違っていたのが原因かもしれません。
うがい薬を使った正しいうがいの方法を知って、効果的に殺菌していきましょう。
- 手をきれいに洗う
- 規定の量を守ってうがいを希釈する
- ブクブクうがいをする
- ガラガラうがいをする
手に付いている殺菌やウイルスが口の中に入らないように、はじめに手洗いをして殺菌を落とします。
次に清潔なコップを使用して、うがい薬を希釈していきます。
この時に大切なのは、うがい薬の濃度を規定通りに希釈することと、希釈したらすぐに使用することです。
うがい薬の希釈濃度は薬によって異なるので、商品説明書の記載通りの量に薄めるようにしてください。
また、希釈液は作り置きせずにうがいの都度用意するようにしましょう。
ここでようやくうがいの開始です。
ただし、いきなり喉を殺菌するガラガラうがいをするのではなく、先に口内を洗浄するブクブクうがいを行い、汚れや食べかすを落としていきます。
希釈したうがい薬を口に含み、左右交互に約15秒ブクブクうがいをしていきます。
最後に喉を殺菌するガラガラうがいをします。
希釈したうがい薬を口に含み、上を向き15秒適度のガラガラうがいを2回繰り返します。
これでうがいの一連の流れは終了です。
このように正しいうがいをすることにより、うがい薬の十分な殺菌効果が得られるのです。
うがい薬の代わりになるもの
喉の健康を守るうがい薬ですが、災害などにより手に入らない時には身近なものがうがい薬になると考えられています。
- 塩
- お茶
- 紅茶
塩は喉への刺激を和らげるとともに痛みも緩和する効果があると言われています。
ただし、塩の入れすぎは逆に刺激を強くしてしまうので、しょっぱくないくらいの濃度で使用してください。
お茶や紅茶に含まれているカテキンにも殺菌作用があると言われており、お茶うがいを推奨する小学校などもありますが、お茶うがいは温度と時間に気を配ることが大切です。
お茶うがいでは火傷防止のために人肌くらいまで冷ましたものを使用すること、水よりも雑菌が?殖しやすいために作り置きはしないことを守りましょう。
また、感染症などの病気を発症している時には勝手な判断はせず、医療機関を受診するか市販のうがい薬を使用するようにしてください。
うがい薬は用法用量を守って正しく使おう
うがい薬には、イソジンをはじめとするポビドンヨードが主成分のものと、アズノールなどのアズレンスルホン酸ナトリウム水和物が主成分のものがあります。
殺菌が高いイソジンは感染予防に、炎症を抑える効果が高いアズノールは喉の痛みの緩和と、症状によって使い分けることが大切です。
また、うがい薬の効果を十分に得るためには、用法用量を守って使うことが重要です。
特に希釈濃度を商品説明書の記載通りにすることが大切になります。
正しくうがい薬を使用して、喉の健康を保っていきましょう。