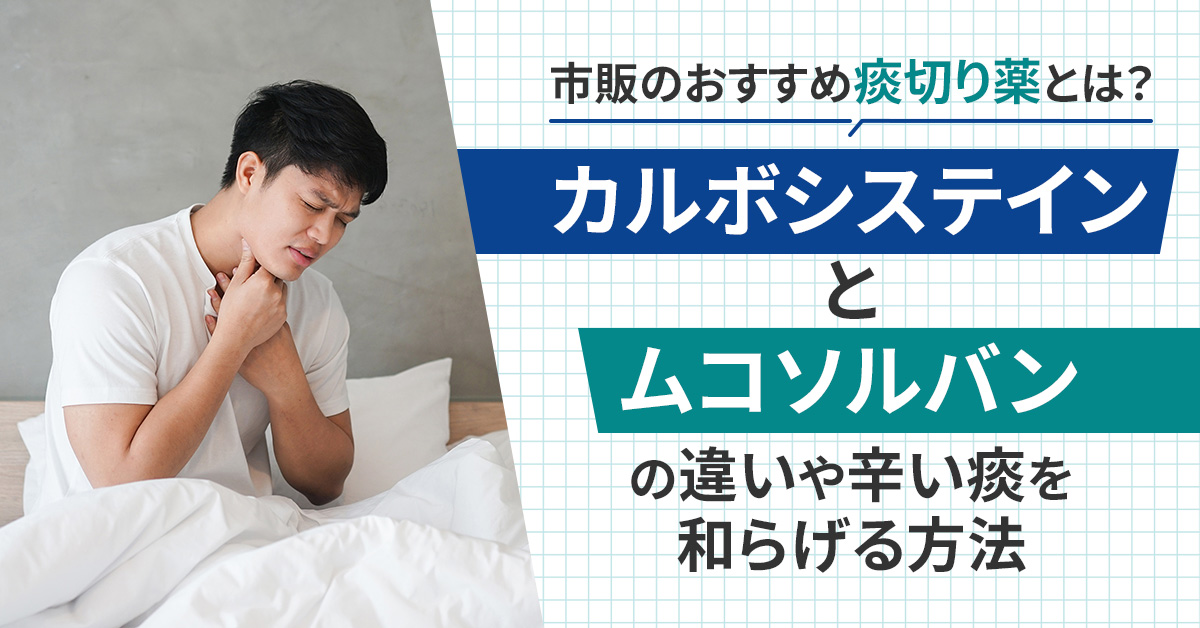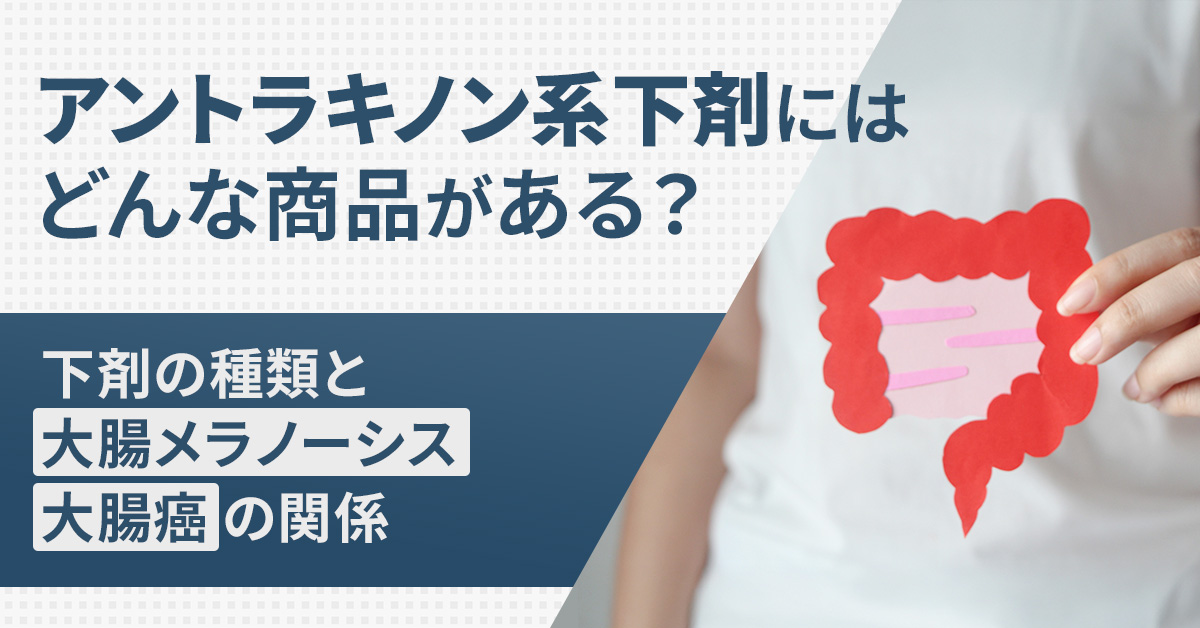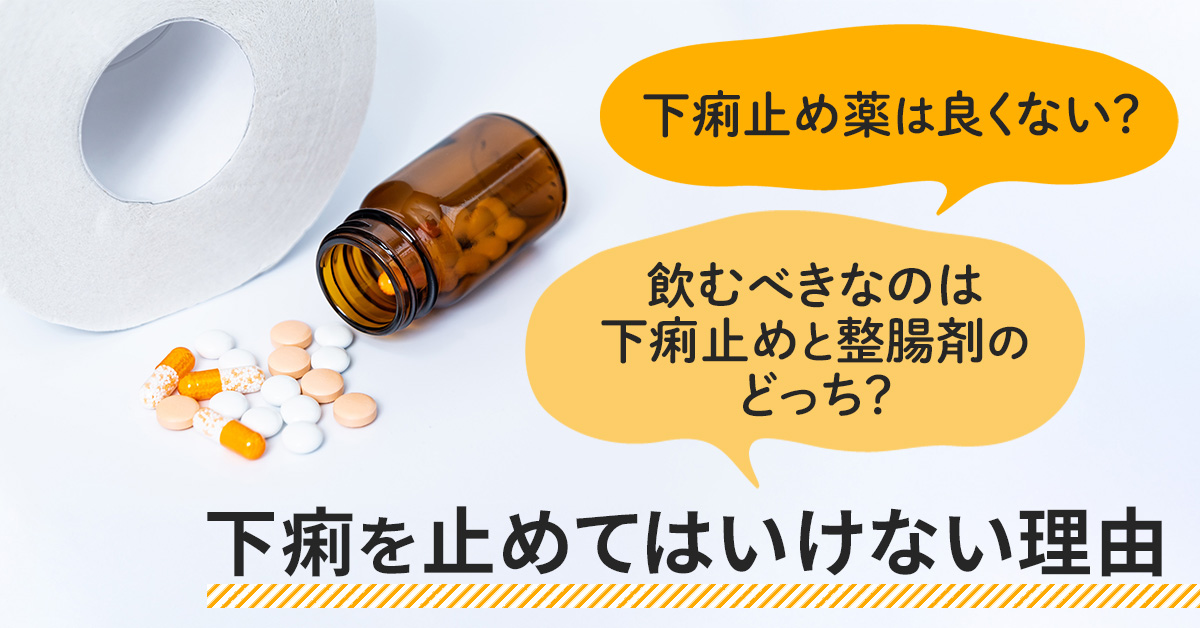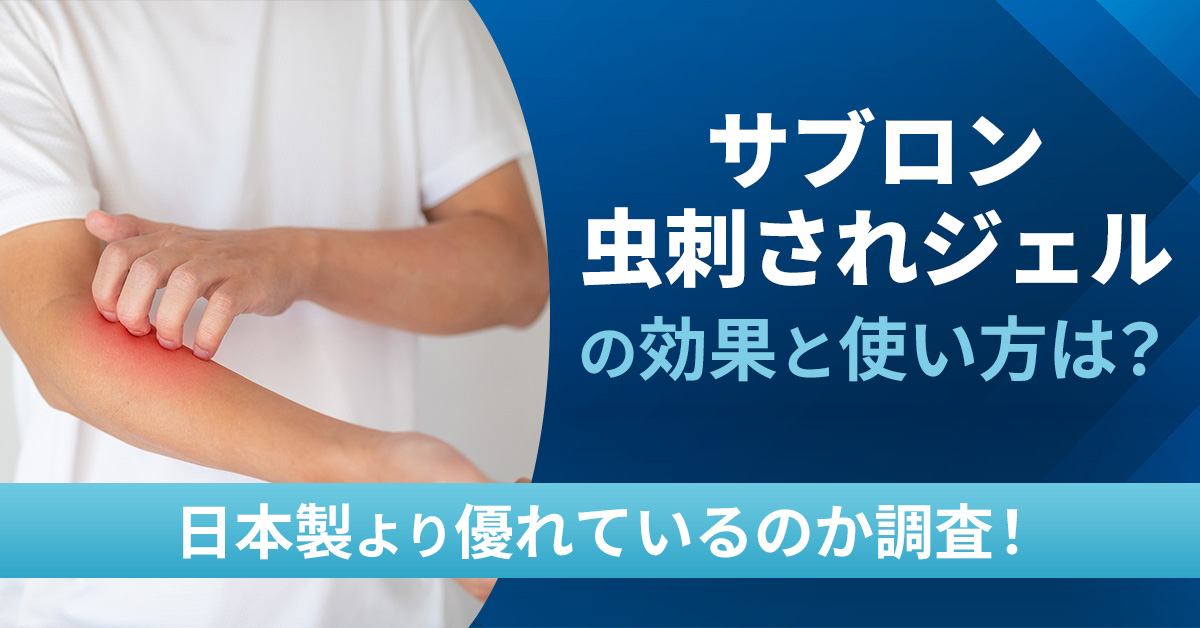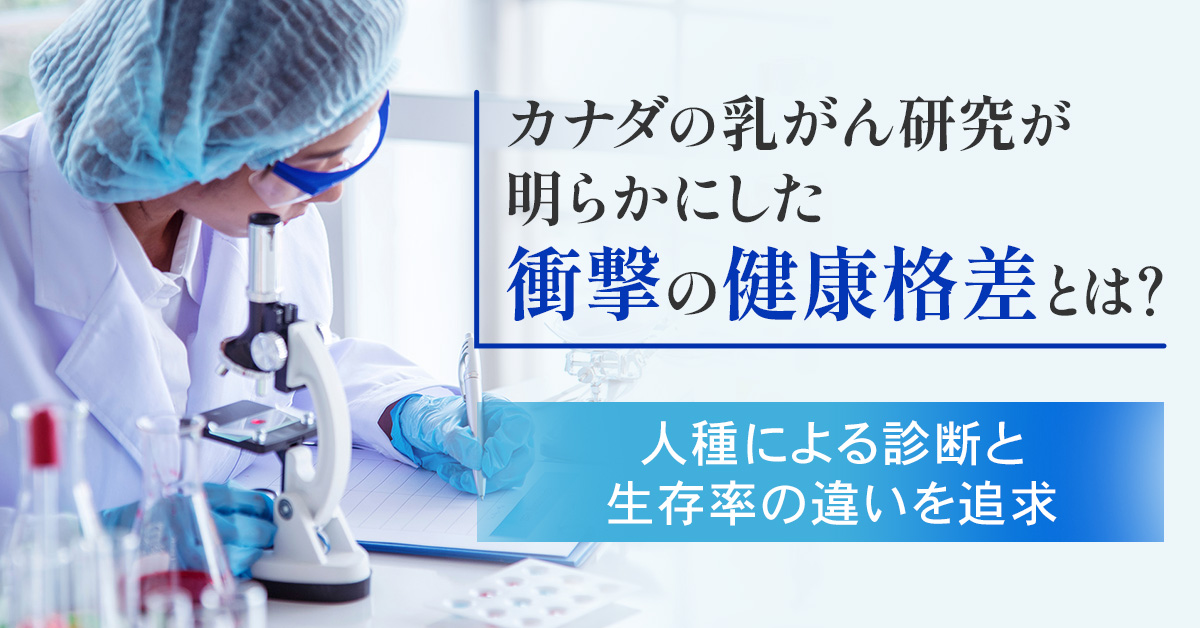喉にへばりつく不快な症状である痰は、体内に入ったウイルスや細菌、埃などを体外に排出する身体の働きの1つです。
大切な身体の働きではありますが、粘り気が増した大量の痰が喉に張り付くようになると、気道が狭くなり呼吸も辛くなってしまいます。
今回はこの辛い痰を切りやすくするおすすめの市販薬と、痰の症状を和らげる方法について解説していきます。
痰切り薬の種類と効果・副作用
風邪を引いた時などに増える痰は、気道が狭くなって呼吸が辛くなるだけでなく、体内で菌を繁殖させてしまう恐れがあるため、できるだけ体外に排出した方が良いと言えます。
痰を出したり、痰切れを良くしたりする方法はいくつかありますが、中でも痰切り薬の利用は効果的です。
ここでは痰切れを良くする一般的な痰切り薬の種類や効果、副作用を紹介していきます。
L-カルボシステイン
主成分をL-カルボシステインとした痰切り薬には、先発薬にムコダイン、後発品にカルボシステインがあります。
剤型には顆粒や錠剤、シロップなどが開発されており、子どもでも服用しやすいよう工夫されています。
L-カルボシステインは痰切り薬の中でも、痰の量を減らしたり、痰自体の粘り気を抑えたりする効果があり、身体が痰を体外にスムーズ排出できるような手助けをしてくれます。
さらに、繊毛運動の機能を改善する働きがあるため、中耳貯留液が溜まる中耳炎や、タバコが原因で起こる慢性気管支炎に対しても利用されることの多い薬剤です。
L-カルボシステインは副作用の少ない薬剤ではありますが、肝障害の報告があることからや長期服用する場合や肝機能に障害を抱えている方は注意が必要です。
また、稀に発疹や痒みなどの皮膚障害、アナフィラキシーショックなどの症状が起きる可能性もあるため、服用後の様子に気を配るようにしてください。
アンブロキソール塩酸塩
アンブロキソール塩酸塩を主成分とした去痰剤には、先発薬ムコソルバンをはじめとした顆粒・錠剤・カプセル・OD錠・シロップなどの多種多様な剤型が開発されています。
アンブロキソール塩酸塩もL-カルボシステインと同様に子どもも服用できる痰切り薬です。
アンブロキソール塩酸塩は気道の繊毛運動を改善して気道粘膜を潤滑にしたり、肺胞を膨らみやすくしたりして特に喉にへばりつく痰に高い効果を発揮し、感染症や気管支炎、喘息の去痰、副鼻腔炎の排膿などに適応するとされています。
また、明け方の痰絡みを和らげる効果が高いため、夕食後の服用を指示される方が多いのもこの薬剤の特徴と言えるでしょう。
アンブロキソール塩酸塩の主な副作用には、胃痛や吐き気、下痢などの胃腸障害と発疹や蕁麻疹、かゆみなどの皮膚症状の報告があります。
重篤な副作用として稀ではありますがアナフィラキシーショックや重い皮膚症状が起きる可能性もあるため、違和感がある時には医療機関に連絡してください。
同じ痰切り薬の仲間であるL-カルボシステインとアンブロキソール塩酸塩は作用にかなりの違いがあるため、併用して使用することが可能となっています。
痰がらみが強い場合にはこの2つの痰切り薬を併用し、辛い症状を緩和していくこともあります。
ブロムヘキシン塩酸塩
ブロムヘキシン塩酸塩を主成分とした去痰剤は、製品名もブロムヘキシン塩酸塩という名称で錠剤・シロップなどの剤型が開発されています。
痰を薄め粘り気を取って体外に排出しやすくする効果と、気道の繊毛運動を良くする効果のある痰切り薬です。
ただし、慢性副鼻腔炎や蓄膿症の排膿にはあまり適しておらず、さらに粘性の低い痰に使用するとサラサラになりすぎて痰が出しにくくなるため、粘性が高い痰に限定して使用されることが多くなっています。
痰が薄まることにより量が増えてしまう可能性や、吐き気や発疹などの症状が起きる副作用があります。
重い副作用にアナフィラキシーショックあるため、服用後の様子に注視することが大切です。
漢方薬
漢方は体内の気・血・水がバランス良く巡ることで健康が保てるとされ、身体に悪い症状が起きている時はどれかのバランスが崩れていると考えられています。
漢方では水の排出に問題がある時に痰や鼻水などの症状が起きることから、水に作用する小青竜湯や清肺湯、五虎湯漢方薬で体調を整えます。
小青竜湯の配合成分は麻黄・桂皮・芍薬・半夏・五味子・細辛・乾姜・甘草で、うすい水様の痰や鼻水に適しており、気管支炎や気管支喘息に加え、鼻炎や花粉症の治療にも使用されています。
副作用には胃腸症状などがあり、ごく稀に偽アルドステロン症と呼ばれるむくみや血圧上昇などの症状や間質性肺炎、肝臓障害などが起こる恐れがあります。
清肺湯は麦門冬・天門冬・杏仁・桔梗・貝母・桑白皮・陳皮・黄ごんなどを配合した漢方薬で、喉や気管の炎症を和らげて痰を出しやすくします。
特に黄緑色の粘り気のある痰に効果があり、痰を伴う咳が続いている場合に使用するケースが多いです。
副作用には胃腸症状や発疹・かゆみなどの皮膚症状、ごく稀に重篤な副作用として間質性肺炎、肝臓障害、腸間膜静脈硬化症が報告されています。
五虎湯の配合成分は麻黄・杏仁・甘草・石膏・桑白皮で、気管支を広げて呼吸を楽にすることから、感染症などによる黄色い粘り気のある痰に有効な漢方薬とされています。
胃腸症状や動悸などの副作用に加え、偽アルドステロン症などの重い副作用が稀に見られます。
また、漢方薬は自然の木や草を使用した生薬ですが、飲み合わせに注意が必要となる場合があります。
他に飲んでいる薬剤がある場合には、医師や薬剤師に相談してください。
スプレー
痰切り薬にはスプレータイプの製品もあります。
例えば、小林製薬から販売されている「ダスモックSP」は、喉にスプレーするだけなので、外出先でも気軽に使用できるメリットがあります。
ただし、痰切りスプレーと痰切り内服薬や風邪薬との併用はできない点には注意が必要です。
副作用は発疹やかゆみなどの皮膚症状や吐き気・嘔吐などの胃腸症状があり、稀に起きる重篤な副作用にはアナフィラキシーショックが挙げられています。
おすすめの痰切り市販薬5選
これまで痰切り薬の種類や効果について解説してきましたが、では実際の市販薬にはどのようなものがあるのでしょうか。
ここでは、子どもが服用可能なものを中心におすすめの市販の痰切り薬を紹介していきます。
ストナ去たんカプセル
佐藤製薬から販売されている「ストナ去たんカプセル」は、有効成分であるL-カルボシステインとブロムヘキシン塩酸塩が配合された粘り気のある痰に効果的な市販の痰切り薬です。
8歳の子どもから服用できる去痰薬で、8~14歳は1回1カプセル、15歳~は1回2カプセルを1日3回服用します。
新フステノン
「新フステノン」はエスエス製薬が開発した有効成分L-カルボシステインを含む市販の痰切り薬です。
咳止め効果のある成分も配合されており苦しい咳の強い味方となりますが、眠気を引き起こすことがあるため、服用後の運転や機械操作は避けるようにしてください。
12~14歳は1回2錠、15歳~は1回4錠を、1日3回服用します。
クールワン去たんソフトカプセルRN
「クールワン去たんソフトカプセルRN」は杏林製薬の市販薬で、有効成分L-カルボシステインとブロムヘキシン塩酸塩が配合された痰切り薬です。
粘度の高い痰に効果的で、痰を薄めて吐き出しやすくする他、粘膜を修復する効果もあります。
8歳の子どもから服用でき、8~14歳は1回1カプセル、15歳~は1回2カプセルを1日3回服用します。
ツムラ漢方清肺湯エキス顆粒
粘り気がある痰が辛い時には、ツムラの漢方薬である「ツムラ漢方清肺湯エキス顆粒」も効果的です。
清肺湯は自然の生薬の力を借りて、喉や気管の炎症を和らげて痰を出しやすくする漢方薬で、特に黄緑色の粘り気のある痰に効果があるとされています。
2歳以上の小さな子どもから服用できるのが特徴で、2~3歳は1回1/3包、4~6歳は1回1/2包、7~14歳は1回2/3包、15歳~は1回1包を1日2回服用します。
「クラシエ」漢方五虎湯エキス顆粒SII
クラシエの「五虎湯」は、激しい咳を伴う粘り気のある痰が辛い時に効果的な市販の漢方薬です。
気管支を広げて呼吸を楽にし、感染症などによる黄色い粘り気のある痰を体外に排出しやすくします。
2歳以上の子どもから飲める漢方薬で、2~3歳は1回1/3包、4~6歳は1回1/2包、7~14歳は1回2/3包、15歳~は1回1包を1日2回服用します。
痰を和らげるために試したい方法
ここでは痰を出しやすくする自宅で簡単にできる方法を中心に紹介していきます。
痰切り薬の服用と併せて行っていきましょう。
- 温かい飲み物を十分にとる
- 食べ物に注意する
- ツボを押す
水分が足りないと痰は粘り気を増して出しにくくなるため、十分に水分を取ることが大切です。
この時、冷たい飲み物は気道を刺激して咳を誘発してしまう可能性があるため、温かい飲み物を選ぶとよいでしょう。
白湯はもちろん、お茶や生姜湯など抗菌効果のある飲み物もおすすめです。
また、痰を切る食べ物を選ぶのも効果的です。
ダイコンや山芋、レンコン、タケノコ、パイナップルなどに痰を和らげる効果があると言われています。
反対に痰に悪い影響を与える食べ物は、味の濃いものや香辛料の多いものなので、痰が辛い時には避けるようにしましょう。
さらに肺の気の流れを整えるツボを押してみるのもおすすめです。
肘の内側のシワにある尺沢、鎖骨外側の下のくぼみ付近にある中府などをゆっくりと気持ち良く感じる強さで押してみてください。
痰切り薬で辛い症状を和らげよう
体内に入った細菌やウイルス、埃などを排出する身体の働きである痰は、風邪を引いた時などには量が増え、粘り気が強くなることがあります。
このような時には市販の痰切り薬や漢方薬を利用し、辛い症状を緩和するのがおすすめです。
また、併せて温かい飲み物を取ったり、ツボを押したりして、痰を上手に体外に排出していきましょう。