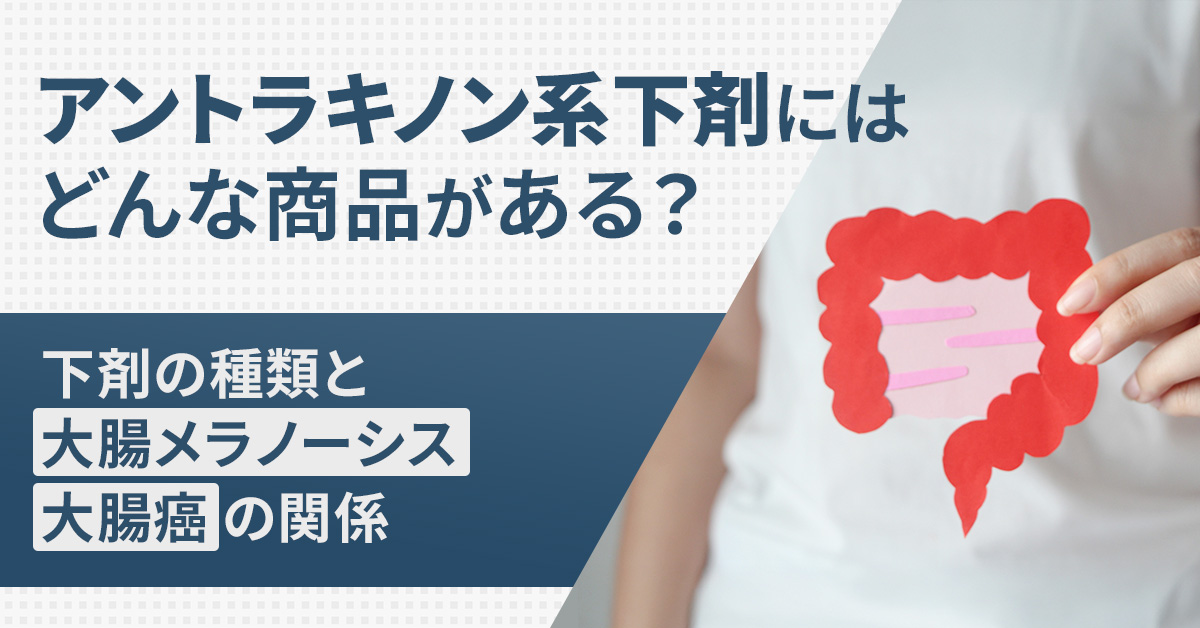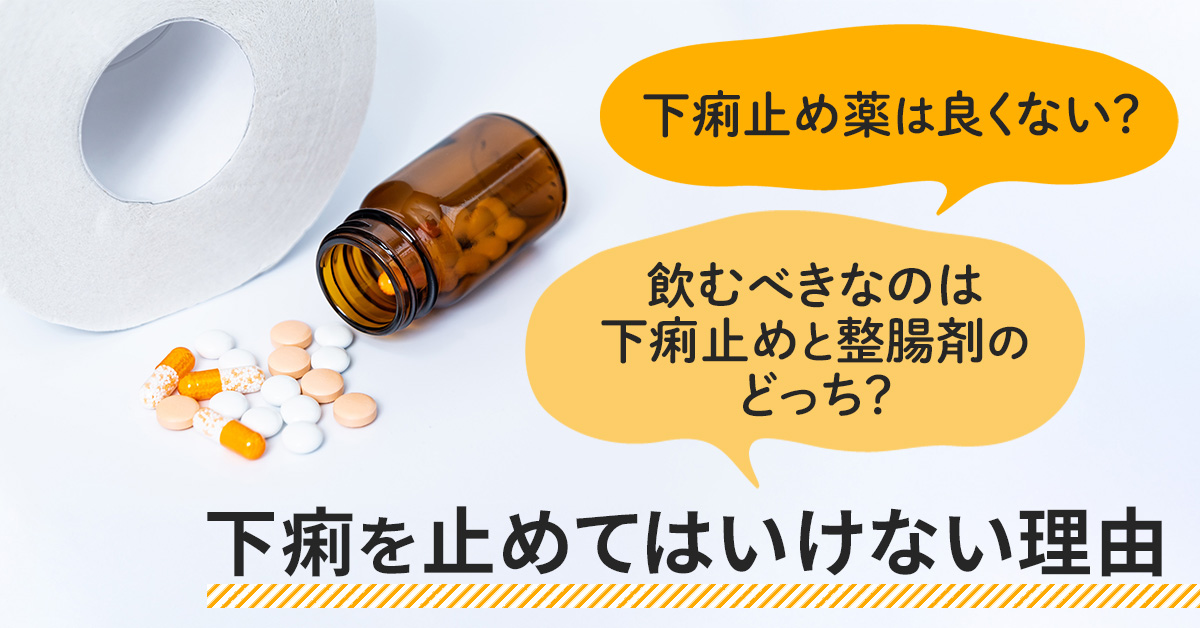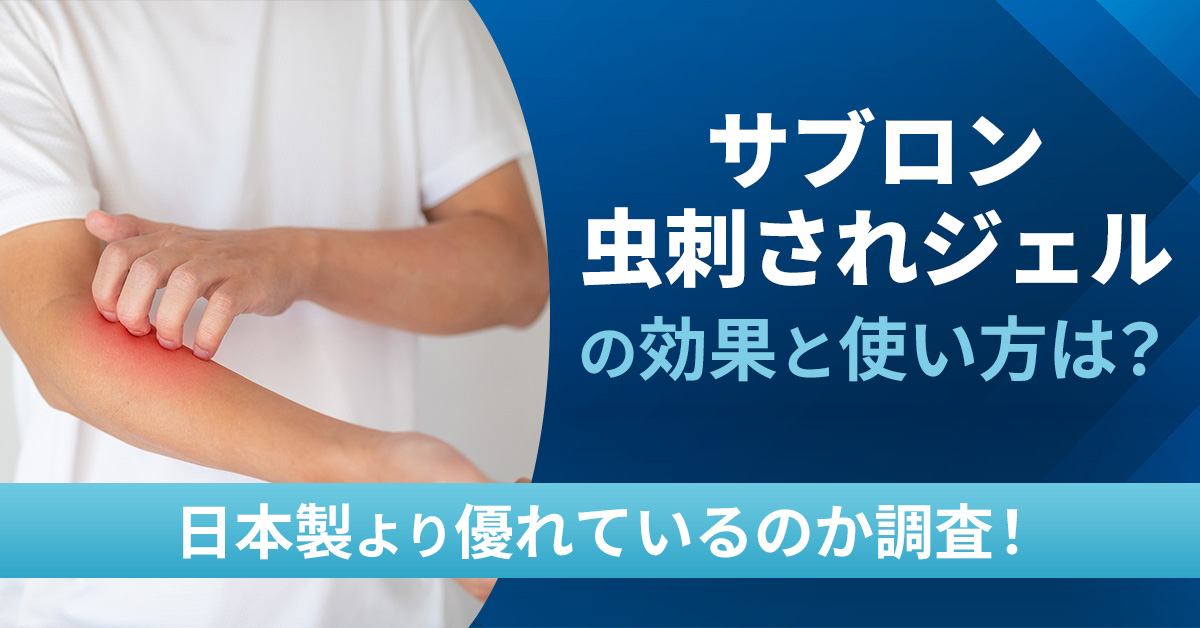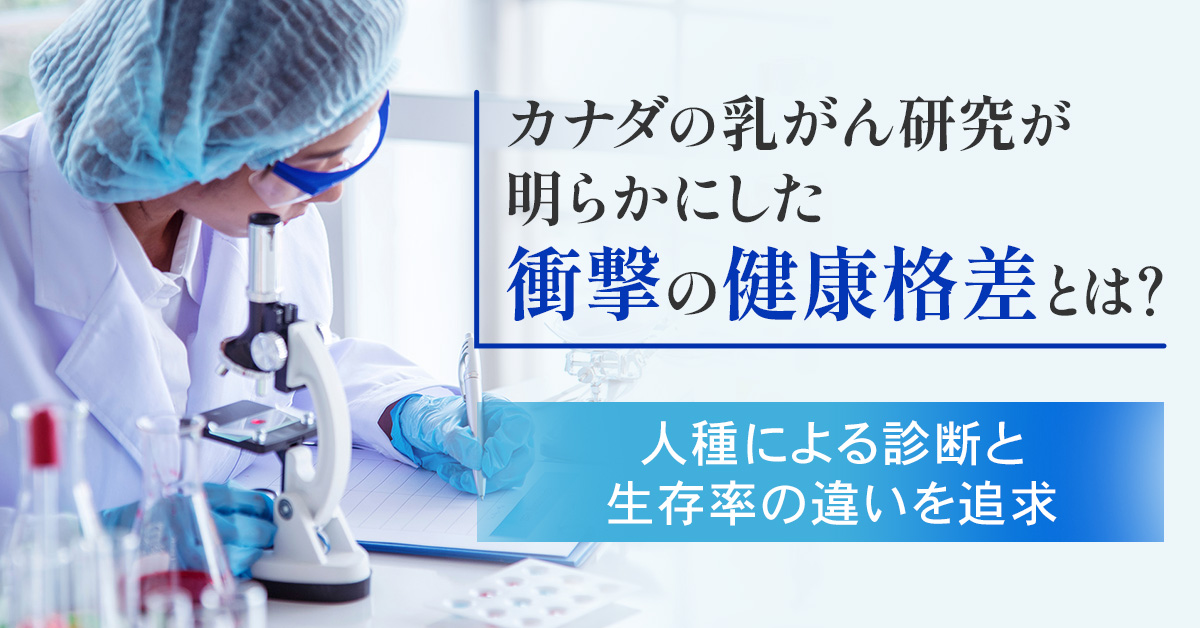風邪の一般的な症状である咳は、辛い症状の1つともいえるかもしれません。
「咳が出て仕事に集中できない」「夜に起きてしまう」などに加え、コロナ禍以降は「咳をする度に視線が痛い」など周囲の反応に困る方も増えているのではないでしょうか。
今回は、咳が辛い時の強い味方となる咳止め薬にフォーカスしていきます。
咳の症状の種類や各種咳止め薬の効果、咳止め薬が効かない理由・対処法などを解説しますので、咳でお悩みの方はぜひ参考にしてください。
咳が出る仕組みと咳の種類
人間は風邪を引いたり、空気の悪い場所へ行ったりすることで咳が出ます。
ここでは咳が出る仕組みと、その時に出る咳の種類を解説していきます。
咳が出る仕組みとは
咳は身体の外から入ってきた埃や細菌、ウイルスなどの異物を気道から取り除く防御反応です。
異物が侵入すると、咽頭・気管・気管支などの気道の粘膜にある咳受容体が刺激されて脳にある咳中枢に信号を送り、脳は咳という反射運動を起こします。
また心因性のストレスによって咳が出ることもあります。
これは咳中枢が大脳皮質によってコントロールされているためで、日中や緊張状態にある時に出やすいのが特徴です。
咳には種類がある
咳は風邪をはじめ、アレルギーによるもの、肺がんなどの重い病気によるものなど様々な原因が考えられますが、持続期間によって大きく3種類に分類されます。
- 急性咳嗽
- 遷延性咳嗽
- 慢性咳嗽
「急性咳嗽」は咳が続く期間が3週間未満の咳で、風邪やインフルエンザ、急性気管支炎などが原因となる呼吸器感染症が原因である可能性が高いです。
特にインフルエンザなどのウイルス性の感染症の場合、咳に加えて発熱や鼻水、喉の痛み、倦怠感などの症状を伴うケースが多いのが特徴です。
約3週間~8週間未満続く咳を「遷延性咳嗽」といい、百日咳やマイコプラズマ、クラミジアからの肺炎の可能性があります。
さらに8週間以上続く咳を「慢性咳嗽」といい、咳喘息やアトピー咳嗽、慢性気管支炎など、感染症以外の原因が考えられます。
また、咳の音による分類では、ゴホゴホとたんが絡んだ咳を「湿性咳嗽」、コンコンとたんの影響が少なく乾いた咳を「乾性咳嗽」と呼びます。
湿性咳嗽が出るのは、たんや鼻水を身体の外に出そうとする反応で、鼻や喉に炎症が起きている状態です。
一方、乾性咳嗽が出るのは肺や気管に炎症が起きており、咳喘息やアトピー咳嗽などが疑われます。
このように咳と言っても様々な種類があり、原因が異なります。
咳症状の陰に他の病気が隠れている可能性もあるため、治りが悪かったり別の症状に気づいたりした場合には、医療機関を受診することが大切です。
咳止め薬の種類と効かない理由
咳の強い味方となる咳止め薬ですが、満足する効果が得られず困っているという方も多いのかもしれません。
ここでは咳止め薬の種類を学び、咳止め薬が効かない理由について考えていきましょう。
咳止め薬の種類
咳止め薬は作用する場所や構造によって「麻薬性中枢性鎮咳薬」「非麻薬性中枢性鎮咳薬」「末梢性鎮咳薬」の3種類に分類されます。
麻薬性中枢性鎮咳薬
麻薬性中枢性鎮咳薬は脳幹の延髄にある咳中枢をしずめて咳を止める作用がある薬剤で、主成分はコデイン、ジヒドロコデインなどです。
古くから使用され、3種類の中では最も強い咳止め効果があるとされていますが、コデインやジヒドロコデインはモルヒネと化学構造が似ているため、長期間摂取すると依存の危険性があるとも言われています。
たんの少ない乾性咳嗽に使われることが多く、たんを伴う咳の場合には去痰薬と併用して使用することがあります。
また12歳以下の子どもは使用できません。
非麻薬性中枢性鎮咳薬
非麻薬性中枢性鎮咳薬も麻薬性中枢性鎮咳薬と同様に、咳中枢をしずめて咳を止める薬剤で、主成分にはチペピジン、デキストロメトルファン、ノスカピンなどが挙げられます。
デキストロメトルファンが主成分の有名な製品にはメジコンがありますが、依存性の真偽が解釈によって様々なため、必要以上に服用を続けることのないように気を付けるとよいでしょう。
主成分によってたんの少ない乾性咳嗽に向くもの、たんを出しやすくする効果があるものなどの差異があります。
また、子どもが服用できる製品があるのも非麻薬性中枢性鎮咳薬の特徴です。
末梢性鎮咳薬
末梢性鎮咳薬は咳中枢ではなく、気管支や肺などに作用して咳を抑える薬剤です。
末梢性鎮咳薬は、去痰薬、気管支拡張薬、吸入薬、漢方薬など多種多様に分類され、それぞれ効果が異なります。
直接、脳に作用して咳をしずめるのではなく、咳に関係する部位の刺激を和らげて咳が出にくい状態にします。
咳中枢に作用する麻薬性中枢性鎮咳薬や非麻薬性中枢性鎮咳薬は乾性咳嗽に効果が高いものが多いですが、末梢性鎮咳薬はたんの絡んだ湿性咳嗽に向いています。
咳止め薬を飲んでも咳が止まらないのはなぜ?
基本的に咳中枢をしずめる麻薬性中枢性鎮咳薬や非麻薬性中枢性鎮咳薬の咳止め薬は、その特徴から乾性咳嗽に有効とされ、湿性咳嗽で服用しても思ったような効果が得られない可能性が高いです。
つまり咳止め薬を飲んでも咳が止まらないのは、適応外の症状で服用していることが原因であると考えられます。
また、たんが絡む湿性咳嗽に咳止め薬を使用すると、身体が咳でたんを出そうとする反応を阻害し、症状が悪化する恐れがあります。
よく「咳止め薬を飲むと治りが遅くなる」という噂を耳にすることがあるかもしれませんが、それはこのように湿性咳嗽で咳止め薬を飲み続けたことが理由であると考えられます。
つまり、湿性咳嗽の時にメジコンなどの乾性咳嗽に効果が高い市販の咳止め薬を飲んでも、思ったような効果が得られない可能性があります。
市販薬で湿性咳嗽を和らげたいのであれば、麦門冬湯などの漢方薬などが向いていると言えるでしょう。
ただし、あまりにも長引く咳には注意が必要です。
3週間以上続く咳の場合は、百日咳やマイコプラズマ肺炎などの感染症、咳喘息、アトピー咳嗽などの可能性があります。
これら病気には咳止め薬はほとんど効果がないうえ、かえって症状を悪化させてしまう恐れがあります。
長引く続く咳の場合には「そのうち治るだろう」と過信せず、医療機関を受診し、適切な処置を受けるようにしてください。
咳止め薬が効かない時の対処法
病院の薬を飲んでもなかなか咳が止まらない時、どうしたら辛い症状を和らげることができるのでしょうか?
ここでは咳を和らげるための対処法を紹介していきます。
喉を温める
喉が冷たいと気道が敏感になり刺激に反応しやすくなるため、咳が辛い時には喉を温めるとよいです。
温かい飲み物を飲んだり、首にネックウォーマーを巻いたりしてみましょう。
また、冷たい空気から喉を守り保湿効果を高めるマスクも効果的です。
水分をとる
喉が乾燥すると咳が出やすくなるため、こまめに水分をとって喉を保湿しましょう。
保湿効果の他に、水分によってたんがやわらかくなり体外に排出しやすくなる効果もあります。
ただし、冷たい飲み物は喉を刺激してしまうので避け、できるだけ温かい飲み物を飲むようにしてください。
のど飴をなめる
のど飴をなめることにより喉が保湿されると咳が出にくくなります。
のど飴は医薬品・医薬部外品・食品の3種類に分類され、効果や販売場所も異なります。
医薬品ののど飴は主に薬剤師や販売登録者のいるドラッグストアや薬局で販売されており、最も効果が期待できる反面、薬剤との飲み合わせや副作用にも注意が必要です。
医薬部外品と食品ののど飴は販売許可が不要のため、スーパーなどの小売店で購入できます。
医薬部外品の効き目は穏やかではありますが有効成分による一定の効果が認められています。
一方、食品ののど飴にはどのくらい効果が期待できるかは不明です。
この3種類を意識してのど飴を選び、効果的に辛い症状を和らげていきましょう。
ハチミツを飲む
これまでの論文や研究で「ハチミツが咳を抑える」というデータが報告されています。
ハチミツに備わっている抗菌力や粘膜保護作用により細菌の増殖を抑えることで、咳が和らぐと言われています。
ハチミツを飲む時間に決まりはありませんが、夜に咳がひどくなるのであれば就寝前にティースプーン約1杯を飲むとよいでしょう。
この時、そのまま舐めても構いませんが、白湯にハチミツとレモン汁を入れて、ハチミツレモンなどにすると飲みやすくなるかもしれません。
ただし、乳児ボツリヌス症になる危険性があるため、1歳未満の子どもには絶対にハチミツを与えないでください。
ツボを押す
東洋医学ではツボを刺激し、体調を整えるという考え方があります。
咳に効果があるとされているツボは肘の内側のシワの上にある尺沢と、鎖骨の外側のくぼみ付近にある中府と呼ばれるツボです。
どちらも肺の気の流れに関係しており、古来より咳に効果があると言われてきました。
気持ち良いと感じる強さでゆっくりと押して、咳を落ち着けましょう。
医療機関を受診する
あまりにも咳が辛い時には、悪化したり他の病気が隠れたりしている可能性があるため、速やかに医療機関を受診してください。
特に息苦しさがある場合や咳が辛くて眠れない、呼吸時にゼーゼーやヒューヒューという音がする時は、危険な状態であると考えられます。
また、咳が長期間続く場合は咳喘息やアトピー咳嗽の可能性が考えられるため、この場合も医療機関を受診しましょう。
咳止め薬は正しく選び上手に対処していこう
今回は咳止め薬が効かない理由について、様々な角度から解説しました。
咳止め薬は乾性咳嗽には効果がありますが、湿性咳嗽には思ったような効果が得られないばかりか、悪化させてしまう恐れがあります。
湿性咳嗽には去痰剤や気管支拡張薬などを使用して、咳の症状を和らげていくとよいでしょう。
また、長引く咳には他の病気が隠れている可能性もあるため、過信せずに医療機関を受診することが大切です。
市販の咳止め薬を使用する時にはこれら点に注意を払うようにしましょう。
咳止め薬以外にも、喉を温めたりツボを押したりして咳を和らげる方法があります。
薬剤だけでは辛い時には、これらの方法を試してみてください。