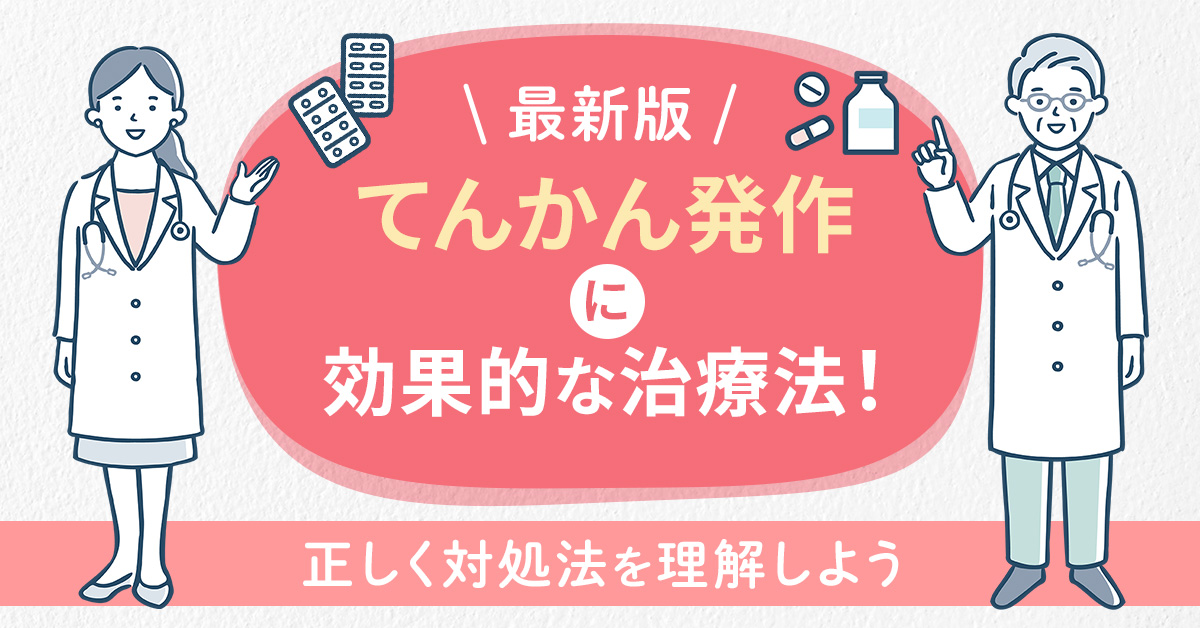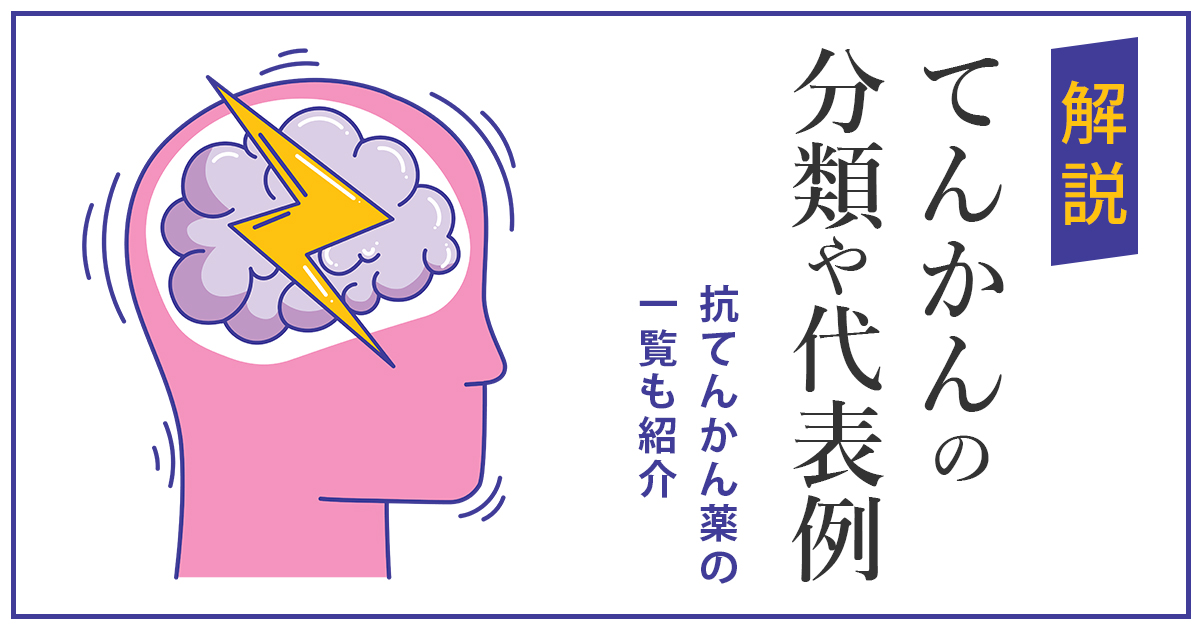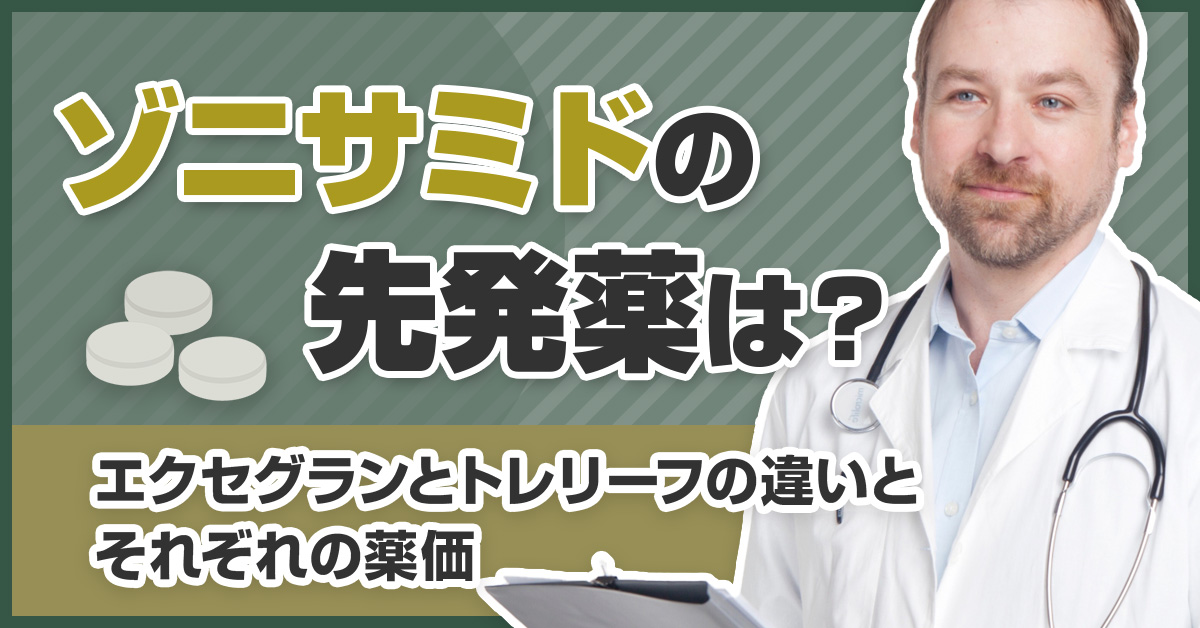「いつ発作が起こるかわからないから毎日辛い…」
「てんかんの薬を飲んでもなかなか発作が治らない…」
てんかん発作の患者さんは、仕事や育児をしながらいつ発作が起きてしまうのか毎日不安を抱えながら生活しているのではないでしょうか。
てんかんの治療は、主に抗てんかん薬を服用し治療します。
薬剤の飲み合わせが悪い場合は、発作を悪化させる可能性があるため、てんかんのタイプや発作の型に合わせた薬剤を飲むことが大切です。
当記事では、てんかん発作に関して説明するとともに最新の治療方法を解説していきます。
てんかん発作を発症して間もない人や治療薬がなかなか効かない人はぜひ参考にしてくださいね。
100人に1人が発症!てんかん発作について
てんかんは、比較的よく見られる神経疾患で、100人に1人が一生のうちに発症すると言われています。
そもそもてんかんとは、脳の神経細胞が何らかの原因により、電気信号のリズムが乱れると、神経細胞が異常に興奮し、それが広がることでてんかん発作を引き起こします。
発作は、大きな病変がなくても発生する場合もあり、原因や症状は多様です。
近年の医療技術の進歩により、てんかんの診断や治療が大きく進化しています。
多くの人々が正しい診断と治療を受けることで、日常生活を安心して送れるようになるでしょう。
ここではてんかんの主な2種類について解説します。
症候性てんかん・突発性てんかんの違い
上記では、脳の神経細胞の電気信号の乱れが生じることで、てんかんが起きると説明しました。
なぜそのような電気信号の乱れが生じるのでしょうか。
てんかんは大きく分けて、症候性てんかんと突発性てんかんに分類されます。
症候性てんかんは、生まれた後に脳に何らかの障害が出ることで発症し、原因としては以下が考えられます。
- 出生時の脳の損傷
- 低酸素
- 脳炎や髄膜炎などの感染症
- 脳出血・脳梗塞などの脳卒中
一方、突発性てんかんは、血液検査や画像検査を行っても明確な原因が見つからない場合に分類されるてんかんです。
このタイプは主に遺伝的要因が関与しているとも言われています。
親がてんかんを持っている場合は、子どももてんかんを発症しやすいです。
症候性てんかんと突発性てんかんは、発作の頻度や治療法にも違いがあります。
医師による正確な診断が、より効果的な治療に繋がります。
脳の一部が興奮して起こる焦点起始発作
てんかん発作の症状は、痙攣や意識障害などの発作で、発作症状は大きく分けて2つみられます。
そのうちの1つである焦点起始発作は、脳の一部から異常に興奮することで発生します。
以前は部分発作とも言われており、焦点起始発作は、興奮する部位によって、発作中の意識の有無の違いがみられるのです。
具体的な症状としては、手や足のつっぱり、首や目が勝手に動くなどの症状として現れることがあります。
一方で、焦点起始発作の類似系として知られる複雑部分発作の症状は、急に動作が止まりぼーっとしたり、自分の意志と関係なく動作を繰り返したりするなどの症状がみられます。
脳の全体が興奮して起こる全般発作
脳の一部分の興奮によって起こる焦点発作とは違い、全般発作は脳全体が同時に異常な電気活動を起こすことによって発生します。
意識を失うことが多く、全身が痙攣するなどの症状が特徴です。
全般発作には非痙攣性の発作もあり、突然ぼんやりしたり、反応が鈍くなったりすることがあります。
全般発作の頻度や重症度は、個人差がありますが、適切な治療を受けることでコントロールが可能になります。
最新のてんかん発作の治療薬の状況について
てんかんの治療方法は、内科治療や外科治療に分けられます。
ほとんどの人は内科治療でてんかん発作を抑えることが出来ますが、中には難治性てんかんと言われる、薬剤を飲んでもコントロール出来ない人もいるのです。
ここでは、現在の内科治療や外科治療の方法に関して解説するとともに、新しいてんかん薬を紹介していきます。
内服などの内科治療
内科治療では、てんかん用の薬剤が主に使用されます。
代表的な薬剤には、バルプロ酸ナトリウムやカルバマゼピンなどがあります。
これらの薬剤は、発作の症状に大きな効果があり、約6~7割の患者さんは薬物治療で発作が緩和されます。
これらの薬剤には副作用もあります。
例えば、眠気やめまい、肝機能障害などです。
最初は、副作用を避けるために、薬剤を少量から飲み始めていきます。
そこから徐々に薬剤の量を増やしていき、途中で血中濃度を測定しながら調整します。
薬物治療で大切なことは、
- 毎日決まった時間に飲み忘れなく服用する
- 生活リズムを整える
- 勝手に服薬を中断しない
上記を守ることで、副作用のリスクや発作の誘発を最小限に留めることができます。
手術などの外科治療
外科治療は、内科治療で効果が出ない難治性てんかん(薬剤抵抗性てんかん)の患者さんに対して、外科手術を選ぶことが多いです。
難治性てんかんの患者さんは、適切に薬剤を内服してきたが、それでも発作がコントロールできない人が該当します。
薬剤の飲み合わせが悪く薬剤を何種類も試すことはよくありますが、7種類目以降に試す薬剤で発作がなくなる見込みは、10%以下と言われています。
外科手術は、すべてのてんかんの患者さんが受けられるわけではなく、発作部分が明確であることや部分てんかんで病変部分を切除しても問題がない場合に治療が可能です。
外科手術には、発作の完全な消失を目指す根治手術と、発作の軽減を目的とする緩和手術の2種類があります。
外科治療は高い専門性を要するため、専門医療機関で治療を受けることが推奨されます。
日本での新しい抗てんかん薬の一覧
近年、てんかん治療に新しい薬剤が導入されています。
例えば、ラコサミドは、従来の薬剤とは異なるメカニズムで作用するため、今まで飲んでいた薬剤で効果がなかった患者さんにも期待できるでしょう。
また、新薬は副作用も比較的少ないため、患者さんの生活の質を大幅に向上できる可能性があります。
新しい研究により、さらに多くの新薬が開発されるでしょう。
このように、新薬の導入は、患者さんのQOLの向上にも大きく関与する可能性があります。
| 商品名 (一般名) | 日本での発売年 | 適応 |
|---|---|---|
| ガバペン(R) (ガバペンチン) | 2006年 | 焦点発作 3歳以上 |
| トピナ(R) (トピラマート) | 2007年 | 焦点発作 併用 4歳以上 |
| ラミクタール(R) (ラモトリギン) | 2009年 | 焦点発作 強直間代発作 定型欠神発作 レノックス・ガストー症候群の全般発作 |
| イーケプラ(R) (レベチラセタム) | 2010年 | 焦点発作 強直間代発作 4歳以上 |
| ディアコミット(R) (スチリペントール) | 2012年 | ドラベ症候群における間代発作・強直間代発作に対するク ロバザムおよびバルプロ酸との併用 1歳以上 |
| イノベロン(R) (ルフィナミド) | 2013年 | レノックス・ガストー症候群における強直発作・脱力発作 併用 4歳以上 |
| サブリル(R) (ビガバトリン) | 2016年 | 点頭てんかん 生後4週以上 処方登録医のみ |
| フィコンパ(R) (ペランパネル) | 2016年 | 焦点発作 強直間代発作 併用 4歳以上 |
| ビムパット(R) (ラコサミド) | 2016年 | 焦点発作 強直間代発作 併用 4歳以上 |
| アフィニトール(R) (エベロリムス) | 2019年 | 結節性硬化症 |
引用:てんかんの最新治療
てんかん発作が起きた場合の対応方法について
てんかん発作を抱える人は、「いつ症状が起きるのだろうか」と常に不安を抱えており、見た目が健康に見えるため、周囲からの理解もなかなか得られにくいです。
前兆症状のある人でも、発作が起きるまでに十分な時間があるわけではありません。
てんかん発作を起こした本人は身体が動かせない場合もあるため、周囲にいる人の理解や援助が必要になります。
ここでは、てんかん発作を持っている本人の対処法や家族や職場の人への対処法を紹介します。
本人の対処法
発作が起きると、意識を失ったり身体の自由がきかない状態になります。
発作自体は命に別状はありませんが、車の運転中や就労、妊婦などの日常生活で、様々な制限があるためQOL(生活の質)が下がる可能性があります。
また、いつ発作が起こるかわからない状態での生活は不安も大きいでしょう。
前兆症状がある人は、直ちに安全な場所へ移動するようにしてください。
さらに、適切に治療するためにどのような発作が起きたのか、発作が起きた際の状況や時間などをメモしておきましょう。
周囲の人への対処法
突然、職場や友人が発作症状を起こした場合、ほとんどの人が動揺して助けてもらいたい際に助けてもらえない状況になってしまいます。
そうならないためにも、職場の人や家族、友人に対し、「自分はてんかん発作を起こす可能性があること」「発作が起きた際の対処法」を伝えるようにしましょう。
発作が起きた場合の対処法として、もし発作が起きた場所が危険であれば、安全な場所へ移動し、衣服を緩めた状態で気道を確保してそのまま様子を見ます。
5分以上意識消失や全身性痙攣が治らない状態であった場合は、すぐに救急車を呼び搬送してもらうようにしましょう。
また、発作は周りの人が止めようと思っても困難なため、名前を呼んだり身体をゆすったりする行動は意味がありません。
口の中にタオルを入れて舌を噛まないようにすることは、窒息する恐れがあるため、絶対にしないように伝えておきましょう。
さらに、嘔吐する危険性もあるため誤嚥を防ぐために身体を横に傾けるなどして環境設定を行うように説明しておくことも重要です。
てんかん発作に関するよくあるQ&A
ここでは、てんかん発作に関するよくあるQ&Aをご紹介します。
てんかん発作の時に救急車は呼んだ方がいいでしょうか
てんかん発作が数分以内に収まる場合は、救急車を呼ぶ必要がないことが多いです。
しかし、発作が5分以上続く場合や意識が戻らない場合、全身性の痙攣を起こす場合は応急処置が必要な場合もあります。
また、初めての発作の場合や妊娠中の方、持病がある方は、状況に応じて早めに医療機関に連絡することをおすすめします。
てんかん発作の薬剤を飲まないとどうなりますか?
てんかんの薬剤を飲まないと、発作の頻度や重症度が増す可能性があります。
中止できる目安として、発作が2年以上起きていないことや脳波が正常になっている場合です。
必ずしも、上記に当てはまるからと言って服薬を中止できるわけではありません。
薬剤を中止する場合は、医師への相談のもと、少しずつ薬剤を減らす必要があります。
てんかんの薬剤は効果が出るまでどのくらいかかりますか?
てんかんの薬剤は、人によって効果が出るまでの時間が異なります。
一般的には、抗てんかん薬の半減期(薬剤が血液の中に入っている薬剤の濃度が半分になるまでの期間)の5倍の期間が必要と言われています。
薬剤の種類によっても半減期は変化するため、半減期の5倍が経過した時点で、効果を判定します。
この期間中は、発作の頻度や症状の変化をよく観察し、医師に報告することが重要です。
薬剤の効果を確認するために、定期的な血液検査や診察が行われます。
てんかんの発作は前兆がありますか?
てんかんの発作には、前兆がある人もいます。
一般的な前兆症状としては以下がみられます。
| 触覚 | 視覚 |
|---|---|
|
・手足のピリつき ・手足の痺れ感 ・手足の温度感(熱い・冷たいなど) |
・ピカピカ光る ・いろいろな形が見える |
| 聴覚 | その他 |
|
・機械音 ・人の声 ・幻聴 |
・運動症状 ・何も食べていないのに突然の味覚 ・めまい ・胃腸の不快感 ・硫黄や焦げの匂い |
前兆の有無や種類を理解することで、発作の予防や適切な対処が可能になります。
また、前兆を感じたら家族や周囲の人に知らせることも大切です。
てんかん発作の治療は周囲の協力が大事!適切な対処法を理解しよう
てんかん発作の治療は、主に抗てんかん薬を服用し治療します。
しかし、何種類か薬剤を変えても発作症状が治らない場合は、難治性てんかんの可能性も考えられます。
まずは、薬剤の効果を最大限発揮させるために、睡眠時間を十分に確保し、暴飲暴食などをしない規則正しい生活を送ることが大切です。
本人は、発作がいつ起きるかわからないため、生活上に支障を来している人もいると思います。
まずは、職場や家族にてんかんが起きた場合の対処法を共有しておき、正しく対応してもらえるようにしましょう。