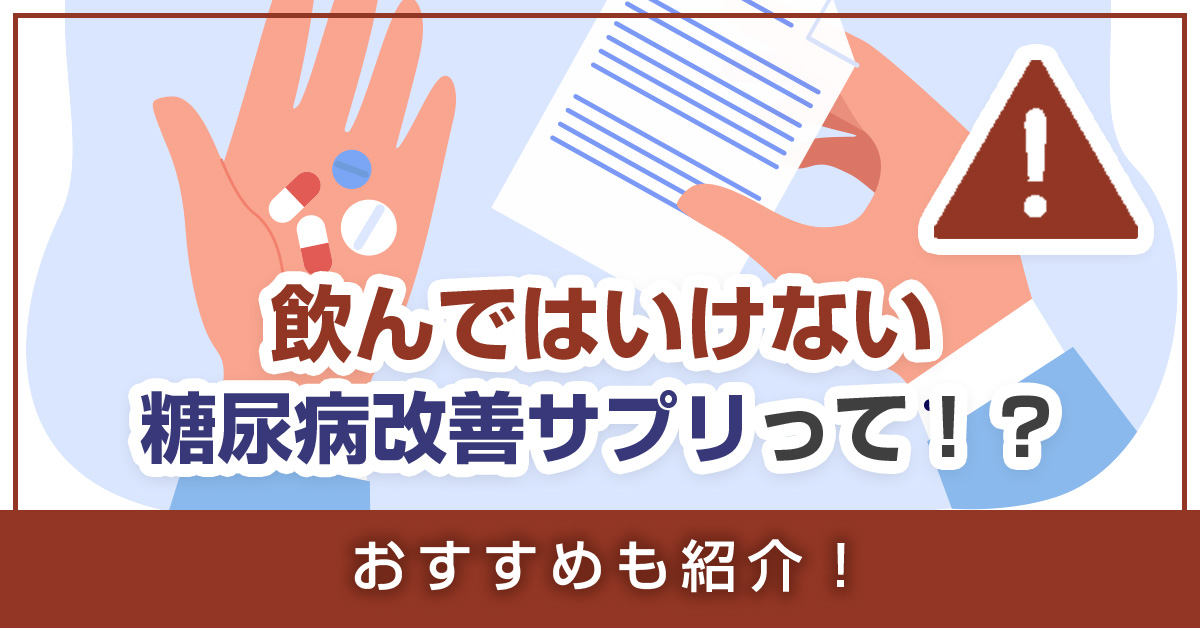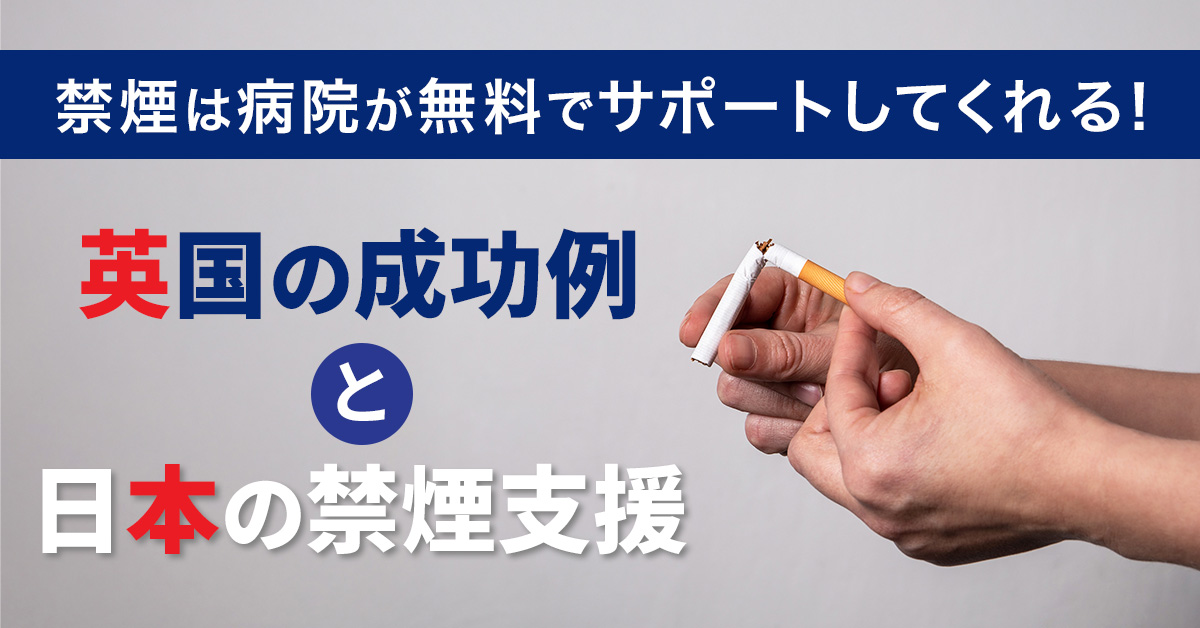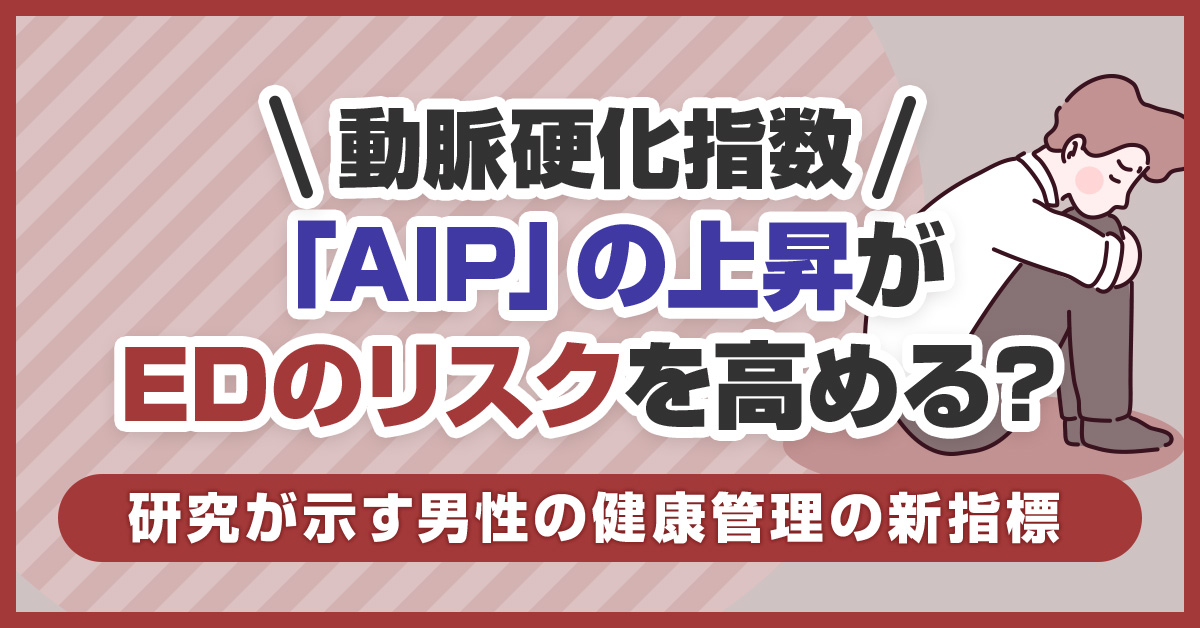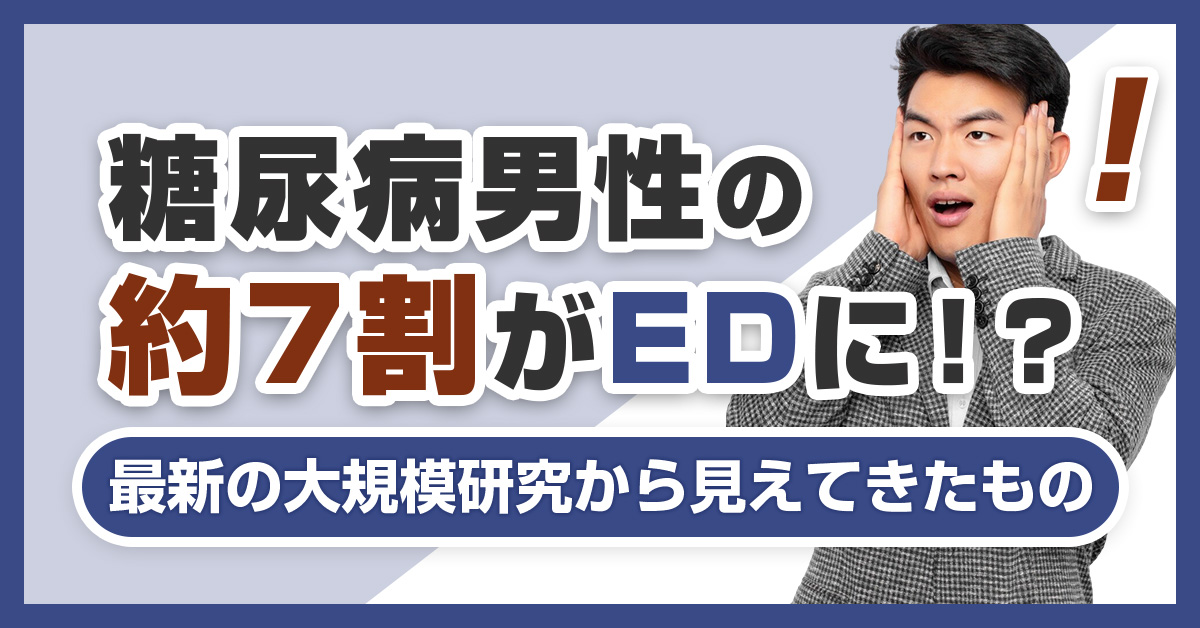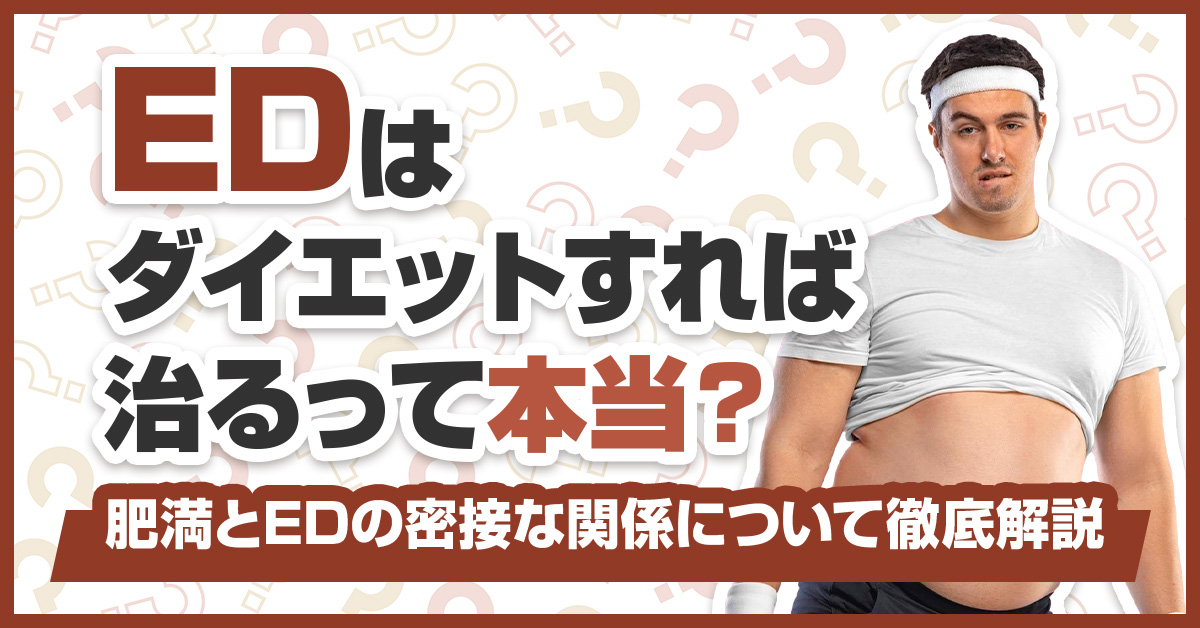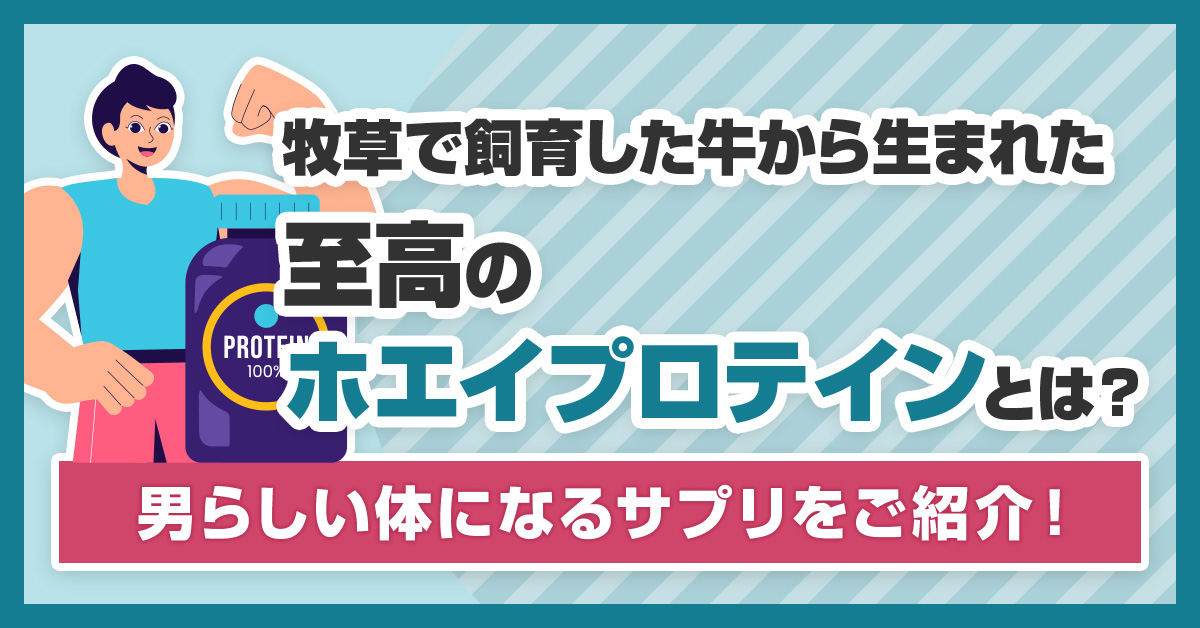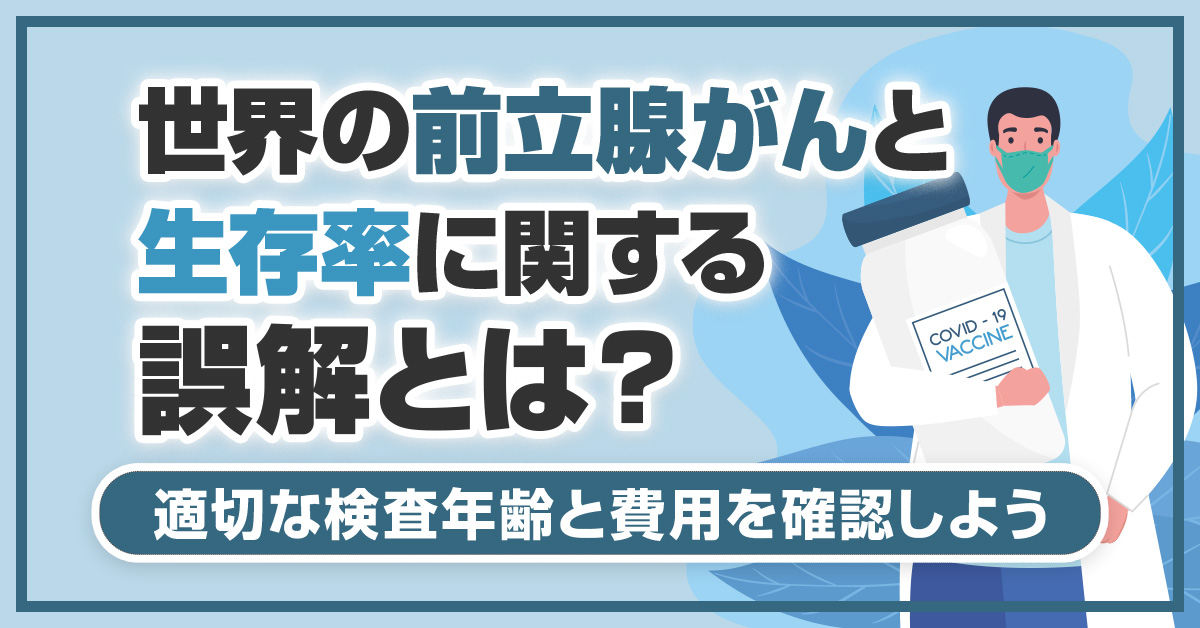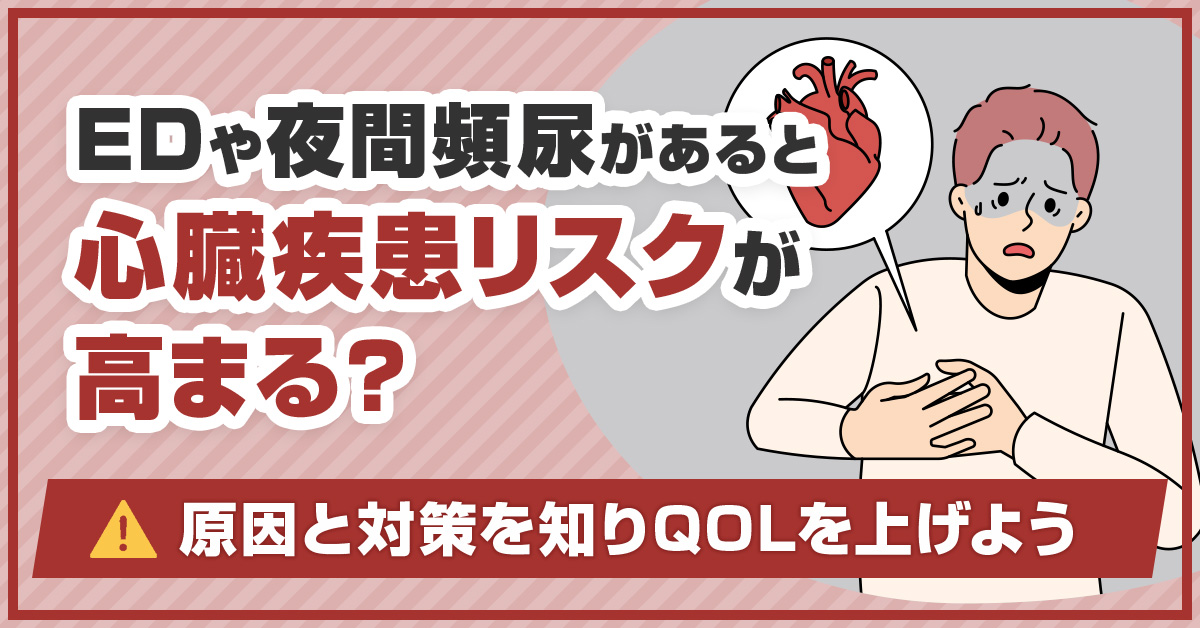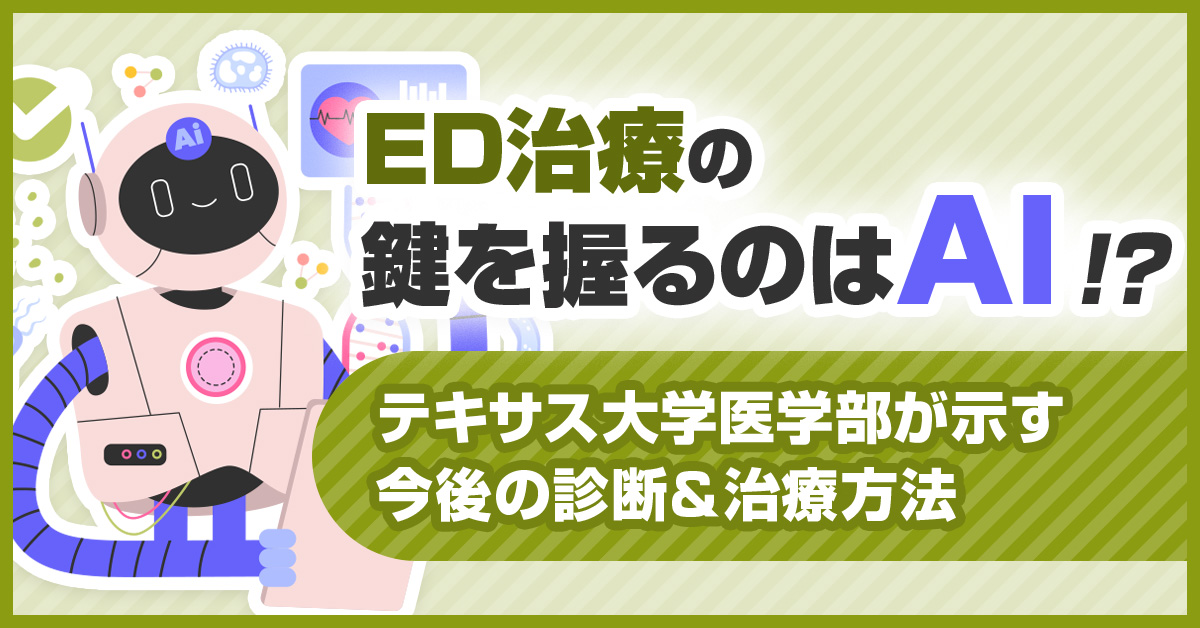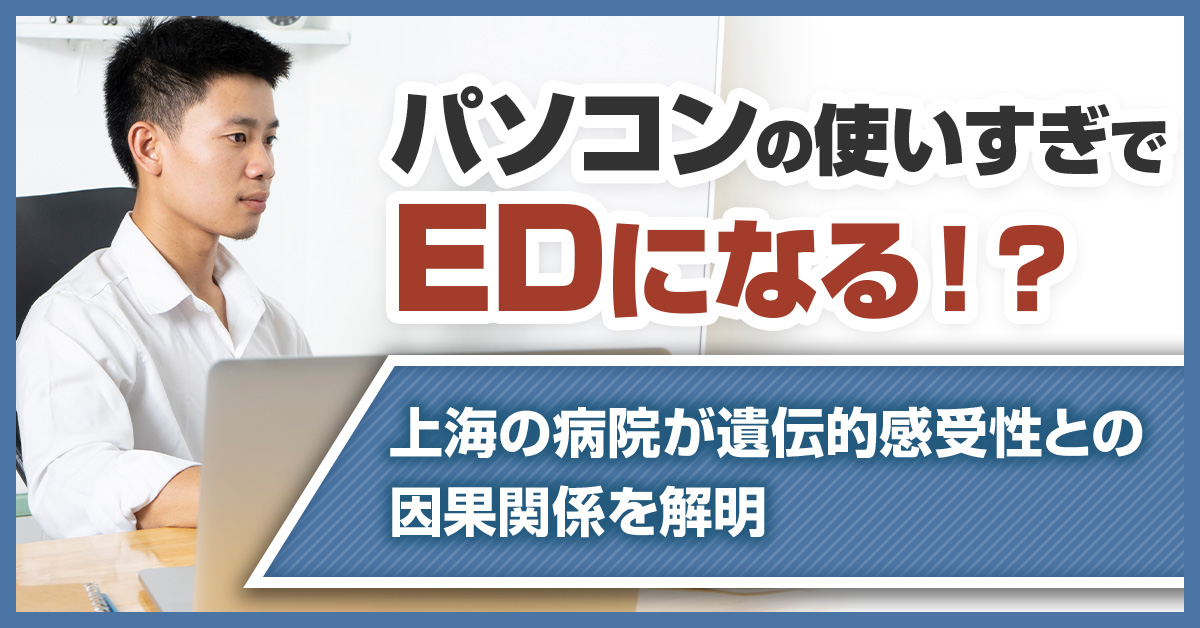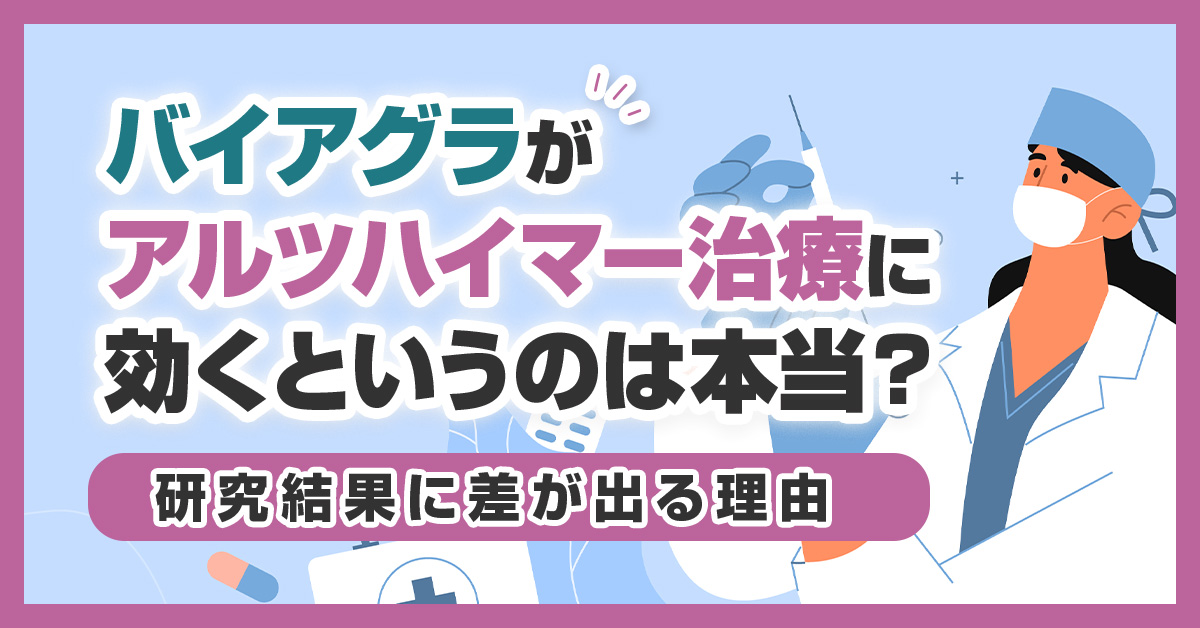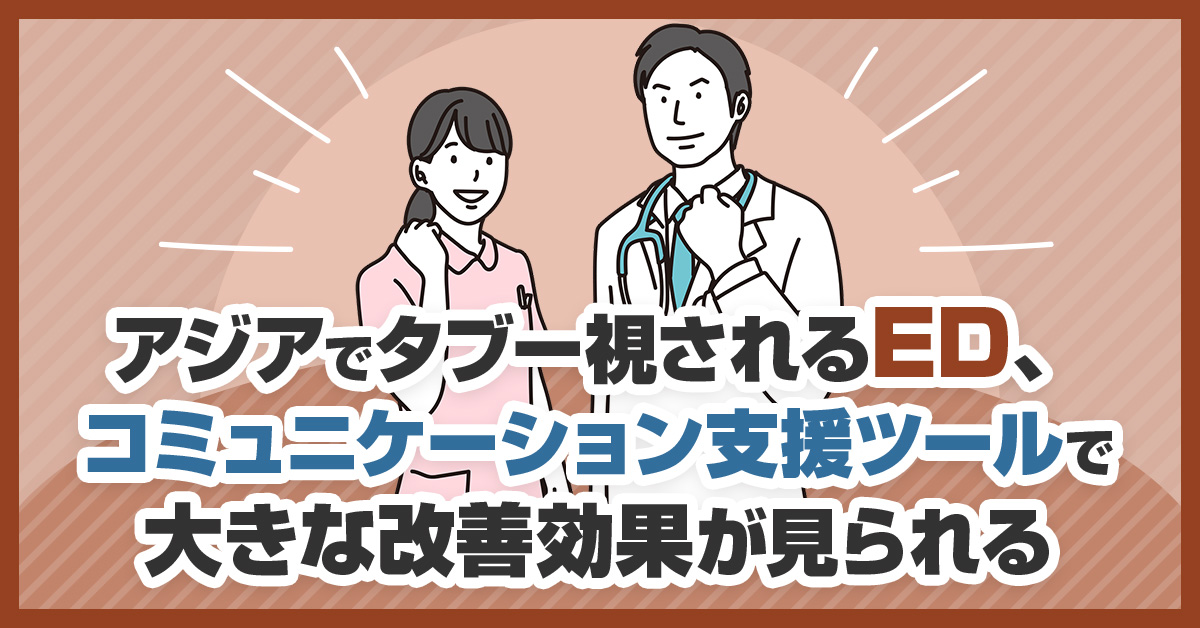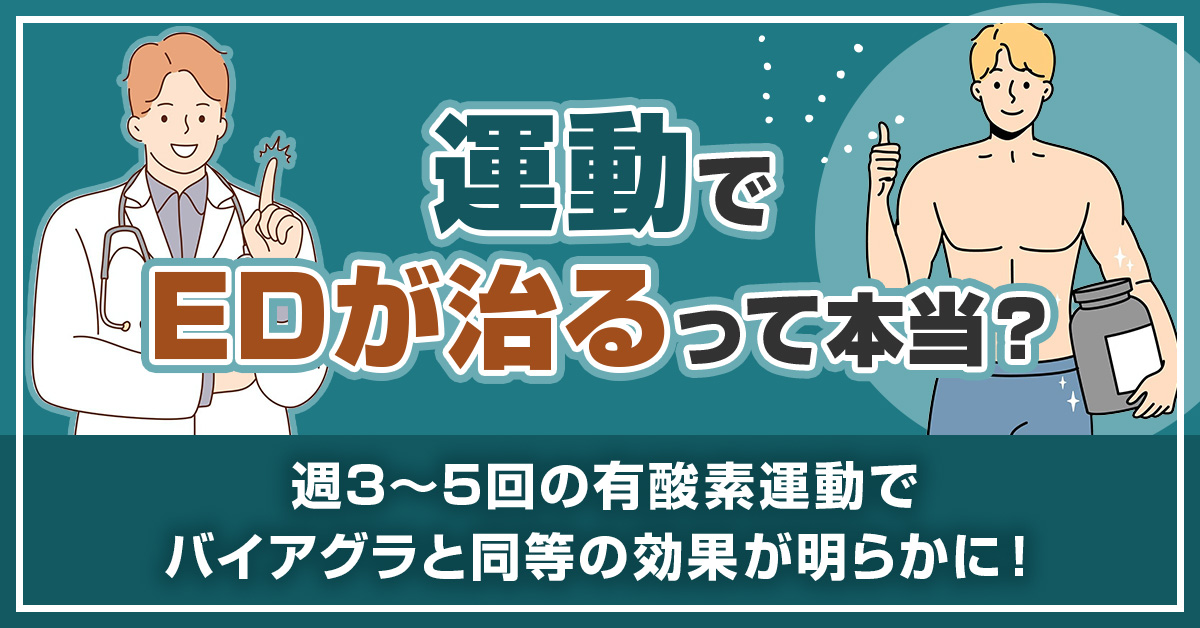糖尿病は現代社会において深刻な健康問題の一つです。
特に、血糖値の管理は糖尿病患者にとって重要な課題になっています。
その影響なのか、近年多くのサプリが市場に登場し、糖尿病の改善や管理に役立つとされています。
しかし、全てのサプリが安全で効果的というわけではありません。
この記事では、糖尿病改善に役立つ市販のサプリや飲んではいけないサプリについて詳しく解説します。
糖尿病改善サプリメントの基本知識
糖尿病の予防などに役立つサプリは多々ありますが、その中には糖尿病に良いとされるビタミン類が配合されています。
では、糖尿病に効くと言われているビタミンや栄養素には、どのようなものがあるのでしょうか。
以下に代表的なものを挙げます。
-
ビタミンD
ビタミンDはインスリンの感受性を向上させる可能性があり、血糖値のコントロールをしてくれます。
ビタミンDの不足が糖尿病のリスクを増加させることが知られています。 -
ビタミンB群
ビタミンB1(チアミン)は糖代謝を助ける働きがあり、ビタミンB6とB12は神経障害の予防に役立ちます。 -
マグネシウム
マグネシウムはインスリンの働きをサポートし、血糖値のコントロールをしてくれます。
これらのビタミンや栄養素を含んだサプリを利用することで、日常生活で足りない成分を効率的に摂取できます。
ただ、サプリメントはその名の通り補助的な効果しかないので、基本となる食事や運動ありきで考えなければならないことには注意しましょう。
サプリ以外で糖尿病に効くビタミンと栄養素を摂取する方法
サプリは手軽に摂取できてとても便利ですが、糖尿病に良いとされるビタミンや栄養素は、できればいつもの食事の中で摂取したいものです。
自然な形で摂取するにはどうすればいいのか、以下にまとめました。
ビタミンD
ビタミンDは骨の健康を維持するために不可欠な栄養素であり、カルシウムとリンの吸収を助けます。
また、免疫機能の調節や、インスリンの分泌と感受性の向上にも影響します。
ビタミンDを含む食品
魚類
特に脂肪の多い魚(サーモンやマグロ、サバなど)はビタミンDが豊富に含まれています。
- サーモン(100gあたり):約10-20μg
- マグロ(100gあたり):約5-6μg
きのこ類
きのこ(特にシイタケやマイタケ)はビタミンD2を多く含みます。
日光を浴びたきのこはビタミンD含有量が増加します。
- シイタケ(乾燥、100gあたり):約3.9μg
卵黄
卵の黄身もビタミンDを含んでいます。
- 卵黄(1個あたり):約1.1μg
実は、ビタミンDは経口摂取以外にも、皮膚が紫外線B(UVB)を受けることによって体内で合成されます。
1日に約15~30分、日光に当たると良いでしょう。
ビタミンB群
ビタミンB群は、エネルギー代謝や神経機能の維持に重要な役割を果たす水溶性ビタミンのグループです。
ビタミンB1(チアミン)、B2(リボフラビン)、B3(ナイアシン)、B5(パントテン酸)、B6(ピリドキシン)、B7(ビオチン)、B9(葉酸)、B12(コバラミン)などが含まれます。
ビタミンB群を含む食品
ビタミンB1
- 豚肉(100gあたり):約0.8-1.2mg
全粒穀物や豆類も良い供給源です。
ビタミンB2
- レバー(100gあたり):約3mg
- 乳製品(特にチーズやヨーグルト)
ビタミンB3
- 鶏肉(100gあたり):約10-15mg
- キノコ類やアスパラガス
ビタミンB5
- 鶏レバー(100gあたり):約5-6mg
- アボカド、ヨーグルト
ビタミンB6
- さつまいも(100gあたり):約0.3mg
- バナナ、サーモン
ビタミンB7
- 卵黄(1個あたり):約10μg
- ナッツ類(アーモンド、クルミ)
ビタミンB9(葉酸)
- ほうれん草(100gあたり):約194μg
- レンズ豆、アスパラガス
ビタミンB12
- サバ(100gあたり):約12μg
- 牛レバー、乳製品
ビタミンB群は多くの食品に含まれているため、バランスの取れた食事を心がけることで不足を防げます。
ただし、水溶性ビタミンであるため、調理中に失われやすい特徴があります。
蒸す、煮るなどの調理法を選ぶとよいでしょう。
マグネシウム
マグネシウムは、筋肉と神経の機能、血糖値のコントロール、血圧の調整、骨の健康維持に重要なミネラルです。
マグネシウムを含む食品
- ナッツ類:特にアーモンドやカシューナッツが豊富です。
- アーモンド(100gあたり):約270mg
- 種子類:かぼちゃの種やチアシード
- かぼちゃの種(100gあたり):約535mg
- 全粒穀物:玄米やオートミール
- 玄米(100gあたり):約110mg
- 豆類:特に黒豆や大豆
- 黒豆(100gあたり):約120mg
- 緑葉野菜:ほうれん草やケール
- ほうれん草(100gあたり):約79mg
- 魚介類:サバや鮭
- サバ(100gあたり):約90mg
マグネシウムも様々な食品に含まれているため、バランスの取れた食事を心がけていれば自然と摂取できます。
飲んではいけないサプリメント!?
サプリの中には、糖尿病患者に適さないものもあります。
特に1型糖尿病患者は注意が必要です。
-
高濃度のビタミンK
ビタミンKは血液が凝固してしまう恐れがあるため、血液凝固障害を伴う糖尿病患者には適しません。 -
特定のハーブサプリメント
例えば、フェヌグリークやクローブは血糖値を急激に下げる可能性があり、低血糖を引き起こすリスクがあります。
何事も過剰摂取はいけませんが、健康的な食事の中で摂取する分には問題ありません。
あまり神経質になるのもストレスなので、気になるサプリがあれば医師に相談してみると良いでしょう。
筆者おすすめ!血糖値を下げるサプリメントランキング
血糖値を下げるサプリはたくさんあり、それぞれに特徴があります。
以下では、筆者おすすめのサプリランキングをご紹介しますので、いろいろな商品を比較してみてください。
第1位!血糖値ダブル対策 30日分【機能性表示食品】
こちらは、DHCから出ている血糖値対策ができるサプリです。
「空腹時&食後血糖値のダブルにアプローチ」という売り文句で、その名の通りダブル対策ができるのがとても魅力的だと感じました!
成分にもこだわりがあり、桑の葉由来イミノシュガーが3.15mg、バナバ葉由来コロソリン酸が1mg配合されています。
これらの成分の機能について、以下のように記載されています。
「桑の葉由来イミノシュガーは、糖の吸収を抑え、食後血糖値の上昇を抑える機能があることが報告されています。バナバ葉由来コロソリン酸は、空腹時血糖値が高めの方の空腹時血糖値を低下させる機能があることが報告されています。」
第2位!ドクターズチョイス グルコサポート
こちらのサプリは、血糖値の急上昇を抑える成分を含んでおり、インスリンの働きをサポートしてくれます。
安定した血糖値の維持に役立つと評価されていて、糖尿病の方に不足しがちな亜鉛、クロム、マグネシウムを配合しているのが心強い!
以下は、公式サイトに記載されている文をまとめたものです。
「亜鉛はインスリンを作るために必要不可欠な材料となり、血糖値を下げるサポートをします。 クロムは血糖値、血圧、コレステロール値を下げる働きに関わり、特にインスリンの働きを助けます。 さらに、マグネシウムはインスリンの働きを促進し、血管を拡張して血圧を下げる効果があります。」
第3位!大人のカロリミット
食事の糖や脂肪の吸収を抑えてくれる心強いサプリは「カロリミット」です。
茶花サポニンや桑の葉イミノシュガー、キトサンの3成分がしっかり働きます。
口コミでは、1回の粒数も3粒なので摂取しやすいとの声も。
食後の血糖値と中性脂肪値の上昇を抑える機能があり、 糖や脂肪が多い食事をとりがちな方のお守りサプリです。
脂肪の代謝を助け消費しやすくし、BMIが高めな方の腹部の脂肪を減らす成分が含まれているため、ダイエットを補助してくれる効果もあります。
お腹周りがなかなか引っ込まない方は、健康的な食事と適度な運動と共に取り入れてみてもいいですね!
サプリメントの飲み合わせと効果的な飲み方
サプリの中には、他の薬剤やサプリと相互作用を起こすものがあります。
例えば、ビタミンKは血液凝固剤との併用に注意が必要です。
また、ハーブサプリは一部の医薬品と相互作用することがあります。
医師や薬剤師に相談し、飲み合わせを確認することが重要です。
いつ飲むのが効果的か
サプリは基本的にはいつ飲んでも構わないものが多いのですが、効果を最大限に引き出すためには、適切なタイミングでの摂取を心掛けると良いでしょう。
サプリによっていくつかベストタイミングがあります。
脂溶性ビタミン(ビタミンDなど)は食事中に摂取すると吸収が良くなりますし、一部のサプリ(例えば、特定のプロバイオティクス)は空腹時に摂取することで効果が高まる場合があります。
薬剤ではないのでそこまで飲む時間を意識する必要はありませんが、知っておくと少しお得かもしれません。
まとめ
糖尿病の管理には、バランスの取れた食事、適度な運動が必要です。
そして時には、サプリの助けを借りても良いでしょう。
サプリを選ぶ際は、口コミやランキングを参考にしつつ、自分の健康状態や生活習慣に合った製品を選ぶことが重要です。
また、サプリの飲み合わせや摂取タイミングについては、医師や薬剤師と相談することをおすすめします。
ビタミンDをはじめとする特定のビタミンや栄養素は、糖尿病の管理に役立つ可能性があります。
これらの栄養素を適切に摂取し、健康的な生活を維持することで、糖尿病の予防ができるでしょう。