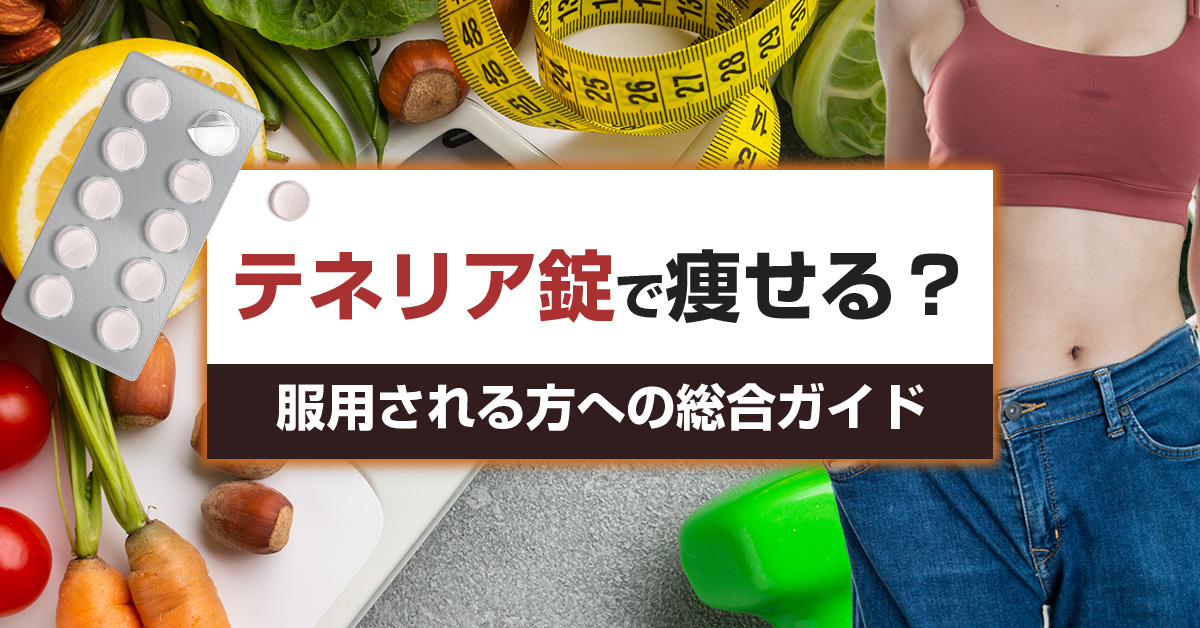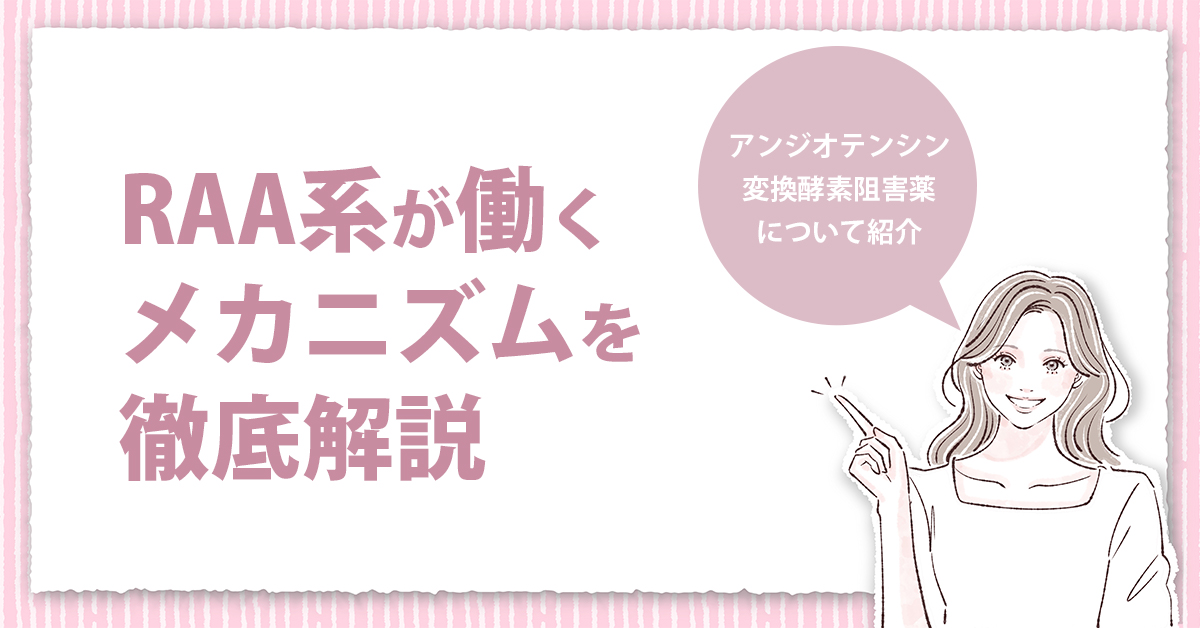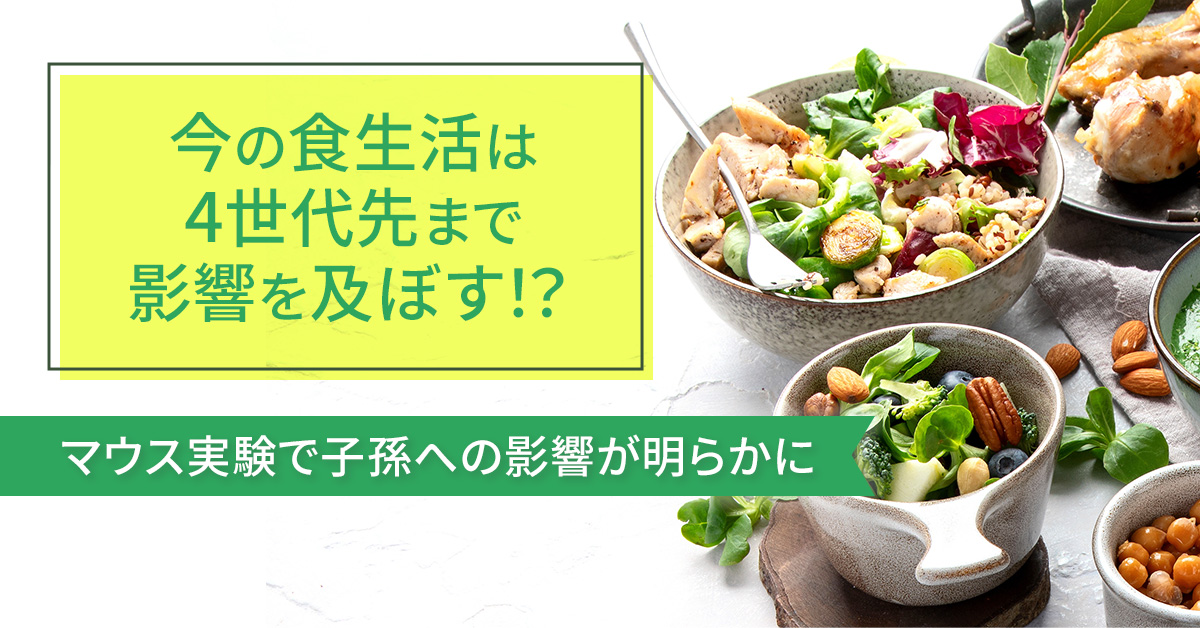糖尿病はよく知られている病気ですが、糖尿病性腎症は、あまり知られていない印象です。
糖尿病性腎症は、糖尿病患者において重要な合併症の一つであり、進行すると腎不全に至ることがあります。
この記事では、糖尿病性腎症とその治療薬について詳しく説明します。
糖尿病性腎症とは
糖尿病性腎症は、糖尿病の合併症の一つで、糖尿病腎症とも呼ばれます。
糖尿病腎症は、長期間にわたる高血糖状態が腎臓の血管を傷つけ、腎機能が低下する疾患です。
進行すると腎不全に至り、透析や腎移植が必要になることがあります。
糖尿病腎症と糖尿病性腎症の違いについては、一般的には同じ意味で使われますが、糖尿病腎症は糖尿病に関連する腎障害全般を指し、糖尿病性腎症は特に糖尿病による腎障害を指します。
糖尿病性腎症のステージ
糖尿病性腎症は進行度に応じてステージ分けされます。
ステージ1(第1期):腎症前期
ステージ1の基準値
尿タンパク(g/gCr):正常(30未満)
eGFR(ml/分/1.73㎡):30以上
ステージ1では、自覚症状はほとんどありません。
この段階では、食事療法を中心として血糖をコントロールする治療が検討されます。
ステージ2(第2期):早期腎症期
ステージ2の基準値
尿タンパク(g/gCr):微量アルブミン尿(30~299)
eGFR(ml/分/1.73㎡):30以上
ステージ2の状態でも自覚症状はほとんどありませんが、ごく微量のタンパク質(微量アルブミン)が漏れ出てくる状態です。
ステージ1と同様に、食事療法を基本とした治療などが検討されます。
ステージ3(第3期):顕性腎症期
ステージ3の基準値
尿タンパク(g/gCr):顕性アルブミン尿(300以上)
eGFR(ml/分/1.73㎡):30以上
ステージ3になると、むくみや息切れ、胸苦しさ、食欲不振、満腹感などの自覚症状があります。
第3期以降では、進行を遅らせることはできても、元の状態に戻すことはできないと言われています。
食事療法の他、運動療法を基本とした治療などが検討されます。
ステージ4(第4期):腎不全期
ステージ4の基準値
尿タンパク(g/gCr):問わない
eGFR(ml/分/1.73㎡):30未満
ステージ4になると、顔色が悪い、嘔気あるいは嘔吐、筋肉の強直、つりやすい、筋肉や骨の痛み、手のしびれや痛み、腹痛と発熱などの自覚症状が出る場合があります。
血圧コントロールや低タンパク食の他、透析療法導入なども検討されます。
ステージ5(第5期):透析療法期
ステージ5の基準値
透析療法中
この段階では、ステージ4と同様の自覚症状が出ることがあり、透析療法や腎移植などが行われる場合もあります。
糖尿病性腎症の症状
ステージの解説で症状について少し触れましたが、初期段階では症状がほとんど現れません。
しかし、進行すると以下のような症状が現れます。
- 尿の泡立ち:尿中の蛋白質が増えると泡立ちやすくなります。
- むくみ:腎機能が低下すると、体内に水分がたまりやすくなります。
- 高血圧:腎臓の機能低下は血圧の上昇を引き起こします。
- 疲労感:腎機能低下に伴い、身体の老廃物を排出する能力が低下し、疲労感が強くなります。
糖尿病性腎症の治療法
糖尿病性腎症の治療法は、病状の進行を遅らせ、腎機能を維持することを目的としています。
治療法には以下のものがあります。
食事療法
食事療法は糖尿病性腎症の管理において重要な役割を果たします。
主なポイントは以下の通りです。
- 塩分制限:高血圧を防ぐために塩分を1日6g未満に制限する。
- 蛋白質制限:腎機能の負担を減らすために、蛋白質の摂取量を制限する。
- カリウム制限:腎機能が低下するとカリウムの排出が難しくなるため、カリウムの摂取を制限する。
- 血糖管理: 食事療法を通じて血糖値を安定させる。
薬物療法と薬剤の一覧
糖尿病性腎症の薬物療法は、患者さんの症状やステージに合わせて行われます。
糖尿病性腎症で処方される薬剤のランキングを一部ご紹介します。
まずは、1~10位を見ていきましょう。
-
メトグルコ錠250mg
ビグアナイド系経口血糖降下剤 -
ジャヌビア錠50mg
選択的DPP-4阻害剤◎糖尿病用剤◎ -
エクメット配合錠HD
選択的DPP-4阻害薬/ビグアナイド系薬配合剤[2型糖尿病治療薬] -
トラゼンタ錠5mg
胆汁排泄型選択的DPP-4阻害剤-2型糖尿病治療剤- -
メトホルミン塩酸塩錠500mgMT「DSPB」
ビグアナイド系経口血糖降下剤 -
トレシーバ注 フレックスタッチ
持効型溶解インスリンアナログ注射液 -
グラクティブ錠50mg
選択的DPP-4阻害剤-糖尿病用剤- -
トルリシティ皮下注0.75mgアテオス
持続性GLP-1受容体作動薬 -
テネリア錠20mg
選択的DPP-4阻害剤 ―2型糖尿病治療剤― -
メトホルミン塩酸塩錠500mgMT「ニプロ」
ビグアナイド系経口血糖降下剤
続いて、11~20位です。
-
メトホルミン塩酸塩錠500mgMT「DSEP」
ビグアナイド系経口血糖降下剤 -
アジルバ錠20mg
持続性AT1レセプターブロッカー -
エクア錠50mg
選択的DPP-4阻害薬[2型糖尿病治療薬] -
ノボラピッド注 フレックスタッチ
超速効型インスリンアナログ注射液 -
メトホルミン塩酸塩錠250mgMT「DSPB」
ビグアナイド系経口血糖降下剤 -
メトグルコ錠500mg
ビグアナイド系経口血糖降下剤 -
オルメサルタンOD錠20mg「DSEP」
高親和性AT1レセプターブロッカー -
ライゾデグ配合注 フレックスタッチ
インスリン デグルデク/インスリン アスパルト配合 溶解インスリンアナログ注射液 -
イニシンク配合錠
選択的DPP-4阻害薬/ビグアナイド系薬配合剤-2型糖尿病治療剤- -
リベルサス錠7mg
2型糖尿病治療剤 経口GLP-1受容体作動薬
これらの薬剤のうちどれが処方されるかは、医師の判断によります。
症状を的確に伝えられるよう、いつからどんな症状があるかメモする癖を付けておくと良いですね。
新薬と最新治療薬
近年、糖尿病性腎症に対する新たな薬剤が開発されています。
最近では、2022年3月3日に厚労省がMR拮抗薬「ケレンディア」の承認を了承しました。
糖尿病腎症に対する適応は国内初の出来事でした。
ケレンディアは、その前の部会では日本人における有効性や安全性が争点となったまま、継続審議となっていました。
しかし、添付文書上で注意喚起をすることを条件に、承認を了承しても差し支えないと判断されました。
腎臓病の最新治療薬は日々研究が重ねられているので、さらに進歩することを祈りましょう。
腎臓を良くする薬剤はあるか
現在、腎臓を完全に治す薬剤は存在しませんが、腎機能を維持・改善する薬剤は多くあります。
SGLT2阻害薬やARB、ACE阻害薬は、腎臓への負担を軽減し、腎機能を維持する効果があります。
また、新たな研究により、腎臓を保護する効果が期待される薬剤も開発されています。
糖尿病性腎症治療のガイドラインに、今後出てくる新薬が載るかもしれませんね。
糖尿病性腎症の第一選択薬
糖尿病性腎症の第一選択薬は、通常、SGLT2阻害薬とされています。
これに加えて、ARBまたはACE阻害薬が併用されることが多いです。
これらの薬剤は、血糖値のコントロールだけでなく、腎臓の保護効果もあり、糖尿病性腎症の進行を遅らせることができます。
糖尿病性腎症に保険適用のあるARBや、そうでない薬剤もあるので、希望する薬剤があれば医師に知らせましょう。
日常生活で気を付けること
糖尿病性腎症は日常生活での注意が重要で、適切な管理を行うことで進行を遅らせることができます。
最後に、糖尿病性腎症の患者さんが日常生活で気を付けるべきことについて説明します。
1. 血糖値の管理
血糖値の管理は糖尿病性腎症の進行を防ぐために最も重要なポイントです。
高血糖状態が続くと腎臓に負担がかかり、腎機能が低下します。
まずは炭水化物の摂取量を管理し、血糖値の急上昇を防ぐために低GI食品を選びましょう。
バランスの取れた食事を心がけ、適切なカロリー摂取を維持します。
そして、自宅で血糖値を測定し、適切な範囲内に保つようにします。
医師の指示に従い、インスリンや他の糖尿病治療薬を適切に使用します。
2. 血圧の管理
高血圧は腎臓に悪影響を与えるため、血圧の管理も重要です。
食塩の摂取を1日6g以下に抑えることを心がけましょう。
加工食品や外食を避け、自宅で調理する際は塩分を控えめにします。
また、適度な運動は血圧を下げる効果があります。
ウォーキングや軽いジョギングなど、無理のない範囲で継続的に行いましょう。
家庭用血圧計を使用して定期的に血圧を測定し、異常があれば医師に相談します。
3. 食事療法
糖尿病性腎症の患者さんは、腎臓に負担をかけない食事を心がけましょう。
過剰な蛋白質摂取は腎臓に負担をかけます。
医師や栄養士の指導に従い、適切な蛋白質量を守るようにしてください。
腎機能が低下するとカリウムの排出が難しくなるため、高カリウム食品の摂取も控えます。
バナナやオレンジ、ほうれん草などの高カリウム食品に注意が必要です。
腎臓がリンの排出を十分にできない場合は、リンの摂取量を制限します。
乳製品や加工食品に多く含まれるため、注意が必要です。
まとめ
糖尿病性腎症は、糖尿病患者にとって深刻な合併症であり、適切な治療と管理が必要です。
SGLT2阻害薬、ARB、ACE阻害薬などの薬物療法に加え、食事療法や運動療法を組み合わせることで、腎機能の低下を遅らせ、生活の質を向上させることが可能です。
糖尿病性腎症と診断されたら、最新のガイドラインに基づいた治療を行い、定期的な検査を受け、糖尿病性腎症の進行を遅らせていきましょう。