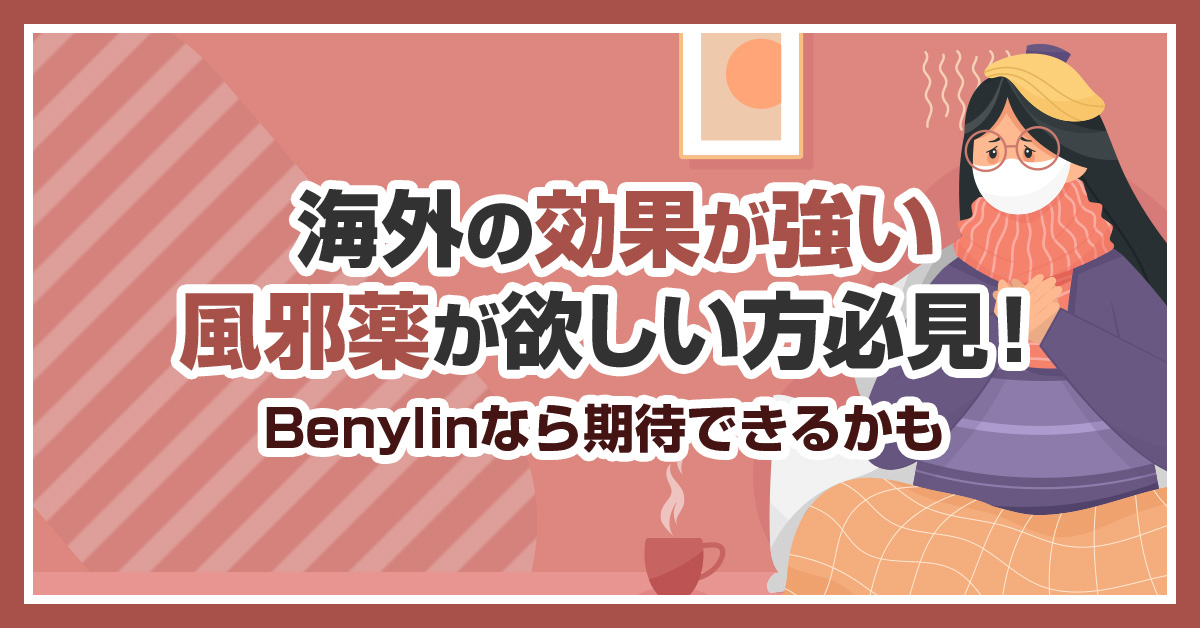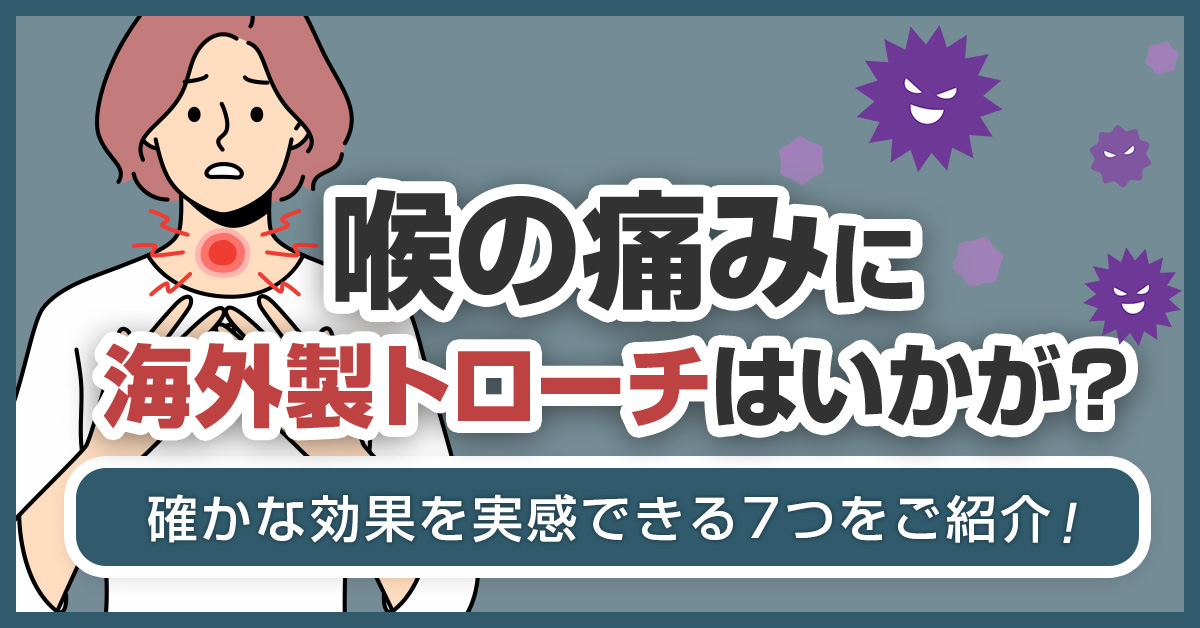鎮咳剤
- 鎮咳剤の3つの種類
-
鎮咳剤は、咳を抑える効果のある薬剤です。
風邪やアレルギー、喘息などによる咳の症状を和らげるために使用されます。
咳は体を守る防御反応ですが、過度な咳は生活の質を低下させ、睡眠を妨げるなど様々な問題を引き起こすことがあります。
そのような場合に鎮咳剤が役立ちます。鎮咳剤は大きく分けて、中枢性鎮咳薬、非麻薬性中枢性鎮咳薬、そして末梢(まっしょう)性鎮咳薬の3つに分かれます。
麻薬性中枢性鎮咳薬での代表的な薬は以下の通りです。
- コデイン
- ジヒドロコデイン
中枢性鎮咳剤は、脳の咳中枢に直接作用して咳を抑えます。
ただし、麻薬性鎮咳薬には依存性があることに注意が必要です。非麻薬性中枢性鎮咳薬には以下があります。
- ノスカピン
- デキストロメトルファン(メジコン)
- チペピジン(アスベリン)
- グアイフェネシン(フストジル)
- ペントキシベリン(トクレス)
麻薬性中枢性鎮咳薬と異なり、依存性がありません。
末梢性鎮咳薬には、ベンゾナテートがあります。
末梢性鎮咳剤は、気道の感覚神経に作用して咳の反射を抑えます。鎮咳薬は、一般的には症状に応じて1日3~4回服用します。
就寝前に服用すると、夜間の咳を抑え、睡眠の質を改善できることがあります。
市販薬の場合は、パッケージの説明書をよく読んで正しく使用しましょう。 - 鎮咳剤を選ぶ際の注意点
-
鎮咳剤を選ぶ際は、咳の性質や原因を考慮することが重要です。
原因が異なれば、使える薬も違ってきます。-
乾いた咳(空咳)
痰のない乾いた咳には、単独の鎮咳剤が適しています。 -
痰のある咳
痰を伴う咳には、去痰作用のある薬剤との併用が効果的です。 -
アレルギー性の咳
アレルギーが原因の咳には、抗ヒスタミン薬との併用が有効な場合があります。 -
喘息による咳
喘息が原因の場合は、気管支拡張剤や吸入ステロイド薬が必要となることがあります。
-
- 鎮咳剤の副作用と注意点
-
鎮咳剤にも他の薬と同様に副作用があります。
-
眠気
特に中枢性鎮咳剤で起こりやすく、車の運転や機械操作時は注意が必要です。 -
便秘
特にコデインなどの麻薬性鎮咳剤で起こりやすい副作用です。 -
吐き気や食欲不振
胃腸への影響が現れることがあります。 -
依存性
麻薬性鎮咳剤の長期使用で起こる可能性があります。
鎮咳剤は症状を和らげるのに効果的ですが、長期間の連続使用は避け、症状が長引く場合は医師に相談しましょう。
咳には重要な役割があるため、必要以上に抑制しないよう注意が必要です。
原因不明の咳が続く場合は、単に鎮咳剤で対処するのではなく、医療機関で原因を特定してください。 -