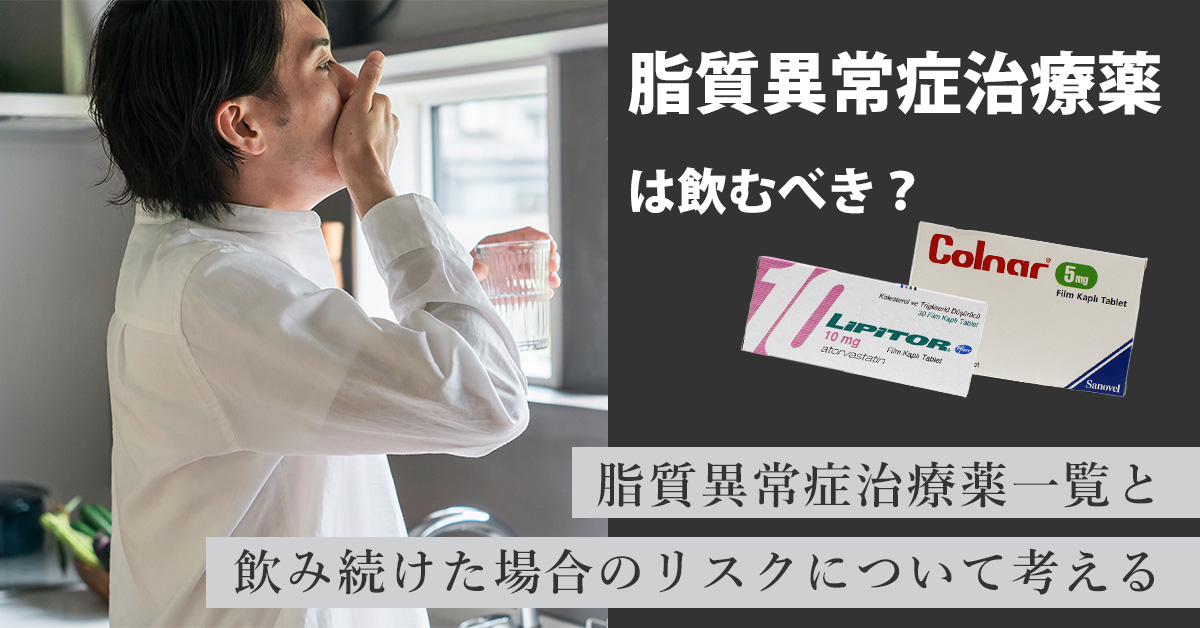コレステロール吸収阻害薬
- コレステロール吸収阻害薬の例と配合薬
-
コレステロール吸収阻害薬は、高コレステロール血症の治療に使用される薬剤の一つです。
腸管でのコレステロール吸収を抑制することで血中のコレステロール値を下げる効果があります。
スタチンとは異なるメカニズムで作用するため、単独使用や他の薬剤との併用で効果的な治療が可能です。現在、日本で使用されている主なコレステロール吸収阻害薬はエゼチミブです。
ゼチーアという商品名で知られており、以下のようなエゼチミブとスタチンとの配合剤もあります。
スタチンも、悪玉コレステロール値を下げる薬です。- アトルバスタチンとの配合剤(アトーゼット配合錠)
- ロスバスタチンとの配合剤(ロスーゼット配合錠)
- ピタバスタチンカルシウムとの配合剤(リバゼブ配合錠)
- 使用方法と注意点
-
コレステロール吸収阻害薬使用時の主な注意点は以下の通りです。
-
副作用
消化器症状(腹痛、下痢など)
筋肉痛(まれ)
肝機能障害(まれ) -
相互作用
一部の薬剤(胆汁酸吸着剤など)との相互作用に注意 -
特殊な状況
妊娠中や授乳中の使用は避ける
重度の肝機能障害がある場合は使用を控える
-
- コレステロール吸収阻害薬の特徴
-
この薬剤には以下のような特徴があります。
-
遺伝的な影響
コレステロール吸収能力が高い人ほど効果が大きい傾向がある -
植物ステロールとの関連
植物ステロールの吸収も阻害するため、サプリメントとの併用に注意が必要 -
他の脂質異常症治療薬との併用
スタチンだけでなく、フィブラート系薬剤や胆汁酸吸着剤との併用も可能
-
- 生活習慣の改善との組み合わせ
-
コレステロール吸収阻害薬の効果を最大限に引き出すためには、以下のような生活習慣の改善も重要です。
- コレステロールや飽和脂肪酸の摂取を控える
- 食物繊維を多く含む食品を積極的に摂取
- 適度な運動を定期的に行う
- 適正体重の維持
- 禁煙
これらの取り組みにより、薬剤の効果がさらに高まり、より効果的な脂質管理が可能になります。
食事に関しては、食物繊維の多い食品として、野菜や海藻類、きのこ、根菜類などを意識的に食べるようにしましょう。
肉などの脂っこい料理を食べる際には、これらの食物繊維を豊富に含んだ料理を一緒に食べることをおすすめします。コレステロール吸収阻害薬は、高コレステロール血症の治療において重要な選択肢の一つとなっています。
特に、スタチンとの併用や、スタチンに不耐性がある患者さんの代替療法として有用です。
個々の状況に応じて、適切な治療法を選択することが大切です。
コレステロール吸収阻害薬として使われる医薬品成分
- アルギニン
- アルギニンは、タンパク質を構成する20種類のアミノ酸の1つです。体内で合成されるため、通常は必須アミノ酸とは見なされませんが、特定の状況下では「条件付き必須アミノ酸」として扱われることがあります。 アルギニンは体内で様々な重要な役割を果たしています。その中でも特に注目されているのが、一酸化窒素(NO)の...
- シトルリン
- シトルリンは、体内で生成される非必須アミノ酸の一つです。スイカに多く含まれることから、ラテン語でスイカを意味する「Citrullus」にちなんで名付けられました。このアミノ酸は、体内でさまざまな働きをしており、健康維持に役立っています。 シトルリンは、体内で重要な役割を果たしています。特に注目されるのは、...
- クコシ
- クコシ(枸杞子)は、クコ(枸杞)の実を乾燥させたもので、中国や東アジアで古くから健康食材として親しまれてきました。学名はLycium barbarumで、英語ではGoji berryとも呼ばれます。赤オレンジ色の小さな実は、独特の甘みと酸味を持ち、栄養価が高いことで知られています。 クコシは昔から様々な効果があるとされていま...
- マカ
- マカは、学名をLepidium meyeniiといい、ペルーのアンデス山脈高原地帯で栽培されるアブラナ科の植物です。その根は何世紀にもわたり、栄養価の高い食材として、また伝統的な健康増進法として利用されてきました。 マカの根は、色によって黄色、赤、黒などの種類があり、それぞれ少しずつ成分が異なります。主な栄養成分...
- オルニチン
- オルニチンは、体内で生成される非必須アミノ酸の一つです。尿素回路で重要な役割を果たし、アンモニアの解毒や体内の窒素バランスの維持に関与しています。近年、様々な健康効果が注目され、サプリメントとしても広く利用されるようになりました。 尿素回路* オルニチンは尿素回路の重要な構成要素です。この回路は、...
- ナイアシン
- ナイアシンは、ビタミンB群の一つで、ビタミンB3とも呼ばれています。人体にとって不可欠な栄養素であり、食事から摂取する必要があります。ナイアシンには、ニコチン酸とニコチンアミドの2つの形態があり、どちらも体内で同様の働きをします。 エネルギー代謝のサポート* ナイアシンは、体内でNAD(ニコチンアミドアデ...