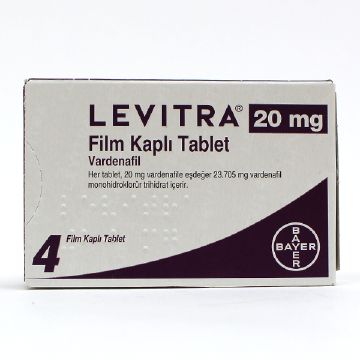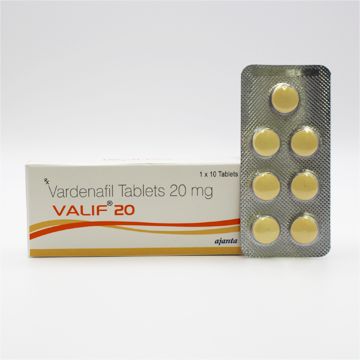ピリン系鎮痛薬
- ピリン系鎮痛薬の概要
-
ピリン系鎮痛薬は、主に痛みや炎症を軽減するために使用される薬です。
19世紀後半に発見され、以来、慢性および急性の痛みをやわらげるためによく利用されてきました。しかし、ピリン系の鎮痛剤は今では一部の市販薬に配合されているのみに留まっています。
その理由は、過敏症や血液障害などの副作用が問題となっているからです。
具体的なピリン系鎮痛剤には「スルピリン」や「アンチピリン」があります。 - アスピリンはピリン系じゃない!
-
上記のような薬には「ピリン」という名前が入っていますが、混同されやすいのは「アスピリン」です。
アスピリンは名前に「ピリン」が入っていますが、非ピリン系鎮痛剤に分類されます。
アスピリンは、頭痛や風邪を引いたときの症状をやわらげるために服用することが多く、よく知られている商品名は「バファリン」です。紛らわしい名前がついてしまった理由は、アスピリンの別名である「アセチルサリチル酸」が原因となっている説があります。
アセチルの「A」と、サリチル酸の別名である植物「SpiraeUlmaria」に由来しピリン系ではないのに名前に「ピリン」が入ってしまったそうです。 - ピリン系鎮痛薬の代表例
-
市販で入手できるピリン系の鎮痛剤の代表例に、「セデス・ハイ(ピリン系)」があります。
商品キャッチフレーズが「がまんできない、つらい痛みによく効く」となっており、痛みに高い効果があることがうかがえます。効果があるものとして表示されているのは、以下の10の症状です。
- いつもの頭痛
- つらい頭痛
- 発熱
- 生理痛
- 肩こり痛
- 腰痛
- 歯痛
- 喉の痛み
- 筋肉痛
- 関節痛
中でも、頭痛と歯痛によく効くことで知られています。
強い痛みによく効くのは、解熱鎮痛成分のイソプロピルアンチピリン(IPA)とアセトアミノフェンが効果を発揮するからです。
また、セデス・ハイは錠剤が小さいため、飲みやすい点もメリットです。「セデス」と言えば色々な種類が出ていますが、それぞれに特徴があります。
「セデス・ハイ プロテクト」と「セデス・ハイ」「セデス・ハイG」すべてに共通するのはそれも4種の鎮痛成分を配合していることですが、「セデス・ハイ プロテクト」は胃を守る成分が含まれています。
また、「セデス・ハイG」は顆粒剤で、「セデス・ハイ プロテクト」「セデス・ハイ」は錠剤の薬となっています。 - 使用方法と副作用
-
ピリン系鎮痛薬は経口薬として使用されることが一般的ですが、外用薬や注射剤としても利用されます。
これらの薬は、短期間の急性痛みの管理から、慢性疾患の長期管理まで幅広く使用されます。しかし、長期使用や高用量の使用には副作用のリスクが伴うことも覚えておきましょう。
最も一般的な副作用は、胃腸障害、胃潰瘍、出血リスクの増加です。
そのため、胃腸障害の既往歴がある患者は注意が必要です。