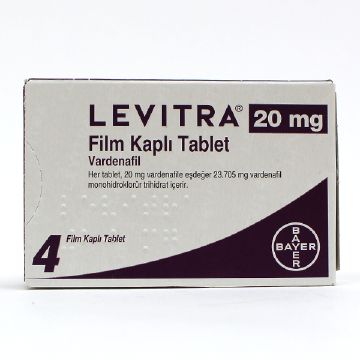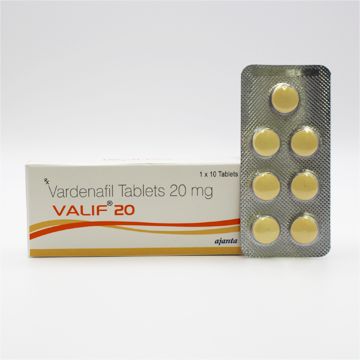硝酸薬(持効性)
- 主な硝酸薬(持効性)の薬
-
持効性硝酸薬は、狭心症の予防や慢性心不全の治療に広く用いられる薬です。
長時間にわたって血管拡張作用を維持することで、持続的な抗狭心症効果を発揮します。主な持効性硝酸薬には、硝酸イソソルビド(持効)と呼ばれる薬があります。
経口剤、貼付剤として使用されます。
経口剤は通常1日2-3回の服用が必要です。
貼付剤は1日1回の使用で効果が持続します。持効性硝酸薬は、狭心症の予防や慢性心不全の長期管理に用いられるため、起きている発作を止める効果はありません。
予防的に毎日服用することが一般的です。
通常、低用量から開始し、効果と副作用を見ながら適宜増減します。
効果が不十分な場合は、他の抗狭心症薬(β遮断薬やカルシウム拮抗薬など)との併用を検討します。 - 持効性硝酸薬の注意点
-
これらの薬剤の使用にあたっては、以下の点に注意が必要です。
-
耐性の発現
持続的な使用により薬剤耐性が生じる可能性があります。 -
頭痛
使用初期に頭痛が生じることがありますが、多くの場合時間とともに軽減します。
重度の頭痛が続く場合は、用量調整や他剤への変更を検討します。 -
起立性低血圧
特に投与開始時や増量時に注意が必要です。
高齢者や脱水状態の患者では、より慎重な観察が求められます。 -
併用禁忌
ホスホジエステラーゼ5阻害薬(シルデナフィル、バルデナフィル、タダラフィルなど)との併用は、重篤な血圧低下を引き起こす可能性があるため禁忌です。 -
妊婦・授乳婦への投与
妊婦または妊娠している可能性のある女性への投与は避けるべきです。
動物実験で胎児毒性が報告されているためです。
授乳中の女性に投与する場合は授乳を中止させる必要があります。 -
他の副作用
めまい、立ちくらみ、倦怠感、悪心などが現れることがあります。
これらの症状が強い場合は、用量調整や投与時間の変更を検討します。 -
相互作用
降圧薬や利尿薬との併用で、過度の血圧低下が起こる可能性があります。
また、アルコールとの併用も血圧低下を増強する可能性があるため注意が必要です。
持効性硝酸薬は、適切に使用することで狭心症の発作頻度を減少させ、患者のQOLを向上させることができます。
ただし、これらの薬剤は対症療法であり、基礎疾患の管理や生活習慣の改善などの総合的なアプローチが必要不可欠と言えます。患者が薬の使い方を理解することも大切です。
発作時の対処法や、持効性硝酸薬と速効性硝酸薬の使い分け、副作用の早期発見と対処法などについて、医師からの十分な説明が必要です。
また、定期的な受診の重要性や、症状の変化が見られた際の早期受診の必要性についても理解しておきましょう。 -